『道草』夏目漱石 ― 2019-12-21
2019-12-21 當山日出夫(とうやまひでお)

夏目漱石.『道草』(新潮文庫).新潮社.1951(2011.改版)
https://www.shinchosha.co.jp/book/101014/
続きである。
やまもも書斎記 2019年12月20日
『こころ』夏目漱石
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/12/20/9191512
この作品も何度か読みかえしている。だが、はっきりいって、私はこの作品が苦手である。嫌いというのではないが、何かしら作品の世界の中にはいっていって読みふけるということがない。とはいえ、今回、新潮文庫版で漱石の作品を順番に読んできて、思うことなど書いてみると、次の二点ぐらいだろうか。
第一には、これは、敗れ去るものの物語ではないだろうか、ということ。
健三は、外国留学を終えて日本に帰ってきたという設定になっている。このあたりは、漱石の自伝的な要素をふくんだ書き方なのだろう。つまり、西洋の本当の近代というものを体験してきた人間ということになる。その健三が、日本の家族とうまくいかない。それのみならず、かつての育ての親から、金の無心をせまられる。健三は、家庭の中で、また、社会、いやこの場合は、世間とでもいった方がいいかもしれない、その中で孤立をふかめていく。
漱石の作品の場合、成功する、勝利するという人物が主人公になることはない。何かしら、社会からの敗残者という側面をもっている。敗残者が極端なら、少なくとも、社会に背を向けている人間である。『坊っちゃん』も敗北する人間の物語であり、『門』などもそうだろう。
この『道草』においても、健三は、結局は、家庭から、また、社会から取り越される人物として描かれている。それを象徴するのは、この作品の最後のシーンだろうと思う。
第二には、この作品になって、登場人物、特に女性のことばがかわってきている、ということ。
『三四郎』からはじまる長編作品においては、女学生ことばをつかう女性が重要な位置をしめてきている。美禰子であり、三千代であり、あるいは、『こころ』の奥さんであり、である。しかし、この女学生ことばをつかう女性は、ほとんど小説のメインのところに顔を出さない。あくまでも、男性の目から見た目で描かれている。
しかし、『道草』になると、その女性のこころのうちを描くようになっている。そして、これは、次の『明暗』にもひきつがれていく。漱石の作品における、女学生ことばをつかう女性、使わない女性、このような視点から見ると、『道草』は、一つの転機になっている作品であると感じるところがある。(たぶん、このようなことは、漱石研究の分野では、すでに誰かが言っていることだろうと思うのだが。)
以上の二点が、『道草』を読んで思うことなどである。
一般的には、『道草』は自伝的な小説ということになっている。だが、しかし、自伝からは最も遠いところに位置する作品であるのかもしれない。この作品では、漱石は、主人公の健三をつきはなした視点から描いている。
『猫』の苦沙弥先生は、なにかしら漱石自身を投影したところを感じる。しかし、この『道草』には、そのようなとことは感じない。ここでは、漱石は、留学帰りの主人公が、日本の因習的な社会のなかでどう生きていかざるをえないか、その有様と苦悩を描いている。ある意味では、もはや、それまでの作品にみられたような、人間のこころのうちを探偵していくことの興味を超えたとことに視点を定めている。
次は、『明暗』である。これも数ヶ月前に読んだ作品であるが、順番に読んで来て、さらに続けて読むことにする。
2019年12月13日記
https://www.shinchosha.co.jp/book/101014/
続きである。
やまもも書斎記 2019年12月20日
『こころ』夏目漱石
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/12/20/9191512
この作品も何度か読みかえしている。だが、はっきりいって、私はこの作品が苦手である。嫌いというのではないが、何かしら作品の世界の中にはいっていって読みふけるということがない。とはいえ、今回、新潮文庫版で漱石の作品を順番に読んできて、思うことなど書いてみると、次の二点ぐらいだろうか。
第一には、これは、敗れ去るものの物語ではないだろうか、ということ。
健三は、外国留学を終えて日本に帰ってきたという設定になっている。このあたりは、漱石の自伝的な要素をふくんだ書き方なのだろう。つまり、西洋の本当の近代というものを体験してきた人間ということになる。その健三が、日本の家族とうまくいかない。それのみならず、かつての育ての親から、金の無心をせまられる。健三は、家庭の中で、また、社会、いやこの場合は、世間とでもいった方がいいかもしれない、その中で孤立をふかめていく。
漱石の作品の場合、成功する、勝利するという人物が主人公になることはない。何かしら、社会からの敗残者という側面をもっている。敗残者が極端なら、少なくとも、社会に背を向けている人間である。『坊っちゃん』も敗北する人間の物語であり、『門』などもそうだろう。
この『道草』においても、健三は、結局は、家庭から、また、社会から取り越される人物として描かれている。それを象徴するのは、この作品の最後のシーンだろうと思う。
第二には、この作品になって、登場人物、特に女性のことばがかわってきている、ということ。
『三四郎』からはじまる長編作品においては、女学生ことばをつかう女性が重要な位置をしめてきている。美禰子であり、三千代であり、あるいは、『こころ』の奥さんであり、である。しかし、この女学生ことばをつかう女性は、ほとんど小説のメインのところに顔を出さない。あくまでも、男性の目から見た目で描かれている。
しかし、『道草』になると、その女性のこころのうちを描くようになっている。そして、これは、次の『明暗』にもひきつがれていく。漱石の作品における、女学生ことばをつかう女性、使わない女性、このような視点から見ると、『道草』は、一つの転機になっている作品であると感じるところがある。(たぶん、このようなことは、漱石研究の分野では、すでに誰かが言っていることだろうと思うのだが。)
以上の二点が、『道草』を読んで思うことなどである。
一般的には、『道草』は自伝的な小説ということになっている。だが、しかし、自伝からは最も遠いところに位置する作品であるのかもしれない。この作品では、漱石は、主人公の健三をつきはなした視点から描いている。
『猫』の苦沙弥先生は、なにかしら漱石自身を投影したところを感じる。しかし、この『道草』には、そのようなとことは感じない。ここでは、漱石は、留学帰りの主人公が、日本の因習的な社会のなかでどう生きていかざるをえないか、その有様と苦悩を描いている。ある意味では、もはや、それまでの作品にみられたような、人間のこころのうちを探偵していくことの興味を超えたとことに視点を定めている。
次は、『明暗』である。これも数ヶ月前に読んだ作品であるが、順番に読んで来て、さらに続けて読むことにする。
2019年12月13日記
『スカーレット』あれこれ「幸せへの大きな一歩」 ― 2019-12-22
2019-12-22 當山日出夫(とうやまひでお)
『スカーレット』第12週「幸せへの大きな一歩」
https://www.nhk.or.jp/scarlet/story/index12_191216.html
前回は、
やまもも書斎記 2019年12月15日
『スカーレット』あれこれ「夢は一緒に」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/12/15/9189442
この週の放送で印象にのこっているのは、やはり水曜日だろう。喜美子と八郎の二人だけの出演だった。丸熊陶業の作業場だけのシーンであった。
ここで二人は、これからの将来のことについて語り合い、そして、お互いの気持ちを確かめ合う。
それにしても、このドラマはスピードの緩急がはげしい。水曜日に二人だけのシーンをじっくりと描いたいたかと思うと、あっというまに結婚してしまった。そして、土曜日には、もう独立して自分たちの工房をもち、さらには子どもまで生まれてしまっている。
が、ともあれ、ここまできて喜美子の生活は安定してきたようである。また、陶芸家としての道筋も見えてきたような気がする。まだ、陶芸家として、自分の作品を作るというところまではいたっていないが、八郎の仕事を手助けしながら、技術を身につけていってるようだ。
ちや子さんも登場していて、信楽初の女性陶芸家をめざしてはとはげましていた。
ただ、残念だったのは……BK(大阪)制作の朝ドラなのだから、写真を撮る場面のカメラマンが、いつものとおりであってほしかった。
次週以降、いろいろ波乱があるようである。このドラマ、次週で今年の放送が終わるかと思う。来年からは、陶芸家としての喜美子が登場することになるのだろうか。楽しみに見ることにしよう。
2019年12月21日記
『スカーレット』第12週「幸せへの大きな一歩」
https://www.nhk.or.jp/scarlet/story/index12_191216.html
前回は、
やまもも書斎記 2019年12月15日
『スカーレット』あれこれ「夢は一緒に」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/12/15/9189442
この週の放送で印象にのこっているのは、やはり水曜日だろう。喜美子と八郎の二人だけの出演だった。丸熊陶業の作業場だけのシーンであった。
ここで二人は、これからの将来のことについて語り合い、そして、お互いの気持ちを確かめ合う。
それにしても、このドラマはスピードの緩急がはげしい。水曜日に二人だけのシーンをじっくりと描いたいたかと思うと、あっというまに結婚してしまった。そして、土曜日には、もう独立して自分たちの工房をもち、さらには子どもまで生まれてしまっている。
が、ともあれ、ここまできて喜美子の生活は安定してきたようである。また、陶芸家としての道筋も見えてきたような気がする。まだ、陶芸家として、自分の作品を作るというところまではいたっていないが、八郎の仕事を手助けしながら、技術を身につけていってるようだ。
ちや子さんも登場していて、信楽初の女性陶芸家をめざしてはとはげましていた。
ただ、残念だったのは……BK(大阪)制作の朝ドラなのだから、写真を撮る場面のカメラマンが、いつものとおりであってほしかった。
次週以降、いろいろ波乱があるようである。このドラマ、次週で今年の放送が終わるかと思う。来年からは、陶芸家としての喜美子が登場することになるのだろうか。楽しみに見ることにしよう。
2019年12月21日記
追記 2019-12-29
この続きは、
やまもも書斎記 2019年12月29日
『スカーレット』あれこれ「愛いっぱいの器」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/12/29/9194985
この続きは、
やまもも書斎記 2019年12月29日
『スカーレット』あれこれ「愛いっぱいの器」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/12/29/9194985
新潮日本古典集成『源氏物語』(五) ― 2019-12-23
2019-12-23 當山日出夫(とうやまひでお)
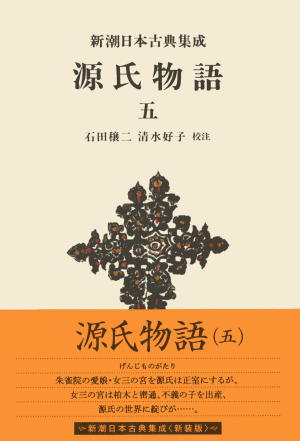
石田穣二・清水好子(校注).『源氏物語』(五)新潮日本古典集成(新装版).新潮社.2014
https://www.shinchosha.co.jp/book/620822/
続きである。
やまもも書斎記 2019年12月16日
新潮日本古典集成『源氏物語』(四)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/12/16/9189826
以前に読んだときのことは、
やまもも書斎記 2019年2月25日
『源氏物語』(五)新潮日本古典集成
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/02/25/9040411
新潮版の第五冊目には、「若菜上」から「鈴虫」までをおさめる。
読んで思ったことかはいろいろあるが、二つばかり書いてみる。
第一には、紫の上の思いである。
女三の宮が光源氏の六条院にやってくる。それをめぐって、紫の上の心がゆれうごく。そのこころのうちの描写が実に丁寧である。これはおそらく、当時の貴族社会にあっての婚姻のあり方とふかく関連しているのであろう。
幼いときに光源氏の目にとまって、ひきとられ、そして妻となった紫の上であるが、女三の宮の降嫁ということの前には、立場がなくなるおそれがある。そう思って見るならば、この『源氏物語』という作品は、男性の側に都合のいいように書かれていることに気付く。夫とする男に新しい女性が現れたとき、元の女性の立場はどうなるのか……男がまだ自分のことを思っていてくれるならばいいが、心がはなれてしまえば、それまでである。この観点からするならば、前に出てきた玉鬘の夫になった髭黒の対象の北の方の乱心ぶりが、ある意味で納得されるところがある。だからこそ、一度関係をもった女性の面倒は最後までみるという光源氏の生き方が理想化されることになる。光源氏ほどの男性のものである紫の上でさえ、新しい女性の出現にはこころがゆれる。ましてや、他の男と女の関係においておや、というところであろうか。
第二には、子どもである。
女三の宮は子どもを産むことになる。後の薫である。その出産からはじめて、六条院での幼いときの薫の様子が描かれる。読んでいて、おもわずほほえんでしまうようなところがある。子ども、それも乳幼児というべき幼い子どもの描写としては、実にリアルであるし、また、読んでいて、子どもに対する愛情というものを感じてしまう。このあたりの叙述は、おそらくは、作者……紫式部……の体験をふまえてのものなのかと思う。
平安時代の貴族にとって、「家庭」とはなんであったのだろうか。おそらく、今日の現代社会のものとは違っていたにちがいない。が、そうは思って見ても、子どもへの情愛というものは、今にも通じるものがあると感じる。
この他にもいろいろ思うところがあるが、ともかく以上の二点を書きとめておく。次の冊から、いよいよ「宇治十帖」をふくむ部分になる。ここは、一気に読んでしまおうと思う。
追記 2019-12-30
この続きは、
やまもも書斎記 2019年12月30日
新潮日本古典集成『源氏物語』(六)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/12/30/9195432
この続きは、
やまもも書斎記 2019年12月30日
新潮日本古典集成『源氏物語』(六)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/12/30/9195432
『いだてん』あれこれ(余談) ― 2019-12-24
2019-12-24 當山日出夫(とうやまひでお)
NHKの大河ドラマ『いだてん~東京オリムピック噺~』が終わった。先週は、もう放送がなかった。ここで、ふりかえっていろいろ思いつくことなど書いてみたい。毎週、火曜日は、大河ドラマについて書くことにしてきたので、その習慣の延長のようなものである。
このドラマが描いてみせたのは、ひょっとすると「明治の精神」ということであったかもしれない。前半の主人公である金栗四三は無論のこと、後半の田畑政治も明治の生まれである。また、重要な登場人物である嘉納治五郎しかりである。
メインの登場人物は、明治に生まれている。そして、その目指したものは、「明治の精神」としての近代スポーツであったのかもしれない、と思う。ドラマがはじまったころ、このドラマは、スポーツにおける「坂の上の雲」であるのだろう……このような意味のことを書いた記憶がある。
司馬遼太郎の『坂の上の雲』は、日露戦争で終わっている。その後ことを、司馬遼太郎は書かなかった。あるいは、書けなかったというべきだろうか。(司馬遼太郎のことについては、折りにふれて、このブログでも書いてきたと思う。)
その日露戦争が終わって、日本が「一等国」になったということは、すなわち、オリンピックに参加するということにつながっている。その結果は、はかばかしくなかった。金栗はマラソンで行方不明になるし、三島は競技を途中で放棄してしまったと憶えている(このあたり、実際どうであったか、総集編でも見て再確認したいと思うが。)
今から思ってみるなば、きわめてみじめな結果に終わったストックホルム大会であった。
だが、そのような結果になったとはいえ、「NIPPON」と書いたプラカードを持ち、日章旗をかかげて、参加した。このとき、日本国政府からの公的な支援はなかった。だが、その参加者(金栗、三島)は、確かに「日本」というものを、国際社会のなかで意識することになった。まさに、「坂の上の雲」をめざした、「明治の精神」を体現していたと言ってよいだろう。
その「坂の上の雲」を最も感じさせたのは、(途中で死んでしまうことになる)嘉納治五郎である。国の枠を越えて純粋にスポーツのみで勝敗をあらそう、この近代オリンピックの精神を、常に説きつづけてきた。
しかし、その嘉納治五郎は、やはり「日本」というものを強く意識していたのかもしれない。国という枠を越えようとするならば、その前にまず国を作らなければならない。ここには、アンビバレントな意識の交錯がある。
『いだてん』というドラマは、いろんな場面で、日章旗が登場しており、また、「日本」を背負って試合にのぞむ選手たちを描いてきた。その代表が、前畑秀子であったといえようか。あるいは、終盤に登場した、女子バレーボールの選手たちもそうだろう。
にもかかわらず、ドラマをみながら、ナショナリズムを感じさせることは、あまりなかった。「日本」を背負っている選手たちを描きながら、同時に、ひたむきにスポーツに打ち込む人間としての側面も描いてきた。
ここには、ナショナリズムを相対化してみる、距離をおいた視点のとりかたがあった。これを、最も代表していたのが、志ん生であった。
志ん生もまた「明治」の人間である。だが、志ん生に、「坂の上の雲」を感じるとことは、まったくなかった。放逸な人生であり、刹那的に生きている。が、芸にかける執念はある。このような人物を、ドラマの語り手にもってきたことによって、「たかがオリンピック」「たかが日本」と、毒をもって笑い飛ばすことができていたのかと思う。
金栗四三や嘉納治五郎が「明治」の人間であるならば、同時に、志ん生もまた「明治」の人間である。このように多彩な視点で「明治」「明治の精神」を描いたところに、このドラマの良さがあったのだと思う。
『いだてん』は、視聴率はよくなかったようである。その理由のひとつに、ナショナリズムの描き方があったと思う。来年は、二〇二〇東京オリンピックである。否応なく、スポーツとナショナリズムが結びつくことになる。スポーツにおける「坂の上の雲」を描きながら、ナショナリズムを感じさせない脚本では、やはり視聴率に結びつかなかったのだろう。(何度も書いているが、私はナショナリズム自体を悪いものだとは思っていない。)
そして、思うことは、志ん生の弟子になる、五りんである。金栗の物語と、志ん生の物語を架橋する役割を担うことになる登場人物である。確かに、この五りんの存在によって、物語の筋は通ったかもしれない。
だが、その一方で、ドラマは「オリンピック人情噺」になってしまった。ここは、もっと志ん生という人間を、毒をもった存在として描いた方がよかったのかもしれない。どうもドラマの終わりの方になって、志ん生が、好々爺になってしまったような印象がある。
……以上、「明治の精神」からはじめて、思いつくままに書いてみた。
司馬遼太郎が、『坂の上の雲』を日露戦争の勝利で小説を終わらせて、その後を書かなかったのと同じように、このドラマにおいては、一九六四年東京オリンピックで終わらざるをえないのかとも思う。スポーツにおける「明治の精神」は、そこでようやく終焉を見たことになるのだろう。
2019年12月23日記
このドラマが描いてみせたのは、ひょっとすると「明治の精神」ということであったかもしれない。前半の主人公である金栗四三は無論のこと、後半の田畑政治も明治の生まれである。また、重要な登場人物である嘉納治五郎しかりである。
メインの登場人物は、明治に生まれている。そして、その目指したものは、「明治の精神」としての近代スポーツであったのかもしれない、と思う。ドラマがはじまったころ、このドラマは、スポーツにおける「坂の上の雲」であるのだろう……このような意味のことを書いた記憶がある。
司馬遼太郎の『坂の上の雲』は、日露戦争で終わっている。その後ことを、司馬遼太郎は書かなかった。あるいは、書けなかったというべきだろうか。(司馬遼太郎のことについては、折りにふれて、このブログでも書いてきたと思う。)
その日露戦争が終わって、日本が「一等国」になったということは、すなわち、オリンピックに参加するということにつながっている。その結果は、はかばかしくなかった。金栗はマラソンで行方不明になるし、三島は競技を途中で放棄してしまったと憶えている(このあたり、実際どうであったか、総集編でも見て再確認したいと思うが。)
今から思ってみるなば、きわめてみじめな結果に終わったストックホルム大会であった。
だが、そのような結果になったとはいえ、「NIPPON」と書いたプラカードを持ち、日章旗をかかげて、参加した。このとき、日本国政府からの公的な支援はなかった。だが、その参加者(金栗、三島)は、確かに「日本」というものを、国際社会のなかで意識することになった。まさに、「坂の上の雲」をめざした、「明治の精神」を体現していたと言ってよいだろう。
その「坂の上の雲」を最も感じさせたのは、(途中で死んでしまうことになる)嘉納治五郎である。国の枠を越えて純粋にスポーツのみで勝敗をあらそう、この近代オリンピックの精神を、常に説きつづけてきた。
しかし、その嘉納治五郎は、やはり「日本」というものを強く意識していたのかもしれない。国という枠を越えようとするならば、その前にまず国を作らなければならない。ここには、アンビバレントな意識の交錯がある。
『いだてん』というドラマは、いろんな場面で、日章旗が登場しており、また、「日本」を背負って試合にのぞむ選手たちを描いてきた。その代表が、前畑秀子であったといえようか。あるいは、終盤に登場した、女子バレーボールの選手たちもそうだろう。
にもかかわらず、ドラマをみながら、ナショナリズムを感じさせることは、あまりなかった。「日本」を背負っている選手たちを描きながら、同時に、ひたむきにスポーツに打ち込む人間としての側面も描いてきた。
ここには、ナショナリズムを相対化してみる、距離をおいた視点のとりかたがあった。これを、最も代表していたのが、志ん生であった。
志ん生もまた「明治」の人間である。だが、志ん生に、「坂の上の雲」を感じるとことは、まったくなかった。放逸な人生であり、刹那的に生きている。が、芸にかける執念はある。このような人物を、ドラマの語り手にもってきたことによって、「たかがオリンピック」「たかが日本」と、毒をもって笑い飛ばすことができていたのかと思う。
金栗四三や嘉納治五郎が「明治」の人間であるならば、同時に、志ん生もまた「明治」の人間である。このように多彩な視点で「明治」「明治の精神」を描いたところに、このドラマの良さがあったのだと思う。
『いだてん』は、視聴率はよくなかったようである。その理由のひとつに、ナショナリズムの描き方があったと思う。来年は、二〇二〇東京オリンピックである。否応なく、スポーツとナショナリズムが結びつくことになる。スポーツにおける「坂の上の雲」を描きながら、ナショナリズムを感じさせない脚本では、やはり視聴率に結びつかなかったのだろう。(何度も書いているが、私はナショナリズム自体を悪いものだとは思っていない。)
そして、思うことは、志ん生の弟子になる、五りんである。金栗の物語と、志ん生の物語を架橋する役割を担うことになる登場人物である。確かに、この五りんの存在によって、物語の筋は通ったかもしれない。
だが、その一方で、ドラマは「オリンピック人情噺」になってしまった。ここは、もっと志ん生という人間を、毒をもった存在として描いた方がよかったのかもしれない。どうもドラマの終わりの方になって、志ん生が、好々爺になってしまったような印象がある。
……以上、「明治の精神」からはじめて、思いつくままに書いてみた。
司馬遼太郎が、『坂の上の雲』を日露戦争の勝利で小説を終わらせて、その後を書かなかったのと同じように、このドラマにおいては、一九六四年東京オリンピックで終わらざるをえないのかとも思う。スポーツにおける「明治の精神」は、そこでようやく終焉を見たことになるのだろう。
2019年12月23日記
ハゼノキ ― 2019-12-25
2019-12-25 當山日出夫(とうやまひでお)
水曜日なので花の写真の日。今日は花ではなく、ハゼノキの紅葉である。
前回は、
やまもも書斎記 2019年12月18日
ガマズミ
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/12/18/9190652
たぶん、ハゼノキだろうと思ってみている。我が家の近辺のかなりのところで目にする。散歩で歩いていると、紅葉した葉っぱが印象的である。
日本国語大辞典(ジャパンナレッジ)を見る。
「はぜのき」で項目がある。
ウルシ科の落葉高木。昔、琉球から渡来したもので、実から蝋(ろう)を採るために栽培されていたものが野生化し、今では、本州の関東以西・四国・九州の暖地に生える。
とあり、さらに説明がある。用例は、書言字考節用集(1717)、日本植物名彙(1884)などからとってある。江戸時代からこの語でつかわれていたようである。
日本植物名彙に「ハゼノキ」とあるのは、これが正式名称、学名ということになるのだろう。ただ、「はぜ」で検索してみると、
「はぜのき(黄櫨)」の異名、とあって、用例は、饅頭屋本節用集(室町末)から見える。また、『言海』にも、「はぜ」であるようだ。
『言海』を見ると、「はぜ」の項目には、「黄櫨(ハジ)ノ轉、其條ヲ見ヨ。」とある。さらに、「はじ」の項目を探すと、
はじ 黄櫨 名 〔はにしノ約〕 又、ハニシ。今、ハゼ。ヤマウルシ。漆ノ木ノ一種、山中ニ多シ、葉ハ漆ニ似テ粗キ鋸齒アリ、木心、黄ナリ、古ヘ、染料トス、黄櫨染(クワウロゼン)コレナリ、秋早ク紅葉スルガ故ニ、はじもみぢナド、歌ニモ詠メリ。又、一種、實ヨリ蝋ヲ採ルモノヲモ、はぜ、はぜうるし、らふのきナドイフ、諸國ニ多ク栽ウ、葉ハ、漆ニ似テ鋸齒無ク長大ニシテ、實モ亦大ナリ。
と、ここまで書いてみて、気付いた。「黄櫨染」ということばは最近目にした。今上天皇の即位の礼のときである。その衣服が、「黄櫨染の御袍」であった。辞書はひいてみるもの、いや今では、検索してみるものである。
水曜日なので花の写真の日。今日は花ではなく、ハゼノキの紅葉である。
前回は、
やまもも書斎記 2019年12月18日
ガマズミ
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/12/18/9190652
たぶん、ハゼノキだろうと思ってみている。我が家の近辺のかなりのところで目にする。散歩で歩いていると、紅葉した葉っぱが印象的である。
日本国語大辞典(ジャパンナレッジ)を見る。
「はぜのき」で項目がある。
ウルシ科の落葉高木。昔、琉球から渡来したもので、実から蝋(ろう)を採るために栽培されていたものが野生化し、今では、本州の関東以西・四国・九州の暖地に生える。
とあり、さらに説明がある。用例は、書言字考節用集(1717)、日本植物名彙(1884)などからとってある。江戸時代からこの語でつかわれていたようである。
日本植物名彙に「ハゼノキ」とあるのは、これが正式名称、学名ということになるのだろう。ただ、「はぜ」で検索してみると、
「はぜのき(黄櫨)」の異名、とあって、用例は、饅頭屋本節用集(室町末)から見える。また、『言海』にも、「はぜ」であるようだ。
『言海』を見ると、「はぜ」の項目には、「黄櫨(ハジ)ノ轉、其條ヲ見ヨ。」とある。さらに、「はじ」の項目を探すと、
はじ 黄櫨 名 〔はにしノ約〕 又、ハニシ。今、ハゼ。ヤマウルシ。漆ノ木ノ一種、山中ニ多シ、葉ハ漆ニ似テ粗キ鋸齒アリ、木心、黄ナリ、古ヘ、染料トス、黄櫨染(クワウロゼン)コレナリ、秋早ク紅葉スルガ故ニ、はじもみぢナド、歌ニモ詠メリ。又、一種、實ヨリ蝋ヲ採ルモノヲモ、はぜ、はぜうるし、らふのきナドイフ、諸國ニ多ク栽ウ、葉ハ、漆ニ似テ鋸齒無ク長大ニシテ、實モ亦大ナリ。
と、ここまで書いてみて、気付いた。「黄櫨染」ということばは最近目にした。今上天皇の即位の礼のときである。その衣服が、「黄櫨染の御袍」であった。辞書はひいてみるもの、いや今では、検索してみるものである。
Nikon D500
AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR
AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR
2019年12月24日記
『明暗』夏目漱石 ― 2019-12-26
2019-12-26 當山日出夫(とうやまひでお)
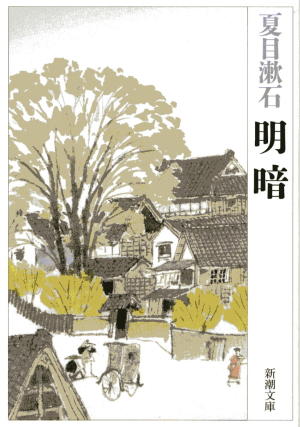
夏目漱石.『明暗』(新潮文庫).新潮社.1987(2010.改版)
https://www.shinchosha.co.jp/book/101019/
続きである。
やまもも書斎記 2019年12月21日
『道草』夏目漱石
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/12/21/9191933
ことし、ふとおもいたって、『草枕』を読んでみた。
やまもも書斎記
『草枕』夏目漱石 2019年7月19日
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/07/19/9130514
この『草枕』のつぎに『明暗』を読んだ。
やまもも書斎記 2019年7月25日
『明暗』夏目漱石
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/07/25/9133086
その後、新潮文庫版で、夏目漱石の作品を読んでおきたくなったので、今、刊行されている分について、順番に買ってよんできた。そして、再度、『明暗』を読んでみたくなって読んだ。
はっきり言って、若いころ、『明暗』という小説は苦手だった。いまひとつその面白さが分からなかったと言える。だが、今、この年になって(もう、還暦をすぎて数年経過している)、漱石の作品を手にとるなかで、この『明暗』が、一番面白いと感じる。
まさに、近代を代表する小説になっていると感じるところがある。特に波瀾万丈の大活劇があるという小説ではない。作品中における時間の経過は、わずかのものにすぎない。登場人物も少ないと言っていいだろう。
が、その少ない登場人物たちのくりひろげる、人間の精神のドラマとでもいうべきものに、魅了されていることになる。とにかく、読んでいて面白いと感じるようになってきた。
その『明暗』の面白さを、国語学の観点から見るならば、やはり、登場人物のつかっていることばにあるだろう。
『三四郎』からはじまって、『こころ』にいたるまで、漱石は、女学生ことばをつかう女性を軸にすえて作品を書いてきている。それが、『道草』でなくなる。そして、『明暗』になると、基本的に、女性の登場人物は、女学生ことばを使っていない。(一部、例外的に、それかと思われる場面があるのだが、これはこれで別の問題があると思う。)
漱石が、女性のこころのうちを描くようになったのは、『明暗』においてであると言っていいだろう。それまでの漱石は、男性主人公の目で描いていた。女性は、あくまでも、見られる立場であった。主体性をもって行動するということがなかった。
しかし、『明暗』になると、女性の登場人物の心理描写、それから、会話文が圧倒的な迫力をもってせまってくる。時代が大正になり、二〇世紀の文学を書こうとした漱石の姿が、そこにはあると思う。
たとえば、津田の細君の名前は、いったい何なのであろうか。「お延」と書かれるところもあれば(地の文においては「お延」である)、会話の相手によって、「延子」「延子さん」と呼称されている。津田の妹の「お秀」についても、同様である。「お秀」と出てくるところもあれば、「秀子」になっているところもある。
このような箇所、気をつけながら読んでみたのだが、というよりも、今回、読みなおしてみて初めて気がついたというべきだが……漱石は、実にこまやかに、このような登場人物の呼称を、使い分けている。その使い分けで、会話している人間の、相手に対する立場や考え方を、暗に示している。
人間の精神のドラマとして読んでこそ、『明暗』は面白い。無論、その対極にある『草枕』の世界にもひかれるところがある。しかし、晩年の漱石が、人間のこころのうちを描いていって、その奥底にあるもの……エゴイズムと言っていいだろう……を、小説で描くことに到達したのが、『明暗』という作品であると感じるところがある。
この『明暗』は、今年になって、新潮文庫版で二回読んでいる。以前は、「漱石全集」で読んだり、「岩波文庫」で読んだりしてきた。新しい「定本漱石全集」で、刊行になったときにも読んでいる。
やまもも書斎記 2017年11月10日
『明暗』夏目漱石
http://yamamomo.m.asablo.jp/blog/2017/11/10/8724386
また、機会をみて、さらに『明暗』を読んでみたいと思う。
2019年12月19日記
『アンナ・カレーニナ』トルストイ/望月哲男(訳)(一) ― 2019-12-27
2019-12-27 當山日出夫(とうやまひでお)

トルストイ.望月哲男(訳).『アンナ・カレーニナ』(一)(光文社古典新訳文庫).光文社.2008
https://www.kotensinyaku.jp/books/book58/
『アンナ・カレーニナ』については、以前、新潮文庫版で読んだ。
やまもも書斎記 2017年1月7日
『アンナ・カレーニナ』トルストイ(新潮文庫)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2017/01/07/8307206
「古典」を読んで時間をつかいたくなってきている。そう思って、『アンナ・カレーニナ』の新しい訳を読んでみることにした。新潮文庫版で読んだのは、約三年ほど前のことになる。このときは、ほぼ一気に全巻を読んだ。今回は、じっくりと味読しながら読んでみようと思う。
以前に読んだ新潮文庫版は、木村浩の訳。文庫としては、1972年(昭和47年)の刊行である。半世紀ほど前の本になる。
まず、光文社古典新訳文庫版(望月哲男訳)の第一冊目である。これを訳している望月哲男のロシア語訳については、ドストエフスキーの『死の家の記録』を読んで、その分かりやすい訳文がいいと思ったことがある。また、光文社古典新訳文庫では、『戦争と平和』(トルストイ)を、望月哲男訳で刊行の予定らしい。
読んで、自分自身で気付くことは、この小説は一九世紀の小説だな、ということ。心理描写が客観的である。これは、去年のことになるが、『失われた時を求めて』(プルースト)を全巻読んだ、その読書経験を経た目で感じることである。
やまもも書斎記 2018年11月1日
『失われた時を求めて』岩波文庫(1)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/11/01/8986844
新しい訳の『アンナ・カレーニナ』であるが……今回、キティという女性の描写がきめ細やかなことに、こころがとまった。無論、この小説においては、その他の登場人物……たとえば、リョーヴィンなど……についても、細かな心理描写がある。それは分かって読むのだが、トルストイは、若い女性のこころのうちを描くのが実にうまいと感じる。
この小説は、一九世紀のロシアが舞台である。しかも、貴族、地主といった人びとが主な登場人物である。今の日本の市井の人びととは、その生活も意識も大きくことなる。だが、読んでいって、思わずにその登場人物のこころの動きに共感してしてしまう自分に気付くことがある。こういうのを、文学的な感銘というのであろう。
それにしても、貴族とはいっても、その生活は楽なものではなかったようだ。光文社古典新訳文庫版の解説を読むと、その当時のロシアの貴族の生活や経済状況について、丁寧に解説してある。これを先に読んだせいかもしれないが、読みながら、貴族の生活といっても大変だなあと、ふと思ってしまう。
また、鉄道のことがある。この『アンナ・カレーニナ』という作品の終わりの方で、鉄道が非常に大きな意味をもつことになる。以前に読んでそのことを知っているのだが、再度読んでみて、ヒロインのアンナ・カレーニナの小説での登場が、まさに鉄道によっていることを、再確認することになった。一九世紀という時代、鉄道というものが、人びとの生活のなかにはいってきて、その行動や価値観に大きな影響をあたえたことが理解される。
漱石の作品(新潮文庫版)を読み終えたので、順次、『アンナ・カレーニナ』(四冊)を読んでいくことにしたい。
https://www.kotensinyaku.jp/books/book58/
『アンナ・カレーニナ』については、以前、新潮文庫版で読んだ。
やまもも書斎記 2017年1月7日
『アンナ・カレーニナ』トルストイ(新潮文庫)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2017/01/07/8307206
「古典」を読んで時間をつかいたくなってきている。そう思って、『アンナ・カレーニナ』の新しい訳を読んでみることにした。新潮文庫版で読んだのは、約三年ほど前のことになる。このときは、ほぼ一気に全巻を読んだ。今回は、じっくりと味読しながら読んでみようと思う。
以前に読んだ新潮文庫版は、木村浩の訳。文庫としては、1972年(昭和47年)の刊行である。半世紀ほど前の本になる。
まず、光文社古典新訳文庫版(望月哲男訳)の第一冊目である。これを訳している望月哲男のロシア語訳については、ドストエフスキーの『死の家の記録』を読んで、その分かりやすい訳文がいいと思ったことがある。また、光文社古典新訳文庫では、『戦争と平和』(トルストイ)を、望月哲男訳で刊行の予定らしい。
読んで、自分自身で気付くことは、この小説は一九世紀の小説だな、ということ。心理描写が客観的である。これは、去年のことになるが、『失われた時を求めて』(プルースト)を全巻読んだ、その読書経験を経た目で感じることである。
やまもも書斎記 2018年11月1日
『失われた時を求めて』岩波文庫(1)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/11/01/8986844
新しい訳の『アンナ・カレーニナ』であるが……今回、キティという女性の描写がきめ細やかなことに、こころがとまった。無論、この小説においては、その他の登場人物……たとえば、リョーヴィンなど……についても、細かな心理描写がある。それは分かって読むのだが、トルストイは、若い女性のこころのうちを描くのが実にうまいと感じる。
この小説は、一九世紀のロシアが舞台である。しかも、貴族、地主といった人びとが主な登場人物である。今の日本の市井の人びととは、その生活も意識も大きくことなる。だが、読んでいって、思わずにその登場人物のこころの動きに共感してしてしまう自分に気付くことがある。こういうのを、文学的な感銘というのであろう。
それにしても、貴族とはいっても、その生活は楽なものではなかったようだ。光文社古典新訳文庫版の解説を読むと、その当時のロシアの貴族の生活や経済状況について、丁寧に解説してある。これを先に読んだせいかもしれないが、読みながら、貴族の生活といっても大変だなあと、ふと思ってしまう。
また、鉄道のことがある。この『アンナ・カレーニナ』という作品の終わりの方で、鉄道が非常に大きな意味をもつことになる。以前に読んでそのことを知っているのだが、再度読んでみて、ヒロインのアンナ・カレーニナの小説での登場が、まさに鉄道によっていることを、再確認することになった。一九世紀という時代、鉄道というものが、人びとの生活のなかにはいってきて、その行動や価値観に大きな影響をあたえたことが理解される。
漱石の作品(新潮文庫版)を読み終えたので、順次、『アンナ・カレーニナ』(四冊)を読んでいくことにしたい。
追記 2019-12-28
この続きは、
やまもも書斎記 2019年12月8日
『アンナ・カレーニナ』トルストイ/望月哲男(訳)(二)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/12/28/9194579
この続きは、
やまもも書斎記 2019年12月8日
『アンナ・カレーニナ』トルストイ/望月哲男(訳)(二)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/12/28/9194579
『アンナ・カレーニナ』トルストイ/望月哲男(訳)(二) ― 2019-12-28
2019-12-28 當山日出夫(とうやまひでお)

続きである。
やまもも書斎記 2019年12月27日
『アンナ・カレーニナ』トルストイ/望月哲男(訳)(一)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/12/27/9194202
第二冊目には、第三部、第四部をおさめる。これを読んで思うことなど書くと、次の二点ぐらいだろうか。
第一には、特にリョーヴィンをめぐる描写。
その農村での農作業の様子が興味深い。農村といっても、無論、日本の農業とはちがう。ロシアのそれである。しかも、革命前の。そのようなことは分かって読むのだが、読んでいて、ふとその農業に従事する労働の充足感とでもいうべきものがつたわってくる。
解説によると、『アンナ・カレーニナ』のなかで、農村の部分はあまり人の興味をひかない部分であるとされているようだ。そのように読めば、そうかなと思う。そう深く、登場人物の心理描写、心理的な劇的なドラマがあるというのではない。
しかし、労働というものになにがしか充実した感覚を見出すとするならば、これは、古今東西を問わず普遍的に語ることのできものではないだろうか。もしそうであるとするならば、この『アンナ・カレーニナ』における、農作業の描写は、労働というものを描いた屈指の文学であるといえるかもしれない。
ただ、その当時のロシアの農村の社会的な歴史的な制度の問題については、不案内なので、今一つ理解のおよばないと感じるところがないではない。
第二には、離婚をめぐる煩悶。
カレーニンは、アンナと離婚するかどうか、悩むことになる。どうもこのあたりのことも、今の日本の婚姻制度、離婚・結婚のシステムと、その当時のロシアのそれとはちがっているので、今ひとつもどかしく思って読むことになる。このことに配慮して、この第二冊の解説では、ロシアにおける離婚の制度について、分かりやすく解説してある。この解説を読むと、なるほどと理解するところがある。
アンナをめぐる三角関係……カレーニンとヴロンスキー……この登場人物のこころのうちに、読みながら、ふとそのドラマチックな展開によみふけってしまう。どの人物に共感するということもないのではあるが、のっぴきならない関係にはいりこんでしまった登場人物たちの、心理のドラマは、まさに一九世紀の小説ならではの物語である。そして、おそらくは、その最高峰にあると言っていいのかもしれない。
以上の二点が、第二冊目を読んで思うことなどである。
この小説、以前にも読んでいる。だから、そのあらすじは知っているのだが、読みなおしてみて、思わずにその物語のなかにはいりこんでしまうことに気付く。小説というかたちで人間を描くという意味において、この作品は、いまなお人をひきつける魅力に満ちている。
ふと気になったこととしてであるが……キティを思うリョーヴィンが、信仰が無いと書いてある。さて、トルストイの文学において宗教というのは重要な意味を持っていると思うのだが、ここで無信仰としてあることの意味は、どういうことなのであろうか。このあたり留意しながら、三冊目以降を読むことにしよう。
やまもも書斎記 2019年12月27日
『アンナ・カレーニナ』トルストイ/望月哲男(訳)(一)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/12/27/9194202
第二冊目には、第三部、第四部をおさめる。これを読んで思うことなど書くと、次の二点ぐらいだろうか。
第一には、特にリョーヴィンをめぐる描写。
その農村での農作業の様子が興味深い。農村といっても、無論、日本の農業とはちがう。ロシアのそれである。しかも、革命前の。そのようなことは分かって読むのだが、読んでいて、ふとその農業に従事する労働の充足感とでもいうべきものがつたわってくる。
解説によると、『アンナ・カレーニナ』のなかで、農村の部分はあまり人の興味をひかない部分であるとされているようだ。そのように読めば、そうかなと思う。そう深く、登場人物の心理描写、心理的な劇的なドラマがあるというのではない。
しかし、労働というものになにがしか充実した感覚を見出すとするならば、これは、古今東西を問わず普遍的に語ることのできものではないだろうか。もしそうであるとするならば、この『アンナ・カレーニナ』における、農作業の描写は、労働というものを描いた屈指の文学であるといえるかもしれない。
ただ、その当時のロシアの農村の社会的な歴史的な制度の問題については、不案内なので、今一つ理解のおよばないと感じるところがないではない。
第二には、離婚をめぐる煩悶。
カレーニンは、アンナと離婚するかどうか、悩むことになる。どうもこのあたりのことも、今の日本の婚姻制度、離婚・結婚のシステムと、その当時のロシアのそれとはちがっているので、今ひとつもどかしく思って読むことになる。このことに配慮して、この第二冊の解説では、ロシアにおける離婚の制度について、分かりやすく解説してある。この解説を読むと、なるほどと理解するところがある。
アンナをめぐる三角関係……カレーニンとヴロンスキー……この登場人物のこころのうちに、読みながら、ふとそのドラマチックな展開によみふけってしまう。どの人物に共感するということもないのではあるが、のっぴきならない関係にはいりこんでしまった登場人物たちの、心理のドラマは、まさに一九世紀の小説ならではの物語である。そして、おそらくは、その最高峰にあると言っていいのかもしれない。
以上の二点が、第二冊目を読んで思うことなどである。
この小説、以前にも読んでいる。だから、そのあらすじは知っているのだが、読みなおしてみて、思わずにその物語のなかにはいりこんでしまうことに気付く。小説というかたちで人間を描くという意味において、この作品は、いまなお人をひきつける魅力に満ちている。
ふと気になったこととしてであるが……キティを思うリョーヴィンが、信仰が無いと書いてある。さて、トルストイの文学において宗教というのは重要な意味を持っていると思うのだが、ここで無信仰としてあることの意味は、どういうことなのであろうか。このあたり留意しながら、三冊目以降を読むことにしよう。
追記 2020-01-04
この続きは、
やまもも書斎記 2020年1月4日
『アンナ・カレーニナ』トルストイ/望月哲男(訳)(三)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/01/04/9197937
この続きは、
やまもも書斎記 2020年1月4日
『アンナ・カレーニナ』トルストイ/望月哲男(訳)(三)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/01/04/9197937
『スカーレット』あれこれ「愛いっぱいの器」 ― 2019-12-29
2019-12-29 當山日出夫(とうやまひでお)
『スカーレット』第13週「愛いっぱいの器」
https://www.nhk.or.jp/scarlet/story/index13_191223.html
前回は、
やまもも書斎記 2019年12月22日
『スカーレット』あれこれ「幸せへの大きな一歩」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/12/22/9192346
この週で、父がなくなった。そこのところの経緯をじっくりと描いていた週であった。
この『スカーレット』というドラマは、緩急がはっきりしている。いそいで話しをとばしてしまうところは、あっというまに先に進んでしまう。だが、じっくりと描くとなると、本当に丁寧な描写になる。
父が病におかされる。余命いくばくもないらしい。その死を目前にしての家族の気持ち、周囲の人びとのこころづかいといったものを、非常にゆっくりと時間をかけて描いていた週であった。これまで、朝ドラでは、何人もの人の死を描いてきている。そのなかにあって、この『スカーレット』の父の死のシーンは、特に印象に残るものではないだろうか。
そして、週の最後になって、ジョージ富士川の再登場であった。ここで、喜美子は自分自身が陶芸家になる気持ちを確認することになるようだ。陶芸の技術は夫の八郎から学ぶことができるかもしれない。だが、芸術という創造の世界になると、完全に個人の領域のことになる。(近代における芸術とは、そのようなものである。)
これから喜美子は陶芸家になっていくのであろう。そのとき、家族の一員、母であり、妻であるということと、創造にたずさわる芸術家であることと、この両面をどのように描いていくことになるのだろうか。
芸術の世界のことを描くのは、近年の朝ドラでは珍しいことかもしれないと思う。ともあれ、年内の放送は終わった。陶芸家として自立する姿を描くのは、来年の放送になってからのことであろう。楽しみに見ることにしよう。
『スカーレット』第13週「愛いっぱいの器」
https://www.nhk.or.jp/scarlet/story/index13_191223.html
前回は、
やまもも書斎記 2019年12月22日
『スカーレット』あれこれ「幸せへの大きな一歩」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/12/22/9192346
この週で、父がなくなった。そこのところの経緯をじっくりと描いていた週であった。
この『スカーレット』というドラマは、緩急がはっきりしている。いそいで話しをとばしてしまうところは、あっというまに先に進んでしまう。だが、じっくりと描くとなると、本当に丁寧な描写になる。
父が病におかされる。余命いくばくもないらしい。その死を目前にしての家族の気持ち、周囲の人びとのこころづかいといったものを、非常にゆっくりと時間をかけて描いていた週であった。これまで、朝ドラでは、何人もの人の死を描いてきている。そのなかにあって、この『スカーレット』の父の死のシーンは、特に印象に残るものではないだろうか。
そして、週の最後になって、ジョージ富士川の再登場であった。ここで、喜美子は自分自身が陶芸家になる気持ちを確認することになるようだ。陶芸の技術は夫の八郎から学ぶことができるかもしれない。だが、芸術という創造の世界になると、完全に個人の領域のことになる。(近代における芸術とは、そのようなものである。)
これから喜美子は陶芸家になっていくのであろう。そのとき、家族の一員、母であり、妻であるということと、創造にたずさわる芸術家であることと、この両面をどのように描いていくことになるのだろうか。
芸術の世界のことを描くのは、近年の朝ドラでは珍しいことかもしれないと思う。ともあれ、年内の放送は終わった。陶芸家として自立する姿を描くのは、来年の放送になってからのことであろう。楽しみに見ることにしよう。
2019年12月28日記
追記 2020-01-12
この続きは、
やまもも書斎記 2020年1月12日
『スカーレット』あれこれ「新しい風が吹いて」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/01/12/9200942
この続きは、
やまもも書斎記 2020年1月12日
『スカーレット』あれこれ「新しい風が吹いて」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/01/12/9200942
新潮日本古典集成『源氏物語』(六) ― 2019-12-30
2019-12-30 當山日出夫(とうやまひでお)

石田穣二・清水好子(校注).『源氏物語』(六)新潮日本古典集成(新装版).新潮社.2014
https://www.shinchosha.co.jp/book/620823/
続きである。
やまもも書斎記 2019年12月23日
新潮日本古典集成『源氏物語』(五)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/12/23/9192818
この本を以前に読んだときのものは、
やまもも書斎記 2019年2月28日
『源氏物語』(六)新潮日本古典集成
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/02/28/9041643
新潮版の第六冊目には「夕霧」から「椎本」までをおさめる。つまり、光源氏の栄華が頂点に達し、同時に、女三の宮の柏木との不義の件があってからのちのこと、紫の上の死から、光源氏の死(ただ、これは暗示されるだけであるが)、そしてその後の人びとのことなど。これが終わって、次に「橋姫」の巻から「宇治十帖」にはいることになる。
ここまで読んで来て感じることは、やはり『源氏物語』の成立論である。次のように思って見る……それは、「宇治十帖」は本編の光源氏の物語が終わってからすぐに書かれた。しかし、その時、いったん、光源氏の物語は終了する必要があった。そのために、「匂兵部卿」「紅梅」「竹河」の巻が書かれた。これらの巻は、光源氏なきあとの後日譚であるが、いかにも、強引に話を終了にもっていったとおぼしい。自然に、光源氏の物語を終わりにするならば、もっと別の書き方があって、余韻を残すこともできたであろう。
では、いつごろ「宇治十帖」が構想されたのか、それは、おそらく「若菜 上・下」を書いているあたりであったのかもしれない。光源氏の栄華の頂点であると同時に、女三宮の降嫁、そして、柏木との不倫。その結果生まれることになる薫。この薫の幼いときの様子が、いかにも印象的である。この薫が成長してどのような人間になるのか、薫を主人公とした物語を書いてみたい、そう思ったのではないだろうか。
たぶん、こんなことは『源氏物語』研究の世界では、とっくに言われていることだろうと思う。私も、今更、『源氏物語』の成立論にかかわるような論文を書いてみたいとも思っていない。
だが、今日において、一人の読者の立場で、『源氏物語』を最初から読んできてみて、上述のような思いをどうしても持ってしまうのである。
そして、「宇治十帖」の作者は、おそらく紫式部だろう。その叙述のなかにみられる、風景描写の見事さ。視覚と聴覚にわたって、あたり全体を俯瞰しながら、場面の転換をはかる……このような筆致は、本編ほどのあざやかさはないとはいえ、「宇治十帖」にも見て取れる。視覚と聴覚にわたり全体を俯瞰しながら、話題の焦点にポイントをもっていく、これは、『紫式部日記』の冒頭に見られる見事な文章に通じるものがある。
さて、次は、残る二冊である。このまま読んでしまうことにする。
https://www.shinchosha.co.jp/book/620823/
続きである。
やまもも書斎記 2019年12月23日
新潮日本古典集成『源氏物語』(五)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/12/23/9192818
この本を以前に読んだときのものは、
やまもも書斎記 2019年2月28日
『源氏物語』(六)新潮日本古典集成
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/02/28/9041643
新潮版の第六冊目には「夕霧」から「椎本」までをおさめる。つまり、光源氏の栄華が頂点に達し、同時に、女三の宮の柏木との不義の件があってからのちのこと、紫の上の死から、光源氏の死(ただ、これは暗示されるだけであるが)、そしてその後の人びとのことなど。これが終わって、次に「橋姫」の巻から「宇治十帖」にはいることになる。
ここまで読んで来て感じることは、やはり『源氏物語』の成立論である。次のように思って見る……それは、「宇治十帖」は本編の光源氏の物語が終わってからすぐに書かれた。しかし、その時、いったん、光源氏の物語は終了する必要があった。そのために、「匂兵部卿」「紅梅」「竹河」の巻が書かれた。これらの巻は、光源氏なきあとの後日譚であるが、いかにも、強引に話を終了にもっていったとおぼしい。自然に、光源氏の物語を終わりにするならば、もっと別の書き方があって、余韻を残すこともできたであろう。
では、いつごろ「宇治十帖」が構想されたのか、それは、おそらく「若菜 上・下」を書いているあたりであったのかもしれない。光源氏の栄華の頂点であると同時に、女三宮の降嫁、そして、柏木との不倫。その結果生まれることになる薫。この薫の幼いときの様子が、いかにも印象的である。この薫が成長してどのような人間になるのか、薫を主人公とした物語を書いてみたい、そう思ったのではないだろうか。
たぶん、こんなことは『源氏物語』研究の世界では、とっくに言われていることだろうと思う。私も、今更、『源氏物語』の成立論にかかわるような論文を書いてみたいとも思っていない。
だが、今日において、一人の読者の立場で、『源氏物語』を最初から読んできてみて、上述のような思いをどうしても持ってしまうのである。
そして、「宇治十帖」の作者は、おそらく紫式部だろう。その叙述のなかにみられる、風景描写の見事さ。視覚と聴覚にわたって、あたり全体を俯瞰しながら、場面の転換をはかる……このような筆致は、本編ほどのあざやかさはないとはいえ、「宇治十帖」にも見て取れる。視覚と聴覚にわたり全体を俯瞰しながら、話題の焦点にポイントをもっていく、これは、『紫式部日記』の冒頭に見られる見事な文章に通じるものがある。
さて、次は、残る二冊である。このまま読んでしまうことにする。
追記 2020-01-06
この続きは、
やまもも書斎記 2020年1月6日
新潮日本古典集成『源氏物語』(七)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/01/06/9198739
この続きは、
やまもも書斎記 2020年1月6日
新潮日本古典集成『源氏物語』(七)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/01/06/9198739







最近のコメント