『真説 日本左翼史 戦後左翼の源流 1945-1960』池上彰・佐藤優 ― 2022-02-11
2022年2月11日 當山日出夫(とうやまひでお)

池上彰・佐藤優.『真説 日本左翼史 戦後左翼の源流 1945-1960』(講談社現代新書).講談社.2021
https://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000348699
売れている本らしい。読んでおくことにした。が、読んでみて思うことは、とても面白い本であり、ためになる本であるということである。
タイトルの通り、日本の「左翼」運動の歴史を対談形式でたどっている。この巻では、戦前からスタートして、おおむね60年安保のあたりまで。時として、冷戦終結、ソ連崩壊のあたりのことまで話しが及んでいる。
「左翼史」とあるが、具体的には、共産党の歴史であり、社会党の歴史が主なところである。なるほど、共産党という政党は、このような歴史があったのか、社会党の凋落はこのあたりに起因するのか、と今になっていろいろと思うことが多い。
私は、一九五五(昭和三〇)年の生まれなのであるが、物心ついたときには、政治の世界は、いわゆる五五年体制でかたまっていた時代である。保革伯仲であり、あるいは、社会党からすれば、三分の一を確保するだけの万年野党であり、自民党としては過半数を確保している安定与党ということになる。緊張感もあったが、しかし、同時にどこかしら生ぬるい感じを覚えている。
この本は「左翼」の歴史をたどっている。左翼というのは革新の立場である。「保守」思想ではない。単純化してみるならば、「左翼」は理性と理論を重視し、「保守」は伝統と感情を重視する。
私はといえば、どちらかといえば、保守的な人間なのであろうとは思う。だが、決して体制的ではないつもりでいる。
歴史、政治の流れをたどるとき、政権の中枢で何がどう決断され実行されてきたかという歴史もあるが、一方で、反体制の側から見る歴史もある。この意味では、戦前から戦後にかけての、反体制の歴史のある面を描き出している。ただ、この巻を読んだところで、やや不満に思うところは、実は左翼は、右翼とも、裏でつながっている……このあたりの感覚は、時代のなかで感じてきたところであるが……ここのところに踏み込んでいないことである。
この巻を読んで思うことは、左翼がだめになったということは、右翼もだらしないし、また政権の側もがたがきているということなのだろう。つづいて、続巻を読むことにしたい。
2022年2月1日記
https://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000348699
売れている本らしい。読んでおくことにした。が、読んでみて思うことは、とても面白い本であり、ためになる本であるということである。
タイトルの通り、日本の「左翼」運動の歴史を対談形式でたどっている。この巻では、戦前からスタートして、おおむね60年安保のあたりまで。時として、冷戦終結、ソ連崩壊のあたりのことまで話しが及んでいる。
「左翼史」とあるが、具体的には、共産党の歴史であり、社会党の歴史が主なところである。なるほど、共産党という政党は、このような歴史があったのか、社会党の凋落はこのあたりに起因するのか、と今になっていろいろと思うことが多い。
私は、一九五五(昭和三〇)年の生まれなのであるが、物心ついたときには、政治の世界は、いわゆる五五年体制でかたまっていた時代である。保革伯仲であり、あるいは、社会党からすれば、三分の一を確保するだけの万年野党であり、自民党としては過半数を確保している安定与党ということになる。緊張感もあったが、しかし、同時にどこかしら生ぬるい感じを覚えている。
この本は「左翼」の歴史をたどっている。左翼というのは革新の立場である。「保守」思想ではない。単純化してみるならば、「左翼」は理性と理論を重視し、「保守」は伝統と感情を重視する。
私はといえば、どちらかといえば、保守的な人間なのであろうとは思う。だが、決して体制的ではないつもりでいる。
歴史、政治の流れをたどるとき、政権の中枢で何がどう決断され実行されてきたかという歴史もあるが、一方で、反体制の側から見る歴史もある。この意味では、戦前から戦後にかけての、反体制の歴史のある面を描き出している。ただ、この巻を読んだところで、やや不満に思うところは、実は左翼は、右翼とも、裏でつながっている……このあたりの感覚は、時代のなかで感じてきたところであるが……ここのところに踏み込んでいないことである。
この巻を読んで思うことは、左翼がだめになったということは、右翼もだらしないし、また政権の側もがたがきているということなのだろう。つづいて、続巻を読むことにしたい。
2022年2月1日記
追記 2022年2月12日
この続きは、
やまもも書斎記 2022年2月12日
『激動 日本左翼史 学生運動と過激派 1960-1972』池上彰・佐藤優
https://yamamomo.asablo.jp/blog/2022/02/12/9463303
この続きは、
やまもも書斎記 2022年2月12日
『激動 日本左翼史 学生運動と過激派 1960-1972』池上彰・佐藤優
https://yamamomo.asablo.jp/blog/2022/02/12/9463303
『自由と成長の経済学』柿埜真吾 ― 2022-01-10
2022年1月10日 當山日出夫(とうやまひでお)
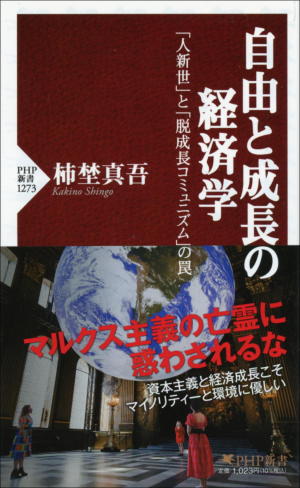
柿埜真吾.『自由と成長の経済学-「人新世」と「脱成長コミュニズム」の罠-』(PHP新書).PHP研究所.2021
https://www.php.co.jp/books/detail.php?isbn=978-4-569-85014-6
『人新世の「資本論」』への反論本である。昨年のうちにつづけて読んだものである。
やまもも書斎記 2021年12月20日
『人新世の「資本論」』斎藤幸平
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2021/12/20/9449350
やはり出るべくして出た反論本であるというべきか。読んで思うこととしては、次の二点ぐらいである。
第一に、『人新世の「資本論」』批判としては、至極まっとうな本であること。
世評としては、『人新世の「資本論」』は確かに高い。だが、この本の主張するところ、特に近未来への提言としては、荒唐無稽としかいいようがない。この批判としては、十分に首肯できる反論になっている。
第二に、しかし将来に限界はあるだろうということ。
限りなく成長する資本主義によってしか、今日の世界の問題は解決しないのだろうか。だが、ここで考えなければならないのは、地球環境というパイはすでに限界が見えてきていることではないかとも思う。今後の課題は、この限られたパイの分割、再配分のあり方と方法をめぐるものになっていくと思う。
以上の二点のことを考える。
『人新世の「資本論」』をただ荒唐無稽として退けるのではなく、その問題提起……特に地球環境の将来……については、十分に考慮しつつ、世界全体でバランスのとれた成長戦略を考えるべきときなのだろうとは思う。それに日本がどのように貢献できるかが問われている。いや、これは楽観的にすぎるかもしれない。どうすればこれからの国際社会のなかで日本が生き残れるかが、問題であるといった方がいいだろうか。
2022年1月9日記
https://www.php.co.jp/books/detail.php?isbn=978-4-569-85014-6
『人新世の「資本論」』への反論本である。昨年のうちにつづけて読んだものである。
やまもも書斎記 2021年12月20日
『人新世の「資本論」』斎藤幸平
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2021/12/20/9449350
やはり出るべくして出た反論本であるというべきか。読んで思うこととしては、次の二点ぐらいである。
第一に、『人新世の「資本論」』批判としては、至極まっとうな本であること。
世評としては、『人新世の「資本論」』は確かに高い。だが、この本の主張するところ、特に近未来への提言としては、荒唐無稽としかいいようがない。この批判としては、十分に首肯できる反論になっている。
第二に、しかし将来に限界はあるだろうということ。
限りなく成長する資本主義によってしか、今日の世界の問題は解決しないのだろうか。だが、ここで考えなければならないのは、地球環境というパイはすでに限界が見えてきていることではないかとも思う。今後の課題は、この限られたパイの分割、再配分のあり方と方法をめぐるものになっていくと思う。
以上の二点のことを考える。
『人新世の「資本論」』をただ荒唐無稽として退けるのではなく、その問題提起……特に地球環境の将来……については、十分に考慮しつつ、世界全体でバランスのとれた成長戦略を考えるべきときなのだろうとは思う。それに日本がどのように貢献できるかが問われている。いや、これは楽観的にすぎるかもしれない。どうすればこれからの国際社会のなかで日本が生き残れるかが、問題であるといった方がいいだろうか。
2022年1月9日記
『〈平成〉の正体』藤井達夫 ― 2022-01-07
2022年1月7日 當山日出夫(とうやまひでお)

藤井達夫.『〈平成〉の正体-なぜこの社会は機能不全に陥ったのか-』(イースト新書).イースト・プレス.2018
https://www.eastpress.co.jp/goods/detail/9784781651057
『代表制民主主義はなぜ失敗したのか』が面白かったので、同じ著者の本を読んでおくことにした。これは、少し前の刊行。2018年の刊行。平成三〇年になる。平成の最後である。
今(二〇二一)の時点から読んでみるならば、どれもごく普通に論じられることばかりである。が、非常に手際よく、今日の日本の社会や政治の状況、問題点などを、論点を整理して書いてある。現在の視点から見ても、なるほどと思うとことが多々ある。
目次を示してみるならば以下のとおり。
ポスト工業化と液状化する社会
ネオリベ化した社会の理想と現実
格差社会の「希望は戦争」
ポスト冷戦と強化される対米依存
五五年体制の終焉と挫折した政治改革
「日常の政治」からポスト平成を切り開く
また、最終章に、辻田真佐憲との対談「保守とリベラルは新しい「物語」をつくれるか?」をおさめる。
平成という時代は、三〇年ほどつづいた。それは、冷戦の終結からバブル経済の崩壊とともにスタートすることになった。今になってみれば、失われた三〇年というべき時代である。このあいだに、社会は変わった。いわく、グローバル化、デジタル化、格差、新自由主義……いくつかの、この時代を説明することばが登場してきている。そのことばのなかに翻弄されてきた時代であった。いや、今も、翻弄されている。
とにかく、平成の終わりの何年か、それは、安倍政権の時代ということになるが、この時代の空虚さを実感することになる。過去の一〇年ほど、この社会は、何を目指してきたということなのだろうか。そこに、COVID-19である。これほど、この日本の社会の、また、政治の、無力、無能ということを感じたことはなかった。
今の日本のおかれた状況を冷静に振り返ってみる意味でも、この本は価値のある本だと思う。
2021年12月17日記
https://www.eastpress.co.jp/goods/detail/9784781651057
『代表制民主主義はなぜ失敗したのか』が面白かったので、同じ著者の本を読んでおくことにした。これは、少し前の刊行。2018年の刊行。平成三〇年になる。平成の最後である。
今(二〇二一)の時点から読んでみるならば、どれもごく普通に論じられることばかりである。が、非常に手際よく、今日の日本の社会や政治の状況、問題点などを、論点を整理して書いてある。現在の視点から見ても、なるほどと思うとことが多々ある。
目次を示してみるならば以下のとおり。
ポスト工業化と液状化する社会
ネオリベ化した社会の理想と現実
格差社会の「希望は戦争」
ポスト冷戦と強化される対米依存
五五年体制の終焉と挫折した政治改革
「日常の政治」からポスト平成を切り開く
また、最終章に、辻田真佐憲との対談「保守とリベラルは新しい「物語」をつくれるか?」をおさめる。
平成という時代は、三〇年ほどつづいた。それは、冷戦の終結からバブル経済の崩壊とともにスタートすることになった。今になってみれば、失われた三〇年というべき時代である。このあいだに、社会は変わった。いわく、グローバル化、デジタル化、格差、新自由主義……いくつかの、この時代を説明することばが登場してきている。そのことばのなかに翻弄されてきた時代であった。いや、今も、翻弄されている。
とにかく、平成の終わりの何年か、それは、安倍政権の時代ということになるが、この時代の空虚さを実感することになる。過去の一〇年ほど、この社会は、何を目指してきたということなのだろうか。そこに、COVID-19である。これほど、この日本の社会の、また、政治の、無力、無能ということを感じたことはなかった。
今の日本のおかれた状況を冷静に振り返ってみる意味でも、この本は価値のある本だと思う。
2021年12月17日記
『代表制民主主義はなぜ失敗したのか』藤井達夫 ― 2021-12-27
2021-12-27 當山日出夫(とうやまひでお)

藤井達夫.『代表制民主主義はなぜ失敗したのか』(集英社新書).集英社.2021
https://books.shueisha.co.jp/items/contents.html?isbn=978-4-08-721194-8
なるほど、安倍晋三のやったことは民主主義の破壊であった、ということが実感できる。
著者は、「民主主義」=「選挙」ではないといっている。漠然と、選挙で選ばれた議員が政治にかかわることを、民主主義だと思っているむきもあるかもしれないが、そうではないということに気づかされる。そして、民主主義を、その歴史からたどって、本当に民主主義を実践するには、いかにして可能なのか、問いかけるところがある。
すくなくとも、少数意見、反対意見への尊重ということがない場合、民主的とはいえない。(この意味では、安倍政権の時代は、とても民主主義の時代ということはできないことになる。)
この著者は、いわゆる一九五五年体制を評価している。その時代にあっては、政党は、ある一定の社会の階級、あるいは、階層を代表するものであり、それを基盤に選挙がおこなわれ、議員が選出されていた……このことに一定の評価を与えている。これは、昭和の昔が良かったという懐古でない。政党というものが、何を代表して組織され、選挙にのぞみ、何を実現することを、その存在意義としているのか、明確であった時代ということになろうか。それが、今日では、政党政治は、人気投票、あるいは、ポピュリズムになってしまっている。
現状の政治の問題点の分析には、なるほどと思うところが多くある。しかし、ではどうすればよいのかということになると、(私の見る限り)あまり説得力がないように読める。これは、この著者の責任ではないだろう。それほど、現在の、日本の、あるいは、世界の民主主義は危機に瀕しているいってよい。有効な対処が見いだせないでいる状況である。
現代の日本の政治状況を考えるうえでは、役に立つ一冊といっていいだろう。
2021年12月10日記
https://books.shueisha.co.jp/items/contents.html?isbn=978-4-08-721194-8
なるほど、安倍晋三のやったことは民主主義の破壊であった、ということが実感できる。
著者は、「民主主義」=「選挙」ではないといっている。漠然と、選挙で選ばれた議員が政治にかかわることを、民主主義だと思っているむきもあるかもしれないが、そうではないということに気づかされる。そして、民主主義を、その歴史からたどって、本当に民主主義を実践するには、いかにして可能なのか、問いかけるところがある。
すくなくとも、少数意見、反対意見への尊重ということがない場合、民主的とはいえない。(この意味では、安倍政権の時代は、とても民主主義の時代ということはできないことになる。)
この著者は、いわゆる一九五五年体制を評価している。その時代にあっては、政党は、ある一定の社会の階級、あるいは、階層を代表するものであり、それを基盤に選挙がおこなわれ、議員が選出されていた……このことに一定の評価を与えている。これは、昭和の昔が良かったという懐古でない。政党というものが、何を代表して組織され、選挙にのぞみ、何を実現することを、その存在意義としているのか、明確であった時代ということになろうか。それが、今日では、政党政治は、人気投票、あるいは、ポピュリズムになってしまっている。
現状の政治の問題点の分析には、なるほどと思うところが多くある。しかし、ではどうすればよいのかということになると、(私の見る限り)あまり説得力がないように読める。これは、この著者の責任ではないだろう。それほど、現在の、日本の、あるいは、世界の民主主義は危機に瀕しているいってよい。有効な対処が見いだせないでいる状況である。
現代の日本の政治状況を考えるうえでは、役に立つ一冊といっていいだろう。
2021年12月10日記
『人新世の「資本論」』斎藤幸平 ― 2021-12-20
2021-12-20 當山日出夫(とうやまひでお)

斎藤幸平.『人新世の「資本論」』(集英社新書).集英社.2020
https://shinsho.shueisha.co.jp/kikan/1035-a/
話題の本ということで読んでみることにした。結論からいうと、私は、この本には賛成しない。その理由を三つばかり書いてみる。
第一には、人間観である。
人間の社会というのは、そんなに善良なものなのであろうか。むしろ、野蛮状態というべきかもしれない。これがいいすぎならば、無秩序と混乱といってもいいだろう。既存の社会のシステムが崩壊した後に、どのような安定した社会を作ることができるか、その道筋について、具体的に何もふれていない。たとえば、現在の中東情勢など見ても、そんなに今後の国際情勢を楽観的に考えることはできないと思う。
第二には、社会観である。
3.5%の人が動くならならば、社会は変革するという。はたして、これが一般的にいえることなのだろうか。そして、重要なことだと思うのは、3.5%の人びとの行動で社会が変わってしまうならば、一般の民主的手続き……選挙であり多数決を原則とする議決である……これは、どうなるのだろうか。まあ、現在の民主的な手続きは、行き詰まりを見せているので、それに変わる代替手段があり得るということかもしれない。だが、それが一般的、普遍的に適用できるという見通しは、まだ無理だろうと思うがどうであろうか。
第三には、中国である。
この本の中には、中国のことがほとんど出てこない。問題視されているのは、日本や欧米の諸国である。しかし、実際の国際社会のなかで、これから中国の存在感が大きくなることが懸念される。気候変動について、中国の責任は大きい。では、その一党独裁専制国家のゆくすえを、どう考えるのか。これも、3.5%の人びとが行動すれば、体制変革が可能というのであろうか。
以上の三つばかりを書いてみた。
無論、この本から学ぶところはいくつかある。特に、始めの方の気候変動への危機感などは、最重要の課題というべきであろう。また、マルクスの思想についても、晩年のマルクスがどのように考えていたか、これはこれとして興味深い。
晩年のマルクスから学ぶことは多くあるにちがいない。しかし、そこで留意すべきは、マルクスの生きた時代の科学、技術のあり方、人びとの生活様式のあり方、これは、二一世紀の今日とは異なっていることである。この点を無視して、ただマルクスがこう考えたで、それをもってくればいいというものではあるまい。晩年のマルクスの主張から脱成長のコミュニズムというのは、短絡していると思わざるを得ない。少なくとも、それほど説得力のある議論とは感じられない。
また、どうして最後のところで、精神論になるのであろうか。このあたりも気になる論のはこびである。以前に読んだ白井聡の本でも、最後は精神論で頑張れで終わっていた。最後は精神論で頑張れで終わるしかないということは、どうもその論理全体が破綻しているとしか思えないのである。
他にもいろいろと思うことはあるが、一読に値する本ではあると思う。
2021年12月13日記
https://shinsho.shueisha.co.jp/kikan/1035-a/
話題の本ということで読んでみることにした。結論からいうと、私は、この本には賛成しない。その理由を三つばかり書いてみる。
第一には、人間観である。
人間の社会というのは、そんなに善良なものなのであろうか。むしろ、野蛮状態というべきかもしれない。これがいいすぎならば、無秩序と混乱といってもいいだろう。既存の社会のシステムが崩壊した後に、どのような安定した社会を作ることができるか、その道筋について、具体的に何もふれていない。たとえば、現在の中東情勢など見ても、そんなに今後の国際情勢を楽観的に考えることはできないと思う。
第二には、社会観である。
3.5%の人が動くならならば、社会は変革するという。はたして、これが一般的にいえることなのだろうか。そして、重要なことだと思うのは、3.5%の人びとの行動で社会が変わってしまうならば、一般の民主的手続き……選挙であり多数決を原則とする議決である……これは、どうなるのだろうか。まあ、現在の民主的な手続きは、行き詰まりを見せているので、それに変わる代替手段があり得るということかもしれない。だが、それが一般的、普遍的に適用できるという見通しは、まだ無理だろうと思うがどうであろうか。
第三には、中国である。
この本の中には、中国のことがほとんど出てこない。問題視されているのは、日本や欧米の諸国である。しかし、実際の国際社会のなかで、これから中国の存在感が大きくなることが懸念される。気候変動について、中国の責任は大きい。では、その一党独裁専制国家のゆくすえを、どう考えるのか。これも、3.5%の人びとが行動すれば、体制変革が可能というのであろうか。
以上の三つばかりを書いてみた。
無論、この本から学ぶところはいくつかある。特に、始めの方の気候変動への危機感などは、最重要の課題というべきであろう。また、マルクスの思想についても、晩年のマルクスがどのように考えていたか、これはこれとして興味深い。
晩年のマルクスから学ぶことは多くあるにちがいない。しかし、そこで留意すべきは、マルクスの生きた時代の科学、技術のあり方、人びとの生活様式のあり方、これは、二一世紀の今日とは異なっていることである。この点を無視して、ただマルクスがこう考えたで、それをもってくればいいというものではあるまい。晩年のマルクスの主張から脱成長のコミュニズムというのは、短絡していると思わざるを得ない。少なくとも、それほど説得力のある議論とは感じられない。
また、どうして最後のところで、精神論になるのであろうか。このあたりも気になる論のはこびである。以前に読んだ白井聡の本でも、最後は精神論で頑張れで終わっていた。最後は精神論で頑張れで終わるしかないということは、どうもその論理全体が破綻しているとしか思えないのである。
他にもいろいろと思うことはあるが、一読に値する本ではあると思う。
2021年12月13日記
『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』ブレイディみかこ ― 2021-07-22
2021-07-22 當山日出夫(とうやまひでお)

ブレイディみかこ.『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』(新潮文庫).新潮社.2021 (新潮社.2019)
https://www.shinchosha.co.jp/book/352681/
話題になっている本と思ってはいたが、なんとなく手を出さずにいた。文庫本になったのをきっかけに読んでみることにした。なるほど、この本がベストセラーになるのは、理解できる。
著者は、いわゆる日本人であるが、英国で結婚して、そこで働いて子育てをしている。その現地の生活の視点……強いていえば労働者階級ということになるが……から、英国の社会の様々な問題を描き出している。
読んで思うことは、次の二点ぐらいであろうか。
第一は、読み物として面白いことである。
とにかく、読んで面白い。これにつきる。著者の夫婦は、その子どもを、地域の、元底辺中学校に通わせることになる。そこでおこる様々なできごとが綴られるのだが、なるほどいろいろと大変なことがあるよなあ、と共感して読んでしまう。無論、日本と英国と、国情がおおいに異なる。同じものさしではかることはできないのだが、しかし、子育ての苦労、そして、中学にはいり自立していく子どもの姿、これがどことなくユーモアのある筆致で描かれている。これが、読み物として非常に面白い。
第二は、さまざまに考えることの多い本であること。
PC(ポリティカルコレクトネス)というが、どの社会環境において、どのような価値観が、PCであるかは、多様性がある。社会の多様性を重視するといっても、では具体的にどうすればいいのか、その状況によって判断していかなければならない。
そこで重要になることとして、著者は、「エンパシー」……シンパシーではなく……といっている。異なる立場の身になって考えてみること。端的に、これを、「他人の靴をはいてみる」こと……といっている。
日本において考えるPCと、英国ロンドンの労働者階級のなかで考えることになるPCでは、おおいに違う。だが、そこに共通していえることは、自分は何者であるかの認識と、自分とは異なる人びと……ジェンダー、人種、国籍、社会的階層、文化など……への、「他人の靴をはいてみる」という配慮である。
これは、おそらくは、今の日本において、あるいは、これからの日本において、きわめて重要な視点になることである。
以上の二点のことを、思ったことして書いてみる。
この本が文庫本になって多くの人びとに読まれるようになるのは、よろこばしいことといっていいだろう。
2021年7月16日記
https://www.shinchosha.co.jp/book/352681/
話題になっている本と思ってはいたが、なんとなく手を出さずにいた。文庫本になったのをきっかけに読んでみることにした。なるほど、この本がベストセラーになるのは、理解できる。
著者は、いわゆる日本人であるが、英国で結婚して、そこで働いて子育てをしている。その現地の生活の視点……強いていえば労働者階級ということになるが……から、英国の社会の様々な問題を描き出している。
読んで思うことは、次の二点ぐらいであろうか。
第一は、読み物として面白いことである。
とにかく、読んで面白い。これにつきる。著者の夫婦は、その子どもを、地域の、元底辺中学校に通わせることになる。そこでおこる様々なできごとが綴られるのだが、なるほどいろいろと大変なことがあるよなあ、と共感して読んでしまう。無論、日本と英国と、国情がおおいに異なる。同じものさしではかることはできないのだが、しかし、子育ての苦労、そして、中学にはいり自立していく子どもの姿、これがどことなくユーモアのある筆致で描かれている。これが、読み物として非常に面白い。
第二は、さまざまに考えることの多い本であること。
PC(ポリティカルコレクトネス)というが、どの社会環境において、どのような価値観が、PCであるかは、多様性がある。社会の多様性を重視するといっても、では具体的にどうすればいいのか、その状況によって判断していかなければならない。
そこで重要になることとして、著者は、「エンパシー」……シンパシーではなく……といっている。異なる立場の身になって考えてみること。端的に、これを、「他人の靴をはいてみる」こと……といっている。
日本において考えるPCと、英国ロンドンの労働者階級のなかで考えることになるPCでは、おおいに違う。だが、そこに共通していえることは、自分は何者であるかの認識と、自分とは異なる人びと……ジェンダー、人種、国籍、社会的階層、文化など……への、「他人の靴をはいてみる」という配慮である。
これは、おそらくは、今の日本において、あるいは、これからの日本において、きわめて重要な視点になることである。
以上の二点のことを、思ったことして書いてみる。
この本が文庫本になって多くの人びとに読まれるようになるのは、よろこばしいことといっていいだろう。
2021年7月16日記
『超空気支配社会』辻田真佐憲 ― 2021-07-01
2021-07-01 當山日出夫(とうやまひでお)

辻田真佐憲.『超空気支配社会』(文春新書).文藝春秋.2021
https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784166613168
辻田真佐憲の最近の文章……主にWEBに掲載のもの……を編集してある。
第一章 ふたつの同調圧力に抗って-五輪とコロナ自粛-
第二章 虚構の戦前回帰-歴史の教訓をアップデートする-
第三章 プロパガンダの最前線へ-音楽から観光まで-
第四章 総合知を復興せよ-健全な中間をめざして-
それぞれの章について、興味深い。まず、SNSが主要メディアでも無視できないような時代の状況のなかにあって、自分の立ち位置をどう決めていくのか。この考察は、示唆に富む。
私が読んで興味深かったのは、第三章。韓国における竹島の領有権をめぐる、一般国民への啓蒙活動。また、中国における共産党の歴史を観光にするテーマパーク。なるほど、こういう事例のレポートを読むと、日本はいかにも生ぬるいというか、もうちょっとどうにかならないかなと思ってしまう。
全体として、問題は、政治的なプロパガンダが、SNSによって、より大きく拡散していく社会にいることだろう。そのなかにあって、冷静に物事を見極めるのは、かなり困難になってきているのかもしれない。(ただ、自分はSNSを見なければそれで済むという問題では、もはやない。)
プロパガンダというと、昔のナチスドイツのことあたりを思い出す。だが、趣旨は異なるとはいえ、今も、より巧妙化して、反日、中国共産党礼賛のプロパガンダが、堂々と行われているというのは、ある意味で驚きでもあある。だが、これは事実であるとしかいいようがない。(ちょうど、今(二〇二一)、中国では共産党の一〇〇周年を迎えようとして、大規模なイベントが企画されている。)
著者が提唱するのが、ジャーナリズム、評論家の役割。アカデミズムではなく、いわば在野の立場から、調査研究して、総合的な俯瞰のもとに情報発信していく人材の必要を、つよくいっている。この本の場合であれば、先日なくなった半藤一利を事例にあげている。(辻田真佐憲も、半藤一利と同様に、昭和戦前の日本についての著書がある。)
さて、総合的な俯瞰的な知といわれればであるが、ちょうど、最近の話題(二〇二一)としては、立花隆がなくなったことが思い浮かぶ。私も、その著書の多くは、若いころに読んだものである。
それから、ちょっと古いところでは、これはアカデミズムよりといわれるかもしれないが、林達夫のことなどが、思い浮かぶ。
ともあれ、SNSによる言論世界から自由ではありえない現代社会において、自分の考えの方向性を考えるうえで、きわめて参考になる知見をあたえてくれる本だと思う。
2021年6月30日記
https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784166613168
辻田真佐憲の最近の文章……主にWEBに掲載のもの……を編集してある。
第一章 ふたつの同調圧力に抗って-五輪とコロナ自粛-
第二章 虚構の戦前回帰-歴史の教訓をアップデートする-
第三章 プロパガンダの最前線へ-音楽から観光まで-
第四章 総合知を復興せよ-健全な中間をめざして-
それぞれの章について、興味深い。まず、SNSが主要メディアでも無視できないような時代の状況のなかにあって、自分の立ち位置をどう決めていくのか。この考察は、示唆に富む。
私が読んで興味深かったのは、第三章。韓国における竹島の領有権をめぐる、一般国民への啓蒙活動。また、中国における共産党の歴史を観光にするテーマパーク。なるほど、こういう事例のレポートを読むと、日本はいかにも生ぬるいというか、もうちょっとどうにかならないかなと思ってしまう。
全体として、問題は、政治的なプロパガンダが、SNSによって、より大きく拡散していく社会にいることだろう。そのなかにあって、冷静に物事を見極めるのは、かなり困難になってきているのかもしれない。(ただ、自分はSNSを見なければそれで済むという問題では、もはやない。)
プロパガンダというと、昔のナチスドイツのことあたりを思い出す。だが、趣旨は異なるとはいえ、今も、より巧妙化して、反日、中国共産党礼賛のプロパガンダが、堂々と行われているというのは、ある意味で驚きでもあある。だが、これは事実であるとしかいいようがない。(ちょうど、今(二〇二一)、中国では共産党の一〇〇周年を迎えようとして、大規模なイベントが企画されている。)
著者が提唱するのが、ジャーナリズム、評論家の役割。アカデミズムではなく、いわば在野の立場から、調査研究して、総合的な俯瞰のもとに情報発信していく人材の必要を、つよくいっている。この本の場合であれば、先日なくなった半藤一利を事例にあげている。(辻田真佐憲も、半藤一利と同様に、昭和戦前の日本についての著書がある。)
さて、総合的な俯瞰的な知といわれればであるが、ちょうど、最近の話題(二〇二一)としては、立花隆がなくなったことが思い浮かぶ。私も、その著書の多くは、若いころに読んだものである。
それから、ちょっと古いところでは、これはアカデミズムよりといわれるかもしれないが、林達夫のことなどが、思い浮かぶ。
ともあれ、SNSによる言論世界から自由ではありえない現代社会において、自分の考えの方向性を考えるうえで、きわめて参考になる知見をあたえてくれる本だと思う。
2021年6月30日記
「100分de名著」『ブルデュー ディスタンクシオン』岸政彦 ― 2021-01-30
2021-01-30 當山日出夫(とうやまひでお)

岸政彦.『100分de名著 ブルデュー ディスタンクシオン』.NHK出版.2020
https://www.nhk-book.co.jp/detail/000062231202020.html
実は、『ディスタンクシオン』は買ってもっている。おそらくNHKのこの番組にあわせたのかもしれないが、昨年、新しい版で廉価版として刊行になっている。これを読もうと思って買ってはあるのだが、その前に予習というような意味で、こっちの本を読んでみた。
ただ、私は、NHKの番組は見てはいない。これはそのテキストである。しかし、良く書けていると思う。
第一に、ブルデューの生いたちからはじまって、『ディスタンクシオン』の概要が簡潔にまとめてある。
第二に、その批判についてどう考えるかが、それぞれの論点について、手際よくまとめてある。
以上の二点をきちんとふまえているし、全体として大部なものではない。あっさりと読めてしまった。(後は、覚悟を決めて『ディスタンクシオン』を読むということになる。)
さらに思ったことを書いてみるならば、次の二点があるだろうか。
第一に、自分はどのような環境に生まれ育った、どのような教育をうけてきた人間なのか、自らを知るという視点を与えてくれるところにある。キーワードとなるのは、「文化資本」である。これを一種の決定論と考えるのではなく、自分自身が何であるかを考える手がかりとしているのが、この本の特徴といっていいのかと思う。
第二に、まさに「文化資本」であるが……結局は、このような本を読むような人間、あるいは家庭環境であるか、あるいは、そうでないのか……このあたりのことが、まさに「文化資本」として現れてくることになるのだろうと思う。『ディスタンクシオン』が廉価版で出たので買っておこうという人間と、そうではない人間の違いといってもいいかもしれない。
以上のようなことを思って見る。
『ディスタンクシオン』のこと、また、「文化資本」ということばは知っていたが、これまであまり考えてみたことはなかったことでもある。いやあるいは、むしろ、自分のこれまでの人生は、ある意味で「文化資本」をどう意識するかということもあったかと思うところがないではない。この本を読んで、自らの過去を顧みて、自分はいったい何であったのか、これから何であり得るのか、さまざまに考えるところがある。
2021年1月29日記
https://www.nhk-book.co.jp/detail/000062231202020.html
実は、『ディスタンクシオン』は買ってもっている。おそらくNHKのこの番組にあわせたのかもしれないが、昨年、新しい版で廉価版として刊行になっている。これを読もうと思って買ってはあるのだが、その前に予習というような意味で、こっちの本を読んでみた。
ただ、私は、NHKの番組は見てはいない。これはそのテキストである。しかし、良く書けていると思う。
第一に、ブルデューの生いたちからはじまって、『ディスタンクシオン』の概要が簡潔にまとめてある。
第二に、その批判についてどう考えるかが、それぞれの論点について、手際よくまとめてある。
以上の二点をきちんとふまえているし、全体として大部なものではない。あっさりと読めてしまった。(後は、覚悟を決めて『ディスタンクシオン』を読むということになる。)
さらに思ったことを書いてみるならば、次の二点があるだろうか。
第一に、自分はどのような環境に生まれ育った、どのような教育をうけてきた人間なのか、自らを知るという視点を与えてくれるところにある。キーワードとなるのは、「文化資本」である。これを一種の決定論と考えるのではなく、自分自身が何であるかを考える手がかりとしているのが、この本の特徴といっていいのかと思う。
第二に、まさに「文化資本」であるが……結局は、このような本を読むような人間、あるいは家庭環境であるか、あるいは、そうでないのか……このあたりのことが、まさに「文化資本」として現れてくることになるのだろうと思う。『ディスタンクシオン』が廉価版で出たので買っておこうという人間と、そうではない人間の違いといってもいいかもしれない。
以上のようなことを思って見る。
『ディスタンクシオン』のこと、また、「文化資本」ということばは知っていたが、これまであまり考えてみたことはなかったことでもある。いやあるいは、むしろ、自分のこれまでの人生は、ある意味で「文化資本」をどう意識するかということもあったかと思うところがないではない。この本を読んで、自らの過去を顧みて、自分はいったい何であったのか、これから何であり得るのか、さまざまに考えるところがある。
2021年1月29日記
『民主主義とは何か』宇野重規 ― 2020-12-17
2020-12-17 當山日出夫(とうやまひでお)

宇野重規.『民主主義とは何か』(講談社現代新書).講談社.2020
https://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000324372
出たときに買っておいて、しばらく積んであった本である。ここしばらく、太宰治を集中的に読んでいた。
これが「話題」の本であるとは思っていた。いうまでもなく学術会議の一件である。
この本を読んでみての感想としては、この本の著者である宇野重規を学術会議に入れなかった判断を下したの誰であるかは知らないが、しかし、その人物について、ある意味で畏敬の念を感じるところがある(無論、皮肉をこめてであるが)。なるほど、このような本を書くと、学術会議から排除されるのか。ならば、排除されずにメンバーになっている学者は、曲学阿世の御用学者ばかりか……ふと、そんなかんぐりをしたくなってくる……だが、問題の本質は、そこのところが不明瞭なままである点にある。基準が不透明なのが、一番の問題点だと思う。
それはともかく、この本は面白い。「民主主義」という日常的に使っていることばであり、あるいは、その中に生きているはずの社会の制度である。それについて、民主主義とはどのような歴史があり、実際に運用するにあたっては、どのような課題があるのか、実に丁寧に分かりやすく説明してある。きちんと手順をふんで、ものごとを丁寧に考えていくとはこういう知性のあり方をしめすのである、その見本のような本である。
もし、私が、まだ若くて……高校生ぐらいであって、この本を読んだとしたら、将来の自分の進路として、法学部を選び、政治思想、政治学をこころざしたかもしれない、そんな気にもなってくる。この本は、特に若いひとに読んでもらいたいと思う本である。これからの日本の「民主主義」は、これからの若いひとがになっていくものである。
そろそろ年末である。この年のベストがいろいろ発表されるころかと思うが、この本は、かならずどこかで取り上げられるにちがいない。
2020年12月14日記
https://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000324372
出たときに買っておいて、しばらく積んであった本である。ここしばらく、太宰治を集中的に読んでいた。
これが「話題」の本であるとは思っていた。いうまでもなく学術会議の一件である。
この本を読んでみての感想としては、この本の著者である宇野重規を学術会議に入れなかった判断を下したの誰であるかは知らないが、しかし、その人物について、ある意味で畏敬の念を感じるところがある(無論、皮肉をこめてであるが)。なるほど、このような本を書くと、学術会議から排除されるのか。ならば、排除されずにメンバーになっている学者は、曲学阿世の御用学者ばかりか……ふと、そんなかんぐりをしたくなってくる……だが、問題の本質は、そこのところが不明瞭なままである点にある。基準が不透明なのが、一番の問題点だと思う。
それはともかく、この本は面白い。「民主主義」という日常的に使っていることばであり、あるいは、その中に生きているはずの社会の制度である。それについて、民主主義とはどのような歴史があり、実際に運用するにあたっては、どのような課題があるのか、実に丁寧に分かりやすく説明してある。きちんと手順をふんで、ものごとを丁寧に考えていくとはこういう知性のあり方をしめすのである、その見本のような本である。
もし、私が、まだ若くて……高校生ぐらいであって、この本を読んだとしたら、将来の自分の進路として、法学部を選び、政治思想、政治学をこころざしたかもしれない、そんな気にもなってくる。この本は、特に若いひとに読んでもらいたいと思う本である。これからの日本の「民主主義」は、これからの若いひとがになっていくものである。
そろそろ年末である。この年のベストがいろいろ発表されるころかと思うが、この本は、かならずどこかで取り上げられるにちがいない。
2020年12月14日記
『フランス革命についての省察』エドマンド・バーク/二木麻里(訳) ― 2020-09-24
2020-09-24 當山日出夫(とうやまひでお)

エドマンド・バーク.二木麻里(訳).『フランス革命についての省察』(光文社古典新訳文庫).光文社.2020
https://www.kotensinyaku.jp/books/book329/
この本を読んでいるとき、日本の政治はというと……八年にわたった安倍政権がおわることになり、次の自民党総裁をえらぶことになった。そして、その結果は、菅義偉が決まった。このような政治状況のなかで、この本を読んだことになる。
率直な感想を言えば……日本の政治家のなんとだらしないことか、という思いである。
ともあれ、この本は、フランス革命に際して、英国から見てそれをどう思うか、考察を加えたものであり、英国保守思想を体系化した書物として、古典的な位置をしめる本である。ひととおり、このようなことは知っていたが、読むのは、これが初めてになる。(たしか、中央公論社の『世界の名著』のなかにはいっていたかと思うが、これはしまい込んだままになっている。)
保守思想とは何かということについては、今更のべるほどのこともないだろう。以前に、少しだけ書いたことがある。
やまもも書斎記 2016年7月1日
宇野重規『保守主義とは何か』
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2016/07/01/8122012
ただ、今回、『フランス革命についての省察』を読んで思うことを記しておくならば、次のことがある。それは、バークがこの本を書いたとき、英国は、立憲君主制を確立しており、まがりなりにも、民主的な制度がととのった状況にあったということである。そのような英国から見て、フランス革命の行きすぎた点、不十分な点、問題点などを、冷静に観察している。そのような批判ができるというのも、その時点に英国における政治制度の熟成ということを、考えておくべきであろう。
この本を読みながら、あえて付箋をつけることはせずに読んだのだが、一箇所だけ注目しておきたいところを引用しておく。
「社会の構成メンバーの利害も多様になれば、さまざまな秩序とさまざまな見方ができて、その数が多いほど社会一般の自由にとっては保障になるのです。」(p.77)
今、社会の多様性ということが、各方面から言われている。このとき、多様な意見を尊重し、耳を傾けること……これこそ、保守主義の最も重視することである。すくなくとも、真性の保守主義者であろうとするならば、このことに十分に配慮しなければならない。
保守を自認するする人、組織、政党などは多いかもしれないが、そこに、多様な意見の尊重という観点が、どれほどあるだろうか。それを欠くような考え方については、私は、保守とは言いたくない。
この本は、保守主義の古典的著作ではあるが、むしろ、リベラルといわれる立場にとっても、非常に有意義なものとなっていると感じる。どのような政治的立場をとるにせよ、熟読する価値のある本であることはまちがいない。
2020年9月16日記
https://www.kotensinyaku.jp/books/book329/
この本を読んでいるとき、日本の政治はというと……八年にわたった安倍政権がおわることになり、次の自民党総裁をえらぶことになった。そして、その結果は、菅義偉が決まった。このような政治状況のなかで、この本を読んだことになる。
率直な感想を言えば……日本の政治家のなんとだらしないことか、という思いである。
ともあれ、この本は、フランス革命に際して、英国から見てそれをどう思うか、考察を加えたものであり、英国保守思想を体系化した書物として、古典的な位置をしめる本である。ひととおり、このようなことは知っていたが、読むのは、これが初めてになる。(たしか、中央公論社の『世界の名著』のなかにはいっていたかと思うが、これはしまい込んだままになっている。)
保守思想とは何かということについては、今更のべるほどのこともないだろう。以前に、少しだけ書いたことがある。
やまもも書斎記 2016年7月1日
宇野重規『保守主義とは何か』
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2016/07/01/8122012
ただ、今回、『フランス革命についての省察』を読んで思うことを記しておくならば、次のことがある。それは、バークがこの本を書いたとき、英国は、立憲君主制を確立しており、まがりなりにも、民主的な制度がととのった状況にあったということである。そのような英国から見て、フランス革命の行きすぎた点、不十分な点、問題点などを、冷静に観察している。そのような批判ができるというのも、その時点に英国における政治制度の熟成ということを、考えておくべきであろう。
この本を読みながら、あえて付箋をつけることはせずに読んだのだが、一箇所だけ注目しておきたいところを引用しておく。
「社会の構成メンバーの利害も多様になれば、さまざまな秩序とさまざまな見方ができて、その数が多いほど社会一般の自由にとっては保障になるのです。」(p.77)
今、社会の多様性ということが、各方面から言われている。このとき、多様な意見を尊重し、耳を傾けること……これこそ、保守主義の最も重視することである。すくなくとも、真性の保守主義者であろうとするならば、このことに十分に配慮しなければならない。
保守を自認するする人、組織、政党などは多いかもしれないが、そこに、多様な意見の尊重という観点が、どれほどあるだろうか。それを欠くような考え方については、私は、保守とは言いたくない。
この本は、保守主義の古典的著作ではあるが、むしろ、リベラルといわれる立場にとっても、非常に有意義なものとなっていると感じる。どのような政治的立場をとるにせよ、熟読する価値のある本であることはまちがいない。
2020年9月16日記
最近のコメント