『暇と退屈の倫理学』國分功一郎 ― 2022-01-13
2022年1月13日 當山日出夫(とうやまひでお)

國分功一郎.『暇と退屈の倫理学』(新潮文庫).新潮社.2022(太田出版.2015)
https://www.shinchosha.co.jp/book/103541/
新潮文庫で刊行になった本であるということもあって、読んでみた。この本の初版は、二〇一一年。その増補新版の文庫化である。著名な本であることは知っていたのだが、なんとなく手にすることなく今にいたってしまった。
この本については、すでにいろいろと言われていることだろう。特に、何ほどのことを書くでもないが、思いつくままに書くとすると次の二点ぐらいがある。
第一に、退屈の文学史である。
この本を読んで、「つれづれ」とも「アンニュイ」とも「懶(ものうし)」とも出てこない。退屈な状態を、文学的に表現するならば、このようになるかと思う。たぶん、これは意図的にそう書いているのかと思う。退屈ということが、古今東西の文学作品のなかでどのように表現され、文学的主題としてあつかわれてきたか、これはこれとして、とても興味あることである。
第二、還世界について。
人間と動物とでは、住んでいる世界が異なる。感知しているまわりの世界が異なることは理解できる。そして、人間においては、多様な世界を行き来できるということもまた、理解はできる。だが、もう一歩踏み込んで分析することも可能かと思う。人間にとって環境とは、意図せずにたまたまそのような環境におかれるという状態もあるだろうし、あるいは、意図的に自らをそのような環境においてみることもできる。このあたりの人間の意志とのかかわりは、もうすこし分析する必要があるかもしれない。また、例えば、色彩の世界についていってみれば、確かに人間の感知することのできる色彩の世界と、モンシロチョウの感知する色彩の世界は違っている(このことは、色彩学の本にはたいてい出てくる。)人間が、多様な環境に身をおくことができるとしても、色彩に限ってみるならば、人間の感知できる範囲は、おのずと決まっている。他の動物のような色彩の環境に容易に入っていけるものではない。
以上の二点のことを書いてみる。
國分功一郎の本では、『中動態の世界』は買ってあるのだが、しまいこんだままになっている。取り出してきて、読んでおきたいと思う。
それから、さらに書いてみるならば、この本では最初に「暇」も「退屈」も定義していない。そうではなくて、この本を読むと、「退屈」とはこのような状態をさすのだな、ということが理解できるように書いてある。このような論のたてかたもあるのだと思う。
2022年1月11日記
https://www.shinchosha.co.jp/book/103541/
新潮文庫で刊行になった本であるということもあって、読んでみた。この本の初版は、二〇一一年。その増補新版の文庫化である。著名な本であることは知っていたのだが、なんとなく手にすることなく今にいたってしまった。
この本については、すでにいろいろと言われていることだろう。特に、何ほどのことを書くでもないが、思いつくままに書くとすると次の二点ぐらいがある。
第一に、退屈の文学史である。
この本を読んで、「つれづれ」とも「アンニュイ」とも「懶(ものうし)」とも出てこない。退屈な状態を、文学的に表現するならば、このようになるかと思う。たぶん、これは意図的にそう書いているのかと思う。退屈ということが、古今東西の文学作品のなかでどのように表現され、文学的主題としてあつかわれてきたか、これはこれとして、とても興味あることである。
第二、還世界について。
人間と動物とでは、住んでいる世界が異なる。感知しているまわりの世界が異なることは理解できる。そして、人間においては、多様な世界を行き来できるということもまた、理解はできる。だが、もう一歩踏み込んで分析することも可能かと思う。人間にとって環境とは、意図せずにたまたまそのような環境におかれるという状態もあるだろうし、あるいは、意図的に自らをそのような環境においてみることもできる。このあたりの人間の意志とのかかわりは、もうすこし分析する必要があるかもしれない。また、例えば、色彩の世界についていってみれば、確かに人間の感知することのできる色彩の世界と、モンシロチョウの感知する色彩の世界は違っている(このことは、色彩学の本にはたいてい出てくる。)人間が、多様な環境に身をおくことができるとしても、色彩に限ってみるならば、人間の感知できる範囲は、おのずと決まっている。他の動物のような色彩の環境に容易に入っていけるものではない。
以上の二点のことを書いてみる。
國分功一郎の本では、『中動態の世界』は買ってあるのだが、しまいこんだままになっている。取り出してきて、読んでおきたいと思う。
それから、さらに書いてみるならば、この本では最初に「暇」も「退屈」も定義していない。そうではなくて、この本を読むと、「退屈」とはこのような状態をさすのだな、ということが理解できるように書いてある。このような論のたてかたもあるのだと思う。
2022年1月11日記
『人新世の「資本論」』斎藤幸平 ― 2021-12-20
2021-12-20 當山日出夫(とうやまひでお)

斎藤幸平.『人新世の「資本論」』(集英社新書).集英社.2020
https://shinsho.shueisha.co.jp/kikan/1035-a/
話題の本ということで読んでみることにした。結論からいうと、私は、この本には賛成しない。その理由を三つばかり書いてみる。
第一には、人間観である。
人間の社会というのは、そんなに善良なものなのであろうか。むしろ、野蛮状態というべきかもしれない。これがいいすぎならば、無秩序と混乱といってもいいだろう。既存の社会のシステムが崩壊した後に、どのような安定した社会を作ることができるか、その道筋について、具体的に何もふれていない。たとえば、現在の中東情勢など見ても、そんなに今後の国際情勢を楽観的に考えることはできないと思う。
第二には、社会観である。
3.5%の人が動くならならば、社会は変革するという。はたして、これが一般的にいえることなのだろうか。そして、重要なことだと思うのは、3.5%の人びとの行動で社会が変わってしまうならば、一般の民主的手続き……選挙であり多数決を原則とする議決である……これは、どうなるのだろうか。まあ、現在の民主的な手続きは、行き詰まりを見せているので、それに変わる代替手段があり得るということかもしれない。だが、それが一般的、普遍的に適用できるという見通しは、まだ無理だろうと思うがどうであろうか。
第三には、中国である。
この本の中には、中国のことがほとんど出てこない。問題視されているのは、日本や欧米の諸国である。しかし、実際の国際社会のなかで、これから中国の存在感が大きくなることが懸念される。気候変動について、中国の責任は大きい。では、その一党独裁専制国家のゆくすえを、どう考えるのか。これも、3.5%の人びとが行動すれば、体制変革が可能というのであろうか。
以上の三つばかりを書いてみた。
無論、この本から学ぶところはいくつかある。特に、始めの方の気候変動への危機感などは、最重要の課題というべきであろう。また、マルクスの思想についても、晩年のマルクスがどのように考えていたか、これはこれとして興味深い。
晩年のマルクスから学ぶことは多くあるにちがいない。しかし、そこで留意すべきは、マルクスの生きた時代の科学、技術のあり方、人びとの生活様式のあり方、これは、二一世紀の今日とは異なっていることである。この点を無視して、ただマルクスがこう考えたで、それをもってくればいいというものではあるまい。晩年のマルクスの主張から脱成長のコミュニズムというのは、短絡していると思わざるを得ない。少なくとも、それほど説得力のある議論とは感じられない。
また、どうして最後のところで、精神論になるのであろうか。このあたりも気になる論のはこびである。以前に読んだ白井聡の本でも、最後は精神論で頑張れで終わっていた。最後は精神論で頑張れで終わるしかないということは、どうもその論理全体が破綻しているとしか思えないのである。
他にもいろいろと思うことはあるが、一読に値する本ではあると思う。
2021年12月13日記
https://shinsho.shueisha.co.jp/kikan/1035-a/
話題の本ということで読んでみることにした。結論からいうと、私は、この本には賛成しない。その理由を三つばかり書いてみる。
第一には、人間観である。
人間の社会というのは、そんなに善良なものなのであろうか。むしろ、野蛮状態というべきかもしれない。これがいいすぎならば、無秩序と混乱といってもいいだろう。既存の社会のシステムが崩壊した後に、どのような安定した社会を作ることができるか、その道筋について、具体的に何もふれていない。たとえば、現在の中東情勢など見ても、そんなに今後の国際情勢を楽観的に考えることはできないと思う。
第二には、社会観である。
3.5%の人が動くならならば、社会は変革するという。はたして、これが一般的にいえることなのだろうか。そして、重要なことだと思うのは、3.5%の人びとの行動で社会が変わってしまうならば、一般の民主的手続き……選挙であり多数決を原則とする議決である……これは、どうなるのだろうか。まあ、現在の民主的な手続きは、行き詰まりを見せているので、それに変わる代替手段があり得るということかもしれない。だが、それが一般的、普遍的に適用できるという見通しは、まだ無理だろうと思うがどうであろうか。
第三には、中国である。
この本の中には、中国のことがほとんど出てこない。問題視されているのは、日本や欧米の諸国である。しかし、実際の国際社会のなかで、これから中国の存在感が大きくなることが懸念される。気候変動について、中国の責任は大きい。では、その一党独裁専制国家のゆくすえを、どう考えるのか。これも、3.5%の人びとが行動すれば、体制変革が可能というのであろうか。
以上の三つばかりを書いてみた。
無論、この本から学ぶところはいくつかある。特に、始めの方の気候変動への危機感などは、最重要の課題というべきであろう。また、マルクスの思想についても、晩年のマルクスがどのように考えていたか、これはこれとして興味深い。
晩年のマルクスから学ぶことは多くあるにちがいない。しかし、そこで留意すべきは、マルクスの生きた時代の科学、技術のあり方、人びとの生活様式のあり方、これは、二一世紀の今日とは異なっていることである。この点を無視して、ただマルクスがこう考えたで、それをもってくればいいというものではあるまい。晩年のマルクスの主張から脱成長のコミュニズムというのは、短絡していると思わざるを得ない。少なくとも、それほど説得力のある議論とは感じられない。
また、どうして最後のところで、精神論になるのであろうか。このあたりも気になる論のはこびである。以前に読んだ白井聡の本でも、最後は精神論で頑張れで終わっていた。最後は精神論で頑張れで終わるしかないということは、どうもその論理全体が破綻しているとしか思えないのである。
他にもいろいろと思うことはあるが、一読に値する本ではあると思う。
2021年12月13日記
『歴史が後ずさりするとき』ウンベルト・エーコ ― 2021-08-10
2021-08-10 當山日出夫(とうやまひでお)

ウンベルト・エーコ.リッカルド・アマディ(訳).『歴史が後ずさりするとき-熱い戦争とメディア-』(岩波現代文庫).岩波書店.2021 (岩波書店.2013)
https://www.iwanami.co.jp/book/b577711.html
エーコの本であるが、単行本が出たときに買いそびれていたものである。岩波現代文庫版で出たので、買って読んでみた。
読んで思うことは、次の二点を書いてみたい。
第一には、PCということ。
PC(政治的な正しさ)については、さまざまに議論がある。一律に、こうすればよいと結論を得ることはむずかしい。いや、PCというのは、むしろそのような精神、知性のあり方の問題かもしれない。ただ、こうすればよいという正解を求めるのではなく、どのように生きてゆきたいのか、どのような社会であるべきか、反省と希望をこめた、人間社会のいとなみそのものであるのかとも思う。
この本は、エッセイ集というべき編集になっているのだが、その編集された章のいくつかは、PCについて言及がある。読んで、なるほど、このような知性のあり方が、PCというものなのかと納得するところがある。ただ、こうすればよいという答えがあるのではなく、なぜそうしなければならないのか、そのよってきたるところを、根源的に問いかけるところがある。
第二には、科学と技術ということ。
日本語で「科学技術」ということばで、ひとまとりにしてしまうことが多い。それを、著者は、厳格に区別してる。「科学」と「技術」は別物であると明確にいいきっている。これは、日常的に「科学技術」という概念で日本語のなかで生活しているものにとっては、かなりインパクトのある発言である。
科学と技術を分けて考えることこそ、科学的なものの考え方につながるといってもいいのだろう。
以上の二点のことを思って見る。
総合的な読後感としては、強靱な、そしてしなやかであり、また、緻密な知性のあり方というものを、強く感じる本である。この本はエッセイ集として、時評という側面もある。中近東の紛争、また、EUにおける移民の問題、このような時事的な問題をふまえながらも、時として、視線は第二次世界大戦、ヒトラーやムッソリーニのことにまでおよぶ。大きな歴史のながれを、良心的かつ冷静に見る姿勢には、思わず読んでいて襟を正す、あるいは、読みふけってしまうところがある。
今の日本で、このような知性の持ち主がいるだろうか。(私の読んだことの範囲では、少し古くなるが、林達夫のことなどを思い出すことになる。)文庫本としては、ちょっと分量があるが、しかし、じっくりと読む価値のある本である。
2021年7月21日記
https://www.iwanami.co.jp/book/b577711.html
エーコの本であるが、単行本が出たときに買いそびれていたものである。岩波現代文庫版で出たので、買って読んでみた。
読んで思うことは、次の二点を書いてみたい。
第一には、PCということ。
PC(政治的な正しさ)については、さまざまに議論がある。一律に、こうすればよいと結論を得ることはむずかしい。いや、PCというのは、むしろそのような精神、知性のあり方の問題かもしれない。ただ、こうすればよいという正解を求めるのではなく、どのように生きてゆきたいのか、どのような社会であるべきか、反省と希望をこめた、人間社会のいとなみそのものであるのかとも思う。
この本は、エッセイ集というべき編集になっているのだが、その編集された章のいくつかは、PCについて言及がある。読んで、なるほど、このような知性のあり方が、PCというものなのかと納得するところがある。ただ、こうすればよいという答えがあるのではなく、なぜそうしなければならないのか、そのよってきたるところを、根源的に問いかけるところがある。
第二には、科学と技術ということ。
日本語で「科学技術」ということばで、ひとまとりにしてしまうことが多い。それを、著者は、厳格に区別してる。「科学」と「技術」は別物であると明確にいいきっている。これは、日常的に「科学技術」という概念で日本語のなかで生活しているものにとっては、かなりインパクトのある発言である。
科学と技術を分けて考えることこそ、科学的なものの考え方につながるといってもいいのだろう。
以上の二点のことを思って見る。
総合的な読後感としては、強靱な、そしてしなやかであり、また、緻密な知性のあり方というものを、強く感じる本である。この本はエッセイ集として、時評という側面もある。中近東の紛争、また、EUにおける移民の問題、このような時事的な問題をふまえながらも、時として、視線は第二次世界大戦、ヒトラーやムッソリーニのことにまでおよぶ。大きな歴史のながれを、良心的かつ冷静に見る姿勢には、思わず読んでいて襟を正す、あるいは、読みふけってしまうところがある。
今の日本で、このような知性の持ち主がいるだろうか。(私の読んだことの範囲では、少し古くなるが、林達夫のことなどを思い出すことになる。)文庫本としては、ちょっと分量があるが、しかし、じっくりと読む価値のある本である。
2021年7月21日記
『ゲンロン戦記』東浩紀 ― 2021-02-18
2021-02-18 當山日出夫(とうやまひでお)

東浩紀.『ゲンロン戦記』(中公新書ラクレ).中央公論社.2020
https://www.chuko.co.jp/laclef/2020/12/150709.html
話題になっている本ということで買って読んでみた。
東浩紀については、その書いたものはいくつか手にとったことはあるのだが、はっきりいってそうひかれることなく、今まで来てしまっている。といって、特に否定的に思っていたわけではない。現代における言論人の一人ぐらいの認識でいた。
この本を読んで、その活動が、ゲンロンという組織、会社に依拠したものであったことを知ったといってよい。なるほど、このような活動をしてきた人物なのかと、認識を新たにしたということが本当のところである。
面白い本なので、一息に読んでしまった。
読んで思ったこととしては、現代における「知」のあり方についての、問いかけになっていることである。既存のシステム……大学であったり研究室であったり、あるいは、マスコミや大手の出版はであったり……に依拠しない、自立した「知」のサークルをつくりあげていったあゆみ、そのあゆみは、決して平坦なものではなかったことがあきらかにになるのだが……そのあしどりを、かなり即物的に語ってある。ここには、形而上的な思弁というものはない。
だが、この本全体を通じて、これは、現代における一つの「知」のあり方を問いかける、ある意味での思想書になり得ていると思う。
COVID-19の影響で、ゲンロンの仕事もオンライン主体になっているようである。これは、時代の趨勢といってしまえばそれまでだが、しかし、このような時代にあって、「知」のあり方を根本から考える足場として、オンラインというのは、一つ新たな地平を切り拓くものであるのかもしれない。
ところで、この本に紹介してあるゲンロンの連想で思うこととしては、京都の上七軒文庫の活動がある。
上七軒文庫
https://kamishitiken-bunko.com/
ともに、これからの時代における「知」のあり方として、注目していきたいと思う。
2021年2月7日記
https://www.chuko.co.jp/laclef/2020/12/150709.html
話題になっている本ということで買って読んでみた。
東浩紀については、その書いたものはいくつか手にとったことはあるのだが、はっきりいってそうひかれることなく、今まで来てしまっている。といって、特に否定的に思っていたわけではない。現代における言論人の一人ぐらいの認識でいた。
この本を読んで、その活動が、ゲンロンという組織、会社に依拠したものであったことを知ったといってよい。なるほど、このような活動をしてきた人物なのかと、認識を新たにしたということが本当のところである。
面白い本なので、一息に読んでしまった。
読んで思ったこととしては、現代における「知」のあり方についての、問いかけになっていることである。既存のシステム……大学であったり研究室であったり、あるいは、マスコミや大手の出版はであったり……に依拠しない、自立した「知」のサークルをつくりあげていったあゆみ、そのあゆみは、決して平坦なものではなかったことがあきらかにになるのだが……そのあしどりを、かなり即物的に語ってある。ここには、形而上的な思弁というものはない。
だが、この本全体を通じて、これは、現代における一つの「知」のあり方を問いかける、ある意味での思想書になり得ていると思う。
COVID-19の影響で、ゲンロンの仕事もオンライン主体になっているようである。これは、時代の趨勢といってしまえばそれまでだが、しかし、このような時代にあって、「知」のあり方を根本から考える足場として、オンラインというのは、一つ新たな地平を切り拓くものであるのかもしれない。
ところで、この本に紹介してあるゲンロンの連想で思うこととしては、京都の上七軒文庫の活動がある。
上七軒文庫
https://kamishitiken-bunko.com/
ともに、これからの時代における「知」のあり方として、注目していきたいと思う。
2021年2月7日記
『リベラリズムの終わり』萱野稔人 ― 2020-12-28
2020-12-28 當山日出夫(とうやまひでお)

萱野稔人.『リベラリズムの終わり-その限界と未来-』(幻冬舎新書).幻冬舎.2019
https://www.gentosha.co.jp/book/b12748.html
たぶん、ここで書く今年最後の本になる。今読んでいるのは向田邦子の作品。今手に入るエッセイなど……文庫本で出ているもの……を、集中的に読んでいる。向田邦子については、年があらたまってから書いていこうと思う。
萱野稔人という人……哲学者……は、気になっている人の一人である。その書いていることに賛成か、そうでないか、判断しかねるところはあるのだが、その問題提起について、なるほどと同感するところが多い。
この本についてもそうである。このような議論からはじまる……同性婚を認めるならば、一夫多妻や一妻多夫も認めなければならなくなる、当事者の合意があり、誰に迷惑をかけるわけではないのであるから……この議論は、確かに読んでいてなるほどこのように考えることもできるのか、と感心した。「リベラル」という立場をつきつめていくならば、どこまでの自由を認めることになるのか、また、その主義主張はどれほど社会的に有効なものであるのか、ここのところを、つきつめて考えてある。
ただ、この本の後半の議論……人びとが分かち合うべきパイの大きさのこととか、『自由論』に言及したあたりになってくると、はっきりいって、私にはよく分からないというのが正直なところである。しかし、著者はその立場として真剣に議論していることは分かる。
私個人としては、かなりリベラルな立場でものを考える方かとは思っている。しかし、なぜそのように考えるのか、そして、その思考の行き着くところはどこで、どのような限界があるのか、あまり考えてみたことはない。この意味においては、リベラルにものを考えるとはどういうことなのか、いったん立ち止まって考えることになる。
COVID-19で明け暮れてしまった一年であったと思うが、このような中にあってこそ、ものを考えること、そしてその考えを追求していくことの重要性を、改めて感じている次第である。
2020年12月27日記
https://www.gentosha.co.jp/book/b12748.html
たぶん、ここで書く今年最後の本になる。今読んでいるのは向田邦子の作品。今手に入るエッセイなど……文庫本で出ているもの……を、集中的に読んでいる。向田邦子については、年があらたまってから書いていこうと思う。
萱野稔人という人……哲学者……は、気になっている人の一人である。その書いていることに賛成か、そうでないか、判断しかねるところはあるのだが、その問題提起について、なるほどと同感するところが多い。
この本についてもそうである。このような議論からはじまる……同性婚を認めるならば、一夫多妻や一妻多夫も認めなければならなくなる、当事者の合意があり、誰に迷惑をかけるわけではないのであるから……この議論は、確かに読んでいてなるほどこのように考えることもできるのか、と感心した。「リベラル」という立場をつきつめていくならば、どこまでの自由を認めることになるのか、また、その主義主張はどれほど社会的に有効なものであるのか、ここのところを、つきつめて考えてある。
ただ、この本の後半の議論……人びとが分かち合うべきパイの大きさのこととか、『自由論』に言及したあたりになってくると、はっきりいって、私にはよく分からないというのが正直なところである。しかし、著者はその立場として真剣に議論していることは分かる。
私個人としては、かなりリベラルな立場でものを考える方かとは思っている。しかし、なぜそのように考えるのか、そして、その思考の行き着くところはどこで、どのような限界があるのか、あまり考えてみたことはない。この意味においては、リベラルにものを考えるとはどういうことなのか、いったん立ち止まって考えることになる。
COVID-19で明け暮れてしまった一年であったと思うが、このような中にあってこそ、ものを考えること、そしてその考えを追求していくことの重要性を、改めて感じている次第である。
2020年12月27日記
『民主主義とは何か』宇野重規 ― 2020-12-17
2020-12-17 當山日出夫(とうやまひでお)

宇野重規.『民主主義とは何か』(講談社現代新書).講談社.2020
https://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000324372
出たときに買っておいて、しばらく積んであった本である。ここしばらく、太宰治を集中的に読んでいた。
これが「話題」の本であるとは思っていた。いうまでもなく学術会議の一件である。
この本を読んでみての感想としては、この本の著者である宇野重規を学術会議に入れなかった判断を下したの誰であるかは知らないが、しかし、その人物について、ある意味で畏敬の念を感じるところがある(無論、皮肉をこめてであるが)。なるほど、このような本を書くと、学術会議から排除されるのか。ならば、排除されずにメンバーになっている学者は、曲学阿世の御用学者ばかりか……ふと、そんなかんぐりをしたくなってくる……だが、問題の本質は、そこのところが不明瞭なままである点にある。基準が不透明なのが、一番の問題点だと思う。
それはともかく、この本は面白い。「民主主義」という日常的に使っていることばであり、あるいは、その中に生きているはずの社会の制度である。それについて、民主主義とはどのような歴史があり、実際に運用するにあたっては、どのような課題があるのか、実に丁寧に分かりやすく説明してある。きちんと手順をふんで、ものごとを丁寧に考えていくとはこういう知性のあり方をしめすのである、その見本のような本である。
もし、私が、まだ若くて……高校生ぐらいであって、この本を読んだとしたら、将来の自分の進路として、法学部を選び、政治思想、政治学をこころざしたかもしれない、そんな気にもなってくる。この本は、特に若いひとに読んでもらいたいと思う本である。これからの日本の「民主主義」は、これからの若いひとがになっていくものである。
そろそろ年末である。この年のベストがいろいろ発表されるころかと思うが、この本は、かならずどこかで取り上げられるにちがいない。
2020年12月14日記
https://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000324372
出たときに買っておいて、しばらく積んであった本である。ここしばらく、太宰治を集中的に読んでいた。
これが「話題」の本であるとは思っていた。いうまでもなく学術会議の一件である。
この本を読んでみての感想としては、この本の著者である宇野重規を学術会議に入れなかった判断を下したの誰であるかは知らないが、しかし、その人物について、ある意味で畏敬の念を感じるところがある(無論、皮肉をこめてであるが)。なるほど、このような本を書くと、学術会議から排除されるのか。ならば、排除されずにメンバーになっている学者は、曲学阿世の御用学者ばかりか……ふと、そんなかんぐりをしたくなってくる……だが、問題の本質は、そこのところが不明瞭なままである点にある。基準が不透明なのが、一番の問題点だと思う。
それはともかく、この本は面白い。「民主主義」という日常的に使っていることばであり、あるいは、その中に生きているはずの社会の制度である。それについて、民主主義とはどのような歴史があり、実際に運用するにあたっては、どのような課題があるのか、実に丁寧に分かりやすく説明してある。きちんと手順をふんで、ものごとを丁寧に考えていくとはこういう知性のあり方をしめすのである、その見本のような本である。
もし、私が、まだ若くて……高校生ぐらいであって、この本を読んだとしたら、将来の自分の進路として、法学部を選び、政治思想、政治学をこころざしたかもしれない、そんな気にもなってくる。この本は、特に若いひとに読んでもらいたいと思う本である。これからの日本の「民主主義」は、これからの若いひとがになっていくものである。
そろそろ年末である。この年のベストがいろいろ発表されるころかと思うが、この本は、かならずどこかで取り上げられるにちがいない。
2020年12月14日記
『フランス革命についての省察』エドマンド・バーク/二木麻里(訳) ― 2020-09-24
2020-09-24 當山日出夫(とうやまひでお)

エドマンド・バーク.二木麻里(訳).『フランス革命についての省察』(光文社古典新訳文庫).光文社.2020
https://www.kotensinyaku.jp/books/book329/
この本を読んでいるとき、日本の政治はというと……八年にわたった安倍政権がおわることになり、次の自民党総裁をえらぶことになった。そして、その結果は、菅義偉が決まった。このような政治状況のなかで、この本を読んだことになる。
率直な感想を言えば……日本の政治家のなんとだらしないことか、という思いである。
ともあれ、この本は、フランス革命に際して、英国から見てそれをどう思うか、考察を加えたものであり、英国保守思想を体系化した書物として、古典的な位置をしめる本である。ひととおり、このようなことは知っていたが、読むのは、これが初めてになる。(たしか、中央公論社の『世界の名著』のなかにはいっていたかと思うが、これはしまい込んだままになっている。)
保守思想とは何かということについては、今更のべるほどのこともないだろう。以前に、少しだけ書いたことがある。
やまもも書斎記 2016年7月1日
宇野重規『保守主義とは何か』
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2016/07/01/8122012
ただ、今回、『フランス革命についての省察』を読んで思うことを記しておくならば、次のことがある。それは、バークがこの本を書いたとき、英国は、立憲君主制を確立しており、まがりなりにも、民主的な制度がととのった状況にあったということである。そのような英国から見て、フランス革命の行きすぎた点、不十分な点、問題点などを、冷静に観察している。そのような批判ができるというのも、その時点に英国における政治制度の熟成ということを、考えておくべきであろう。
この本を読みながら、あえて付箋をつけることはせずに読んだのだが、一箇所だけ注目しておきたいところを引用しておく。
「社会の構成メンバーの利害も多様になれば、さまざまな秩序とさまざまな見方ができて、その数が多いほど社会一般の自由にとっては保障になるのです。」(p.77)
今、社会の多様性ということが、各方面から言われている。このとき、多様な意見を尊重し、耳を傾けること……これこそ、保守主義の最も重視することである。すくなくとも、真性の保守主義者であろうとするならば、このことに十分に配慮しなければならない。
保守を自認するする人、組織、政党などは多いかもしれないが、そこに、多様な意見の尊重という観点が、どれほどあるだろうか。それを欠くような考え方については、私は、保守とは言いたくない。
この本は、保守主義の古典的著作ではあるが、むしろ、リベラルといわれる立場にとっても、非常に有意義なものとなっていると感じる。どのような政治的立場をとるにせよ、熟読する価値のある本であることはまちがいない。
2020年9月16日記
https://www.kotensinyaku.jp/books/book329/
この本を読んでいるとき、日本の政治はというと……八年にわたった安倍政権がおわることになり、次の自民党総裁をえらぶことになった。そして、その結果は、菅義偉が決まった。このような政治状況のなかで、この本を読んだことになる。
率直な感想を言えば……日本の政治家のなんとだらしないことか、という思いである。
ともあれ、この本は、フランス革命に際して、英国から見てそれをどう思うか、考察を加えたものであり、英国保守思想を体系化した書物として、古典的な位置をしめる本である。ひととおり、このようなことは知っていたが、読むのは、これが初めてになる。(たしか、中央公論社の『世界の名著』のなかにはいっていたかと思うが、これはしまい込んだままになっている。)
保守思想とは何かということについては、今更のべるほどのこともないだろう。以前に、少しだけ書いたことがある。
やまもも書斎記 2016年7月1日
宇野重規『保守主義とは何か』
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2016/07/01/8122012
ただ、今回、『フランス革命についての省察』を読んで思うことを記しておくならば、次のことがある。それは、バークがこの本を書いたとき、英国は、立憲君主制を確立しており、まがりなりにも、民主的な制度がととのった状況にあったということである。そのような英国から見て、フランス革命の行きすぎた点、不十分な点、問題点などを、冷静に観察している。そのような批判ができるというのも、その時点に英国における政治制度の熟成ということを、考えておくべきであろう。
この本を読みながら、あえて付箋をつけることはせずに読んだのだが、一箇所だけ注目しておきたいところを引用しておく。
「社会の構成メンバーの利害も多様になれば、さまざまな秩序とさまざまな見方ができて、その数が多いほど社会一般の自由にとっては保障になるのです。」(p.77)
今、社会の多様性ということが、各方面から言われている。このとき、多様な意見を尊重し、耳を傾けること……これこそ、保守主義の最も重視することである。すくなくとも、真性の保守主義者であろうとするならば、このことに十分に配慮しなければならない。
保守を自認するする人、組織、政党などは多いかもしれないが、そこに、多様な意見の尊重という観点が、どれほどあるだろうか。それを欠くような考え方については、私は、保守とは言いたくない。
この本は、保守主義の古典的著作ではあるが、むしろ、リベラルといわれる立場にとっても、非常に有意義なものとなっていると感じる。どのような政治的立場をとるにせよ、熟読する価値のある本であることはまちがいない。
2020年9月16日記
『日本思想史』末木文美士 ― 2020-09-18
2020-09-18 當山日出夫(とうやまひでお)

末木文美士.『日本思想史』(岩波新書).岩波書店.2020
https://www.iwanami.co.jp/book/b492574.html
これは出た時に買った本なのだが、しばらく積んであった。最初の方だけ読んでみて、なるほどと思う反面、ちょっとつまらないかなと感じるところが半分、ということで、置いたままになってしまっていた。夏休みの時間のとれるときにと思って、最初から、再度読みなおしてみた。
正直言って、なんとなく味気ない。たしかに、「日本思想史」というテーマで、目一杯のことを詰めこんで書いてあるという印象はある。そのせいか、結果として、なんとなく、教科書的な事項の羅列になってしまっているということになる。
だが、これも、視点を変えて見るならば、自分の知識の整理、確認という意味では、読んでいて、勉強になる本である。ときには、このようなこと、人物、言説があったのかと、改めて気付くところがあったりもする。
ただ、この本の冒頭に掲げてあること……日本の思想を、「神仏」と「王権」で読み解く、時代区分としては、古代から近世まで、明治から昭和戦前まで、戦後から今日まで……このような整理のしかたをこころみていることになるのだが、はたして、これが成功したかどうかとなると、どうもそうは思えない。「神仏」「王権」はまあ、そのような見方もあるかとは思うが、時代区分については、どうかと思う。近現代についても、その底流にあるものを古代からの流れのなかで考えるべきではないだろうか。あるは、明治以降の近代というものも、近世からの連続として考える歴史の考え方もあるだろう。
そうはいっても、この本が一定の水準にあることはたしかである。私の専門でわかる範囲のこと、日本の文字についての記述、仮名の成立とか、漢文訓読とか、これは、基本的に通説にしたがって書いてある。そう逸脱した独自の見解が示されているということはない。(だが、より専門的な目で見るならば、この本の記述の範囲は、あくまでも通説の範囲をこえるものとはなっていない。)
このような意味では、一定の信頼をおいて読んでいい本だというのが、印象として残ることである。知識の整理という観点からは、よく書けている本だと思う。
2020年9月16日記
https://www.iwanami.co.jp/book/b492574.html
これは出た時に買った本なのだが、しばらく積んであった。最初の方だけ読んでみて、なるほどと思う反面、ちょっとつまらないかなと感じるところが半分、ということで、置いたままになってしまっていた。夏休みの時間のとれるときにと思って、最初から、再度読みなおしてみた。
正直言って、なんとなく味気ない。たしかに、「日本思想史」というテーマで、目一杯のことを詰めこんで書いてあるという印象はある。そのせいか、結果として、なんとなく、教科書的な事項の羅列になってしまっているということになる。
だが、これも、視点を変えて見るならば、自分の知識の整理、確認という意味では、読んでいて、勉強になる本である。ときには、このようなこと、人物、言説があったのかと、改めて気付くところがあったりもする。
ただ、この本の冒頭に掲げてあること……日本の思想を、「神仏」と「王権」で読み解く、時代区分としては、古代から近世まで、明治から昭和戦前まで、戦後から今日まで……このような整理のしかたをこころみていることになるのだが、はたして、これが成功したかどうかとなると、どうもそうは思えない。「神仏」「王権」はまあ、そのような見方もあるかとは思うが、時代区分については、どうかと思う。近現代についても、その底流にあるものを古代からの流れのなかで考えるべきではないだろうか。あるは、明治以降の近代というものも、近世からの連続として考える歴史の考え方もあるだろう。
そうはいっても、この本が一定の水準にあることはたしかである。私の専門でわかる範囲のこと、日本の文字についての記述、仮名の成立とか、漢文訓読とか、これは、基本的に通説にしたがって書いてある。そう逸脱した独自の見解が示されているということはない。(だが、より専門的な目で見るならば、この本の記述の範囲は、あくまでも通説の範囲をこえるものとはなっていない。)
このような意味では、一定の信頼をおいて読んでいい本だというのが、印象として残ることである。知識の整理という観点からは、よく書けている本だと思う。
2020年9月16日記
『マックス・ウェーバー』野口雅弘 ― 2020-06-11
2020-06-11 當山日出夫(とうやまひでお)
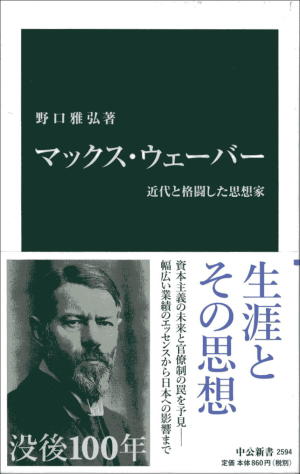
野口雅弘.『マックス・ウェーバー-近代と格闘した思想家-』(中公新書).中央公論新社.2020
https://www.chuko.co.jp/shinsho/2020/05/102594.html
中公新書と岩波新書で、マックス・ウェーバーについての本がほぼ同時に出た。これは、両方買って読むことにした。どちらから読んでもいいようなものかもしれないが、中公新書の方から読むことにした。著者の野口雅弘は、『仕事としての学問』の新訳など出している。これは出たときに買って読んだ。
やまもも書斎記 2018年7月27日
『仕事としての学問』マックス・ウェーバー
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/07/27/8926433
この訳が印象にのこっているので、中公新書の方からということにした。
中公新書『マックス・ウェーバー』であるが、この本の特徴とすべき点については、この本のあとがきで、著者自身がきちんと整理して書いてある。特に、何ほどのことを付け足すこともないかと思う。
が、読んで印象に残ったことなど書くとすれば、次の二点ぐらいだろうか。
第一には、マックス・ウェーバーの現代的な意味である。
現代において、特に、現代の日本において、マックス・ウェーバーの著作を読むことに、どのような意味があるかという問いかけが随所にある。かつて、マックス・ウェーバーが描き出した、ヨーロッパの近代というものが、日本においては、ある種の理想視されていたという側面がある。私が学生のころ、まさに、マックス・ウェーバーは、そのように読まれていたと言っていいだろう。特に、岩波文庫『プロ倫』の訳者である、大塚久雄の影響力はかなり大きかったと、今になって回想してみることになる。
ヨーロッパの近代を絶対視することがなくなって、あるいは、それを世界的規模のなかで相対的に見るような視点がうまれてきて、「近代」や「宗教」というもの対する考え方も、また変わってきているところがある。そころのところの問題点を、この本はするどく指摘している。
第二には、マックス・ウェーバーを歴史のなかで見る視点である。
たとえば、マックス・ウェーバーと、スコット・フィッツジェラルドを同時代の人間として、見るような視点の設定である。そういえば、『グレート・ギャツビー』も読んではいるのだが、これも、再度読みなおしてみたくなった。
その他、幾多の同時代の登場人物が出てくる。多彩な歴史的な人物群のなかにおくことで、マックス・ウェーバー自身もまた、歴史のなかに位置する一人として描かれることになる。
以上の二点が、中公新書の『マックス・ウェーバー』を読んで思ったことなどである。
さて、岩波新書の『マックス・ヴェーバー』も出たときに買ってある。つづけて読むことにしたい。
2020年6月8日記
https://www.chuko.co.jp/shinsho/2020/05/102594.html
中公新書と岩波新書で、マックス・ウェーバーについての本がほぼ同時に出た。これは、両方買って読むことにした。どちらから読んでもいいようなものかもしれないが、中公新書の方から読むことにした。著者の野口雅弘は、『仕事としての学問』の新訳など出している。これは出たときに買って読んだ。
やまもも書斎記 2018年7月27日
『仕事としての学問』マックス・ウェーバー
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/07/27/8926433
この訳が印象にのこっているので、中公新書の方からということにした。
中公新書『マックス・ウェーバー』であるが、この本の特徴とすべき点については、この本のあとがきで、著者自身がきちんと整理して書いてある。特に、何ほどのことを付け足すこともないかと思う。
が、読んで印象に残ったことなど書くとすれば、次の二点ぐらいだろうか。
第一には、マックス・ウェーバーの現代的な意味である。
現代において、特に、現代の日本において、マックス・ウェーバーの著作を読むことに、どのような意味があるかという問いかけが随所にある。かつて、マックス・ウェーバーが描き出した、ヨーロッパの近代というものが、日本においては、ある種の理想視されていたという側面がある。私が学生のころ、まさに、マックス・ウェーバーは、そのように読まれていたと言っていいだろう。特に、岩波文庫『プロ倫』の訳者である、大塚久雄の影響力はかなり大きかったと、今になって回想してみることになる。
ヨーロッパの近代を絶対視することがなくなって、あるいは、それを世界的規模のなかで相対的に見るような視点がうまれてきて、「近代」や「宗教」というもの対する考え方も、また変わってきているところがある。そころのところの問題点を、この本はするどく指摘している。
第二には、マックス・ウェーバーを歴史のなかで見る視点である。
たとえば、マックス・ウェーバーと、スコット・フィッツジェラルドを同時代の人間として、見るような視点の設定である。そういえば、『グレート・ギャツビー』も読んではいるのだが、これも、再度読みなおしてみたくなった。
その他、幾多の同時代の登場人物が出てくる。多彩な歴史的な人物群のなかにおくことで、マックス・ウェーバー自身もまた、歴史のなかに位置する一人として描かれることになる。
以上の二点が、中公新書の『マックス・ウェーバー』を読んで思ったことなどである。
さて、岩波新書の『マックス・ヴェーバー』も出たときに買ってある。つづけて読むことにしたい。
2020年6月8日記
『保守と大東亜戦争』中島岳志 ― 2018-10-11
2018-10-11 當山日出夫(とうやまひでお)

中島岳志.『保守と大東亜戦争』(集英社新書).集英社.2018
http://shinsho.shueisha.co.jp/kikan/0941-a/
集英社新書で出た本ということもあって、気楽に読んだ本である。特に目新しいことが書いてあるということはない。しかし、この本に書かれているようなこと踏まえたうえで、歴史の議論はなされるべきだろうと思う。
この本を読んで思うことなど書くとすると、次の二点。
第一には、著者ならではの「保守」の論理にしたがっている。「保守思想」について、まず定義がある。
著者(中島岳志)が、大学にはいってから手にした西部邁を引用する。
「自由民主主義は保守主義であらざるをえない」
さらにつづけて、このように著者(中島岳志)は記している。
「保守は人間に対する懐疑的な見方を共有し、理性の万能性や無謬を疑います。そして、その懐疑的な人間観は自己にも向けられます。自分の理性や知性もパーフェクトなものではなく、自分の主張の中にも間違いや誤認が含まれていると考えます。その自己認識は、異なる他者の意見を聞こうとする姿勢につながり、対話や議論を促進します。そして、他者の見解の中に理があると判断した場合には、協議による合意形成を進めていきます。」(p.18)
このような心性のありかたこそ、リベラルであるとする。これはこれで一つの立場であると認める。
このような意味では、現在の政権の政策などは、「保守」「リベラル」から最も遠いものであるということになるであろう。
第二には、このような「保守」の心性を持った人びとが、戦前・戦中の時期にどのような、言論活動をおこなったかをみていくことになる。
取り上げられているのは、
竹山道雄
田中美知太郎
猪木正道
福田恆存
池島信平
山本七平
会田雄次
林健太郎
などである。
これらの人びとの言説をとりあげながら、「保守」の心性をもった人間こそが、戦争に反対していたと論じる。
ここのところ、特に目新しい議論というわけではない。だが、改めて、この本に示されているような形で提示されると、なるほど、「保守」とは、現実の政治の動きに抵抗し、歴史と伝統のなかに自己の立脚点を見いだす……このようなことが再確認される。
以上の二点が、この本を読んで感ずることなどである。
無論、戦前、戦中において、戦争に反対した立場をとったのは、「保守」だけに限らないであろう。だが、今の時代において、「保守」といえば、ただ戦前回帰、大東亜戦争肯定論、このように考えがちな傾向に対しては、ちょっと待って考えてみようとすることになる。
この本からすこし引用しておくと、鶴見俊輔について、次のように述べる。
「鶴見の指摘は非常に重要です。戦前の日本は保守的だったから権威主義体制を拡大させ、全体主義的なヴィジョンにのめり込んでいったのではありません。逆です。近代日本における保守の空洞化こそが、大東亜戦争に至るプロセスを制止できなかった要因なのです。」(p.67)
戦前の歴史について、さらに考えてみることの必要性をつよく感じさせる本である。
http://shinsho.shueisha.co.jp/kikan/0941-a/
集英社新書で出た本ということもあって、気楽に読んだ本である。特に目新しいことが書いてあるということはない。しかし、この本に書かれているようなこと踏まえたうえで、歴史の議論はなされるべきだろうと思う。
この本を読んで思うことなど書くとすると、次の二点。
第一には、著者ならではの「保守」の論理にしたがっている。「保守思想」について、まず定義がある。
著者(中島岳志)が、大学にはいってから手にした西部邁を引用する。
「自由民主主義は保守主義であらざるをえない」
さらにつづけて、このように著者(中島岳志)は記している。
「保守は人間に対する懐疑的な見方を共有し、理性の万能性や無謬を疑います。そして、その懐疑的な人間観は自己にも向けられます。自分の理性や知性もパーフェクトなものではなく、自分の主張の中にも間違いや誤認が含まれていると考えます。その自己認識は、異なる他者の意見を聞こうとする姿勢につながり、対話や議論を促進します。そして、他者の見解の中に理があると判断した場合には、協議による合意形成を進めていきます。」(p.18)
このような心性のありかたこそ、リベラルであるとする。これはこれで一つの立場であると認める。
このような意味では、現在の政権の政策などは、「保守」「リベラル」から最も遠いものであるということになるであろう。
第二には、このような「保守」の心性を持った人びとが、戦前・戦中の時期にどのような、言論活動をおこなったかをみていくことになる。
取り上げられているのは、
竹山道雄
田中美知太郎
猪木正道
福田恆存
池島信平
山本七平
会田雄次
林健太郎
などである。
これらの人びとの言説をとりあげながら、「保守」の心性をもった人間こそが、戦争に反対していたと論じる。
ここのところ、特に目新しい議論というわけではない。だが、改めて、この本に示されているような形で提示されると、なるほど、「保守」とは、現実の政治の動きに抵抗し、歴史と伝統のなかに自己の立脚点を見いだす……このようなことが再確認される。
以上の二点が、この本を読んで感ずることなどである。
無論、戦前、戦中において、戦争に反対した立場をとったのは、「保守」だけに限らないであろう。だが、今の時代において、「保守」といえば、ただ戦前回帰、大東亜戦争肯定論、このように考えがちな傾向に対しては、ちょっと待って考えてみようとすることになる。
この本からすこし引用しておくと、鶴見俊輔について、次のように述べる。
「鶴見の指摘は非常に重要です。戦前の日本は保守的だったから権威主義体制を拡大させ、全体主義的なヴィジョンにのめり込んでいったのではありません。逆です。近代日本における保守の空洞化こそが、大東亜戦争に至るプロセスを制止できなかった要因なのです。」(p.67)
戦前の歴史について、さらに考えてみることの必要性をつよく感じさせる本である。
最近のコメント