『西郷どん』あれこれ「斉彬の遺言」 ― 2018-05-01
2018-05-01 當山日出夫(とうやまひでお)
『西郷どん』2018年4月29日、第16回「斉彬の遺言」
https://www.nhk.or.jp/segodon/story/16/
前回は、
やまもも書斎記 2018年4月24日
『西郷どん』あれこれ「殿の死」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/04/24/8832129
今回描かれていたのは、月照との関係、それから、西郷の斉彬への忠誠心、ということになるだろう。
月照という人物、幕末史には登場するのだが、いったい何をした人物なのか今ひとつはっきり知らないでいる。勤王の僧ということで名前は知っているのだが。そして、西郷とともに入水自殺をこころみて、西郷は助かるが、月照は死んでしまう。
斉彬の死ということを契機にして、西郷の斉彬への忠誠心は最高潮に達しているかのごとくである。忠誠心、これは、前近代の封建的なエトスと言っていいだろう。それを基盤にして、これからの西郷の活躍……幕末の薩摩藩を率いて倒幕へとつきすすんでいく……になる。この前近代的な心情と、近代国家としての日本の建設者としての理念、これがどう西郷という人物のなかでひとつにまとまっていくことになるのか、このあたりが、今後の展開で気になるところである。
ドラマはまだ江戸時代、幕末である。近代というものが見えていない。これから、このドラマで、近代というものをどのようなものとして描くことになるのだろうか。かろうじて近代を予見していたのが、斉彬だったのかもしれないが、死んでしまっている。その斉彬の遺志としての近代、これを西郷がうけついでいくことになるのかと思う。封建的主従関係における忠誠心と、近代国家としての合理主義、これらが今後の西郷のなかでどう結びついていくことになるのだろうか。
ところで、今回も、品川の妓楼、磯田屋の場面があった。他の場面、特に江戸城でのシーンなどと比べると、どうもNHKは、この品川の磯田屋のセットの方に、コストを費やしているように思える。逆に見れば、江戸城のシーンが、いかにもショボいのであるが、これは、予算の関係でいたしかたないのかもしれない。
また、今回の『西郷どん』では、天皇は登場しないようだ。以前の『八重の桜』で、孝明天皇が重要な登場人物として出ていたのにくらべると、ここもちょっと残念な気がする。そして、これから、明治になるとして、明治天皇は登場することになるのだろうか。
次回は、西郷と月照の入水となるらしい。これも楽しみに見ることにしよう。
追記 2018-05-08
この続きは、
やまもも書斎記 2018年5月8日
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/05/08/8846726
『西郷どん』2018年4月29日、第16回「斉彬の遺言」
https://www.nhk.or.jp/segodon/story/16/
前回は、
やまもも書斎記 2018年4月24日
『西郷どん』あれこれ「殿の死」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/04/24/8832129
今回描かれていたのは、月照との関係、それから、西郷の斉彬への忠誠心、ということになるだろう。
月照という人物、幕末史には登場するのだが、いったい何をした人物なのか今ひとつはっきり知らないでいる。勤王の僧ということで名前は知っているのだが。そして、西郷とともに入水自殺をこころみて、西郷は助かるが、月照は死んでしまう。
斉彬の死ということを契機にして、西郷の斉彬への忠誠心は最高潮に達しているかのごとくである。忠誠心、これは、前近代の封建的なエトスと言っていいだろう。それを基盤にして、これからの西郷の活躍……幕末の薩摩藩を率いて倒幕へとつきすすんでいく……になる。この前近代的な心情と、近代国家としての日本の建設者としての理念、これがどう西郷という人物のなかでひとつにまとまっていくことになるのか、このあたりが、今後の展開で気になるところである。
ドラマはまだ江戸時代、幕末である。近代というものが見えていない。これから、このドラマで、近代というものをどのようなものとして描くことになるのだろうか。かろうじて近代を予見していたのが、斉彬だったのかもしれないが、死んでしまっている。その斉彬の遺志としての近代、これを西郷がうけついでいくことになるのかと思う。封建的主従関係における忠誠心と、近代国家としての合理主義、これらが今後の西郷のなかでどう結びついていくことになるのだろうか。
ところで、今回も、品川の妓楼、磯田屋の場面があった。他の場面、特に江戸城でのシーンなどと比べると、どうもNHKは、この品川の磯田屋のセットの方に、コストを費やしているように思える。逆に見れば、江戸城のシーンが、いかにもショボいのであるが、これは、予算の関係でいたしかたないのかもしれない。
また、今回の『西郷どん』では、天皇は登場しないようだ。以前の『八重の桜』で、孝明天皇が重要な登場人物として出ていたのにくらべると、ここもちょっと残念な気がする。そして、これから、明治になるとして、明治天皇は登場することになるのだろうか。
次回は、西郷と月照の入水となるらしい。これも楽しみに見ることにしよう。
追記 2018-05-08
この続きは、
やまもも書斎記 2018年5月8日
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/05/08/8846726
藤の花 ― 2018-05-02
2018-05-02 當山日出夫(とうやまひでお)
水曜日なので花の写真の日。今日は藤である。
前回は、
やまもも書斎記 2018年4月25日
シャガの花
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/04/25/8832794
今年は、桜も早かったが、藤も早い。去年撮った写真の日付など確認してみると、五月の連休ぐらいで満開という状態である。今年は、終わりかけにちかい。
藤棚が半分に分けてあって、早く咲くのと、少し遅れて咲くのとになっている。早く咲く方の藤は、もう終わってしまっている。散ってしまったあとである。写真に写したのは、遅く咲いている方。それでも、すでに盛りを少しすぎているぐらいだろうか。
『日本国語大辞典』(ジャパンナレッジ)を検索してみる。「藤」は、万葉集から用例がある。また、重ねの色目としての用法も、枕草子からある。藤という花、そして、その色合いは、古くから親しまれてきたことが理解される。
Facebookでは、四月の後半は主に藤の花を掲載していた。他には、山吹やすみれなど。朝起きて、一通りの用事をすませて(ブログのアップロードなど)、カメラと三脚を持って外に出る。藤の花を一枚写して、それを掲載する。これも、先月で終わりである。五月になって、次は何の花にしようかと思っている。とりあえず、紫蘭が咲き始めたので、それを写してみた。このブログも、来週は紫蘭になるかもしれない。あるいは、先月のうちに写しておいたものから選ぶことになるかもしれない。花の写真を撮るようになって、季節の変化の早さというのを感じるようになってきている。
水曜日なので花の写真の日。今日は藤である。
前回は、
やまもも書斎記 2018年4月25日
シャガの花
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/04/25/8832794
今年は、桜も早かったが、藤も早い。去年撮った写真の日付など確認してみると、五月の連休ぐらいで満開という状態である。今年は、終わりかけにちかい。
藤棚が半分に分けてあって、早く咲くのと、少し遅れて咲くのとになっている。早く咲く方の藤は、もう終わってしまっている。散ってしまったあとである。写真に写したのは、遅く咲いている方。それでも、すでに盛りを少しすぎているぐらいだろうか。
『日本国語大辞典』(ジャパンナレッジ)を検索してみる。「藤」は、万葉集から用例がある。また、重ねの色目としての用法も、枕草子からある。藤という花、そして、その色合いは、古くから親しまれてきたことが理解される。
Facebookでは、四月の後半は主に藤の花を掲載していた。他には、山吹やすみれなど。朝起きて、一通りの用事をすませて(ブログのアップロードなど)、カメラと三脚を持って外に出る。藤の花を一枚写して、それを掲載する。これも、先月で終わりである。五月になって、次は何の花にしようかと思っている。とりあえず、紫蘭が咲き始めたので、それを写してみた。このブログも、来週は紫蘭になるかもしれない。あるいは、先月のうちに写しておいたものから選ぶことになるかもしれない。花の写真を撮るようになって、季節の変化の早さというのを感じるようになってきている。
Nikon D7500
AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR
AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR
追記 2018-05-09
この続きは、
やまもも書斎記 2018年5月9日
クロバイ
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/05/09/8847429
『警官の掟』佐々木譲 ― 2018-05-03
2018-05-03 當山日出夫(とうやまひでお)
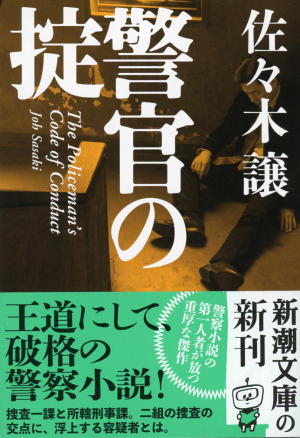
佐々木譲.『警官の掟』(新潮文庫).新潮社.2018 (新潮社.2015 『犬の掟』改題)
http://www.shinchosha.co.jp/book/122328/
年をとったせいなのだろうが、本を読むとき、以前よりもじっくりと読むようになった。たいていの本は、細かに字を追っていくことにしている。だが、この本だけは、途中で斜め読みになってしまった。これは、失敗であったのかもしれない。
東京湾岸で発見された、男の射殺死体。それを捜査する、蒲田署の警察官。一方、警視庁でも、独自に調査を開始する。その捜査の途上にうかぶ過去の事件……謎の女医の事件や、教師の溺死事件など。そして、最後にあかされる、驚きの真相。
簡単に書けばこのようになる。
が、この小説、あまりにも、登場人物の視点が錯綜している。所轄署の刑事たち、それとは別に、警視庁の刑事たち。複数の視点が、同時並行で語られる。それが最後に一つになったとき、真相が明らかになる……このようなストーリーの展開であることは分かるのだが、今ひとつ、登場人物に感情移入できないで読んでしまった。(これも、じっくりと読んでみれば、そうではなかったのかもしれないのだが。)
警察小説というのは、やはり、登場人物の視点はシンプルであった方がいい。そして、その視点人物(警官)に感情移入しながら読み進めるというのが、理解しやすい。この作品、構成において大胆な試みをもってきた、斬新な警察小説であるという気はするのだが、従来の警察小説の枠組みの印象で読んでいくと、無理を感じる。
警察小説というのは、警察官という特殊な職業の人間にどれだけ、感情移入して読めるかだと思う。それが、素朴な正義感であったり、あるいは、悪徳警官であったりしても。(私の読んだ印象では)この作品の場合、結局、どの登場人物にも共感できないで終わってしまった。といって、再度読んでみようという気もおこらないのであるが。とはいえ、リアリズム警察小説としては、一級のできばえの作品ではあると思う。
気をとりなおして、宮部みゆきを読むことにしようかと思っている。
http://www.shinchosha.co.jp/book/122328/
年をとったせいなのだろうが、本を読むとき、以前よりもじっくりと読むようになった。たいていの本は、細かに字を追っていくことにしている。だが、この本だけは、途中で斜め読みになってしまった。これは、失敗であったのかもしれない。
東京湾岸で発見された、男の射殺死体。それを捜査する、蒲田署の警察官。一方、警視庁でも、独自に調査を開始する。その捜査の途上にうかぶ過去の事件……謎の女医の事件や、教師の溺死事件など。そして、最後にあかされる、驚きの真相。
簡単に書けばこのようになる。
が、この小説、あまりにも、登場人物の視点が錯綜している。所轄署の刑事たち、それとは別に、警視庁の刑事たち。複数の視点が、同時並行で語られる。それが最後に一つになったとき、真相が明らかになる……このようなストーリーの展開であることは分かるのだが、今ひとつ、登場人物に感情移入できないで読んでしまった。(これも、じっくりと読んでみれば、そうではなかったのかもしれないのだが。)
警察小説というのは、やはり、登場人物の視点はシンプルであった方がいい。そして、その視点人物(警官)に感情移入しながら読み進めるというのが、理解しやすい。この作品、構成において大胆な試みをもってきた、斬新な警察小説であるという気はするのだが、従来の警察小説の枠組みの印象で読んでいくと、無理を感じる。
警察小説というのは、警察官という特殊な職業の人間にどれだけ、感情移入して読めるかだと思う。それが、素朴な正義感であったり、あるいは、悪徳警官であったりしても。(私の読んだ印象では)この作品の場合、結局、どの登場人物にも共感できないで終わってしまった。といって、再度読んでみようという気もおこらないのであるが。とはいえ、リアリズム警察小説としては、一級のできばえの作品ではあると思う。
気をとりなおして、宮部みゆきを読むことにしようかと思っている。
『言葉の海へ』高田宏 ― 2018-05-04
2018-05-04 當山日出夫(とうやまひでお)

高田宏.『言葉の海へ』(新潮文庫).新潮社.2018 (新潮社.1978)
http://www.shinchosha.co.jp/book/133301/
この本は再読になる。最初出た時に買って読んだのを覚えている。学生のときだった。
はっきり言って、学生の時……国文学、国語学ということを勉強する……この本を読んであまり関心しなかったのが印象として残っている。『言海』という辞書の成立論をあつかったものとして読むと、今ひとつ物足りなく感じてしまったのであろう。
だが、それから四〇年ほどたって、文庫版で再読してみて……なるほど、若い時にこの本の良さが分からなかったのも無理はない、と反省するところがある。この本は『言海』という辞書の成立論……学問的分野でいえば、国語学史ということになる……の本ではない。そうではなく、幕末から明治にかけて、近代を生きた大槻文彦という人物の、その生涯をつらぬいていたものが何であったかの評伝なのである。これは、近代という時代を作ってきた、一人の人間、大槻文彦の人生を追った作品である。
逆に言えば、この本からは、「近代」というものを見てとることができるかもしれない。そのような広い視点にたって読まないといけない。
この本は、明治24年、芝公園の紅葉館での、『言海』出版記念の祝宴のときからはじまる。この時の祝宴に集まった人びとを紹介した後、著者(高田宏)は、次のように書いている。
「参会者を貴顕碩学の諸士と呼べばそれまでだが、この顔ぶれには実は三つの焦点がある。(中略)/円の一つは「条約改正への関心」であり、二つは「反藩閥の心情」、そして三つが「洋学を背景にした国家意識」だ。ナショナリズムとも呼べる感情が、この三つを結んでいる。」(pp.30-31)
この本『言葉の海へ』で描き出される大槻文彦の人生は、ナショナリズムの人生であるといってよいであろう。
断っておくと、私は、ナショナリズムを悪い意味でつかおうとは思わない。幕末から明治の初期にかけて、近代的な国家である日本をどのように築いていくか、その根底にある素朴な、だが一方で熱烈な、感情である。これを私は、肯定的に受けとめておきたいと思っているし、また、この本を読んで感じる、大槻文彦のナショナリズムは、素直に肯定できるものして描かれている。
そして、このナショナリズムの感情が起こってくる背景にあるのが、仙台という土地にかかわる、江戸時代以来の感情……リージョナリズム(郷土意識とでも言おうか)……、それと、大槻文彦の学んだ洋学、そして、漢学、である。
この本から浮かび上がってくるのは、大槻文彦という一人の人間の人生であると同時に、大槻が生きた時代……幕末から明治にかけて……その「近代」という時代の様相である。それは、明治維新をなしとげた薩長藩閥でもない、仙台という地に根ざした地方の感覚から、日本という近代国家へと変貌していくプロセスでもある。
新しい新潮文庫本は、明治150年ということで刊行になったらしい。「近代」という時代を考えてみるのに役に立つ、すぐれた本であると思う。
追記 2018-05-05
この続きは、
やまもも書斎記 2018年5月5日
『言葉の海へ』高田宏(その二)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/05/05/8844424
http://www.shinchosha.co.jp/book/133301/
この本は再読になる。最初出た時に買って読んだのを覚えている。学生のときだった。
はっきり言って、学生の時……国文学、国語学ということを勉強する……この本を読んであまり関心しなかったのが印象として残っている。『言海』という辞書の成立論をあつかったものとして読むと、今ひとつ物足りなく感じてしまったのであろう。
だが、それから四〇年ほどたって、文庫版で再読してみて……なるほど、若い時にこの本の良さが分からなかったのも無理はない、と反省するところがある。この本は『言海』という辞書の成立論……学問的分野でいえば、国語学史ということになる……の本ではない。そうではなく、幕末から明治にかけて、近代を生きた大槻文彦という人物の、その生涯をつらぬいていたものが何であったかの評伝なのである。これは、近代という時代を作ってきた、一人の人間、大槻文彦の人生を追った作品である。
逆に言えば、この本からは、「近代」というものを見てとることができるかもしれない。そのような広い視点にたって読まないといけない。
この本は、明治24年、芝公園の紅葉館での、『言海』出版記念の祝宴のときからはじまる。この時の祝宴に集まった人びとを紹介した後、著者(高田宏)は、次のように書いている。
「参会者を貴顕碩学の諸士と呼べばそれまでだが、この顔ぶれには実は三つの焦点がある。(中略)/円の一つは「条約改正への関心」であり、二つは「反藩閥の心情」、そして三つが「洋学を背景にした国家意識」だ。ナショナリズムとも呼べる感情が、この三つを結んでいる。」(pp.30-31)
この本『言葉の海へ』で描き出される大槻文彦の人生は、ナショナリズムの人生であるといってよいであろう。
断っておくと、私は、ナショナリズムを悪い意味でつかおうとは思わない。幕末から明治の初期にかけて、近代的な国家である日本をどのように築いていくか、その根底にある素朴な、だが一方で熱烈な、感情である。これを私は、肯定的に受けとめておきたいと思っているし、また、この本を読んで感じる、大槻文彦のナショナリズムは、素直に肯定できるものして描かれている。
そして、このナショナリズムの感情が起こってくる背景にあるのが、仙台という土地にかかわる、江戸時代以来の感情……リージョナリズム(郷土意識とでも言おうか)……、それと、大槻文彦の学んだ洋学、そして、漢学、である。
この本から浮かび上がってくるのは、大槻文彦という一人の人間の人生であると同時に、大槻が生きた時代……幕末から明治にかけて……その「近代」という時代の様相である。それは、明治維新をなしとげた薩長藩閥でもない、仙台という地に根ざした地方の感覚から、日本という近代国家へと変貌していくプロセスでもある。
新しい新潮文庫本は、明治150年ということで刊行になったらしい。「近代」という時代を考えてみるのに役に立つ、すぐれた本であると思う。
追記 2018-05-05
この続きは、
やまもも書斎記 2018年5月5日
『言葉の海へ』高田宏(その二)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/05/05/8844424
『言葉の海へ』高田宏(その二) ― 2018-05-05
2018-05-05 當山日出夫(とうやまひでお)

続きである。
やまもも書斎記
『言葉の海へ』高田宏
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/05/04/8843351
高田宏.『言葉の海へ』(新潮文庫).新潮社.2018 (新潮社.1978)
http://www.shinchosha.co.jp/book/133301/
この画像は、私が持っている『言海』の「あ」の冒頭の部分である。学生の時に古書店で買って今も持っているものである。
この本を読みながら付箋をつけた箇所を、すこし引用しておきたい。
「「日本」はすこしずつ育ってはいたが、文彦のうちにあるような「日本」は、まだこの国には根づいていない。在るべき「日本」のために、「日本辞書」と「日本文法」は、なにほどかを為し得るはずだ。そして、この仕事は余人に任せることはできぬ。いや、自分のほかに人はいない。この仕事の重さを知ること、この仕事と「日本」との関わりを明確に見ること、そして、この仕事を洋学上に築くこと、それは、この大槻文彦にしかできぬ。」(pp.245-246)
「右か左かと分ける見方からすれば、てんでんばらばらかも知れない。しかし、ひとつの思想で国は育たない。「世界」を最も知る明六社の人びとが、多様な方向に仕事をすることで、「日本」が育って行った。大槻文彦の『言海』も、そのひとつである。/或る微妙な、国家形成のかなめの仕事が、この人びとの手に成っていった。政治権力と反政府行動と、その両者だけではネーションは生まれない。必要なのは、或る微妙な、「知」を活性化した触媒である。」(p.247)
他にも多数の付箋をつけたのだが、明治の初期のナショナリズムの中に大槻文彦がいたことは確かだろう。いや、そのような人物として、著者(高田宏)は、大槻文彦を描いている。
ここで、大槻文彦のナショナリズムは、きわめて肯定的に描かれている。それが、国語辞典の編纂とストレートにむすびついている。
今日、このようなストレートなナショナリズムで、国語辞典を語ることはできなくなっている。国語辞典とは、いったい誰のための、何のための辞書であるのか、これが、改めて問われる時代をむかえている。
ひとつには、日本語という言語が、日本語を母語とする人びとだけのものではなくなってきている。外国人受け入れなどにともなって、日本語を母語としない人びとをも視野にいれる必要がおこってきている。
だが、かつて、大槻文彦が『言海』を編纂した時代は、まさに、日本語が「国語」になる、その時代でもあった。このことについて、今日の視点からは、極めて否定的にとらえる傾向が強い。だが、そのような時代、いや、それ以前の前近代、幕末期から開国の時代をむかえて、国家が成立していく過程において、日本語の辞書、文法が、自らの手によって編纂されるべきという、これは必然の意識である。
『言海』については、今日多くの研究がある。その中にあって、『言葉の海へ』は、『言海』の生まれた時代背景、明治のナショナリズムと日本語の辞書、文法ということについて、一つの見解をしめしている。ことばや辞書ということを考えていくと、どうしてもナショナリズムの問題を避けてはとおれない。『言海』とナショナリズムを考えるうえで、今後もこの本『言葉の海へ』は重要な位置を占めるものであるにちがいない。
やまもも書斎記
『言葉の海へ』高田宏
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/05/04/8843351
高田宏.『言葉の海へ』(新潮文庫).新潮社.2018 (新潮社.1978)
http://www.shinchosha.co.jp/book/133301/
この画像は、私が持っている『言海』の「あ」の冒頭の部分である。学生の時に古書店で買って今も持っているものである。
この本を読みながら付箋をつけた箇所を、すこし引用しておきたい。
「「日本」はすこしずつ育ってはいたが、文彦のうちにあるような「日本」は、まだこの国には根づいていない。在るべき「日本」のために、「日本辞書」と「日本文法」は、なにほどかを為し得るはずだ。そして、この仕事は余人に任せることはできぬ。いや、自分のほかに人はいない。この仕事の重さを知ること、この仕事と「日本」との関わりを明確に見ること、そして、この仕事を洋学上に築くこと、それは、この大槻文彦にしかできぬ。」(pp.245-246)
「右か左かと分ける見方からすれば、てんでんばらばらかも知れない。しかし、ひとつの思想で国は育たない。「世界」を最も知る明六社の人びとが、多様な方向に仕事をすることで、「日本」が育って行った。大槻文彦の『言海』も、そのひとつである。/或る微妙な、国家形成のかなめの仕事が、この人びとの手に成っていった。政治権力と反政府行動と、その両者だけではネーションは生まれない。必要なのは、或る微妙な、「知」を活性化した触媒である。」(p.247)
他にも多数の付箋をつけたのだが、明治の初期のナショナリズムの中に大槻文彦がいたことは確かだろう。いや、そのような人物として、著者(高田宏)は、大槻文彦を描いている。
ここで、大槻文彦のナショナリズムは、きわめて肯定的に描かれている。それが、国語辞典の編纂とストレートにむすびついている。
今日、このようなストレートなナショナリズムで、国語辞典を語ることはできなくなっている。国語辞典とは、いったい誰のための、何のための辞書であるのか、これが、改めて問われる時代をむかえている。
ひとつには、日本語という言語が、日本語を母語とする人びとだけのものではなくなってきている。外国人受け入れなどにともなって、日本語を母語としない人びとをも視野にいれる必要がおこってきている。
だが、かつて、大槻文彦が『言海』を編纂した時代は、まさに、日本語が「国語」になる、その時代でもあった。このことについて、今日の視点からは、極めて否定的にとらえる傾向が強い。だが、そのような時代、いや、それ以前の前近代、幕末期から開国の時代をむかえて、国家が成立していく過程において、日本語の辞書、文法が、自らの手によって編纂されるべきという、これは必然の意識である。
『言海』については、今日多くの研究がある。その中にあって、『言葉の海へ』は、『言海』の生まれた時代背景、明治のナショナリズムと日本語の辞書、文法ということについて、一つの見解をしめしている。ことばや辞書ということを考えていくと、どうしてもナショナリズムの問題を避けてはとおれない。『言海』とナショナリズムを考えるうえで、今後もこの本『言葉の海へ』は重要な位置を占めるものであるにちがいない。
『半分、青い。』あれこれ「東京、行きたい!」 ― 2018-05-06
2018-05-06 當山日出夫(とうやまひでお)
『半分、青い。』第5週「東京、行きたい!」
https://www.nhk.or.jp/hanbunaoi/story/week_05.html
前回は、
やまもも書斎記 2018年4月29日
『半分、青い。』あれこれ「夢見たい!」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/04/29/8835686
最後の土曜日になって、「やってまった」の鈴愛であったが、これからどうなるのだろう。
この週で描かれていたのは、家族・故郷への思いと、未来への希望・夢だったろうか。
秋風羽織に認められて(といっても、漫画家としての才能というよりも、五平餅の方かもしれないのだが)、東京行きを決意する鈴愛。しかし、その心中は、決して一直線というわけではない。農協への就職を世話してくれた祖父への思いもある。また、鈴愛を、東京に一人で行かせたくない、父や母の気持ちもわかる。
この鈴愛の家族への思いが、じんわりと描かれていたように思う。これから東京に出て行くとして、その東京で故郷のことを懐かしく思い出すことになるのだろう。
一方、律の方は、京都大学を受験するようだが、これは無事に合格するのだろうか。ドラマのこれからを考えると、律も東京に行くことになるのかもしれないと思ったりする。結局、京大も駄目で、東京の私立の有名校といったあたりだろうか。
1989年から1990年にかけてである。日本の情勢はといえば、バブル経済の絶頂期と言っていいだろう。サンバランドは実現しなかったようだが、これは、その後のことを考えると、幸いというべきである。
ちょうど昭和が終わって平成になる時期である。また、世界では、ベルリンの壁が崩壊し、東西冷戦が終わった時期になる。一つの大きな時代の転換点でもある。この時期に、東京に出て生活を始めることになる地方出身者は、どんな思いでいたのだろうか。
ただバブルの風俗を描くだけにとどまらず、社会情勢、国際情勢のなかで、その社会を生きてきた若者の姿を描いてほしいと思う。ベルリンの壁を壊した若者と同じ時代の空気のなかで生きてきたことになるのである。
ただ気になるのは、鈴愛が漫画家になりたいのか、それとも、故郷を出て東京に行きたいと思っているのか、このあたりの気持ちが、はっきりしていないことである。どうも見ていると、漫画家という仕事、また、その業界について、そんなに知っているということではないようだ。鈴愛は、漫画は「夢」であると言っていた。それは、ある意味でそのとおりなのだが、現実には、その業界の中で生きのびるということが待っているはずである。(漫画家志望の若者といえば、『ひよっこ』に出てきた、富山出身の青年たちを思い出すのだが。)
ともあれ、この週は、鈴愛の故郷と家族への思いが感じられる展開であった。東京に出てから、この故郷と家族が、どのように思い出されることになるのか、このあたり気になるところでもある。
『半分、青い。』第5週「東京、行きたい!」
https://www.nhk.or.jp/hanbunaoi/story/week_05.html
前回は、
やまもも書斎記 2018年4月29日
『半分、青い。』あれこれ「夢見たい!」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/04/29/8835686
最後の土曜日になって、「やってまった」の鈴愛であったが、これからどうなるのだろう。
この週で描かれていたのは、家族・故郷への思いと、未来への希望・夢だったろうか。
秋風羽織に認められて(といっても、漫画家としての才能というよりも、五平餅の方かもしれないのだが)、東京行きを決意する鈴愛。しかし、その心中は、決して一直線というわけではない。農協への就職を世話してくれた祖父への思いもある。また、鈴愛を、東京に一人で行かせたくない、父や母の気持ちもわかる。
この鈴愛の家族への思いが、じんわりと描かれていたように思う。これから東京に出て行くとして、その東京で故郷のことを懐かしく思い出すことになるのだろう。
一方、律の方は、京都大学を受験するようだが、これは無事に合格するのだろうか。ドラマのこれからを考えると、律も東京に行くことになるのかもしれないと思ったりする。結局、京大も駄目で、東京の私立の有名校といったあたりだろうか。
1989年から1990年にかけてである。日本の情勢はといえば、バブル経済の絶頂期と言っていいだろう。サンバランドは実現しなかったようだが、これは、その後のことを考えると、幸いというべきである。
ちょうど昭和が終わって平成になる時期である。また、世界では、ベルリンの壁が崩壊し、東西冷戦が終わった時期になる。一つの大きな時代の転換点でもある。この時期に、東京に出て生活を始めることになる地方出身者は、どんな思いでいたのだろうか。
ただバブルの風俗を描くだけにとどまらず、社会情勢、国際情勢のなかで、その社会を生きてきた若者の姿を描いてほしいと思う。ベルリンの壁を壊した若者と同じ時代の空気のなかで生きてきたことになるのである。
ただ気になるのは、鈴愛が漫画家になりたいのか、それとも、故郷を出て東京に行きたいと思っているのか、このあたりの気持ちが、はっきりしていないことである。どうも見ていると、漫画家という仕事、また、その業界について、そんなに知っているということではないようだ。鈴愛は、漫画は「夢」であると言っていた。それは、ある意味でそのとおりなのだが、現実には、その業界の中で生きのびるということが待っているはずである。(漫画家志望の若者といえば、『ひよっこ』に出てきた、富山出身の青年たちを思い出すのだが。)
ともあれ、この週は、鈴愛の故郷と家族への思いが感じられる展開であった。東京に出てから、この故郷と家族が、どのように思い出されることになるのか、このあたり気になるところでもある。
追記 2018-05-13
この続きは、
やまもも書斎記 2018年5月13日
『半分、青い。』あれこれ「叫びたい!」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/05/13/8850229
この続きは、
やまもも書斎記 2018年5月13日
『半分、青い。』あれこれ「叫びたい!」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/05/13/8850229
『三鬼』宮部みゆき ― 2018-05-07
2018-05-07 當山日出夫(とうやまひでお)

宮部みゆき.『三鬼 三島屋変調百物語四之続』.日本経済新聞出版社.2016
https://www.nikkeibook.com/book/78878
このシリーズの最新作『あやかし草紙』が出て読もうと思ったのだが、実は、その前作になるこの本が未読で積んであった。取り出してきて読んでおくことにした。
このシリーズも、これで四冊目である。三島屋にすまいするおちか。彼女が、いろんな人から怪異の話し、不思議な話しを聞く、という筋立て。「語って語り捨て、聞いて聞き捨て」の物語である。作品の長さからいえば、中編の集になる。
この本には、次の作品をおさめてある。
「迷いの旅籠」
「食客ひだる神」
「三鬼」
「おくらさま」
宮部みゆきは多彩な作品を書いているが、時代小説として、どこかしら怪異を含む作品群がある。その近年の代表作は、『この世の春』であろうか。これについては、すでに書いた。
やまもも書斎記 2017年9月8日
『この世の春』宮部みゆき
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2017/09/08/8672570
この時にも書いたことだが、宮部みゆきの時代小説、怪異小説は、どんどん話しがあっちに行ったり、こっちに行ったりする。どこに着地点があるのか、全体の構成がどうなっているのか、読んでいって不安になるところがある。特に長編だとそれを感じる。そして、評価によっては、これはマイナスの要因になるだろう。
だが、中編の作品の場合、その不安がない。比較的短い作品のなかで、登場人物(語り手)の登場があって、その話を語ることの範囲で、どうにか一つの作品がおさまっている。手際よく、こじんまりと中編のなかにまとめてある。これは、安心して読める。
怪異の話し……これは、今ではあまり流行らなくなった文学の形式かもしれない。いや、そうではないということがあるのかとも思う。私が知らないだけで、現代には現代なりの怪異文学というものがあるのかもしれない。
宮部みゆきの怪異の話しは、身の毛もよだつという恐怖を感じるものはすくない。むしろ、この世の不条理、切なさ、やるせなさ、といった諸々の感情を表象するものとしての、怪異の話しであるように読める。合理的な人の世の道理では、説明のつかない、それでは割り切ることのできないどうしようもない、この世の人の有様の不可解さ、理不尽さとでもいうべきものである。それを、宮部みゆきは、怪異の話しとして書いている。
だが、私が読んで面白いのと感じるのは、怪異といっても、怖いというよりも、どことなくユーモアを感じさせるような作品である。例えば、以前の作品であれば、「あんじゅう」がそうであった。今回の作品『三鬼』に所収の作品としては、「食客ひだる神」がそうだろう。
宮部みゆきは、現代小説でもある意味で怪異の話しとでもいうべきものを書いている。その一方で、純然たるミステリも書いている。「本格」といってもよい。
初期の宮部みゆきは、リアリズムの作家であったと認識している。だが、そのリアリズムの視点では、「現代」という時代を描けないのかもしれない。「現代」に生きている我々の感性にうったえかけるものは、リアリズムではなく、怪異、あるいは、ファンタジーであるのだろうか。
三島屋シリーズは、時代小説ではあるが、しかし、「現代」に生きる我々に語りかけるものがある。それは、この世に生きることの不条理とでもいうべきものである。それは、リアリズムでは表現することが、もはや困難なものである。
ただ、怒りとか、悲しみとか、不安とか、そのようなことばで表現してしまうことのできない、それからあふれる何かである。そのようなものに、人は生きているかぎり、どこかでかかわりをもたざるをえない。そのような何かを描き出すのに、時代小説の形をかりた怪異の話しというのが、もっともふさわしいということなのかもしれない。
宮部みゆきは、時代小説を書いているが、その視野のなかには、「現代」が見えていると感じる。
https://www.nikkeibook.com/book/78878
このシリーズの最新作『あやかし草紙』が出て読もうと思ったのだが、実は、その前作になるこの本が未読で積んであった。取り出してきて読んでおくことにした。
このシリーズも、これで四冊目である。三島屋にすまいするおちか。彼女が、いろんな人から怪異の話し、不思議な話しを聞く、という筋立て。「語って語り捨て、聞いて聞き捨て」の物語である。作品の長さからいえば、中編の集になる。
この本には、次の作品をおさめてある。
「迷いの旅籠」
「食客ひだる神」
「三鬼」
「おくらさま」
宮部みゆきは多彩な作品を書いているが、時代小説として、どこかしら怪異を含む作品群がある。その近年の代表作は、『この世の春』であろうか。これについては、すでに書いた。
やまもも書斎記 2017年9月8日
『この世の春』宮部みゆき
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2017/09/08/8672570
この時にも書いたことだが、宮部みゆきの時代小説、怪異小説は、どんどん話しがあっちに行ったり、こっちに行ったりする。どこに着地点があるのか、全体の構成がどうなっているのか、読んでいって不安になるところがある。特に長編だとそれを感じる。そして、評価によっては、これはマイナスの要因になるだろう。
だが、中編の作品の場合、その不安がない。比較的短い作品のなかで、登場人物(語り手)の登場があって、その話を語ることの範囲で、どうにか一つの作品がおさまっている。手際よく、こじんまりと中編のなかにまとめてある。これは、安心して読める。
怪異の話し……これは、今ではあまり流行らなくなった文学の形式かもしれない。いや、そうではないということがあるのかとも思う。私が知らないだけで、現代には現代なりの怪異文学というものがあるのかもしれない。
宮部みゆきの怪異の話しは、身の毛もよだつという恐怖を感じるものはすくない。むしろ、この世の不条理、切なさ、やるせなさ、といった諸々の感情を表象するものとしての、怪異の話しであるように読める。合理的な人の世の道理では、説明のつかない、それでは割り切ることのできないどうしようもない、この世の人の有様の不可解さ、理不尽さとでもいうべきものである。それを、宮部みゆきは、怪異の話しとして書いている。
だが、私が読んで面白いのと感じるのは、怪異といっても、怖いというよりも、どことなくユーモアを感じさせるような作品である。例えば、以前の作品であれば、「あんじゅう」がそうであった。今回の作品『三鬼』に所収の作品としては、「食客ひだる神」がそうだろう。
宮部みゆきは、現代小説でもある意味で怪異の話しとでもいうべきものを書いている。その一方で、純然たるミステリも書いている。「本格」といってもよい。
初期の宮部みゆきは、リアリズムの作家であったと認識している。だが、そのリアリズムの視点では、「現代」という時代を描けないのかもしれない。「現代」に生きている我々の感性にうったえかけるものは、リアリズムではなく、怪異、あるいは、ファンタジーであるのだろうか。
三島屋シリーズは、時代小説ではあるが、しかし、「現代」に生きる我々に語りかけるものがある。それは、この世に生きることの不条理とでもいうべきものである。それは、リアリズムでは表現することが、もはや困難なものである。
ただ、怒りとか、悲しみとか、不安とか、そのようなことばで表現してしまうことのできない、それからあふれる何かである。そのようなものに、人は生きているかぎり、どこかでかかわりをもたざるをえない。そのような何かを描き出すのに、時代小説の形をかりた怪異の話しというのが、もっともふさわしいということなのかもしれない。
宮部みゆきは、時代小説を書いているが、その視野のなかには、「現代」が見えていると感じる。
『西郷どん』あれこれ「西郷入水」 ― 2018-05-08
2018-05-08 當山日出夫(とうやまひでお)
『西郷どん』2018年5月6日、第17回「西郷入水」
https://www.nhk.or.jp/segodon/story/17/
前回は、
やまもも書斎記 2018年5月1日
『西郷どん』あれこれ「斉彬の遺言」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/05/01/8838524
民俗学、文化人類学の観点から言うならば、一度死の体験を経て甦る、通過儀礼を経て、新たな人生がスタートする……このように解釈できる。西郷の場合、擬似的な体験というよりも、ほとんど実際に死にかけたということである。
この回のメインは、月照と西郷の関係。だが、月照が本格的に登場したのが前回ぐらいからである。いったいこの月照という僧は、何をしたという人物なのであろうか。また、斉彬との関係はどうであったのだろうか。ここのところを描いてなかったので、どうして、西郷は、そこまで月照に思い入れするのか、今ひとつ理解できないところがあった。
今のところ、西郷の中にあるのは、故・主君斉彬への忠誠心である。そして、斉彬のためということが、イコール、薩摩藩のためであり、そして、それが、さらにイコールで、日本のためと、つながっている。このところは、西郷という人物の中では、自然な感情として描かれている。
この時点では、西郷にはまだ「近代」が見えているとは思えない。斉彬の夢みたものとして、はるかかなたに茫漠としてある、ある種の理想……それは斉彬が思っていた……のようなものである。
しかし、斉興などは、そうは思っていないようだ。「近代」などということは考えていない。あくまでも、幕藩体制における薩摩藩のためと思っている。
このあたり、幕末の薩摩藩において、藩のためということが、日本のためになり、さらに、倒幕へと動き、「近代」をもたらす、そのダイナミズムを、このドラマはどう描くことになるのであろうか。ここでは、西郷という一つの人格を描きながらも、幕末の薩摩藩というものがもっていたダイナミックな政治的判断……それは、熱狂的であると同時に怜悧なものであろうが……を、どう描き出すか、このあたりが、これからの見どころかと思う。はたして、西郷の人生のゆくすえに「近代」ということが、どのように見えてくるのであろうか。
次週、西郷は、流罪になるらしい。流罪ということも、西郷の人生を振り返ってみれば、一種の通過儀礼(イニシエーション)ということになるのかもしれない。流罪の時期をどう描くか、楽しみに見ることにしよう。
『西郷どん』2018年5月6日、第17回「西郷入水」
https://www.nhk.or.jp/segodon/story/17/
前回は、
やまもも書斎記 2018年5月1日
『西郷どん』あれこれ「斉彬の遺言」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/05/01/8838524
民俗学、文化人類学の観点から言うならば、一度死の体験を経て甦る、通過儀礼を経て、新たな人生がスタートする……このように解釈できる。西郷の場合、擬似的な体験というよりも、ほとんど実際に死にかけたということである。
この回のメインは、月照と西郷の関係。だが、月照が本格的に登場したのが前回ぐらいからである。いったいこの月照という僧は、何をしたという人物なのであろうか。また、斉彬との関係はどうであったのだろうか。ここのところを描いてなかったので、どうして、西郷は、そこまで月照に思い入れするのか、今ひとつ理解できないところがあった。
今のところ、西郷の中にあるのは、故・主君斉彬への忠誠心である。そして、斉彬のためということが、イコール、薩摩藩のためであり、そして、それが、さらにイコールで、日本のためと、つながっている。このところは、西郷という人物の中では、自然な感情として描かれている。
この時点では、西郷にはまだ「近代」が見えているとは思えない。斉彬の夢みたものとして、はるかかなたに茫漠としてある、ある種の理想……それは斉彬が思っていた……のようなものである。
しかし、斉興などは、そうは思っていないようだ。「近代」などということは考えていない。あくまでも、幕藩体制における薩摩藩のためと思っている。
このあたり、幕末の薩摩藩において、藩のためということが、日本のためになり、さらに、倒幕へと動き、「近代」をもたらす、そのダイナミズムを、このドラマはどう描くことになるのであろうか。ここでは、西郷という一つの人格を描きながらも、幕末の薩摩藩というものがもっていたダイナミックな政治的判断……それは、熱狂的であると同時に怜悧なものであろうが……を、どう描き出すか、このあたりが、これからの見どころかと思う。はたして、西郷の人生のゆくすえに「近代」ということが、どのように見えてくるのであろうか。
次週、西郷は、流罪になるらしい。流罪ということも、西郷の人生を振り返ってみれば、一種の通過儀礼(イニシエーション)ということになるのかもしれない。流罪の時期をどう描くか、楽しみに見ることにしよう。
追記 2018-05-15
この続きは、
やまもも書斎記 2018年5月15日
やまもも書斎記 『西郷どん』あれこれ「流人 菊池源吾」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/05/15/8851445
この続きは、
やまもも書斎記 2018年5月15日
やまもも書斎記 『西郷どん』あれこれ「流人 菊池源吾」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/05/15/8851445
クロバイ ― 2018-05-09
2018-05-09 當山日出夫(とうやまひでお)
水曜日は花の写真の日。今日は、クロバイである。
前回は、
やまもも書斎記 2018年5月2日
藤の花
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/05/02/8839973
我が家から少し歩いたところに咲いていた。ほぼ毎日散歩で歩くところにある。木に白い花の咲いているのが目について、写真にとって、WEBで聞いてみた。クロバイとのことである。調べてみると、どうやらクロバイであっているらしい。
ハイノキ科の常緑高木。
いつものように、日本国語大辞典(ジャパンナレッジ)を見てみる。「クロバイ」の語は、大和本草批正(1810頃)から見える。
一方、「ハイノキ」の方を見てみると、こちらは古くからある。新撰字鏡、伊呂波字類抄、から見える。
この木の花、観察してみると、その盛りの時期は意外と短い。ほぼ満開になったかなと思ったところで、雨が降って散ってしまった。季節の花の写真をとりはじめて、ほぼ一年近くになる。去年見た花が今年も見られるかどうか、気になっている。年々歳々……とはいうが、花もまた、年によって微妙に異なる。その咲いている時期を写そうと思うと、シャッターチャンスは、ほんのわずかの時期しかない。
これからどれだけの花・樹木を確認できるかわからない。相変わらずの毎日を過ごしているようでいて、花を見ていると季節の移り変わりが、確実に、そして、早いことが実感できる。
水曜日は花の写真の日。今日は、クロバイである。
前回は、
やまもも書斎記 2018年5月2日
藤の花
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/05/02/8839973
我が家から少し歩いたところに咲いていた。ほぼ毎日散歩で歩くところにある。木に白い花の咲いているのが目について、写真にとって、WEBで聞いてみた。クロバイとのことである。調べてみると、どうやらクロバイであっているらしい。
ハイノキ科の常緑高木。
いつものように、日本国語大辞典(ジャパンナレッジ)を見てみる。「クロバイ」の語は、大和本草批正(1810頃)から見える。
一方、「ハイノキ」の方を見てみると、こちらは古くからある。新撰字鏡、伊呂波字類抄、から見える。
この木の花、観察してみると、その盛りの時期は意外と短い。ほぼ満開になったかなと思ったところで、雨が降って散ってしまった。季節の花の写真をとりはじめて、ほぼ一年近くになる。去年見た花が今年も見られるかどうか、気になっている。年々歳々……とはいうが、花もまた、年によって微妙に異なる。その咲いている時期を写そうと思うと、シャッターチャンスは、ほんのわずかの時期しかない。
これからどれだけの花・樹木を確認できるかわからない。相変わらずの毎日を過ごしているようでいて、花を見ていると季節の移り変わりが、確実に、そして、早いことが実感できる。
Nikon D7500
AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR
『パルムの僧院』スタンダール ― 2018-05-10
2018-05-10 當山日出夫(とうやまひでお)
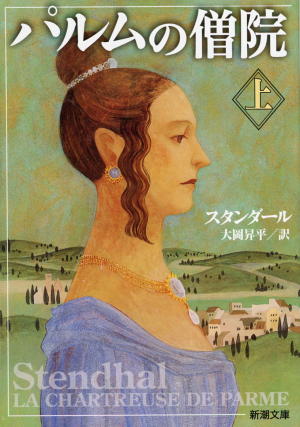
スタンダール.大岡昇平(訳).『パルムの僧院』(上・下)(新潮文庫).新潮社.1951 (2005.改版)
http://www.shinchosha.co.jp/book/200801/
http://www.shinchosha.co.jp/book/200802/
世界文学の名作、名著の読み直し。この本は、若い時に手にしたかどうか、それすら覚えていない。今になって読んでみてであるが、はっきり言ってこの作品は、分からなかった。
スタンダールの作品では、新潮文庫に『赤と黒』がある。これは、去年、読んだ。
やまもも書斎記 2017年6月1日
『赤と黒』スタンダール
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2017/06/01/8581779
『赤と黒』は、まがりなりにも、主人公(ジュリヤン・ソレル)の感情に共感するところがないではなかった。しかし、『パルムの僧院』になると、主人公(ファブリス)が、なんとも理解できない。
これは、たぶん、私の予備知識が無いせいだろう。この作品の書かれた当時のフランス、それから、作品の舞台になったイタリアの地域・歴史について、それなりに知っていれば、この作品が何を語ろうとしているいるのか、分かるのだろう。だが、世界史といえば、高校でならった世界史の範囲をそう超えるものではない私としては、この作品世界の背景の理解は、手にあまる。
もし、フランス語が十分に分かるのなら、原文でじっくりと読めば、きっと面白い本であるにちがいない、とは感じるところがあった。19世紀フランスのリアリズムの小説ということなのであるが、そのリアリズムの感覚が、どうも現代の感覚と違っている。今ひとつ作品世界の中に、没入していくことができなかった。
そうはいっても、読みながらふと作品に引きずり込まれるようなときもあった。それは、登場人物の心中思惟の場面においてである。リアリズム小説というのは、私の理解するところでは、登場人物の心理描写に、その特徴を発揮する。このような作品の延長に、近現代の文学のいろんな作品があるのだろうということは理解できるつもりでいる。
といって、今から、西欧の歴史、文学史を勉強し直す気力もない。だが、機会があれば、再度、読み直してみたい作品ではある。文学作品のとしての魅力を、奥底に秘めている、そんな感じのする作品であった。
追記 2018-05-11
この続きは、
やまもも書斎記 2018年5月11日
『パルムの僧院』スタンダール(その二)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/05/11/8848862








最近のコメント