東京国立博物館「帝室博物館総長森鷗外の筆跡」を見てきた ― 2018-06-23
2018-06-23 當山日出夫(とうやまひでお)
2018年6月9日の語彙・辞書研究会の次の日、帰るまえに寄ってきたのが、東京国立博物館である。ちょうど、「帝室博物館総長森鷗外の筆跡」の展示をやっているので、それを見てきた。
一室だけのこぢんまりとした展示である。また、展示されているものも、博物館の業務上の記録書類のようなもので派手さはない。きわめて地味な印象の展示である。だが、博物館の歴史、また、そこにいた森鴎外という人物のことを考えるには、きわめて興味深い展示であった。
東京国立博物館
就任100年 帝室博物館総長森鷗外の筆跡
http://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=1916
面白いと思ったのは、鴎外の花押である。閲覧した書類、書跡などに、鴎外は花押を記している。いや、逆に、花押のある書類などを探してきて、展示してあったというべきだろうか。見ていくと、鴎外は、博物館の収蔵品のあり方について、いろいろ思いをめぐらしていたことが見てとれる。
そして、この帝室博物館の時代は、晩年の鴎外の、いわゆる史伝ものが書かれた時代でもある。鴎外の史伝……その代表作は『渋江抽斎』『伊沢蘭軒』『北条霞亭』などであろうが……が、どのような生活、仕事を背景として生まれたのか、このような観点から見ると、非常に興味深いものがあった。
鴎外の史伝などは、本は持っている。読んだのもある。「全集」「選集」もそろえてある(岩波版)。これからは、おちついてじっくりと史伝を読んで時間をすごしたいものである。
東京から帰って、『渋江抽斎』(岩波文庫版)を読みかえしたみた。『伊沢蘭軒』『北条霞亭』など、読んでおきたい。
2018年6月9日の語彙・辞書研究会の次の日、帰るまえに寄ってきたのが、東京国立博物館である。ちょうど、「帝室博物館総長森鷗外の筆跡」の展示をやっているので、それを見てきた。
一室だけのこぢんまりとした展示である。また、展示されているものも、博物館の業務上の記録書類のようなもので派手さはない。きわめて地味な印象の展示である。だが、博物館の歴史、また、そこにいた森鴎外という人物のことを考えるには、きわめて興味深い展示であった。
東京国立博物館
就任100年 帝室博物館総長森鷗外の筆跡
http://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=1916
面白いと思ったのは、鴎外の花押である。閲覧した書類、書跡などに、鴎外は花押を記している。いや、逆に、花押のある書類などを探してきて、展示してあったというべきだろうか。見ていくと、鴎外は、博物館の収蔵品のあり方について、いろいろ思いをめぐらしていたことが見てとれる。
そして、この帝室博物館の時代は、晩年の鴎外の、いわゆる史伝ものが書かれた時代でもある。鴎外の史伝……その代表作は『渋江抽斎』『伊沢蘭軒』『北条霞亭』などであろうが……が、どのような生活、仕事を背景として生まれたのか、このような観点から見ると、非常に興味深いものがあった。
鴎外の史伝などは、本は持っている。読んだのもある。「全集」「選集」もそろえてある(岩波版)。これからは、おちついてじっくりと史伝を読んで時間をすごしたいものである。
東京から帰って、『渋江抽斎』(岩波文庫版)を読みかえしたみた。『伊沢蘭軒』『北条霞亭』など、読んでおきたい。
『半分、青い。』あれこれ「結婚したい!」 ― 2018-06-24
2018-06-24 當山日出夫(とうやまひでお)
『半分、青い。』第12週「結婚したい!」
https://www.nhk.or.jp/hanbunaoi/story/week_12.html
前回は、
やまもも書斎記
『半分、青い。』あれこれ「デビューしたい!」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/06/17/8895939
結婚したのは、裕子だった。
この週のみどころは、鈴愛よりも裕子の決断の方かもしれない。漫画家として行き詰まる。スランプである。さらに漫画家をつづけるよりも、結婚を選んだことになる。
このあたりの描写……漫画家は、ゼロから作品を作っていかなければならない、そのようなつらい仕事はもういやだ……裕子は、このような意味のことを言っていた。ここには、このドラマの作者・北川悦吏子の矜恃があっての台詞なのだろうと思って見ていた。
ドラマの脚本も、ゼロから作る。特に、今回の『半分、青い。』はオリジナル脚本である。前作、『わろてんか』のように歴史的なモデルが存在するというものではない。このドラマ『半分、青い。』は、自分がゼロから発想して作っている作品世界なのである、このようなメッセージが込められていたような気がしてならない。
脚本家にとって、ジャンルは違うとはいえ、漫画家という創造、創作にかかわる仕事を、どう描いてみせるかは、相当の覚悟があってのことだと思う。それは、今のところ、成功していると感じる。天才的漫画家としての秋風羽織、まだかけだしの鈴愛、そして、創作に行き詰まって漫画家をやめることにした裕子。それぞれの立場からの漫画創作への思いが伝わってくる週であった。
ただ、時代背景としてはバブル崩壊後のときである。この時代の若者の生き方をどう描くかというところも、興味を持って見ているのだが、今のところ、そう大きく時代背景が、鈴愛たちの生き方に影響しているということはなさそうである。それよりも、漫画というメディアと時代、という観点かもしれないと思っているが、どうだろうか。
そして、次週は、漫画家としての鈴愛にも試練の時がおとづれるようである。また、律との関係はどうなるのだろうか。
『半分、青い。』第12週「結婚したい!」
https://www.nhk.or.jp/hanbunaoi/story/week_12.html
前回は、
やまもも書斎記
『半分、青い。』あれこれ「デビューしたい!」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/06/17/8895939
結婚したのは、裕子だった。
この週のみどころは、鈴愛よりも裕子の決断の方かもしれない。漫画家として行き詰まる。スランプである。さらに漫画家をつづけるよりも、結婚を選んだことになる。
このあたりの描写……漫画家は、ゼロから作品を作っていかなければならない、そのようなつらい仕事はもういやだ……裕子は、このような意味のことを言っていた。ここには、このドラマの作者・北川悦吏子の矜恃があっての台詞なのだろうと思って見ていた。
ドラマの脚本も、ゼロから作る。特に、今回の『半分、青い。』はオリジナル脚本である。前作、『わろてんか』のように歴史的なモデルが存在するというものではない。このドラマ『半分、青い。』は、自分がゼロから発想して作っている作品世界なのである、このようなメッセージが込められていたような気がしてならない。
脚本家にとって、ジャンルは違うとはいえ、漫画家という創造、創作にかかわる仕事を、どう描いてみせるかは、相当の覚悟があってのことだと思う。それは、今のところ、成功していると感じる。天才的漫画家としての秋風羽織、まだかけだしの鈴愛、そして、創作に行き詰まって漫画家をやめることにした裕子。それぞれの立場からの漫画創作への思いが伝わってくる週であった。
ただ、時代背景としてはバブル崩壊後のときである。この時代の若者の生き方をどう描くかというところも、興味を持って見ているのだが、今のところ、そう大きく時代背景が、鈴愛たちの生き方に影響しているということはなさそうである。それよりも、漫画というメディアと時代、という観点かもしれないと思っているが、どうだろうか。
そして、次週は、漫画家としての鈴愛にも試練の時がおとづれるようである。また、律との関係はどうなるのだろうか。
追記 2018-07-01
この続きは、
やまもも書斎記 2018年7月1日
『半分、青い。』あれこれ「仕事が欲しい!」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/07/01/8906998
この続きは、
やまもも書斎記 2018年7月1日
『半分、青い。』あれこれ「仕事が欲しい!」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/07/01/8906998
『街場の憂国論』内田樹 ― 2018-06-25
2018-06-25 當山日出夫(とうやまひでお)
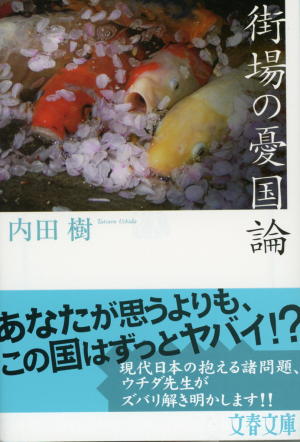
内田樹.『街場の憂国論』(文春文庫).文藝春秋.2018 (晶文社.2013)
https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784167910945
文庫本ででたものであるので、買って読んでみた。内田樹の本は、時々買って読む。この本も、ブログなど各所に書いたものを編集したものである。内容的には、かなり重複するところがある。
この本で、著者が言わんとしているところは、次の二つのことに要約できるだろう。
第一は、国民経済である。一国の経済をどうするかという議論。これは、その国……この本の場合であれば、日本ということになるが……の国民を養うために、である。その国の国民が、働いて、稼いで、それで生活できるようにするのが、国民経済の基本であるとする。
それをこわそうとしているのが、昨今のいわゆるグローバリズムという図式で語られる。
第二は、教育、なかんずく公教育の課題。これは、次世代の公民を育成するためであるとする。これも、近年の、教育現場への市場原理の導入への批判として語られる。
以上の二点、国民経済と教育、この二つの論点に、この本はつきると思う。
そして、このことは今まで内田樹の本について書いてきたことであるが、きわめて保守的な発想である。言っていることをとりあげてみれば、現政権に対しては、反体制的である。しかし、その心情の底にあるものは、きわめて保守的な心性であるといわざるをえない。
この保守の感覚を、非常によく表している本だと思って読んだことになる。
内田樹の保守の感覚に、時代にあらがう過激さのようなものはあまり感じない。むしろ、市民的感覚と言っていいだろうか。この市民感覚での保守を語った人物として、今世紀初頭に働いた人物として、内田樹の名前は記憶されることになるのだろうと思っている。
https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784167910945
文庫本ででたものであるので、買って読んでみた。内田樹の本は、時々買って読む。この本も、ブログなど各所に書いたものを編集したものである。内容的には、かなり重複するところがある。
この本で、著者が言わんとしているところは、次の二つのことに要約できるだろう。
第一は、国民経済である。一国の経済をどうするかという議論。これは、その国……この本の場合であれば、日本ということになるが……の国民を養うために、である。その国の国民が、働いて、稼いで、それで生活できるようにするのが、国民経済の基本であるとする。
それをこわそうとしているのが、昨今のいわゆるグローバリズムという図式で語られる。
第二は、教育、なかんずく公教育の課題。これは、次世代の公民を育成するためであるとする。これも、近年の、教育現場への市場原理の導入への批判として語られる。
以上の二点、国民経済と教育、この二つの論点に、この本はつきると思う。
そして、このことは今まで内田樹の本について書いてきたことであるが、きわめて保守的な発想である。言っていることをとりあげてみれば、現政権に対しては、反体制的である。しかし、その心情の底にあるものは、きわめて保守的な心性であるといわざるをえない。
この保守の感覚を、非常によく表している本だと思って読んだことになる。
内田樹の保守の感覚に、時代にあらがう過激さのようなものはあまり感じない。むしろ、市民的感覚と言っていいだろうか。この市民感覚での保守を語った人物として、今世紀初頭に働いた人物として、内田樹の名前は記憶されることになるのだろうと思っている。
『西郷どん』あれこれ「地の果てにて」 ― 2018-06-26
2018-06-26 當山日出夫(とうやまひでお)
『西郷どん』2018年6月24日、第24回「地の果てにて」
https://www.nhk.or.jp/segodon/story/24/
前回は、
やまもも書斎記 2018年6月19日
『西郷どん』あれこれ「寺田屋騒動」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/06/19/8897651
西郷は再び島流しになる。徳之島、そして、沖永良部島である。西郷のおかれた境遇は、いよいよ過酷なものとなっていく。
だが、それに反比例するかのように、「西郷」という人格に対する尊崇の念は、さらに一層ひとびとの間にひろまっていく。流罪の島の地で、西郷は、先生と呼ばれている。これからの日本を背負ってたつ人物にちがいないと、南の果ての島の島民も、西郷に敬愛の念をいだいている。
この西郷への評価の高さは、江戸でも見られる。一橋慶喜は、西郷をきわめて高く評価している描写があった。はて、いったいいつから、慶喜は西郷をこれほど高く評価するようになったのだろうか。この経緯はよくわからない。
これに対して、評価の下がっているのが、島津久光である。
ここのところの、西郷への評価の高まりと、久光のダメっぷりが、わかりやすいといえば、わかりやすく描かれていた。ここのところ、斉彬亡き後、どのようにして西郷が、人望を集めるようになったのか、その間の経緯がドラマでは、ばっさりと切り捨てられている。だから、結論として、西郷という一つの人格に、南の島の島民から、将軍家にいたるまで、信頼されることになる西郷というひとつの人格……このようにしかいいようがないだろう……が、いつの間にか登場することになっている。
次回は、生麦事件のことになるらしい。これも幕末の重要な出来事である。楽しみに見ることにしよう。
『西郷どん』2018年6月24日、第24回「地の果てにて」
https://www.nhk.or.jp/segodon/story/24/
前回は、
やまもも書斎記 2018年6月19日
『西郷どん』あれこれ「寺田屋騒動」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/06/19/8897651
西郷は再び島流しになる。徳之島、そして、沖永良部島である。西郷のおかれた境遇は、いよいよ過酷なものとなっていく。
だが、それに反比例するかのように、「西郷」という人格に対する尊崇の念は、さらに一層ひとびとの間にひろまっていく。流罪の島の地で、西郷は、先生と呼ばれている。これからの日本を背負ってたつ人物にちがいないと、南の果ての島の島民も、西郷に敬愛の念をいだいている。
この西郷への評価の高さは、江戸でも見られる。一橋慶喜は、西郷をきわめて高く評価している描写があった。はて、いったいいつから、慶喜は西郷をこれほど高く評価するようになったのだろうか。この経緯はよくわからない。
これに対して、評価の下がっているのが、島津久光である。
ここのところの、西郷への評価の高まりと、久光のダメっぷりが、わかりやすいといえば、わかりやすく描かれていた。ここのところ、斉彬亡き後、どのようにして西郷が、人望を集めるようになったのか、その間の経緯がドラマでは、ばっさりと切り捨てられている。だから、結論として、西郷という一つの人格に、南の島の島民から、将軍家にいたるまで、信頼されることになる西郷というひとつの人格……このようにしかいいようがないだろう……が、いつの間にか登場することになっている。
次回は、生麦事件のことになるらしい。これも幕末の重要な出来事である。楽しみに見ることにしよう。
追記 2018-07-03
この続きは、
やまもも書斎記 2018年7月3日
『西郷どん』あれこれ「生かされた命」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/07/03/8908156
この続きは、
やまもも書斎記 2018年7月3日
『西郷どん』あれこれ「生かされた命」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/07/03/8908156
ネジキ ― 2018-06-27
2018-06-27 當山日出夫(とうやまひでお)
水曜日は花の写真。今日はネジキ。
前回は、
やまもも書斎記 2018年6月20日
ウツギ
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/06/20/8898569
これは先月写したものである。毎日の散歩道に咲いているのが眼にとまった。とりあえず写真にとって、WEBで聞いてみた。ネジキというらしい。その後、調べてみたりするとネジキであっているようだ。5月ごろに白い花が咲く。そして、木の幹がねじれたようになっている。
日本国語大辞典(ジャパンナレッジ)を見る。
ねじき 捩木・綟木
として、
ツツジ科の落葉高木。本州、四国、九州の山地に生える。高さ約五メートル。幹はややねじれ、若枝は赤色を帯びる。
とあり、用例は、
重訂本草綱目啓蒙(1847)
から見える。言海にもあるよし。
『言海』をひいてみると、次のようにある。
ねぢき 捩木
山ニ生ズ、樹大ニシテ、皆捩(ネヂ)レテ直理ナラズ、新枝ハ、色、朱漆ノ如シ、葉ハ互生ス、夏、三寸許ノ穂ヲナシテ、白花ヲ開ク、筒形ニシテ、長サ三分許、飯粒ノ如シ、枝ヲ炭トシテ、漆塗ノ磨出(トギダシ)ニ用ヰ、かしおずみトイフ
水曜日は花の写真。今日はネジキ。
前回は、
やまもも書斎記 2018年6月20日
ウツギ
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/06/20/8898569
これは先月写したものである。毎日の散歩道に咲いているのが眼にとまった。とりあえず写真にとって、WEBで聞いてみた。ネジキというらしい。その後、調べてみたりするとネジキであっているようだ。5月ごろに白い花が咲く。そして、木の幹がねじれたようになっている。
日本国語大辞典(ジャパンナレッジ)を見る。
ねじき 捩木・綟木
として、
ツツジ科の落葉高木。本州、四国、九州の山地に生える。高さ約五メートル。幹はややねじれ、若枝は赤色を帯びる。
とあり、用例は、
重訂本草綱目啓蒙(1847)
から見える。言海にもあるよし。
『言海』をひいてみると、次のようにある。
ねぢき 捩木
山ニ生ズ、樹大ニシテ、皆捩(ネヂ)レテ直理ナラズ、新枝ハ、色、朱漆ノ如シ、葉ハ互生ス、夏、三寸許ノ穂ヲナシテ、白花ヲ開ク、筒形ニシテ、長サ三分許、飯粒ノ如シ、枝ヲ炭トシテ、漆塗ノ磨出(トギダシ)ニ用ヰ、かしおずみトイフ
Nikon D7500
AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR
『天子蒙塵』(第三巻)浅田次郎 ― 2018-06-28
2018-06-28 當山日出夫(とうやまひでお)

浅田次郎.『天子蒙塵』(第三巻).講談社.2018
http://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000310569
これは、『蒼穹の昴』シリーズの、第五部にあたる。満州国が主な舞台となっている。第三巻になって、物語は、いよいよ佳境にさしかかったというところか。新たな登場人物も多い。
これまでの巻については、
やまもも書斎記 2017年1月4日
『天子蒙塵』(第一巻)浅田次郎
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2017/01/04/8302238
やまもも書斎記 2017年3月15日
『天子蒙塵』(第二巻)浅田次郎
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2017/03/15/8406288
この第三巻では、二人の「私」の語りからはじまる。一人は、張学良。そして、もう一人は、溥儀。この二人の語りが交互に出てきて、このまま小説が進むのかと思っていると、突然、視点が変わる。普通の小説のスタイルになる。
そして、多彩な登場人物が出てくる。甘粕正彦、吉田茂、川島芳子、といった歴史上の人物も登場すれば、日本から逃走してきた、いわくありげな二人の少年、また、駆け落ちしてきた男女。さらには、春児といった、このシリーズの最初から出来ている人物まで。実に多彩な人物がでてくる。
作者は、これら多彩な登場人物の視点を行ったり来たりしながら、総合的に、満洲国という、歴史上わずかに存在した国家……それは、今の視点から見れば、日本の傀儡国家ということになるのだが……を描き出そうとしている。
これが成功しているかどうか……私の判断としては、微妙である。
事実は小説よりも奇なり、とは言うが、この時代、昭和初期の満洲国の話しのころになると、歴史的事実の方が、はっきりいってフィクションよりも面白い。ジャンルは異なるが、NHKが放送した「映像の世紀」のシリーズ。これなどいくつかの回には、溥儀の姿があったように覚えている。そして、ドキュメンタリーとして残っている溥儀の姿の方が、フィクションとして描かれた溥儀の姿よりも、圧倒的に存在感がある。これは、いたしかたのないことかもしれないが。
実際に残されている映像記録の方が、浅田次郎の文学的創造、想像の世界を、その印象の強さにおいて、はるかに凌駕してしてしまっているのである。
だが、そうはいっても、浅田次郎のことである。当時の日本、満洲国のあり方を、特に軍隊、そのなかでも、兵卒の視点から描いた場面には、説得力がある。
「日本がまちがっているのだ。支那の山河を奪ってわがものにせんとした。その戦には大義のかけらもない。醜い利欲のあるばかりだった。」(p.192)
「いや、悪いのは俺たちじゃない。大学を出ても就職先が軍隊しかないような不景気を、事実上の植民地経営で回復させようとする政治は、資本主義の退歩にちがいない。」(p.247)
「同行者を拘引せよとの命令には従えません。それは皇軍を私する不届き者がでっちあげた、偽命令にちがいないからであります。」(p.256)
それから、この小説で問いかけていることの一つは、「中国」とは何であるか、ということがある。満洲は「中国」なのであろうか。これは、東洋学、中国学の分野におけるきわめて基本的で、かつ、重要な課題である。これに、今日の日本の小説家の想像力でどのような答えを出すことになるのか……この続き、第四巻を楽しみにして読むことにしようと思っている。
http://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000310569
これは、『蒼穹の昴』シリーズの、第五部にあたる。満州国が主な舞台となっている。第三巻になって、物語は、いよいよ佳境にさしかかったというところか。新たな登場人物も多い。
これまでの巻については、
やまもも書斎記 2017年1月4日
『天子蒙塵』(第一巻)浅田次郎
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2017/01/04/8302238
やまもも書斎記 2017年3月15日
『天子蒙塵』(第二巻)浅田次郎
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2017/03/15/8406288
この第三巻では、二人の「私」の語りからはじまる。一人は、張学良。そして、もう一人は、溥儀。この二人の語りが交互に出てきて、このまま小説が進むのかと思っていると、突然、視点が変わる。普通の小説のスタイルになる。
そして、多彩な登場人物が出てくる。甘粕正彦、吉田茂、川島芳子、といった歴史上の人物も登場すれば、日本から逃走してきた、いわくありげな二人の少年、また、駆け落ちしてきた男女。さらには、春児といった、このシリーズの最初から出来ている人物まで。実に多彩な人物がでてくる。
作者は、これら多彩な登場人物の視点を行ったり来たりしながら、総合的に、満洲国という、歴史上わずかに存在した国家……それは、今の視点から見れば、日本の傀儡国家ということになるのだが……を描き出そうとしている。
これが成功しているかどうか……私の判断としては、微妙である。
事実は小説よりも奇なり、とは言うが、この時代、昭和初期の満洲国の話しのころになると、歴史的事実の方が、はっきりいってフィクションよりも面白い。ジャンルは異なるが、NHKが放送した「映像の世紀」のシリーズ。これなどいくつかの回には、溥儀の姿があったように覚えている。そして、ドキュメンタリーとして残っている溥儀の姿の方が、フィクションとして描かれた溥儀の姿よりも、圧倒的に存在感がある。これは、いたしかたのないことかもしれないが。
実際に残されている映像記録の方が、浅田次郎の文学的創造、想像の世界を、その印象の強さにおいて、はるかに凌駕してしてしまっているのである。
だが、そうはいっても、浅田次郎のことである。当時の日本、満洲国のあり方を、特に軍隊、そのなかでも、兵卒の視点から描いた場面には、説得力がある。
「日本がまちがっているのだ。支那の山河を奪ってわがものにせんとした。その戦には大義のかけらもない。醜い利欲のあるばかりだった。」(p.192)
「いや、悪いのは俺たちじゃない。大学を出ても就職先が軍隊しかないような不景気を、事実上の植民地経営で回復させようとする政治は、資本主義の退歩にちがいない。」(p.247)
「同行者を拘引せよとの命令には従えません。それは皇軍を私する不届き者がでっちあげた、偽命令にちがいないからであります。」(p.256)
それから、この小説で問いかけていることの一つは、「中国」とは何であるか、ということがある。満洲は「中国」なのであろうか。これは、東洋学、中国学の分野におけるきわめて基本的で、かつ、重要な課題である。これに、今日の日本の小説家の想像力でどのような答えを出すことになるのか……この続き、第四巻を楽しみにして読むことにしようと思っている。
追記 2018-10-04
この続きは、
やまもも書斎記 2018年10月4日
『天子蒙塵』(第四巻)浅田次郎
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/10/04/8968473
この続きは、
やまもも書斎記 2018年10月4日
『天子蒙塵』(第四巻)浅田次郎
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/10/04/8968473
京都国立近代美術館「横山大観展」を見てきた ― 2018-06-29
2018-06-29 當山日出夫(とうやまひでお)

京都国立近代美術館で開催の「横山大観展」に行ってきた。
梅雨というのに暑い日だった。地下鉄の東山から美術館まで歩くだけで、汗みずくになってしまった。眼鏡に汗がついてしまった。午前中に行ったのだが、かなりの人であった。このごろ、どの展覧会に行っても、人が多い。これはこれで、美術館の運営上しかたないことなのかもしれない。が、横山大観は、ゆっくりと見たい気がする。
横山大観は日本画家である。そのなかで、新しい技法、テーマを追求していった様子が、年代順に展示されていた。見ていって感じたことは、確かに、大観は、新たな画題を追求していったと思うのだが、それを見て、我々のものを見る感覚が影響されて変わってくる、という気はあまりしなかった。むしろ、伝統的な、画題、見方、描き方を尊重していたように感じたのであった。(そのなかにあっても、斬新な工夫を見ることはできるのだが。)
まったく個人的な思いを記せば、ある絵画が、ものを見る感覚、風景の見方を変える……このことについて、私が、一番つよく感じているのは、岸田劉生の作品においてである。その代表作の一つ、「道路と土手と塀(切通之写生)」である。これは、WEBで見ることができるようになっている。
東京国立近代美術館
岸田劉生 道路と土手と塀(切通之写生)
http://kanshokyoiku.jp/keymap/momat03.html
そうはいいながら、やはり横山大観の畢生の作である「生々流転」には、感動を覚える。長大な巻物のなかに、風景が流れていく。それを見ていくと、自分が、その流れる風景の中に溶け込んでいくような感じなる。
「生々流転」は、たしか東京国立近代美術館に展示されていたのを、若いとき……東京に住んでいたとき……何度か、眼にしたかと覚えている。この作品をみて、横に長い、巻子本という形式を採用することによって、季節と自然の流れを表現することができていると感じる。ここには、独自の自然観とでもいうべきものがある。このような自然の見方があったのか、表現の方法があったのかと、気づかせてくれる。
美術、芸術とは、それまで目にしてきたこと、体験してきたことを、新たな視点、感覚で、再発見をうながすものであると思う。無論、その作品によってはじめて体験する感動というものもある。その一方で、これまで目にしてきた風景や自然について、新たな面目を提示してくれる、新たな目で「風景」を見る自分を再発見させてくれるものでもあろう。芸術による風景の発見といってもよいだろうか。この意味で、特に「生々流転」は、近代日本において、一つの「風景」を示してくれている作品であると思う。
総合して考えることは、やはり横山大観という画家は、日本の近代を生きたということが実感できる展覧会であった。
梅雨というのに暑い日だった。地下鉄の東山から美術館まで歩くだけで、汗みずくになってしまった。眼鏡に汗がついてしまった。午前中に行ったのだが、かなりの人であった。このごろ、どの展覧会に行っても、人が多い。これはこれで、美術館の運営上しかたないことなのかもしれない。が、横山大観は、ゆっくりと見たい気がする。
横山大観は日本画家である。そのなかで、新しい技法、テーマを追求していった様子が、年代順に展示されていた。見ていって感じたことは、確かに、大観は、新たな画題を追求していったと思うのだが、それを見て、我々のものを見る感覚が影響されて変わってくる、という気はあまりしなかった。むしろ、伝統的な、画題、見方、描き方を尊重していたように感じたのであった。(そのなかにあっても、斬新な工夫を見ることはできるのだが。)
まったく個人的な思いを記せば、ある絵画が、ものを見る感覚、風景の見方を変える……このことについて、私が、一番つよく感じているのは、岸田劉生の作品においてである。その代表作の一つ、「道路と土手と塀(切通之写生)」である。これは、WEBで見ることができるようになっている。
東京国立近代美術館
岸田劉生 道路と土手と塀(切通之写生)
http://kanshokyoiku.jp/keymap/momat03.html
そうはいいながら、やはり横山大観の畢生の作である「生々流転」には、感動を覚える。長大な巻物のなかに、風景が流れていく。それを見ていくと、自分が、その流れる風景の中に溶け込んでいくような感じなる。
「生々流転」は、たしか東京国立近代美術館に展示されていたのを、若いとき……東京に住んでいたとき……何度か、眼にしたかと覚えている。この作品をみて、横に長い、巻子本という形式を採用することによって、季節と自然の流れを表現することができていると感じる。ここには、独自の自然観とでもいうべきものがある。このような自然の見方があったのか、表現の方法があったのかと、気づかせてくれる。
美術、芸術とは、それまで目にしてきたこと、体験してきたことを、新たな視点、感覚で、再発見をうながすものであると思う。無論、その作品によってはじめて体験する感動というものもある。その一方で、これまで目にしてきた風景や自然について、新たな面目を提示してくれる、新たな目で「風景」を見る自分を再発見させてくれるものでもあろう。芸術による風景の発見といってもよいだろうか。この意味で、特に「生々流転」は、近代日本において、一つの「風景」を示してくれている作品であると思う。
総合して考えることは、やはり横山大観という画家は、日本の近代を生きたということが実感できる展覧会であった。
『老いの荷風』川本三郎 ― 2018-06-30
2018-06-30 當山日出夫(とうやまひでお)

川本三郎.『老いの荷風』.白水社.2017
https://www.hakusuisha.co.jp/book/b285611.html
去年、出た時に買っておいた本である。その後、なんとなく読まずに本の中に埋もれてしまっていた。部屋の本を少し整理して出てきたので、改めて読んでみた。これも、読んで、しばらくおいてあった。
特に、読後感などを書くのに難しいという本ではないと感じるのだが、しかし、なかなかこの本のことについて書こうという気にならなかったのは、荷風という存在による。私は、荷風は好きである。このごろでは、荷風それ自体を読むよりも、荷風について書かれた書物などを読むのが多くなってきた。この本もその中の一つ。
荷風について書かれた本について書こうと思うと、どうしても荷風に触れることになる。それが、このごろ、なんとなく気が重く感じるようになってきた。
荷風は、「老い」を描き得た作家であると思っている。若くより、自分自身を、〈亡命者〉〈隠遁者〉とでも思い定めた、いわば、この世から一歩さがったところから世間を見る、いわば老境のまなざしで、その作品を残したと言っていいだろうか。この意味において、自分自身が年をとって、さて、自分の老境とでもいうべきものを、どう考えるか、荷風を読むと、自分のことに思いがいってしまうのである。これが、荷風について書くのをためらわせている遠因だろうかと、自らをかえりみて思う次第である。
ところで、この本を読んで、付箋をつけた箇所をすこし引用しておきたい。
「自分一人の感慨に浸り切る。散歩は荷風にとっては、きわめて孤独な文学的行為だったといえるし、また、徹底した、個の意識に支えられていたという点で、町の隠居の散歩とは明らかに違った近代人の知的行為でもあった。」(p.126)
「『日和下駄』が単なる散歩随筆、東京案内に終わっていないのは、その根底には、自分はついに見る人でしかないという荷風の断念があるからである。」(p.129)
このような意味において、荷風の生き方は、単なる「老い」ではない。そこには、世間からあえて身をしりぞけた覚悟とでもいうべきものがあることになる。荷風が東京の「江戸」「下町」に心ひかれたことは、言うまでもないことである。が、それも、近代の西欧を体験を経た後のことであることを忘れてはならないだろう。
たまに東京に行って街をあるいても、あるいは、近辺の都市として京都の街をあるいても、私の場合、もはや荷風がかつて東京をあるいたような感覚で、街の風景を見ることはできない。時代の違いか、立場の違いか、考え方の違いか。ともあれ、荷風のように生きることは出来ないだろうと感じながらも、その一方で、近代という時代に生きた荷風という一人の人物の生き方に、ひかれるところがあるのも、確かなことである。
荷風のような、知的営為……その中には、反近代の感覚をふくむ……としての散歩は、私のよくなしうるところではないと、感じている。
https://www.hakusuisha.co.jp/book/b285611.html
去年、出た時に買っておいた本である。その後、なんとなく読まずに本の中に埋もれてしまっていた。部屋の本を少し整理して出てきたので、改めて読んでみた。これも、読んで、しばらくおいてあった。
特に、読後感などを書くのに難しいという本ではないと感じるのだが、しかし、なかなかこの本のことについて書こうという気にならなかったのは、荷風という存在による。私は、荷風は好きである。このごろでは、荷風それ自体を読むよりも、荷風について書かれた書物などを読むのが多くなってきた。この本もその中の一つ。
荷風について書かれた本について書こうと思うと、どうしても荷風に触れることになる。それが、このごろ、なんとなく気が重く感じるようになってきた。
荷風は、「老い」を描き得た作家であると思っている。若くより、自分自身を、〈亡命者〉〈隠遁者〉とでも思い定めた、いわば、この世から一歩さがったところから世間を見る、いわば老境のまなざしで、その作品を残したと言っていいだろうか。この意味において、自分自身が年をとって、さて、自分の老境とでもいうべきものを、どう考えるか、荷風を読むと、自分のことに思いがいってしまうのである。これが、荷風について書くのをためらわせている遠因だろうかと、自らをかえりみて思う次第である。
ところで、この本を読んで、付箋をつけた箇所をすこし引用しておきたい。
「自分一人の感慨に浸り切る。散歩は荷風にとっては、きわめて孤独な文学的行為だったといえるし、また、徹底した、個の意識に支えられていたという点で、町の隠居の散歩とは明らかに違った近代人の知的行為でもあった。」(p.126)
「『日和下駄』が単なる散歩随筆、東京案内に終わっていないのは、その根底には、自分はついに見る人でしかないという荷風の断念があるからである。」(p.129)
このような意味において、荷風の生き方は、単なる「老い」ではない。そこには、世間からあえて身をしりぞけた覚悟とでもいうべきものがあることになる。荷風が東京の「江戸」「下町」に心ひかれたことは、言うまでもないことである。が、それも、近代の西欧を体験を経た後のことであることを忘れてはならないだろう。
たまに東京に行って街をあるいても、あるいは、近辺の都市として京都の街をあるいても、私の場合、もはや荷風がかつて東京をあるいたような感覚で、街の風景を見ることはできない。時代の違いか、立場の違いか、考え方の違いか。ともあれ、荷風のように生きることは出来ないだろうと感じながらも、その一方で、近代という時代に生きた荷風という一人の人物の生き方に、ひかれるところがあるのも、確かなことである。
荷風のような、知的営為……その中には、反近代の感覚をふくむ……としての散歩は、私のよくなしうるところではないと、感じている。
追記 2018-07-02
この続きは、
やまもも書斎記 2018年7月2日
『老いの荷風』川本三郎(その二)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/07/02/8907507
この続きは、
やまもも書斎記 2018年7月2日
『老いの荷風』川本三郎(その二)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/07/02/8907507





最近のコメント