キンシバイ ― 2018-07-11
2018-07-11 當山日出夫(とうやまひでお)
水曜日なので花の写真。今日はキンシバイ「金糸梅」である。
前回は、
やまもも書斎記 2018年7月4日
セイヨウイボタノキ
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/07/04/8908790
キンシバイの花の時期は長い。漢字では、「金糸梅」と書く。かれこれ一月ぐらい咲いているだろうか。我が家には幾株かのキンシバイの木がある。花が散って地面に黄色い花びらが見えるころになっても、まだ、つぼみの状態のものがあったりする。
日本国語大辞典(ジャパンナレッジ)をひいてみる。「きんしばい」の項目では、
オトギリソウ科の半落葉小低木。中国原産で、観賞用に庭園で栽植される。
とあり、説明が書いてある。ことばの用例としては、
物類品隲(1763)
から見える。近世になってから、ひろまったものらしい。季語としては、夏になる。
この花の名前は、残念ながら『言海』にはない。
ここに掲載の写真は、先月のうちに撮影しておいたものである。RAWデータから、JPEGにしてある。
水曜日なので花の写真。今日はキンシバイ「金糸梅」である。
前回は、
やまもも書斎記 2018年7月4日
セイヨウイボタノキ
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/07/04/8908790
キンシバイの花の時期は長い。漢字では、「金糸梅」と書く。かれこれ一月ぐらい咲いているだろうか。我が家には幾株かのキンシバイの木がある。花が散って地面に黄色い花びらが見えるころになっても、まだ、つぼみの状態のものがあったりする。
日本国語大辞典(ジャパンナレッジ)をひいてみる。「きんしばい」の項目では、
オトギリソウ科の半落葉小低木。中国原産で、観賞用に庭園で栽植される。
とあり、説明が書いてある。ことばの用例としては、
物類品隲(1763)
から見える。近世になってから、ひろまったものらしい。季語としては、夏になる。
この花の名前は、残念ながら『言海』にはない。
ここに掲載の写真は、先月のうちに撮影しておいたものである。RAWデータから、JPEGにしてある。
Nikon D7500
AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR
追記 2018-07-19
この続きは、
やまもも書斎記 2018年7月19日
この続きは、
やまもも書斎記 2018年7月19日
栗
『城』カフカ ― 2018-07-12
2018-07-12 當山日出夫(とうやまひでお)
カフカ.前田敬作(訳).『城』(新潮文庫).新潮社.1971(2005.改版)
http://www.shinchosha.co.jp/book/207102/
カフカ.前田敬作(訳).『城』(新潮文庫).新潮社.1971(2005.改版)
http://www.shinchosha.co.jp/book/207102/
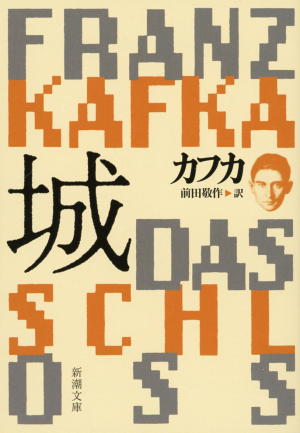
カフカの作品、先日、『変身』を読んだ。
やまもも書斎記 2018年8月5日
『変身』カフカ
世界文学の名作の読み直し、『城』(カフカ)である。この作品、読んだかどうかも覚えていないのだが、たしか読まなかったような……ともあれ、新潮文庫の改版してきれいになっている本で読んでみた。
ちょっと違和感を感じたのは、この作品の紹介として、
「職業が人間の唯一の存在形式となった現代人の疎外された姿を抉り出す。」
の文言。文庫本の裏の紹介文に書いてあるし、それから、新潮社のHPのこの作品のところにも、同じことが書いてある。
出てくる職業は「測量士」……いったい何の仕事だろうと思って読んでみたのだが、ただ、主人公「K」の仕事が「測量士」として出てはくる、しかし、その仕事の具体的なことは一切出てこない。だからこそ、この作品の意図における、ある職業の名称としての「測量士」ということなのかとも思うが、よくわからなかったところである。
ともあれ、この作品、ある組織、あるいは、社会、さらには、世界、から疎外された状態にある人間の有様を、描いている。このようにしかいいようがない。私の読んだ印象では、別に、主人公「K」の仕事が「測量士」でなくても、この作品はなりたつものであると感じる。
読みながら付箋をつけた箇所。
「あなたは、お城の人でもなければ、村の人間でもない。あなたは、何者でもいらっしゃらない。でも、お気の毒なことに、あなたは、やはり何者かでいらっしゃる。あなたは、つまり他国者なのです。不必要な、どこへ行っても邪魔になる人、たえず迷惑の種になる人(中略)あなたは、そういう他国者でいらっしゃる。」(p.104)
このような疎外感、いわば実存的な不安とでもいうべきものがこの作品をつらぬいている。何といって大事件がおこるようなストーリーではない。〈城〉に呼ばれ、しかし、疎外され続ける主人公「K」について子細に描写される。そこにあるのは、いいようのない不安感とでもいえばいいだろうか。
だが、その一方で、逆に、この作品から感じるものとしては、このような疎外感、実存的な不安を語ることによって逆説的に感じるのが、無償の愛、とでもいうべきもの。または、完全なる自由、とでも言っていいだろうか。または、確たるアイデンティティーと言ってもよいか。〈城〉から疎外され続ける主人公「K」に共感して読むというよりも、「K」が得られないでいるものが何であるかを、感じ取ってしまうのである。
カフカがこの作品を書いた背景には、その当時のユダヤ人というものがあったにちがいない。そして、文学史的な理解としては、それをどのように文学的に表現しているか、ということで読むことになるのだろう。それは、読んだ文庫本の解説に書いてあるような、(私なりに理解したところでいえば)世界と自己との亀裂とでも表現できるような意識のあり方であろう。
そして、世紀末、ヨーロッパにおけるユダヤ人の疎外感……このことで思い浮かぶのは、マーラーでもある。カフカとマーラーを並べて論じたものがあるのかどうか、私は知らないが、ヨーロッパ世界にあって、多層的に疎外された意識ということでは、共通するものがあるのかもしれない。
カフカという作家、現代ではあまり読まれない作家になってしまっているともいえそうである。文庫本の解説には、
「今日、世界がふたつの陣営に分裂し、そのいずれにも属さない生きかたはありえないといわれるとき、このようなカフカの存在把握は、おそろしいまでに予言的な真実性をもっている。」(p.623)
この解説も、時代を感じさせる。1971年である。そして、ベルリンの壁の崩壊後、グローバルという名のもとに世界はある。その世界のなかで、疎外される自己というものがあるとするならば、それを、まさに、カフカの作品は預言的に描いたと言えるだろう。
ちょっと違和感を感じたのは、この作品の紹介として、
「職業が人間の唯一の存在形式となった現代人の疎外された姿を抉り出す。」
の文言。文庫本の裏の紹介文に書いてあるし、それから、新潮社のHPのこの作品のところにも、同じことが書いてある。
出てくる職業は「測量士」……いったい何の仕事だろうと思って読んでみたのだが、ただ、主人公「K」の仕事が「測量士」として出てはくる、しかし、その仕事の具体的なことは一切出てこない。だからこそ、この作品の意図における、ある職業の名称としての「測量士」ということなのかとも思うが、よくわからなかったところである。
ともあれ、この作品、ある組織、あるいは、社会、さらには、世界、から疎外された状態にある人間の有様を、描いている。このようにしかいいようがない。私の読んだ印象では、別に、主人公「K」の仕事が「測量士」でなくても、この作品はなりたつものであると感じる。
読みながら付箋をつけた箇所。
「あなたは、お城の人でもなければ、村の人間でもない。あなたは、何者でもいらっしゃらない。でも、お気の毒なことに、あなたは、やはり何者かでいらっしゃる。あなたは、つまり他国者なのです。不必要な、どこへ行っても邪魔になる人、たえず迷惑の種になる人(中略)あなたは、そういう他国者でいらっしゃる。」(p.104)
このような疎外感、いわば実存的な不安とでもいうべきものがこの作品をつらぬいている。何といって大事件がおこるようなストーリーではない。〈城〉に呼ばれ、しかし、疎外され続ける主人公「K」について子細に描写される。そこにあるのは、いいようのない不安感とでもいえばいいだろうか。
だが、その一方で、逆に、この作品から感じるものとしては、このような疎外感、実存的な不安を語ることによって逆説的に感じるのが、無償の愛、とでもいうべきもの。または、完全なる自由、とでも言っていいだろうか。または、確たるアイデンティティーと言ってもよいか。〈城〉から疎外され続ける主人公「K」に共感して読むというよりも、「K」が得られないでいるものが何であるかを、感じ取ってしまうのである。
カフカがこの作品を書いた背景には、その当時のユダヤ人というものがあったにちがいない。そして、文学史的な理解としては、それをどのように文学的に表現しているか、ということで読むことになるのだろう。それは、読んだ文庫本の解説に書いてあるような、(私なりに理解したところでいえば)世界と自己との亀裂とでも表現できるような意識のあり方であろう。
そして、世紀末、ヨーロッパにおけるユダヤ人の疎外感……このことで思い浮かぶのは、マーラーでもある。カフカとマーラーを並べて論じたものがあるのかどうか、私は知らないが、ヨーロッパ世界にあって、多層的に疎外された意識ということでは、共通するものがあるのかもしれない。
カフカという作家、現代ではあまり読まれない作家になってしまっているともいえそうである。文庫本の解説には、
「今日、世界がふたつの陣営に分裂し、そのいずれにも属さない生きかたはありえないといわれるとき、このようなカフカの存在把握は、おそろしいまでに予言的な真実性をもっている。」(p.623)
この解説も、時代を感じさせる。1971年である。そして、ベルリンの壁の崩壊後、グローバルという名のもとに世界はある。その世界のなかで、疎外される自己というものがあるとするならば、それを、まさに、カフカの作品は預言的に描いたと言えるだろう。
『城』カフカ(その二) ― 2018-07-13
2018-07-13 當山日出夫(とうやまひでお)
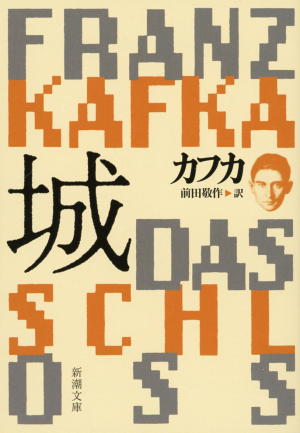
続きである。
やまもも書斎記 2018年7月12日
『城』カフカ
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/07/12/8914217
カフカという作家、私の学生の頃には、もっと読まれていたように思う。この頃では、そんなに人気のある作家ということではないように思える。
ところで、『城』を読みながら付箋をつけた箇所を引用しておきたい。
「Kは、これで他人とのあらゆるつながりが断ち切られ、もちろん、自分はこれまでより自由な身になり、ふつうなら入れてもらえないこの場所で好きなだけ待っていることができる、そして、この自由は、自分が戦いとったもので、他人にはとてもできないことだろう、いまやだれも自分にふれたり、ここから追いだしたりすることはできない、それどころか、自分に話しかけることもできまいと、思った。しかし、それと同時に、この確信も同じくらいにつよかったのだが、この自由は、こうして待っていること、こうしてだれからも干渉されずにいられること以上に無意味で絶望的なことがあるだろうかという気もするのだった。」(pp.217-218)
ここに引用したような「自由」についての感覚は、ベルリンの壁の崩壊後の世界に蔓延しているといっていいのではないだろうか。絶望的な自由、無意味な自由、である。ベルリンの壁の崩壊後、社会主義陣営は崩れ去った。その後、多くの人びとは、自由を得たはずである。それが、はたして真の自由というべきものなのか、今の世界は問われているように思える。
また、今日の世界の「自由主義」……そこにあるのは、本当の自由なのだろうか。
カフカの文学は、今日の世界を預言している、このような感覚を読んでいていだくのである。他のカフカの作品を読んでおきたい。
やまもも書斎記 2018年7月12日
『城』カフカ
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/07/12/8914217
カフカという作家、私の学生の頃には、もっと読まれていたように思う。この頃では、そんなに人気のある作家ということではないように思える。
ところで、『城』を読みながら付箋をつけた箇所を引用しておきたい。
「Kは、これで他人とのあらゆるつながりが断ち切られ、もちろん、自分はこれまでより自由な身になり、ふつうなら入れてもらえないこの場所で好きなだけ待っていることができる、そして、この自由は、自分が戦いとったもので、他人にはとてもできないことだろう、いまやだれも自分にふれたり、ここから追いだしたりすることはできない、それどころか、自分に話しかけることもできまいと、思った。しかし、それと同時に、この確信も同じくらいにつよかったのだが、この自由は、こうして待っていること、こうしてだれからも干渉されずにいられること以上に無意味で絶望的なことがあるだろうかという気もするのだった。」(pp.217-218)
ここに引用したような「自由」についての感覚は、ベルリンの壁の崩壊後の世界に蔓延しているといっていいのではないだろうか。絶望的な自由、無意味な自由、である。ベルリンの壁の崩壊後、社会主義陣営は崩れ去った。その後、多くの人びとは、自由を得たはずである。それが、はたして真の自由というべきものなのか、今の世界は問われているように思える。
また、今日の世界の「自由主義」……そこにあるのは、本当の自由なのだろうか。
カフカの文学は、今日の世界を預言している、このような感覚を読んでいていだくのである。他のカフカの作品を読んでおきたい。
『城』カフカ(その三) ― 2018-07-14
2018-07-14 當山日出夫(とうやまひでお)
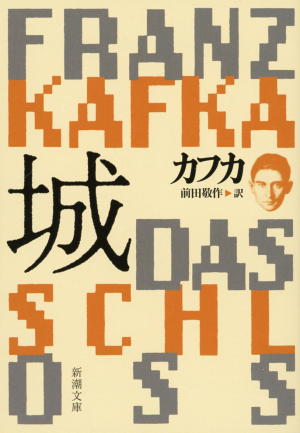
続きである。
やまもも書斎記 2018年7月13日
『城』カフカ(その二)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/07/13/8914796
カフカ.前田敬作(訳).『城』(新潮文庫).新潮社.1971(2005.改版)
http://www.shinchosha.co.jp/book/207102/
さらに、読みながら付箋をつけた箇所を引用しておきたい。
「彼女の視線は、いつものように冷たく、澄んでいて、すこしも動かなかった。それは、自分が観察する対象にまともに向けられず、わずかばかり、ほとんど気づかないほどだが、それでもまぎれもなく対象のそばを素通りしているのだった。見られているほうでは、そにひどくこころを乱された。こういう視線になる原因は、元気がないからでも、当惑や無礼のせいでもなく、たえず他のどんな感情にもまして孤独をつよく望んでいるためであるようにおもえた。」(p.337)
しかし、これにつづけて次のようにもある。
「といって、この視線そのものは、けっしていやらしいものではなく、うちとけはしないものの、率直さにみちていた。」(p.338)
寓意に満ちたこの作品に下手に解釈を加えるものではないと思う。だが、上記のような箇所を読むと、現代における「孤独」というものの本質をついているように感じる。絶望的に孤独でしかありえないような、人間存在の深い淵をのぞきこんでいるような描写である。ここには、「孤独」を楽しむというような、いわゆる近代の憂愁とでもいうべきものは、もはやまったくない。そこには、不気味な絶望感を感じる。しかし、だからといって、そこに悪意を感じることはない。嫌悪してはいない。ただ、孤独な人間のあり方を語っているだけである。その語り口は、むしろ素直ですらある。淡々と絶望的な孤独を語っている。
交わることのない視線。しかし、それは率直なものでもある。このような孤独な視線を一世紀以上も前に描きえた、カフカという作家の文学的想像力に敬服するばかりである。
おそらく、文学史的には、その当時のチェコスロバキアにおけるドイツ系ユダヤ人としての、アイデンティティーの喪失、社会からの疎外感、とでもいうようなことばで説明することになるのかもしれない。もし、このように文学史的には説明されるとしても、今日、この作品を読んで感じる、いいようのない文学的感銘……絶望的な孤独感……の表現は、カフカの天稟であったと感じる。
いや逆なのであろう。今日、カフカを読むことによって、現代における孤独というものに気づく、これが文学というものなのである。
やまもも書斎記 2018年7月13日
『城』カフカ(その二)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/07/13/8914796
カフカ.前田敬作(訳).『城』(新潮文庫).新潮社.1971(2005.改版)
http://www.shinchosha.co.jp/book/207102/
さらに、読みながら付箋をつけた箇所を引用しておきたい。
「彼女の視線は、いつものように冷たく、澄んでいて、すこしも動かなかった。それは、自分が観察する対象にまともに向けられず、わずかばかり、ほとんど気づかないほどだが、それでもまぎれもなく対象のそばを素通りしているのだった。見られているほうでは、そにひどくこころを乱された。こういう視線になる原因は、元気がないからでも、当惑や無礼のせいでもなく、たえず他のどんな感情にもまして孤独をつよく望んでいるためであるようにおもえた。」(p.337)
しかし、これにつづけて次のようにもある。
「といって、この視線そのものは、けっしていやらしいものではなく、うちとけはしないものの、率直さにみちていた。」(p.338)
寓意に満ちたこの作品に下手に解釈を加えるものではないと思う。だが、上記のような箇所を読むと、現代における「孤独」というものの本質をついているように感じる。絶望的に孤独でしかありえないような、人間存在の深い淵をのぞきこんでいるような描写である。ここには、「孤独」を楽しむというような、いわゆる近代の憂愁とでもいうべきものは、もはやまったくない。そこには、不気味な絶望感を感じる。しかし、だからといって、そこに悪意を感じることはない。嫌悪してはいない。ただ、孤独な人間のあり方を語っているだけである。その語り口は、むしろ素直ですらある。淡々と絶望的な孤独を語っている。
交わることのない視線。しかし、それは率直なものでもある。このような孤独な視線を一世紀以上も前に描きえた、カフカという作家の文学的想像力に敬服するばかりである。
おそらく、文学史的には、その当時のチェコスロバキアにおけるドイツ系ユダヤ人としての、アイデンティティーの喪失、社会からの疎外感、とでもいうようなことばで説明することになるのかもしれない。もし、このように文学史的には説明されるとしても、今日、この作品を読んで感じる、いいようのない文学的感銘……絶望的な孤独感……の表現は、カフカの天稟であったと感じる。
いや逆なのであろう。今日、カフカを読むことによって、現代における孤独というものに気づく、これが文学というものなのである。
『半分、青い。』あれこれ「すがりたい!」 ― 2018-07-15
2018-07-15 當山日出夫(とうやまひでお)
『半分、青い。』第15週「すがりたい!」
https://www.nhk.or.jp/hanbunaoi/story/week_15.html
前回は、
やまもも書斎記 2018年7月8日
『半分、青い。』あれこれ「羽ばたきたい!」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/07/08/8911562
この週も急展開の週であった。鈴愛は、結婚することになる。
結婚するのはいいとしても、よくわからないのが、その動機、というか、気持ち。まあ、好きになってしまったといえば、それまでなのであるけれど。だが、それにしても急展開である。
ドラマとしては、この急な二人……鈴愛と涼次……の気持ちを、どのように説得力を持って描けているか、このところが見どころだったと思う。確かに急な展開ではあるが、さして不自然な感じはしなかった。
百円ショップで、繁忙期にアルバイトでやってきた若い男性と、恋におちる。それをもっとも印象的に表現していたのが、雨の中のダンスシーンである。雨が降る中で抱擁して、二人は、気持ちをたしかめあうことになる。この雨のシーンが、この週の一番の見どころ、中心となるとこであったと思う。雨のシーンによって、あまりにも急な展開の二人の接近が、自然なものに感じられる。このあたりは、このドラマの脚本の巧さなのであると感じる。
それにしても、岐阜の鈴愛の家のあわてぶりが、定番とでもいうべきもので、これはこれで巧く作ってあると感じさせる。弟の草太の結婚話もからんできているようだが、これが、この先、どう影響してくるのか、気になるところでもある。
ところで、亡くなった涼次の母親……三姉妹の長女……の名前が、繭子であった。「ま」ではじまる。つまり、この四姉妹は、「まみむめ」の順で名前がついていることになる。となると、鈴愛と涼次に子ども(女の子)ができると「も」ではじまるのか。いや、これは余計な心配か。
次週は、秋風羽織も登場するようである。たのしみに見ることにしよう。それから、監督の次回作『追憶のかたつむり2』は、無事にできるのだろうか。これも気になるところである。
『半分、青い。』第15週「すがりたい!」
https://www.nhk.or.jp/hanbunaoi/story/week_15.html
前回は、
やまもも書斎記 2018年7月8日
『半分、青い。』あれこれ「羽ばたきたい!」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/07/08/8911562
この週も急展開の週であった。鈴愛は、結婚することになる。
結婚するのはいいとしても、よくわからないのが、その動機、というか、気持ち。まあ、好きになってしまったといえば、それまでなのであるけれど。だが、それにしても急展開である。
ドラマとしては、この急な二人……鈴愛と涼次……の気持ちを、どのように説得力を持って描けているか、このところが見どころだったと思う。確かに急な展開ではあるが、さして不自然な感じはしなかった。
百円ショップで、繁忙期にアルバイトでやってきた若い男性と、恋におちる。それをもっとも印象的に表現していたのが、雨の中のダンスシーンである。雨が降る中で抱擁して、二人は、気持ちをたしかめあうことになる。この雨のシーンが、この週の一番の見どころ、中心となるとこであったと思う。雨のシーンによって、あまりにも急な展開の二人の接近が、自然なものに感じられる。このあたりは、このドラマの脚本の巧さなのであると感じる。
それにしても、岐阜の鈴愛の家のあわてぶりが、定番とでもいうべきもので、これはこれで巧く作ってあると感じさせる。弟の草太の結婚話もからんできているようだが、これが、この先、どう影響してくるのか、気になるところでもある。
ところで、亡くなった涼次の母親……三姉妹の長女……の名前が、繭子であった。「ま」ではじまる。つまり、この四姉妹は、「まみむめ」の順で名前がついていることになる。となると、鈴愛と涼次に子ども(女の子)ができると「も」ではじまるのか。いや、これは余計な心配か。
次週は、秋風羽織も登場するようである。たのしみに見ることにしよう。それから、監督の次回作『追憶のかたつむり2』は、無事にできるのだろうか。これも気になるところである。
追記 2018-07-22
この続きは、
やまもも書斎記 2018年7月22日
『半分、青い。』あれこれ「抱きしめたい!」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/07/22/8923031
この続きは、
やまもも書斎記 2018年7月22日
『半分、青い。』あれこれ「抱きしめたい!」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/07/22/8923031
『ワーニャ伯父さん』チェーホフ ― 2018-07-16
2018-07-16 當山日出夫(とうやまひでお)

チェーホフ.神西清(訳).『かもめ・ワーニャ伯父さん』(新潮文庫).新潮社.1967(2004.改版)
http://www.shinchosha.co.jp/book/206502/
今日は、『ワーニャ伯父さん』である。チェーホフの著名な四戯曲では、二番目になる。新潮文庫版では、『かもめ』と同じ巻にいれてある。『かもめ』については、すでに書いた。
やまもも書斎記 2018年7月9日
『かもめ』チェーホフ
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/07/09/8912315
この作品については、ラストの次の台詞を引用しておきたい。
「ソーニャ でも、仕方がないわ、生きていかなければ! (間)ね、ワーニャ伯父さん、生きていきましょうよ。長い、はてしないその日その日を、いつ明けるとも知れない夜また夜を、じっと生き通していきましょうね。運命がわたしたちにくだす試みを、辛抱づよく、じっとこらえて行きましょうね。今のうちも、やがて年をとってからも、片時も休まずに、人のために働きましょうね。(以下、略)」(p.238)
ちょっと長めの台詞であるが、この台詞の中に、この作品の語らんとしていることが、凝縮されてある。最後のこの台詞になって、ようやく、このドラマが終わるという感慨をもって読み終えることができる。
このようなチェーホフの作品、特に戯曲で端的に表されている、人生に対する賛美の念……これが、若いときにはわからなかったといってよい。『ワーニャ伯父さん』も、若い時に、古い新潮文庫版で読んだかと覚えているのだが、特に、ここの台詞が記憶に残っているということはない。強いていえば、それがまさに若い時の読書というものであったのかもしれない、と今になって感じる。(若いころは、ロシア文学といえば、ドストエフスキーというような感じで本を読んでいた。)
私も、この年になって、チェーホフの作品を再読してみて、『かもめ』の「忍耐」、そして、『ワーニャ伯父さん』の、この生きることへの意思、これにつよく感銘をうける。そろそろ夏休みになる。残りの戯曲『桜の園』『三人姉妹』も、順番に読んでおきたいと思う。どれも四幕の、比較的短い作品である。ちょっと時間のとれるときに、じっくりと味わって読んでおきたいと思っている。
http://www.shinchosha.co.jp/book/206502/
今日は、『ワーニャ伯父さん』である。チェーホフの著名な四戯曲では、二番目になる。新潮文庫版では、『かもめ』と同じ巻にいれてある。『かもめ』については、すでに書いた。
やまもも書斎記 2018年7月9日
『かもめ』チェーホフ
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/07/09/8912315
この作品については、ラストの次の台詞を引用しておきたい。
「ソーニャ でも、仕方がないわ、生きていかなければ! (間)ね、ワーニャ伯父さん、生きていきましょうよ。長い、はてしないその日その日を、いつ明けるとも知れない夜また夜を、じっと生き通していきましょうね。運命がわたしたちにくだす試みを、辛抱づよく、じっとこらえて行きましょうね。今のうちも、やがて年をとってからも、片時も休まずに、人のために働きましょうね。(以下、略)」(p.238)
ちょっと長めの台詞であるが、この台詞の中に、この作品の語らんとしていることが、凝縮されてある。最後のこの台詞になって、ようやく、このドラマが終わるという感慨をもって読み終えることができる。
このようなチェーホフの作品、特に戯曲で端的に表されている、人生に対する賛美の念……これが、若いときにはわからなかったといってよい。『ワーニャ伯父さん』も、若い時に、古い新潮文庫版で読んだかと覚えているのだが、特に、ここの台詞が記憶に残っているということはない。強いていえば、それがまさに若い時の読書というものであったのかもしれない、と今になって感じる。(若いころは、ロシア文学といえば、ドストエフスキーというような感じで本を読んでいた。)
私も、この年になって、チェーホフの作品を再読してみて、『かもめ』の「忍耐」、そして、『ワーニャ伯父さん』の、この生きることへの意思、これにつよく感銘をうける。そろそろ夏休みになる。残りの戯曲『桜の園』『三人姉妹』も、順番に読んでおきたいと思う。どれも四幕の、比較的短い作品である。ちょっと時間のとれるときに、じっくりと味わって読んでおきたいと思っている。
『西郷どん』あれこれ「西郷、京へ」 ― 2018-07-17
2018-07-17 當山日出夫(とうやまひでお)
『西郷どん』2018年7月15日、第26回「西郷、京へ」
https://www.nhk.or.jp/segodon/story/26/
前回は、
やまもも書斎記 2018年7月1日
『西郷どん』あれこれ「生かされた命」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/07/03/8908156
前回の放送がスペシャルだったが、今回からもとにもどってドラマの続き。いよいよ「革命編」とでもいうべき段階である。
しかし、明治維新が「革命」であるかどうか、というのは、歴史学においても、かなり問題のあるところだと思うのだが……このドラマは、明治維新=革命、という路線で作るようだ。
その革命の時期にあっては、誰が敵で誰が味方なのかわからない……今回では、幕府(一橋慶喜)と薩摩(西郷)は、堅い絆で結ばれているかのごとくである。しかし、現代の我々は歴史の行方を知っている。薩摩は、この後、長州と組んで、倒幕の側に立つことになる。その指揮をするのが、西郷となるはずである。
これから、毎回、虚々実々の駆け引きがつづくのだろう。いった誰が味方なのか、敵なのか、何を考えているのか、信頼と裏切り、権謀術数の時代となる。
ところで、うまいと思ったのは、ふき……品川の妓楼にいた……という女性の使い方。慶喜に身請けされて側にいることになったようだ。ふきを介して、慶喜は西郷と連絡をとりあうことになる。
明治維新=革命、という歴史で描くとなる、その延長に、おそらく西南戦争のことが登場してくることになるのだろうと考える。明治維新=革命、それを成し遂げた後の、総決算として、西南戦争が起こる必然性を描くことになるのかと予測する。革命の理想を掲げることになるのが西郷、そして、その理想をかたくなに信じるが故に、明治新政府の現実と対立することになるという図式になるだろうか。
斉彬の遺志をついで革命をなしとげ、さらに、その遺志に殉ずることとしての西南戦争という展開を予想してみている。
『西郷どん』2018年7月15日、第26回「西郷、京へ」
https://www.nhk.or.jp/segodon/story/26/
前回は、
やまもも書斎記 2018年7月1日
『西郷どん』あれこれ「生かされた命」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/07/03/8908156
前回の放送がスペシャルだったが、今回からもとにもどってドラマの続き。いよいよ「革命編」とでもいうべき段階である。
しかし、明治維新が「革命」であるかどうか、というのは、歴史学においても、かなり問題のあるところだと思うのだが……このドラマは、明治維新=革命、という路線で作るようだ。
その革命の時期にあっては、誰が敵で誰が味方なのかわからない……今回では、幕府(一橋慶喜)と薩摩(西郷)は、堅い絆で結ばれているかのごとくである。しかし、現代の我々は歴史の行方を知っている。薩摩は、この後、長州と組んで、倒幕の側に立つことになる。その指揮をするのが、西郷となるはずである。
これから、毎回、虚々実々の駆け引きがつづくのだろう。いった誰が味方なのか、敵なのか、何を考えているのか、信頼と裏切り、権謀術数の時代となる。
ところで、うまいと思ったのは、ふき……品川の妓楼にいた……という女性の使い方。慶喜に身請けされて側にいることになったようだ。ふきを介して、慶喜は西郷と連絡をとりあうことになる。
明治維新=革命、という歴史で描くとなる、その延長に、おそらく西南戦争のことが登場してくることになるのだろうと考える。明治維新=革命、それを成し遂げた後の、総決算として、西南戦争が起こる必然性を描くことになるのかと予測する。革命の理想を掲げることになるのが西郷、そして、その理想をかたくなに信じるが故に、明治新政府の現実と対立することになるという図式になるだろうか。
斉彬の遺志をついで革命をなしとげ、さらに、その遺志に殉ずることとしての西南戦争という展開を予想してみている。
追記 2018-07-24
この続きは、
やまもも書斎記 2018年7月24日
『西郷どん』あれこれ「禁門の変」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/07/24/8924402
この続きは、
やまもも書斎記 2018年7月24日
『西郷どん』あれこれ「禁門の変」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/07/24/8924402
日曜劇場『この世界の片隅に』第一話 ― 2018-07-18
2018-07-18 當山日出夫(とうやまひでお)
TBS日曜劇場『この世界の片隅に』第一話
http://www.tbs.co.jp/konoseka_tbs/story/v1.html
このドラマの漫画(原作)を読んだのは、一昨年のことになる。
やまもも書斎記 2016年12月11日
こうの史代『この世界の片隅に』
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2016/12/11/8273353
日曜日の放送を録画しておいて、見て、文章を書いてとなると、水曜日のアップロードになる。(火曜日は、通例のこととして『西郷どん』について書いている。)
このドラマを見ておきたいという気になったのは、やはり脚本の岡田惠和によるところが大きい。岡田惠和は、これまでNHKの朝ドラの脚本をいくつか書いている。『ちゅらさん』(2001)、『おひさま』(2011)、『ひよっこ』(2017)である。これらはほとんど全部の回を見ている。『おひさま』は、再放送を含めれば、全部の回を見たと覚えている。太平洋戦争の時代に、「普通」に生きてきた一人の女性(陽子)の物語であった。特に何をなしとげたというわけではない、ごく「普通」に生活している人びとの生活の様子が、きめ細やかに描かれていた。
その岡田惠和が、『この世界の片隅に』をどのように描くか……これは見ておきたいと思った。
一回目を見た感想としては、かなり原作に忠実に雰囲気を出しているなということ。
ただ、大きく改作してあるのが、現代の視点を持ち込んでいることである。呉の街にいた北條すずという女性を探してやってくる、男女の二人。この二人が、どういう関係か(恋人どうしのようであるが)、また、なぜ北條すずのことを知っているのか、このあたりは、まだ説明されていない。(このあたり、『おひさま』でも、現代になってから、過去を回想するという枠組みを使ってドラマが作られていたのを思い出す。)
それから、実写ドラマとして作った場合、気になるのが、冒頭のいくつかのシーン。海苔を売りに行って、まだ小さい北條周作と出会う場面、人さらいに連れ去られそうになるところである。それから、座敷童の少女(リン)のこと。これらのシーンは、漫画というメディアで描くと、どことなく、ふんわりとした思い出、本当にあったことなのかどうか定かではない幻想的なシーンとして描ける。夢のような幻想的な場面として、漫画の冒頭に序章的に入れられていて、違和感がない。だが、実写ドラマではそうはいかない。リアルに感じてしまうことになる。
あえて省略してもよかったかもしれないとこかもしれない。ただ、その場合、なぜ周作がすずの名前を知っているのかが分からなくなってしまう。このあたり、脚本としては、難しいところだったろうと思う。
この作品(原作の漫画)の魅力は、太平洋戦争中の人びとの暮らしを、緻密な考証のもとに、リアルに、だが、その一方で、抒情的に、また、場合によっては、幻想的な雰囲気をもって描き出したところにあると思っている。
この原作の雰囲気を、ドラマではうまく表現していたように思う。主演の松本穂香(すず)の雰囲気が、非常にいい。原作(漫画)は原作として、また映画(アニメ)はそれとして、さらに、テレビドラマはそれとして、見ればいいと思っている。その中にあって、精細な時代考証の裏付けをもちながら、ある時代を「普通」に生きた人びとの物語を抒情的に描き出すことが出来ていればいいのだと思う。
そこに特に、思想性とでもいうべきものを持ち込むことはないだろう。この意味では、『ちゅらさん』で沖縄を描きながら、特に、日本と沖縄の歴史的意味などをドラマに持ち込むことをあえてしなかった岡田惠和の脚本を信頼しておきたいと思っている。
また、このドラマ、ある意味では、NHKの朝ドラにならって作っている印象がある。脚本しかり、キャストしかり、である。このあたりのことについては、報道でもとりあげられているようだ。
毎日新聞
http://mainichi.jp/articles/20180716/dyo/00m/200/021000c
ともあれ、原作の漫画を再読してみて、次週も楽しみに見ることにしよう。
TBS日曜劇場『この世界の片隅に』第一話
http://www.tbs.co.jp/konoseka_tbs/story/v1.html
このドラマの漫画(原作)を読んだのは、一昨年のことになる。
やまもも書斎記 2016年12月11日
こうの史代『この世界の片隅に』
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2016/12/11/8273353
日曜日の放送を録画しておいて、見て、文章を書いてとなると、水曜日のアップロードになる。(火曜日は、通例のこととして『西郷どん』について書いている。)
このドラマを見ておきたいという気になったのは、やはり脚本の岡田惠和によるところが大きい。岡田惠和は、これまでNHKの朝ドラの脚本をいくつか書いている。『ちゅらさん』(2001)、『おひさま』(2011)、『ひよっこ』(2017)である。これらはほとんど全部の回を見ている。『おひさま』は、再放送を含めれば、全部の回を見たと覚えている。太平洋戦争の時代に、「普通」に生きてきた一人の女性(陽子)の物語であった。特に何をなしとげたというわけではない、ごく「普通」に生活している人びとの生活の様子が、きめ細やかに描かれていた。
その岡田惠和が、『この世界の片隅に』をどのように描くか……これは見ておきたいと思った。
一回目を見た感想としては、かなり原作に忠実に雰囲気を出しているなということ。
ただ、大きく改作してあるのが、現代の視点を持ち込んでいることである。呉の街にいた北條すずという女性を探してやってくる、男女の二人。この二人が、どういう関係か(恋人どうしのようであるが)、また、なぜ北條すずのことを知っているのか、このあたりは、まだ説明されていない。(このあたり、『おひさま』でも、現代になってから、過去を回想するという枠組みを使ってドラマが作られていたのを思い出す。)
それから、実写ドラマとして作った場合、気になるのが、冒頭のいくつかのシーン。海苔を売りに行って、まだ小さい北條周作と出会う場面、人さらいに連れ去られそうになるところである。それから、座敷童の少女(リン)のこと。これらのシーンは、漫画というメディアで描くと、どことなく、ふんわりとした思い出、本当にあったことなのかどうか定かではない幻想的なシーンとして描ける。夢のような幻想的な場面として、漫画の冒頭に序章的に入れられていて、違和感がない。だが、実写ドラマではそうはいかない。リアルに感じてしまうことになる。
あえて省略してもよかったかもしれないとこかもしれない。ただ、その場合、なぜ周作がすずの名前を知っているのかが分からなくなってしまう。このあたり、脚本としては、難しいところだったろうと思う。
この作品(原作の漫画)の魅力は、太平洋戦争中の人びとの暮らしを、緻密な考証のもとに、リアルに、だが、その一方で、抒情的に、また、場合によっては、幻想的な雰囲気をもって描き出したところにあると思っている。
この原作の雰囲気を、ドラマではうまく表現していたように思う。主演の松本穂香(すず)の雰囲気が、非常にいい。原作(漫画)は原作として、また映画(アニメ)はそれとして、さらに、テレビドラマはそれとして、見ればいいと思っている。その中にあって、精細な時代考証の裏付けをもちながら、ある時代を「普通」に生きた人びとの物語を抒情的に描き出すことが出来ていればいいのだと思う。
そこに特に、思想性とでもいうべきものを持ち込むことはないだろう。この意味では、『ちゅらさん』で沖縄を描きながら、特に、日本と沖縄の歴史的意味などをドラマに持ち込むことをあえてしなかった岡田惠和の脚本を信頼しておきたいと思っている。
また、このドラマ、ある意味では、NHKの朝ドラにならって作っている印象がある。脚本しかり、キャストしかり、である。このあたりのことについては、報道でもとりあげられているようだ。
毎日新聞
http://mainichi.jp/articles/20180716/dyo/00m/200/021000c
ともあれ、原作の漫画を再読してみて、次週も楽しみに見ることにしよう。
追記 2018-07-25
この続きは、
やまもも書斎記 2018年7月25日
日曜劇場『この世界の片隅に』第二話
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/07/25/8924945
この続きは、
やまもも書斎記 2018年7月25日
日曜劇場『この世界の片隅に』第二話
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/07/25/8924945
栗 ― 2018-07-19
2018-07-19 當山日出夫(とうやまひでお)
花の写真は、いつもは水曜日に掲載するのだが、今週は、『この世界の片隅に』について書いているので、木曜日になった。
前回は、
やまもも書斎記 2018年7月11日
キンシバイ
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/07/11/8913633
栗の花については、去年にも書いている。
やまもも書斎記 2017年6月14日
栗の花
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2017/06/14/8595337
今年も例年どおりに栗の木が花をつけて、さらに実をつけている。
「くり」の用例を見てみると、日本国語大辞典(ジャパンナレッジ)では、
ブナ科の落葉高木。また、その実。北海道の南西部、本州、四国、九州の山地に生え、果樹として栽培もされる。
として説明がある。用例は古く、日本書紀、万葉集から見える。古来より、親しまれてきた樹木であることが確認できる。
『言海』にも載っている。引用しておくと、次のようにある。
くり 名 栗 [皮ノ色ノ涅(クリ)ナル意カ] 喬木、高サ二三丈、葉、甚ダ櫟(クヌギ)ニ類ス、梅雨ノ中ニ、葉ノ間ニ三四寸ノ穂ヲ垂レテ、黄白色ノ極メテ小キ花蔟リ開ク、後ニ、実ヲ結ブ、円ク扁クシテ、毛刺(イガ)密ニ生ジテ鋭シ、中ニ二三子アリ、秋ノ末ニ、自ラ裂ケテ落ツ、皮堅ク稜(カド)アリ、色赭黒ニシテ、肉甚ダ甘美ナリ、材堅クシテ用多シ。
写真は、先月のうちに写しておいたものである(花)。それから、ちょっと時間をおいて、実のなったところを撮っておいた。
花の写真は、いつもは水曜日に掲載するのだが、今週は、『この世界の片隅に』について書いているので、木曜日になった。
前回は、
やまもも書斎記 2018年7月11日
キンシバイ
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/07/11/8913633
栗の花については、去年にも書いている。
やまもも書斎記 2017年6月14日
栗の花
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2017/06/14/8595337
今年も例年どおりに栗の木が花をつけて、さらに実をつけている。
「くり」の用例を見てみると、日本国語大辞典(ジャパンナレッジ)では、
ブナ科の落葉高木。また、その実。北海道の南西部、本州、四国、九州の山地に生え、果樹として栽培もされる。
として説明がある。用例は古く、日本書紀、万葉集から見える。古来より、親しまれてきた樹木であることが確認できる。
『言海』にも載っている。引用しておくと、次のようにある。
くり 名 栗 [皮ノ色ノ涅(クリ)ナル意カ] 喬木、高サ二三丈、葉、甚ダ櫟(クヌギ)ニ類ス、梅雨ノ中ニ、葉ノ間ニ三四寸ノ穂ヲ垂レテ、黄白色ノ極メテ小キ花蔟リ開ク、後ニ、実ヲ結ブ、円ク扁クシテ、毛刺(イガ)密ニ生ジテ鋭シ、中ニ二三子アリ、秋ノ末ニ、自ラ裂ケテ落ツ、皮堅ク稜(カド)アリ、色赭黒ニシテ、肉甚ダ甘美ナリ、材堅クシテ用多シ。
写真は、先月のうちに写しておいたものである(花)。それから、ちょっと時間をおいて、実のなったところを撮っておいた。
Nikon D7500
AF-S DX Nicro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR
『日はまた昇る』ヘミングウェイ ― 2018-07-20
2018-07-20 當山日出夫(とうやまひでお)

ヘミングウェイ.高見浩(訳).『日はまた昇る』(新潮文庫).新潮社.2003
http://www.shinchosha.co.jp/book/210013/
世界文学の再読。『日はまた昇る』である。読んだのは、半年ほど前になる。それより前に、若い頃、読んでいたかどうかも、はっきり覚えていない。
この作品、傑作であることは分かるのだが、どこがどうとなるととたんにことばにつまる。どう言っていいか分からなくなる。ただ、小説を読んでいる時間の雰囲気、気分だけが残ると言っていいだろうか。
小説の主な舞台は、フランスのパリ、それから、スペイン。ただ、「今日」「今」だけに刹那的に生きる、幾人かの物語である。読み終わっても、そのストーリーに感銘をうけるという作品ではない。しかし、読んでいるときの、なんとなくけだるい感覚のようなものだけが残る。
おそらく、歴史的には、この小説に描かれているような世界に、非常に共感する時代があり、その世代の人びとがいたということは、確かなことであろう。確かに、この作品は、ある時代、世代の人びとの感覚を、ただその生活の感覚だけをたどって描いている。
読みながら付箋をつけておいた箇所を引用してみると、
「すると、もちろん、ぼくはまたみじめな気持ちに突き落とされた。昼間なら、何につけ無感動(ハード・ボイルド)をきめこむのは造作もないことだ。が、夜になると、そうはいかなかった。」(p.68)
「おまえさんは祖国放棄者だ、で、もう祖国の土の感触もわからない。なのに、えばりくさっている。まがいもののヨーロッパの価値観にすっかり毒されちまっている。」(p.213)
ヘミングウェイの作品は、他に読んだものとしては、長編では、
やまもも書斎記 2018年5月14日
『誰がために鐘は鳴る』ヘミングウェイ
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/05/14/8850880
やまもも書斎記 2018年6月4日
『武器よさらば』ヘミングウェイ
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/06/04/8868453
がある。読んでいって、まぎれもなく『日はまた昇る』は傑作であると感じる。この作品は、確かに、ある時代のある人びとの人生を描き出すことに成功している。他の、ヘミングウェイの作品、短篇など、読んだ上でこの作品は、さらに読みなおしておきたいと感じる。
http://www.shinchosha.co.jp/book/210013/
世界文学の再読。『日はまた昇る』である。読んだのは、半年ほど前になる。それより前に、若い頃、読んでいたかどうかも、はっきり覚えていない。
この作品、傑作であることは分かるのだが、どこがどうとなるととたんにことばにつまる。どう言っていいか分からなくなる。ただ、小説を読んでいる時間の雰囲気、気分だけが残ると言っていいだろうか。
小説の主な舞台は、フランスのパリ、それから、スペイン。ただ、「今日」「今」だけに刹那的に生きる、幾人かの物語である。読み終わっても、そのストーリーに感銘をうけるという作品ではない。しかし、読んでいるときの、なんとなくけだるい感覚のようなものだけが残る。
おそらく、歴史的には、この小説に描かれているような世界に、非常に共感する時代があり、その世代の人びとがいたということは、確かなことであろう。確かに、この作品は、ある時代、世代の人びとの感覚を、ただその生活の感覚だけをたどって描いている。
読みながら付箋をつけておいた箇所を引用してみると、
「すると、もちろん、ぼくはまたみじめな気持ちに突き落とされた。昼間なら、何につけ無感動(ハード・ボイルド)をきめこむのは造作もないことだ。が、夜になると、そうはいかなかった。」(p.68)
「おまえさんは祖国放棄者だ、で、もう祖国の土の感触もわからない。なのに、えばりくさっている。まがいもののヨーロッパの価値観にすっかり毒されちまっている。」(p.213)
ヘミングウェイの作品は、他に読んだものとしては、長編では、
やまもも書斎記 2018年5月14日
『誰がために鐘は鳴る』ヘミングウェイ
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/05/14/8850880
やまもも書斎記 2018年6月4日
『武器よさらば』ヘミングウェイ
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/06/04/8868453
がある。読んでいって、まぎれもなく『日はまた昇る』は傑作であると感じる。この作品は、確かに、ある時代のある人びとの人生を描き出すことに成功している。他の、ヘミングウェイの作品、短篇など、読んだ上でこの作品は、さらに読みなおしておきたいと感じる。









最近のコメント