『村上ラヂオ3』村上春樹・大橋歩 ― 2020-01-11
2020-01-11 當山日出夫(とうやまひでお)

村上春樹・大橋歩.『村上ラヂオ3-サラダ好きのライオン-』(新潮文庫).新潮社.2016(マガジンハウス.2012)
https://www.shinchosha.co.jp/book/100168/
続きである。
やまもも書斎記 2019年12月7日
『村上ラヂオ2』村上春樹・大橋歩
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/12/07/9186095
やまもも書斎記 2019年12月13日
『ビギナーズ』レイモンド・カーヴァー/村上春樹(訳)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/12/13/9188650
久々の村上春樹である。本は、昨年のうちに読んでしまってあったのだが、そのまま積んであった。他の本のことなど書いているうちに時間がたってしまった。
この本も楽しいエッセイである。ただ、このシリーズ「村上ラヂオ」は、たぶん意図的に、あえて内容をはぐらかしたような、わざとに中身の無いような文章になっている。あるいは、特に大上段ににふりかぶって、何かを論じるということをしていない。これは、文章の発表の媒体が「アンアン」という雑誌であるせいだろうと思う。
村上春樹の長編小説、短編小説を読んできた目からすると、このような軽妙な……とりようによっては、軽薄なとも受けとめられかねない……文章を書くことのできる人であったのかと、村上春樹に対する認識をあたらにするところがある。おそらく村上春樹の文学世界の、ある部分を端的に表しているのが、このようなエッセイ類なのだろうと思う。(また、他には、主にアメリカ現代文学の翻訳者という側面も持っている。)
しかし、考えようによっては、このエッセイのように、わざと何の役にもたたないような文章を書くというのも、これはこれでかなり高等なテクニックを必要とすることでもある。村上春樹の文章のテクニシャンとしての側面を見ることができようか。
次の村上春樹は、翻訳小説にもどって『頼むから静かにしてくれ』である。
2020年1月10日記
https://www.shinchosha.co.jp/book/100168/
続きである。
やまもも書斎記 2019年12月7日
『村上ラヂオ2』村上春樹・大橋歩
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/12/07/9186095
やまもも書斎記 2019年12月13日
『ビギナーズ』レイモンド・カーヴァー/村上春樹(訳)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/12/13/9188650
久々の村上春樹である。本は、昨年のうちに読んでしまってあったのだが、そのまま積んであった。他の本のことなど書いているうちに時間がたってしまった。
この本も楽しいエッセイである。ただ、このシリーズ「村上ラヂオ」は、たぶん意図的に、あえて内容をはぐらかしたような、わざとに中身の無いような文章になっている。あるいは、特に大上段ににふりかぶって、何かを論じるということをしていない。これは、文章の発表の媒体が「アンアン」という雑誌であるせいだろうと思う。
村上春樹の長編小説、短編小説を読んできた目からすると、このような軽妙な……とりようによっては、軽薄なとも受けとめられかねない……文章を書くことのできる人であったのかと、村上春樹に対する認識をあたらにするところがある。おそらく村上春樹の文学世界の、ある部分を端的に表しているのが、このようなエッセイ類なのだろうと思う。(また、他には、主にアメリカ現代文学の翻訳者という側面も持っている。)
しかし、考えようによっては、このエッセイのように、わざと何の役にもたたないような文章を書くというのも、これはこれでかなり高等なテクニックを必要とすることでもある。村上春樹の文章のテクニシャンとしての側面を見ることができようか。
次の村上春樹は、翻訳小説にもどって『頼むから静かにしてくれ』である。
2020年1月10日記
追記 2020-01-25
この続きは、
やまもも書斎記 2020年1月25日
『頼むから静かにしてくれ Ⅰ』レイモンド・カーヴァー/村上春樹(訳)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/01/25/9206094
この続きは、
やまもも書斎記 2020年1月25日
『頼むから静かにしてくれ Ⅰ』レイモンド・カーヴァー/村上春樹(訳)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/01/25/9206094
『スカーレット』あれこれ「新しい風が吹いて」 ― 2020-01-12
2020-01-12 當山日出夫(とうやまひでお)
『スカーレット』第14週「新しい風が吹いて」
https://www.nhk.or.jp/scarlet/story/index14_200106.html
前回は、
やまもも書斎記 2019年12月29日
『スカーレット』あれこれ「愛いっぱいの器」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/12/29/9194985
この週から、新しい登場人物が加わった。弟子の三津である。
年があらたまって、このドラマもいよいよ陶芸家としての喜美子を描くようである。
第一には、新しい弟子のこと。
押しかけのようにしてやってきた、三津という女性。八郎の弟子入り志願である。八郎はことわるが、なんとか喜美子のとりなしで、弟子入りということになった。
ここで描いていたのは、八郎の陶芸家としての生き方であろう。いろんな材料や技法を提案する三津に対して、あくまでも信楽の土地にこだわって制作をつづけていいきたいという気持ちを語る。信楽の土地とともにあるということが、八郎の陶芸家としての立場なのであろう。
第二には、陶芸家としての喜美子。
本格的に喜美子も陶芸の道を歩み始めることになる。作品作りである。そして、喜美子は作品づくりに貪欲である。これまでに作ってきたものを破壊して、先に進もうとする。だが、そのような意気込みは、八郎の立場とは異なるものである。
ここで、八郎は最後につぶやく。喜美子に側にいられるのは、しんどい、と。
以上の二点が、この週の見どころかと思う。
これから、陶芸家としての喜美子を描くとなると、そこで八郎と、どうおりあいをつけることになるのだろうか。夫婦としてすれ違い、あるいは、対立するということになるのだろうか。そして、そこに弟子の三津がどうからんでくることになるのか。
ところで、印象的だったのは、喜美子がおにぎりをつくって、海苔で顔を作るシーン。おにぎりの数も増えてきているようだ。おにぎりに、喜美子の家族への思いがこめられていると感じるシーンであった。
『スカーレット』第14週「新しい風が吹いて」
https://www.nhk.or.jp/scarlet/story/index14_200106.html
前回は、
やまもも書斎記 2019年12月29日
『スカーレット』あれこれ「愛いっぱいの器」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/12/29/9194985
この週から、新しい登場人物が加わった。弟子の三津である。
年があらたまって、このドラマもいよいよ陶芸家としての喜美子を描くようである。
第一には、新しい弟子のこと。
押しかけのようにしてやってきた、三津という女性。八郎の弟子入り志願である。八郎はことわるが、なんとか喜美子のとりなしで、弟子入りということになった。
ここで描いていたのは、八郎の陶芸家としての生き方であろう。いろんな材料や技法を提案する三津に対して、あくまでも信楽の土地にこだわって制作をつづけていいきたいという気持ちを語る。信楽の土地とともにあるということが、八郎の陶芸家としての立場なのであろう。
第二には、陶芸家としての喜美子。
本格的に喜美子も陶芸の道を歩み始めることになる。作品作りである。そして、喜美子は作品づくりに貪欲である。これまでに作ってきたものを破壊して、先に進もうとする。だが、そのような意気込みは、八郎の立場とは異なるものである。
ここで、八郎は最後につぶやく。喜美子に側にいられるのは、しんどい、と。
以上の二点が、この週の見どころかと思う。
これから、陶芸家としての喜美子を描くとなると、そこで八郎と、どうおりあいをつけることになるのだろうか。夫婦としてすれ違い、あるいは、対立するということになるのだろうか。そして、そこに弟子の三津がどうからんでくることになるのか。
ところで、印象的だったのは、喜美子がおにぎりをつくって、海苔で顔を作るシーン。おにぎりの数も増えてきているようだ。おにぎりに、喜美子の家族への思いがこめられていると感じるシーンであった。
2020年1月11日記
追記 2020-01-19
この続きは、
やまもも書斎記 2020年1月19日
『スカーレット』あれこれ「優しさが交差して」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/01/19/9203726
この続きは、
やまもも書斎記 2020年1月19日
『スカーレット』あれこれ「優しさが交差して」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/01/19/9203726
新潮日本古典集成『源氏物語』(八) ― 2020-01-13
2020-01-13 當山日出夫(とうやまひでお)
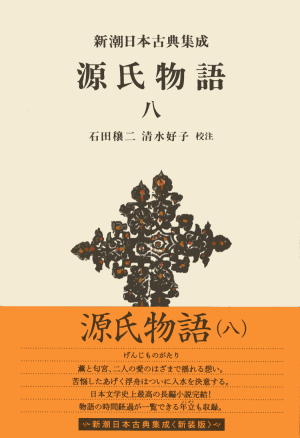
石田穣二・清水好子(校注).『源氏物語』(八)新潮日本古典集成(新装版).新潮社.2014
https://www.shinchosha.co.jp/book/620825/
続きである。
やまもも書斎記 2020年1月6日
新潮日本古典集成『源氏物語』(七)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/01/06/9198739
この本を前回読んだときのことは、
やまもも書斎記 2019年3月2日
『源氏物語』(八)新潮日本古典集成
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/03/02/9042336
※以下の文章は、昨年(2019)のうち、夏の間に、書いておいたものである。
最後の八冊目には「浮舟」から「夢浮橋」をおさめる。
今年になって二回目の『源氏物語』通読である。読み始めたきっかけは、『源氏物語』と「文字」ということを考えてみようということであった。『源氏物語』の世界のなかで、「文字」あるいは「書く」ということは、どのような意味があるのか、自分でテキストを読みながら考えてみたいと思った。
そう思って読んで見ると、たしかに『源氏物語』は、「書く」ということと密接に関連してなりたっている。特に最後の「夢浮橋」において、薫の使いとして小君が、消息を、出家してしまった浮舟のところにもっていくことで、話が終わっている。以前に読んだときには、このような問題意識をもたずに読んできたせいもあるのだが、消息(書簡)を持って行くことが、物語の展開のうえで重要な意味を持っていることに気付かずに過ごしてきてしまった。
また、「宇治十帖」になってからもそうなのであるが、登場人物たちは、頻繁に手紙のやりとりをしている。歌が出てくるときには、どんな紙に、どんな筆跡で書いたのか、詳細に説明がある。たぶん、このような説明のない歌のやりとりの方が少ないかもしれない。
さらに、書いたもの(書簡)が無い場合、口頭でつたえるような場合には、そうであったことのむね、断り書きがある。つまりこれは、基本が、書いたものをわたすということが前提になっている記述と思われる。
ところで、「宇治十帖」であるが、本編とは同じ作者なのであろうか、あるいは、別作者なのであろうか。古来より、様々に説があるところである。今、思うことを書いてみるならば、同じ人間が書いたとするならば、それは、かなり本編とは筆致が異なっている。逆に、別の人間が書いたとするならば、本編ほどの作品を書く、それ以上の物語の筆力がなければ、「宇治十帖」は書けないだろう。どちらにも傾きかねる、微妙な印象を持つことになる。
ただ、そうはいいながらも、「宇治十帖」もまた、先行する昔物語や説話の世界があって成立していることは感じ取れる。失踪した浮舟が発見されるあたりは、観音霊験譚であろうし、また、「宇治十帖」の主要なモチーフになっている、二人の男性(薫・匂宮)に言い寄られて身をなげてしまう女性(浮舟)という設定も、先行する話があってこそ書けたものだろう。この意味においては、『源氏物語』の物語世界は、説話の世界とつらなるところがある。
後期の講義の準備と思って読んでみた『源氏物語』であるが、もう老後の読書である。ただ、楽しみのために本のページを繰ることになってしまうところがある。これは、これでいいのだろう。もはや『源氏物語』で論文を書こうという気もない。しかし、まだ、『源氏物語』であれば、現代の校注本で、さほど難儀することなく読める、このような読書をつづけていきたいものである。
https://www.shinchosha.co.jp/book/620825/
続きである。
やまもも書斎記 2020年1月6日
新潮日本古典集成『源氏物語』(七)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/01/06/9198739
この本を前回読んだときのことは、
やまもも書斎記 2019年3月2日
『源氏物語』(八)新潮日本古典集成
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/03/02/9042336
※以下の文章は、昨年(2019)のうち、夏の間に、書いておいたものである。
最後の八冊目には「浮舟」から「夢浮橋」をおさめる。
今年になって二回目の『源氏物語』通読である。読み始めたきっかけは、『源氏物語』と「文字」ということを考えてみようということであった。『源氏物語』の世界のなかで、「文字」あるいは「書く」ということは、どのような意味があるのか、自分でテキストを読みながら考えてみたいと思った。
そう思って読んで見ると、たしかに『源氏物語』は、「書く」ということと密接に関連してなりたっている。特に最後の「夢浮橋」において、薫の使いとして小君が、消息を、出家してしまった浮舟のところにもっていくことで、話が終わっている。以前に読んだときには、このような問題意識をもたずに読んできたせいもあるのだが、消息(書簡)を持って行くことが、物語の展開のうえで重要な意味を持っていることに気付かずに過ごしてきてしまった。
また、「宇治十帖」になってからもそうなのであるが、登場人物たちは、頻繁に手紙のやりとりをしている。歌が出てくるときには、どんな紙に、どんな筆跡で書いたのか、詳細に説明がある。たぶん、このような説明のない歌のやりとりの方が少ないかもしれない。
さらに、書いたもの(書簡)が無い場合、口頭でつたえるような場合には、そうであったことのむね、断り書きがある。つまりこれは、基本が、書いたものをわたすということが前提になっている記述と思われる。
ところで、「宇治十帖」であるが、本編とは同じ作者なのであろうか、あるいは、別作者なのであろうか。古来より、様々に説があるところである。今、思うことを書いてみるならば、同じ人間が書いたとするならば、それは、かなり本編とは筆致が異なっている。逆に、別の人間が書いたとするならば、本編ほどの作品を書く、それ以上の物語の筆力がなければ、「宇治十帖」は書けないだろう。どちらにも傾きかねる、微妙な印象を持つことになる。
ただ、そうはいいながらも、「宇治十帖」もまた、先行する昔物語や説話の世界があって成立していることは感じ取れる。失踪した浮舟が発見されるあたりは、観音霊験譚であろうし、また、「宇治十帖」の主要なモチーフになっている、二人の男性(薫・匂宮)に言い寄られて身をなげてしまう女性(浮舟)という設定も、先行する話があってこそ書けたものだろう。この意味においては、『源氏物語』の物語世界は、説話の世界とつらなるところがある。
後期の講義の準備と思って読んでみた『源氏物語』であるが、もう老後の読書である。ただ、楽しみのために本のページを繰ることになってしまうところがある。これは、これでいいのだろう。もはや『源氏物語』で論文を書こうという気もない。しかし、まだ、『源氏物語』であれば、現代の校注本で、さほど難儀することなく読める、このような読書をつづけていきたいものである。
『朱夏』宮尾登美子 ― 2020-01-14
2020-01-14 當山日出夫(とうやまひでお)

宮尾登美子.『朱夏』(新潮文庫).新潮社.1998(2006.改版)
https://www.shinchosha.co.jp/book/129309/
続きである。
やまもも書斎記
『春燈』宮尾登美子 2020年1月10日
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/01/10/9200266
書かれた順番からいうと、この『朱夏』の方が、『春燈』より先になる。が、小説の時間のうえでは、『櫂』からはじまって、次に『春燈』、そして『朱夏』となる。今回は、小説の時間の順にしたがって読んだ。
この作品、出たときに買って読んだのを憶えている。そのころ、宮尾登美子の作品の多くを買って読んでいたものである。『序の舞』が新聞に連載されていたのも、時折読んだかと思う。
この『朱夏』であるが……作者の高知での結婚からスタートして、満州に舞台は移る。昭和二〇年のことである。その開拓村の教員の妻として、満州国に赴くことになる。そこでの生活、そして終戦、その後の難民生活を経て、日本に帰国するまでの、およそ一年半ほどのことが記される。
『朱夏』を読んで感じることは、やはり、このような体験が、かつての日本にはあったのだ、という感慨であり、また、よくこれを、「文学」として描くことができているという、感嘆のようなものである。
描かれている難民生活は、悲惨のひとことにつきると言ってよいだろう。が、ノンフィクションではなく、「小説」として、綾子という主人公の物語として描くことによって、その体験のもつ意味をかみしめることになっていると感じる。
『櫂』『春燈』と順番に読むとであるが、綾子は、その性格の強さが際立っている。高知の街で芸妓娼妓紹介業の家に生まれ育った経歴からくるのであろう、その独特の人間観が、綾子の個性と言っていいだろうか、過酷な逆境にあっても、まわりの人間から距離のある存在として、浮かびあがってくる。このような綾子の存在を、「小説」という形式において描くことは、おそらく作者(宮尾登美子)にとって、どうしようもない通過儀礼のようなものであったかとも思う。
この小説も、ある意味では明るい。どんなに悲惨な経験があったとしても、それを、作者は距離をおいてながめ、回想しているところがある。それが、ある意味で、このような重厚な作品を読みながらでも、最後は、無事に生きているだろう、その確信につながっている。
また、この作品は、日本における満州とはどのようなものであったのか、満州にわたった人びとにとって、その地は何であり、また、故郷の日本は何であったのか……について、考えさせてくれる。この意味において、この『朱夏』は、読まれ続けるべき作品であろうと思う。
https://www.shinchosha.co.jp/book/129309/
続きである。
やまもも書斎記
『春燈』宮尾登美子 2020年1月10日
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/01/10/9200266
書かれた順番からいうと、この『朱夏』の方が、『春燈』より先になる。が、小説の時間のうえでは、『櫂』からはじまって、次に『春燈』、そして『朱夏』となる。今回は、小説の時間の順にしたがって読んだ。
この作品、出たときに買って読んだのを憶えている。そのころ、宮尾登美子の作品の多くを買って読んでいたものである。『序の舞』が新聞に連載されていたのも、時折読んだかと思う。
この『朱夏』であるが……作者の高知での結婚からスタートして、満州に舞台は移る。昭和二〇年のことである。その開拓村の教員の妻として、満州国に赴くことになる。そこでの生活、そして終戦、その後の難民生活を経て、日本に帰国するまでの、およそ一年半ほどのことが記される。
『朱夏』を読んで感じることは、やはり、このような体験が、かつての日本にはあったのだ、という感慨であり、また、よくこれを、「文学」として描くことができているという、感嘆のようなものである。
描かれている難民生活は、悲惨のひとことにつきると言ってよいだろう。が、ノンフィクションではなく、「小説」として、綾子という主人公の物語として描くことによって、その体験のもつ意味をかみしめることになっていると感じる。
『櫂』『春燈』と順番に読むとであるが、綾子は、その性格の強さが際立っている。高知の街で芸妓娼妓紹介業の家に生まれ育った経歴からくるのであろう、その独特の人間観が、綾子の個性と言っていいだろうか、過酷な逆境にあっても、まわりの人間から距離のある存在として、浮かびあがってくる。このような綾子の存在を、「小説」という形式において描くことは、おそらく作者(宮尾登美子)にとって、どうしようもない通過儀礼のようなものであったかとも思う。
この小説も、ある意味では明るい。どんなに悲惨な経験があったとしても、それを、作者は距離をおいてながめ、回想しているところがある。それが、ある意味で、このような重厚な作品を読みながらでも、最後は、無事に生きているだろう、その確信につながっている。
また、この作品は、日本における満州とはどのようなものであったのか、満州にわたった人びとにとって、その地は何であり、また、故郷の日本は何であったのか……について、考えさせてくれる。この意味において、この『朱夏』は、読まれ続けるべき作品であろうと思う。
2019年12月23日記
梅の冬芽 ― 2020-01-15
2020-01-15 當山日出夫(とうやまひでお)
水曜日なので花の写真。今日は、梅の冬芽である。
前回は、
やまもも書斎記 2020年1月8日
山茶花
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/01/08/9199503
これは昨年も掲載している。
やまもも書斎記 2019年2月6日
梅の冬芽
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/02/06/9032947
今年の冬は暖かい。そのせいか、見ていると梅の木の冬芽の様子も、例年よりも早く花が咲きそうな感じである。
撮影のレンズは、昨年末に新しく買ったタムロンの90ミリをつかっている。おそらく、日本のカメラ、レンズの歴史の中では、名前の残る製品の一つであろう。特に動植物の写真においては、ひときわ際立った存在感があるといっていい。ただ、ニコンのDXでつかうと、1.5倍の焦点距離の換算になる。つまり、35ミリフルサイズでいえば、135ミリの画角のレンズである。
このレンズ、その描写もいいが、被写体と距離をとれるのがいい。今日のような写真をとろうと思うとき、レンズフードをつけても、かなり余裕をもって、被写体との距離をとれる。このところは、朝庭に出て写真を写すときには、このレンズを使うようになっている。
これから冬を越して、春、暖かくなってきて梅の花が咲くころ、また、同じように梅の花の写真を撮れればいいと思っている。
水曜日なので花の写真。今日は、梅の冬芽である。
前回は、
やまもも書斎記 2020年1月8日
山茶花
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/01/08/9199503
これは昨年も掲載している。
やまもも書斎記 2019年2月6日
梅の冬芽
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/02/06/9032947
今年の冬は暖かい。そのせいか、見ていると梅の木の冬芽の様子も、例年よりも早く花が咲きそうな感じである。
撮影のレンズは、昨年末に新しく買ったタムロンの90ミリをつかっている。おそらく、日本のカメラ、レンズの歴史の中では、名前の残る製品の一つであろう。特に動植物の写真においては、ひときわ際立った存在感があるといっていい。ただ、ニコンのDXでつかうと、1.5倍の焦点距離の換算になる。つまり、35ミリフルサイズでいえば、135ミリの画角のレンズである。
このレンズ、その描写もいいが、被写体と距離をとれるのがいい。今日のような写真をとろうと思うとき、レンズフードをつけても、かなり余裕をもって、被写体との距離をとれる。このところは、朝庭に出て写真を写すときには、このレンズを使うようになっている。
これから冬を越して、春、暖かくなってきて梅の花が咲くころ、また、同じように梅の花の写真を撮れればいいと思っている。
Nikon D500
TAMRON SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD
2020年1月13日記
『仁淀川』宮尾登美子 ― 2020-01-16
2020-01-16 當山日出夫(とうやまひでお)

宮尾登美子.『仁淀川』(新潮文庫).新潮社.2003
https://www.shinchosha.co.jp/book/129317/
続きである。
やまもも書斎記 2020年1月14日
『朱夏』宮尾登美子
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/01/14/9201803
ふと思って、『櫂』を再読してみたくなった。宮尾登美子の自伝的作品である。描かれた時代順にいえば、『櫂』『春燈』『朱夏』そして『仁淀川』になる。ここまで読んで、一番いいと感じるのは、『櫂』。文学的達成という意味では、最高であろう。また、『朱夏』もいい。このような悲惨な満州体験というものがあった、このことを文学的に書きとめてあることの意義は大きい。『春燈』は、その『櫂』と『朱夏』をつなぐものとしての、高知での幼少、少女時代のことがえがかれる。
『仁淀川』であるが……はっきりいって、この作品は、小説として読んで、あまり面白くない。つまらないというのではないが、『櫂』のように、思わずにその小説世界の中に入り込んで読んでしまうというところがない。どことなく散漫な感じがしてしまう。(ただ、これは、私が、あまり集中してこの本を読めなかったせいかもしれないが。)
しかし、読後に感じるのは、作者(宮尾登美子)としては、この作品を書かねばならなかった必然性ということを強く感じる。
この作品で、父の岩伍……宮尾登美子が最も嫌っていた職業……芸妓娼妓紹介業……女衒……であるが、その死が描かれる。また『櫂』の主人公であり、綾子の「母」である喜和も死ぬ。そして、最後のところで、作者(宮尾登美子/綾子)は、作家になる決意を固める。その決心のところまで読んで、この『櫂』から始まる一連の作品は、作者にとっては、どうしても書いておかなければならない作品であったのだということを強く思う。
また、この作品は、戦後の高知が舞台になる。その目で読むならば、『櫂』に描かれた戦前の高知の街の風物は、戦災で失われてしまったものであることに気付く。そして、そう思ってみると、まさに『櫂』は、失ってしまったものへの哀惜の念の小説であったことに、改めて思いがいたる。
『仁淀川』は、作家としての宮尾登美子を理解するうえで、きわめて重要な位置にある作品であるといえよう。
つづけて、宮尾登美子の作品について、未読であったものを中心に読んでおきたいと思う。
2019年12月27日記
https://www.shinchosha.co.jp/book/129317/
続きである。
やまもも書斎記 2020年1月14日
『朱夏』宮尾登美子
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/01/14/9201803
ふと思って、『櫂』を再読してみたくなった。宮尾登美子の自伝的作品である。描かれた時代順にいえば、『櫂』『春燈』『朱夏』そして『仁淀川』になる。ここまで読んで、一番いいと感じるのは、『櫂』。文学的達成という意味では、最高であろう。また、『朱夏』もいい。このような悲惨な満州体験というものがあった、このことを文学的に書きとめてあることの意義は大きい。『春燈』は、その『櫂』と『朱夏』をつなぐものとしての、高知での幼少、少女時代のことがえがかれる。
『仁淀川』であるが……はっきりいって、この作品は、小説として読んで、あまり面白くない。つまらないというのではないが、『櫂』のように、思わずにその小説世界の中に入り込んで読んでしまうというところがない。どことなく散漫な感じがしてしまう。(ただ、これは、私が、あまり集中してこの本を読めなかったせいかもしれないが。)
しかし、読後に感じるのは、作者(宮尾登美子)としては、この作品を書かねばならなかった必然性ということを強く感じる。
この作品で、父の岩伍……宮尾登美子が最も嫌っていた職業……芸妓娼妓紹介業……女衒……であるが、その死が描かれる。また『櫂』の主人公であり、綾子の「母」である喜和も死ぬ。そして、最後のところで、作者(宮尾登美子/綾子)は、作家になる決意を固める。その決心のところまで読んで、この『櫂』から始まる一連の作品は、作者にとっては、どうしても書いておかなければならない作品であったのだということを強く思う。
また、この作品は、戦後の高知が舞台になる。その目で読むならば、『櫂』に描かれた戦前の高知の街の風物は、戦災で失われてしまったものであることに気付く。そして、そう思ってみると、まさに『櫂』は、失ってしまったものへの哀惜の念の小説であったことに、改めて思いがいたる。
『仁淀川』は、作家としての宮尾登美子を理解するうえで、きわめて重要な位置にある作品であるといえよう。
つづけて、宮尾登美子の作品について、未読であったものを中心に読んでおきたいと思う。
2019年12月27日記
『国語教育 混迷する改革』紅野謙介 ― 2020-01-17
2020-01-17 當山日出夫(とうやまひでお)
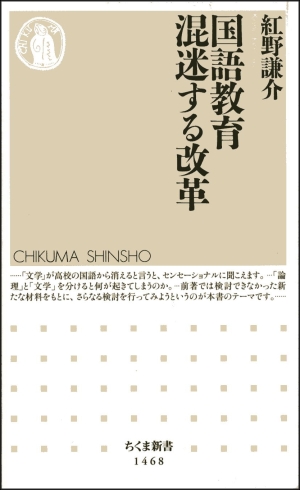
紅野謙介.『国語教育 混迷する改革』(ちくま新書).筑摩書房.2020
https://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480072801/
国語学、日本語学という学問のはしくれで仕事をしてきた人間として、国語教育という分野のことは、まったく他人事ではない。また、今回の改革とされるものが、そもそもの教育と何か、学校はどうあるべきかの、根本にかかわる問題にもつながっている。等閑視するわけにはいかない。さらには、昨年から、議論のつづいている「古典は本当に必要なのか」の論点にもふみこむところがある。
もうやめてしまったのだが、以前、大学で、「アカデミック・ライティング」という授業を担当していたことがある。大学生に、論文やレポートの書き方を教えていた。そのとき、主に参考にしたのは、木下是雄の著作であった。直接、テキストに採用したのは、戸田山和久の『論文の教室』であった。
このとき、私は、学校における、(いまでいう)コミュニケーション・スキル、プレンゼテーション・スキルの重要性について、学生に語ったものである。そして、文学教育、情操教育に偏重している、日本の国語教育については、批判的であった。
だが、今になって、学習指導要領の改訂、さらには、大学入試共通テスト、これらによって変わるであろう、これからの日本の国語教育の未来には、不安を感じずにはいられない。
この本で直接対象としているのは、学習指導要領であり、予定されている大学入試共通テストである。大学入試共通テストについては、英語の民間試験利用が中止になったり、さらには、国語と数学における記述式問題の是非が話題になっている。
だが、問題は、国語の試験において、記述式問題を導入することにあるのではない。どのような試験を課すのか、それによって、どのような勉強が必要なるのか。影響の範囲は大きい。
同時に、大学入試の改革にあわせて、国語の科目のカリキュラムも大きく変わろうとしている。
国語……ことばの教育……というのは、それを学ぶ人間のこころに刻み込まれる。場合によっては、人を傷つけもする。だからこそ、学校という場所における「ことば」は、より慎重でなければならない。ことばというものに対する畏敬の念が必要である。ことばの教育については、常に謙虚である必要がある。
しかし、新しい学習指導要領を見ると、どうやらそうではないようだ。
ところで、「古典は本当に必要なのか」の議論と関連して、次の箇所を引用しておきたい。新しく設定される「言語文化」の授業について、次のように指摘する。
「もとより、自文化に対する知識と誇りをもたない者が、国際社会で自立した社会人として扱われることなどあり得ない」、藤森さんはそう書いています。しかし、それはずいぶん偏った認識です。中東やアフリカで内戦や混乱によって難民となり、あるいは他国に移り住んだ人がわずかな幸運と並々ならぬ努力によって国境を越えて新たな土地で活躍している、そうしたケースがたくさんあります。「国際社会で自立した社会人」というとき、そういう人たちの存在が浮かばないとしたら、思い描かれている「国際社会」といはせいぜい日本の延長線上にある名ばかりの「国際」社会ではないでしょうか。
以上、p.177
これからの日本、これからの国際社会において、古典教育とはどうあるべきか、改めてかえりみるべきところがある。
2020年1月12日記
https://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480072801/
国語学、日本語学という学問のはしくれで仕事をしてきた人間として、国語教育という分野のことは、まったく他人事ではない。また、今回の改革とされるものが、そもそもの教育と何か、学校はどうあるべきかの、根本にかかわる問題にもつながっている。等閑視するわけにはいかない。さらには、昨年から、議論のつづいている「古典は本当に必要なのか」の論点にもふみこむところがある。
もうやめてしまったのだが、以前、大学で、「アカデミック・ライティング」という授業を担当していたことがある。大学生に、論文やレポートの書き方を教えていた。そのとき、主に参考にしたのは、木下是雄の著作であった。直接、テキストに採用したのは、戸田山和久の『論文の教室』であった。
このとき、私は、学校における、(いまでいう)コミュニケーション・スキル、プレンゼテーション・スキルの重要性について、学生に語ったものである。そして、文学教育、情操教育に偏重している、日本の国語教育については、批判的であった。
だが、今になって、学習指導要領の改訂、さらには、大学入試共通テスト、これらによって変わるであろう、これからの日本の国語教育の未来には、不安を感じずにはいられない。
この本で直接対象としているのは、学習指導要領であり、予定されている大学入試共通テストである。大学入試共通テストについては、英語の民間試験利用が中止になったり、さらには、国語と数学における記述式問題の是非が話題になっている。
だが、問題は、国語の試験において、記述式問題を導入することにあるのではない。どのような試験を課すのか、それによって、どのような勉強が必要なるのか。影響の範囲は大きい。
同時に、大学入試の改革にあわせて、国語の科目のカリキュラムも大きく変わろうとしている。
国語……ことばの教育……というのは、それを学ぶ人間のこころに刻み込まれる。場合によっては、人を傷つけもする。だからこそ、学校という場所における「ことば」は、より慎重でなければならない。ことばというものに対する畏敬の念が必要である。ことばの教育については、常に謙虚である必要がある。
しかし、新しい学習指導要領を見ると、どうやらそうではないようだ。
ところで、「古典は本当に必要なのか」の議論と関連して、次の箇所を引用しておきたい。新しく設定される「言語文化」の授業について、次のように指摘する。
「もとより、自文化に対する知識と誇りをもたない者が、国際社会で自立した社会人として扱われることなどあり得ない」、藤森さんはそう書いています。しかし、それはずいぶん偏った認識です。中東やアフリカで内戦や混乱によって難民となり、あるいは他国に移り住んだ人がわずかな幸運と並々ならぬ努力によって国境を越えて新たな土地で活躍している、そうしたケースがたくさんあります。「国際社会で自立した社会人」というとき、そういう人たちの存在が浮かばないとしたら、思い描かれている「国際社会」といはせいぜい日本の延長線上にある名ばかりの「国際」社会ではないでしょうか。
以上、p.177
これからの日本、これからの国際社会において、古典教育とはどうあるべきか、改めてかえりみるべきところがある。
2020年1月12日記
『鬼龍院花子の生涯』宮尾登美子 ― 2020-01-18
2020-01-18 當山日出夫(とうやまひでお)

宮尾登美子.『鬼龍院花子の生涯』(文春文庫).文藝春秋.2011(文藝春秋.1980)
https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784167287139
この作品は再読になる。
まず、「別冊文藝春秋」(145~149に連載)。単行本が、1980年。文春文庫(旧版)が、1982。その新装版である。私が、以前に読んだのは、旧版の文春文庫であったろうかと思う。
この作品、むしろ映画の方が有名かもしれない。これは、私も見ている。夏目雅子の迫力のある演技が印象にのこる。そして、五社英雄監督の、けれんみたっぷりの演出。映画の印象がつよく残っている。
が、再度、この作品を読んでみて、映画で描いていない、この作品の魅力をつよく感じた。
主な登場人物は、三人になるだろう。まず、タイトルに名前のある鬼龍院花子。しかし、この小説は、この花子の生涯をおってっはいるものの、それがメインのストーリーにになっていない。むしろ、その父親になる、鬼龍院政五郎こそが主人公といっていいだろう。その鬼龍院政五郎の生いたちからはじまって、侠客として隆盛をきわめ、さらには、その落魄の晩年にいたるまでを、詳細につづってある。そして、それを見ているのは、鬼龍院政五郎に養女として育てられることになる松恵という女性である。全編、基本的には、この松恵の視点から描かれることになる。
この『鬼龍院花子の生涯』を読んで思うことを書くならば、次の二点だろうか。
第一には、この作品は、まさにヤクザ小説、任侠小説である。
鬼龍院政五郎の侠客としての一生を描いた作品といってよい。そして、興味深いのは、大正から昭和戦前にかけてのやくざの社会的位置づけである。飛行機、相撲、そして、演芸などの興行にからんで、そのなりわいの資金としてしている。さらには、当時の社会運動にも関係している。「強きをくじき、弱きをたすける」ということで、社会主義とも共鳴するところのある、任侠道というものになる。このところは、以前に読んだときには見逃していたが、今回、読みなおしてみて、興味深かったところである。
神戸の山口組なども、実名で登場する。近代の侠客の歴史の一面を描いた作品であるといっていいだろう。
第二には、宮尾登美子という小説家は、「老い」を描くことのできる作家であることの確認である。
『櫂』を読みなおしてみたくなって、『春燈』『朱夏』『仁淀川』と読んで、次に手にしたのが、この『鬼龍院花子の生涯』である。これらの作品を通じて、確かに作者(宮尾登美子)は「老い」というものを描いている。『仁淀川』における晩年の、岩伍、それから、喜和。また、『鬼龍院花子の生涯』においても、侠客である鬼龍院政五郎の最盛期のときのみならず、おちぶれ病を得た晩年から死にいたるまでをも、冷静な目で描いている。
日本の近現代の小説のなかで「老い」というのは、どのように描かれてきたであろうか。自分自身、もう若くはない。還暦をとうにすぎた。この年になってみると、「若さ」を描いた小説は、それなりに面白のだが、それと同時に、「老い」というものをどう文学的に描くか、読みながら気になるようになってきた。
この観点から読んでみて、宮尾登美子の作品は、確かな、そして、冷徹とでもいうような視線で、人間の「老い」をみつめているところがある。
以上の二点が、『鬼龍院花子の生涯』を再読して思ったことなどである。
さらに書いておくならば、宮尾登美子の小説のうまさがひかる作品でもある。特に、松恵という女性の視点から描くことによって、タイトルになっている花子の無残な人生を、冷酷に見つめているようなところがある。また、鬼龍院政五郎についても、その侠客としての人生を冷静に描くことにつながっている。無論、松恵自身の人生の波乱も描かれる。それを通じて、この作品全編にわたって、作品としての奥行きと広がりをあたえている。このあたりの小説の作り方として、実にうまいと感じさせる。
あるいは他の宮尾登美子作品が読まれなくなったとしても、この『鬼龍院花子の生涯』は読まれ続けていくようにも思う。それは、この作品が、近代の極道小説であると同時に、松恵という一人の女性の自立の物語にもなっているからである。自立した女性を描いた作品として、この作品は確固たるものをもっている。
2019年12月27日記
https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784167287139
この作品は再読になる。
まず、「別冊文藝春秋」(145~149に連載)。単行本が、1980年。文春文庫(旧版)が、1982。その新装版である。私が、以前に読んだのは、旧版の文春文庫であったろうかと思う。
この作品、むしろ映画の方が有名かもしれない。これは、私も見ている。夏目雅子の迫力のある演技が印象にのこる。そして、五社英雄監督の、けれんみたっぷりの演出。映画の印象がつよく残っている。
が、再度、この作品を読んでみて、映画で描いていない、この作品の魅力をつよく感じた。
主な登場人物は、三人になるだろう。まず、タイトルに名前のある鬼龍院花子。しかし、この小説は、この花子の生涯をおってっはいるものの、それがメインのストーリーにになっていない。むしろ、その父親になる、鬼龍院政五郎こそが主人公といっていいだろう。その鬼龍院政五郎の生いたちからはじまって、侠客として隆盛をきわめ、さらには、その落魄の晩年にいたるまでを、詳細につづってある。そして、それを見ているのは、鬼龍院政五郎に養女として育てられることになる松恵という女性である。全編、基本的には、この松恵の視点から描かれることになる。
この『鬼龍院花子の生涯』を読んで思うことを書くならば、次の二点だろうか。
第一には、この作品は、まさにヤクザ小説、任侠小説である。
鬼龍院政五郎の侠客としての一生を描いた作品といってよい。そして、興味深いのは、大正から昭和戦前にかけてのやくざの社会的位置づけである。飛行機、相撲、そして、演芸などの興行にからんで、そのなりわいの資金としてしている。さらには、当時の社会運動にも関係している。「強きをくじき、弱きをたすける」ということで、社会主義とも共鳴するところのある、任侠道というものになる。このところは、以前に読んだときには見逃していたが、今回、読みなおしてみて、興味深かったところである。
神戸の山口組なども、実名で登場する。近代の侠客の歴史の一面を描いた作品であるといっていいだろう。
第二には、宮尾登美子という小説家は、「老い」を描くことのできる作家であることの確認である。
『櫂』を読みなおしてみたくなって、『春燈』『朱夏』『仁淀川』と読んで、次に手にしたのが、この『鬼龍院花子の生涯』である。これらの作品を通じて、確かに作者(宮尾登美子)は「老い」というものを描いている。『仁淀川』における晩年の、岩伍、それから、喜和。また、『鬼龍院花子の生涯』においても、侠客である鬼龍院政五郎の最盛期のときのみならず、おちぶれ病を得た晩年から死にいたるまでをも、冷静な目で描いている。
日本の近現代の小説のなかで「老い」というのは、どのように描かれてきたであろうか。自分自身、もう若くはない。還暦をとうにすぎた。この年になってみると、「若さ」を描いた小説は、それなりに面白のだが、それと同時に、「老い」というものをどう文学的に描くか、読みながら気になるようになってきた。
この観点から読んでみて、宮尾登美子の作品は、確かな、そして、冷徹とでもいうような視線で、人間の「老い」をみつめているところがある。
以上の二点が、『鬼龍院花子の生涯』を再読して思ったことなどである。
さらに書いておくならば、宮尾登美子の小説のうまさがひかる作品でもある。特に、松恵という女性の視点から描くことによって、タイトルになっている花子の無残な人生を、冷酷に見つめているようなところがある。また、鬼龍院政五郎についても、その侠客としての人生を冷静に描くことにつながっている。無論、松恵自身の人生の波乱も描かれる。それを通じて、この作品全編にわたって、作品としての奥行きと広がりをあたえている。このあたりの小説の作り方として、実にうまいと感じさせる。
あるいは他の宮尾登美子作品が読まれなくなったとしても、この『鬼龍院花子の生涯』は読まれ続けていくようにも思う。それは、この作品が、近代の極道小説であると同時に、松恵という一人の女性の自立の物語にもなっているからである。自立した女性を描いた作品として、この作品は確固たるものをもっている。
2019年12月27日記
『スカーレット』あれこれ「優しさが交差して」 ― 2020-01-19
2020-01-19 當山日出夫(とうやまひでお)
『スカーレット』第15週「優しさが交差して」
https://www.nhk.or.jp/scarlet/story/index15_200113.html
前回は、
やまもも書斎記 2020年1月12日
『スカーレット』あれこれ「新しい風が吹いて」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/01/12/9200942
この週で描いていたのは、陶芸家夫婦の情愛ということだろうか。
喜美子は、自分の作品をつくろうとする。また、陶芸家として道にまよっている八郎に対して、個展をやめるように助言する。しかし、八郎は、個展にむけて頑張ろうとする。一方、喜美子は、絵付けの皿の大量注文を受ける。
いわゆる内助の功というのではないが、陶芸家である夫を助けながら、また同時に自分自身の作品にもうちこもうとする喜美子の姿が、情感を込めて描かれていたように思う。
そこに、新しく入ってきた弟子の三津が、微妙にからんでくる。三津の存在が、これからの二人の陶芸家としての歩みに、どのような影響を与えることになるのだろうか、興味深いところである。
また、妹の百合子と信作とのこと、直子のこと、など家族のことが、これは、コミカルに描かれていた。
このドラマは、陶芸家としての喜美子の成長の物語であるように思う。その成長の過程を、夫との感情の行き違い、また、お互いの思いやりをふくめて、じっくりと描くようである。
喜美子は、次世代展に応募したが、落選してしまった。しかし、喜美子はあきらめない。八郎が東京に行って留守の間に、次の作品にとりかかっている。この喜美子の陶芸にかける静かなひたむきさが、このドラマの軸になっていくのだろう。
次週以降、いろいろ波乱もあるようだ。楽しみに見ることにしよう。
『スカーレット』第15週「優しさが交差して」
https://www.nhk.or.jp/scarlet/story/index15_200113.html
前回は、
やまもも書斎記 2020年1月12日
『スカーレット』あれこれ「新しい風が吹いて」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/01/12/9200942
この週で描いていたのは、陶芸家夫婦の情愛ということだろうか。
喜美子は、自分の作品をつくろうとする。また、陶芸家として道にまよっている八郎に対して、個展をやめるように助言する。しかし、八郎は、個展にむけて頑張ろうとする。一方、喜美子は、絵付けの皿の大量注文を受ける。
いわゆる内助の功というのではないが、陶芸家である夫を助けながら、また同時に自分自身の作品にもうちこもうとする喜美子の姿が、情感を込めて描かれていたように思う。
そこに、新しく入ってきた弟子の三津が、微妙にからんでくる。三津の存在が、これからの二人の陶芸家としての歩みに、どのような影響を与えることになるのだろうか、興味深いところである。
また、妹の百合子と信作とのこと、直子のこと、など家族のことが、これは、コミカルに描かれていた。
このドラマは、陶芸家としての喜美子の成長の物語であるように思う。その成長の過程を、夫との感情の行き違い、また、お互いの思いやりをふくめて、じっくりと描くようである。
喜美子は、次世代展に応募したが、落選してしまった。しかし、喜美子はあきらめない。八郎が東京に行って留守の間に、次の作品にとりかかっている。この喜美子の陶芸にかける静かなひたむきさが、このドラマの軸になっていくのだろう。
次週以降、いろいろ波乱もあるようだ。楽しみに見ることにしよう。
2020年1月18日記
追記 2020-01-26
この続きは、
やまもも書斎記 2020年1月16日
『スカーレット』あれこれ「熱くなる瞬間」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/01/26/9206544
この続きは、
やまもも書斎記 2020年1月16日
『スカーレット』あれこれ「熱くなる瞬間」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/01/26/9206544
『太平記』岩波文庫(一) ― 2020-01-20
2020-01-20 當山日出夫(とうやまひでお)

兵藤裕己(校注).『太平記』(一)(岩波文庫).岩波書店.2014
https://www.iwanami.co.jp/book/b245752.html
『太平記』を読んでおきたいと思って読んでいる。
理由としては、岩波文庫の太平記(兵藤裕己校注)が、六冊揃って刊行になっているということがある。これは、それぞれ出たときに買っていって、揃えて持っている。
また、この岩波文庫本の刊行をうけてのことだろうが、『アナホリッシュ國文學』が「特集:太平記」を刊行した。これを読んでみたいと思った。
持っている本として、すでに本棚にある本では、
兵藤裕己.『太平記〈よみ〉の可能性』(講談社学術文庫).講談社.2005
若尾政希.『「太平記読み」の時代』(平凡社ライブラリー).平凡社.2012
などがある。これらの本も、読んでおきたいと思ったこともある。
『太平記』であるが……若いころ、岩波の古典大系本で、手にとったことはある。そのとき……若い時……どうにも退屈な物語だなと感じたのが正直なところ。しかし、この歳になって、新しい岩波文庫で読んでみて、こんなにも面白い物語だったのかと認識を新たにしたところがある。
出てくる武将たちの行動、精神、それをとりまく大きな歴史のながれ……これらが、実に興味深い。とにかく読んでいて面白いのである。
それは、一つには、出てくる文章の装飾的な引用など、和漢の故事に言及したところが多いのだが、これらについて、これまでの勉強で、どこかで見たことがあるものが多くなってきたということもあるのかと思う。この故事や引用は、見た記憶ががある、というものが多くなってきた。また、同時に、そのような引用があっても、特にその典拠を原典にあたって調べながら読もうという気が、もうなくなってしまった、ということもある。ただ、読んで楽しみたい、そのように思って読むようになった。
第一冊目(第一巻から第八巻をおさめる)を読んで思うことは次の二点ぐらいだろうか。
第一に、登場人物……主に武士であるが……の、行動の根底にあるもの……エトスと言ってもいいだろうか……が、面白い。非常に功利的、実利的に判断して行動している面がある。その一方で、忠義という理念のために行動する、戦う、自害する。また、さまざまに計略をめぐらす。これらの武士の行動が、躍動的である。
第二に、これは、『平家物語』などと比べての印象になるのだが……登場人物たちの行動が、論理的という印象をもつ。これは、現代の人間の論理とは異なるのは無論だが、『平家物語』や『今昔物語集』などの登場人物に比べて見るならば、格段に論理的な判断力と、説明がある。これは、やはり、一四世紀、中世も後半になって、人びとのものの考え方が変わってきたな、と思わせるところがある。だからといって、その人びとの行動規範に、素直に共感できるというのではない。やはり、そこは、時代の隔たりというものを感じる。
以上の二点が、第一冊を読んで思うことなどである。
『平家物語』も、二〇一九年になってから改めて全巻を通して読んだ。岩波文庫で四冊。これを思い返してみると、『平家物語』は、まだ、どこか「もののあはれ」を感じさせる文学である。だが、『太平記』には、それが無い。このあたりも、時代の流れ、潮流というものを感じる。
ところで、『太平記』は、近世から近代……戦前……までは、広く読まれた作品であるが、近年は、あまり読まれないようだ。これも、「古典」とは何であるかという問題とも関連して、考えてみたいことのひとつである。
2019年12月7日記
https://www.iwanami.co.jp/book/b245752.html
『太平記』を読んでおきたいと思って読んでいる。
理由としては、岩波文庫の太平記(兵藤裕己校注)が、六冊揃って刊行になっているということがある。これは、それぞれ出たときに買っていって、揃えて持っている。
また、この岩波文庫本の刊行をうけてのことだろうが、『アナホリッシュ國文學』が「特集:太平記」を刊行した。これを読んでみたいと思った。
持っている本として、すでに本棚にある本では、
兵藤裕己.『太平記〈よみ〉の可能性』(講談社学術文庫).講談社.2005
若尾政希.『「太平記読み」の時代』(平凡社ライブラリー).平凡社.2012
などがある。これらの本も、読んでおきたいと思ったこともある。
『太平記』であるが……若いころ、岩波の古典大系本で、手にとったことはある。そのとき……若い時……どうにも退屈な物語だなと感じたのが正直なところ。しかし、この歳になって、新しい岩波文庫で読んでみて、こんなにも面白い物語だったのかと認識を新たにしたところがある。
出てくる武将たちの行動、精神、それをとりまく大きな歴史のながれ……これらが、実に興味深い。とにかく読んでいて面白いのである。
それは、一つには、出てくる文章の装飾的な引用など、和漢の故事に言及したところが多いのだが、これらについて、これまでの勉強で、どこかで見たことがあるものが多くなってきたということもあるのかと思う。この故事や引用は、見た記憶ががある、というものが多くなってきた。また、同時に、そのような引用があっても、特にその典拠を原典にあたって調べながら読もうという気が、もうなくなってしまった、ということもある。ただ、読んで楽しみたい、そのように思って読むようになった。
第一冊目(第一巻から第八巻をおさめる)を読んで思うことは次の二点ぐらいだろうか。
第一に、登場人物……主に武士であるが……の、行動の根底にあるもの……エトスと言ってもいいだろうか……が、面白い。非常に功利的、実利的に判断して行動している面がある。その一方で、忠義という理念のために行動する、戦う、自害する。また、さまざまに計略をめぐらす。これらの武士の行動が、躍動的である。
第二に、これは、『平家物語』などと比べての印象になるのだが……登場人物たちの行動が、論理的という印象をもつ。これは、現代の人間の論理とは異なるのは無論だが、『平家物語』や『今昔物語集』などの登場人物に比べて見るならば、格段に論理的な判断力と、説明がある。これは、やはり、一四世紀、中世も後半になって、人びとのものの考え方が変わってきたな、と思わせるところがある。だからといって、その人びとの行動規範に、素直に共感できるというのではない。やはり、そこは、時代の隔たりというものを感じる。
以上の二点が、第一冊を読んで思うことなどである。
『平家物語』も、二〇一九年になってから改めて全巻を通して読んだ。岩波文庫で四冊。これを思い返してみると、『平家物語』は、まだ、どこか「もののあはれ」を感じさせる文学である。だが、『太平記』には、それが無い。このあたりも、時代の流れ、潮流というものを感じる。
ところで、『太平記』は、近世から近代……戦前……までは、広く読まれた作品であるが、近年は、あまり読まれないようだ。これも、「古典」とは何であるかという問題とも関連して、考えてみたいことのひとつである。
2019年12月7日記






最近のコメント