『頼むから静かにしてくれ Ⅱ』レイモンド・カーヴァー/村上春樹(訳) ― 2020-02-01
2020-02-01 當山日出夫(とうやまひでお)

レイモンド・カーヴァー.村上春樹(訳).『頼むから静かにしてくれ Ⅱ』(村上春樹翻訳ライブラリー).中央公論新社.2006
http://www.chuko.co.jp/tanko/2006/03/403496.html
続きである。
やまもも書斎記 2020年1月25日
『頼むから静かにしてくれ Ⅰ』レイモンド・カーヴァー/村上春樹(訳)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/01/25/9206094
レイモンド・カーヴァーの短篇集。村上春樹訳で、その後半である。
読んで一番感銘がふかいのは、表題作の「頼むから静かにしてくれ」かなと思う。レイモンド・カーヴァーの作品は、どれも特に波瀾万丈の大活劇があるというものではない。ごく普通の人びとの、ごく普通の生活のなかでの、あるときのふとした出来事を印象的に描いている。どの作品も、読み始めて、その文学的世界にはいっていく。あたりまえのような日常世界のなかで、あるときに感じる、人生の影のようなものを描いているといっていいだろうか。
また、これは、特に村上春樹が訳しているからということを意識するせいなのかもしれないが、その文学的感銘は、村上春樹の作品……特にその短篇……と、共鳴するところがあるように感じてしまう。
この本、二冊目は、解題(村上春樹)から読んだのであるが、これを読むと、レイモンド・カーヴァーの作品の解説としてすぐれているだけではなく、広く文学一般の理解として、村上春樹はきわだった読み手であると感じさせるところがある。このようなアメリカ現代文学の日本への紹介者として、この面をとりあげるだけでも、その功績は大なるものがあるだろう。
レイモンド・カーヴァーの作品は、また機会をつくって、改めて読みなおしてみたいと思っている。
http://www.chuko.co.jp/tanko/2006/03/403496.html
続きである。
やまもも書斎記 2020年1月25日
『頼むから静かにしてくれ Ⅰ』レイモンド・カーヴァー/村上春樹(訳)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/01/25/9206094
レイモンド・カーヴァーの短篇集。村上春樹訳で、その後半である。
読んで一番感銘がふかいのは、表題作の「頼むから静かにしてくれ」かなと思う。レイモンド・カーヴァーの作品は、どれも特に波瀾万丈の大活劇があるというものではない。ごく普通の人びとの、ごく普通の生活のなかでの、あるときのふとした出来事を印象的に描いている。どの作品も、読み始めて、その文学的世界にはいっていく。あたりまえのような日常世界のなかで、あるときに感じる、人生の影のようなものを描いているといっていいだろうか。
また、これは、特に村上春樹が訳しているからということを意識するせいなのかもしれないが、その文学的感銘は、村上春樹の作品……特にその短篇……と、共鳴するところがあるように感じてしまう。
この本、二冊目は、解題(村上春樹)から読んだのであるが、これを読むと、レイモンド・カーヴァーの作品の解説としてすぐれているだけではなく、広く文学一般の理解として、村上春樹はきわだった読み手であると感じさせるところがある。このようなアメリカ現代文学の日本への紹介者として、この面をとりあげるだけでも、その功績は大なるものがあるだろう。
レイモンド・カーヴァーの作品は、また機会をつくって、改めて読みなおしてみたいと思っている。
2020年1月30日記
『スカーレット』あれこれ「涙のち晴れ」 ― 2020-02-02
2020-02-02 當山日出夫(とうやまひでお)
『スカーレット』第17週「涙のち晴れ」
https://www.nhk.or.jp/scarlet/story/index17_200127.html
前回は、
やまもも書斎記 2020年1月26日
『スカーレット』あれこれ「熱くなる瞬間」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/01/26/9206544
この週の見どころは、次の二点かなと思う。
第一に、喜美子の執念。
穴窯での陶芸に、喜美子は再度、再々度、こころみるが失敗におわる。それでも、喜美子はあきらめらないようだ。八郎は、そんな喜美子に愛想をつかしたかのようである。家を出ていってしまう。それでも、まだ、喜美子は穴窯での陶芸に執念を見せる。
このあたりの喜美子の陶芸への執念が、これからの喜美子の根底にあることになるのだろう。
第二、その挫折した喜美子を救う、荒木荘の人びと。
穴窯に挫折した喜美子は、大阪に出る。ちや子さんに会うためである。そこで、ちや子さんのみならず、雄太郎さん(信楽太郎)とも、また、大久保さんとも出会う。さらに、さえずりのマスターも登場していた。そして、大久保さんは言う……家事のできる人間なら何でもできる、と。
これらの人びとの再開を通じて、喜美子はさらに陶芸家としての道を進むことを決意したようだ。
以上の二点が、この週のみどころかと思ってみていた。
さらに書いてみるならば、弟子の三津は、喜美子と八郎のもとを去っていった。特に、八郎との間に何があったということでもないのだが、しかし、喜美子の家族の和をみだしてはいけないと、自ら身をひいたという感じであった。
それから、その喜美子をとりまく信楽の人びと……照子、信作、百合子、それから、母親など、これらの人びとのことが、じんわりと描かれていたように思う。
次週、喜美子はさらに陶芸の道に邁進することになるようだ。楽しみに見ることにしよう。
『スカーレット』第17週「涙のち晴れ」
https://www.nhk.or.jp/scarlet/story/index17_200127.html
前回は、
やまもも書斎記 2020年1月26日
『スカーレット』あれこれ「熱くなる瞬間」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/01/26/9206544
この週の見どころは、次の二点かなと思う。
第一に、喜美子の執念。
穴窯での陶芸に、喜美子は再度、再々度、こころみるが失敗におわる。それでも、喜美子はあきらめらないようだ。八郎は、そんな喜美子に愛想をつかしたかのようである。家を出ていってしまう。それでも、まだ、喜美子は穴窯での陶芸に執念を見せる。
このあたりの喜美子の陶芸への執念が、これからの喜美子の根底にあることになるのだろう。
第二、その挫折した喜美子を救う、荒木荘の人びと。
穴窯に挫折した喜美子は、大阪に出る。ちや子さんに会うためである。そこで、ちや子さんのみならず、雄太郎さん(信楽太郎)とも、また、大久保さんとも出会う。さらに、さえずりのマスターも登場していた。そして、大久保さんは言う……家事のできる人間なら何でもできる、と。
これらの人びとの再開を通じて、喜美子はさらに陶芸家としての道を進むことを決意したようだ。
以上の二点が、この週のみどころかと思ってみていた。
さらに書いてみるならば、弟子の三津は、喜美子と八郎のもとを去っていった。特に、八郎との間に何があったということでもないのだが、しかし、喜美子の家族の和をみだしてはいけないと、自ら身をひいたという感じであった。
それから、その喜美子をとりまく信楽の人びと……照子、信作、百合子、それから、母親など、これらの人びとのことが、じんわりと描かれていたように思う。
次週、喜美子はさらに陶芸の道に邁進することになるようだ。楽しみに見ることにしよう。
2020年2月1日記
追記 2020-02-09
この続きは、
やまもも書斎記 2020年2月9日
『スカーレット』あれこれ「炎を信じて」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/02/09/9211772
この続きは、
やまもも書斎記 2020年2月9日
『スカーレット』あれこれ「炎を信じて」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/02/09/9211772
『太平記』岩波文庫(三) ― 2020-02-03
2020-02-03 當山日出夫(とうやまひでお)

兵藤裕己(校注).『太平記』(三)(岩波文庫).岩波書店.2015
https://www.iwanami.co.jp/book/b245754.html
続きである。
やまもも書斎記 2020年1月27日
『太平記』岩波文庫(二)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/01/27/9206987
岩波文庫で三冊目まで読んだ。ここまで読んできて、ようやく「歴史」という感覚で読めるようになったかと思う。
『太平記』は、一般には、文学史的には、軍記物というジャンルになる。その叙述のほとんどの部分が、合戦場面である。その戦闘の様子であり、あるいは、戦場におけるかけひきであったり、裏切りであったり、逆に、忠節であったりする。
これも、あまり同じような記述がつづくと、途中で飽きてくる。が、この三冊目になって、楠木正成が死に、新田義貞が死に、さらには、後醍醐天皇の崩御が語られる。これらのできごとを追って読んでくると、この長大な物語が、ようやく「歴史」を語っているのであるといことが、感じ取れるようになってくる。
近世から近代にかけて、『太平記』は「歴史」を語った書物として受容されてきたということがある。だからこそ、近代的な歴史学の登場にあたって、『太平記』の「史料」としての側面が注目されることになる。史料的価値の有無が判断されるようになった。
だが、今日においては、「近代の歴史学」という学問自体が、まさに「歴史」の所産であることを認識することができよう。この意味において、『太平記』の語った「歴史」を、新たな視点から、再構築して見ることができるのかもしれない。
それから、この本を、ただ楽しみのために読んでいるとはいっても、どうしても国語学、日本語学的なことで気になるところがないではない。いくつかのことばについては、時折、辞書(ジャパンナレッジ、日本国語大辞典)を検索しながら読んだ。そのなかで、特に「機」ということばの意味、用法が、注目される。これは、『太平記』における「機」ということで、改めて調べてみれば、いろいろ面白いことが分かるかもしれないと思って読んだ。
また、『太平記』は、あきらかに『平家物語』を意識して書いてあることが分かる。『太平記』を読み終えたら、『平家物語』を、再々度、読みなおしておきたいと思う。
続けて、岩波文庫の第四冊目である。
2020年1月18日記
『麒麟がくる』あれこれ「美濃の国」 ― 2020-02-04
2020-02-04 當山日出夫(とうやまひでお)
『麒麟がくる』第三回「美濃の国」
https://www.nhk.or.jp/kirin/story/3.html
前回は、
やまもも書斎記 2020年1月28日
『麒麟がくる』あれこれ「道三の罠」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/01/28/9207333
この回で描いていたのは、戦国の武将たちの権謀術数といっていいだろうか。
美濃の国の支配権をめぐって、土岐頼芸と斉藤道三の確執、さらに、斎藤道三とその子どもの高政との関係。その美濃に対しては、尾張の織田が関心をしめし、さらには、東からは今川がやってくる。このような状況のなかで、このドラマの主人公である明智光秀は、どのような生き方を選ぶことになるのだろうか。
武士としての忠誠心ということならば、主君筋である土岐に対してということになる。だが、その土岐の家も一つにはまとまっていない。そして、まだドラマには登場してこないが、いずれ、足利将軍も出てくれば、織田信長も出てくるであろう。そのような登場人物たちのなかで、光秀の生きる道はどのようなものなっていくのであろうか。
ところで、この回を見て思ったことであるが……この『麒麟がくる』では、女性の登場人物について、特に違和感の無い限り、床に座るとき立て膝で座るように演出しているようである。深芳野が化粧をする場面がそうであったし、また、斎藤の屋敷でのシーンでもそうだった。帰蝶も傷の手当ての場面では、立て膝だった。(これは、時代考証としては、立て膝で座るのがあっていると思う。)
また、このドラマには、架空の登場人物も出てくる。駒がそうであるし、菊丸もそうである。これら、武士ではない人間……いわば庶民といってもいいだろうか……のつかうことばが、ちょっと気になる。武士ではないから、(時代劇語としての)武士ことばはつかっていない。だが、その地方の方言というのでもない。現代の標準的な日本語に近い。だが、特に、その社会的階層を意識させるようなことばはつかっていない。
それから気のついたこととしては、この回では「国衆」ということばが出てきていた。「国衆」を軸にしたドラマとしては、以前の『真田丸』がある。さて、これから、光秀が生きていくなかで、「国衆」としてどのような生き方を模索することになるのであろうか。
強大な戦国大名たちが覇権をあらそう時代において、光秀は自分の生き方を考えていくことになるのだろう。次回は、尾張が舞台になるようだ。楽しみにみることにしよう。
2020年2月3日記
『麒麟がくる』第三回「美濃の国」
https://www.nhk.or.jp/kirin/story/3.html
前回は、
やまもも書斎記 2020年1月28日
『麒麟がくる』あれこれ「道三の罠」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/01/28/9207333
この回で描いていたのは、戦国の武将たちの権謀術数といっていいだろうか。
美濃の国の支配権をめぐって、土岐頼芸と斉藤道三の確執、さらに、斎藤道三とその子どもの高政との関係。その美濃に対しては、尾張の織田が関心をしめし、さらには、東からは今川がやってくる。このような状況のなかで、このドラマの主人公である明智光秀は、どのような生き方を選ぶことになるのだろうか。
武士としての忠誠心ということならば、主君筋である土岐に対してということになる。だが、その土岐の家も一つにはまとまっていない。そして、まだドラマには登場してこないが、いずれ、足利将軍も出てくれば、織田信長も出てくるであろう。そのような登場人物たちのなかで、光秀の生きる道はどのようなものなっていくのであろうか。
ところで、この回を見て思ったことであるが……この『麒麟がくる』では、女性の登場人物について、特に違和感の無い限り、床に座るとき立て膝で座るように演出しているようである。深芳野が化粧をする場面がそうであったし、また、斎藤の屋敷でのシーンでもそうだった。帰蝶も傷の手当ての場面では、立て膝だった。(これは、時代考証としては、立て膝で座るのがあっていると思う。)
また、このドラマには、架空の登場人物も出てくる。駒がそうであるし、菊丸もそうである。これら、武士ではない人間……いわば庶民といってもいいだろうか……のつかうことばが、ちょっと気になる。武士ではないから、(時代劇語としての)武士ことばはつかっていない。だが、その地方の方言というのでもない。現代の標準的な日本語に近い。だが、特に、その社会的階層を意識させるようなことばはつかっていない。
それから気のついたこととしては、この回では「国衆」ということばが出てきていた。「国衆」を軸にしたドラマとしては、以前の『真田丸』がある。さて、これから、光秀が生きていくなかで、「国衆」としてどのような生き方を模索することになるのであろうか。
強大な戦国大名たちが覇権をあらそう時代において、光秀は自分の生き方を考えていくことになるのだろう。次回は、尾張が舞台になるようだ。楽しみにみることにしよう。
2020年2月3日記
追記 2020-02-11
この続きは、
やまもも書斎記 2020年2月11日
『麒麟がくる』あれこれ「尾張潜入指令」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/02/11/9212461
この続きは、
やまもも書斎記 2020年2月11日
『麒麟がくる』あれこれ「尾張潜入指令」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/02/11/9212461
梅の花芽 ― 2020-02-05
2020-02-05 當山日出夫(とうやまひでお)
水曜日なので花の写真。今日は梅の木である。その花がさく前の姿を撮ってみた。
前回は、
やまもも書斎記 2020年1月29日
センリョウ
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/01/29/9207722
この梅の木については、以前にも写している。
やまもも書斎記 2020年1月15日
梅の冬芽
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/01/15/9202194
このところ、毎朝、この木を見ている。今年は暖かいせいだろうか、例年よりも花が早く咲きそうな感じである。冬芽というのではないが、まだ、花が咲く前のつぼみというのでもない。このような状態をなんといえばいいのか。とりあえず花芽といってみる。
だんだんと冬芽がふくらんできて、花びらのように外側が変化してくる。そのまんなかあたりが、赤くなって見える。見ると星のかたちになって五弁の花びらがあるように見える。もうちょっとするとさらにふくらんできて、つぼみといっていいようになる。ただ、この梅は八重咲きである。このさき、花が咲いたときには、またさらに写してみようと思っている。
使ったレンズは、タムロンの90ミリである。今年になってから、外に出て植物の写真を撮るには、ほとんどこのレンズをつかっている。
水曜日なので花の写真。今日は梅の木である。その花がさく前の姿を撮ってみた。
前回は、
やまもも書斎記 2020年1月29日
センリョウ
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/01/29/9207722
この梅の木については、以前にも写している。
やまもも書斎記 2020年1月15日
梅の冬芽
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/01/15/9202194
このところ、毎朝、この木を見ている。今年は暖かいせいだろうか、例年よりも花が早く咲きそうな感じである。冬芽というのではないが、まだ、花が咲く前のつぼみというのでもない。このような状態をなんといえばいいのか。とりあえず花芽といってみる。
だんだんと冬芽がふくらんできて、花びらのように外側が変化してくる。そのまんなかあたりが、赤くなって見える。見ると星のかたちになって五弁の花びらがあるように見える。もうちょっとするとさらにふくらんできて、つぼみといっていいようになる。ただ、この梅は八重咲きである。このさき、花が咲いたときには、またさらに写してみようと思っている。
使ったレンズは、タムロンの90ミリである。今年になってから、外に出て植物の写真を撮るには、ほとんどこのレンズをつかっている。
Nikon D500
TAMRON SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD
2020年2月4日記
『陽暉楼』宮尾登美子 ― 2020-02-06
2020-02-06 當山日出夫(とうやまひでお)

この作品は、再読になる。映画も見たと憶えている。探せば古い本がみつかるかとも思うが、新しい中公文庫版を買って読んだ。正直、読み始めるまえ、どうしようかと思った。一度読んでいるし、もう一回読むのも手間かな、という気もしないではなかった。しかし、読み終えたあとでは、やはり、この作品を読んでよかったと感じる。(ただ、本文の字が小さいのがつらかった。もう老眼である。)
『陽暉楼』を読んで思うことを書くならば次の二点。
第一には、昭和戦前の土佐の芸妓の世界。
芸妓のことを描いた作品である。小説は「保名」の踊りのシーンからはじまる。主人公は房子。芸妓……ただ、本文には、この語に「げいしゃ」のルビをつけた箇所がある……である。表向きは、芸で身を立てていることになる。その仕事の舞台を提供しているのが、陽暉楼という、妓楼というか、料亭というか、である。
踊りの稽古の場面とか、芸妓の日常生活、毎日の様子、一年の年中行事などが、こまやかな筆致で描かれる。表向きには華やかの芸妓の世界、お座敷の様子が、重厚で緻密な文章でつづってある。読みながら、このような芸の世界が昔はあったのか、と思う。
第二は、その世界の実情。
芸妓の世界といっても、これを、現代の価値観で表現するならば、人身売買であり、売春の横行する世界である。借金でがんじがらめされて、行動の自由をうばわれた芸妓。また、客がのぞむならば、その夜の相手もしなければならない。
この二つのことが、からまりあって物語は進行する。人身売買と売春の世界といってみたが、この作品には、そのことを、現代の価値基準から糾弾するようなところはない。ただ、そのような人びとの世界があり、そこに生きて、生活していた、多くの女性たち、また、男性たちがいた、このことを、情感を込めて描いている。そして、それは、もはや今のわれわれからすれば、失ってしまったものでもある。そこには、そこはかとない哀惜の情を感じるところもある。
とはいえ、この小説は、房子という芸妓の生涯……それは、今日の目からみれば残酷で不幸なものであるといえるかもしれないが……を、高知の陽暉楼という店においてくりひろげられる人間模様をからめながら、情緒をこめて描いている。芸妓という、いわば特殊な職業のことを描きながら、そこにあるのは、市井の人びとに共通する情感である。
この小説が、これからも読まれていくとするならば、一つには、昭和戦前の土佐の妓楼における人間ドラマとしてであり、さらには、そこから感じ取ることができる人間の情愛……芸にかける心意気であったり、家族の気持ちであったり、朋輩への思いやりであったり、あるいは、恋であったり、子どもへの思いであったり……さまざまな人間の情感を、こまやかで落ち着いた文章でつづってある……への共感においてであろう。
まさに宮尾登美子でなければ書けなかった小説であることを強く感じる。
2020年1月2日記
『陽暉楼』を読んで思うことを書くならば次の二点。
第一には、昭和戦前の土佐の芸妓の世界。
芸妓のことを描いた作品である。小説は「保名」の踊りのシーンからはじまる。主人公は房子。芸妓……ただ、本文には、この語に「げいしゃ」のルビをつけた箇所がある……である。表向きは、芸で身を立てていることになる。その仕事の舞台を提供しているのが、陽暉楼という、妓楼というか、料亭というか、である。
踊りの稽古の場面とか、芸妓の日常生活、毎日の様子、一年の年中行事などが、こまやかな筆致で描かれる。表向きには華やかの芸妓の世界、お座敷の様子が、重厚で緻密な文章でつづってある。読みながら、このような芸の世界が昔はあったのか、と思う。
第二は、その世界の実情。
芸妓の世界といっても、これを、現代の価値観で表現するならば、人身売買であり、売春の横行する世界である。借金でがんじがらめされて、行動の自由をうばわれた芸妓。また、客がのぞむならば、その夜の相手もしなければならない。
この二つのことが、からまりあって物語は進行する。人身売買と売春の世界といってみたが、この作品には、そのことを、現代の価値基準から糾弾するようなところはない。ただ、そのような人びとの世界があり、そこに生きて、生活していた、多くの女性たち、また、男性たちがいた、このことを、情感を込めて描いている。そして、それは、もはや今のわれわれからすれば、失ってしまったものでもある。そこには、そこはかとない哀惜の情を感じるところもある。
とはいえ、この小説は、房子という芸妓の生涯……それは、今日の目からみれば残酷で不幸なものであるといえるかもしれないが……を、高知の陽暉楼という店においてくりひろげられる人間模様をからめながら、情緒をこめて描いている。芸妓という、いわば特殊な職業のことを描きながら、そこにあるのは、市井の人びとに共通する情感である。
この小説が、これからも読まれていくとするならば、一つには、昭和戦前の土佐の妓楼における人間ドラマとしてであり、さらには、そこから感じ取ることができる人間の情愛……芸にかける心意気であったり、家族の気持ちであったり、朋輩への思いやりであったり、あるいは、恋であったり、子どもへの思いであったり……さまざまな人間の情感を、こまやかで落ち着いた文章でつづってある……への共感においてであろう。
まさに宮尾登美子でなければ書けなかった小説であることを強く感じる。
2020年1月2日記
『一絃の琴』宮尾登美子 ― 2020-02-07
2020-02-07 當山日出夫(とうやまひでお)
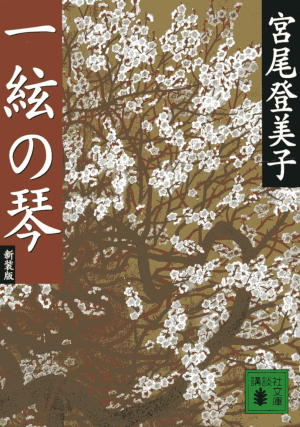
宮尾登美子.『一絃の琴』(講談社文庫).講談社.2008(講談社.1978)
http://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000137809
続きである。
やまもも書斎記 2020年2月6日
『陽暉楼』宮尾登美子
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/02/06/9210721
宮尾登美子は、この作品で直木賞をとった。
だが、そんなことは、今ではもうどうでもいいことのように思える。直木賞作品というようなことからは独立して、この作品は生き続けてきている。読まれ続けてきている。講談社文庫でも、1982年に刊行している。それを改版して文字を大きくしたものが、今の本である。
宮尾登美子の文学作品は、伝統的な芸事に題材をとったものが多い。この意味では、『きのね』などの系譜に属するといえるだろう。
ただ、私は、宮尾登美子の作品の特質、なかんずく直木賞をとったこの作品には、次のことを読みとっておきたいと思う。
第一には、人間の生老病死を冷静にみつめるまなざしであり、そこからうまれる喜怒哀楽のさまざまな情感を、きめこまやかに描いている。特に、老いと、病、とか、死とか、普通の人間が生きている限りさけてとおることのできないことについて、冷酷なまでに、心の奥底にまでわけいって描いている。
第二には、その人間の心の奥底にある、影のようなものである。たしかに宮尾登美子の作品の登場人物は、がんばっている。だが、そのがんばりのこころの奥底には、なにかしら影がある。場合によっては、それは競争心のようなものであったり、嫉妬であったりもする。
以上の二つの点において、宮尾登美子の文学作品は、普遍性を獲得しているといっていいだろうと思う。
一般に、宮尾登美子の作品を評して、がんばっている女性を描いたという意味のことがいわれる。文庫本などの解説はたいていそうである。たしかに、これまで、読んできた作品(再読をふくむ)においては、主人公の女性は、がんばっている。『蔵』の烈しかり、『陽暉楼』の房子しかりである。
しかし、宮尾登美子の作品に感じるのは、主人公の女性のがんばり、苦労、だけではない。その生き方にともなう、人生のさまざまな場面での情感……それには、時として邪悪とでもいうべき心情もふくまれる……を、きめこまやかに丁寧に描いていることが、魅力として感じるところである。
さらに、蛇足で書くと、この作品は、再読である。今回、この作品を読みなおしてみるまで、寺田寅彦が高知出身であるという認識がなかった。この作品をみて、あらためて、寺田寅彦の出身地を知った。
それから、以前、この作品を読んだのは、わかいときのこと、単行本でだったか、文庫本でだったか、もうわすれてしまっている。今、新しい文庫本で読んでみて、「一絃琴」の音色が気になった。今は、便利な時代である。YouTubeで「一弦琴」で検索すると、その演奏の映像と音楽が、パソコンで見ることができる。なるほど、こういう音の楽器だったのか、こんな音楽だったのか、興味深いものがあった。
2020年1月4日記
『伽羅の香』宮尾登美子 ― 2020-02-08
2020-02-08 當山日出夫(とうやまひでお)

宮尾登美子.『伽羅の香』(中公文庫).中央公論新社.1984(1996.改版)
http://www.chuko.co.jp/bunko/1996/07/202641.html
続きである。
やまもも書斎記 2020年2月7日
『一絃の琴』宮尾登美子
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/02/07/9211091
この作品は再読だと思う。が、以前に読んだときのことは、もうすっかり忘れてしまっている。新たな気持ちで最初から読んだ。
読み始めてしばらくはちょっと退屈である。三重の山奥、炭焼きをいとなむ素封家の家に生まれた葵。その成長のものがたりがしばらくつづく。葵は、ふとしたことから香道にひきよせられる。その香道のことも興味深いのであるが、小説が面白くなるのは、半分ほど読んだあたりからだろうか。
子どもの死、それに夫の死、さらに、その後の判明する夫の不倫……華麗な香道の世界に君臨するかの主人公、葵、その心のうちは、黒いほむらでもえさかる。葵は一途である……他の宮尾登美子の作品のヒロインと同様に……しかし、その一途な心には、かならず影の部分がある。その影の部分を、この作品は丁寧におっていく。
また、この小説でも描かれているのが、「老、病、死」といった、人間として生きていく限り避けられないことなど。ひょっとして、現代の小説において、人間の「老、病、死」について、宮尾登美子ほど、細やかな筆づかいで語っている小説家はないのかもしれない。
宮尾登美子の作品の魅力は、ヒロインの頑張りでもある。だが、その頑張りによりそう心の影の部分に、読んで、より心をひかれる。そこには、人間というものを描く普遍性がある。
若いときに読んだ宮尾登美子の作品は、そのヒロインの頑張りに魅力を感じたものである。しかし、この年になってから再読していくと、人間としての影の部分、あるいは、強いて言うならば、心のうちにある邪悪なもの……それを冷静に見つめる落ち着いた文章のはこびに、魅力を感じるようになってきている。
ここしばらくは、宮尾登美子の作品を読んでいきたいと思う。
2020年1月13日記
http://www.chuko.co.jp/bunko/1996/07/202641.html
続きである。
やまもも書斎記 2020年2月7日
『一絃の琴』宮尾登美子
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/02/07/9211091
この作品は再読だと思う。が、以前に読んだときのことは、もうすっかり忘れてしまっている。新たな気持ちで最初から読んだ。
読み始めてしばらくはちょっと退屈である。三重の山奥、炭焼きをいとなむ素封家の家に生まれた葵。その成長のものがたりがしばらくつづく。葵は、ふとしたことから香道にひきよせられる。その香道のことも興味深いのであるが、小説が面白くなるのは、半分ほど読んだあたりからだろうか。
子どもの死、それに夫の死、さらに、その後の判明する夫の不倫……華麗な香道の世界に君臨するかの主人公、葵、その心のうちは、黒いほむらでもえさかる。葵は一途である……他の宮尾登美子の作品のヒロインと同様に……しかし、その一途な心には、かならず影の部分がある。その影の部分を、この作品は丁寧におっていく。
また、この小説でも描かれているのが、「老、病、死」といった、人間として生きていく限り避けられないことなど。ひょっとして、現代の小説において、人間の「老、病、死」について、宮尾登美子ほど、細やかな筆づかいで語っている小説家はないのかもしれない。
宮尾登美子の作品の魅力は、ヒロインの頑張りでもある。だが、その頑張りによりそう心の影の部分に、読んで、より心をひかれる。そこには、人間というものを描く普遍性がある。
若いときに読んだ宮尾登美子の作品は、そのヒロインの頑張りに魅力を感じたものである。しかし、この年になってから再読していくと、人間としての影の部分、あるいは、強いて言うならば、心のうちにある邪悪なもの……それを冷静に見つめる落ち着いた文章のはこびに、魅力を感じるようになってきている。
ここしばらくは、宮尾登美子の作品を読んでいきたいと思う。
2020年1月13日記
『スカーレット』あれこれ「炎を信じて」 ― 2020-02-09
2020-02-09 當山日出夫(とうやまひでお)
『スカーレット』第18週「炎を信じて」
https://www.nhk.or.jp/scarlet/story/index18_200203.html
前回は、
やまもも書斎記 2020年2月2日
『スカーレット』あれこれ「涙のち晴れ」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/02/02/9209362
このドラマは、女性陶芸家としての喜美子の活躍、奮闘、苦労といったものはあまり描かない方針のようだ。それよりも、一人の人間として、妻として、母として、どう家族と生きることになるのか、こういったところをじっくりと描くことになっている。
この週で描いていたこととしては、次の二点を思ってみる。
第一に、女性陶芸家としての成功。長期間にわたって火をたき続けることで、ようやくのことで喜美子は自分の思っていたとおりの色を出すことができた。
たぶん、普通のドラマの作り方であれば、このあたりのことをクライマックスにもってきて、もっとドラマチックに描くところだろうと思う。それを、このドラマでは、非常にあっさりとした描写であった。つまり、女性の陶芸家として名をなすということは、ドラマの筋の一つではあるのだが、本筋ではないと理解していいのだろう。
第二に、陶芸家として成功した喜美子のその後の日常。陶芸家としては成功したことになるのだが、しかし、その一方で、夫の八郎とはわかれることになってしまう。喜美子のもとには、子どもの武志が残る。
その武志との生活を描いたのが、この週の終わりであった。武志は、京都の美大をめざし陶芸家になるという。そこに、かつての夫であり、武志の父である八郎の助言があったようだ。八郎と武志は、おたがいに縁が切れることなく連絡をとりあっていた。父と子である。
しかし、喜美子とは、分かれたきりである。喜美子は、しみじみと思うことになる。大切なものをうしなってしまったのである、と。
以上の二点が、この週を見ていて思うことなどである。
得てして、朝ドラでは、「女性の……」ということで、その苦労話を描くことが多い。このドラマも、女性陶芸家の草別としての存在がないではない。だが、そのことよりも、一人の人間としてどのように生きていくことになるのか、このことの方を軸に描いていると感じる。これは、あるいは、朝ドラとしては、新しい流れの作り方ではないかと思って見ている。
これからの喜美子の生き方をどう描くことになるのか、次週以降を楽しみに見ることにしよう。
2020年2月8日記
『スカーレット』第18週「炎を信じて」
https://www.nhk.or.jp/scarlet/story/index18_200203.html
前回は、
やまもも書斎記 2020年2月2日
『スカーレット』あれこれ「涙のち晴れ」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/02/02/9209362
このドラマは、女性陶芸家としての喜美子の活躍、奮闘、苦労といったものはあまり描かない方針のようだ。それよりも、一人の人間として、妻として、母として、どう家族と生きることになるのか、こういったところをじっくりと描くことになっている。
この週で描いていたこととしては、次の二点を思ってみる。
第一に、女性陶芸家としての成功。長期間にわたって火をたき続けることで、ようやくのことで喜美子は自分の思っていたとおりの色を出すことができた。
たぶん、普通のドラマの作り方であれば、このあたりのことをクライマックスにもってきて、もっとドラマチックに描くところだろうと思う。それを、このドラマでは、非常にあっさりとした描写であった。つまり、女性の陶芸家として名をなすということは、ドラマの筋の一つではあるのだが、本筋ではないと理解していいのだろう。
第二に、陶芸家として成功した喜美子のその後の日常。陶芸家としては成功したことになるのだが、しかし、その一方で、夫の八郎とはわかれることになってしまう。喜美子のもとには、子どもの武志が残る。
その武志との生活を描いたのが、この週の終わりであった。武志は、京都の美大をめざし陶芸家になるという。そこに、かつての夫であり、武志の父である八郎の助言があったようだ。八郎と武志は、おたがいに縁が切れることなく連絡をとりあっていた。父と子である。
しかし、喜美子とは、分かれたきりである。喜美子は、しみじみと思うことになる。大切なものをうしなってしまったのである、と。
以上の二点が、この週を見ていて思うことなどである。
得てして、朝ドラでは、「女性の……」ということで、その苦労話を描くことが多い。このドラマも、女性陶芸家の草別としての存在がないではない。だが、そのことよりも、一人の人間としてどのように生きていくことになるのか、このことの方を軸に描いていると感じる。これは、あるいは、朝ドラとしては、新しい流れの作り方ではないかと思って見ている。
これからの喜美子の生き方をどう描くことになるのか、次週以降を楽しみに見ることにしよう。
2020年2月8日記
追記 2020-02-16
この続きは、
やまもも書斎記 2020年2月16日
『スカーレット』あれこれ「春は出会いの季節」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/02/16/9214394
この続きは、
やまもも書斎記 2020年2月16日
『スカーレット』あれこれ「春は出会いの季節」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/02/16/9214394
『太平記』岩波文庫(四) ― 2020-02-10
2020-02-10 當山日出夫(とうやまひでお)

兵藤裕己(校注).『太平記』(四)(岩波文庫).岩波書店.2015
https://www.iwanami.co.jp/book/b245755.html
続きである。
やまもも書斎記 2020年2月3日
『太平記』岩波文庫(三)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/02/03/9209750
岩波文庫版で四冊目である。巻二十二が欠巻で、二十三から二十九までをおさめる。
歴史的には、吉野の炎上から、高師直の死までを描くことになる。が、この四冊目を読んで、私にとって興味深いのは、怪異とでもいうべき部分である。楠正成の亡霊が登場する。また、天狗も出てくる。さらには、「未来記」についての記述もある。
おそらく、狭義の「歴史学」という分野においては、切って棄てる部分になるにちがいない。しかし、私は、これこそ、中世の人々の世界だと感じる。『太平記』という書物が、「歴史学」に意味のあるものなのかどうか、これは明治以降において議論のあるところであることは承知しているつもりでいる。この意味において、無意味と捨て去られるような部分においてこそ、私は、『太平記』という「物語」の成立の意味を感じとる。
これは、私の勉強してきたことが、歴史学の周辺にはあっても、狭義の歴史学ではなかったことによるものかと思う。学生のころに、折口信夫や柳田国男を読んだ。いわゆる民俗学につらなる国文学の系譜である。このような視点をおいて見るならば、歴史学から排除されるような部分にこそ、まさに、このような精神世界に中世の人々が生きていた、その息づかいのようなものを感じるのである。
また、国語学、日本語学の分野から見ても興味深い。各種のことばの意味、用法、語法などにおいて、これを用例をあつめて考えてみれば、面白い研究ができるだろう、というところがいくつも目につく。だが、残念ながら、この岩波文庫本は、古本系統の「西源院本」をつかっているのだが、その表記などについては、かなり改めた校訂になっている。そうはいっても、この文庫の本文を見るだけでも、いろいろ興味の種はつきない。
もう私自身としても、国語学、日本語学という研究の分野から引退しようかと思う。これを追求して論文を書いてみたりしようという気にはならないでいる。だが、国語学、日本語学的に見て興味深いものであることは、読みながら思うところである。
ようやく後期の講義も、後は試験を残すのみとなった。つづけて、五冊目を読むことにしたい。
2020年1月28日記
https://www.iwanami.co.jp/book/b245755.html
続きである。
やまもも書斎記 2020年2月3日
『太平記』岩波文庫(三)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/02/03/9209750
岩波文庫版で四冊目である。巻二十二が欠巻で、二十三から二十九までをおさめる。
歴史的には、吉野の炎上から、高師直の死までを描くことになる。が、この四冊目を読んで、私にとって興味深いのは、怪異とでもいうべき部分である。楠正成の亡霊が登場する。また、天狗も出てくる。さらには、「未来記」についての記述もある。
おそらく、狭義の「歴史学」という分野においては、切って棄てる部分になるにちがいない。しかし、私は、これこそ、中世の人々の世界だと感じる。『太平記』という書物が、「歴史学」に意味のあるものなのかどうか、これは明治以降において議論のあるところであることは承知しているつもりでいる。この意味において、無意味と捨て去られるような部分においてこそ、私は、『太平記』という「物語」の成立の意味を感じとる。
これは、私の勉強してきたことが、歴史学の周辺にはあっても、狭義の歴史学ではなかったことによるものかと思う。学生のころに、折口信夫や柳田国男を読んだ。いわゆる民俗学につらなる国文学の系譜である。このような視点をおいて見るならば、歴史学から排除されるような部分にこそ、まさに、このような精神世界に中世の人々が生きていた、その息づかいのようなものを感じるのである。
また、国語学、日本語学の分野から見ても興味深い。各種のことばの意味、用法、語法などにおいて、これを用例をあつめて考えてみれば、面白い研究ができるだろう、というところがいくつも目につく。だが、残念ながら、この岩波文庫本は、古本系統の「西源院本」をつかっているのだが、その表記などについては、かなり改めた校訂になっている。そうはいっても、この文庫の本文を見るだけでも、いろいろ興味の種はつきない。
もう私自身としても、国語学、日本語学という研究の分野から引退しようかと思う。これを追求して論文を書いてみたりしようという気にはならないでいる。だが、国語学、日本語学的に見て興味深いものであることは、読みながら思うところである。
ようやく後期の講義も、後は試験を残すのみとなった。つづけて、五冊目を読むことにしたい。
2020年1月28日記






最近のコメント