『文章読本』三島由紀夫 ― 2020-04-11
2020-04-11 當山日出夫(とうやまひでお)
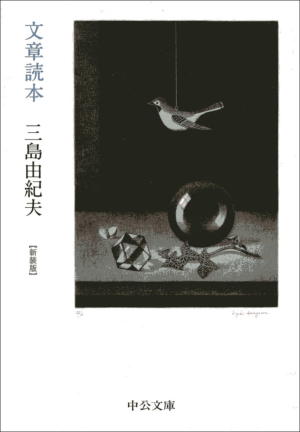
三島由紀夫.『文章読本 新装版』(中公文庫).1973(2020.改版)(1959.中央公論社)
https://www.chuko.co.jp/bunko/2020/03/206860.html
初出は、昭和三四年の『婦人公論』の別冊。それが、単行本になって、文庫本になって、さらに、改版して新しくなったものである。
『文章読本』については、おそらく谷崎潤一郎のものが最も有名かもしれない。が、私は、これを読んでそう深く感じるところがなかった。
やまもも書斎記 2016年8月23日
谷崎潤一郎『文章読本』
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2016/08/23/8160014
また、中村真一郎の『文章読本』も読んだ。
やまもも書斎記 2017年8月25日
『文章読本』中村真一郎
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2017/08/25/8655979
さらに、斎藤美奈子の本も読んでいる。
やまもも書斎記 2016年9月1日
斎藤美奈子『文章読本さん江』
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2016/09/01/8167221
さて、この三島由紀夫の『文章読本』であるが、読んで思うところは、次の二点だろうか。
第一には、これは、文学のための文章読本であるということ。
三島由紀夫は、実用文というのを排除して考えている。芸術のための文章としての、文章読本を書いている。おそらく、日本の近代の文学史において、三島由紀夫あたりまでが、小説家というものが、芸術家であった時代だと思う。今では、芸術というよりもエンタテイメントに近いだろうか。あるいは、別の方向では、思想家というべきかもしれない。ともあれ、三島由紀夫、それから、川端康成あたりまでは、小説家は芸術家であった。
その芸術家としての視点から、小説の文章はどうあるべきかを論じたものである。この意味では、昨今の大学でのリテラシ教育とは、あまり縁がない本であるともいえよう。
第二には、三島由紀夫の文学観を強く反映したものであるということ。
この本のなかで、三島由紀夫は、自分の文章に対する好き嫌いをはっきりとうちだしている。それが、とりもなおさず、三島由紀夫自身の文章観、芸術観につらなるものになっている。この本は、三島由紀夫の文学の理解にとって、きわめて有効なヒントを与えてくれるにちがいない。
以上の二点が、この『文章読本』を読んで思ったことなどである。
さらに書いてみるならば、私はこの本を以前に読んでいる。今回で、二回目、三回目ぐらいになるだろうか。最初、これを読んだのは、学校の(たぶん高校生だったと思う)の国語の教科書においてである。そのとき、森鷗外の「寒山拾得」にふれて、「水が来た」の名言にふれた。三島由紀夫は、この「水が来た」をかなり強く意識しているようである。「豊饒の海」のなかで、これをつかって、「酒が来た」と書いてあるところがあった。
さらに余計なことを書いておくと、この「水が来た」は、浅田次郎にも影響を与えている。その作品のどれか、たしか「天切り松」のシリーズだったかと思うが、これに言及した箇所があったと覚えている。
それから、例によってというべきだが、三島由紀夫『文章読本』では、日本語という言語が非論理的なものであると書いている。現代の言語学の知見からするならば、特に日本語という言語が非論理的であるとは考えないだろう。(ただ、その運用のおいて、どのように使われるかという観点からの問題提起はあるかもしれないが。)
まあ、このあたりのところは読み流しておけばいいところだと思って読んだ。
そうはいっても、主に近代日本語の文学の文章を論じながら、古くは平安朝の文学作品にまでさかのぼって、日本文学の文章の流れをたどっていく観点には、これはこれとして興味深いものがある。このような日本語の文章の歴史の考え方がある、その一例として読んでおくことになるかと思うところである。
学校での文学教育ということを肯定的に考えてみたとき、この三島由紀夫『文章読本』は、さらに読まれる価値のある本だと思う。
続けて、三島由紀夫の他の作品。それから、他の『文章読本』についても読んでみたいと思っている。
2020年3月29日記
https://www.chuko.co.jp/bunko/2020/03/206860.html
初出は、昭和三四年の『婦人公論』の別冊。それが、単行本になって、文庫本になって、さらに、改版して新しくなったものである。
『文章読本』については、おそらく谷崎潤一郎のものが最も有名かもしれない。が、私は、これを読んでそう深く感じるところがなかった。
やまもも書斎記 2016年8月23日
谷崎潤一郎『文章読本』
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2016/08/23/8160014
また、中村真一郎の『文章読本』も読んだ。
やまもも書斎記 2017年8月25日
『文章読本』中村真一郎
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2017/08/25/8655979
さらに、斎藤美奈子の本も読んでいる。
やまもも書斎記 2016年9月1日
斎藤美奈子『文章読本さん江』
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2016/09/01/8167221
さて、この三島由紀夫の『文章読本』であるが、読んで思うところは、次の二点だろうか。
第一には、これは、文学のための文章読本であるということ。
三島由紀夫は、実用文というのを排除して考えている。芸術のための文章としての、文章読本を書いている。おそらく、日本の近代の文学史において、三島由紀夫あたりまでが、小説家というものが、芸術家であった時代だと思う。今では、芸術というよりもエンタテイメントに近いだろうか。あるいは、別の方向では、思想家というべきかもしれない。ともあれ、三島由紀夫、それから、川端康成あたりまでは、小説家は芸術家であった。
その芸術家としての視点から、小説の文章はどうあるべきかを論じたものである。この意味では、昨今の大学でのリテラシ教育とは、あまり縁がない本であるともいえよう。
第二には、三島由紀夫の文学観を強く反映したものであるということ。
この本のなかで、三島由紀夫は、自分の文章に対する好き嫌いをはっきりとうちだしている。それが、とりもなおさず、三島由紀夫自身の文章観、芸術観につらなるものになっている。この本は、三島由紀夫の文学の理解にとって、きわめて有効なヒントを与えてくれるにちがいない。
以上の二点が、この『文章読本』を読んで思ったことなどである。
さらに書いてみるならば、私はこの本を以前に読んでいる。今回で、二回目、三回目ぐらいになるだろうか。最初、これを読んだのは、学校の(たぶん高校生だったと思う)の国語の教科書においてである。そのとき、森鷗外の「寒山拾得」にふれて、「水が来た」の名言にふれた。三島由紀夫は、この「水が来た」をかなり強く意識しているようである。「豊饒の海」のなかで、これをつかって、「酒が来た」と書いてあるところがあった。
さらに余計なことを書いておくと、この「水が来た」は、浅田次郎にも影響を与えている。その作品のどれか、たしか「天切り松」のシリーズだったかと思うが、これに言及した箇所があったと覚えている。
それから、例によってというべきだが、三島由紀夫『文章読本』では、日本語という言語が非論理的なものであると書いている。現代の言語学の知見からするならば、特に日本語という言語が非論理的であるとは考えないだろう。(ただ、その運用のおいて、どのように使われるかという観点からの問題提起はあるかもしれないが。)
まあ、このあたりのところは読み流しておけばいいところだと思って読んだ。
そうはいっても、主に近代日本語の文学の文章を論じながら、古くは平安朝の文学作品にまでさかのぼって、日本文学の文章の流れをたどっていく観点には、これはこれとして興味深いものがある。このような日本語の文章の歴史の考え方がある、その一例として読んでおくことになるかと思うところである。
学校での文学教育ということを肯定的に考えてみたとき、この三島由紀夫『文章読本』は、さらに読まれる価値のある本だと思う。
続けて、三島由紀夫の他の作品。それから、他の『文章読本』についても読んでみたいと思っている。
2020年3月29日記
『エール』あれこれ「運命のかぐや姫」 ― 2020-04-12
2020-04-12 當山日出夫(とうやまひでお)
『エール』第2週「運命のかぐや姫」
https://www.nhk.or.jp/yell/story/week_02.html
前回は、
やまもも書斎記 2020年4月5日
『エール』あれこれ「初めてのエール」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/04/05/9231712
この二週目では、音のことがメインであった。見て思うことを書いてみれば、次の二点だろうか。
第一には、音と音楽のこと。
音も音楽に興味関心がある。教会で、双浦環(柴咲コウ)の歌う歌……「私のお父さん」……に魅了される。また、学芸会でも、竹取物語の最後のシーンが、音の歌う歌……唱歌「朧月夜」……であった。このような音が、将来において、裕一と出会う伏線になっているのだろう。
第二には、その音の頑張り。
突然のことだったが、父が死ぬことになる。母(薬師丸ひろ子)と姉妹三人で、どうにか商売を続けていくことになる。逆境にあってもくじけない音のたくましさというものが描かれていたと思う。
以上の二点が、この週を見て思ったことなどである。
さらに書いてみるならば、音にむかって語りかけるシーン……双浦環であったり、お父さんであったりしたが……これらのシーンで、大人が音の目線にかがんで話しかけていたことが、印象に残っている。大人の目の高さから見下ろして語るのではなく、同じ目線の高さで語りかけていた。父は言っていた……誰もが主役になれるわけではない、と。双浦環はこう言った……音楽にこころざすなら穴をあけるようなことがあっては駄目だ、と。これら、これからの音の人生がどのようなもになるにしても、重要なことばだと思う。
次週は、もとにもどって、裕一の成長してからのことになるようだ。これも楽しみに見ることにしよう。
2020年4月11日記
『エール』第2週「運命のかぐや姫」
https://www.nhk.or.jp/yell/story/week_02.html
前回は、
やまもも書斎記 2020年4月5日
『エール』あれこれ「初めてのエール」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/04/05/9231712
この二週目では、音のことがメインであった。見て思うことを書いてみれば、次の二点だろうか。
第一には、音と音楽のこと。
音も音楽に興味関心がある。教会で、双浦環(柴咲コウ)の歌う歌……「私のお父さん」……に魅了される。また、学芸会でも、竹取物語の最後のシーンが、音の歌う歌……唱歌「朧月夜」……であった。このような音が、将来において、裕一と出会う伏線になっているのだろう。
第二には、その音の頑張り。
突然のことだったが、父が死ぬことになる。母(薬師丸ひろ子)と姉妹三人で、どうにか商売を続けていくことになる。逆境にあってもくじけない音のたくましさというものが描かれていたと思う。
以上の二点が、この週を見て思ったことなどである。
さらに書いてみるならば、音にむかって語りかけるシーン……双浦環であったり、お父さんであったりしたが……これらのシーンで、大人が音の目線にかがんで話しかけていたことが、印象に残っている。大人の目の高さから見下ろして語るのではなく、同じ目線の高さで語りかけていた。父は言っていた……誰もが主役になれるわけではない、と。双浦環はこう言った……音楽にこころざすなら穴をあけるようなことがあっては駄目だ、と。これら、これからの音の人生がどのようなもになるにしても、重要なことばだと思う。
次週は、もとにもどって、裕一の成長してからのことになるようだ。これも楽しみに見ることにしよう。
2020年4月11日記
追記 2020-04-19
この続きは、
やまもも書斎記 2020年4月19日
『エール』あれこれ「いばらの道」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/04/19/9236927
この続きは、
やまもも書斎記 2020年4月19日
『エール』あれこれ「いばらの道」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/04/19/9236927
『源氏物語』岩波文庫(四) ― 2020-04-13
2020-04-13 當山日出夫(とうやまひでお)

柳井滋(他)(校注).『源氏物語(三)』(岩波文庫).岩波書店.2018
https://www.iwanami.co.jp/book/b374920.html
続きである。
やまもも書斎記 2020年4月6日
『源氏物語』岩波文庫(三)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/04/06/9232136
岩波文庫の編集でたまたまそうなっているのだろうが、この第四冊目には、玉鬘の物語をおさめる。遠い九州の地で生い育った玉鬘が、京にでてくるところからはじまって、最後は、髭黒の大将と一緒になるまでの一連の物語である。
いわゆる『源氏物語』の三段階成立論からすれば、これらの巻は、後から加筆、挿入された部分ということになる。そう思って読むせいもあるのだろうか、これらの玉鬘の物語は、これはこれとして、『源氏物語』の一部をなしながら、独立した印象を持つ。
読んで思うことを書いてみると、次の二点ほどである。
第一に、(これは前にも書いているが)やはり、京の都に上ってきた玉鬘が右近と遭遇するあたりの記述は、長谷寺の観音霊験譚とおぼしい。このような霊験譚については、後の宇治十帖でも感じるところである。
第二に、その玉鬘と光源氏との関係。光源氏は玉鬘に心をよせる。だが、これは、以前にその母親である夕顔……これは、なにがしの院でもののけにとりころされてしまうのであるが……と、その娘に、両方に関係をもつことになる。このあたり、おそらくは、『源氏物語』の当時にあっても、不倫めいた印象があったのだろう、はっきりと玉鬘と光源氏が関係をもつとは書いていない。しかし、ただならぬ関係になりつつある思いを、玉鬘の立場からも、また、光源氏のたちばからも、どうしようもできない心のうちを描いている。
ここは、いっそのこと、玉鬘と光源氏との関係があってもいいような気もしてしまうのだが、物語の叙述は、きわどいところで筆をとめている。
以上の二点が、この第四冊の玉鬘にまつわる巻を読んで感じるところなどである。
さらに書いてみるならば、この玉鬘の話として平行して出てくる、近江の君の話。これは、滑稽な話としてして読んでおけばいいのかもしれない。これは、玉鬘と近江の君と、対照的に描いてある。
このようなこと……どこかに昔関係した女が生んだ娘がいて、それを探し出してきて、ひきとってそだてる。それも、あわよくば、宮中に入内することもあり得るのかもしれない。このような昔物語が先行するものとして、きっとあったにちがいないと感じるところもある。
それから、よくわからないのが、髭黒の大将と、その北の方、子どもたち……女の子と男の子……である。これは、この当時の婚姻制度、男女の関係が、かなり今の感覚と違っていることを感じさせる。女の子は、母親の方についていくが、男の子はそうでもない。このあたり、平安貴族の婚姻の習俗がどのようなものであったか、興味深いところである。
また、これもすでに書いてみたことであるが……北の方が乱心して、香炉の灰を夫の髭黒の大将にあびせかけるシーン。これなど、『源氏物語』のなかにあって、非常に説話的な部分である。これも、おそらくは、もののけにとりつかれた妻の夫に対する行為として、流布していた話しがあってのことかもしれないと思ったりする。
さて、次は、第五冊目である。『若菜』の上・下になる。『源氏物語』で最も中核をなすところになる。このまま続けてよむことにしよう。
2020年2月8日記
https://www.iwanami.co.jp/book/b374920.html
続きである。
やまもも書斎記 2020年4月6日
『源氏物語』岩波文庫(三)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/04/06/9232136
岩波文庫の編集でたまたまそうなっているのだろうが、この第四冊目には、玉鬘の物語をおさめる。遠い九州の地で生い育った玉鬘が、京にでてくるところからはじまって、最後は、髭黒の大将と一緒になるまでの一連の物語である。
いわゆる『源氏物語』の三段階成立論からすれば、これらの巻は、後から加筆、挿入された部分ということになる。そう思って読むせいもあるのだろうか、これらの玉鬘の物語は、これはこれとして、『源氏物語』の一部をなしながら、独立した印象を持つ。
読んで思うことを書いてみると、次の二点ほどである。
第一に、(これは前にも書いているが)やはり、京の都に上ってきた玉鬘が右近と遭遇するあたりの記述は、長谷寺の観音霊験譚とおぼしい。このような霊験譚については、後の宇治十帖でも感じるところである。
第二に、その玉鬘と光源氏との関係。光源氏は玉鬘に心をよせる。だが、これは、以前にその母親である夕顔……これは、なにがしの院でもののけにとりころされてしまうのであるが……と、その娘に、両方に関係をもつことになる。このあたり、おそらくは、『源氏物語』の当時にあっても、不倫めいた印象があったのだろう、はっきりと玉鬘と光源氏が関係をもつとは書いていない。しかし、ただならぬ関係になりつつある思いを、玉鬘の立場からも、また、光源氏のたちばからも、どうしようもできない心のうちを描いている。
ここは、いっそのこと、玉鬘と光源氏との関係があってもいいような気もしてしまうのだが、物語の叙述は、きわどいところで筆をとめている。
以上の二点が、この第四冊の玉鬘にまつわる巻を読んで感じるところなどである。
さらに書いてみるならば、この玉鬘の話として平行して出てくる、近江の君の話。これは、滑稽な話としてして読んでおけばいいのかもしれない。これは、玉鬘と近江の君と、対照的に描いてある。
このようなこと……どこかに昔関係した女が生んだ娘がいて、それを探し出してきて、ひきとってそだてる。それも、あわよくば、宮中に入内することもあり得るのかもしれない。このような昔物語が先行するものとして、きっとあったにちがいないと感じるところもある。
それから、よくわからないのが、髭黒の大将と、その北の方、子どもたち……女の子と男の子……である。これは、この当時の婚姻制度、男女の関係が、かなり今の感覚と違っていることを感じさせる。女の子は、母親の方についていくが、男の子はそうでもない。このあたり、平安貴族の婚姻の習俗がどのようなものであったか、興味深いところである。
また、これもすでに書いてみたことであるが……北の方が乱心して、香炉の灰を夫の髭黒の大将にあびせかけるシーン。これなど、『源氏物語』のなかにあって、非常に説話的な部分である。これも、おそらくは、もののけにとりつかれた妻の夫に対する行為として、流布していた話しがあってのことかもしれないと思ったりする。
さて、次は、第五冊目である。『若菜』の上・下になる。『源氏物語』で最も中核をなすところになる。このまま続けてよむことにしよう。
2020年2月8日記
『麒麟がくる』あれこれ「帰蝶のはかりごと」 ― 2020-04-14
2020-04-14 當山日出夫(とうやまひでお)
『麒麟がくる』第十三回「帰蝶のはかりごと」
https://www.nhk.or.jp/kirin/story/13.html
前回は、
やまもも書斎記 2020年4月7日
『麒麟がくる』あれこれ「十兵衛の嫁」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/04/07/9232519
光秀が歴史の表舞台にでてくるのはまだ先のことになるようだ。
この回を見て思ったことを書けば、次の二点になるだろうか。
第一には、帰蝶のこと。
美濃から尾張に送られた人質であったはずの帰蝶である。だが、その帰蝶が、実は歴史の歯車を裏で動かしていた。まあ、これはドラマであるから、そのように描いているのであろうが、これはこれとして面白い。
伊呂波太夫もただの旅芸人ではない。その伊呂波太夫に傭兵をあつめるように依頼することになる帰蝶も、ただものではない。いったいあれほどの砂金をどのような手段で差配しているというのだろうか。
第二には、道三と高政のこと。
この二人は一触即発の雰囲気である。はたして本当の父と子であるのか、それも疑わしいといえばいえる。この二人をとりなそうとする、母である深芳野は、いったい何を思っているのか。ただ、その姿は妖艶でもある。(ちょっと化粧が濃いような気もしないではないが。)
以上の二点が、この回を見て思ったことなどである。
さらに書いてみるならば……藤吉郎が登場していた。後の豊臣秀吉である。これで、戦国のおもだった登場人物が出そろったとでもいえるだろうか。
ところで、ドラマのなかで読んでいた本が、どうやら『徒然草』とおぼしい。今となっては、『徒然草』は、古典の定番だが、『徒然草』が「古典」になったのは、比較的新しいということもできる(近世になって版本が刊行されるようになってから)。このあたりは、歴史考証の面で、ちょっと考えていいところかもしれない。
ドラマの最後は、聖徳寺での会見を前に、信長の一行を道三がのぞき見るシーンであった。長い槍、それから、多くの鉄砲。このあたりのことは、たしか『国盗り物語』で司馬遼太郎が描いていたところかと覚えている。また、この会見も、ある意味では、帰蝶の姿が背後に見えるという筋書きでもあった。
さて、帰蝶は、これからこのドラマでどのような役割を果たすことなるのだろうか。次回以降の展開を楽しみに見ることにしよう。
2020年4月13日記
『麒麟がくる』第十三回「帰蝶のはかりごと」
https://www.nhk.or.jp/kirin/story/13.html
前回は、
やまもも書斎記 2020年4月7日
『麒麟がくる』あれこれ「十兵衛の嫁」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/04/07/9232519
光秀が歴史の表舞台にでてくるのはまだ先のことになるようだ。
この回を見て思ったことを書けば、次の二点になるだろうか。
第一には、帰蝶のこと。
美濃から尾張に送られた人質であったはずの帰蝶である。だが、その帰蝶が、実は歴史の歯車を裏で動かしていた。まあ、これはドラマであるから、そのように描いているのであろうが、これはこれとして面白い。
伊呂波太夫もただの旅芸人ではない。その伊呂波太夫に傭兵をあつめるように依頼することになる帰蝶も、ただものではない。いったいあれほどの砂金をどのような手段で差配しているというのだろうか。
第二には、道三と高政のこと。
この二人は一触即発の雰囲気である。はたして本当の父と子であるのか、それも疑わしいといえばいえる。この二人をとりなそうとする、母である深芳野は、いったい何を思っているのか。ただ、その姿は妖艶でもある。(ちょっと化粧が濃いような気もしないではないが。)
以上の二点が、この回を見て思ったことなどである。
さらに書いてみるならば……藤吉郎が登場していた。後の豊臣秀吉である。これで、戦国のおもだった登場人物が出そろったとでもいえるだろうか。
ところで、ドラマのなかで読んでいた本が、どうやら『徒然草』とおぼしい。今となっては、『徒然草』は、古典の定番だが、『徒然草』が「古典」になったのは、比較的新しいということもできる(近世になって版本が刊行されるようになってから)。このあたりは、歴史考証の面で、ちょっと考えていいところかもしれない。
ドラマの最後は、聖徳寺での会見を前に、信長の一行を道三がのぞき見るシーンであった。長い槍、それから、多くの鉄砲。このあたりのことは、たしか『国盗り物語』で司馬遼太郎が描いていたところかと覚えている。また、この会見も、ある意味では、帰蝶の姿が背後に見えるという筋書きでもあった。
さて、帰蝶は、これからこのドラマでどのような役割を果たすことなるのだろうか。次回以降の展開を楽しみに見ることにしよう。
2020年4月13日記
追記 2020-04-21
この続きは、
やまもも書斎記 2020年4月21日
『麒麟がくる』あれこれ「聖徳寺の会見」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/04/21/9237651
この続きは、
やまもも書斎記 2020年4月21日
『麒麟がくる』あれこれ「聖徳寺の会見」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/04/21/9237651
散る桜 ― 2020-04-15
2020-04-15 當山日出夫(とうやまひでお)
水曜日なので写真の日。今日は桜の花の散っている様を写してみた。
前回は、
やまもも書斎記 2020年4月8日
サンシュユ
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/04/08/9232908
我が家、また、その周辺には、いくつかの桜の木がある。そのうちで、この駐車場にある木をいつも目にする。毎朝、子どもを仕事におくっていくとき、この桜の木の横を通る。
この桜の花ももう終わってしまった。今年は、あまりゆっくりと花の咲くのを愛でる余裕もなく時間がたってしまったような感じである。掲載の写真は、桜の花が散ってしまって、少し花びらが残っているところを写したものである。写真に撮ると、このような桜の花もまた、これはこれで見どころがあるという印象を持つ。
使っているレンズは、タムロンの180ミリ。大きく重く、AFは遅い。しかし、花の写真をとるには、きわめてすぐれたレンズである。ちょっと木の上にある花でも、十分に余裕をもって接写できる。このところ、カメラ(D500)には、このレンズをつけっぱなしのような状態になっている。
そろそろ花粉症のシーズンも終わるので、天気がよければ散歩に出ようかと思っている。三脚とカメラとこのレンズでは、かなりの装備になるが、まあ運動がてらである。
水曜日なので写真の日。今日は桜の花の散っている様を写してみた。
前回は、
やまもも書斎記 2020年4月8日
サンシュユ
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/04/08/9232908
我が家、また、その周辺には、いくつかの桜の木がある。そのうちで、この駐車場にある木をいつも目にする。毎朝、子どもを仕事におくっていくとき、この桜の木の横を通る。
この桜の花ももう終わってしまった。今年は、あまりゆっくりと花の咲くのを愛でる余裕もなく時間がたってしまったような感じである。掲載の写真は、桜の花が散ってしまって、少し花びらが残っているところを写したものである。写真に撮ると、このような桜の花もまた、これはこれで見どころがあるという印象を持つ。
使っているレンズは、タムロンの180ミリ。大きく重く、AFは遅い。しかし、花の写真をとるには、きわめてすぐれたレンズである。ちょっと木の上にある花でも、十分に余裕をもって接写できる。このところ、カメラ(D500)には、このレンズをつけっぱなしのような状態になっている。
そろそろ花粉症のシーズンも終わるので、天気がよければ散歩に出ようかと思っている。三脚とカメラとこのレンズでは、かなりの装備になるが、まあ運動がてらである。
Nikon D500
TAMRON SP AF 180mm F/3.5 Di MACRO 1:1
2020年4月14日記
『小説読本』三島由紀夫 ― 2020-04-16
2020-04-16 當山日出夫(とうやまひでお)

三島由紀夫.『小説読本』(中公文庫).中央公論新社.2016(中央公論新社.2010)
http://www.chuko.co.jp/bunko/2016/10/206302.html
『文章読本』を久しぶりに読んでみて、面白かったので、続けて読んでみることにした。これを読むと、三島由紀夫が類い希なる小説の読み手であったことが分かる。
読んで思うところは、次の二点ぐらいだろうか。
第一には、これはこれとして、すぐれた文学案内……文学のうちでも特に近代の小説ということにはなるが……となっていることである。なるほど、小説とはこのような読み方、味わい方ができるものなのかと、認識を新たにするところがいくつかあった。
第二には、著者(三島由紀夫)自身の小説の書き方の内側をのぞき見ることができるという興味である。この本に収められたいくつかの文章で、三島由紀夫は、自分自身の小説に対するこころがまえのようなものを語っている。それを読むと、三島由紀夫の文学の裏側を自ら語っていると感じるところがある。
特に、三島由紀夫は、小説を書くとき、そのラストをイメージしてから書くという。これは、興味深い。たとえば、『午後の曳航』とか『金閣寺』とかのラストは、きわめて印象的に覚えているのだが、これは、そのようなラストを書くことをあらかじめイメージしていたのかと思う。また、「豊饒の海」四部作の最後『天人五衰』の最後も、忘れることはできない。はたして、三島由紀夫は、『天人五衰』のラストのシーンをイメージして、市ヶ谷に向かったのだろうか。
以上の二点が、この本を読んで感じるところである。
そして、忘れてはならないことは、三島由紀夫にとって、小説とは芸術であったのである。今の日本の文学を語るとき、特に小説を語るとき、芸術という発想で見ることはあまりないように思う。しかし、三島由紀夫にとって、はっきりと小説は芸術でなければならなかった。このことを確認する意味でも、この本は価値があると思う。
また興味深いのは、法律、なかでも、刑事訴訟法に魅力を感じていたと書いているあたりのこと。三島由紀夫の文学と法学というのも、きわめて興味あるテーマにちがいない。
この本は、2010年になって、中央公論新社で新しく、編集して刊行されたものである。三島由紀夫の生前の編集になるものではない。「全集」から、近代の小説について書かれたものを選んで、一冊に作ったものである。
つづけて、同じ中公文庫の『古典文学読本』を読むことにしたいと思う。
2020年4月1日記
http://www.chuko.co.jp/bunko/2016/10/206302.html
『文章読本』を久しぶりに読んでみて、面白かったので、続けて読んでみることにした。これを読むと、三島由紀夫が類い希なる小説の読み手であったことが分かる。
読んで思うところは、次の二点ぐらいだろうか。
第一には、これはこれとして、すぐれた文学案内……文学のうちでも特に近代の小説ということにはなるが……となっていることである。なるほど、小説とはこのような読み方、味わい方ができるものなのかと、認識を新たにするところがいくつかあった。
第二には、著者(三島由紀夫)自身の小説の書き方の内側をのぞき見ることができるという興味である。この本に収められたいくつかの文章で、三島由紀夫は、自分自身の小説に対するこころがまえのようなものを語っている。それを読むと、三島由紀夫の文学の裏側を自ら語っていると感じるところがある。
特に、三島由紀夫は、小説を書くとき、そのラストをイメージしてから書くという。これは、興味深い。たとえば、『午後の曳航』とか『金閣寺』とかのラストは、きわめて印象的に覚えているのだが、これは、そのようなラストを書くことをあらかじめイメージしていたのかと思う。また、「豊饒の海」四部作の最後『天人五衰』の最後も、忘れることはできない。はたして、三島由紀夫は、『天人五衰』のラストのシーンをイメージして、市ヶ谷に向かったのだろうか。
以上の二点が、この本を読んで感じるところである。
そして、忘れてはならないことは、三島由紀夫にとって、小説とは芸術であったのである。今の日本の文学を語るとき、特に小説を語るとき、芸術という発想で見ることはあまりないように思う。しかし、三島由紀夫にとって、はっきりと小説は芸術でなければならなかった。このことを確認する意味でも、この本は価値があると思う。
また興味深いのは、法律、なかでも、刑事訴訟法に魅力を感じていたと書いているあたりのこと。三島由紀夫の文学と法学というのも、きわめて興味あるテーマにちがいない。
この本は、2010年になって、中央公論新社で新しく、編集して刊行されたものである。三島由紀夫の生前の編集になるものではない。「全集」から、近代の小説について書かれたものを選んで、一冊に作ったものである。
つづけて、同じ中公文庫の『古典文学読本』を読むことにしたいと思う。
2020年4月1日記
『山椒大夫・高瀬舟』森鷗外/新潮文庫 ― 2020-04-17
2020-04-17 當山日出夫(とうやまひでお)

森鷗外.『山椒大夫・高瀬舟』(新潮文庫).新潮社.1968(2006.改版)
https://www.shinchosha.co.jp/book/102005/
芥川龍之介の作品を新潮文庫版でまとめて読みかえして、次に手にしたの森鷗外の作品である。森鷗外については、その「全集」(岩波版)は持っている。だが、それを取り出してきて、最初からひもといてみようという気力がもうない。新潮文庫で現在読める作品を読んでおきたいと思う。
最初は、『山椒大夫・高瀬舟』である。次の作品が収録されている。
杯
普請中
カズイスチカ
妄想
百物語
興津弥五右衛門の遺書
護持院原の敵討
山椒大夫
二人の友
最後の一句
高瀬舟
これらの作品、最初に読んだのは、中学か高校のころだったかと思う。その後、岩波で出た「全集」は買った。今でも持っている。
このうち「高瀬舟」「最後の一句」については、最近読んでいる。
やまもも書斎記 2020年3月13日
『教科書名短篇-人間の情景-』中公文庫
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/03/13/9223694
ここに収められた作品を読んで印象に残るのは、やはり「高瀬舟」だろうか。静かな語り口でありながら、その問いかけるところは、奥が深い。この作品が、今にいたるまで、学校教育において教科書に採用されているのは、うなずけるところがある。(が、これも、今般の国語教育改革でどうなるかわからないところもあるが。)
私の思いを記すならば、「高瀬舟」はこれからも読まれ続けていってほしい。これからの時代、人びとの多様性の尊重ということが重要になる。そのとき、自分の価値観のよってきたるところが何であるか、また、自分とは違う価値観の人に接したときどうであるべきか……これは、そう簡単に答えの出せる問題ではない。だが、文学作品というなかにおいては、そのような体験をこころみることができる。文学的想像力といってもいいだろう。この文学的想像力の無いところに、文化や社会の多様性の尊重ということは、育たないだろう。
森鷗外の作品をまとめて読みなおすのは、何十年ぶりかなる。読んで感じるところとしては、森鷗外は、孤高の作家であるという印象である。よく、鷗外は漱石と比較される。漱石は、職業的な小説家になり、その晩年は多くの知人や門下生にかこまれていた。これに対して、たしかに、鷗外は、常に孤独であったような気がする。特に晩年の史伝などになると、いったいどれほどの読者が共感して読んでくれただろうかという気にもなる。(そのなかで、『渋江抽斎』などは、面白いと思うのではあるが。)
夏目漱石も、また、芥川龍之介も「孤独」であったと思う。その作品の多くは、「孤独」な近代人の内面を描いている。そして、森鷗外もまた、「孤独」な作家であったと強く感じる。
続けて、文庫本で森鷗外を読んでいきたいと思う。
2020年4月14日記
https://www.shinchosha.co.jp/book/102005/
芥川龍之介の作品を新潮文庫版でまとめて読みかえして、次に手にしたの森鷗外の作品である。森鷗外については、その「全集」(岩波版)は持っている。だが、それを取り出してきて、最初からひもといてみようという気力がもうない。新潮文庫で現在読める作品を読んでおきたいと思う。
最初は、『山椒大夫・高瀬舟』である。次の作品が収録されている。
杯
普請中
カズイスチカ
妄想
百物語
興津弥五右衛門の遺書
護持院原の敵討
山椒大夫
二人の友
最後の一句
高瀬舟
これらの作品、最初に読んだのは、中学か高校のころだったかと思う。その後、岩波で出た「全集」は買った。今でも持っている。
このうち「高瀬舟」「最後の一句」については、最近読んでいる。
やまもも書斎記 2020年3月13日
『教科書名短篇-人間の情景-』中公文庫
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/03/13/9223694
ここに収められた作品を読んで印象に残るのは、やはり「高瀬舟」だろうか。静かな語り口でありながら、その問いかけるところは、奥が深い。この作品が、今にいたるまで、学校教育において教科書に採用されているのは、うなずけるところがある。(が、これも、今般の国語教育改革でどうなるかわからないところもあるが。)
私の思いを記すならば、「高瀬舟」はこれからも読まれ続けていってほしい。これからの時代、人びとの多様性の尊重ということが重要になる。そのとき、自分の価値観のよってきたるところが何であるか、また、自分とは違う価値観の人に接したときどうであるべきか……これは、そう簡単に答えの出せる問題ではない。だが、文学作品というなかにおいては、そのような体験をこころみることができる。文学的想像力といってもいいだろう。この文学的想像力の無いところに、文化や社会の多様性の尊重ということは、育たないだろう。
森鷗外の作品をまとめて読みなおすのは、何十年ぶりかなる。読んで感じるところとしては、森鷗外は、孤高の作家であるという印象である。よく、鷗外は漱石と比較される。漱石は、職業的な小説家になり、その晩年は多くの知人や門下生にかこまれていた。これに対して、たしかに、鷗外は、常に孤独であったような気がする。特に晩年の史伝などになると、いったいどれほどの読者が共感して読んでくれただろうかという気にもなる。(そのなかで、『渋江抽斎』などは、面白いと思うのではあるが。)
夏目漱石も、また、芥川龍之介も「孤独」であったと思う。その作品の多くは、「孤独」な近代人の内面を描いている。そして、森鷗外もまた、「孤独」な作家であったと強く感じる。
続けて、文庫本で森鷗外を読んでいきたいと思う。
2020年4月14日記
『戦争と平和』(一)トルストイ/岩波文庫 ― 2020-04-18
2020-04-18 當山日出夫(とうやまひでお)

トルストイ.藤沼貴(訳).『戦争と平和』(一)(岩波文庫).岩波書店.2006
https://www.iwanami.co.jp/book/b248226.html
以前に、読んだときのことは、
やまもも書斎記 2016年9月9日
トルストイ『戦争と平和』
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2016/09/09/8175825
このときは、新潮文庫(四冊)で読んだ。今回は、岩波文庫(六冊)で読んでみようと思う。
『復活』を何気なく読んだら、『戦争と平和』を読んでみたくなった。岩波文庫で、同じ藤沼貴の訳で出ている。
やまもも書斎記
『復活』(上)トルストイ/岩波文庫
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/03/05/9220796
『復活』(下)トルストイ/岩波文庫
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/03/06/9221152
この『戦争と平和』については、光文社古典新訳文庫で、望月哲男訳が刊行になる。現在(二〇二〇年二月)の時点では、第一冊目が刊行になっている。これでも読んでおくつもりでいるのだが、『復活』と同じ訳者ということで、岩波文庫版でも読むことにした。これは、新しく訳したものである。
第一冊目を読んで思うことは、次の二点であろうか。
第一には、『戦争と平和』を読むのは、二回目(あるいは三回目になるか)であるが、今回は、登場人物の心理のうちによりそって読めるように感じる。以前に読んでいるので、だいたいのことは一度読んで、頭にはいっている。といっても、複雑多岐な登場人物の細部を憶えているということはないのであるが。しかし、全体としてどんな小説であるかは、分かっている。今回は、それをじっくりと未読しながら読むことになる。
そうすると、一九世紀のロシアの貴族……これを、二一世紀の日本において読んで、そのこころの動きに共感するところを感じる。まさに「文学」なのである。
些細なことかもしれないが、岩波文庫版には、登場人物の一覧が、本のはじめの方についている。ときおり、これを参照しながら読んで行く。まあ、ある意味では、この一覧に名前の出てこない人物のことについては、読み飛ばしてしまうことにもなるのだが。
ピエールの、アンドレイの、ニコライの、このような登場人物の心の動きを感じ取りながら読むことができたかと思う。
第二には、これは、おそらくロシアにおける国民文学なのであろうということがある。私は、ロシア文学には不案内である。今日のロシアにおいて、トルストイがどのように読まれる作家であるかは知らない。
しかし、読んでいって、ナポレオンとの戦争のことを描いたこの小説は、まさにロシアの人びとの今の生活につながるものとしてあるのだろう……このようなことを感じる。日本において、このような国民的な文学があるだろうか。明治の夏目漱石の作品がそうかもしれない。あるいは、司馬遼太郎の『坂の上の雲』がそうであるのかもしれない。
以上の二つのことが、とりあえず第一冊目を読んで思うことなどである。
ただ、今回読んでみてであるが、戦争の戦闘シーンについては、今一つ理解が及ばないと感じるところがある。ナポレオン時代の戦争のあり方と、現代の我々のもっている戦争のイメージが、どうもうまくつながらない。この小説において、戦争の描写が重要な意味を持っていることは、以前に読んだときのこととして、理解はできるのだが。
ともあれ、続けて第二冊を読むことにしようと思う。
2020年2月29日記
https://www.iwanami.co.jp/book/b248226.html
以前に、読んだときのことは、
やまもも書斎記 2016年9月9日
トルストイ『戦争と平和』
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2016/09/09/8175825
このときは、新潮文庫(四冊)で読んだ。今回は、岩波文庫(六冊)で読んでみようと思う。
『復活』を何気なく読んだら、『戦争と平和』を読んでみたくなった。岩波文庫で、同じ藤沼貴の訳で出ている。
やまもも書斎記
『復活』(上)トルストイ/岩波文庫
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/03/05/9220796
『復活』(下)トルストイ/岩波文庫
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/03/06/9221152
この『戦争と平和』については、光文社古典新訳文庫で、望月哲男訳が刊行になる。現在(二〇二〇年二月)の時点では、第一冊目が刊行になっている。これでも読んでおくつもりでいるのだが、『復活』と同じ訳者ということで、岩波文庫版でも読むことにした。これは、新しく訳したものである。
第一冊目を読んで思うことは、次の二点であろうか。
第一には、『戦争と平和』を読むのは、二回目(あるいは三回目になるか)であるが、今回は、登場人物の心理のうちによりそって読めるように感じる。以前に読んでいるので、だいたいのことは一度読んで、頭にはいっている。といっても、複雑多岐な登場人物の細部を憶えているということはないのであるが。しかし、全体としてどんな小説であるかは、分かっている。今回は、それをじっくりと未読しながら読むことになる。
そうすると、一九世紀のロシアの貴族……これを、二一世紀の日本において読んで、そのこころの動きに共感するところを感じる。まさに「文学」なのである。
些細なことかもしれないが、岩波文庫版には、登場人物の一覧が、本のはじめの方についている。ときおり、これを参照しながら読んで行く。まあ、ある意味では、この一覧に名前の出てこない人物のことについては、読み飛ばしてしまうことにもなるのだが。
ピエールの、アンドレイの、ニコライの、このような登場人物の心の動きを感じ取りながら読むことができたかと思う。
第二には、これは、おそらくロシアにおける国民文学なのであろうということがある。私は、ロシア文学には不案内である。今日のロシアにおいて、トルストイがどのように読まれる作家であるかは知らない。
しかし、読んでいって、ナポレオンとの戦争のことを描いたこの小説は、まさにロシアの人びとの今の生活につながるものとしてあるのだろう……このようなことを感じる。日本において、このような国民的な文学があるだろうか。明治の夏目漱石の作品がそうかもしれない。あるいは、司馬遼太郎の『坂の上の雲』がそうであるのかもしれない。
以上の二つのことが、とりあえず第一冊目を読んで思うことなどである。
ただ、今回読んでみてであるが、戦争の戦闘シーンについては、今一つ理解が及ばないと感じるところがある。ナポレオン時代の戦争のあり方と、現代の我々のもっている戦争のイメージが、どうもうまくつながらない。この小説において、戦争の描写が重要な意味を持っていることは、以前に読んだときのこととして、理解はできるのだが。
ともあれ、続けて第二冊を読むことにしようと思う。
2020年2月29日記
追記 2020-04-25
この続きは、
やまもも書斎記 2020年4月25日
『戦争と平和』(二)トルスト/岩波文庫
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/04/25/9238990
この続きは、
やまもも書斎記 2020年4月25日
『戦争と平和』(二)トルスト/岩波文庫
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/04/25/9238990
『エール』あれこれ「いばらの道」 ― 2020-04-19
2020-04-19 當山日出夫(とうやまひでお)
『エール』第3週「いばらの道」
https://www.nhk.or.jp/yell/story/week_03.html
前回は、
やまもも書斎記 2020年4月12日
『エール』あれこれ「運命のかぐや姫」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/04/12/9234473
この週で描いていたのは、裕一の青年時代のこと。怒濤の展開であった。思いつくままに書いてみる。
第一には、音楽への情熱。
裕一は、ハーモニカ倶楽部で活躍する。新曲を作曲して、それが選ばれることになる。音楽家しての裕一の才能の発露といっていいだろう。
第二は、養子のこと。
家の仕事がうまくいかない。融資をうける条件として、兄弟のうちどちらかが養子に行かなければならない。家業は、弟が継ぐことになって、結局、裕一が家を出る。
第三は、銀行のこと。
養子に出るとして、まず、裕一は銀行員になる。そこで修行をしてということらしい。この銀行での、他の行員とのやりとりがコミカルで面白かった。
第四には、ダンスホールのこと。
銀行の仲間にさそわれて、裕一はダンスホールに行くことになる。そこで、踊り子の志津と出会う。どうやら一目惚れのようだった。そして、接吻大作戦となる。その結末は、まさに意外な展開であった。
以上のようなことがこの週の見どころであったかと思う。
それから、子どものころの仲間である鉄男が登場していた。これから、裕一の音楽の友になるのだろう。
次週以降、いよいよ、音と裕一の人生が交錯するようである。これも楽しみに見ることにしよう。
2020年4月18日記
『エール』第3週「いばらの道」
https://www.nhk.or.jp/yell/story/week_03.html
前回は、
やまもも書斎記 2020年4月12日
『エール』あれこれ「運命のかぐや姫」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/04/12/9234473
この週で描いていたのは、裕一の青年時代のこと。怒濤の展開であった。思いつくままに書いてみる。
第一には、音楽への情熱。
裕一は、ハーモニカ倶楽部で活躍する。新曲を作曲して、それが選ばれることになる。音楽家しての裕一の才能の発露といっていいだろう。
第二は、養子のこと。
家の仕事がうまくいかない。融資をうける条件として、兄弟のうちどちらかが養子に行かなければならない。家業は、弟が継ぐことになって、結局、裕一が家を出る。
第三は、銀行のこと。
養子に出るとして、まず、裕一は銀行員になる。そこで修行をしてということらしい。この銀行での、他の行員とのやりとりがコミカルで面白かった。
第四には、ダンスホールのこと。
銀行の仲間にさそわれて、裕一はダンスホールに行くことになる。そこで、踊り子の志津と出会う。どうやら一目惚れのようだった。そして、接吻大作戦となる。その結末は、まさに意外な展開であった。
以上のようなことがこの週の見どころであったかと思う。
それから、子どものころの仲間である鉄男が登場していた。これから、裕一の音楽の友になるのだろう。
次週以降、いよいよ、音と裕一の人生が交錯するようである。これも楽しみに見ることにしよう。
2020年4月18日記
追記 2020-04-26
この続きは、
やまもも書斎記 2020年4月26日
『エール』あれこれ「君はるか」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/04/26/9239365
この続きは、
やまもも書斎記 2020年4月26日
『エール』あれこれ「君はるか」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/04/26/9239365
『源氏物語』岩波文庫(五) ― 2020-04-20
2020-04-20 當山日出夫(とうやまひでお)
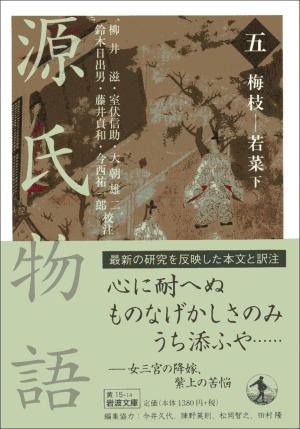
柳井滋(他)(校注).『源氏物語(五)』(岩波文庫).岩波書店.2019
https://www.iwanami.co.jp/book/b440441.html
続きである。
やまもも書斎記
『源氏物語』岩波文庫(四)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/04/13/9234836
第五冊には、「梅枝」から「若菜上」「若菜下」までをおさめる。実質的、「若菜」の上下巻が大部分をしめる。
この第四冊を読んで思うことを記してみる。
第一には、『源氏物語』が「書かれた」文学であるということの再確認である。あるいは、『源氏物語』は、ことばを文字に書くとくことに、非常に自覚的であるといってもよい。そのことが、端的に表れているのが、「梅枝」の巻にみられる、仮名についての様々な言及。
おそらく大きな流れとしては、九世紀には仮名ができていたであろう。そして、「草(そう)」とも異なるものとして、「仮名」が生まれてくることになる。さらには、そのなかにおいても、「女手」と称されるべき、特に女性に好まれる仮名の書風があったと推測される。
『源氏物語』は、仮名文というものが誕生してから生まれた文学である。その仮名文は、どう書かれ、読まれたのであろうか。
たぶん、音読ということもあったにちがいない。いわゆる、源氏物語音読論である。『源氏物語』のなかにも、紫の上などが、女房などに、物語を読んで聴かせるというシーンがある。また、岩波文庫本の底本である大島本の表記……岩波文庫は、仮名遣いを原則的に歴史的仮名遣いに改める他は、底本の表記をたどれるように本文がつくってある……を見ると、音読したのでなければそのようにはならないであろう各種の表記が目につく。たとえば、「几帳」であるが、これが、普通の古語の表記とされる「几帳」の文字で出てくることは、希であるとさえいっていいだろう。多くは、他の漢字による当て字である。
その他、踊り字(繰り返し符号)の使い方などみても、文法的な語の表記の切れ目と合致しない例が非常に多い。
とにかく、大島本の表記は、目で読むものとしてよりも音読するテクストであったとおぼしい箇所が多く見られる。
だが、『源氏物語』の文章を読んでみて感じることだが、これは、音読の音声を聞いていただけでは、たぶん理解できないと思われるところもある。平安朝古文に特有のことだが、とにかく主語などの省略が多い。いったい誰が、誰に向かって、何のことを言っているのか、その前後を読み、あるいは、数行先のところまで読んで戻って考えてみないと理解できないようなところがたくさんある。このような箇所を見ると、これは、音読を聞いただけで理解できず、じっくりと目で読むということがあったにちがいないとも、考えられる。
第二には、「若菜」(上・下)で感じたことであるが、このあたりになって、「老い」というものを、感じさせるようになってきた。以前に読んだときには、あまりそのようなことは思って読まなかった。しかし、今回読んでみて、ふと人生の晩年にさしかかって、自分のこれからのこと、死と老いということが、この巻の底流にあることを、強く感じた。
光源氏は、女三宮の降嫁を受け入れる。女三宮は若い、というよりも、むしろ幼い。その幼さの故に、柏木との不倫ということにもなるのであるが……その女三宮との関係において、光源氏は、自らの年齢のことを思い、また、過去の様々な女性とのこと、その中には、藤壷との関係も含まれることになるが、過去を回想する。
また、紫の上も出家を願い、病気にもなる。ここで、六条御息所のもののけが現れることになる。幸い、ここでは、まだ紫の上は死なない。だが、出家への思いは強い。だが、光源氏は、それを許さない。自分より先に紫の上が出家して、世を離れてしまうことを許す気にはなれない。
このようなところ、年老いてきた光源氏というものを感じる。表面的には、準太上天皇ということで、栄達の極みに達するのであるが、それと同時に、その人生には、老いの影がしのびこんできている。
以上の二点が、第四冊を読んで感じるところなどである。
「若菜」(上・下)の巻は、若いときに読んだ。岩波の旧日本古典大系本であった。学生のころであった。池田彌三郎先生は、『源氏物語』は、「若菜」(上・下)をきちんと読んでおくと、それまでのストーリーがそこに吸収され、また、そこから新たな次のストーリーが展開していく、核になる部分である……このような意味のことを語っておられた。そのせいもあって、とにかく「若菜」(上・下)は読んだものである。
若いときに読んだ印象としては、女三宮と柏木との不倫のことに関心があった。今、読んでも、「若菜」(上・下)のメインのテーマが、ここにあることは確かなのであるが、それだけではない、様々な人生の悲喜こもごもが、このところに凝縮されて描かれていることを思う。
『源氏物語』は、現在までの既刊分としては、後二冊。続けてこれを読んでしまおうと思っている。
2020年2月10日記
https://www.iwanami.co.jp/book/b440441.html
続きである。
やまもも書斎記
『源氏物語』岩波文庫(四)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/04/13/9234836
第五冊には、「梅枝」から「若菜上」「若菜下」までをおさめる。実質的、「若菜」の上下巻が大部分をしめる。
この第四冊を読んで思うことを記してみる。
第一には、『源氏物語』が「書かれた」文学であるということの再確認である。あるいは、『源氏物語』は、ことばを文字に書くとくことに、非常に自覚的であるといってもよい。そのことが、端的に表れているのが、「梅枝」の巻にみられる、仮名についての様々な言及。
おそらく大きな流れとしては、九世紀には仮名ができていたであろう。そして、「草(そう)」とも異なるものとして、「仮名」が生まれてくることになる。さらには、そのなかにおいても、「女手」と称されるべき、特に女性に好まれる仮名の書風があったと推測される。
『源氏物語』は、仮名文というものが誕生してから生まれた文学である。その仮名文は、どう書かれ、読まれたのであろうか。
たぶん、音読ということもあったにちがいない。いわゆる、源氏物語音読論である。『源氏物語』のなかにも、紫の上などが、女房などに、物語を読んで聴かせるというシーンがある。また、岩波文庫本の底本である大島本の表記……岩波文庫は、仮名遣いを原則的に歴史的仮名遣いに改める他は、底本の表記をたどれるように本文がつくってある……を見ると、音読したのでなければそのようにはならないであろう各種の表記が目につく。たとえば、「几帳」であるが、これが、普通の古語の表記とされる「几帳」の文字で出てくることは、希であるとさえいっていいだろう。多くは、他の漢字による当て字である。
その他、踊り字(繰り返し符号)の使い方などみても、文法的な語の表記の切れ目と合致しない例が非常に多い。
とにかく、大島本の表記は、目で読むものとしてよりも音読するテクストであったとおぼしい箇所が多く見られる。
だが、『源氏物語』の文章を読んでみて感じることだが、これは、音読の音声を聞いていただけでは、たぶん理解できないと思われるところもある。平安朝古文に特有のことだが、とにかく主語などの省略が多い。いったい誰が、誰に向かって、何のことを言っているのか、その前後を読み、あるいは、数行先のところまで読んで戻って考えてみないと理解できないようなところがたくさんある。このような箇所を見ると、これは、音読を聞いただけで理解できず、じっくりと目で読むということがあったにちがいないとも、考えられる。
第二には、「若菜」(上・下)で感じたことであるが、このあたりになって、「老い」というものを、感じさせるようになってきた。以前に読んだときには、あまりそのようなことは思って読まなかった。しかし、今回読んでみて、ふと人生の晩年にさしかかって、自分のこれからのこと、死と老いということが、この巻の底流にあることを、強く感じた。
光源氏は、女三宮の降嫁を受け入れる。女三宮は若い、というよりも、むしろ幼い。その幼さの故に、柏木との不倫ということにもなるのであるが……その女三宮との関係において、光源氏は、自らの年齢のことを思い、また、過去の様々な女性とのこと、その中には、藤壷との関係も含まれることになるが、過去を回想する。
また、紫の上も出家を願い、病気にもなる。ここで、六条御息所のもののけが現れることになる。幸い、ここでは、まだ紫の上は死なない。だが、出家への思いは強い。だが、光源氏は、それを許さない。自分より先に紫の上が出家して、世を離れてしまうことを許す気にはなれない。
このようなところ、年老いてきた光源氏というものを感じる。表面的には、準太上天皇ということで、栄達の極みに達するのであるが、それと同時に、その人生には、老いの影がしのびこんできている。
以上の二点が、第四冊を読んで感じるところなどである。
「若菜」(上・下)の巻は、若いときに読んだ。岩波の旧日本古典大系本であった。学生のころであった。池田彌三郎先生は、『源氏物語』は、「若菜」(上・下)をきちんと読んでおくと、それまでのストーリーがそこに吸収され、また、そこから新たな次のストーリーが展開していく、核になる部分である……このような意味のことを語っておられた。そのせいもあって、とにかく「若菜」(上・下)は読んだものである。
若いときに読んだ印象としては、女三宮と柏木との不倫のことに関心があった。今、読んでも、「若菜」(上・下)のメインのテーマが、ここにあることは確かなのであるが、それだけではない、様々な人生の悲喜こもごもが、このところに凝縮されて描かれていることを思う。
『源氏物語』は、現在までの既刊分としては、後二冊。続けてこれを読んでしまおうと思っている。
2020年2月10日記







最近のコメント