『街道をゆく 甲賀と伊賀のみち、砂鉄のみち ほか』司馬遼太郎/朝日文庫 ― 2023-07-08
2023年7月8日 當山日出夫

司馬遼太郎.『街道をゆく 甲賀と伊賀のみち、砂鉄のみち ほか』(朝日文庫).朝日新聞出版.2008
https://publications.asahi.com/kaidou/07/index.shtml
もとは、一九七三年から七五年にかけて、「週刊朝日」連載。
収録するのは、
「甲賀と伊賀のみち」
「大和・壺坂のみち」
「明石海峡と淡路みち」
「砂鉄のみち」
司馬遼太郎の語る日本の歴史は、基本的にコメを基本としている。弥生時代になって米作をおこなうひとびとが日本にやってきて、日本でコメを作るようになった。その影響下に、その後の歴史はずっとある。武士の成立もそうであるし、戦国の時代も、また、江戸時代から近代にいたるまで、米作を基盤に日本の文化があるとする。
だが、時として、米作からはなれた論考を語ることがある。この本の中では、漁業民のことが出てくる。淡路に行ったときのこととしてである。漁業で生計をたててきた人びとのことに思いをはせている。
また、砂鉄のことにふれて、古代の出雲や中国地方において、製鉄をなりわいとしていた人びとのことを、いろいろと考えている。
漁業にせよ、製鉄にせよ、いわゆる非農業民である。これらの人びとが、古代からどのように暮らしてきたのか、これはこれで興味のあるところである。
ところで、ちょっと前のことになるが、NHKで、タタラ製鉄のことをやっていたのを思い出す。これはちょっと大変な仕事であると思って見ていた。今も、タタラの技法は、どうにか受け継がれているようである。
この本をスタートにして、日本における漁業史、あるいは、製鉄史ということを考えてみてもいいのかもしれない。が、今しばらくは、「街道をゆく」を続けて読んでいきたいと思っている。
2023年7月2日記
https://publications.asahi.com/kaidou/07/index.shtml
もとは、一九七三年から七五年にかけて、「週刊朝日」連載。
収録するのは、
「甲賀と伊賀のみち」
「大和・壺坂のみち」
「明石海峡と淡路みち」
「砂鉄のみち」
司馬遼太郎の語る日本の歴史は、基本的にコメを基本としている。弥生時代になって米作をおこなうひとびとが日本にやってきて、日本でコメを作るようになった。その影響下に、その後の歴史はずっとある。武士の成立もそうであるし、戦国の時代も、また、江戸時代から近代にいたるまで、米作を基盤に日本の文化があるとする。
だが、時として、米作からはなれた論考を語ることがある。この本の中では、漁業民のことが出てくる。淡路に行ったときのこととしてである。漁業で生計をたててきた人びとのことに思いをはせている。
また、砂鉄のことにふれて、古代の出雲や中国地方において、製鉄をなりわいとしていた人びとのことを、いろいろと考えている。
漁業にせよ、製鉄にせよ、いわゆる非農業民である。これらの人びとが、古代からどのように暮らしてきたのか、これはこれで興味のあるところである。
ところで、ちょっと前のことになるが、NHKで、タタラ製鉄のことをやっていたのを思い出す。これはちょっと大変な仕事であると思って見ていた。今も、タタラの技法は、どうにか受け継がれているようである。
この本をスタートにして、日本における漁業史、あるいは、製鉄史ということを考えてみてもいいのかもしれない。が、今しばらくは、「街道をゆく」を続けて読んでいきたいと思っている。
2023年7月2日記
『街道をゆく 韓のくに紀行』司馬遼太郎/朝日文庫 ― 2023-07-06
2023年7月6日 當山日出夫
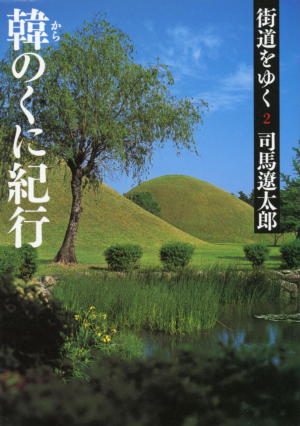
司馬遼太郎.『街道をゆく 韓のくに紀行』(朝日文庫).朝日新聞出版.2008
https://publications.asahi.com/kaidou/02/index.shtml
もとは、一九七一年から七二年、「週刊朝日」連載。
「街道をゆくシリーズ」の二冊目である。つまり、このシリーズが始まって早いころに司馬遼太郎は、韓国に行っている。一九七二年というと、私は高校生のころになる。
この時代の韓国はどんなだったろうか。歴史的には、まだ軍事政権下ということになる。このころ、「北朝鮮」のことがテレビのニュースなどで出てくると、必ず、「朝鮮民主主義人民共和国」と、追加して言っていたのを憶えている。これが、単に「北朝鮮」とだけ呼称するようになったのは、いつごろからになるだろうか。
司馬遼太郎の書いたものとしては、やや異質な感じがする。公平な目で歴史を見るという観点が乏しいと言わざるをえない。とにかく悪いのは、秀吉の朝鮮派兵であり、近代になってからの併合である。そして、あくまでも美しいのは、李氏朝鮮であり、儒教であり、田舎の風景である。
かなりバイアスのかかった見方で書かれている。
だが、この当時、「週刊朝日」というところに書くとなると、このような書き方にならざるをえなかったのか、という観点から、これはこれで、ある意味で歴史的価値のある文章であると読める。
大邱のホテルでのマッサージ師のくだりは、まあ、こんなふうに考えれば考えることもできるかなあ、というぐらいで読んでおくのがいいのだろう。
それにしても、もし、司馬遼太郎が生きていて、今の韓国、あるいは、日韓関係のことを見たらどんなふうに書くだろうかと、思ってみたくなる。
2023年6月30日記
https://publications.asahi.com/kaidou/02/index.shtml
もとは、一九七一年から七二年、「週刊朝日」連載。
「街道をゆくシリーズ」の二冊目である。つまり、このシリーズが始まって早いころに司馬遼太郎は、韓国に行っている。一九七二年というと、私は高校生のころになる。
この時代の韓国はどんなだったろうか。歴史的には、まだ軍事政権下ということになる。このころ、「北朝鮮」のことがテレビのニュースなどで出てくると、必ず、「朝鮮民主主義人民共和国」と、追加して言っていたのを憶えている。これが、単に「北朝鮮」とだけ呼称するようになったのは、いつごろからになるだろうか。
司馬遼太郎の書いたものとしては、やや異質な感じがする。公平な目で歴史を見るという観点が乏しいと言わざるをえない。とにかく悪いのは、秀吉の朝鮮派兵であり、近代になってからの併合である。そして、あくまでも美しいのは、李氏朝鮮であり、儒教であり、田舎の風景である。
かなりバイアスのかかった見方で書かれている。
だが、この当時、「週刊朝日」というところに書くとなると、このような書き方にならざるをえなかったのか、という観点から、これはこれで、ある意味で歴史的価値のある文章であると読める。
大邱のホテルでのマッサージ師のくだりは、まあ、こんなふうに考えれば考えることもできるかなあ、というぐらいで読んでおくのがいいのだろう。
それにしても、もし、司馬遼太郎が生きていて、今の韓国、あるいは、日韓関係のことを見たらどんなふうに書くだろうかと、思ってみたくなる。
2023年6月30日記
『白河・会津のみち、赤坂散歩』司馬遼太郎/朝日文庫 ― 2023-07-04
2023年7月4日 當山日出夫
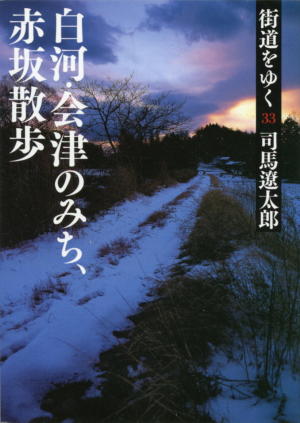
司馬遼太郎.『白河・会津のみち、赤坂散歩』(朝日文庫).朝日新聞出版.2009
https://publications.asahi.com/kaidou/33/index.shtml
もとは、一九八八年から八九年。「週刊朝日」連載。
東北の方にはほとんど行ったことがない。白河と言われても、名前を知っている。あるいは、古典の知識として「白河の関」を知っている程度である。
会津にも行ったことがない。
この本を読むと、古風なひなびた景色が、これが書かれた時代まではまだ残っていたことが知られる。
会津のことは、以前のNHKの大河ドラマの『八重の桜』のイメージが強い。幕末の時代にあって、貧乏くじをひくことになった……と言っていいかどうかは微妙だが……の会津藩の悲哀が、強く印象に残っている。
「赤坂散歩」は、この「街道をゆく」シリーズで、始めて取りあげた東京ということになる。それを赤坂から始めることとしたのは、本所深川のあたりは土俗的にすぎるという理由もあり、また、自分の家、東京での宿から、出発してその地のことを考えるというスタイルにも由来するもののようだ。
司馬遼太郎は、オークラに宿泊すると決めていたらしい。そういえば、たしか以前読んだ高峰秀子のエッセイに、司馬遼太郎とオークラで会うシーンがあったように記憶するのだが、どうだったろうか。
自分の家から出発して考えるというのは、先に読んだ「十津川村」についてもいえる。司馬遼太郎は、十津川村に大阪から入っている。自分の住まいする場所から見ての十津川村を描いている。
赤坂あたりは、昔は閑静な街でもあった。そのころの面影を、司馬遼太郎はたどっている。今の赤坂はどうだろうか。都会のまんなかという印象になってしまった感じがする。もう東京に行っても赤坂あたりを歩くことはないだろうと思う。昔、学生のころは、赤坂見附から国立劇場まで歩いたりしたものであったが。
2023年6月30日記
https://publications.asahi.com/kaidou/33/index.shtml
もとは、一九八八年から八九年。「週刊朝日」連載。
東北の方にはほとんど行ったことがない。白河と言われても、名前を知っている。あるいは、古典の知識として「白河の関」を知っている程度である。
会津にも行ったことがない。
この本を読むと、古風なひなびた景色が、これが書かれた時代まではまだ残っていたことが知られる。
会津のことは、以前のNHKの大河ドラマの『八重の桜』のイメージが強い。幕末の時代にあって、貧乏くじをひくことになった……と言っていいかどうかは微妙だが……の会津藩の悲哀が、強く印象に残っている。
「赤坂散歩」は、この「街道をゆく」シリーズで、始めて取りあげた東京ということになる。それを赤坂から始めることとしたのは、本所深川のあたりは土俗的にすぎるという理由もあり、また、自分の家、東京での宿から、出発してその地のことを考えるというスタイルにも由来するもののようだ。
司馬遼太郎は、オークラに宿泊すると決めていたらしい。そういえば、たしか以前読んだ高峰秀子のエッセイに、司馬遼太郎とオークラで会うシーンがあったように記憶するのだが、どうだったろうか。
自分の家から出発して考えるというのは、先に読んだ「十津川村」についてもいえる。司馬遼太郎は、十津川村に大阪から入っている。自分の住まいする場所から見ての十津川村を描いている。
赤坂あたりは、昔は閑静な街でもあった。そのころの面影を、司馬遼太郎はたどっている。今の赤坂はどうだろうか。都会のまんなかという印象になってしまった感じがする。もう東京に行っても赤坂あたりを歩くことはないだろうと思う。昔、学生のころは、赤坂見附から国立劇場まで歩いたりしたものであったが。
2023年6月30日記
『若草物語』オルコット/麻生九美(訳)/光文社古典新訳文庫 ― 2023-07-03
2023年7月3日 當山日出夫

オルコット.麻生九美(訳).『若草物語』(光文社古典新訳文庫).光文社.2017
https://www.kobunsha.com/shelf/book/isbn/9784334753634
駒井稔の『編集者の読書論』を読んだら、これを読みたくなったので手にした。
やまもも書斎記 2023年6月6日
『編集者の読書論』駒井稔/光文社新書
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2023/06/06/9592259
この作品のことは小さいときから知っている。小学生か中学生かのころに、翻案抄訳本を読んだだろうか。だいたいのことは知っている。しかし、きちんと読んでみるのは初めてになる。
読んで思うこととしては、読んで面白い作品だということである。なるほど、アメリカの南北戦争の時代に書かれた作品が、今にいたるまで読み継がれているのには、それなりのわけがあると理解される。
思うこととして、やはり次の二点がある。
第一には、古風な価値観。
今の価値観からすれば、保守的で古めかしい価値観の作品ではある。だが、これは、この作品が書かれた時代……アメリカの南北戦争の時代……ということを考えれば、そのような女性の生き方が考えられた時代があったと思うことになる。
このあたり、ある意味では、安心して読める作品ということになっているのかもしれない。
第二には、新しい女性。
そうはいっても、この作品に出てくる女性たちはたくましい。時代の流れのなかにあって、おかれた境遇のなかで、自分の生きる道を見出そうとしている。自分の才覚で生きていこうとする。特に、このことは、次女のジョーについて強く感じるところである。
時代の状況のなかにあって、新しい生き方を求める女性の姿、これがこの作品の魅力なのかとも思う。
以上のように、古風さと新しさを、この作品には感じ取ることができる。
そしてなによりも、この作品の根底にある人間観がいい。今のことばでいえば、ヒューマニズムといっていいだろうか。人間というものをあくまでも肯定的に見ている。また、その人間のあつまりのなかにおいて、人間性の最も善良な部分を描き出している。これが、今の時代の文学なら、人間性の邪悪な部分をえぐるような作品もあり得よう。しかし、そうなってはいない。あくまでも、人間というものを、よきものとして描いている。この人間観が、この作品の最大の魅力といっていいだろうか。
『若草物語』は、日本語訳のタイトルである。光文社古典新訳文庫は、新しい訳本を作るにあたって、それまでの翻訳タイトルを改めることが多い。しかし、この作品については、原題「LITTLE WOMEN」をそのまま日本語にすることはしていない。従来の『若草物語』を採用している。
この作品が、日本で長く読まれてきていることの理由の一つには、このタイトルの魅力もあるのだろうと思う。
2023年6月6日記
https://www.kobunsha.com/shelf/book/isbn/9784334753634
駒井稔の『編集者の読書論』を読んだら、これを読みたくなったので手にした。
やまもも書斎記 2023年6月6日
『編集者の読書論』駒井稔/光文社新書
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2023/06/06/9592259
この作品のことは小さいときから知っている。小学生か中学生かのころに、翻案抄訳本を読んだだろうか。だいたいのことは知っている。しかし、きちんと読んでみるのは初めてになる。
読んで思うこととしては、読んで面白い作品だということである。なるほど、アメリカの南北戦争の時代に書かれた作品が、今にいたるまで読み継がれているのには、それなりのわけがあると理解される。
思うこととして、やはり次の二点がある。
第一には、古風な価値観。
今の価値観からすれば、保守的で古めかしい価値観の作品ではある。だが、これは、この作品が書かれた時代……アメリカの南北戦争の時代……ということを考えれば、そのような女性の生き方が考えられた時代があったと思うことになる。
このあたり、ある意味では、安心して読める作品ということになっているのかもしれない。
第二には、新しい女性。
そうはいっても、この作品に出てくる女性たちはたくましい。時代の流れのなかにあって、おかれた境遇のなかで、自分の生きる道を見出そうとしている。自分の才覚で生きていこうとする。特に、このことは、次女のジョーについて強く感じるところである。
時代の状況のなかにあって、新しい生き方を求める女性の姿、これがこの作品の魅力なのかとも思う。
以上のように、古風さと新しさを、この作品には感じ取ることができる。
そしてなによりも、この作品の根底にある人間観がいい。今のことばでいえば、ヒューマニズムといっていいだろうか。人間というものをあくまでも肯定的に見ている。また、その人間のあつまりのなかにおいて、人間性の最も善良な部分を描き出している。これが、今の時代の文学なら、人間性の邪悪な部分をえぐるような作品もあり得よう。しかし、そうなってはいない。あくまでも、人間というものを、よきものとして描いている。この人間観が、この作品の最大の魅力といっていいだろうか。
『若草物語』は、日本語訳のタイトルである。光文社古典新訳文庫は、新しい訳本を作るにあたって、それまでの翻訳タイトルを改めることが多い。しかし、この作品については、原題「LITTLE WOMEN」をそのまま日本語にすることはしていない。従来の『若草物語』を採用している。
この作品が、日本で長く読まれてきていることの理由の一つには、このタイトルの魅力もあるのだろうと思う。
2023年6月6日記
『街道をゆく 十津川街道』司馬遼太郎/朝日文庫 ― 2023-07-02
2023年7月2日 當山日出夫

司馬遼太郎.『街道をゆく 十津川街道』(朝日文庫).朝日新聞出版.2008
https://publications.asahi.com/kaidou/12/index.shtml
もとは一九七七年から七八年、「週刊朝日」に連載。
この本は、とにかく理屈っぽい。奈良県の十津川村とその周辺……その当時の大塔村のことなどをふくめて……が語られるのだが、十津川村がなぜ、周囲から孤立した山の中の村なのか、理詰めで考えようとしている。その特殊性が、これでもかと強調されている。
歴史の話題としては、主に南北朝のころ、戦国時代、さらには、幕末のころのことが出てくる。これを読むと、確かに十津川村の人びとが、かなり特別な働きをしていたと思うところがある。
ただ、これも今の観点から見ると、一昔前、二昔前の十津川村の情景を記した紀行文として読むこともできる。今の十津川村は、過疎の村である。だが、道路が整備された今日からすると、司馬遼太郎が旅したころの十津川は、さらにひなびた村であったことが分かる。電灯がついたの、戦後になってからであるというようなエピソードが出てくる。
NHKのローカルのニュース、天気予報では、十津川村は頻繁に出てくる。特に風屋という地名は、気象の観測点になってもいる。日常的に馴染みのあるところではあるのだが、行ってみようと思うと、これは大変である。たぶん、泊まりがけで行くようなところになる。奈良県の北の方に住んでいると、どうしてもそういう感覚を持ってしまう。
奈良県に住んでいると、十津川村を、県の北部から見てしまいがちである。しかし、司馬遼太郎は、大阪の方から十津川村に入っている。あるいは、大阪に住まいする司馬遼太郎として、これが自然な見方なのかとも思う。
司馬遼太郎が若いとき、徒歩で旅行して知らずに寺の納屋で寝てしまっていて、翌日、粥を御馳走になったエピソードがいい。この時代、そのように旅をすることができた時代であり、また、旅人をもてなす気持ちが生きていた時代である。(宮本常一のことをふと思ってしまった。)
なお、十津川村は、日本語学、特にアクセント研究の分野では著名なところである。しかし、この本のなかでそのことに言及していなかったのは、ちょっとさびしい。
2023年6月29日記
https://publications.asahi.com/kaidou/12/index.shtml
もとは一九七七年から七八年、「週刊朝日」に連載。
この本は、とにかく理屈っぽい。奈良県の十津川村とその周辺……その当時の大塔村のことなどをふくめて……が語られるのだが、十津川村がなぜ、周囲から孤立した山の中の村なのか、理詰めで考えようとしている。その特殊性が、これでもかと強調されている。
歴史の話題としては、主に南北朝のころ、戦国時代、さらには、幕末のころのことが出てくる。これを読むと、確かに十津川村の人びとが、かなり特別な働きをしていたと思うところがある。
ただ、これも今の観点から見ると、一昔前、二昔前の十津川村の情景を記した紀行文として読むこともできる。今の十津川村は、過疎の村である。だが、道路が整備された今日からすると、司馬遼太郎が旅したころの十津川は、さらにひなびた村であったことが分かる。電灯がついたの、戦後になってからであるというようなエピソードが出てくる。
NHKのローカルのニュース、天気予報では、十津川村は頻繁に出てくる。特に風屋という地名は、気象の観測点になってもいる。日常的に馴染みのあるところではあるのだが、行ってみようと思うと、これは大変である。たぶん、泊まりがけで行くようなところになる。奈良県の北の方に住んでいると、どうしてもそういう感覚を持ってしまう。
奈良県に住んでいると、十津川村を、県の北部から見てしまいがちである。しかし、司馬遼太郎は、大阪の方から十津川村に入っている。あるいは、大阪に住まいする司馬遼太郎として、これが自然な見方なのかとも思う。
司馬遼太郎が若いとき、徒歩で旅行して知らずに寺の納屋で寝てしまっていて、翌日、粥を御馳走になったエピソードがいい。この時代、そのように旅をすることができた時代であり、また、旅人をもてなす気持ちが生きていた時代である。(宮本常一のことをふと思ってしまった。)
なお、十津川村は、日本語学、特にアクセント研究の分野では著名なところである。しかし、この本のなかでそのことに言及していなかったのは、ちょっとさびしい。
2023年6月29日記
『街道をゆく 叡山の諸道』司馬遼太郎/朝日文庫 ― 2023-07-01
2023年6月30日 當山日出夫

司馬遼太郎.『街道をゆく 叡山の諸道』(朝日文庫).朝日新聞出版.2008
https://publications.asahi.com/kaidou/16/index.shtml
もとは、一九七九年から八〇年に「週刊朝日」。
比叡山には登ったことはある。だが、そんなに考えることなく、見て帰っただけである。
司馬遼太郎の比叡山概論というべき内容である。古く最澄の事跡からはじまって、現代にまで伝わる法華大会の見学のときのことにおよぶ。
日本仏教史の専門家の目から見れば、いろいろと言いたいことがあるだろうと思う。
しかし、紀行文として読めば、とてもいい。比叡山をおとずれて、その雰囲気を感じとっている。比叡山にはきらびやかさがない。かつて、平安朝には貴族とともに栄えた寺ではあるが、その後、ある意味ではさびれてしまったとも言える。無論、信長の焼き討ち以降は、かつての面影はほとんどない。が、比叡の深山幽谷には、むかしの面影をしのぶことができる。
この本を読んで、(この本には出てこない)『源氏物語』のことを思った。その最後のところである。比叡の山のなかで、世から引きこもってしまうことを決意する浮舟が、どんな住まいをしていたのか、想像してみることになる。
また、比叡山について書いていながら、ほとんど京都のことが出てこない。出てくるのは、むしろ近江の方面である。私にとって、比叡山というのは、京都の街から見るものというイメージが強いのだが、近江から見る比叡山の視点もまた興味深いものがある。
この本の書かれたころの比叡山は、魑魅魍魎、もののけなどがいてもおかしくない。今はどうだろうか。
2023年6月29日記
https://publications.asahi.com/kaidou/16/index.shtml
もとは、一九七九年から八〇年に「週刊朝日」。
比叡山には登ったことはある。だが、そんなに考えることなく、見て帰っただけである。
司馬遼太郎の比叡山概論というべき内容である。古く最澄の事跡からはじまって、現代にまで伝わる法華大会の見学のときのことにおよぶ。
日本仏教史の専門家の目から見れば、いろいろと言いたいことがあるだろうと思う。
しかし、紀行文として読めば、とてもいい。比叡山をおとずれて、その雰囲気を感じとっている。比叡山にはきらびやかさがない。かつて、平安朝には貴族とともに栄えた寺ではあるが、その後、ある意味ではさびれてしまったとも言える。無論、信長の焼き討ち以降は、かつての面影はほとんどない。が、比叡の深山幽谷には、むかしの面影をしのぶことができる。
この本を読んで、(この本には出てこない)『源氏物語』のことを思った。その最後のところである。比叡の山のなかで、世から引きこもってしまうことを決意する浮舟が、どんな住まいをしていたのか、想像してみることになる。
また、比叡山について書いていながら、ほとんど京都のことが出てこない。出てくるのは、むしろ近江の方面である。私にとって、比叡山というのは、京都の街から見るものというイメージが強いのだが、近江から見る比叡山の視点もまた興味深いものがある。
この本の書かれたころの比叡山は、魑魅魍魎、もののけなどがいてもおかしくない。今はどうだろうか。
2023年6月29日記
『街道をゆく 本所深川散歩、神田界隈』司馬遼太郎/朝日文庫 ― 2023-06-30
2023年6月30日 當山日出夫
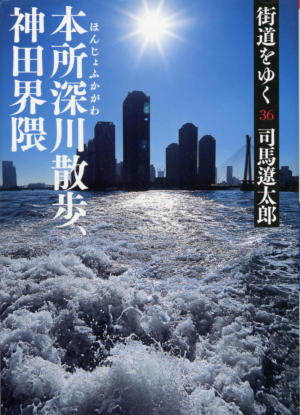
司馬遼太郎.『街道をゆく 本所深川散歩、神田界隈』(朝日文庫).朝日新聞出版.2009
https://publications.asahi.com/kaidou/36/index.shtml
もとは、一九九〇年から九一年、「週刊朝日」連載。
「本郷界隈」につづいて読んだ。連載の順番からいうと、こちらの方が先になる。
本所深川あたりには、ほとんど土地勘がない。東京に住んでいるときも、隅田川を見たことはほとんどなかったと思う。
しかし、江戸から東京の歴史を考えるとき、この地域は重要である。
司馬遼太郎が、落語好きであるということを、この本を読んで初めて知った。随所に落語のことが出てくる。
神田は神保町のあたりが話しの中心となる。岩波書店のこと、岡茂雄の『本屋風情』のこと、反町茂雄のことなどが出てくる。神田が、明治から学校の街であり、それにともなって本の街になった経緯が興味深く綴られる。このあたりは、東京のなかでもよく知っている地域なので、面白く読んだ。
2023年6月29日記
https://publications.asahi.com/kaidou/36/index.shtml
もとは、一九九〇年から九一年、「週刊朝日」連載。
「本郷界隈」につづいて読んだ。連載の順番からいうと、こちらの方が先になる。
本所深川あたりには、ほとんど土地勘がない。東京に住んでいるときも、隅田川を見たことはほとんどなかったと思う。
しかし、江戸から東京の歴史を考えるとき、この地域は重要である。
司馬遼太郎が、落語好きであるということを、この本を読んで初めて知った。随所に落語のことが出てくる。
神田は神保町のあたりが話しの中心となる。岩波書店のこと、岡茂雄の『本屋風情』のこと、反町茂雄のことなどが出てくる。神田が、明治から学校の街であり、それにともなって本の街になった経緯が興味深く綴られる。このあたりは、東京のなかでもよく知っている地域なので、面白く読んだ。
2023年6月29日記
『街道をゆく 本郷界隈』司馬遼太郎/朝日文庫 ― 2023-06-29
2023年6月29日 當山日出夫

司馬遼太郎.『街道をゆく 本郷界隈』(朝日文庫).朝日新聞出版.2009
https://publications.asahi.com/kaidou/37/index.shtml
もとは、一九九一年から九二年、「週刊朝日」連載。
これは面白かった。
本郷には行くことがある。秋の訓点語学会が東京大学で開催ということになってから、年に一回は東大に行く。これも、COVID-19のせいで、しばらく行っていない。オンライン開催が続いた。
本郷、東大の周辺は、そんなに詳しいということではないが、しかし、東京のなかでは、比較的知っている地域になる。
本郷界隈ということで、主に東京大学を中心として、その周辺の地域をめぐり、関連する人びと、歴史的なできごとへと、次から次へと連想の赴くままに、筆がすすんでいる。
夏目漱石、森鷗外、樋口一葉といった近代の文学者はもちろん、朱舜水、最上徳内、水戸光圀など、多方面にわたる。無論、東京大学のあった前田家のことについても詳しい。
また東京大学を論じて、明治という時代についても言及する。
馴染みの地名が多く出てくるせいかもしれないが、これまで読んだ「街道をゆく」のなかでは、特に面白いものである。これは、大仰な日本文化論、日本史講釈が出てこないせいかもしれない。まあ、このあたりは読む人の好みの分かれるところかもしれないが。
司馬遼太郎の書いた、漱石の『三四郞』論として読んでも興味深い。
2023年6月27日記
『街道をゆく 北海道の諸道』司馬遼太郎/朝日文庫 ― 2023-06-28
2023年6月28日 當山日出夫
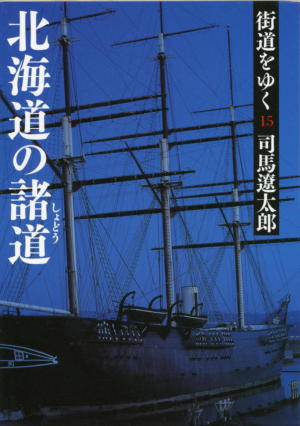
司馬遼太郎.『街道をゆく 北海道の諸道』(朝日文庫).朝日新聞出版.2008
https://publications.asahi.com/kaidou/15/index.shtml
もとは一九七九年に「週刊朝日」に連載。このころは、私の大学生のころになる。
『オホーツク街道』を読んだので、北海道について書いたものを読んでみたくなった。なるほど、この本の後に『オホーツク街道』を書いた理由が分かるような気がする。
主に、近世、幕末の北海道の話しである。函館の話しが多い。松前のことも出てくる。このあたりは、他の司馬遼太郎の本でも出てくるかと思う。読んで特に印象に残るのは、近代になってからの北海道の開拓の話しである。その開拓者の苦労が語られる。
樺戸集治監のことは、名前は知っていた。山田風太郎の小説に出てくる。
榎本武揚については、かなり以前に『武揚伝』(佐々木譲)を読んだのを憶えている。
この本を読んで感じることとしては、司馬遼太郎の批判精神である。それがあたっているかどうかは別としても、弥生時代以降の日本の文化の基底をなすものとしてコメを重視している。たしかに、そのような歴史観もなりたつとは思う。これも、現代の歴史学からすれば、批判的に再検討することもあるかとは思うが。
また、随所に、司馬遼太郎自身が兵隊であったときのことが出てくる。司馬遼太郎にとって、日本の近代、特に昭和になってからの軍隊というものは、徹底的に嫌悪するものである。
新十津川村のことも出てくる。今、奈良県に住んでいるので、NHKのローカルニュースを見ていると、県内のこととして十津川村はしょっちゅう登場する。司馬遼太郎は、十津川村には、そうとうの思い入れがあるようだ。(ただ、これも、今の私の感覚からすると、奈良県の十津川村は、過疎地の一つということにはなるのだが。奈良県のニュースで、北海道の新十津川村のことは出てこない。)
ラストは、関寛斎のこと。『胡蝶の夢』は読んだのを憶えている。『胡蝶の夢』における関寛斎は印象深い。この『北海道の諸道』における関寛斎についての記述も印象的である。
2023年6月26日記
https://publications.asahi.com/kaidou/15/index.shtml
もとは一九七九年に「週刊朝日」に連載。このころは、私の大学生のころになる。
『オホーツク街道』を読んだので、北海道について書いたものを読んでみたくなった。なるほど、この本の後に『オホーツク街道』を書いた理由が分かるような気がする。
主に、近世、幕末の北海道の話しである。函館の話しが多い。松前のことも出てくる。このあたりは、他の司馬遼太郎の本でも出てくるかと思う。読んで特に印象に残るのは、近代になってからの北海道の開拓の話しである。その開拓者の苦労が語られる。
樺戸集治監のことは、名前は知っていた。山田風太郎の小説に出てくる。
榎本武揚については、かなり以前に『武揚伝』(佐々木譲)を読んだのを憶えている。
この本を読んで感じることとしては、司馬遼太郎の批判精神である。それがあたっているかどうかは別としても、弥生時代以降の日本の文化の基底をなすものとしてコメを重視している。たしかに、そのような歴史観もなりたつとは思う。これも、現代の歴史学からすれば、批判的に再検討することもあるかとは思うが。
また、随所に、司馬遼太郎自身が兵隊であったときのことが出てくる。司馬遼太郎にとって、日本の近代、特に昭和になってからの軍隊というものは、徹底的に嫌悪するものである。
新十津川村のことも出てくる。今、奈良県に住んでいるので、NHKのローカルニュースを見ていると、県内のこととして十津川村はしょっちゅう登場する。司馬遼太郎は、十津川村には、そうとうの思い入れがあるようだ。(ただ、これも、今の私の感覚からすると、奈良県の十津川村は、過疎地の一つということにはなるのだが。奈良県のニュースで、北海道の新十津川村のことは出てこない。)
ラストは、関寛斎のこと。『胡蝶の夢』は読んだのを憶えている。『胡蝶の夢』における関寛斎は印象深い。この『北海道の諸道』における関寛斎についての記述も印象的である。
2023年6月26日記
『街道をゆく 湖西のみち、甲州街道、長州路ほか』司馬遼太郎/朝日文庫 ― 2023-06-27
2023年6月27日 當山日出夫

司馬遼太郎.『街道をゆく 湖西のみち、甲州街道、長州路ほか』(朝日文庫)、朝日新聞出版.2008
https://publications.asahi.com/kaidou/01/index.shtml
収録するのは、
湖西のみち
竹内街道
甲州街道
葛城道
長州路
主に、日本の古代から、幕末のあたりがあつかわれる。
もとは一九七一年に「週刊朝日」の連載である。これが、「街道をゆく」シリーズの最初である。一九七一年というと、私は高校生のころのことになる。まだ、小説家としての司馬遼太郎は読んでいなかったと思う。無論、「街道をゆく」のことは知らなかった。
「街道をゆく」を読んでいる。その始まりがどんなふうだったかと思って、この本を読んでみることにした。
その後長く続くことになるシリーズの最初は、近江の湖西からである。なるほど、日本の歴史をもし京都を中心としてみるとするならば、それに隣接する湖西のあたりを、旅の始まりにえらんだ、司馬遼太郎の慧眼といわざるをえない。
読んで思うことは、妙に理屈っぽい。司馬遼太郎が小説の余談として書いているようなことが、次々に出てくるのだが、一家言のべておくというような雰囲気を感じる。これが、後の「奈良散歩」あたりになると、雑談の連想が心地よく感じるのだが。
そうはいっても、これは司馬遼太郎の世界が確固としてあると思う。
この時代、一九七〇年代の初めごろ、日本語の起源とか、日本文化の起源とか、さかんに言われていたことを思い出す。今、日本語学の領域において、日本語の起源ということは、ほとんど論じられなくなっている。今から思えば、私の若いころ、学生のころの話しである。この意味では、読んでいて、ふと懐かしい思いになるところがある。
興味の赴くままに、「街道をゆく」を読んでいってみようと思う。
2023年6月26日記
https://publications.asahi.com/kaidou/01/index.shtml
収録するのは、
湖西のみち
竹内街道
甲州街道
葛城道
長州路
主に、日本の古代から、幕末のあたりがあつかわれる。
もとは一九七一年に「週刊朝日」の連載である。これが、「街道をゆく」シリーズの最初である。一九七一年というと、私は高校生のころのことになる。まだ、小説家としての司馬遼太郎は読んでいなかったと思う。無論、「街道をゆく」のことは知らなかった。
「街道をゆく」を読んでいる。その始まりがどんなふうだったかと思って、この本を読んでみることにした。
その後長く続くことになるシリーズの最初は、近江の湖西からである。なるほど、日本の歴史をもし京都を中心としてみるとするならば、それに隣接する湖西のあたりを、旅の始まりにえらんだ、司馬遼太郎の慧眼といわざるをえない。
読んで思うことは、妙に理屈っぽい。司馬遼太郎が小説の余談として書いているようなことが、次々に出てくるのだが、一家言のべておくというような雰囲気を感じる。これが、後の「奈良散歩」あたりになると、雑談の連想が心地よく感じるのだが。
そうはいっても、これは司馬遼太郎の世界が確固としてあると思う。
この時代、一九七〇年代の初めごろ、日本語の起源とか、日本文化の起源とか、さかんに言われていたことを思い出す。今、日本語学の領域において、日本語の起源ということは、ほとんど論じられなくなっている。今から思えば、私の若いころ、学生のころの話しである。この意味では、読んでいて、ふと懐かしい思いになるところがある。
興味の赴くままに、「街道をゆく」を読んでいってみようと思う。
2023年6月26日記
最近のコメント