『仏像と日本人』碧海寿広 ― 2018-08-27
2018-08-27 當山日出夫(とうやまひでお)
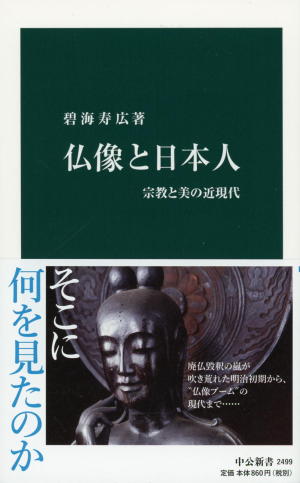
碧海寿広.『仏像と日本人-宗教と美の近現代-』(中公新書).中央公論新社.2018
http://www.chuko.co.jp/shinsho/2018/07/102499.html
和辻哲郎の『初版 古寺巡礼』を読んで、亀井勝一郎の『大和古寺風物誌』を読んだ。
やまもも書斎記 2018年8月18日
『初版 古寺巡礼』和辻哲郎
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/08/18/8944613
やまもも書斎記 2018年8月20日
『大和古寺風物誌』亀井勝一郎
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/08/20/8946045
これらの本を読んだときに、ちょうどタイミングよく刊行になった本なので、これも読んでみることにした。
読んだ印象を一言で言えば……近現代における仏像鑑賞の歴史としてよくまとまっている、ということだろうか。明治のころ、フェノロサあたりのことからはじまり、国立の博物館の設立の経緯などを経て、和辻哲郎、亀井勝一郎、などに説き及ぶ。そして、仏像写真の代表として、土門拳、入江泰吉について書いてある。戦後では、白州正子が登場する。そして、最後は、いとうせいこう・みうらじゅんの『見仏記』についてふれてある(この本については、私は未読である。)それから、京都の古都税をめぐる一件についても、言及がある。
結局のところ、仏像は信仰の対象である、だが、その一方で、仏像の美を理解するということが、近代になってからの「教養」となってきた。少なくとも仏教美術史の概略は、教養の一科目として意識されるようになってきた歴史、このようにとらえていいのではないだろうか。
やや不満に感じたところを記すならば、和辻哲郎の『古寺巡礼』が、どのように読まれ、また、改訂されてきたかについて言及があってもよかったように思う。この本では、すこしだが亀井勝一郎の『大和古寺風物誌』も、改訂の手が加わっていることが記されている。しかし、現行の新潮文庫版では、そのことがわからない。
これらの代表的な書物については、作者がどのような意図で書き、また、戦後になって改訂の手を加えていったものなのか、興味のあるところである。
現代、我々は、仏像を〈美〉の対象として見る感覚のなかにいる。教養である。だが、その一方で、〈信仰〉の対象でもある。このあたりの事情は、近年の博物館の仏像の展示方法の変化に見て取ることができるかもしれない。この本では、書かれていないことだが、東京国立博物館の仏像の展示など、近年になって大きく変わってきている。単なる〈美術品〉としてだけではなく、〈信仰〉の対象であるという側面に配慮するようになってきていると感じる。
和辻哲郎も亀井勝一郎も、歴史の中で仕事を残した人たちなのである。この歴史に今一歩踏み込んでもよかったのではないか。また、個人的な思いとしてであるが、土門拳と入江泰吉の写真には、微妙な違い……仏像をどのようなものとして見ているか……あるように感じているのだが、近代における仏像写真の歴史もまた興味深いところである。
この本では触れられていないが、さらに現代では、仏像の3Dデジタル画像、CTスキャンなど、最先端の技術をつかって、その姿にせまろうとする動きもある。文化財とデジタル技術の関係の今後を考えるうえでも、いろいろ考えるところがある。
ともあれ、今日の我々の仏像に対する見方というものも、歴史的な経緯があって形成されてきたものであるということを、再確認する意味では、この本は有益な内容になっていると感じる。このような歴史的経緯をわかったうえで、では、どのような態度で仏像に接することになるのか、いろいろ考えることになる。
http://www.chuko.co.jp/shinsho/2018/07/102499.html
和辻哲郎の『初版 古寺巡礼』を読んで、亀井勝一郎の『大和古寺風物誌』を読んだ。
やまもも書斎記 2018年8月18日
『初版 古寺巡礼』和辻哲郎
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/08/18/8944613
やまもも書斎記 2018年8月20日
『大和古寺風物誌』亀井勝一郎
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/08/20/8946045
これらの本を読んだときに、ちょうどタイミングよく刊行になった本なので、これも読んでみることにした。
読んだ印象を一言で言えば……近現代における仏像鑑賞の歴史としてよくまとまっている、ということだろうか。明治のころ、フェノロサあたりのことからはじまり、国立の博物館の設立の経緯などを経て、和辻哲郎、亀井勝一郎、などに説き及ぶ。そして、仏像写真の代表として、土門拳、入江泰吉について書いてある。戦後では、白州正子が登場する。そして、最後は、いとうせいこう・みうらじゅんの『見仏記』についてふれてある(この本については、私は未読である。)それから、京都の古都税をめぐる一件についても、言及がある。
結局のところ、仏像は信仰の対象である、だが、その一方で、仏像の美を理解するということが、近代になってからの「教養」となってきた。少なくとも仏教美術史の概略は、教養の一科目として意識されるようになってきた歴史、このようにとらえていいのではないだろうか。
やや不満に感じたところを記すならば、和辻哲郎の『古寺巡礼』が、どのように読まれ、また、改訂されてきたかについて言及があってもよかったように思う。この本では、すこしだが亀井勝一郎の『大和古寺風物誌』も、改訂の手が加わっていることが記されている。しかし、現行の新潮文庫版では、そのことがわからない。
これらの代表的な書物については、作者がどのような意図で書き、また、戦後になって改訂の手を加えていったものなのか、興味のあるところである。
現代、我々は、仏像を〈美〉の対象として見る感覚のなかにいる。教養である。だが、その一方で、〈信仰〉の対象でもある。このあたりの事情は、近年の博物館の仏像の展示方法の変化に見て取ることができるかもしれない。この本では、書かれていないことだが、東京国立博物館の仏像の展示など、近年になって大きく変わってきている。単なる〈美術品〉としてだけではなく、〈信仰〉の対象であるという側面に配慮するようになってきていると感じる。
和辻哲郎も亀井勝一郎も、歴史の中で仕事を残した人たちなのである。この歴史に今一歩踏み込んでもよかったのではないか。また、個人的な思いとしてであるが、土門拳と入江泰吉の写真には、微妙な違い……仏像をどのようなものとして見ているか……あるように感じているのだが、近代における仏像写真の歴史もまた興味深いところである。
この本では触れられていないが、さらに現代では、仏像の3Dデジタル画像、CTスキャンなど、最先端の技術をつかって、その姿にせまろうとする動きもある。文化財とデジタル技術の関係の今後を考えるうえでも、いろいろ考えるところがある。
ともあれ、今日の我々の仏像に対する見方というものも、歴史的な経緯があって形成されてきたものであるということを、再確認する意味では、この本は有益な内容になっていると感じる。このような歴史的経緯をわかったうえで、では、どのような態度で仏像に接することになるのか、いろいろ考えることになる。
『大和古寺風物誌』亀井勝一郎 ― 2018-08-20
2018-08-20 當山日出夫(とうやまひでお)

亀井勝一郎.『大和古寺風物誌』(新潮文庫).新潮社.1953(2015.改版)
http://www.shinchosha.co.jp/book/101301/
和辻哲郎の『初版 古寺巡礼』を読んで、次に読んでおきたくなって、手にした本である。再読、いや、再々々読ぐらいになるだろう。これまで何回か読み返した本である。
やまもも書斎記 2018年8月18日
『初版 古寺巡礼』和辻哲郎
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/08/18/8944613
亀井勝一郎は、私が学生のころ……今から40年以上も前になるが……現役で読まれていた評論家であった。今、亀井勝一郎で読めるのは、この新潮文庫の『大和古寺風物誌』がある。他に、数点は、今でも読める本があるようであるが、やはり、知名度からすれば、まずこの本になるだろう。そして、この本は、今でも読まれている本である。新潮文庫は、近年になって改版して、新しい版で刊行している。
若いころ、『古寺巡礼』(和辻哲郎、岩波文庫版)を読んで、大和の古仏について書かれたものとしては、こちらの『大和古寺風物誌』(亀井勝一郎)の方が、いいと感じていたものである。何よりも、仏像を信仰の対象として見る姿勢に、共感したものである。
今になって、何十年かぶりに読み返してみて、感じることは、次の二点だろうか。
第一には、この本に掲載の文章が書かれたのは、戦時中であったこと。太平洋戦争のさなかに書かれている。主に、昭和17年ごろの文章が中心である。
その時代背景をどことなく感じさせる文章である。特に戦意昂揚というようなことはないが、自国の過去の文化への礼賛の雰囲気がただよっている。それが、特に、いやになるということはないのであるが、読んでいて、その時代背景を感じながら読むことになる。
第二には、亀井勝一郎という評論家は、左翼からの転向者であった(通俗的な文学史の理解からすれば、このような表現になる)。このことを、若い時、学生の頃、亀井勝一郎という人物の書いたものを読んだりするときには、特に意識しなかった。
だが、そのような背景がある人物であること、また、戦時中に書かれた文章であること、これらを考えて読んで見ると、保守的な浪漫主義とでもいうべきものを感じる。
以上の二点ぐらいが、久々にこの本を読んで感じるところである。若いときに比べれば、かなり批判的な目で、文章に接するようになってきていることに気づく。
とはいえ、やはりこの作品を読んで感じるのは、仏像をあくまでも信仰の対象として見ようとする姿勢にある。この部分については、今でも、共感できるものとしてあると感じる。博物館、美術館で、陳列ケースのなかで、美術品として鑑賞するのではなく、寺院、それも奈良の古寺において、古代の信仰をうけついでいるものとしての仏像に接する。この基本姿勢は、今でも、通じるものがある。
ところで、この本も、戦後になって改訂の手が加わっているらしい。そのことは、
碧海寿広.『仏像と日本人-宗教と美の近現代-』(中公新書).中央公論新社.2018
http://www.chuko.co.jp/shinsho/2018/07/102499.html
を読んで知った。この本のことについては、改めて書いてみたいと思っている。
『初版 古寺巡礼』和辻哲郎 ― 2018-08-18
2018-08-18 當山日出夫(とうやまひでお)
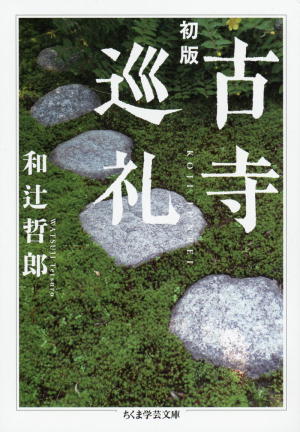
和辻哲郎.『初版 古寺巡礼』(ちくま学芸文庫).筑摩書房.2012
http://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480094544/
和辻哲郎の『古寺巡礼』は、若いころに読んだ本であった。二回ほどは読んでいるだろうか。が、それは、今から思ってみるならば、岩波文庫版であった。筑摩書房のちくま学芸文庫版で『初版 古寺巡礼』が出ていることを知って、これも読んでおきたくなって読んでみた。
はっきり言って、若い頃、和辻哲郎『古寺巡礼』はあまり好きな本ではなかった。そのあまりにも理知的なスタイル、仏像を信仰の対象としてではなく「美術品」として見ようとする、その姿勢に、なにかしら違和感のようなものを感じていた。若い頃の読書としては、和辻哲郎の『古寺巡礼』よりも、亀井勝一郎の『大和古寺風物誌』の方が断然いいと思っていた。
しかし、今回、『初版 古寺巡礼』を読んで見て、その印象はがらりとかわった。和辻哲郎は、なんと初々しい(としかいいようのないような)豊かな感受性で、奈良の古寺、古仏を見ていることか、認識を新たにするところがあった。
ちくま学芸文庫版の解説を読むと、後年の改訂版となったときに、かなりの手を加えたものであるということである。その中には、学問的な誤りの訂正というべきものもある。だが、それ以上に、より理知的で冷静な文章に書きかえているとのこと。(岩波文庫版の解説にも、このところについての言及はあるらしいが、昔読んだときには読み過ごしていたようだ。)
今回、『初版 古寺巡礼』を読んで感じることは……今から、一世紀ほど昔になるのだろうか、奈良の古寺をめぐる旅とは、こんなにも人を感動させるものであったのか、という感慨である。今の奈良の古社寺拝観、観光からは、とても想像ができない。このようにして、古仏に接していた時代がかつてあったのだ、このことを確認する意味でも、この本は一読の価値があると思う。
仏像を見る感覚、感受性、美的意識、というようなことについて、改めて考えてみたいと思った本である。
http://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480094544/
和辻哲郎の『古寺巡礼』は、若いころに読んだ本であった。二回ほどは読んでいるだろうか。が、それは、今から思ってみるならば、岩波文庫版であった。筑摩書房のちくま学芸文庫版で『初版 古寺巡礼』が出ていることを知って、これも読んでおきたくなって読んでみた。
はっきり言って、若い頃、和辻哲郎『古寺巡礼』はあまり好きな本ではなかった。そのあまりにも理知的なスタイル、仏像を信仰の対象としてではなく「美術品」として見ようとする、その姿勢に、なにかしら違和感のようなものを感じていた。若い頃の読書としては、和辻哲郎の『古寺巡礼』よりも、亀井勝一郎の『大和古寺風物誌』の方が断然いいと思っていた。
しかし、今回、『初版 古寺巡礼』を読んで見て、その印象はがらりとかわった。和辻哲郎は、なんと初々しい(としかいいようのないような)豊かな感受性で、奈良の古寺、古仏を見ていることか、認識を新たにするところがあった。
ちくま学芸文庫版の解説を読むと、後年の改訂版となったときに、かなりの手を加えたものであるということである。その中には、学問的な誤りの訂正というべきものもある。だが、それ以上に、より理知的で冷静な文章に書きかえているとのこと。(岩波文庫版の解説にも、このところについての言及はあるらしいが、昔読んだときには読み過ごしていたようだ。)
今回、『初版 古寺巡礼』を読んで感じることは……今から、一世紀ほど昔になるのだろうか、奈良の古寺をめぐる旅とは、こんなにも人を感動させるものであったのか、という感慨である。今の奈良の古社寺拝観、観光からは、とても想像ができない。このようにして、古仏に接していた時代がかつてあったのだ、このことを確認する意味でも、この本は一読の価値があると思う。
仏像を見る感覚、感受性、美的意識、というようなことについて、改めて考えてみたいと思った本である。
追記 2018-08-20
亀井勝一郎『大和古寺風物誌』については、
やまもも書斎記 2018年8月20日
『大和古寺風物誌』亀井勝一郎
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/08/20/8946045
亀井勝一郎『大和古寺風物誌』については、
やまもも書斎記 2018年8月20日
『大和古寺風物誌』亀井勝一郎
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/08/20/8946045
「釈宗演と近代日本」を見てきた ― 2018-06-21
2018-06-21 當山日出夫(とうやまひでお)
先日、東京に行ったのは、語彙・辞書研究会(53回、2018年6月9日)で発表するためである。そのついでというわけではないが、発表なので前日から行って、慶應義塾大学で今やっている「釈宗演と近代日本」の展示を見てきた。
釈宗演と近代日本-若き禅僧、世界を駆ける-
http://www.art-c.keio.ac.jp/news-events/event-archive/shaku2018/
https://www.keio.ac.jp/ja/news/2018/6/18/27-44913/index.html
釈宗演という名前は知っていた。漱石関係のものを読めば名前が出てくる。特に、『門』で描かれた鎌倉での参禅の様子など、自身の体験をもとにしたことであるらしい。その時に、漱石研究として名前の出てくるのが、釈宗演である。
その釈宗演は、安政6年(1859)、福井に生まれた。三井寺で倶舎論を学び、その後、円覚寺で、洪川宗温に参禅。印可をうける。明治18年(1886)、慶應義塾に入学(無論、この当時は、福澤諭吉の時代である)。その後、セイロンに行く。円覚寺の管長に就任。明治26年(1893)、アメリカのシカゴ万博にあわせて開催された万国宗教者会議に日本代表として参加。
世界に、「禅」(ZEN)をはじめて紹介した人物ということになる。
展覧会は、その生いたち、修行の時期のことから、慶應義塾在学の時の資料、また、その後の、世界での活躍の様子など、様々な方面にわたる資料の展示であった。
私もとおりいっぺんの知識は持っていたが、展覧会を見て、これほどまでに多彩な活動をしたのかと、認識を新たにした。
見て思ったことのいささかでも書いておくならば……日本近代の宗教、なかんずく仏教の近代化とは何であったのか、そこのところが今ひとつ分からなかったというのが正直なところ。それは、釈宗演の次の世代の仕事ということになるのであろうか。たとえば、禅であれば、鈴木大拙など。
また、今回の展覧会で大きく扱われていたことに、日露戦争での従軍がある。従軍布教師として、大陸にわたっている。このことを、現代の価値観から批判することはたやすいかもしれない。が、それよりも、慶應義塾で学び、その当時の世界を見ていた釈宗演にとって、日露戦争は近代の日本において、避けてとおることのできな大きな出来事であったことを理解しておくべきだろう。
どうでもいいことかもしれないが、参禅者の名簿があって、夏目漱石の名前があった。それには、北海道平民と書いてあったのに眼がとまった。漱石は、本籍を北海道に移していたのであった。
個人的な思いを書けば、慶應義塾の出身者の中に、釈宗演という人物がいたことは、もっと知られていいことだと思うし、また、仏教、禅の近代ということについても、さらに研究が進むことを願っている。
なお、カタログを売っている方の会場には、僧侶の方がいた。話しをちょっと聞いてみると、円覚寺から派遣されてきているとのことだった。
先日、東京に行ったのは、語彙・辞書研究会(53回、2018年6月9日)で発表するためである。そのついでというわけではないが、発表なので前日から行って、慶應義塾大学で今やっている「釈宗演と近代日本」の展示を見てきた。
釈宗演と近代日本-若き禅僧、世界を駆ける-
http://www.art-c.keio.ac.jp/news-events/event-archive/shaku2018/
https://www.keio.ac.jp/ja/news/2018/6/18/27-44913/index.html
釈宗演という名前は知っていた。漱石関係のものを読めば名前が出てくる。特に、『門』で描かれた鎌倉での参禅の様子など、自身の体験をもとにしたことであるらしい。その時に、漱石研究として名前の出てくるのが、釈宗演である。
その釈宗演は、安政6年(1859)、福井に生まれた。三井寺で倶舎論を学び、その後、円覚寺で、洪川宗温に参禅。印可をうける。明治18年(1886)、慶應義塾に入学(無論、この当時は、福澤諭吉の時代である)。その後、セイロンに行く。円覚寺の管長に就任。明治26年(1893)、アメリカのシカゴ万博にあわせて開催された万国宗教者会議に日本代表として参加。
世界に、「禅」(ZEN)をはじめて紹介した人物ということになる。
展覧会は、その生いたち、修行の時期のことから、慶應義塾在学の時の資料、また、その後の、世界での活躍の様子など、様々な方面にわたる資料の展示であった。
私もとおりいっぺんの知識は持っていたが、展覧会を見て、これほどまでに多彩な活動をしたのかと、認識を新たにした。
見て思ったことのいささかでも書いておくならば……日本近代の宗教、なかんずく仏教の近代化とは何であったのか、そこのところが今ひとつ分からなかったというのが正直なところ。それは、釈宗演の次の世代の仕事ということになるのであろうか。たとえば、禅であれば、鈴木大拙など。
また、今回の展覧会で大きく扱われていたことに、日露戦争での従軍がある。従軍布教師として、大陸にわたっている。このことを、現代の価値観から批判することはたやすいかもしれない。が、それよりも、慶應義塾で学び、その当時の世界を見ていた釈宗演にとって、日露戦争は近代の日本において、避けてとおることのできな大きな出来事であったことを理解しておくべきだろう。
どうでもいいことかもしれないが、参禅者の名簿があって、夏目漱石の名前があった。それには、北海道平民と書いてあったのに眼がとまった。漱石は、本籍を北海道に移していたのであった。
個人的な思いを書けば、慶應義塾の出身者の中に、釈宗演という人物がいたことは、もっと知られていいことだと思うし、また、仏教、禅の近代ということについても、さらに研究が進むことを願っている。
なお、カタログを売っている方の会場には、僧侶の方がいた。話しをちょっと聞いてみると、円覚寺から派遣されてきているとのことだった。
『沈黙』遠藤周作(その四) ― 2017-01-30
2017-01-30 當山日出夫
遠藤周作.『沈黙』(新潮文庫).新潮社.1981(2003改版) (原著 新潮社.1966)
http://www.shinchosha.co.jp/book/112315/
さらに続けることにする。
やまもも書斎記 2017年1月29日
『沈黙』遠藤周作(その三)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2017/01/29/8339638
『沈黙』の問いかけていることの意味を、現代社会のなかで考えてみたい。
この作品では、キリスト教への信仰とその形式(踏み絵)が、重要な意味を持つことはいうまでもない。踏み絵を踏んでしまうことが、はたして、本当にキリスト教の信仰を捨てることになるのだろうか。あるいは、そのような行為を神はよしとされるのであろうか。そして、なぜ、そのときにおよんでも神は沈黙しているのか。
この踏み絵のようなこと……作中では、きわめて形式的な意味で語られる。ただ、踏みさえすればよい。ただ、形式的なことなのである、と。
作品中には、次のようなことばがある。
「ほんの形だけのことだ。形などどうでもいいことではないか」通辞は興奮し、せいていた。「形だけ踏めばよいことだ。」(p.268)
つまり、形式的に、踏み絵を踏むだけで、その心のうち……内面の信仰……にまで、とやかくいうものではない。そのようにいわれる踏み絵を踏んでしまうこと、そのときの足のいたみ、これが、この作品における、重要なポイントであることは確かである。
信仰と形式という。では、現代社会においてはどうであろうか。
公の場においては、特定の信仰を表すことはよくないとする立場がある。具体的には、女性のスカーフを禁ずる/許容する。あるいは、学校の教室には十字架を掲げてはならない/許容する……これらの判断は、妥当なことなのだろうか。これも、きわめて形式的なことである。ただ、形式を要求しているだけであって、その内面の信仰、その信教の自由にまでふみこもうというのではない。このような論理は、現在では、普通のことになっているように思われる。むしろ、今日のリベラルな価値観からするならば、内面の信教の自由こそが尊いのであって、形式的なことにこだわるべきではない、とされるのかもしれない。
だが、今日の社会での、このような宗教にかかわる形式の要求と、『沈黙』に描かれた踏み絵と、どれほどの違いがあるというのか。
信仰が、ある形式をともなう、あるいは、必要とするのであるならば、それはそれとして尊重されねばならないだろう。『沈黙』において、問いかけられた信仰と形式の問題は、まさに、今現代の我々の社会のなかにおいて、真摯に考えるべき課題としてあるように、私には思われる。
ただ小説として、日本の近世初期のキリシタン弾圧という特殊な事情のなかのできごととしてではなく、今の社会のなかにおいて、多様な宗教が、相互にその尊厳を尊重しながら共存する道はないか、これを考えるひとつ出発点を与えていてくれる作品である。これからの社会、この『沈黙』という作品は、この意味において、読まれていくべき作品であると思うのである。
『沈黙』を読んで思ったことを、書いてきたが、最後に、蛇足で書いておきたいことがひとつ。
今から30年近く前のこと。昭和天皇が崩御された。その大喪の礼のとき、このような議論があった。鳥居があって、神職の姿をした人間が行事をおこなうのは、宗教儀礼にあたるので、政教分離の原則から、否定される。しかし、鳥居のないところで、一般の喪服で拝礼をするのは、許容される。いまから考えればなんとも滑稽な議論であるが、その当時は、かなり真剣に議論されたと記憶している。
宗教が宗教としてなりたつことと、儀礼の形式とは、いろいろと複雑な問題があると思うべきだろう。
遠藤周作.『沈黙』(新潮文庫).新潮社.1981(2003改版) (原著 新潮社.1966)
http://www.shinchosha.co.jp/book/112315/
さらに続けることにする。
やまもも書斎記 2017年1月29日
『沈黙』遠藤周作(その三)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2017/01/29/8339638
『沈黙』の問いかけていることの意味を、現代社会のなかで考えてみたい。
この作品では、キリスト教への信仰とその形式(踏み絵)が、重要な意味を持つことはいうまでもない。踏み絵を踏んでしまうことが、はたして、本当にキリスト教の信仰を捨てることになるのだろうか。あるいは、そのような行為を神はよしとされるのであろうか。そして、なぜ、そのときにおよんでも神は沈黙しているのか。
この踏み絵のようなこと……作中では、きわめて形式的な意味で語られる。ただ、踏みさえすればよい。ただ、形式的なことなのである、と。
作品中には、次のようなことばがある。
「ほんの形だけのことだ。形などどうでもいいことではないか」通辞は興奮し、せいていた。「形だけ踏めばよいことだ。」(p.268)
つまり、形式的に、踏み絵を踏むだけで、その心のうち……内面の信仰……にまで、とやかくいうものではない。そのようにいわれる踏み絵を踏んでしまうこと、そのときの足のいたみ、これが、この作品における、重要なポイントであることは確かである。
信仰と形式という。では、現代社会においてはどうであろうか。
公の場においては、特定の信仰を表すことはよくないとする立場がある。具体的には、女性のスカーフを禁ずる/許容する。あるいは、学校の教室には十字架を掲げてはならない/許容する……これらの判断は、妥当なことなのだろうか。これも、きわめて形式的なことである。ただ、形式を要求しているだけであって、その内面の信仰、その信教の自由にまでふみこもうというのではない。このような論理は、現在では、普通のことになっているように思われる。むしろ、今日のリベラルな価値観からするならば、内面の信教の自由こそが尊いのであって、形式的なことにこだわるべきではない、とされるのかもしれない。
だが、今日の社会での、このような宗教にかかわる形式の要求と、『沈黙』に描かれた踏み絵と、どれほどの違いがあるというのか。
信仰が、ある形式をともなう、あるいは、必要とするのであるならば、それはそれとして尊重されねばならないだろう。『沈黙』において、問いかけられた信仰と形式の問題は、まさに、今現代の我々の社会のなかにおいて、真摯に考えるべき課題としてあるように、私には思われる。
ただ小説として、日本の近世初期のキリシタン弾圧という特殊な事情のなかのできごととしてではなく、今の社会のなかにおいて、多様な宗教が、相互にその尊厳を尊重しながら共存する道はないか、これを考えるひとつ出発点を与えていてくれる作品である。これからの社会、この『沈黙』という作品は、この意味において、読まれていくべき作品であると思うのである。
『沈黙』を読んで思ったことを、書いてきたが、最後に、蛇足で書いておきたいことがひとつ。
今から30年近く前のこと。昭和天皇が崩御された。その大喪の礼のとき、このような議論があった。鳥居があって、神職の姿をした人間が行事をおこなうのは、宗教儀礼にあたるので、政教分離の原則から、否定される。しかし、鳥居のないところで、一般の喪服で拝礼をするのは、許容される。いまから考えればなんとも滑稽な議論であるが、その当時は、かなり真剣に議論されたと記憶している。
宗教が宗教としてなりたつことと、儀礼の形式とは、いろいろと複雑な問題があると思うべきだろう。
『沈黙』遠藤周作(その三) ― 2017-01-29
2017-01-29 當山日出夫
遠藤周作.『沈黙』(新潮文庫).新潮社.1981(2003改版) (原著 新潮社.1966)
http://www.shinchosha.co.jp/book/112315/
さらに一昨日・昨日のつづきである。
やまもも書斎記 2017年1月28日
『沈黙』遠藤周作(その二)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2017/01/28/8337757
読みながら付箋をつけたことばがある。それは「愛」「愛する」である。
キリスト教が日本にはいってきて、それが日本でどのように受容されたかを考えるためのキーワードになる。なお、『沈黙』が舞台設定としている近世初期のキリシタン布教においては、「愛」ということばは、宗教用語としてはつかっていなかったと理解している。
『日本国語大辞典』(ジャパンナレッジ)を見ると、「愛、愛する」には、様々な用法があげられているが、ここで問題になるのは、次の意味である。
(7)キリスト教で、神が人類のすべてを無限にいつくしむこと。また、神の持っているような私情を離れた無限の慈悲。→アガペー
初出例は、1890 植村正久
これと、
(8)男女が互いにいとしいと思い合うこと。異性を慕わしく思うこと。恋愛。ラブ。また一般に、相手の人格を認識し理解して、いつくしみ慕う感情をいう。
初出例は、1890 森鴎外
おそらく、キリスト教の用語として、ここにあげた用法は、厳密に区別して使われなければならないものと考える。でなければ、キリスト教における「愛」の意義が雲散霧消してしまう。
『沈黙』には、かなりの「愛、愛する」の用例がひろえる。
まず、基督の像の顔を見ての感想。
「私はその顔に愛を感じます。男がその恋人の顔に引きつけられるように、私は基督の顔にいつも引きつけられるのです。」(p.31)
このような用例は、まだ、キリスト教の「愛」に近い用例かもしれない。次の用例はどうか。
「怒りと、憎しみのためか。それともこれは愛から出た言葉か。」(p.116)
この用例は、キリスト教の「愛」として理解できようか。だが、次の例はどうか、
「たとえば、妻に裏切られた夫を想像するといい。彼はまだ妻を愛し続けている。」(p.117)
この箇所は、連続して出てくる。まず、基督のユダに対する思いを「愛」といい、それにつづけて、男女の間にある感情を、おなじく「愛」とことばで表して、類似するもののようにあつかっている。
他にも数多くの「愛、愛する」の用例はひろえる。これらの用例を見ていくと、どうも、キリスト教本来の「愛」の用法と、男女の間の「愛」とが、そう厳密には区別されることなく、使われているように観察される。
たぶん、この問題を考えていくならば、遠藤周作におけるキリスト教の「愛」とは何であるのか、その思想、信仰の根本にかかわる課題となってくるであろう。
私は、遠藤周作、そのキリスト教文学について論じようという気はないので、これ以上の詮索はやめにしておく。だが、「愛」ということばから見えてくる遠藤周作の信仰の世界というものがあるだろう、とはいえそうである。
付記 2017-01-30
この続きは、
やまもも書斎記 2017年1月30日
『沈黙』遠藤周作(その四)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2017/01/30/8341477
遠藤周作.『沈黙』(新潮文庫).新潮社.1981(2003改版) (原著 新潮社.1966)
http://www.shinchosha.co.jp/book/112315/
さらに一昨日・昨日のつづきである。
やまもも書斎記 2017年1月28日
『沈黙』遠藤周作(その二)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2017/01/28/8337757
読みながら付箋をつけたことばがある。それは「愛」「愛する」である。
キリスト教が日本にはいってきて、それが日本でどのように受容されたかを考えるためのキーワードになる。なお、『沈黙』が舞台設定としている近世初期のキリシタン布教においては、「愛」ということばは、宗教用語としてはつかっていなかったと理解している。
『日本国語大辞典』(ジャパンナレッジ)を見ると、「愛、愛する」には、様々な用法があげられているが、ここで問題になるのは、次の意味である。
(7)キリスト教で、神が人類のすべてを無限にいつくしむこと。また、神の持っているような私情を離れた無限の慈悲。→アガペー
初出例は、1890 植村正久
これと、
(8)男女が互いにいとしいと思い合うこと。異性を慕わしく思うこと。恋愛。ラブ。また一般に、相手の人格を認識し理解して、いつくしみ慕う感情をいう。
初出例は、1890 森鴎外
おそらく、キリスト教の用語として、ここにあげた用法は、厳密に区別して使われなければならないものと考える。でなければ、キリスト教における「愛」の意義が雲散霧消してしまう。
『沈黙』には、かなりの「愛、愛する」の用例がひろえる。
まず、基督の像の顔を見ての感想。
「私はその顔に愛を感じます。男がその恋人の顔に引きつけられるように、私は基督の顔にいつも引きつけられるのです。」(p.31)
このような用例は、まだ、キリスト教の「愛」に近い用例かもしれない。次の用例はどうか。
「怒りと、憎しみのためか。それともこれは愛から出た言葉か。」(p.116)
この用例は、キリスト教の「愛」として理解できようか。だが、次の例はどうか、
「たとえば、妻に裏切られた夫を想像するといい。彼はまだ妻を愛し続けている。」(p.117)
この箇所は、連続して出てくる。まず、基督のユダに対する思いを「愛」といい、それにつづけて、男女の間にある感情を、おなじく「愛」とことばで表して、類似するもののようにあつかっている。
他にも数多くの「愛、愛する」の用例はひろえる。これらの用例を見ていくと、どうも、キリスト教本来の「愛」の用法と、男女の間の「愛」とが、そう厳密には区別されることなく、使われているように観察される。
たぶん、この問題を考えていくならば、遠藤周作におけるキリスト教の「愛」とは何であるのか、その思想、信仰の根本にかかわる課題となってくるであろう。
私は、遠藤周作、そのキリスト教文学について論じようという気はないので、これ以上の詮索はやめにしておく。だが、「愛」ということばから見えてくる遠藤周作の信仰の世界というものがあるだろう、とはいえそうである。
付記 2017-01-30
この続きは、
やまもも書斎記 2017年1月30日
『沈黙』遠藤周作(その四)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2017/01/30/8341477
『沈黙』遠藤周作(その二) ― 2017-01-28
2017-01-28 當山日出夫
遠藤周作.『沈黙』(新潮文庫).新潮社.1981(2003改版) (原著 新潮社.1966)
http://www.shinchosha.co.jp/book/112315/
昨日のつづきである。
やまもも書斎記 2017年1月27日
『沈黙』遠藤周作(その一)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2017/01/27/8335811
この作品を、宗教をあつかった文学として読んだとき、気になるのは次の二点である。
第一には、日本におけるキリスト教は、本当に本物のキリスト教といえるのだろうか、という問題。日本で信仰されているキリスト教は、日本的なものに変質しているのではないか、ということがこの作品の一つの宗教的テーマとしてある。
これは、今日の文化人類学とか宗教学とかの課題かもしれない。
たしかに、キリスト教、特に、カトリックの教えは、ある種の普遍性をめざしているものであろう。だが、その教えが、日本のなかにはいってきたとき、土着の日本古来の信仰(仏教、民俗宗教)のなかにとりこまれてしまって、変質してしまうのではないか。このことが、本書のテーマの一つであることは、読み取れることだろう。
第二には、「キチジロー」に代表されるような、弱いもの、あるいは、転んでしまったロドリゴのようなもの、これらを、「神」はよしとされるであろうか、という問いかけがある。
いいかえるならば、「悪人」(親鸞)である。このようなものは、絶対の「神」の前にどのようにふるまえばよいのであろうか。また、「神」は、このような「悪人」を、どう判断されるのであろうか。
これは、あまりにも、強引な解釈かもしれないが、しかし、私の読んだ印象としては、この問いかけが、『沈黙』のなかにはあるように感じる。このような問いかけをふまえたうえで、なぜ「神」は「沈黙」しているのであろうか、このことが、読者の前に突きつけられるように思うのである。
以上の二点が、この作品のなかにある、宗教についてのメッセージであると、私は読み取った。ただ、禁教に対する神の沈黙をあつかったのではない、それ以上に、根源的な人間、そして、社会・文化と、宗教・信仰へのといかけがこの作品にはある。これは、日本の近世初期のキリシタン弾圧という時代的背景のもとに、特殊な状況でのみ考えるべきではないだろう。小説に描かれたような特殊な状況から、さらに踏み込んで、より一般的な、普遍的な、宗教のあり方への問題提起をよみとるべきでである。
昨日、書いたように、かつて私がこの作品を若いときに読んだとき、それは、「転向」(共産主義からの)と、密接に関連するものとして読んだという記憶がある。それが、時代を経て、ようやく、この小説が本来もっている、宗教と人間のかかわりについてのテーマを軸に読むことができるようになった。近代日本文学における宗教小説として、この作品は、これから読まれていくことになるであろう。そして、その問いかけたものは、深くするどい。この問いにどう答えるか、考えていくか、これからの課題ということになると思う次第である。
追記 2017-01-29
このつづきは、
やまもも書斎記 2017年1月29日
『沈黙』遠藤周作(その三)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2017/01/29/8339638
遠藤周作.『沈黙』(新潮文庫).新潮社.1981(2003改版) (原著 新潮社.1966)
http://www.shinchosha.co.jp/book/112315/
昨日のつづきである。
やまもも書斎記 2017年1月27日
『沈黙』遠藤周作(その一)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2017/01/27/8335811
この作品を、宗教をあつかった文学として読んだとき、気になるのは次の二点である。
第一には、日本におけるキリスト教は、本当に本物のキリスト教といえるのだろうか、という問題。日本で信仰されているキリスト教は、日本的なものに変質しているのではないか、ということがこの作品の一つの宗教的テーマとしてある。
これは、今日の文化人類学とか宗教学とかの課題かもしれない。
たしかに、キリスト教、特に、カトリックの教えは、ある種の普遍性をめざしているものであろう。だが、その教えが、日本のなかにはいってきたとき、土着の日本古来の信仰(仏教、民俗宗教)のなかにとりこまれてしまって、変質してしまうのではないか。このことが、本書のテーマの一つであることは、読み取れることだろう。
第二には、「キチジロー」に代表されるような、弱いもの、あるいは、転んでしまったロドリゴのようなもの、これらを、「神」はよしとされるであろうか、という問いかけがある。
いいかえるならば、「悪人」(親鸞)である。このようなものは、絶対の「神」の前にどのようにふるまえばよいのであろうか。また、「神」は、このような「悪人」を、どう判断されるのであろうか。
これは、あまりにも、強引な解釈かもしれないが、しかし、私の読んだ印象としては、この問いかけが、『沈黙』のなかにはあるように感じる。このような問いかけをふまえたうえで、なぜ「神」は「沈黙」しているのであろうか、このことが、読者の前に突きつけられるように思うのである。
以上の二点が、この作品のなかにある、宗教についてのメッセージであると、私は読み取った。ただ、禁教に対する神の沈黙をあつかったのではない、それ以上に、根源的な人間、そして、社会・文化と、宗教・信仰へのといかけがこの作品にはある。これは、日本の近世初期のキリシタン弾圧という時代的背景のもとに、特殊な状況でのみ考えるべきではないだろう。小説に描かれたような特殊な状況から、さらに踏み込んで、より一般的な、普遍的な、宗教のあり方への問題提起をよみとるべきでである。
昨日、書いたように、かつて私がこの作品を若いときに読んだとき、それは、「転向」(共産主義からの)と、密接に関連するものとして読んだという記憶がある。それが、時代を経て、ようやく、この小説が本来もっている、宗教と人間のかかわりについてのテーマを軸に読むことができるようになった。近代日本文学における宗教小説として、この作品は、これから読まれていくことになるであろう。そして、その問いかけたものは、深くするどい。この問いにどう答えるか、考えていくか、これからの課題ということになると思う次第である。
追記 2017-01-29
このつづきは、
やまもも書斎記 2017年1月29日
『沈黙』遠藤周作(その三)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2017/01/29/8339638
『沈黙』遠藤周作(その一) ― 2017-01-27
2017-01-27 當山日出夫
遠藤周作.『沈黙』(新潮文庫).新潮社.1981(2003改版) (原著 新潮社.1966)
http://www.shinchosha.co.jp/book/112315/
私の記憶では、たしか、学校の教科書に採用されていたように憶えているのだが、どうだろうか。ともあれ、高校生ぐらいの時に、この作品の全部を読んでいる。上記の書誌を記してみて、新潮文庫の旧版が出たときは、もう大学生になってからになるので、単行本で買って読んだのだろうか。どうも、そのあたりの記憶があいまいである。
ともあれ、私の世代ぐらいだと遠藤周作は、読んでいる本の中にはいっていたものである。
この『沈黙』である。今般、映画が作られたということで、話題になっているようだ。そのこともあって、久しぶりに、昔、読んだ本を読み直したくなって読んでみた。
今日、ここで書いておきたいことは……かつて、私が、この本を読んだとき、キリスト教からの「転び」ということと、共産党からの「転向」ということを、ダブって理解していたように憶えている。
絶対の真理としての「神」、そして、それを裏切ること。これは、まさに、日本の近代史の中であった、共産主義への信奉と、その弾圧、「転向」ということと、重なっていた。いや、そのように、理解して読んでしまった、というべきであろうか。
このような読み方が、この作品の理解として正当なものではないともいえよう。しかし、ある時代、この作品は、このように理解され受容されていたのである。このことは、一般的に書く文学史や、文芸評論では、論じられないことがらかもしれない。しかし、そうであったということは、少なくとも、私個人の経験にてらして、言ってもよいと思う。
だが、いま、この時代になって、1989年のベルリンの壁の崩壊以降、世界の情勢は大きく変わった。もう、共産主義への信奉(ほとんど、それは「信仰」に近いともいえよう)は、終わりを告げた。ようやく、『沈黙』という小説が、その本来の作者の意図、宗教をあつかった文学として読むことのできる時代になった。こう考えていいだろう。
では、宗教をあつかった文学としてこの小説の問いかけるものは何であるのか、それは、明日、書くことにする。
追記 2017-01-28
つづきは、
やまもも書斎記 2017年1月28日
『沈黙』遠藤周作(その二)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2017/01/28/8337757
遠藤周作.『沈黙』(新潮文庫).新潮社.1981(2003改版) (原著 新潮社.1966)
http://www.shinchosha.co.jp/book/112315/
私の記憶では、たしか、学校の教科書に採用されていたように憶えているのだが、どうだろうか。ともあれ、高校生ぐらいの時に、この作品の全部を読んでいる。上記の書誌を記してみて、新潮文庫の旧版が出たときは、もう大学生になってからになるので、単行本で買って読んだのだろうか。どうも、そのあたりの記憶があいまいである。
ともあれ、私の世代ぐらいだと遠藤周作は、読んでいる本の中にはいっていたものである。
この『沈黙』である。今般、映画が作られたということで、話題になっているようだ。そのこともあって、久しぶりに、昔、読んだ本を読み直したくなって読んでみた。
今日、ここで書いておきたいことは……かつて、私が、この本を読んだとき、キリスト教からの「転び」ということと、共産党からの「転向」ということを、ダブって理解していたように憶えている。
絶対の真理としての「神」、そして、それを裏切ること。これは、まさに、日本の近代史の中であった、共産主義への信奉と、その弾圧、「転向」ということと、重なっていた。いや、そのように、理解して読んでしまった、というべきであろうか。
このような読み方が、この作品の理解として正当なものではないともいえよう。しかし、ある時代、この作品は、このように理解され受容されていたのである。このことは、一般的に書く文学史や、文芸評論では、論じられないことがらかもしれない。しかし、そうであったということは、少なくとも、私個人の経験にてらして、言ってもよいと思う。
だが、いま、この時代になって、1989年のベルリンの壁の崩壊以降、世界の情勢は大きく変わった。もう、共産主義への信奉(ほとんど、それは「信仰」に近いともいえよう)は、終わりを告げた。ようやく、『沈黙』という小説が、その本来の作者の意図、宗教をあつかった文学として読むことのできる時代になった。こう考えていいだろう。
では、宗教をあつかった文学としてこの小説の問いかけるものは何であるのか、それは、明日、書くことにする。
追記 2017-01-28
つづきは、
やまもも書斎記 2017年1月28日
『沈黙』遠藤周作(その二)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2017/01/28/8337757
『宗教学の名著30』島薗進 ― 2017-01-15
2017-01-15 當山日出夫
島薗進.『宗教学の名著30』(ちくま新書).筑摩書房.2008
http://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480064424/
このところ、ちくま新書の『~~の名著30』のシリーズを手にしてながめている。文字通り、眺めているであって、具体的にそこに掲載されている本を読もうというところまではいっていないのであるが。
この本もそのひとつ。学問的な研究分野としては、宗教学は、私の専門ではない。しかし、その周辺に属する領域のことを勉強してきた。そして、宗教学、あるいは、宗教についての書物というものも、ある意味で、ひろい意味での「文学」にふくめて考えてよいと思う。
「はじめに」のところを読み始めて、ちょっと驚いた。
「宗教学は発展途上の学である。」(p.9)
とある。つづけて、
「すでに成熟して果汁がしたたり落ちるような学問分野も、あるいはすでに衰退の相を示している分野もあると思うが、宗教学はまだ若い。青い果実の段階だ。というのは、その望みが大きいからである。(中略)「未来」の学とも言えるし、なお「未熟」とも言える。」
仏教学とか、キリスト教学とか、ゆうに千年以上の歴史があるのに、と思ってつづきを読む。
「まず、古今東西を見渡して、安心して「宗教」という言葉を使える段階に至っていない。「宗教」だけではない。西洋中心の宗教観にのっとって形づくられた諸概念を超えて、世界各地で通用する概念の道具立てがまだ明確ではない。一九六〇年代以来、「宗教」という概念が近代西洋の考え方の偏りをもっていることが鋭く批判されていて、それにかわる「宗教」理解が願われているが、なお堅固な基礎をもった方針が形成されていない。」(p.9)
このような理解の上で、古今東西の主教にかかわる古典的名著の解説となっている。
「Ⅰ 宗教学の先駆け」では、
空海 『三教指帰』
イブン=ハルドゥーン 『歴史序説』
富永仲基 『翁の文』
ヒューム 『宗教の自然史』
順次見ていくと、
ウェーバー 『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』
とか、
柳田国男 『桃太郎の母』
などが、出てくる。つまり、宗教を、社会のあり方や民俗などとも関連させて論じようという姿勢がみてとれる。『プロテスタンティズム~~』などは、そう言われてみれば、たしかに、宗教を論じた書物であるとは理解される。
また、狭い意味での「文学」からも宗教にアプローチすることもできる。
バフチン 『ドストエフスキーの詩学の諸問題』
もあげてある。
文学作品を読むとき、その根底にある宗教観というものを抜きにして、本当の理解はないだろうと思う。ドストエフスキーしかり、トルストイしかり、そして、日本の『源氏物語』『平家物語』しかり、である。
これからの読書のてがかりとして、この本もそばにおいておきたいと思っている。
島薗進.『宗教学の名著30』(ちくま新書).筑摩書房.2008
http://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480064424/
このところ、ちくま新書の『~~の名著30』のシリーズを手にしてながめている。文字通り、眺めているであって、具体的にそこに掲載されている本を読もうというところまではいっていないのであるが。
この本もそのひとつ。学問的な研究分野としては、宗教学は、私の専門ではない。しかし、その周辺に属する領域のことを勉強してきた。そして、宗教学、あるいは、宗教についての書物というものも、ある意味で、ひろい意味での「文学」にふくめて考えてよいと思う。
「はじめに」のところを読み始めて、ちょっと驚いた。
「宗教学は発展途上の学である。」(p.9)
とある。つづけて、
「すでに成熟して果汁がしたたり落ちるような学問分野も、あるいはすでに衰退の相を示している分野もあると思うが、宗教学はまだ若い。青い果実の段階だ。というのは、その望みが大きいからである。(中略)「未来」の学とも言えるし、なお「未熟」とも言える。」
仏教学とか、キリスト教学とか、ゆうに千年以上の歴史があるのに、と思ってつづきを読む。
「まず、古今東西を見渡して、安心して「宗教」という言葉を使える段階に至っていない。「宗教」だけではない。西洋中心の宗教観にのっとって形づくられた諸概念を超えて、世界各地で通用する概念の道具立てがまだ明確ではない。一九六〇年代以来、「宗教」という概念が近代西洋の考え方の偏りをもっていることが鋭く批判されていて、それにかわる「宗教」理解が願われているが、なお堅固な基礎をもった方針が形成されていない。」(p.9)
このような理解の上で、古今東西の主教にかかわる古典的名著の解説となっている。
「Ⅰ 宗教学の先駆け」では、
空海 『三教指帰』
イブン=ハルドゥーン 『歴史序説』
富永仲基 『翁の文』
ヒューム 『宗教の自然史』
順次見ていくと、
ウェーバー 『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』
とか、
柳田国男 『桃太郎の母』
などが、出てくる。つまり、宗教を、社会のあり方や民俗などとも関連させて論じようという姿勢がみてとれる。『プロテスタンティズム~~』などは、そう言われてみれば、たしかに、宗教を論じた書物であるとは理解される。
また、狭い意味での「文学」からも宗教にアプローチすることもできる。
バフチン 『ドストエフスキーの詩学の諸問題』
もあげてある。
文学作品を読むとき、その根底にある宗教観というものを抜きにして、本当の理解はないだろうと思う。ドストエフスキーしかり、トルストイしかり、そして、日本の『源氏物語』『平家物語』しかり、である。
これからの読書のてがかりとして、この本もそばにおいておきたいと思っている。
『「ひとり」の哲学』山折哲雄(その二) ― 2017-01-06
2017-01-06 當山日出夫
昨日のつづきである。
やまもも書斎記 2017年1月5日
『「ひとり」の哲学』山折哲雄
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2017/01/05/8303134
読んでいて、私が付箋をつけた箇所について、いささか。
「法然や親鸞、道元や日蓮の〈思想の本質〉が、今日の日本においては少数の〈知的エリート〉をのぞいて、ほとんど何の影響ものこしてはいないということだ。なるほどその後、法然や親鸞を開祖とする教団は社会的な一大勢力を形成し、同じように曹洞宗教団や日蓮宗教団も広範な民衆のあいだに教線をひろげていった。しかしそれは、けっして開祖たちの思想そのものを起動力にして発展していったものではない。開祖たちの信仰の灯を唯一の導きとして拡大していったわけでもなかった。/大教団として発展が可能になったのは、ひとえに先祖供養を中心とする土着の民間宗教がそれを支えたからである。」(p.175) ※〈 〉内、原文傍点。
これは、そのとおり。日本の仏教史の常識的な知識といっていいかもしれない。
ただ、一般的には、教科書的な知識として、これらの教団・宗派の開祖の登場と同時に、社会的影響力をもつ大きな教団が形成されたと理解されているのかとも思う。この意味においては、ここのところを、もう少し掘り下げて論じておいてほしかった気がする。先祖供養と日本仏教の関係は、非常に重要な課題である。(たぶん、このあたりの記述のものたりなさが、この本の評価を下げる要因になっているのかとも思ったりする。)
また、特に、親鸞や日蓮の、近代日本仏教における理解というのは、近代仏教史を考えるうえで、はずすことはできないであろう。
島薗進・中島岳志.『愛国と信仰の構造-全体主義はよみがえるのか-』 (集英社新書) .集英社.2016
http://shinsho.shueisha.co.jp/kikan/0822-a/
そういえば、この本については、ちょっとだけ言及しながら、その後、書いていなかった。
やまもも書斎記 2016年6月9日
安丸良夫『神々の明治維新』
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2016/06/09/8107799
それから、現代における、道元の理解、特に、『正法眼蔵』の理解については、昨日も書いたが、唐木順三の仕事がある。山折哲雄が、唐木順三の本を知らないでいたとは思えないので、やはりこの本は「無用者」として書いた本かという気がしてくる。
昨日のつづきである。
やまもも書斎記 2017年1月5日
『「ひとり」の哲学』山折哲雄
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2017/01/05/8303134
読んでいて、私が付箋をつけた箇所について、いささか。
「法然や親鸞、道元や日蓮の〈思想の本質〉が、今日の日本においては少数の〈知的エリート〉をのぞいて、ほとんど何の影響ものこしてはいないということだ。なるほどその後、法然や親鸞を開祖とする教団は社会的な一大勢力を形成し、同じように曹洞宗教団や日蓮宗教団も広範な民衆のあいだに教線をひろげていった。しかしそれは、けっして開祖たちの思想そのものを起動力にして発展していったものではない。開祖たちの信仰の灯を唯一の導きとして拡大していったわけでもなかった。/大教団として発展が可能になったのは、ひとえに先祖供養を中心とする土着の民間宗教がそれを支えたからである。」(p.175) ※〈 〉内、原文傍点。
これは、そのとおり。日本の仏教史の常識的な知識といっていいかもしれない。
ただ、一般的には、教科書的な知識として、これらの教団・宗派の開祖の登場と同時に、社会的影響力をもつ大きな教団が形成されたと理解されているのかとも思う。この意味においては、ここのところを、もう少し掘り下げて論じておいてほしかった気がする。先祖供養と日本仏教の関係は、非常に重要な課題である。(たぶん、このあたりの記述のものたりなさが、この本の評価を下げる要因になっているのかとも思ったりする。)
また、特に、親鸞や日蓮の、近代日本仏教における理解というのは、近代仏教史を考えるうえで、はずすことはできないであろう。
島薗進・中島岳志.『愛国と信仰の構造-全体主義はよみがえるのか-』 (集英社新書) .集英社.2016
http://shinsho.shueisha.co.jp/kikan/0822-a/
そういえば、この本については、ちょっとだけ言及しながら、その後、書いていなかった。
やまもも書斎記 2016年6月9日
安丸良夫『神々の明治維新』
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2016/06/09/8107799
それから、現代における、道元の理解、特に、『正法眼蔵』の理解については、昨日も書いたが、唐木順三の仕事がある。山折哲雄が、唐木順三の本を知らないでいたとは思えないので、やはりこの本は「無用者」として書いた本かという気がしてくる。
最近のコメント