『仏像と日本人』碧海寿広 ― 2018-08-27
2018-08-27 當山日出夫(とうやまひでお)
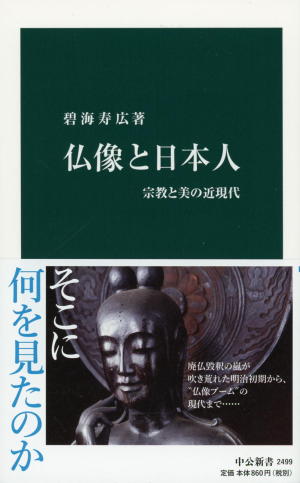
碧海寿広.『仏像と日本人-宗教と美の近現代-』(中公新書).中央公論新社.2018
http://www.chuko.co.jp/shinsho/2018/07/102499.html
和辻哲郎の『初版 古寺巡礼』を読んで、亀井勝一郎の『大和古寺風物誌』を読んだ。
やまもも書斎記 2018年8月18日
『初版 古寺巡礼』和辻哲郎
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/08/18/8944613
やまもも書斎記 2018年8月20日
『大和古寺風物誌』亀井勝一郎
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/08/20/8946045
これらの本を読んだときに、ちょうどタイミングよく刊行になった本なので、これも読んでみることにした。
読んだ印象を一言で言えば……近現代における仏像鑑賞の歴史としてよくまとまっている、ということだろうか。明治のころ、フェノロサあたりのことからはじまり、国立の博物館の設立の経緯などを経て、和辻哲郎、亀井勝一郎、などに説き及ぶ。そして、仏像写真の代表として、土門拳、入江泰吉について書いてある。戦後では、白州正子が登場する。そして、最後は、いとうせいこう・みうらじゅんの『見仏記』についてふれてある(この本については、私は未読である。)それから、京都の古都税をめぐる一件についても、言及がある。
結局のところ、仏像は信仰の対象である、だが、その一方で、仏像の美を理解するということが、近代になってからの「教養」となってきた。少なくとも仏教美術史の概略は、教養の一科目として意識されるようになってきた歴史、このようにとらえていいのではないだろうか。
やや不満に感じたところを記すならば、和辻哲郎の『古寺巡礼』が、どのように読まれ、また、改訂されてきたかについて言及があってもよかったように思う。この本では、すこしだが亀井勝一郎の『大和古寺風物誌』も、改訂の手が加わっていることが記されている。しかし、現行の新潮文庫版では、そのことがわからない。
これらの代表的な書物については、作者がどのような意図で書き、また、戦後になって改訂の手を加えていったものなのか、興味のあるところである。
現代、我々は、仏像を〈美〉の対象として見る感覚のなかにいる。教養である。だが、その一方で、〈信仰〉の対象でもある。このあたりの事情は、近年の博物館の仏像の展示方法の変化に見て取ることができるかもしれない。この本では、書かれていないことだが、東京国立博物館の仏像の展示など、近年になって大きく変わってきている。単なる〈美術品〉としてだけではなく、〈信仰〉の対象であるという側面に配慮するようになってきていると感じる。
和辻哲郎も亀井勝一郎も、歴史の中で仕事を残した人たちなのである。この歴史に今一歩踏み込んでもよかったのではないか。また、個人的な思いとしてであるが、土門拳と入江泰吉の写真には、微妙な違い……仏像をどのようなものとして見ているか……あるように感じているのだが、近代における仏像写真の歴史もまた興味深いところである。
この本では触れられていないが、さらに現代では、仏像の3Dデジタル画像、CTスキャンなど、最先端の技術をつかって、その姿にせまろうとする動きもある。文化財とデジタル技術の関係の今後を考えるうえでも、いろいろ考えるところがある。
ともあれ、今日の我々の仏像に対する見方というものも、歴史的な経緯があって形成されてきたものであるということを、再確認する意味では、この本は有益な内容になっていると感じる。このような歴史的経緯をわかったうえで、では、どのような態度で仏像に接することになるのか、いろいろ考えることになる。
http://www.chuko.co.jp/shinsho/2018/07/102499.html
和辻哲郎の『初版 古寺巡礼』を読んで、亀井勝一郎の『大和古寺風物誌』を読んだ。
やまもも書斎記 2018年8月18日
『初版 古寺巡礼』和辻哲郎
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/08/18/8944613
やまもも書斎記 2018年8月20日
『大和古寺風物誌』亀井勝一郎
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/08/20/8946045
これらの本を読んだときに、ちょうどタイミングよく刊行になった本なので、これも読んでみることにした。
読んだ印象を一言で言えば……近現代における仏像鑑賞の歴史としてよくまとまっている、ということだろうか。明治のころ、フェノロサあたりのことからはじまり、国立の博物館の設立の経緯などを経て、和辻哲郎、亀井勝一郎、などに説き及ぶ。そして、仏像写真の代表として、土門拳、入江泰吉について書いてある。戦後では、白州正子が登場する。そして、最後は、いとうせいこう・みうらじゅんの『見仏記』についてふれてある(この本については、私は未読である。)それから、京都の古都税をめぐる一件についても、言及がある。
結局のところ、仏像は信仰の対象である、だが、その一方で、仏像の美を理解するということが、近代になってからの「教養」となってきた。少なくとも仏教美術史の概略は、教養の一科目として意識されるようになってきた歴史、このようにとらえていいのではないだろうか。
やや不満に感じたところを記すならば、和辻哲郎の『古寺巡礼』が、どのように読まれ、また、改訂されてきたかについて言及があってもよかったように思う。この本では、すこしだが亀井勝一郎の『大和古寺風物誌』も、改訂の手が加わっていることが記されている。しかし、現行の新潮文庫版では、そのことがわからない。
これらの代表的な書物については、作者がどのような意図で書き、また、戦後になって改訂の手を加えていったものなのか、興味のあるところである。
現代、我々は、仏像を〈美〉の対象として見る感覚のなかにいる。教養である。だが、その一方で、〈信仰〉の対象でもある。このあたりの事情は、近年の博物館の仏像の展示方法の変化に見て取ることができるかもしれない。この本では、書かれていないことだが、東京国立博物館の仏像の展示など、近年になって大きく変わってきている。単なる〈美術品〉としてだけではなく、〈信仰〉の対象であるという側面に配慮するようになってきていると感じる。
和辻哲郎も亀井勝一郎も、歴史の中で仕事を残した人たちなのである。この歴史に今一歩踏み込んでもよかったのではないか。また、個人的な思いとしてであるが、土門拳と入江泰吉の写真には、微妙な違い……仏像をどのようなものとして見ているか……あるように感じているのだが、近代における仏像写真の歴史もまた興味深いところである。
この本では触れられていないが、さらに現代では、仏像の3Dデジタル画像、CTスキャンなど、最先端の技術をつかって、その姿にせまろうとする動きもある。文化財とデジタル技術の関係の今後を考えるうえでも、いろいろ考えるところがある。
ともあれ、今日の我々の仏像に対する見方というものも、歴史的な経緯があって形成されてきたものであるということを、再確認する意味では、この本は有益な内容になっていると感じる。このような歴史的経緯をわかったうえで、では、どのような態度で仏像に接することになるのか、いろいろ考えることになる。
コメント
トラックバック
このエントリのトラックバックURL: http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/08/27/8950799/tb
※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。
コメントをどうぞ
※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。
※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。
※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。