「悪女について」(前編) ― 2023-07-01
2023年7月1日 當山日出夫
NHK 「悪女について」(前編)
原作は有吉佐和子である。これを読んだのは、高校生のころだったろうか。あるいは、大学生になっていただろうか。面白く読んだのを憶えている。そのころ、有吉佐和子は流行の小説家であった。
今日、有吉佐和子が再び読まれているという。
私のなかで印象に残っている有吉佐和子の作品というと、『悪女について』と『華岡青洲の妻』になるだろうか。
『悪女について』は、たしか、全編、語りでなりたっていたと記憶する。いろんな登場人物が出てきて、それぞれの立場から、公子のことについて証言する。それが、それぞれに微妙に重なっていたり、食い違っていたりして、結局、公子とはどんな人物なのか、最後まで分からないままでおわる。ただ、「悪女」という印象のみが残る。そんな小説であったと憶えている。
これは、私の専門領域につながるところでは、計量文体論として非常に興味深い。一人の作家が、どれだけ、文体を変えて文章を書けるものなのか、その典型のような小説でもある。
ドラマであるが……原作にあった、虚実入り交じった、いや、いったい何が虚で何が実なのか分からない、錯綜した迷路のなかに入りこんでしまうようなところは、あまり感じない。そこそこ、リアルに作ってある。ただ、公子は嘘つきである。
このドラマに興味を持ったのは、主演が田中みな実である、ということもある。私の憶えている『悪女について』の公子の、イメージに重なるところがある。たぶん、田中みな実主演ということで、成りたっているドラマであると言ってもいいかもしれない。
さて、後編はどう展開することになるだろうか。はたして公子の真実というものが明らかになるという脚本としてあるのかどうか。続きを楽しみに見ることにしよう。
2023年6月30日記
NHK 「悪女について」(前編)
原作は有吉佐和子である。これを読んだのは、高校生のころだったろうか。あるいは、大学生になっていただろうか。面白く読んだのを憶えている。そのころ、有吉佐和子は流行の小説家であった。
今日、有吉佐和子が再び読まれているという。
私のなかで印象に残っている有吉佐和子の作品というと、『悪女について』と『華岡青洲の妻』になるだろうか。
『悪女について』は、たしか、全編、語りでなりたっていたと記憶する。いろんな登場人物が出てきて、それぞれの立場から、公子のことについて証言する。それが、それぞれに微妙に重なっていたり、食い違っていたりして、結局、公子とはどんな人物なのか、最後まで分からないままでおわる。ただ、「悪女」という印象のみが残る。そんな小説であったと憶えている。
これは、私の専門領域につながるところでは、計量文体論として非常に興味深い。一人の作家が、どれだけ、文体を変えて文章を書けるものなのか、その典型のような小説でもある。
ドラマであるが……原作にあった、虚実入り交じった、いや、いったい何が虚で何が実なのか分からない、錯綜した迷路のなかに入りこんでしまうようなところは、あまり感じない。そこそこ、リアルに作ってある。ただ、公子は嘘つきである。
このドラマに興味を持ったのは、主演が田中みな実である、ということもある。私の憶えている『悪女について』の公子の、イメージに重なるところがある。たぶん、田中みな実主演ということで、成りたっているドラマであると言ってもいいかもしれない。
さて、後編はどう展開することになるだろうか。はたして公子の真実というものが明らかになるという脚本としてあるのかどうか。続きを楽しみに見ることにしよう。
2023年6月30日記
『街道をゆく 叡山の諸道』司馬遼太郎/朝日文庫 ― 2023-07-01
2023年6月30日 當山日出夫

司馬遼太郎.『街道をゆく 叡山の諸道』(朝日文庫).朝日新聞出版.2008
https://publications.asahi.com/kaidou/16/index.shtml
もとは、一九七九年から八〇年に「週刊朝日」。
比叡山には登ったことはある。だが、そんなに考えることなく、見て帰っただけである。
司馬遼太郎の比叡山概論というべき内容である。古く最澄の事跡からはじまって、現代にまで伝わる法華大会の見学のときのことにおよぶ。
日本仏教史の専門家の目から見れば、いろいろと言いたいことがあるだろうと思う。
しかし、紀行文として読めば、とてもいい。比叡山をおとずれて、その雰囲気を感じとっている。比叡山にはきらびやかさがない。かつて、平安朝には貴族とともに栄えた寺ではあるが、その後、ある意味ではさびれてしまったとも言える。無論、信長の焼き討ち以降は、かつての面影はほとんどない。が、比叡の深山幽谷には、むかしの面影をしのぶことができる。
この本を読んで、(この本には出てこない)『源氏物語』のことを思った。その最後のところである。比叡の山のなかで、世から引きこもってしまうことを決意する浮舟が、どんな住まいをしていたのか、想像してみることになる。
また、比叡山について書いていながら、ほとんど京都のことが出てこない。出てくるのは、むしろ近江の方面である。私にとって、比叡山というのは、京都の街から見るものというイメージが強いのだが、近江から見る比叡山の視点もまた興味深いものがある。
この本の書かれたころの比叡山は、魑魅魍魎、もののけなどがいてもおかしくない。今はどうだろうか。
2023年6月29日記
https://publications.asahi.com/kaidou/16/index.shtml
もとは、一九七九年から八〇年に「週刊朝日」。
比叡山には登ったことはある。だが、そんなに考えることなく、見て帰っただけである。
司馬遼太郎の比叡山概論というべき内容である。古く最澄の事跡からはじまって、現代にまで伝わる法華大会の見学のときのことにおよぶ。
日本仏教史の専門家の目から見れば、いろいろと言いたいことがあるだろうと思う。
しかし、紀行文として読めば、とてもいい。比叡山をおとずれて、その雰囲気を感じとっている。比叡山にはきらびやかさがない。かつて、平安朝には貴族とともに栄えた寺ではあるが、その後、ある意味ではさびれてしまったとも言える。無論、信長の焼き討ち以降は、かつての面影はほとんどない。が、比叡の深山幽谷には、むかしの面影をしのぶことができる。
この本を読んで、(この本には出てこない)『源氏物語』のことを思った。その最後のところである。比叡の山のなかで、世から引きこもってしまうことを決意する浮舟が、どんな住まいをしていたのか、想像してみることになる。
また、比叡山について書いていながら、ほとんど京都のことが出てこない。出てくるのは、むしろ近江の方面である。私にとって、比叡山というのは、京都の街から見るものというイメージが強いのだが、近江から見る比叡山の視点もまた興味深いものがある。
この本の書かれたころの比叡山は、魑魅魍魎、もののけなどがいてもおかしくない。今はどうだろうか。
2023年6月29日記
『街道をゆく 十津川街道』司馬遼太郎/朝日文庫 ― 2023-07-02
2023年7月2日 當山日出夫

司馬遼太郎.『街道をゆく 十津川街道』(朝日文庫).朝日新聞出版.2008
https://publications.asahi.com/kaidou/12/index.shtml
もとは一九七七年から七八年、「週刊朝日」に連載。
この本は、とにかく理屈っぽい。奈良県の十津川村とその周辺……その当時の大塔村のことなどをふくめて……が語られるのだが、十津川村がなぜ、周囲から孤立した山の中の村なのか、理詰めで考えようとしている。その特殊性が、これでもかと強調されている。
歴史の話題としては、主に南北朝のころ、戦国時代、さらには、幕末のころのことが出てくる。これを読むと、確かに十津川村の人びとが、かなり特別な働きをしていたと思うところがある。
ただ、これも今の観点から見ると、一昔前、二昔前の十津川村の情景を記した紀行文として読むこともできる。今の十津川村は、過疎の村である。だが、道路が整備された今日からすると、司馬遼太郎が旅したころの十津川は、さらにひなびた村であったことが分かる。電灯がついたの、戦後になってからであるというようなエピソードが出てくる。
NHKのローカルのニュース、天気予報では、十津川村は頻繁に出てくる。特に風屋という地名は、気象の観測点になってもいる。日常的に馴染みのあるところではあるのだが、行ってみようと思うと、これは大変である。たぶん、泊まりがけで行くようなところになる。奈良県の北の方に住んでいると、どうしてもそういう感覚を持ってしまう。
奈良県に住んでいると、十津川村を、県の北部から見てしまいがちである。しかし、司馬遼太郎は、大阪の方から十津川村に入っている。あるいは、大阪に住まいする司馬遼太郎として、これが自然な見方なのかとも思う。
司馬遼太郎が若いとき、徒歩で旅行して知らずに寺の納屋で寝てしまっていて、翌日、粥を御馳走になったエピソードがいい。この時代、そのように旅をすることができた時代であり、また、旅人をもてなす気持ちが生きていた時代である。(宮本常一のことをふと思ってしまった。)
なお、十津川村は、日本語学、特にアクセント研究の分野では著名なところである。しかし、この本のなかでそのことに言及していなかったのは、ちょっとさびしい。
2023年6月29日記
https://publications.asahi.com/kaidou/12/index.shtml
もとは一九七七年から七八年、「週刊朝日」に連載。
この本は、とにかく理屈っぽい。奈良県の十津川村とその周辺……その当時の大塔村のことなどをふくめて……が語られるのだが、十津川村がなぜ、周囲から孤立した山の中の村なのか、理詰めで考えようとしている。その特殊性が、これでもかと強調されている。
歴史の話題としては、主に南北朝のころ、戦国時代、さらには、幕末のころのことが出てくる。これを読むと、確かに十津川村の人びとが、かなり特別な働きをしていたと思うところがある。
ただ、これも今の観点から見ると、一昔前、二昔前の十津川村の情景を記した紀行文として読むこともできる。今の十津川村は、過疎の村である。だが、道路が整備された今日からすると、司馬遼太郎が旅したころの十津川は、さらにひなびた村であったことが分かる。電灯がついたの、戦後になってからであるというようなエピソードが出てくる。
NHKのローカルのニュース、天気予報では、十津川村は頻繁に出てくる。特に風屋という地名は、気象の観測点になってもいる。日常的に馴染みのあるところではあるのだが、行ってみようと思うと、これは大変である。たぶん、泊まりがけで行くようなところになる。奈良県の北の方に住んでいると、どうしてもそういう感覚を持ってしまう。
奈良県に住んでいると、十津川村を、県の北部から見てしまいがちである。しかし、司馬遼太郎は、大阪の方から十津川村に入っている。あるいは、大阪に住まいする司馬遼太郎として、これが自然な見方なのかとも思う。
司馬遼太郎が若いとき、徒歩で旅行して知らずに寺の納屋で寝てしまっていて、翌日、粥を御馳走になったエピソードがいい。この時代、そのように旅をすることができた時代であり、また、旅人をもてなす気持ちが生きていた時代である。(宮本常一のことをふと思ってしまった。)
なお、十津川村は、日本語学、特にアクセント研究の分野では著名なところである。しかし、この本のなかでそのことに言及していなかったのは、ちょっとさびしい。
2023年6月29日記
『らんまん』あれこれ「ヤマザクラ」 ― 2023-07-02
2023年7月2日 當山日出夫
『らんまん』第13週「ヤマザクラ」
万太郎と寿恵子は祝言をあげることになった。
万太郎は寿恵子をつれて土佐に帰った。そこで、故郷の人びとに祝福される。だが、祖母のタキの病状がおもわしくない。タキが元気なうちにということなのだろう、東京から寿恵子の母(まつ)がやってくる。仲人(大畑夫妻)も一緒である。
同時に、竹雄と綾も一緒になって、これからの峰屋をもりたてていくということになった。
この祝言の場面なのだが、タキは、これからは「家」の時代ではない。個人がそれぞれに幸福を追求する時代である……という意味のことを語った。それまでは、本家と分家ということをやかましく言っていたタキが、考え方を変えたことになる。これには、分家の方としては不満もあったようだ。だが、このあたりは、ドラマの作りとしてはこのようなものかと思う。
ただ、この時代、まだ東京ではこれから鹿鳴館の時代になろうかというころであるが、この時代において、家ではなく個人の幸福ということを言うのは、早すぎるようにも思えてならない。家と個人というのは、日本の近代文学において、明治期以降、戦後にいたるまで大きなテーマとして書かれてきたところである。文学史的には、二葉亭四迷の『浮雲』もまだ登場していない(はずである)。
時代考証の点で疑問が残るというところにはなる。
しかし、これからの万太郎と寿恵子のことを考えると、このような展開であってもいいと思う。たぶん、万太郎は寿恵子と一緒に植物の世界の中で生きていくことになるのだろう。そこには、もはや峰屋も槙野の家も関係ないにちがいない。
次週以降、植物学者としての万太郎の新しい生活がはじまる。楽しみに見ることにしよう。
2023年7月1日記
『らんまん』第13週「ヤマザクラ」
万太郎と寿恵子は祝言をあげることになった。
万太郎は寿恵子をつれて土佐に帰った。そこで、故郷の人びとに祝福される。だが、祖母のタキの病状がおもわしくない。タキが元気なうちにということなのだろう、東京から寿恵子の母(まつ)がやってくる。仲人(大畑夫妻)も一緒である。
同時に、竹雄と綾も一緒になって、これからの峰屋をもりたてていくということになった。
この祝言の場面なのだが、タキは、これからは「家」の時代ではない。個人がそれぞれに幸福を追求する時代である……という意味のことを語った。それまでは、本家と分家ということをやかましく言っていたタキが、考え方を変えたことになる。これには、分家の方としては不満もあったようだ。だが、このあたりは、ドラマの作りとしてはこのようなものかと思う。
ただ、この時代、まだ東京ではこれから鹿鳴館の時代になろうかというころであるが、この時代において、家ではなく個人の幸福ということを言うのは、早すぎるようにも思えてならない。家と個人というのは、日本の近代文学において、明治期以降、戦後にいたるまで大きなテーマとして書かれてきたところである。文学史的には、二葉亭四迷の『浮雲』もまだ登場していない(はずである)。
時代考証の点で疑問が残るというところにはなる。
しかし、これからの万太郎と寿恵子のことを考えると、このような展開であってもいいと思う。たぶん、万太郎は寿恵子と一緒に植物の世界の中で生きていくことになるのだろう。そこには、もはや峰屋も槙野の家も関係ないにちがいない。
次週以降、植物学者としての万太郎の新しい生活がはじまる。楽しみに見ることにしよう。
2023年7月1日記
『若草物語』オルコット/麻生九美(訳)/光文社古典新訳文庫 ― 2023-07-03
2023年7月3日 當山日出夫

オルコット.麻生九美(訳).『若草物語』(光文社古典新訳文庫).光文社.2017
https://www.kobunsha.com/shelf/book/isbn/9784334753634
駒井稔の『編集者の読書論』を読んだら、これを読みたくなったので手にした。
やまもも書斎記 2023年6月6日
『編集者の読書論』駒井稔/光文社新書
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2023/06/06/9592259
この作品のことは小さいときから知っている。小学生か中学生かのころに、翻案抄訳本を読んだだろうか。だいたいのことは知っている。しかし、きちんと読んでみるのは初めてになる。
読んで思うこととしては、読んで面白い作品だということである。なるほど、アメリカの南北戦争の時代に書かれた作品が、今にいたるまで読み継がれているのには、それなりのわけがあると理解される。
思うこととして、やはり次の二点がある。
第一には、古風な価値観。
今の価値観からすれば、保守的で古めかしい価値観の作品ではある。だが、これは、この作品が書かれた時代……アメリカの南北戦争の時代……ということを考えれば、そのような女性の生き方が考えられた時代があったと思うことになる。
このあたり、ある意味では、安心して読める作品ということになっているのかもしれない。
第二には、新しい女性。
そうはいっても、この作品に出てくる女性たちはたくましい。時代の流れのなかにあって、おかれた境遇のなかで、自分の生きる道を見出そうとしている。自分の才覚で生きていこうとする。特に、このことは、次女のジョーについて強く感じるところである。
時代の状況のなかにあって、新しい生き方を求める女性の姿、これがこの作品の魅力なのかとも思う。
以上のように、古風さと新しさを、この作品には感じ取ることができる。
そしてなによりも、この作品の根底にある人間観がいい。今のことばでいえば、ヒューマニズムといっていいだろうか。人間というものをあくまでも肯定的に見ている。また、その人間のあつまりのなかにおいて、人間性の最も善良な部分を描き出している。これが、今の時代の文学なら、人間性の邪悪な部分をえぐるような作品もあり得よう。しかし、そうなってはいない。あくまでも、人間というものを、よきものとして描いている。この人間観が、この作品の最大の魅力といっていいだろうか。
『若草物語』は、日本語訳のタイトルである。光文社古典新訳文庫は、新しい訳本を作るにあたって、それまでの翻訳タイトルを改めることが多い。しかし、この作品については、原題「LITTLE WOMEN」をそのまま日本語にすることはしていない。従来の『若草物語』を採用している。
この作品が、日本で長く読まれてきていることの理由の一つには、このタイトルの魅力もあるのだろうと思う。
2023年6月6日記
https://www.kobunsha.com/shelf/book/isbn/9784334753634
駒井稔の『編集者の読書論』を読んだら、これを読みたくなったので手にした。
やまもも書斎記 2023年6月6日
『編集者の読書論』駒井稔/光文社新書
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2023/06/06/9592259
この作品のことは小さいときから知っている。小学生か中学生かのころに、翻案抄訳本を読んだだろうか。だいたいのことは知っている。しかし、きちんと読んでみるのは初めてになる。
読んで思うこととしては、読んで面白い作品だということである。なるほど、アメリカの南北戦争の時代に書かれた作品が、今にいたるまで読み継がれているのには、それなりのわけがあると理解される。
思うこととして、やはり次の二点がある。
第一には、古風な価値観。
今の価値観からすれば、保守的で古めかしい価値観の作品ではある。だが、これは、この作品が書かれた時代……アメリカの南北戦争の時代……ということを考えれば、そのような女性の生き方が考えられた時代があったと思うことになる。
このあたり、ある意味では、安心して読める作品ということになっているのかもしれない。
第二には、新しい女性。
そうはいっても、この作品に出てくる女性たちはたくましい。時代の流れのなかにあって、おかれた境遇のなかで、自分の生きる道を見出そうとしている。自分の才覚で生きていこうとする。特に、このことは、次女のジョーについて強く感じるところである。
時代の状況のなかにあって、新しい生き方を求める女性の姿、これがこの作品の魅力なのかとも思う。
以上のように、古風さと新しさを、この作品には感じ取ることができる。
そしてなによりも、この作品の根底にある人間観がいい。今のことばでいえば、ヒューマニズムといっていいだろうか。人間というものをあくまでも肯定的に見ている。また、その人間のあつまりのなかにおいて、人間性の最も善良な部分を描き出している。これが、今の時代の文学なら、人間性の邪悪な部分をえぐるような作品もあり得よう。しかし、そうなってはいない。あくまでも、人間というものを、よきものとして描いている。この人間観が、この作品の最大の魅力といっていいだろうか。
『若草物語』は、日本語訳のタイトルである。光文社古典新訳文庫は、新しい訳本を作るにあたって、それまでの翻訳タイトルを改めることが多い。しかし、この作品については、原題「LITTLE WOMEN」をそのまま日本語にすることはしていない。従来の『若草物語』を採用している。
この作品が、日本で長く読まれてきていることの理由の一つには、このタイトルの魅力もあるのだろうと思う。
2023年6月6日記
ブラタモリ「木曽三川」 ― 2023-07-03
2023年7月3日 當山日出夫
ブラタモリ 木曽三川
「木曽三川」ということばを始めて知ったというのが、正直なところである。その地域が、いくつかの川が一緒になる地域であるということは知っていたが、それがそのように総称され、歴史的にも由緒のある地域だとは、知らなかった。(たぶん、地理学の方面では、よく知られていることなのだろうとは思うが。)
「輪中」は知っていた。というか、昔、学校の教科書に出てきていたのを憶えている。だが、あんなに大規模なもので、独自の排水設備まで持っていたことは知らなかった。
断層とか、標高八メートルの山とか、いろいろと面白かった。
今から数十年前まで、戦後しばらくのころまで、「堀田」が普通に見られたという。今、我々が、イメージする、日本の稲作耕作の風景というのは、意外と新しいものなのだろうと思う。きちんと区画整理整理された水田、あるいは、山腹につくられた棚田などを思い浮かべるが、はたして、これらは、歴史的にどのようにして形成されたものなのだろうか。
日本の歴史を考えるとき、とにかくキーになるのが、米作である。米を基準に、主に弥生時代以降の日本文化を考えることもできよう。日本人はずっと米を作ってきたのだと。あるいは、そうではなく、漁業や林業、それから、商工業など、米作以外の生業にたずさわる人びとを考えることも重要である。これらをどう総合的に考えるべきなのか、今から勉強してみようという気にはならないのだが、ただ、興味関心としては持っている。
2023年7月2日記
ブラタモリ 木曽三川
「木曽三川」ということばを始めて知ったというのが、正直なところである。その地域が、いくつかの川が一緒になる地域であるということは知っていたが、それがそのように総称され、歴史的にも由緒のある地域だとは、知らなかった。(たぶん、地理学の方面では、よく知られていることなのだろうとは思うが。)
「輪中」は知っていた。というか、昔、学校の教科書に出てきていたのを憶えている。だが、あんなに大規模なもので、独自の排水設備まで持っていたことは知らなかった。
断層とか、標高八メートルの山とか、いろいろと面白かった。
今から数十年前まで、戦後しばらくのころまで、「堀田」が普通に見られたという。今、我々が、イメージする、日本の稲作耕作の風景というのは、意外と新しいものなのだろうと思う。きちんと区画整理整理された水田、あるいは、山腹につくられた棚田などを思い浮かべるが、はたして、これらは、歴史的にどのようにして形成されたものなのだろうか。
日本の歴史を考えるとき、とにかくキーになるのが、米作である。米を基準に、主に弥生時代以降の日本文化を考えることもできよう。日本人はずっと米を作ってきたのだと。あるいは、そうではなく、漁業や林業、それから、商工業など、米作以外の生業にたずさわる人びとを考えることも重要である。これらをどう総合的に考えるべきなのか、今から勉強してみようという気にはならないのだが、ただ、興味関心としては持っている。
2023年7月2日記
ドキュメント72時間「大病院の屋上庭園で」 ― 2023-07-03
2023年7月3日 當山日出夫
ドキュメント72時間 大病院の屋上庭園で
東京医科歯科大学にある屋上庭園が舞台。
病院だけに、登場するのは、病気の人あるいは医療関係者である。こういうのを見るといろいろ考えることが多くある。病気になって、人は何を思うのだろうか。
シロツメクサに寄ってくる蜜蜂に、都会のなかで、ふと自然のいとなみを見つける、そんなよろこびのシーンが印象的である。
得てして暗くなりがちな話題かもしれないが、最後にでてきていた(再登場)の子供の笑顔がよかった。病院には、やはり笑顔がふさわしいのかもしれない。
2023年7月2日記
ドキュメント72時間 大病院の屋上庭園で
東京医科歯科大学にある屋上庭園が舞台。
病院だけに、登場するのは、病気の人あるいは医療関係者である。こういうのを見るといろいろ考えることが多くある。病気になって、人は何を思うのだろうか。
シロツメクサに寄ってくる蜜蜂に、都会のなかで、ふと自然のいとなみを見つける、そんなよろこびのシーンが印象的である。
得てして暗くなりがちな話題かもしれないが、最後にでてきていた(再登場)の子供の笑顔がよかった。病院には、やはり笑顔がふさわしいのかもしれない。
2023年7月2日記
『白河・会津のみち、赤坂散歩』司馬遼太郎/朝日文庫 ― 2023-07-04
2023年7月4日 當山日出夫
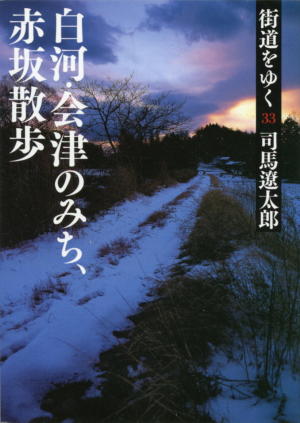
司馬遼太郎.『白河・会津のみち、赤坂散歩』(朝日文庫).朝日新聞出版.2009
https://publications.asahi.com/kaidou/33/index.shtml
もとは、一九八八年から八九年。「週刊朝日」連載。
東北の方にはほとんど行ったことがない。白河と言われても、名前を知っている。あるいは、古典の知識として「白河の関」を知っている程度である。
会津にも行ったことがない。
この本を読むと、古風なひなびた景色が、これが書かれた時代まではまだ残っていたことが知られる。
会津のことは、以前のNHKの大河ドラマの『八重の桜』のイメージが強い。幕末の時代にあって、貧乏くじをひくことになった……と言っていいかどうかは微妙だが……の会津藩の悲哀が、強く印象に残っている。
「赤坂散歩」は、この「街道をゆく」シリーズで、始めて取りあげた東京ということになる。それを赤坂から始めることとしたのは、本所深川のあたりは土俗的にすぎるという理由もあり、また、自分の家、東京での宿から、出発してその地のことを考えるというスタイルにも由来するもののようだ。
司馬遼太郎は、オークラに宿泊すると決めていたらしい。そういえば、たしか以前読んだ高峰秀子のエッセイに、司馬遼太郎とオークラで会うシーンがあったように記憶するのだが、どうだったろうか。
自分の家から出発して考えるというのは、先に読んだ「十津川村」についてもいえる。司馬遼太郎は、十津川村に大阪から入っている。自分の住まいする場所から見ての十津川村を描いている。
赤坂あたりは、昔は閑静な街でもあった。そのころの面影を、司馬遼太郎はたどっている。今の赤坂はどうだろうか。都会のまんなかという印象になってしまった感じがする。もう東京に行っても赤坂あたりを歩くことはないだろうと思う。昔、学生のころは、赤坂見附から国立劇場まで歩いたりしたものであったが。
2023年6月30日記
https://publications.asahi.com/kaidou/33/index.shtml
もとは、一九八八年から八九年。「週刊朝日」連載。
東北の方にはほとんど行ったことがない。白河と言われても、名前を知っている。あるいは、古典の知識として「白河の関」を知っている程度である。
会津にも行ったことがない。
この本を読むと、古風なひなびた景色が、これが書かれた時代まではまだ残っていたことが知られる。
会津のことは、以前のNHKの大河ドラマの『八重の桜』のイメージが強い。幕末の時代にあって、貧乏くじをひくことになった……と言っていいかどうかは微妙だが……の会津藩の悲哀が、強く印象に残っている。
「赤坂散歩」は、この「街道をゆく」シリーズで、始めて取りあげた東京ということになる。それを赤坂から始めることとしたのは、本所深川のあたりは土俗的にすぎるという理由もあり、また、自分の家、東京での宿から、出発してその地のことを考えるというスタイルにも由来するもののようだ。
司馬遼太郎は、オークラに宿泊すると決めていたらしい。そういえば、たしか以前読んだ高峰秀子のエッセイに、司馬遼太郎とオークラで会うシーンがあったように記憶するのだが、どうだったろうか。
自分の家から出発して考えるというのは、先に読んだ「十津川村」についてもいえる。司馬遼太郎は、十津川村に大阪から入っている。自分の住まいする場所から見ての十津川村を描いている。
赤坂あたりは、昔は閑静な街でもあった。そのころの面影を、司馬遼太郎はたどっている。今の赤坂はどうだろうか。都会のまんなかという印象になってしまった感じがする。もう東京に行っても赤坂あたりを歩くことはないだろうと思う。昔、学生のころは、赤坂見附から国立劇場まで歩いたりしたものであったが。
2023年6月30日記
『どうする家康』あれこれ「はるかに遠い夢」 ― 2023-07-04
2023年7月4日 當山日出夫
『どうする家康』第25回「はるかに遠い夢」
歴史の事実として、瀬名(築山殿)と信康がどうなるか、だいたいのところは分かっていたところである。そこを、このドラマでは、どう描いてみせるかというのが、たぶん。ドラマの前半の見せ場ということになろうか。
このドラマでは、瀬名をいい人に描いている。その考えるところは、今の政治感覚からしえも空想的ともいえるが、しかし、平和な世の中がくることを望んでいた、その理想を求める気持ちはつたわってくる。これに、信康も、また家康も、基本的には同意していたようである。
だが、信長の圧倒的な勢力の前では、そのような理想論はふきとんでしまう。また、武田も瀬名の理想に同調するということはなかった。信長のことを考えれば、その決着を自らつけるということは、いたしかたないことなのかもしれない。
それでも、信長の目を欺いて逃げるということは可能だったかとも思う。
ここで、瀬名と信康の自害の場にいたのが、大鼠と服部半蔵であった。最後は、これらの人物の手を借りるということになるのは、他の家臣では手が出せない役目ということなのであろう。
ところで、ちょっとだけ出ていたのが千代。勝頼のもとを去るときの笑みが、いったい何を意味するのであろうか。これから、再び千代が登場することがあるだろうか。(できれば、これで終わりではなく、登場してもらいたいと思っている。)
次回、瀬名のなきあとの家康を描くことになるようだ。楽しみに見ることにしよう。
2023年7月3日記
『どうする家康』第25回「はるかに遠い夢」
歴史の事実として、瀬名(築山殿)と信康がどうなるか、だいたいのところは分かっていたところである。そこを、このドラマでは、どう描いてみせるかというのが、たぶん。ドラマの前半の見せ場ということになろうか。
このドラマでは、瀬名をいい人に描いている。その考えるところは、今の政治感覚からしえも空想的ともいえるが、しかし、平和な世の中がくることを望んでいた、その理想を求める気持ちはつたわってくる。これに、信康も、また家康も、基本的には同意していたようである。
だが、信長の圧倒的な勢力の前では、そのような理想論はふきとんでしまう。また、武田も瀬名の理想に同調するということはなかった。信長のことを考えれば、その決着を自らつけるということは、いたしかたないことなのかもしれない。
それでも、信長の目を欺いて逃げるということは可能だったかとも思う。
ここで、瀬名と信康の自害の場にいたのが、大鼠と服部半蔵であった。最後は、これらの人物の手を借りるということになるのは、他の家臣では手が出せない役目ということなのであろう。
ところで、ちょっとだけ出ていたのが千代。勝頼のもとを去るときの笑みが、いったい何を意味するのであろうか。これから、再び千代が登場することがあるだろうか。(できれば、これで終わりではなく、登場してもらいたいと思っている。)
次回、瀬名のなきあとの家康を描くことになるようだ。楽しみに見ることにしよう。
2023年7月3日記
ドキュメント20min.「CО2ジャーニー」 ― 2023-07-04
2023年7月4日 當山日出夫
ドキュメント20min. CО2ジャーニー
この番組の一番いいところは、最後に、この番組の製作のためにどれだけのCO2を排出することになったか、示していたところかもしれない。放送番組の製作それ自体も、確実にCO2を排出することになる。
いい企画だと思う。旅行することで、いったいどれほどのCO2を排出するのか、個々の移動手段に応じて、数値で示しているのが分かりやすい。また、その排出したCO2を吸収するのに、どれほどの森林が必要になるのか、これも具体的で分かりやすいものだった。
たぶん意図的にだと思うが、この番組の中で、SDGsということばを一度も使っていなかった(ように思う。)このようなことばの有無とは別の次元で、日常の生活のなかで出来ることをすることに意味がある、ということなのだろう。
2023年7月3日記
ドキュメント20min. CО2ジャーニー
この番組の一番いいところは、最後に、この番組の製作のためにどれだけのCO2を排出することになったか、示していたところかもしれない。放送番組の製作それ自体も、確実にCO2を排出することになる。
いい企画だと思う。旅行することで、いったいどれほどのCO2を排出するのか、個々の移動手段に応じて、数値で示しているのが分かりやすい。また、その排出したCO2を吸収するのに、どれほどの森林が必要になるのか、これも具体的で分かりやすいものだった。
たぶん意図的にだと思うが、この番組の中で、SDGsということばを一度も使っていなかった(ように思う。)このようなことばの有無とは別の次元で、日常の生活のなかで出来ることをすることに意味がある、ということなのだろう。
2023年7月3日記
最近のコメント