『アンナ・カレーニナ』トルストイ/望月哲男(訳)(四) ― 2020-01-05
2020-01-05 當山日出夫(とうやまひでお)
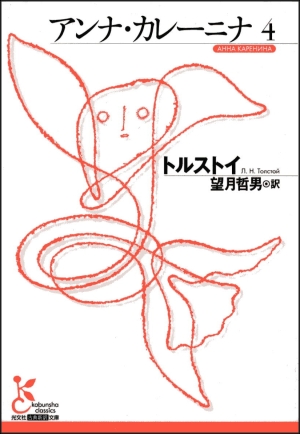
トルストイ.望月哲男(訳).『アンナ・カレーニナ』(一)(光文社古典新訳文庫).光文社.2008
https://www.kotensinyaku.jp/books/book70/
続きである。
やまもも書斎記 2020年1月4日
『アンナ・カレーニナ』トルストイ/望月哲男(訳)(三)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/01/04/9197937
『アンナ・カレーニナ』を読むのは、意識しては二回目になる。若いころ、手にしたような記憶が無いではないのだが、さっぱり忘れてしまっている。もうこの年になって、新しい本を読むよりも、「古典」……狭義の文学にこだわらず人文学の古典……を読んで時間をつかいたいと思うようになってきた。この意味においても、『アンナ・カレーニナ』は、何度読んでもいいと感じる。
全巻を読んでの印象は、やはり一九世紀的な恋愛小説だな、ということである。だが、それのみではない。作者(トルストイ)は、この小説の中に、小説という文学の形式に盛り込めるだけのすべてをそそぎこんでいるとも感じる。(それをより強く感じるのは『戦争と平和』なのであるが、これも、新しい訳が出るようなので、それで再読してみたいと思っている。)
前回読んだときには、アンナの最後の死の場面で、もうこれで終わっていいのではないかと感じたものである。が、今回、読んでみて、その後日譚のところにこころひかれる。作者としては、アンナの死の後の登場人物のことまで書いて、この小説は完成する。それだけ、この小説のふくむ範囲は広い。
そして、このようなことは当たり前のことかもしれないが、読後感に残るのは、ある種の宗教的感銘とでもいうべきものである。特におもてだって、宗教……キリスト教……のことが大きく書かれているというのではないが、読み終わって、大きく宗教的な意識の中に回帰していくことを、感じるのである。
私は、ロシアのキリスト教のことについてはうとい。しかし、宗教というものが、何かしら普遍性をもつものであるとするならば、トルストイの作品は、ロシアのキリスト教を描くことによって、宗教一般の普遍性……そのようなものを考えてみるとしてであるが……を、見事に作品のなかにとりこんでいると思える。この『アンナ・カレーニナ』が、ただアンナという女性の恋の物語におわっていない、さらにその外側に、あるいは、さらにその高みに達していると言っていいであろうか。
これからも、「古典」を読んでいきたいと強く感じる次第である。
2019年12月27日記
https://www.kotensinyaku.jp/books/book70/
続きである。
やまもも書斎記 2020年1月4日
『アンナ・カレーニナ』トルストイ/望月哲男(訳)(三)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/01/04/9197937
『アンナ・カレーニナ』を読むのは、意識しては二回目になる。若いころ、手にしたような記憶が無いではないのだが、さっぱり忘れてしまっている。もうこの年になって、新しい本を読むよりも、「古典」……狭義の文学にこだわらず人文学の古典……を読んで時間をつかいたいと思うようになってきた。この意味においても、『アンナ・カレーニナ』は、何度読んでもいいと感じる。
全巻を読んでの印象は、やはり一九世紀的な恋愛小説だな、ということである。だが、それのみではない。作者(トルストイ)は、この小説の中に、小説という文学の形式に盛り込めるだけのすべてをそそぎこんでいるとも感じる。(それをより強く感じるのは『戦争と平和』なのであるが、これも、新しい訳が出るようなので、それで再読してみたいと思っている。)
前回読んだときには、アンナの最後の死の場面で、もうこれで終わっていいのではないかと感じたものである。が、今回、読んでみて、その後日譚のところにこころひかれる。作者としては、アンナの死の後の登場人物のことまで書いて、この小説は完成する。それだけ、この小説のふくむ範囲は広い。
そして、このようなことは当たり前のことかもしれないが、読後感に残るのは、ある種の宗教的感銘とでもいうべきものである。特におもてだって、宗教……キリスト教……のことが大きく書かれているというのではないが、読み終わって、大きく宗教的な意識の中に回帰していくことを、感じるのである。
私は、ロシアのキリスト教のことについてはうとい。しかし、宗教というものが、何かしら普遍性をもつものであるとするならば、トルストイの作品は、ロシアのキリスト教を描くことによって、宗教一般の普遍性……そのようなものを考えてみるとしてであるが……を、見事に作品のなかにとりこんでいると思える。この『アンナ・カレーニナ』が、ただアンナという女性の恋の物語におわっていない、さらにその外側に、あるいは、さらにその高みに達していると言っていいであろうか。
これからも、「古典」を読んでいきたいと強く感じる次第である。
2019年12月27日記
コメント
トラックバック
このエントリのトラックバックURL: http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/01/05/9198302/tb
※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。
コメントをどうぞ
※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。
※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。
※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。