『保守と大東亜戦争』中島岳志 ― 2018-10-11
2018-10-11 當山日出夫(とうやまひでお)

中島岳志.『保守と大東亜戦争』(集英社新書).集英社.2018
http://shinsho.shueisha.co.jp/kikan/0941-a/
集英社新書で出た本ということもあって、気楽に読んだ本である。特に目新しいことが書いてあるということはない。しかし、この本に書かれているようなこと踏まえたうえで、歴史の議論はなされるべきだろうと思う。
この本を読んで思うことなど書くとすると、次の二点。
第一には、著者ならではの「保守」の論理にしたがっている。「保守思想」について、まず定義がある。
著者(中島岳志)が、大学にはいってから手にした西部邁を引用する。
「自由民主主義は保守主義であらざるをえない」
さらにつづけて、このように著者(中島岳志)は記している。
「保守は人間に対する懐疑的な見方を共有し、理性の万能性や無謬を疑います。そして、その懐疑的な人間観は自己にも向けられます。自分の理性や知性もパーフェクトなものではなく、自分の主張の中にも間違いや誤認が含まれていると考えます。その自己認識は、異なる他者の意見を聞こうとする姿勢につながり、対話や議論を促進します。そして、他者の見解の中に理があると判断した場合には、協議による合意形成を進めていきます。」(p.18)
このような心性のありかたこそ、リベラルであるとする。これはこれで一つの立場であると認める。
このような意味では、現在の政権の政策などは、「保守」「リベラル」から最も遠いものであるということになるであろう。
第二には、このような「保守」の心性を持った人びとが、戦前・戦中の時期にどのような、言論活動をおこなったかをみていくことになる。
取り上げられているのは、
竹山道雄
田中美知太郎
猪木正道
福田恆存
池島信平
山本七平
会田雄次
林健太郎
などである。
これらの人びとの言説をとりあげながら、「保守」の心性をもった人間こそが、戦争に反対していたと論じる。
ここのところ、特に目新しい議論というわけではない。だが、改めて、この本に示されているような形で提示されると、なるほど、「保守」とは、現実の政治の動きに抵抗し、歴史と伝統のなかに自己の立脚点を見いだす……このようなことが再確認される。
以上の二点が、この本を読んで感ずることなどである。
無論、戦前、戦中において、戦争に反対した立場をとったのは、「保守」だけに限らないであろう。だが、今の時代において、「保守」といえば、ただ戦前回帰、大東亜戦争肯定論、このように考えがちな傾向に対しては、ちょっと待って考えてみようとすることになる。
この本からすこし引用しておくと、鶴見俊輔について、次のように述べる。
「鶴見の指摘は非常に重要です。戦前の日本は保守的だったから権威主義体制を拡大させ、全体主義的なヴィジョンにのめり込んでいったのではありません。逆です。近代日本における保守の空洞化こそが、大東亜戦争に至るプロセスを制止できなかった要因なのです。」(p.67)
戦前の歴史について、さらに考えてみることの必要性をつよく感じさせる本である。
http://shinsho.shueisha.co.jp/kikan/0941-a/
集英社新書で出た本ということもあって、気楽に読んだ本である。特に目新しいことが書いてあるということはない。しかし、この本に書かれているようなこと踏まえたうえで、歴史の議論はなされるべきだろうと思う。
この本を読んで思うことなど書くとすると、次の二点。
第一には、著者ならではの「保守」の論理にしたがっている。「保守思想」について、まず定義がある。
著者(中島岳志)が、大学にはいってから手にした西部邁を引用する。
「自由民主主義は保守主義であらざるをえない」
さらにつづけて、このように著者(中島岳志)は記している。
「保守は人間に対する懐疑的な見方を共有し、理性の万能性や無謬を疑います。そして、その懐疑的な人間観は自己にも向けられます。自分の理性や知性もパーフェクトなものではなく、自分の主張の中にも間違いや誤認が含まれていると考えます。その自己認識は、異なる他者の意見を聞こうとする姿勢につながり、対話や議論を促進します。そして、他者の見解の中に理があると判断した場合には、協議による合意形成を進めていきます。」(p.18)
このような心性のありかたこそ、リベラルであるとする。これはこれで一つの立場であると認める。
このような意味では、現在の政権の政策などは、「保守」「リベラル」から最も遠いものであるということになるであろう。
第二には、このような「保守」の心性を持った人びとが、戦前・戦中の時期にどのような、言論活動をおこなったかをみていくことになる。
取り上げられているのは、
竹山道雄
田中美知太郎
猪木正道
福田恆存
池島信平
山本七平
会田雄次
林健太郎
などである。
これらの人びとの言説をとりあげながら、「保守」の心性をもった人間こそが、戦争に反対していたと論じる。
ここのところ、特に目新しい議論というわけではない。だが、改めて、この本に示されているような形で提示されると、なるほど、「保守」とは、現実の政治の動きに抵抗し、歴史と伝統のなかに自己の立脚点を見いだす……このようなことが再確認される。
以上の二点が、この本を読んで感ずることなどである。
無論、戦前、戦中において、戦争に反対した立場をとったのは、「保守」だけに限らないであろう。だが、今の時代において、「保守」といえば、ただ戦前回帰、大東亜戦争肯定論、このように考えがちな傾向に対しては、ちょっと待って考えてみようとすることになる。
この本からすこし引用しておくと、鶴見俊輔について、次のように述べる。
「鶴見の指摘は非常に重要です。戦前の日本は保守的だったから権威主義体制を拡大させ、全体主義的なヴィジョンにのめり込んでいったのではありません。逆です。近代日本における保守の空洞化こそが、大東亜戦争に至るプロセスを制止できなかった要因なのです。」(p.67)
戦前の歴史について、さらに考えてみることの必要性をつよく感じさせる本である。
『カササギ殺人事件』アンソニー・ホロヴィッツ ― 2018-10-12
2018-10-12 當山日出夫(とうやまひでお)

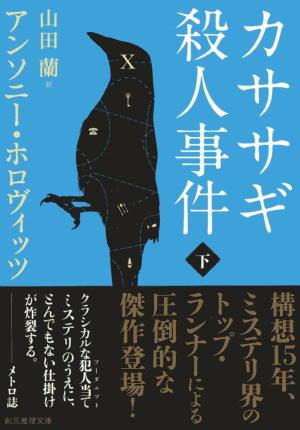
アンソニー・ホロヴィッツ.山田蘭(訳).『カササギ殺人事件』(上・下)(創元推理文庫).東京創元社.2018
http://www.tsogen.co.jp/np/isbn/9784488265076
http://www.tsogen.co.jp/np/isbn/9784488265083
上下二巻になる大作である。たぶん、今年のミステリベストには絶対入るにちがいない。まさに、ミステリの王道をいきながら、大胆で斬新なトリックでもある。
この本について書くのはむずかしい。が、思うところを記せば以下の三点ぐらいになるだろうか。
第一に、古典的フーダニットの作品。しかも、それが、多重構造になっている(まあ、ここまでは書いていいだろう)。
第二に、クリスティなどの古典的探偵小説へのオマージュにあふれている。ここのところは、さりげなく書いてあったり、あるいは、はっきりとそのように書いてあったりであるが、いたるところに、古典ミステリへの郷愁がただよっている。
第三に、これは、この作品のトリックには、東京創元社の編集部も加担している……としか思えない、本のつくりになっている。文庫本を手にして読み始めて、ふとある疑問をいだく。普通のミステリの文庫本と違う編集になっていると感じさせるところがある。それが、意味のあることであることは、読み終えて始めてわかる。
以上の三点ぐらいであろうか。
とにかく、上巻は、一気に読める。そして、下巻を読み始めてみると、いったいこれは何だと、大きな疑問の中につきおとされる。だが、こここで、上下巻を通じての多層構造になった謎は、最後には、見事に解き明かされる。フーダニットの傑作である。
なお、付言するならば……通常のミステリ作品として、登場人物の一覧が、本の中にある。だが、ある登場人物だけは、その一覧に出てきていない。これは、ミステリの老舗、東京創元社ならではのプライドをかけた編集と理解しておきたい。
http://www.tsogen.co.jp/np/isbn/9784488265076
http://www.tsogen.co.jp/np/isbn/9784488265083
上下二巻になる大作である。たぶん、今年のミステリベストには絶対入るにちがいない。まさに、ミステリの王道をいきながら、大胆で斬新なトリックでもある。
この本について書くのはむずかしい。が、思うところを記せば以下の三点ぐらいになるだろうか。
第一に、古典的フーダニットの作品。しかも、それが、多重構造になっている(まあ、ここまでは書いていいだろう)。
第二に、クリスティなどの古典的探偵小説へのオマージュにあふれている。ここのところは、さりげなく書いてあったり、あるいは、はっきりとそのように書いてあったりであるが、いたるところに、古典ミステリへの郷愁がただよっている。
第三に、これは、この作品のトリックには、東京創元社の編集部も加担している……としか思えない、本のつくりになっている。文庫本を手にして読み始めて、ふとある疑問をいだく。普通のミステリの文庫本と違う編集になっていると感じさせるところがある。それが、意味のあることであることは、読み終えて始めてわかる。
以上の三点ぐらいであろうか。
とにかく、上巻は、一気に読める。そして、下巻を読み始めてみると、いったいこれは何だと、大きな疑問の中につきおとされる。だが、こここで、上下巻を通じての多層構造になった謎は、最後には、見事に解き明かされる。フーダニットの傑作である。
なお、付言するならば……通常のミステリ作品として、登場人物の一覧が、本の中にある。だが、ある登場人物だけは、その一覧に出てきていない。これは、ミステリの老舗、東京創元社ならではのプライドをかけた編集と理解しておきたい。
『カフカ短篇集』(岩波文庫) ― 2018-10-13
2018-10-13 當山日出夫(とうやまひでお)
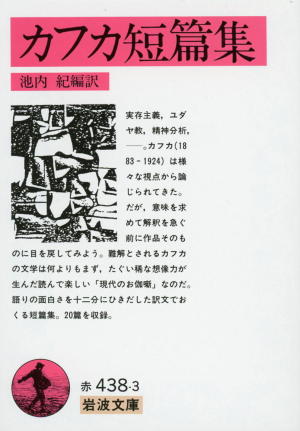
カフカ.池内紀(訳).『カフカ短篇集』(岩波文庫).岩波書店.1987
https://www.iwanami.co.jp/book/b247782.html
はっきりいって、よくわからない。しかし、何かしら人をひきつける魅力のある作品である。
世界文学の名作の読み直しで、カフカを手にしている。今、短篇集で手軽に読めるものとしては、岩波文庫版ということになるようだ。
なんといえばいいのだろうか、たとえていえば、世界が反転して反対側から見えてしまうような、そんな感覚におちいる。そして、どの作品も、何かしら「寓意」を感じさせる。ここに、無理に、何かを読みとってしまおうとはしない方がいいのかもしれない。(無論、文学研究という分野では、カフカの作品をどのように解釈するかということで、大きな問題があるであろうことは、理解できるつもりだが。)
読みながら付箋をつけた箇所。「プロメテウス」という作品の最後。
「あとには不可解な岩がのこった。言い伝えは不可解なものを解きあかそうとつとめるだろう。だが、真理をおびて始まるものは、しょせんは不可解なものとして終わらなくてはならないのだ。」(p.231)
たぶん、この作品のこのことばほど、カフカの作品について、その「不可解」について、語ったものはないのではないだろうか。
https://www.iwanami.co.jp/book/b247782.html
はっきりいって、よくわからない。しかし、何かしら人をひきつける魅力のある作品である。
世界文学の名作の読み直しで、カフカを手にしている。今、短篇集で手軽に読めるものとしては、岩波文庫版ということになるようだ。
なんといえばいいのだろうか、たとえていえば、世界が反転して反対側から見えてしまうような、そんな感覚におちいる。そして、どの作品も、何かしら「寓意」を感じさせる。ここに、無理に、何かを読みとってしまおうとはしない方がいいのかもしれない。(無論、文学研究という分野では、カフカの作品をどのように解釈するかということで、大きな問題があるであろうことは、理解できるつもりだが。)
読みながら付箋をつけた箇所。「プロメテウス」という作品の最後。
「あとには不可解な岩がのこった。言い伝えは不可解なものを解きあかそうとつとめるだろう。だが、真理をおびて始まるものは、しょせんは不可解なものとして終わらなくてはならないのだ。」(p.231)
たぶん、この作品のこのことばほど、カフカの作品について、その「不可解」について、語ったものはないのではないだろうか。
『まんぷく』あれこれ「…会いません、今は」 ― 2018-10-14
2018-10-14 當山日出夫(とうやまひでお)
『まんぷく』第2週「…会いません、今は」
https://www.nhk.or.jp/mampuku/story/
前回は、
やまもも書斎記 2018年10月7日
『まんぷく』あれこれ「結婚はまだまだ先!」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/10/07/8969552
前作の『半分、青い。』が、あえて朝ドラらしくない作り方でのぞんでいたのに対して、この作は、逆に朝ドラの本筋を行くようである。
この週の流れは、次の二つだろうか。
第一に、姉の咲の死。
咲の結婚式の時の幻灯のときのことが、福子と萬平との出会いの一コマであることを思うと、この週での咲の死は、いかにも悲しい出来事である。いや、幻灯の時のことがあるからこそ、福子は萬平を、より意識するようになったようでもある。
第二に、咲の病気から死ぬまでに関係して、福子と萬平の恋(?)のゆくえ。
最終的には、咲の死ということはあったものの、福子は萬平のとこに赴くことになる。しかし、依然として母(鈴)は、二人の関係に反対のようではあるが、ここは、ドラマの約束として、それを乗り越えて、福子と萬平は結ばれることになるのだろう。
この二つの軸を中心にして、この週の展開があったと見ていた。
とにかくこのドラマは、主演の二人(安藤サクラ、長谷川博己)がうまい。
時代は、昭和一七年。まだ、戦況としては、日本が決定的に不利になる前ということになる。そうであろうか、金属の供出などのことはあったとしても、人びとは、この戦争が勝利で終わることを、信じて疑わないようである。(無論、現在の我々は、この後の歴史の結果を知ってはいるのであるが。)
また、ホテルの従業員(保科)めぐっての野呂と牧も、コミカルで面白い。
そして、最後、土曜日のおわりで、ドラマは新たな展開を見せるところで終わっていた。まあ、怪しいのは、共同経営者、社長の、加治谷ということなんだろうが……このあたり、次週、どのように決着をみるか、楽しみでもある。
『まんぷく』第2週「…会いません、今は」
https://www.nhk.or.jp/mampuku/story/
前回は、
やまもも書斎記 2018年10月7日
『まんぷく』あれこれ「結婚はまだまだ先!」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/10/07/8969552
前作の『半分、青い。』が、あえて朝ドラらしくない作り方でのぞんでいたのに対して、この作は、逆に朝ドラの本筋を行くようである。
この週の流れは、次の二つだろうか。
第一に、姉の咲の死。
咲の結婚式の時の幻灯のときのことが、福子と萬平との出会いの一コマであることを思うと、この週での咲の死は、いかにも悲しい出来事である。いや、幻灯の時のことがあるからこそ、福子は萬平を、より意識するようになったようでもある。
第二に、咲の病気から死ぬまでに関係して、福子と萬平の恋(?)のゆくえ。
最終的には、咲の死ということはあったものの、福子は萬平のとこに赴くことになる。しかし、依然として母(鈴)は、二人の関係に反対のようではあるが、ここは、ドラマの約束として、それを乗り越えて、福子と萬平は結ばれることになるのだろう。
この二つの軸を中心にして、この週の展開があったと見ていた。
とにかくこのドラマは、主演の二人(安藤サクラ、長谷川博己)がうまい。
時代は、昭和一七年。まだ、戦況としては、日本が決定的に不利になる前ということになる。そうであろうか、金属の供出などのことはあったとしても、人びとは、この戦争が勝利で終わることを、信じて疑わないようである。(無論、現在の我々は、この後の歴史の結果を知ってはいるのであるが。)
また、ホテルの従業員(保科)めぐっての野呂と牧も、コミカルで面白い。
そして、最後、土曜日のおわりで、ドラマは新たな展開を見せるところで終わっていた。まあ、怪しいのは、共同経営者、社長の、加治谷ということなんだろうが……このあたり、次週、どのように決着をみるか、楽しみでもある。
追記 2018-10-23
この続きは、
やまもも書斎記 2018年10月23日
『まんぷく』あれこれ「そんなん絶対ウソ!」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/10/23/8980523
この続きは、
やまもも書斎記 2018年10月23日
『まんぷく』あれこれ「そんなん絶対ウソ!」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/10/23/8980523
『審判』カフカ ― 2018-10-15
2018-10-15 當山日出夫(とうやまひでお)

カフカ.辻瑆(訳).『審判』(岩波文庫).岩波書店.1966
https://www.iwanami.co.jp/book/b247781.html
とにかく読んだのだが……はっきりいって、カフカのこの作品はよくわからなかった。
普通のサラリーマンが突然に逮捕されて、裁判にかけられる。たしかに、いいようのない不条理である。が、その裁判、あるいは、裁判所が、『城』のように明確なイメージで語られることがない。そのような状況に陥ったことはわかるのだが、では、どうだというのであろう。いまひとつ、登場人物に共感できないで終わってしまった。
とはいえ、作品自体は、きわめて読みやすい。だが、カフカの作品は、これが決定稿であるというものがない。翻訳につかってあるのは1946年版。
この作品、個々の章、個々の場面は、明瞭なのであるが、しかし、では、この「小説」全体として何を語ろうとしているのか、それがはっきりしない。何かの寓意のようなものを感じるところがないではないが、これも、カフカを文学史的にどう理解するかということと、不可分なものであるとともいえる。
読みながら付箋をつけた箇所。岩波文庫版で第九章の終わり。
「「だから私は裁判所の者なのだ」と僧は言い、「ならばどうしてあなたに求めることがあろう。裁判所はあなたに何も求めはしないのだ。あなたが来れば迎え、行くならば去らせるだけだ」(p.329)
少なくとも二一世紀の今日において読んでみても、何かしらの文学的感銘とでもいうべきものを、どこかに感じることができる作品でもある。この作品、光文社古典新訳文庫で『訴訟』のタイトルでも別の訳が出ている。こちらも、読んでおきたいと思う。
https://www.iwanami.co.jp/book/b247781.html
とにかく読んだのだが……はっきりいって、カフカのこの作品はよくわからなかった。
普通のサラリーマンが突然に逮捕されて、裁判にかけられる。たしかに、いいようのない不条理である。が、その裁判、あるいは、裁判所が、『城』のように明確なイメージで語られることがない。そのような状況に陥ったことはわかるのだが、では、どうだというのであろう。いまひとつ、登場人物に共感できないで終わってしまった。
とはいえ、作品自体は、きわめて読みやすい。だが、カフカの作品は、これが決定稿であるというものがない。翻訳につかってあるのは1946年版。
この作品、個々の章、個々の場面は、明瞭なのであるが、しかし、では、この「小説」全体として何を語ろうとしているのか、それがはっきりしない。何かの寓意のようなものを感じるところがないではないが、これも、カフカを文学史的にどう理解するかということと、不可分なものであるとともいえる。
読みながら付箋をつけた箇所。岩波文庫版で第九章の終わり。
「「だから私は裁判所の者なのだ」と僧は言い、「ならばどうしてあなたに求めることがあろう。裁判所はあなたに何も求めはしないのだ。あなたが来れば迎え、行くならば去らせるだけだ」(p.329)
少なくとも二一世紀の今日において読んでみても、何かしらの文学的感銘とでもいうべきものを、どこかに感じることができる作品でもある。この作品、光文社古典新訳文庫で『訴訟』のタイトルでも別の訳が出ている。こちらも、読んでおきたいと思う。
追記 2018-10-27
『訴訟』(光文社古典新訳文庫)については、
やまもも書斎記 2018年10月27日
『訴訟』カフカ
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/10/27/8984271
『訴訟』(光文社古典新訳文庫)については、
やまもも書斎記 2018年10月27日
『訴訟』カフカ
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/10/27/8984271
『西郷どん』あれこれ「傷だらけの維新」 ― 2018-10-16
2018-10-16 當山日出夫(とうやまひでお)
『西郷どん』2018年10月14日、第38回「傷だらけの維新」
https://www.nhk.or.jp/segodon/story/38/
前回は、
やまもも書斎記 2018年10月9日
『西郷どん』あれこれ「江戸無血開城」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/10/09/8970383
まあ、これはこれで明治維新というものの描き方の一つなんだろうなあ、と思うのだが、ドラマとして面白いかどうかとなると、どうだろうか。あるいは、このようなことを感じることの背景としては、私なりの西郷隆盛のイメージがあってのことなのかもしれない。
歴史としては、官軍をひきいて戊辰戦争を戦ったのは、西郷吉之助ということになる。それを、このドラマは、軍の司令官とその私情……弟の吉二郎とのこと……において描いていた。
しかし、私などが期待するのは、来たるべき国家の経綸をめぐって、その主軸となった西郷のイメージなのである。あるいは、敵であった旧幕府軍の方にどのような正義があったのか、このあたりのことも気になる。
新しい国家……明治の国家……を建設するためには、旧幕府軍は徹底的にうちのめさなければならない。そして、それは、徳川幕府に代わる、新しい明治国家の建設の展望があってのことでなければならない。ここのところが、まったく描かれていなかった。
むしろ、この回の最後では、西郷は、一連の倒幕運動、新国家建設の動きから、身をひくことを決意したかのごとくである。自分の役目はもう終わった……と。それならば、それはそれとして、なぜ、旧幕府をこわさねばならないのか、その歴史観のようなものが描かれていてもよかったのではないだろうか。
このドラマには、江戸時代から、明治政府になるにあたって、その当事者たちをどう描くかということについての歴史観が見られないのである。
西郷が、自分の役目はもう終わったと思うならば、それはそれでよい。だが、それは、明治維新という大きな歴史の変革の当事者としての意識でなければならない。ただ、身内の吉二郎を死なせてしまったということではないはずである。そのような私情を越えたところにある、西郷という人物の位置づけがあるのではないか……まあ、いってみれば、これは、私なりの西郷のイメージの投影にすぎないかもしれないのだが。
ところで、次回以降、菊次郎が登場するらしい。明治なってから、西南戦争がおわってから……回顧してみて、西郷は何をなした人物なのか、そこを問いかけることになるのだろうか。これはこれとして、一つのドラマをつくる視点ではあると思う。
『西郷どん』2018年10月14日、第38回「傷だらけの維新」
https://www.nhk.or.jp/segodon/story/38/
前回は、
やまもも書斎記 2018年10月9日
『西郷どん』あれこれ「江戸無血開城」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/10/09/8970383
まあ、これはこれで明治維新というものの描き方の一つなんだろうなあ、と思うのだが、ドラマとして面白いかどうかとなると、どうだろうか。あるいは、このようなことを感じることの背景としては、私なりの西郷隆盛のイメージがあってのことなのかもしれない。
歴史としては、官軍をひきいて戊辰戦争を戦ったのは、西郷吉之助ということになる。それを、このドラマは、軍の司令官とその私情……弟の吉二郎とのこと……において描いていた。
しかし、私などが期待するのは、来たるべき国家の経綸をめぐって、その主軸となった西郷のイメージなのである。あるいは、敵であった旧幕府軍の方にどのような正義があったのか、このあたりのことも気になる。
新しい国家……明治の国家……を建設するためには、旧幕府軍は徹底的にうちのめさなければならない。そして、それは、徳川幕府に代わる、新しい明治国家の建設の展望があってのことでなければならない。ここのところが、まったく描かれていなかった。
むしろ、この回の最後では、西郷は、一連の倒幕運動、新国家建設の動きから、身をひくことを決意したかのごとくである。自分の役目はもう終わった……と。それならば、それはそれとして、なぜ、旧幕府をこわさねばならないのか、その歴史観のようなものが描かれていてもよかったのではないだろうか。
このドラマには、江戸時代から、明治政府になるにあたって、その当事者たちをどう描くかということについての歴史観が見られないのである。
西郷が、自分の役目はもう終わったと思うならば、それはそれでよい。だが、それは、明治維新という大きな歴史の変革の当事者としての意識でなければならない。ただ、身内の吉二郎を死なせてしまったということではないはずである。そのような私情を越えたところにある、西郷という人物の位置づけがあるのではないか……まあ、いってみれば、これは、私なりの西郷のイメージの投影にすぎないかもしれないのだが。
ところで、次回以降、菊次郎が登場するらしい。明治なってから、西南戦争がおわってから……回顧してみて、西郷は何をなした人物なのか、そこを問いかけることになるのだろうか。これはこれとして、一つのドラマをつくる視点ではあると思う。
追記 2018-10-24
この続きは、
やまもも書斎記 2018年10月24日
『西郷どん』あれこれ「父、西郷隆盛」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/10/24/8980911
この続きは、
やまもも書斎記 2018年10月24日
『西郷どん』あれこれ「父、西郷隆盛」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/10/24/8980911
ハナミズキの実 ― 2018-10-17
2018-10-17 當山日出夫(とうやまひでお)
水曜日なので、花の写真。今日は、ハナミズキの実である。
前回は、
やまもも書斎記 2018年10月10日
マルバルコウ
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/10/10/8970775
日本国語大辞典(ジャパンナレッジ)を見てみる。
ミズキ科の落葉高木。北アメリカ原産で庭木や公園木として広く栽植される。
とあり、さらに説明があるのだが、ことばとしての用例が載っていない。ここは、国語辞典としては、用例を示しておいてもらいたいところである。
この木、我が家の駐車場のすみに植えてある。初夏に花をつける。観察して見ていると、実をつけているようなので、写真に撮ってみたものである。確認してみると、ハナミズキであっているらしい。
去年はどうだったろうか、実の実っているところを写真にはとらなかったと憶えている。それよりも、葉の紅葉した姿がきれいだったので写した記憶がある。ハナミズキの木は、街路樹などで、街を歩いていて目にすることに多い木である。その季節の移り変わりを見ていくのも、また楽しみでもある。
この木の名前「はなみずき」は、『言海』には載っていない。
水曜日なので、花の写真。今日は、ハナミズキの実である。
前回は、
やまもも書斎記 2018年10月10日
マルバルコウ
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/10/10/8970775
日本国語大辞典(ジャパンナレッジ)を見てみる。
ミズキ科の落葉高木。北アメリカ原産で庭木や公園木として広く栽植される。
とあり、さらに説明があるのだが、ことばとしての用例が載っていない。ここは、国語辞典としては、用例を示しておいてもらいたいところである。
この木、我が家の駐車場のすみに植えてある。初夏に花をつける。観察して見ていると、実をつけているようなので、写真に撮ってみたものである。確認してみると、ハナミズキであっているらしい。
去年はどうだったろうか、実の実っているところを写真にはとらなかったと憶えている。それよりも、葉の紅葉した姿がきれいだったので写した記憶がある。ハナミズキの木は、街路樹などで、街を歩いていて目にすることに多い木である。その季節の移り変わりを見ていくのも、また楽しみでもある。
この木の名前「はなみずき」は、『言海』には載っていない。
Nikon D7500
AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR
AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR
『古典を読む 江戸漢詩』中村真一郎 ― 2018-10-18
2018-10-18 當山日出夫(とうやまひでお)

中村真一郎.『古典を読む 江戸漢詩』(同時代ライブラリー).岩波書店.1998 (岩波書店.1985)
https://www.iwanami.co.jp/book/b270253.html
岩波の同時代ライブラリー版で読んだ。今では、もう売っていない。古本で買った。(さがせば、もとの本を買って持っているかもしれないのだが、その元気もないので、古書で買うことにした。)
中村真一郎の本で、江戸の漢詩を意識するようになった。きっかけは、去年、ちくま学芸文庫で刊行になった『頼山陽とその時代』(上・下)を読んだことによる。これも再読である。最初、出た時に買ってざっと読んだままになっていたのだが、文庫版で新しく出たので、読んでみた。
こんどはじっくりと、引用してある漢詩にまで目をとおした。『頼山陽とその時代』には、あまり引用の漢詩に語釈をほどこすということをしていない。やや難渋するところもあったのだが、読み終えた。
この時に感じたのは、江戸時代の漢詩人に共感するところのある、現代に生きている自分……このおどろきである。いや、そのようなものとして、江戸時代の漢詩人を描き出したのが、中村真一郎の功績といえるのかもしれない。一八~一九世紀にかけての江戸後期の漢詩人の作品に、近代文学の萌芽とでもいうべき、自由で個人的で都市的な、さらにはデカダンスのイメージを読みとっている。
去年、『頼山陽とその時代』を読んだので、今年は、『蠣崎波響の生涯』を読もうと思った。ただ、これは、途中で中断してしまった。改めて、最初からじっくりと読んでおきたい。
ともあれ、明治になってから文明開化とともに起こった「近代文学」ではないところにある、一つの文学の流れとして、江戸時代からの漢詩文の世界があることは確かである。そして、それは、ある面では、明治の「近代文学」を越えた達成をしめしてもいる。
菅茶山(新日本古典文学大系)など、これから読みたい本の一つである。
https://www.iwanami.co.jp/book/b270253.html
岩波の同時代ライブラリー版で読んだ。今では、もう売っていない。古本で買った。(さがせば、もとの本を買って持っているかもしれないのだが、その元気もないので、古書で買うことにした。)
中村真一郎の本で、江戸の漢詩を意識するようになった。きっかけは、去年、ちくま学芸文庫で刊行になった『頼山陽とその時代』(上・下)を読んだことによる。これも再読である。最初、出た時に買ってざっと読んだままになっていたのだが、文庫版で新しく出たので、読んでみた。
こんどはじっくりと、引用してある漢詩にまで目をとおした。『頼山陽とその時代』には、あまり引用の漢詩に語釈をほどこすということをしていない。やや難渋するところもあったのだが、読み終えた。
この時に感じたのは、江戸時代の漢詩人に共感するところのある、現代に生きている自分……このおどろきである。いや、そのようなものとして、江戸時代の漢詩人を描き出したのが、中村真一郎の功績といえるのかもしれない。一八~一九世紀にかけての江戸後期の漢詩人の作品に、近代文学の萌芽とでもいうべき、自由で個人的で都市的な、さらにはデカダンスのイメージを読みとっている。
去年、『頼山陽とその時代』を読んだので、今年は、『蠣崎波響の生涯』を読もうと思った。ただ、これは、途中で中断してしまった。改めて、最初からじっくりと読んでおきたい。
ともあれ、明治になってから文明開化とともに起こった「近代文学」ではないところにある、一つの文学の流れとして、江戸時代からの漢詩文の世界があることは確かである。そして、それは、ある面では、明治の「近代文学」を越えた達成をしめしてもいる。
菅茶山(新日本古典文学大系)など、これから読みたい本の一つである。
『幻影の明治』渡辺京二 ― 2018-10-19
2018-10-19 當山日出夫(とうやまひでお)

渡辺京二.『幻影の明治-名もなき人びとの肖像-』(平凡社ライブラリー).平凡社.2018 (平凡社.2014)
http://www.heibonsha.co.jp/book/b372202.html
渡辺京二の明治時代についてのいくつかの文章を編集したものである。もとの本も持っていたかと思うのだが、平凡社ライブラリー版が出たので、これで読んでみることにした。
この本は、まず、山田風太郎の明治小説についての論評からはじまる。著者(渡辺京二)は、よほど山田風太郎が気にいっているらしい。
山田風太郎の明治小説……あるいは、私としては、明治伝奇小説といいたいのだが……これについては、私も高く評価することでは負けていないと思う。『警視庁草紙』を読んだのは、学生のころだったろうか。これは、文庫本で読んだのを憶えている。これをきっかけに、山田風太郎の明治伝奇小説は読んできた。その多くは、単行本で出た時に買って読んできている。
それから、『戦中派不戦日記』も強く印象に残っている。あの硬質な文体でこそ、戦時中を生きのびたと感じさせる。
ともあれ、山田風太郎の明治伝奇小説のファンとして、渡辺京二もいることになる。これは、私としてもうれしく思ったことである。
その他、この本には、明治、近代についての様々な考察が収められている。読みながら付箋をつけた箇所を一つ引用しておく。
「そしてこの近代国民国家なるものは、徳川期日本もそのひとつである近世国家とは重大な一点で決定的に相違してた。すなわち、近世国家においては統治者以外の国民はおのれの生活圏で一生を終えて、国家的大事にかかわる必要がなく、不本意にもかかわらねばならぬときは天災のとごくやりすごすことができたのに対して、近代的国民国家においては国民は国家的大事にすべて有責として自覚的にかかわることが求められた。」(p.98)
近代における国家と国民との関係は、まさにここに指摘してあることになるのだろう。
ところで、著者(渡辺京二)は、司馬遼太郎が嫌いらしい。『坂の上の雲』について、手厳しく批判してある。この批判の箇所は、読んでなるほどと感じるところがある。
渡辺京二の本としては、『逝きし世の面影』を読んだのはかなり以前のことになる。その後、出た本は買って未読のものがある。「歴史家」としての渡辺京二の本を、読んでおきたいと思う。
http://www.heibonsha.co.jp/book/b372202.html
渡辺京二の明治時代についてのいくつかの文章を編集したものである。もとの本も持っていたかと思うのだが、平凡社ライブラリー版が出たので、これで読んでみることにした。
この本は、まず、山田風太郎の明治小説についての論評からはじまる。著者(渡辺京二)は、よほど山田風太郎が気にいっているらしい。
山田風太郎の明治小説……あるいは、私としては、明治伝奇小説といいたいのだが……これについては、私も高く評価することでは負けていないと思う。『警視庁草紙』を読んだのは、学生のころだったろうか。これは、文庫本で読んだのを憶えている。これをきっかけに、山田風太郎の明治伝奇小説は読んできた。その多くは、単行本で出た時に買って読んできている。
それから、『戦中派不戦日記』も強く印象に残っている。あの硬質な文体でこそ、戦時中を生きのびたと感じさせる。
ともあれ、山田風太郎の明治伝奇小説のファンとして、渡辺京二もいることになる。これは、私としてもうれしく思ったことである。
その他、この本には、明治、近代についての様々な考察が収められている。読みながら付箋をつけた箇所を一つ引用しておく。
「そしてこの近代国民国家なるものは、徳川期日本もそのひとつである近世国家とは重大な一点で決定的に相違してた。すなわち、近世国家においては統治者以外の国民はおのれの生活圏で一生を終えて、国家的大事にかかわる必要がなく、不本意にもかかわらねばならぬときは天災のとごくやりすごすことができたのに対して、近代的国民国家においては国民は国家的大事にすべて有責として自覚的にかかわることが求められた。」(p.98)
近代における国家と国民との関係は、まさにここに指摘してあることになるのだろう。
ところで、著者(渡辺京二)は、司馬遼太郎が嫌いらしい。『坂の上の雲』について、手厳しく批判してある。この批判の箇所は、読んでなるほどと感じるところがある。
渡辺京二の本としては、『逝きし世の面影』を読んだのはかなり以前のことになる。その後、出た本は買って未読のものがある。「歴史家」としての渡辺京二の本を、読んでおきたいと思う。
追記 2018-10-20
この続きは、
やまもも書斎記 2018年10月20日
『幻影の明治』渡辺京二(その二)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/10/20/8978564
この続きは、
やまもも書斎記 2018年10月20日
『幻影の明治』渡辺京二(その二)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/10/20/8978564
『幻影の明治』渡辺京二(その二) ― 2018-10-20
2018-10-20 當山日出夫(とうやまひでお)

渡辺京二.『幻影の明治-名もなき人びとの肖像-』(平凡社ライブラリー).平凡社.2018 (平凡社.2014)
http://www.heibonsha.co.jp/book/b372202.html
この本についてさらにつづける。
http://www.heibonsha.co.jp/book/b372202.html
この本についてさらにつづける。
やまもも書斎記 2018年10月19日
『幻影の明治』渡辺京二
明治初期の士族反乱にふれて次のようにある。引用しておきたい。
「だが、この二例で明らかなのは、思想というものの力だと思う。むろん、士族反乱には、彼らの階級的利害が紛れ込んでくる。だが、それがいかなる思想によって導かれたかということをみないでは、後藤順平のような博労、広田尚のような豪農が剣をとった動機は、ついに歴史の中に埋没するだろう。そういう埋没に痛む心こそ、歴史する者の心ではないだろうか。」(pp.126-127)
また、自由民権運動については、
「自由民権というと、いかにも近代的個人の自由の主張のように聞こえますが、その実体はこのような、古き共同性の喪失の危機感であったのです。旧藩時代に存在していたような社会の絆、さらに参政権をわれわれは失ってしまった。それを再建せよというのが「自由民権」であったのです。」(p.144)
さらに、新保裕司との対談で、自らについてつぎのように語る。
「(渡辺)というよりも、それ以前に、僕はある意味で「日本人」じゃないんです。日本人であることは間違いないけれども、昨日も、大連一中の同窓会で、「君が『逝きし世の面影』を書けたのは、大連にいたからだよね。引揚者だから書けたんだ」と言われた。全くその通りなわけです。」(p.203)
どのような姿勢で「歴史」に対するのか……渡辺京二の書いたものを、さらに読んでおきたくなっている。『逝きし世の面影』も再読してみたい。




最近のコメント