『カムカムエヴリバディ』あれこれ「第3週」 ― 2021-11-21
2021-11-21 當山日出夫(とうやまひでお)
『カムカムエヴリバディ』第3週
https://www.nhk.or.jp/comecome/story/details/story_details_03.html
前回は、
やまもも書斎記 2021年11月14日
『カムカムエヴリバディ』あれこれ「第2週」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2021/11/14/9440120
この週は、太平洋戦争がはじまって、戦況が不利になるなか、学徒出陣のころまで。
大阪の大学に進学していた稔も、出征することになる。それまでの間に、安子と結婚することになった。実にあわただしい展開なのであるが、このドラマは、そのあわただしさを感じさせることなく、じっくりと人びとの気持ちを描いていたと思う。
基本は、二つの家族の物語。
橘の家では、祖父が亡くなる。残った家族だけで、戦時下、ほそぼそと店をつづけている。これも、どうにか店を開いているという状況のようだ。戦時下の人びとのつつましい暮らしぶりが、情感をこめて描かれていたと感じる。
一方、雉真の家では、稔の結婚をめぐってどうもしっくりしない。母親は、稔と安子を別れさせようととする。父も銀行の頭取の娘との縁談をすすめている。しかし、稔は安子のことを思っている。あきらめない。
この二つの家がまじわることになるのが、稔の父が橘の店を訪れたシーンであった。小さいながらも堅実な商売をしている和菓子屋。その主人と娘。そこを訪れた、雉真の父。ここでの三人の場面が、実にいい。それぞれに、自分の仕事にかける思い、また、家族への思いがにじみ出ていたと感じる。
最後になって、安子と稔は結婚することになるのだが、それも長くは続かないようである。
印象的だったのは、やはり安子と稔の二人のシーンで流れる、渡辺貞夫の音楽。甘い演奏が、二人の気持ちを表している。これからも、この渡辺貞夫の音楽が使われるシーンがあるのだろうか。
ひなたの道を歩いていきたい……と語っていた。これから、戦争はひどくなり、また、戦後の混乱の時期を迎えることになるはずである。二人が、ひなたの道をあるけるときは、再びやってくるのだろうか。
次週、一九四五年まで時代は進むようである。戦争の時代、岡山の人びとはどのように生きることになるのか。楽しみに見ることにしよう。
2021年11月20日記
『カムカムエヴリバディ』第3週
https://www.nhk.or.jp/comecome/story/details/story_details_03.html
前回は、
やまもも書斎記 2021年11月14日
『カムカムエヴリバディ』あれこれ「第2週」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2021/11/14/9440120
この週は、太平洋戦争がはじまって、戦況が不利になるなか、学徒出陣のころまで。
大阪の大学に進学していた稔も、出征することになる。それまでの間に、安子と結婚することになった。実にあわただしい展開なのであるが、このドラマは、そのあわただしさを感じさせることなく、じっくりと人びとの気持ちを描いていたと思う。
基本は、二つの家族の物語。
橘の家では、祖父が亡くなる。残った家族だけで、戦時下、ほそぼそと店をつづけている。これも、どうにか店を開いているという状況のようだ。戦時下の人びとのつつましい暮らしぶりが、情感をこめて描かれていたと感じる。
一方、雉真の家では、稔の結婚をめぐってどうもしっくりしない。母親は、稔と安子を別れさせようととする。父も銀行の頭取の娘との縁談をすすめている。しかし、稔は安子のことを思っている。あきらめない。
この二つの家がまじわることになるのが、稔の父が橘の店を訪れたシーンであった。小さいながらも堅実な商売をしている和菓子屋。その主人と娘。そこを訪れた、雉真の父。ここでの三人の場面が、実にいい。それぞれに、自分の仕事にかける思い、また、家族への思いがにじみ出ていたと感じる。
最後になって、安子と稔は結婚することになるのだが、それも長くは続かないようである。
印象的だったのは、やはり安子と稔の二人のシーンで流れる、渡辺貞夫の音楽。甘い演奏が、二人の気持ちを表している。これからも、この渡辺貞夫の音楽が使われるシーンがあるのだろうか。
ひなたの道を歩いていきたい……と語っていた。これから、戦争はひどくなり、また、戦後の混乱の時期を迎えることになるはずである。二人が、ひなたの道をあるけるときは、再びやってくるのだろうか。
次週、一九四五年まで時代は進むようである。戦争の時代、岡山の人びとはどのように生きることになるのか。楽しみに見ることにしよう。
2021年11月20日記
追記 2021年11月28日
この続きは、
やまもも書斎記 2021年11月28日
『カムカムエヴリバディ』あれこれ「第4週」
https://yamamomo.asablo.jp/blog/2021/11/28/9443704
この続きは、
やまもも書斎記 2021年11月28日
『カムカムエヴリバディ』あれこれ「第4週」
https://yamamomo.asablo.jp/blog/2021/11/28/9443704
『現代文解釈の基礎 新訂版』遠藤嘉基・渡辺実 ― 2021-11-22
2021-11-22 當山日出夫(とうやまひでお)
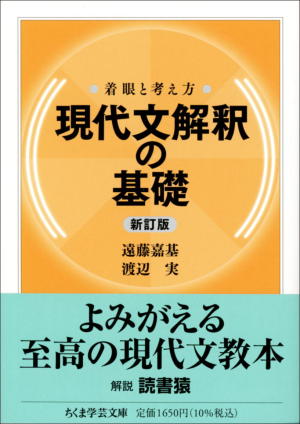
遠藤嘉基・渡辺実.『着眼と考え方 現代文解釈の基礎 新訂版』(ちくま学芸文庫).ちくま書房.2021(1963.1991.中央図書出版)
https://www.chikumashobo.co.jp/special/genbun-basic/
話題の本の一つということで読んでみた。読んで思うこととしては、次の二点ぐらいを書いておく。
第一には、国語学と国語教育。
この本を実質的に書いたのは、渡辺実だろうが、日本を代表する文法学者の一人である。その著書である、『平安朝文章史』『国語構文論』などは、出たときに買って読んだ。その後、『平安朝文章史』は、文庫本にもなったので、それも読んだ。
今、国語学とはいわなくなってしまっている。日本語学という。それで実質的にどう変わったということもないようなものだが、ただいえることとしては、日本語学になってから国語教育とのかかわりが薄くなってしまったことはたしかだろう。そのかわりに関係を深めてきているのが、いわゆる外国人を対象とした日本語教育である。
読んでまず思ったことは、これが、『平安朝文章史』や『国語構文論』などを書いた学者の手になるものか、という率直なおどろきのようなものである。日本語の学問的研究において、今は忘れ去ってしまった、重要な何かをこの本は語りかけてくれる。
第二には、文学教育ということ。
日本の国語教育は大きく変わろうとしている。文学教育の他に、論理国語なるものが設定される。文学作品を読むことと、論理的な論説文や説明文を読むこととは、別のことがらとしてとらえるようになってきている。
だが、この本を読むと、このごろの国語教育改革が、いかに浅薄なものであるかがわかる。文学作品を的確に理解し読解していくことと、評論や論説文を読み解くこととの間に、本質的な違いがあるわけではない。どちらも日本語で書かれた文章なのである。
以上の二点のようなことを思って見る。
さらに書いてみるならば、読んで、『山月記』『俘虜記』などの文学作品、また、『「である」ことと「する」こと」』のような論説文、これらの解釈は実に面白い。なるほど、こういう論理構成で、このようなことを語っている文章だったのか、と思わず再確認して納得するところがある。
強いて難をいえば、なかで例文としてあげられている文章が、今日の観点からはちょっと古いかなという気がしないでもない。もう今では、亀井勝一郎の文章は読まれることはあまりないだろうし、その文学観もいささか古めかしい。
学生にすすめてみようと思って、行っている大学の図書館を検索してみたが、この本は収蔵されていないようである。高校生向けの学習参考書だから、大学図書館ではいれないのも、そうなのかと思う。が、今般、ちくま学芸文庫という形で再刊された本でもあるので、これは大学生にもひろく読まれることを期待したい。
2021年11月21日記
https://www.chikumashobo.co.jp/special/genbun-basic/
話題の本の一つということで読んでみた。読んで思うこととしては、次の二点ぐらいを書いておく。
第一には、国語学と国語教育。
この本を実質的に書いたのは、渡辺実だろうが、日本を代表する文法学者の一人である。その著書である、『平安朝文章史』『国語構文論』などは、出たときに買って読んだ。その後、『平安朝文章史』は、文庫本にもなったので、それも読んだ。
今、国語学とはいわなくなってしまっている。日本語学という。それで実質的にどう変わったということもないようなものだが、ただいえることとしては、日本語学になってから国語教育とのかかわりが薄くなってしまったことはたしかだろう。そのかわりに関係を深めてきているのが、いわゆる外国人を対象とした日本語教育である。
読んでまず思ったことは、これが、『平安朝文章史』や『国語構文論』などを書いた学者の手になるものか、という率直なおどろきのようなものである。日本語の学問的研究において、今は忘れ去ってしまった、重要な何かをこの本は語りかけてくれる。
第二には、文学教育ということ。
日本の国語教育は大きく変わろうとしている。文学教育の他に、論理国語なるものが設定される。文学作品を読むことと、論理的な論説文や説明文を読むこととは、別のことがらとしてとらえるようになってきている。
だが、この本を読むと、このごろの国語教育改革が、いかに浅薄なものであるかがわかる。文学作品を的確に理解し読解していくことと、評論や論説文を読み解くこととの間に、本質的な違いがあるわけではない。どちらも日本語で書かれた文章なのである。
以上の二点のようなことを思って見る。
さらに書いてみるならば、読んで、『山月記』『俘虜記』などの文学作品、また、『「である」ことと「する」こと」』のような論説文、これらの解釈は実に面白い。なるほど、こういう論理構成で、このようなことを語っている文章だったのか、と思わず再確認して納得するところがある。
強いて難をいえば、なかで例文としてあげられている文章が、今日の観点からはちょっと古いかなという気がしないでもない。もう今では、亀井勝一郎の文章は読まれることはあまりないだろうし、その文学観もいささか古めかしい。
学生にすすめてみようと思って、行っている大学の図書館を検索してみたが、この本は収蔵されていないようである。高校生向けの学習参考書だから、大学図書館ではいれないのも、そうなのかと思う。が、今般、ちくま学芸文庫という形で再刊された本でもあるので、これは大学生にもひろく読まれることを期待したい。
2021年11月21日記
『青天を衝け』あれこれ「栄一と千代」 ― 2021-11-23
やまもも書斎記 2021年11月16日
『青天を衝け』あれこれ「栄一、もてなす」
『青天を衝け』あれこれ「栄一、もてなす」
この回で千代が死ぬことになる。ここは史実に忠実につくる以上、しかたのないことかもしれない。
見ていて印象にのこったのは、次の二点ぐらいである。
第一に、新自由主義。
このドラマの作り方としては、三菱は悪役である。そして、その岩崎弥太郎の主張するところは、今日でいう新自由主義である。実力のあるもの、富のあるものが、その才覚をいかして金儲けをするのは当然という立場である。
これに対して、渋沢栄一は、異なる立場にいる。社会の弱者を保護することに、十分な意義があると認識している。
このあたり、今日の社会のあり方をふまえると、ステレオタイプの描き方ではあるが、分かりやすい。そして、渋沢栄一のめざした経済のあり方は、現代の新自由主義とは異なるものであったこともたしかである。
第二に、千代のこと。
思い起こせば、このドラマの子役のときから、千代は登場してきていた。栄一が、尊皇攘夷の運動に奔走し、その後一橋家につかえ、さらには、パリにまで行ってしまう。その留守宅を、千代は守ってきた。いわゆる内助の功の典型といっていいのだろう。
千代のような妻がいたからこそ、渋沢栄一の経済人としての活躍もありえたと感じるところがある。
以上の二点が、印象に残ったところである。
ところで、渋沢家の暮らしは、飛鳥山を拠点に描かれていた。洋風の住まいで、洋食。しかし、その服装は、和風である。和洋折衷の生活様式も、これも明治ならではのものかもしれない。
明治一四年の政変。それから、自由民権運動。学校の教科書に出てきたこととして覚えている。その後、いろいろ本などで読んだりもしている。近代史のエピソードをなぞりながら、これからの渋沢栄一の生涯を描いていくことになるのだろう。
次週、三菱との確執はつづくようだ。千代の亡くなったあと栄一はどうすなるのか。楽しみに見ることにしよう。
2021年11月22日記
見ていて印象にのこったのは、次の二点ぐらいである。
第一に、新自由主義。
このドラマの作り方としては、三菱は悪役である。そして、その岩崎弥太郎の主張するところは、今日でいう新自由主義である。実力のあるもの、富のあるものが、その才覚をいかして金儲けをするのは当然という立場である。
これに対して、渋沢栄一は、異なる立場にいる。社会の弱者を保護することに、十分な意義があると認識している。
このあたり、今日の社会のあり方をふまえると、ステレオタイプの描き方ではあるが、分かりやすい。そして、渋沢栄一のめざした経済のあり方は、現代の新自由主義とは異なるものであったこともたしかである。
第二に、千代のこと。
思い起こせば、このドラマの子役のときから、千代は登場してきていた。栄一が、尊皇攘夷の運動に奔走し、その後一橋家につかえ、さらには、パリにまで行ってしまう。その留守宅を、千代は守ってきた。いわゆる内助の功の典型といっていいのだろう。
千代のような妻がいたからこそ、渋沢栄一の経済人としての活躍もありえたと感じるところがある。
以上の二点が、印象に残ったところである。
ところで、渋沢家の暮らしは、飛鳥山を拠点に描かれていた。洋風の住まいで、洋食。しかし、その服装は、和風である。和洋折衷の生活様式も、これも明治ならではのものかもしれない。
明治一四年の政変。それから、自由民権運動。学校の教科書に出てきたこととして覚えている。その後、いろいろ本などで読んだりもしている。近代史のエピソードをなぞりながら、これからの渋沢栄一の生涯を描いていくことになるのだろう。
次週、三菱との確執はつづくようだ。千代の亡くなったあと栄一はどうすなるのか。楽しみに見ることにしよう。
2021年11月22日記
追記 2021年11月30日
この続きは、
やまもも書斎記 2021年11月30日
『青天を衝け』あれこれ「栄一、あがく」
https://yamamomo.asablo.jp/blog/2021/11/30/9444241
この続きは、
やまもも書斎記 2021年11月30日
『青天を衝け』あれこれ「栄一、あがく」
https://yamamomo.asablo.jp/blog/2021/11/30/9444241
綿毛 ― 2021-11-24
2021-11-24 當山日出夫(とうやまひでお)
水曜日なので写真の日。今日は綿毛である。
前回は、
やまもも書斎記 2021年11月17日
山茱萸
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2021/11/17/9440865
新しいレンズを買ってみた。シグマの150ミリのマクロである。これは、今ではもう作っていない。中古で買った。
望遠のマクロは、タムロンの180ミリを使ってきた。特に不満ということもないのだが、強いていえば、AFが遅い。一度ピントを外すと、再度ピントが合うまでに、いったりきたりする。困るということはないのではあるが、なかなかピントが合わなくて困惑することもある。
ニコンのZマウントのミラーレス機のことも考えてはいる。しかし、花を撮る、小さいものを撮るということでは、むしろ、センサーサイズの小さい(DX)のカメラの方が便利ということもある。これからも、FマウントのDX機は使いつづけるだろうと思う。
そう思って、Fマウントのレンズを買ってみることにした。シグマの150ミリは、以前に、タムロンの180ミリを買ったときにも、どちらにしようかと迷ったレンズである。
買って使ってみるとなかなかいい。描写がシャープなのはいうまでもないが、ボケもきれいである。150ミリ、F/2.8というのも、使いやすい。無論、AFは早い。これは、まったく不満に思うところがない。
家の周りを見ていると、綿毛が目についたので写してみることにした。家の周囲のところどころに見ることができる。写真としては定番の被写体であるが、実際に写してみるといいレンズだということがわかる。
水曜日なので写真の日。今日は綿毛である。
前回は、
やまもも書斎記 2021年11月17日
山茱萸
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2021/11/17/9440865
新しいレンズを買ってみた。シグマの150ミリのマクロである。これは、今ではもう作っていない。中古で買った。
望遠のマクロは、タムロンの180ミリを使ってきた。特に不満ということもないのだが、強いていえば、AFが遅い。一度ピントを外すと、再度ピントが合うまでに、いったりきたりする。困るということはないのではあるが、なかなかピントが合わなくて困惑することもある。
ニコンのZマウントのミラーレス機のことも考えてはいる。しかし、花を撮る、小さいものを撮るということでは、むしろ、センサーサイズの小さい(DX)のカメラの方が便利ということもある。これからも、FマウントのDX機は使いつづけるだろうと思う。
そう思って、Fマウントのレンズを買ってみることにした。シグマの150ミリは、以前に、タムロンの180ミリを買ったときにも、どちらにしようかと迷ったレンズである。
買って使ってみるとなかなかいい。描写がシャープなのはいうまでもないが、ボケもきれいである。150ミリ、F/2.8というのも、使いやすい。無論、AFは早い。これは、まったく不満に思うところがない。
家の周りを見ていると、綿毛が目についたので写してみることにした。家の周囲のところどころに見ることができる。写真としては定番の被写体であるが、実際に写してみるといいレンズだということがわかる。
Nikon D500
SIGMA APO MACRO 150mm F2.8 EX DG OS HSM
2021年11月23日記
『斎藤茂吉随筆集』岩波文庫 ― 2021-11-25
2021-11-25 當山日出夫(とうやまひでお)
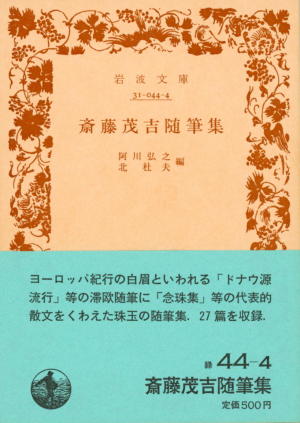
阿川弘之・北杜夫(編).『斎藤茂吉随筆集』(岩波文庫).岩波書店.1986
https://www.iwanami.co.jp/book/b249168.html
北杜夫を読んで、その後、斎藤茂吉の歌を読んだりした。これも読んでおきたくなって、古本で買った。
読んで思うことは、まさに、この斎藤茂吉あって、北杜夫があるという印象である。
第一に、品の良さ。
どの文章も端正で、品がある。書いてある内容は、かなりきわどいことにもふれてあるのだが、読んでいていやな気にはならない。素直に、その文章の世界にはいっていける。
第二、ユーモア。
斎藤茂吉は、ユーモアの人であることがよく理解できる。これは、その人格から自ずからにじみでるものである。大真面目に書いているのが、堅苦しくない。ちょっと距離をおいて眺めてみると、どことなくユーモアを感じる文章が多い。
この、文章の品の良さとユーモアは、北杜夫に受け継がれているものにほかならない。
斎藤茂吉というとどうしても歌人という印象が強い。アララギ派の重鎮ということで、万葉風の歌であり、そして、非常に繊細な感覚を詠んだ歌人というイメージである。だが、散文において、歌人とはまたちがった才能を発揮している。この随筆集など、もっと読まれていい作品だとつよく思う。
なお、餅のことを「おかちん」ということは、『楡家の人びと』に出てくるエピソードの一つであるが、それをこの本のなかでも確認できる。『楡家の人びと』を読んでいると、より面白く読める本でもある。
2021年11月22日記
https://www.iwanami.co.jp/book/b249168.html
北杜夫を読んで、その後、斎藤茂吉の歌を読んだりした。これも読んでおきたくなって、古本で買った。
読んで思うことは、まさに、この斎藤茂吉あって、北杜夫があるという印象である。
第一に、品の良さ。
どの文章も端正で、品がある。書いてある内容は、かなりきわどいことにもふれてあるのだが、読んでいていやな気にはならない。素直に、その文章の世界にはいっていける。
第二、ユーモア。
斎藤茂吉は、ユーモアの人であることがよく理解できる。これは、その人格から自ずからにじみでるものである。大真面目に書いているのが、堅苦しくない。ちょっと距離をおいて眺めてみると、どことなくユーモアを感じる文章が多い。
この、文章の品の良さとユーモアは、北杜夫に受け継がれているものにほかならない。
斎藤茂吉というとどうしても歌人という印象が強い。アララギ派の重鎮ということで、万葉風の歌であり、そして、非常に繊細な感覚を詠んだ歌人というイメージである。だが、散文において、歌人とはまたちがった才能を発揮している。この随筆集など、もっと読まれていい作品だとつよく思う。
なお、餅のことを「おかちん」ということは、『楡家の人びと』に出てくるエピソードの一つであるが、それをこの本のなかでも確認できる。『楡家の人びと』を読んでいると、より面白く読める本でもある。
2021年11月22日記
映像の世紀プレミアム(16)「オリンピック 激動の祭典」 ― 2021-11-26
2021-11-26 當山日出夫(とうやまひでお)
映像の世紀プレミアム(16) オリンピック 激動の祭典
順次、再放送を見ていっている。録画しておいて、後日ゆっくりと見ることにしている。これは、以前の放送のときに見た記憶がある。二〇二〇年の放送。まさに、二度目の東京オリンピック(これは、延期ということになったのだが)に合わせた企画であった。
見て思うことはいろいろある。思いつくままに書いてみる。
レニ・リーフェンシュタールの映像の美しさが光っている。今、映画史のなかで、どのように評価されているのかは知らないのだが、しかし、この放送で使用された場面だけを見る限りでも、その映像美というものを感じ取ることができる。
大きくとりあげられていたのが、マラソン。日本の最初のマラソン選手であった金栗四三。それから、日本統治下の朝鮮から出場した、孫基禎。二〇一九年のNHKの大河ドラマ『いだてん』では、金栗四三は主人公として大きく取り上げられていたが、孫基禎はほとんど触れられることがなかった。これは、ドラマの題材としてあつかうには、デリケートな問題であるということなのだろうか。
以前の放送のときにも思ったことなのだが、オリンピックの歴史ということで作った番組であるにもかかわらず、出てこなかったのが、ミュンヘン・オリンピックのテロ事件。が、これも、映像の世紀プレミアムで、以前に取り扱っているので、ここはあえて触れなかったということかもしれない。
メキシコ・オリンピックのことは、なんとなく覚えているのだが、陸上競技での人種差別抗議の事件のことは記憶にない。(今年、行われた、二〇二一の東京オリンピックでは、政治的行動もある程度は許容されるということのようだったが、しかし、オリンピックについては、ほとんどテレビなど見ていないので、実際どうだったのか分からない。)
番組であつかっていたのは、一九八八年のソウル・オリンピックまでであった。ここで、孫基禎が登場していた。
モスクワ・オリンピックとロサンゼルス・オリンピックの、東西両陣営のボイコットのことは、ニュースでは知っていた。しかし、このオリンピックのころは、テレビの無い生活をしていたころなので、その競技の実際については、ほとんど記憶がない。
一九六四年の東京オリンピックについては、ほとんど触れることがなかった。これは、この映像の世紀プレミアムの前の回が、一九六四の東京をテーマとしたものであったから、あえて省いたということでいいのだろう。
それにしても、改めてオリンピックの歴史を振り返ってみて、今年(二〇二一)の東京オリンピックの、なんと空疎なことかと感じるところがある。その商業主義だけは巨大化しているものの、スポーツの祭典という意義は、いったいどこにいってしまったのだろうか。まったく印象に残らない大会であった。あるいは、逆説的には、VOVID-19パンデミックのなかで、あえて開催したオリンピックということでは、歴史に残る大会になったのであろうが。
2021年11月25日記
映像の世紀プレミアム(16) オリンピック 激動の祭典
順次、再放送を見ていっている。録画しておいて、後日ゆっくりと見ることにしている。これは、以前の放送のときに見た記憶がある。二〇二〇年の放送。まさに、二度目の東京オリンピック(これは、延期ということになったのだが)に合わせた企画であった。
見て思うことはいろいろある。思いつくままに書いてみる。
レニ・リーフェンシュタールの映像の美しさが光っている。今、映画史のなかで、どのように評価されているのかは知らないのだが、しかし、この放送で使用された場面だけを見る限りでも、その映像美というものを感じ取ることができる。
大きくとりあげられていたのが、マラソン。日本の最初のマラソン選手であった金栗四三。それから、日本統治下の朝鮮から出場した、孫基禎。二〇一九年のNHKの大河ドラマ『いだてん』では、金栗四三は主人公として大きく取り上げられていたが、孫基禎はほとんど触れられることがなかった。これは、ドラマの題材としてあつかうには、デリケートな問題であるということなのだろうか。
以前の放送のときにも思ったことなのだが、オリンピックの歴史ということで作った番組であるにもかかわらず、出てこなかったのが、ミュンヘン・オリンピックのテロ事件。が、これも、映像の世紀プレミアムで、以前に取り扱っているので、ここはあえて触れなかったということかもしれない。
メキシコ・オリンピックのことは、なんとなく覚えているのだが、陸上競技での人種差別抗議の事件のことは記憶にない。(今年、行われた、二〇二一の東京オリンピックでは、政治的行動もある程度は許容されるということのようだったが、しかし、オリンピックについては、ほとんどテレビなど見ていないので、実際どうだったのか分からない。)
番組であつかっていたのは、一九八八年のソウル・オリンピックまでであった。ここで、孫基禎が登場していた。
モスクワ・オリンピックとロサンゼルス・オリンピックの、東西両陣営のボイコットのことは、ニュースでは知っていた。しかし、このオリンピックのころは、テレビの無い生活をしていたころなので、その競技の実際については、ほとんど記憶がない。
一九六四年の東京オリンピックについては、ほとんど触れることがなかった。これは、この映像の世紀プレミアムの前の回が、一九六四の東京をテーマとしたものであったから、あえて省いたということでいいのだろう。
それにしても、改めてオリンピックの歴史を振り返ってみて、今年(二〇二一)の東京オリンピックの、なんと空疎なことかと感じるところがある。その商業主義だけは巨大化しているものの、スポーツの祭典という意義は、いったいどこにいってしまったのだろうか。まったく印象に残らない大会であった。あるいは、逆説的には、VOVID-19パンデミックのなかで、あえて開催したオリンピックということでは、歴史に残る大会になったのであろうが。
2021年11月25日記
『戦争と平和』(二)トルストイ/望月哲男(訳)光文社古典新訳文庫 ― 2021-11-27
2021-11-27 當山日出夫(とうやまひでお)
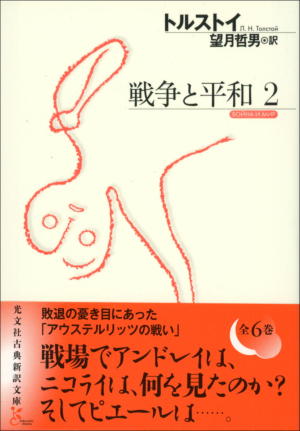
トルストイ.望月哲男(訳).『戦争と平和』(二)(光文社古典新訳文庫).光文社.2020
https://www.kotensinyaku.jp/books/book324/
続きである。
やまもも書斎記 2021年11月20日
『戦争と平和』(一)トルストイ/望月哲男(訳)光文社古典新訳文庫
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2021/11/20/9441633
『戦争と平和』の光文社古典新訳文庫の二冊目である。
『戦争と平和』を読むのは、何度目かになる。これまで何回か読んできているのだが、今回ほど、この小説の面白さを実感したことはない。登場人物が、それぞれに生き生きと躍動している感じである。そして、それぞれの登場人物の背景にある、大きな歴史の流れというものがある。なるほど、この作品が、世界文学のなかの名作として、読み継がれてきているのはもっともなことであると、ようやく理解が及んだということになるであろうか。
だが、やはり、一九世紀の初めごろのロシアであり、ヨーロッパである。二一世紀の日本からは、なかなか分かりにくいところがいくつかある。その分かりにくさというものが、ロシアの貴族社会と軍隊ということになるだろうか。
われわれが知っている軍隊というのは、おそらくは二〇世紀になってからの、国民国家とその軍隊になる。第一世界大戦を戦った軍隊である。その軍隊の基本的性質、国民と国家との関係は、基本的に今日にいたるまで受け継がれているといっていいのかもしれない。(ただ、このあたりのイメージは、「映像の世紀」を見ての印象が強いということはあるかもしれないが。)
軍隊の組織とは、別に貴族の人びとのなかでの人脈というものが歴然としてあるようだ。ここのところが分かりにくい。近代的な軍隊は、世俗的な身分秩序の外に確固たるものとして存在する、そのようなイメージをもっていると、この『戦争と平和』における軍隊というのが、どうも奇妙な存在に見える。おそらくは、貴族社会における中世的な軍隊から、近代的な国民国家への軍隊へと変化していく途中の形態といっていいのかもしれない。
それから、名前は知っているがよく分からないのが、フリーメイソン。ピエールは、フリーメイソンのメンバーとなる。このあたりの描写は、『戦争と平和』のなかでも、特に印象的な場面の一つである。
だが、このフリーメイソンというのが、今日のわれわれの普通の感覚からは、今一つよくわからないものでもある。(文庫本の解説には、このあたりのことが書いてあるのだが、読んでもはっきりいって、どうもぴんとこないところがどうしてもある。)
また、この冊のなかで出てくる戦場のシーン。アンドレイが、空を見上げる場面。ここも印象的なところである。日本的な感覚でとらえるならば、一種の無常感とでもいうものを感じてしまうことになる。
2021年10月11日記
https://www.kotensinyaku.jp/books/book324/
続きである。
やまもも書斎記 2021年11月20日
『戦争と平和』(一)トルストイ/望月哲男(訳)光文社古典新訳文庫
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2021/11/20/9441633
『戦争と平和』の光文社古典新訳文庫の二冊目である。
『戦争と平和』を読むのは、何度目かになる。これまで何回か読んできているのだが、今回ほど、この小説の面白さを実感したことはない。登場人物が、それぞれに生き生きと躍動している感じである。そして、それぞれの登場人物の背景にある、大きな歴史の流れというものがある。なるほど、この作品が、世界文学のなかの名作として、読み継がれてきているのはもっともなことであると、ようやく理解が及んだということになるであろうか。
だが、やはり、一九世紀の初めごろのロシアであり、ヨーロッパである。二一世紀の日本からは、なかなか分かりにくいところがいくつかある。その分かりにくさというものが、ロシアの貴族社会と軍隊ということになるだろうか。
われわれが知っている軍隊というのは、おそらくは二〇世紀になってからの、国民国家とその軍隊になる。第一世界大戦を戦った軍隊である。その軍隊の基本的性質、国民と国家との関係は、基本的に今日にいたるまで受け継がれているといっていいのかもしれない。(ただ、このあたりのイメージは、「映像の世紀」を見ての印象が強いということはあるかもしれないが。)
軍隊の組織とは、別に貴族の人びとのなかでの人脈というものが歴然としてあるようだ。ここのところが分かりにくい。近代的な軍隊は、世俗的な身分秩序の外に確固たるものとして存在する、そのようなイメージをもっていると、この『戦争と平和』における軍隊というのが、どうも奇妙な存在に見える。おそらくは、貴族社会における中世的な軍隊から、近代的な国民国家への軍隊へと変化していく途中の形態といっていいのかもしれない。
それから、名前は知っているがよく分からないのが、フリーメイソン。ピエールは、フリーメイソンのメンバーとなる。このあたりの描写は、『戦争と平和』のなかでも、特に印象的な場面の一つである。
だが、このフリーメイソンというのが、今日のわれわれの普通の感覚からは、今一つよくわからないものでもある。(文庫本の解説には、このあたりのことが書いてあるのだが、読んでもはっきりいって、どうもぴんとこないところがどうしてもある。)
また、この冊のなかで出てくる戦場のシーン。アンドレイが、空を見上げる場面。ここも印象的なところである。日本的な感覚でとらえるならば、一種の無常感とでもいうものを感じてしまうことになる。
2021年10月11日記
追記 2021年12月4日
この続きは、
やまもも書斎記 2021年12月4日
『戦争と平和』(三)トルストイ/望月哲男(訳)光文社古典新訳文庫
https://yamamomo.asablo.jp/blog/2021/12/04/9445298
この続きは、
やまもも書斎記 2021年12月4日
『戦争と平和』(三)トルストイ/望月哲男(訳)光文社古典新訳文庫
https://yamamomo.asablo.jp/blog/2021/12/04/9445298
『カムカムエヴリバディ』あれこれ「第4週」 ― 2021-11-28
2021-11-28 當山日出夫(とうやまひでお)
『カムカムエヴリバディ』第4週
https://www.nhk.or.jp/comecome/story/details/story_details_04.html
前回は、
やまもも書斎記 2021年11月21日
『カムカムエヴリバディ』あれこれ「第3週」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2021/11/21/9441891
このドラマは、一〇〇年の物語ということなのだが、時間の進行が早い。しかし、その早さをあまり感じさせない。じっくりと物語を描いているように感じる。今まで見たところとしては、おそらくこれまでの朝ドラ史上に残る名作といってよいだろう。
この週もいろいろとあった。稔の出征。子どもの誕生。さらには、勇も出征することになった。岡山は空襲にあう。安子の母と祖母が亡くなることになる。たちばなの店もなくなる。しかし、そこから父親は店を再開することになる。終戦。やっと戦争が終わって、たちばなの店もなんとかスタートするのだが、その父も亡くなってしまう。勇が帰還した。そして、最後には、稔の戦死の知らせがとどくことになる。
実にいろいろなことのあった週である。だが、その慌ただしい時間の流れのなかで、戦時下の岡山の人びと、玉音放送、そして戦後の暮らし、といったものが、情感をこめて描かれていたと思う。
生まれた女の子は、るいという名前になった。このドラマにおいては、安子のつぎのヒロインということになる。安子とるいは、ひなたの道を歩くことができるだろうか。
印象に残っているのは、父親の金太の亡くなるときのシーン。おはぎを売りに行った少年が帰ってくるところから、現実と幻想がいりまじって、最後はナレーションで締めくくっていた。これは、こころに残る。
ここまでは、安子の岡山での生活を描いてきたが、これからどうなるのだろうか。戦後の人びとの暮らしのなかで、安子とるいのことが気になる。
それから、気になっているのが、おはぎを売りに行った少年のこと。この少年は、再びドラマに登場することがあるのだろうか。今後の展開の伏線としてなのか、このあたりが気になるところでもある。
次週、戦後になって、いよいよラジオで「カムカムエヴリバディ」が始まるようだ。楽しみに見ることにしよう。
2021年11月27日記
『カムカムエヴリバディ』第4週
https://www.nhk.or.jp/comecome/story/details/story_details_04.html
前回は、
やまもも書斎記 2021年11月21日
『カムカムエヴリバディ』あれこれ「第3週」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2021/11/21/9441891
このドラマは、一〇〇年の物語ということなのだが、時間の進行が早い。しかし、その早さをあまり感じさせない。じっくりと物語を描いているように感じる。今まで見たところとしては、おそらくこれまでの朝ドラ史上に残る名作といってよいだろう。
この週もいろいろとあった。稔の出征。子どもの誕生。さらには、勇も出征することになった。岡山は空襲にあう。安子の母と祖母が亡くなることになる。たちばなの店もなくなる。しかし、そこから父親は店を再開することになる。終戦。やっと戦争が終わって、たちばなの店もなんとかスタートするのだが、その父も亡くなってしまう。勇が帰還した。そして、最後には、稔の戦死の知らせがとどくことになる。
実にいろいろなことのあった週である。だが、その慌ただしい時間の流れのなかで、戦時下の岡山の人びと、玉音放送、そして戦後の暮らし、といったものが、情感をこめて描かれていたと思う。
生まれた女の子は、るいという名前になった。このドラマにおいては、安子のつぎのヒロインということになる。安子とるいは、ひなたの道を歩くことができるだろうか。
印象に残っているのは、父親の金太の亡くなるときのシーン。おはぎを売りに行った少年が帰ってくるところから、現実と幻想がいりまじって、最後はナレーションで締めくくっていた。これは、こころに残る。
ここまでは、安子の岡山での生活を描いてきたが、これからどうなるのだろうか。戦後の人びとの暮らしのなかで、安子とるいのことが気になる。
それから、気になっているのが、おはぎを売りに行った少年のこと。この少年は、再びドラマに登場することがあるのだろうか。今後の展開の伏線としてなのか、このあたりが気になるところでもある。
次週、戦後になって、いよいよラジオで「カムカムエヴリバディ」が始まるようだ。楽しみに見ることにしよう。
2021年11月27日記
追記 2021年12月5日
この続きは、
やまもも書斎記 2021年12月5日
『カムカムエヴリバディ』あれこれ「第5週」
https://yamamomo.asablo.jp/blog/2021/12/05/9445550
この続きは、
やまもも書斎記 2021年12月5日
『カムカムエヴリバディ』あれこれ「第5週」
https://yamamomo.asablo.jp/blog/2021/12/05/9445550
『「太平洋の巨鷲」山本五十六』大木毅 ― 2021-11-29
2021-11-29 當山日出夫(とうやまひでお)

大木毅.『「太平洋の巨鷲」山本五十六-用兵思想からみた真価-』(角川新書).角川書店.2021
https://www.kadokawa.co.jp/product/322005000654/
子どものころのことになるが、山本五十六の映画を見に行ったのを憶えている。私の場合、山本五十六については、軍神というイメージはないものの、真珠湾攻撃を成功させた名将ということで記憶していることになる。
大木毅の本では、これまでに、『独ソ戦』(岩波新書)を読んでいる。軍事史の専門家という認識でいる。その著者の書いた、「山本五十六」ということで、読んでみることにした。(買ったのは本が出てすぐであったが、なんとなく読みそびれてしまっていて、読み終わるのが今になった。)
山本五十六については、これまでに多くの研究や評伝がある。映画などでもあつかわれている。その功績について、非常に限定的に、軍事的な意味合いからのみ評価するとどうであるのか、これはこれとしてとても興味深いテーマである。
ただ、この本は、山本五十六の生いたちからはじまって、やや評伝風の記述がつづく。軍人として力量を発揮した、太平洋戦争開戦当時のことが出てくるのは、かなり読んでからのことになる。
読んだ印象としては、軍事的には……この本の趣旨にしたがうならば、戦略的にはというべきだろうが……なるほど、そうかなという気がする。そして、戦術において、また、作戦において、どう評価することになるのか、このあたりも興味深い指摘である。
山本五十六という、あまりにも神格化されている面があると、私は感じるところがある。純然と軍事的に論じるというアプローチがあってしかるべきであろう。その意味では、この本は面白い。
また、山本五十六の事跡を追うということで、昭和戦前の日本の政治史、外交史についても、いろいろと、教えられるところの多い本である。
2021年11月28日記
https://www.kadokawa.co.jp/product/322005000654/
子どものころのことになるが、山本五十六の映画を見に行ったのを憶えている。私の場合、山本五十六については、軍神というイメージはないものの、真珠湾攻撃を成功させた名将ということで記憶していることになる。
大木毅の本では、これまでに、『独ソ戦』(岩波新書)を読んでいる。軍事史の専門家という認識でいる。その著者の書いた、「山本五十六」ということで、読んでみることにした。(買ったのは本が出てすぐであったが、なんとなく読みそびれてしまっていて、読み終わるのが今になった。)
山本五十六については、これまでに多くの研究や評伝がある。映画などでもあつかわれている。その功績について、非常に限定的に、軍事的な意味合いからのみ評価するとどうであるのか、これはこれとしてとても興味深いテーマである。
ただ、この本は、山本五十六の生いたちからはじまって、やや評伝風の記述がつづく。軍人として力量を発揮した、太平洋戦争開戦当時のことが出てくるのは、かなり読んでからのことになる。
読んだ印象としては、軍事的には……この本の趣旨にしたがうならば、戦略的にはというべきだろうが……なるほど、そうかなという気がする。そして、戦術において、また、作戦において、どう評価することになるのか、このあたりも興味深い指摘である。
山本五十六という、あまりにも神格化されている面があると、私は感じるところがある。純然と軍事的に論じるというアプローチがあってしかるべきであろう。その意味では、この本は面白い。
また、山本五十六の事跡を追うということで、昭和戦前の日本の政治史、外交史についても、いろいろと、教えられるところの多い本である。
2021年11月28日記
『青天を衝け』あれこれ「栄一、あがく」 ― 2021-11-30
2021-11-30 當山日出夫(とうやまひでお)
『青天を衝け』第37回「栄一、あがく」
https://www.nhk.or.jp/seiten/story/37/
前回は、
やまもも書斎記 2021年11月23日
『青天を衝け』あれこれ「栄一と千代」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2021/11/23/9442479
このドラマでは、三菱は悪役である。まあ、これはドラマの作り方としてそうなっているということなのであろうが。
その悪役の三菱と、栄一は運漕会社で競争することになる。端的には、値下げ合戦であり、シェアのうばいあいである。双方疲弊してきたところで、五代友厚が仲裁にはいる。結果的には、もうこれ以上競争をつづけていても、双方のためにならない、また日本のためにはならないということで、三菱と栄一は仲直りということになる。まあ、このあたりは、史実に基づいて描いて、それを渋沢栄一の側から見ればどうなのか、ということになるのかと思う。
しかし、結果的には新しくできた会社が、海運業を独占することになると思うのだが、このあたり問題はなかったのだろうか。(これも、明治という時代、成長途上にある日本の国、資本主義ということでは、許容されることなのかもしれない。)
また、この回で栄一は再婚する。これも史実のとおりに作ってある。栄一は、渋沢の「家」というものをかなり意識した人物だと思うのだが、その一族の一員として、新しい妻の兼子は、しっかりと役割を果たしている。
養育院も栄一の努力でつづけることになった。これは、渋沢栄一の社会福祉事業へのかかわりということで、今後も続くことになる。
このドラマも、次週はもう一二月である。放送はあと何回もない。どこまで描くことになるのだろうか。史実としては、昭和六年に渋沢栄一は亡くなっている。このところまで描くとなると、これからはかなりスピードを上げることになりそうだ。
渋沢栄一が、後年尽力することになる、日米の民間外交というあたりは、どのようになるのか。そして、渋沢の「家」の二代目はどう成長するのか。(これは結果としては、敬三に受け継がれることになるのだが。)
ところで、この回で面白かったのは、神田伯山の登場。明治という時代、講談師という職業がちまたに存在していた時代といっていいのであろう。栄一と三菱との確執を講談師が語るというのも、ドラマの趣向としては非常に面白い。
次回、明治になってからの徳川家を描くことになるようだ。また、篤二のこともでてくる。楽しみに見ることにしよう。
2021年11月29日記
『青天を衝け』第37回「栄一、あがく」
https://www.nhk.or.jp/seiten/story/37/
前回は、
やまもも書斎記 2021年11月23日
『青天を衝け』あれこれ「栄一と千代」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2021/11/23/9442479
このドラマでは、三菱は悪役である。まあ、これはドラマの作り方としてそうなっているということなのであろうが。
その悪役の三菱と、栄一は運漕会社で競争することになる。端的には、値下げ合戦であり、シェアのうばいあいである。双方疲弊してきたところで、五代友厚が仲裁にはいる。結果的には、もうこれ以上競争をつづけていても、双方のためにならない、また日本のためにはならないということで、三菱と栄一は仲直りということになる。まあ、このあたりは、史実に基づいて描いて、それを渋沢栄一の側から見ればどうなのか、ということになるのかと思う。
しかし、結果的には新しくできた会社が、海運業を独占することになると思うのだが、このあたり問題はなかったのだろうか。(これも、明治という時代、成長途上にある日本の国、資本主義ということでは、許容されることなのかもしれない。)
また、この回で栄一は再婚する。これも史実のとおりに作ってある。栄一は、渋沢の「家」というものをかなり意識した人物だと思うのだが、その一族の一員として、新しい妻の兼子は、しっかりと役割を果たしている。
養育院も栄一の努力でつづけることになった。これは、渋沢栄一の社会福祉事業へのかかわりということで、今後も続くことになる。
このドラマも、次週はもう一二月である。放送はあと何回もない。どこまで描くことになるのだろうか。史実としては、昭和六年に渋沢栄一は亡くなっている。このところまで描くとなると、これからはかなりスピードを上げることになりそうだ。
渋沢栄一が、後年尽力することになる、日米の民間外交というあたりは、どのようになるのか。そして、渋沢の「家」の二代目はどう成長するのか。(これは結果としては、敬三に受け継がれることになるのだが。)
ところで、この回で面白かったのは、神田伯山の登場。明治という時代、講談師という職業がちまたに存在していた時代といっていいのであろう。栄一と三菱との確執を講談師が語るというのも、ドラマの趣向としては非常に面白い。
次回、明治になってからの徳川家を描くことになるようだ。また、篤二のこともでてくる。楽しみに見ることにしよう。
2021年11月29日記
追記 2021-12-07
この続きは、
やまもも書斎記 2021年12月7日
『青天を衝け』あれこれ「栄一の嫡男」
https://yamamomo.asablo.jp/blog/2021/12/07/9446073
この続きは、
やまもも書斎記 2021年12月7日
『青天を衝け』あれこれ「栄一の嫡男」
https://yamamomo.asablo.jp/blog/2021/12/07/9446073





最近のコメント