『にんげん蚤の市』高峰秀子/河出文庫 ― 2022-12-01
2022年12月1日 當山日出夫
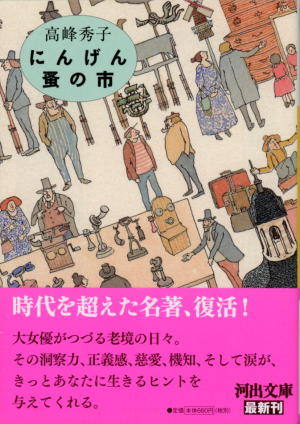
高峰秀子.『にんげん蚤の市』(河出文庫).河出書房新社.2018(1997.文藝春秋)
https://www.kawade.co.jp/sp/isbn/9784309415925/
このところ高峰秀子の本を読んでいる。これも、ちくま文庫版の『高峰秀子ベスト・エッセイ』に収録されたものと、いくぶんの重複がる。しかし、その文章をもとのエッセイの文脈に位置づけて読むという意味では、特に気にならない。というよりも、このような読み方をすると、『高峰秀子ベスト・エッセイ』の編集(斎藤明美)の意図を感じ取ることができる。
文章が巧い、これがまず最初の印象である。『わたしの渡世日記』が一九七五年で、高峰秀子は、二〇一〇年に亡くなっているので、かなり晩年の作品ということになる。文章を書く、エッセイを書くということに、手慣れてきているという印象をもつ。といって、その巧みさがいやになるということはない。うまいエッセイとして、読むのが楽しい。
やはり人間観察の目の確かさということになるのだろうと思う。映画女優として生きてきた高峰秀子であるから、一般の生活とはちょっと違った人生を歩んできたことになる。しかし、映画女優という立場で生きていくためには、映画の観客である一般の人びとの感性に通じていなければならない。高峰秀子のエッセイが魅力的であるのは、この一般の人びとの感性というところだろうと、読んで思う。
読んで共感できることとして、ギリシャでのクルーズ船について、静かなことがいいと言っていることである。雑音の無い静寂というのは、今の時代において、もっとも贅沢なことかもしれない。これは、豪華客船だからという贅沢ではない。一般に言えることである。そして、一般の人びとにも手のとどくところにあるものである。だが、これも考えようだが、静寂こそ今の時代においては最も贅沢なものかもしれない。
この本を読んで、新藤兼人監督の映画を見てみたくなった。
2022年11月16日記
『平家物語』石母田正/岩波文庫 ― 2022-12-02
2022年12月2日 當山日出夫
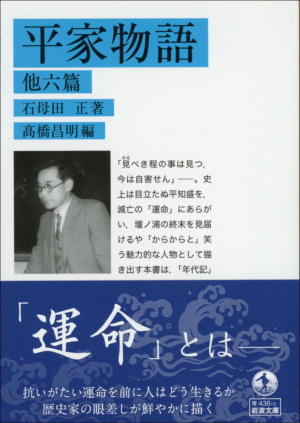
石母田正.高橋昌明(編).『平家物語 他六編』(岩波文庫).岩波書店.2022
https://www.iwanami.co.jp/book/b615161.html
もとの本は、岩波新書の『平家物語』(一九五七)である。これを読むのは、少なくとも三度目になる。
若い時、学生のころ、岩波新書で出ていたのを買って読んだ。そのときに印象にのこったこととしては、やはり、知盛の「見るべき程の事は見つ」ということば、そして「運命」ということであった。
何年前になるだろうか、ふとこの本を読みなおしてみたくなって、古書で買って読んだ。このとき、歴史学者としての石母田正の評価はどうだったろうか。もう、過去の人という雰囲気であったかなと思う。久々に読みなおしてみて、歴史学者の考える「運命」とはどんなものなのだろうかと、いろいろと考えたものである。
それが、岩波文庫版として新しく刊行になったので、買って読んでみた。
読んで思うこととしては、率直に面白い本であるということになる。『平家物語』という作品の魅力を、「運命」「叙事詩」というようなキーワードで読み解いていく。今の時点で読んでみて、その語っていることすべてに賛成できるということはないのであるが、しかし、読んで面白かった。昔読んだ時には、こんなに面白い本だとは思わなかったというのが、正直なところである。
『平家物語』は、これも若い時に目を通した。これで論文を書いたこともある。だが、一つの文学作品として、最初から順番にページを繰っていくということは、近年になってからのことである。その文学史的な位置も一通り知っており、どんな作品かは知っているとしても、一つの文学作品として、ただ読むということは、あまりしてこなかった。が、これも、老後の読書と割り切って、特に論文など書こうと思わないで、ただ楽しみのためにだけ、古典を読んでおきたいと思うようになっている。『平家物語』も、きちんと読みたい作品の一つ。その読書の手助けとして、この石母田正の「平家物語」は非常にいい。
ただ、『平家物語』を、「叙事詩」としてとらえることには、ちょっと疑問がないではない。日本文学の歴史をふりかえって、「叙事詩」というべき作品を探すとなると、確かに『平家物語』がある。だから、『平家物語』が「叙事詩」であるとするのは、やや短絡的である。ここは、石母田正が書いているように、この作品の作者の持っていた「物語精神」を読みとるべきだろう。これは、『源氏物語』とも『今昔物語集』とも違った、鎌倉時代という時代になって生まれた、新しい文学である。
この本を読んで、再度、『平家物語』をじっくりと読みなおしてみたくなった。
2022年11月27日記
https://www.iwanami.co.jp/book/b615161.html
もとの本は、岩波新書の『平家物語』(一九五七)である。これを読むのは、少なくとも三度目になる。
若い時、学生のころ、岩波新書で出ていたのを買って読んだ。そのときに印象にのこったこととしては、やはり、知盛の「見るべき程の事は見つ」ということば、そして「運命」ということであった。
何年前になるだろうか、ふとこの本を読みなおしてみたくなって、古書で買って読んだ。このとき、歴史学者としての石母田正の評価はどうだったろうか。もう、過去の人という雰囲気であったかなと思う。久々に読みなおしてみて、歴史学者の考える「運命」とはどんなものなのだろうかと、いろいろと考えたものである。
それが、岩波文庫版として新しく刊行になったので、買って読んでみた。
読んで思うこととしては、率直に面白い本であるということになる。『平家物語』という作品の魅力を、「運命」「叙事詩」というようなキーワードで読み解いていく。今の時点で読んでみて、その語っていることすべてに賛成できるということはないのであるが、しかし、読んで面白かった。昔読んだ時には、こんなに面白い本だとは思わなかったというのが、正直なところである。
『平家物語』は、これも若い時に目を通した。これで論文を書いたこともある。だが、一つの文学作品として、最初から順番にページを繰っていくということは、近年になってからのことである。その文学史的な位置も一通り知っており、どんな作品かは知っているとしても、一つの文学作品として、ただ読むということは、あまりしてこなかった。が、これも、老後の読書と割り切って、特に論文など書こうと思わないで、ただ楽しみのためにだけ、古典を読んでおきたいと思うようになっている。『平家物語』も、きちんと読みたい作品の一つ。その読書の手助けとして、この石母田正の「平家物語」は非常にいい。
ただ、『平家物語』を、「叙事詩」としてとらえることには、ちょっと疑問がないではない。日本文学の歴史をふりかえって、「叙事詩」というべき作品を探すとなると、確かに『平家物語』がある。だから、『平家物語』が「叙事詩」であるとするのは、やや短絡的である。ここは、石母田正が書いているように、この作品の作者の持っていた「物語精神」を読みとるべきだろう。これは、『源氏物語』とも『今昔物語集』とも違った、鎌倉時代という時代になって生まれた、新しい文学である。
この本を読んで、再度、『平家物語』をじっくりと読みなおしてみたくなった。
2022年11月27日記
『私たちはAIを信頼できるか』大澤真幸・川添愛・三宅陽一郎・山本貴光・吉川浩満 ― 2022-12-03
2022年12月3日 當山日出夫

大澤真幸・川添愛・三宅陽一郎・山本貴光・吉川浩満.『私たちはAIを信頼できるか』.文藝春秋.2022
https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163915944
もとは『文學界』に掲載の文章。それをまとめて一冊にし、追加の文章を加えて編集したもの。
正直なところ、AIというような領域からは距離をおきたいと思っている。最新の知見、といっても普通に手に入る廉価な本というような範囲においてであるが、についていくのが、つらく感じるようになってきた。それよりも、昔読んだ古典というべき文学作品を再読したりして時間をつかいたい。
だが、そうはいっても、今の話題となっていることに興味関心がないわけではない。特にAIについては、言語研究という領域に限らず、そもそも人間が人間たるゆえんは何であるのか、ということを考えるうえで重要な事柄であるという認識は持っている。
この本は、もとが『文學界』に掲載ということもあるし、また、対談を基本とした読みやすい体裁ということもあって、読んでおくことにした。そして、執筆者が既存のアカデミズムの枠から離れたところで活躍していということも、AIについて幅広く考えるうえで、意味のあることかとも思う。
読んで思うことは、なるほどAIとはこのような問題提起をもたらすものなのか、ということの再認識である。人間とは、言語とは、共同体とは……いろいろと考えるところが多い。
この本の特徴としては、AI概論、AI入門ではなく、AIと人間についてのかなり高度で広範囲な考察となっているところであろう。概論、入門書ではなく、AIがこれから我々の社会のなかに存在するようになるとして、それは人間にとって何をもたらすものなのか、重要なポイントが分かりやすく説明されている。なかで重要なのが、「信頼」ということになる。これは、この本のタイトルが採用していることばであり、概念でもある。
「信頼」とは何であるのか、社会学的に重要なテーマである。人間が、「他者」とともにあるものである限り、「信頼」についての考察ははずせない。ここに議論のポイントを持ってきているところが、この本の優れているところと言っていいだろう。
巻末には、山本貴光と吉川浩満によるブックガイドがついている。これを読んで、これから、AIについて考えてみようという気にはならない(もう、私も若くはない)のであるが、気になった本については、手にとってみたい。
2022年11月27日記
https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163915944
もとは『文學界』に掲載の文章。それをまとめて一冊にし、追加の文章を加えて編集したもの。
正直なところ、AIというような領域からは距離をおきたいと思っている。最新の知見、といっても普通に手に入る廉価な本というような範囲においてであるが、についていくのが、つらく感じるようになってきた。それよりも、昔読んだ古典というべき文学作品を再読したりして時間をつかいたい。
だが、そうはいっても、今の話題となっていることに興味関心がないわけではない。特にAIについては、言語研究という領域に限らず、そもそも人間が人間たるゆえんは何であるのか、ということを考えるうえで重要な事柄であるという認識は持っている。
この本は、もとが『文學界』に掲載ということもあるし、また、対談を基本とした読みやすい体裁ということもあって、読んでおくことにした。そして、執筆者が既存のアカデミズムの枠から離れたところで活躍していということも、AIについて幅広く考えるうえで、意味のあることかとも思う。
読んで思うことは、なるほどAIとはこのような問題提起をもたらすものなのか、ということの再認識である。人間とは、言語とは、共同体とは……いろいろと考えるところが多い。
この本の特徴としては、AI概論、AI入門ではなく、AIと人間についてのかなり高度で広範囲な考察となっているところであろう。概論、入門書ではなく、AIがこれから我々の社会のなかに存在するようになるとして、それは人間にとって何をもたらすものなのか、重要なポイントが分かりやすく説明されている。なかで重要なのが、「信頼」ということになる。これは、この本のタイトルが採用していることばであり、概念でもある。
「信頼」とは何であるのか、社会学的に重要なテーマである。人間が、「他者」とともにあるものである限り、「信頼」についての考察ははずせない。ここに議論のポイントを持ってきているところが、この本の優れているところと言っていいだろう。
巻末には、山本貴光と吉川浩満によるブックガイドがついている。これを読んで、これから、AIについて考えてみようという気にはならない(もう、私も若くはない)のであるが、気になった本については、手にとってみたい。
2022年11月27日記
『舞いあがれ!』あれこれ「私らはチームや」 ― 2022-12-04
2022年12月4日 當山日出夫
『舞いあがれ!』第9週「私らはチームや」
https://www.nhk.or.jp/maiagare/movie/week09/
パイロットになるための資質とはどんなものであるべきなのだろうか。
大河内教官は、自分を過信するものはパイロットに向いていないという意味のことを強く言っていた。これは、なるほどと思うところがある。この大河内教官は、あくまでも沈着冷静である。もとは自衛隊の戦闘機のパイロットだったという。
その一方で、柏木の言うことも一理あると感じる。最終的には、パイロットは自分で判断を下さなければならない。その責任がある。
これに対して、舞は、チームの協調性を主張する。機長ひとりだけで飛んでいるのではない。多くの人びとの支えがあって飛んでいるのである。この認識も、また頷けるものである。なによりも、まだ訓練の段階なのである。一人でなにもかも正確な判断ができるわけではないだろう。
ただ、ドラマの展開としては、舞の言う周りの人びととの協調性という方向で動いていく。柏木は、始めかたくなであったが、徐々に同期の仲間に打ち解けていくようでもある。
この週は、帯広に移ってからのことになるのだが、自分で飛行機を操縦して空を飛ぶときの緊張感と、そして、その楽しさが、うまく表現されていたように思う。
ところで、単純に思うことだが、訓練用の飛行機には、GPSはついていないらしい。想像するだけなのだが、今の時代、GPS無しで空を飛ぶということは、現実的ではない。しかし、訓練としては、そのようなものに頼らずに、飛行できないといけないということなのだろう。
さて、次週以降、舞と柏木はどうなるのだろうか。同期の仲間たちは、無事に課程を終えることができるだろうか。続きを楽しみに見ることにしよう。
2022年12月3日記
『舞いあがれ!』第9週「私らはチームや」
https://www.nhk.or.jp/maiagare/movie/week09/
パイロットになるための資質とはどんなものであるべきなのだろうか。
大河内教官は、自分を過信するものはパイロットに向いていないという意味のことを強く言っていた。これは、なるほどと思うところがある。この大河内教官は、あくまでも沈着冷静である。もとは自衛隊の戦闘機のパイロットだったという。
その一方で、柏木の言うことも一理あると感じる。最終的には、パイロットは自分で判断を下さなければならない。その責任がある。
これに対して、舞は、チームの協調性を主張する。機長ひとりだけで飛んでいるのではない。多くの人びとの支えがあって飛んでいるのである。この認識も、また頷けるものである。なによりも、まだ訓練の段階なのである。一人でなにもかも正確な判断ができるわけではないだろう。
ただ、ドラマの展開としては、舞の言う周りの人びととの協調性という方向で動いていく。柏木は、始めかたくなであったが、徐々に同期の仲間に打ち解けていくようでもある。
この週は、帯広に移ってからのことになるのだが、自分で飛行機を操縦して空を飛ぶときの緊張感と、そして、その楽しさが、うまく表現されていたように思う。
ところで、単純に思うことだが、訓練用の飛行機には、GPSはついていないらしい。想像するだけなのだが、今の時代、GPS無しで空を飛ぶということは、現実的ではない。しかし、訓練としては、そのようなものに頼らずに、飛行できないといけないということなのだろう。
さて、次週以降、舞と柏木はどうなるのだろうか。同期の仲間たちは、無事に課程を終えることができるだろうか。続きを楽しみに見ることにしよう。
2022年12月3日記
ブラタモリ「静岡」 ― 2022-12-05
2022年12月5日 當山日出夫
ブラタモリ 静岡
静岡というと、新幹線に乗って通過してばかりである。降りたことはない。
家康の作った城下町として、とても面白かった。江戸の街ができはじめのころ、むしろ駿府の方が、ある意味で重要な街であったことは興味深い。小判なども駿府で作っていたことは、この番組を見て知った。
古代より国府の置かれてきた土地であり、今川氏もここに居城を構えた。この古代からの歴史にもう少し触れるところがあってもよかったのではないかと感じる。それから、明治以降、徳川慶喜がここに住んだことは知られていることだが、同時に、幕臣たちも多く移り住んできた。その暮らしがどんなふうであったか、これも興味のあるところである。(このあたりは、大化がドラマの『青天を衝け』でも描いてところではあったが。)
来年の大河ドラマは、家康である。どのような駿府の街が描かれることになるのか、興味がわいてきた。
2022年12月4日記
ブラタモリ 静岡
静岡というと、新幹線に乗って通過してばかりである。降りたことはない。
家康の作った城下町として、とても面白かった。江戸の街ができはじめのころ、むしろ駿府の方が、ある意味で重要な街であったことは興味深い。小判なども駿府で作っていたことは、この番組を見て知った。
古代より国府の置かれてきた土地であり、今川氏もここに居城を構えた。この古代からの歴史にもう少し触れるところがあってもよかったのではないかと感じる。それから、明治以降、徳川慶喜がここに住んだことは知られていることだが、同時に、幕臣たちも多く移り住んできた。その暮らしがどんなふうであったか、これも興味のあるところである。(このあたりは、大化がドラマの『青天を衝け』でも描いてところではあったが。)
来年の大河ドラマは、家康である。どのような駿府の街が描かれることになるのか、興味がわいてきた。
2022年12月4日記
『鎌倉殿の13人』あれこれ「将軍になった女」 ― 2022-12-06
2022年12月6日 當山日出夫
『鎌倉殿の13人』第46回「将軍になった女」
https://www.nhk.or.jp/kamakura13/story/46.html
前回は、
やまもも書斎記 2022年11月29日
『鎌倉殿の13人』あれこれ「八幡宮の階段」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2022/11/29/9544457
鎌倉は北条のためにあり、その北条は義時そのものである。そして、その義時の権力の傍らにあるのが、三浦ということになるのだろう。
次の鎌倉殿をめぐって鎌倉はおだやかでない。権謀術数のうずまく、政権の中枢である。そのなかで、あくまでも権力を維持し、そして、後鳥羽上皇の朝廷に立ち向かおうとしているのが、義時たちということになる。鎌倉は、義時の意志で動くことになる。
この回でよかったと感じるのが、実衣。このドラマの最初から登場していたが、ここにきて、鎌倉のなかで存在感が摩している。権力のなかでもてあそばれることになった女性と言っていいだろうか。そういえば、りくもそうかもしれない。鎌倉の北条や御家人たちの、男の世界を描きながら、同時に、女性もこのドラマでは丁寧に描いてきたと思う。
ところで、新しい鎌倉殿は、朝廷や源氏とどのような関係になるのか。一度聞いただけではわからない。いや何度聞いても分からないかもしれない。まるで、「天璋院様の御右筆の~~」である。
結局、政子が尼将軍ということになった。ここで政子の活躍となるのかもしれないが、放送回数がもうほとんどない。承久の乱をどう描くことになるのか。残りの放送を楽しみに見ることにしよう。
2022年12月5日記
『鎌倉殿の13人』第46回「将軍になった女」
https://www.nhk.or.jp/kamakura13/story/46.html
前回は、
やまもも書斎記 2022年11月29日
『鎌倉殿の13人』あれこれ「八幡宮の階段」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2022/11/29/9544457
鎌倉は北条のためにあり、その北条は義時そのものである。そして、その義時の権力の傍らにあるのが、三浦ということになるのだろう。
次の鎌倉殿をめぐって鎌倉はおだやかでない。権謀術数のうずまく、政権の中枢である。そのなかで、あくまでも権力を維持し、そして、後鳥羽上皇の朝廷に立ち向かおうとしているのが、義時たちということになる。鎌倉は、義時の意志で動くことになる。
この回でよかったと感じるのが、実衣。このドラマの最初から登場していたが、ここにきて、鎌倉のなかで存在感が摩している。権力のなかでもてあそばれることになった女性と言っていいだろうか。そういえば、りくもそうかもしれない。鎌倉の北条や御家人たちの、男の世界を描きながら、同時に、女性もこのドラマでは丁寧に描いてきたと思う。
ところで、新しい鎌倉殿は、朝廷や源氏とどのような関係になるのか。一度聞いただけではわからない。いや何度聞いても分からないかもしれない。まるで、「天璋院様の御右筆の~~」である。
結局、政子が尼将軍ということになった。ここで政子の活躍となるのかもしれないが、放送回数がもうほとんどない。承久の乱をどう描くことになるのか。残りの放送を楽しみに見ることにしよう。
2022年12月5日記
追記 2022年12月13日
この続きは、
やまもも書斎記 2022年12月13日
『鎌倉殿の13人』あれこれ「ある朝敵、ある演説」
https://yamamomo.asablo.jp/blog/2022/12/13/9547577
この続きは、
やまもも書斎記 2022年12月13日
『鎌倉殿の13人』あれこれ「ある朝敵、ある演説」
https://yamamomo.asablo.jp/blog/2022/12/13/9547577
紅葉 ― 2022-12-07
2022年12月7日 當山日出夫
水曜日なので写真の日。今日は紅葉である。
前回は、
やまもも書斎記 2022年11月30日
山茶花
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2022/11/30/9544676
我が家のうちには、幾種類か紅葉する木があるが、この木が一番遅くに赤くなる。だいたい十一月の終わりから、十二月の始めにかけてが見頃である。
これも毎年同じような写真を撮っている。年々歳々とは言うが、毎年同じような写真が撮れることも、また自然の営みなのであり、幸せとすべきであろう。
この紅葉の葉が落ちると、毎年冬になったと感じる。
山茶花の花のうち、赤い花が咲いている。ピンクの花よりは少し遅れて咲く。千両や万両の木の実も赤くなっている。南天の赤い実も、まだ鳥が食べきってしまわずに残っている。
水曜日なので写真の日。今日は紅葉である。
前回は、
やまもも書斎記 2022年11月30日
山茶花
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2022/11/30/9544676
我が家のうちには、幾種類か紅葉する木があるが、この木が一番遅くに赤くなる。だいたい十一月の終わりから、十二月の始めにかけてが見頃である。
これも毎年同じような写真を撮っている。年々歳々とは言うが、毎年同じような写真が撮れることも、また自然の営みなのであり、幸せとすべきであろう。
この紅葉の葉が落ちると、毎年冬になったと感じる。
山茶花の花のうち、赤い花が咲いている。ピンクの花よりは少し遅れて咲く。千両や万両の木の実も赤くなっている。南天の赤い実も、まだ鳥が食べきってしまわずに残っている。
Nikon D500
AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR
2022年12月6日記
『22世紀の民主主義』成田悠輔 ― 2022-12-08
2022年12月8日 當山日出夫

成田悠輔.『22世紀の民主主義』(SB新書).SBクリエイティブ.2022
https://www.sbcr.jp/product/4815615604/
売れている本ということで読んでみることにした。読んで思うこととしては、次の二点になる。
第一には共感できるところ。
現在の民主主義、この本では選挙制度といっていいと思うのだが、これについて、二一世紀になった今、制度的に様々な問題があることは理解できる。なぜ、選挙区にわけて、数年に一度選挙するのか。その選挙の結果、国や社会はよりよい方向にむかっていくのだろうか。ここについては、疑問のあるところである。
この本で指摘されているように、近年、民主主義のシステムを採用している、いわゆる西欧先進諸国……日本を含めてということになるが……の衰退傾向が目立つ。それに対して、独裁的な政治体制の国の方が、経済成長の面だけとりだしてみれば、うまくいっているように見える。
だから独裁体制の方がいいということはない。しかし、代議制民主主義、選挙というシステムが、二一世紀の今日において、制度的に問題のあることは、あきらかではないだろうか。このあたりの問題意識については、かなり共感できるところがある。
第二に共感できないところ。
人間が無意識に感じているところ、それを種々の方法によって、政治に反映することのこころみが語られる。このあたりの主張については、どう楽観的にすぎるように思われる。
私がそう思っているだけなのかもしれないが、人間とは邪悪なものである。それをどうごまかして、よりよい社会にしていくのか、そう簡単ではないと思う。アルゴリズムの進展で、それは克服できると著者は主張するようなのだが、これには納得しかねるところがある。
また、言語とか、宗教とか、文化とか、民族とか、このような問題については、これからどうあるべきなのだろうか。これもアルゴリズムで解決できるということなのだろうか。さらには、統治の正統性とか、法の正義とかは、どうなるのだろうか。そもそも、そのような状態において、国家とは何であるのか。
どうもこの本の言っていることは、アルゴリズムということを、極めて肯定的に、あるいは、楽観的に捕らえているとしか思えない。このあたり、この本に今一つ共感できないところでもある。
以上の二点が、この本を読んで思ったことなどである。
書いてあることに全面的に賛同するということはない。しかし、現在の、選挙制度、民主主義のあり方について、考えることは重要である。一読には値する本だと思う。
2022年10月18日記
https://www.sbcr.jp/product/4815615604/
売れている本ということで読んでみることにした。読んで思うこととしては、次の二点になる。
第一には共感できるところ。
現在の民主主義、この本では選挙制度といっていいと思うのだが、これについて、二一世紀になった今、制度的に様々な問題があることは理解できる。なぜ、選挙区にわけて、数年に一度選挙するのか。その選挙の結果、国や社会はよりよい方向にむかっていくのだろうか。ここについては、疑問のあるところである。
この本で指摘されているように、近年、民主主義のシステムを採用している、いわゆる西欧先進諸国……日本を含めてということになるが……の衰退傾向が目立つ。それに対して、独裁的な政治体制の国の方が、経済成長の面だけとりだしてみれば、うまくいっているように見える。
だから独裁体制の方がいいということはない。しかし、代議制民主主義、選挙というシステムが、二一世紀の今日において、制度的に問題のあることは、あきらかではないだろうか。このあたりの問題意識については、かなり共感できるところがある。
第二に共感できないところ。
人間が無意識に感じているところ、それを種々の方法によって、政治に反映することのこころみが語られる。このあたりの主張については、どう楽観的にすぎるように思われる。
私がそう思っているだけなのかもしれないが、人間とは邪悪なものである。それをどうごまかして、よりよい社会にしていくのか、そう簡単ではないと思う。アルゴリズムの進展で、それは克服できると著者は主張するようなのだが、これには納得しかねるところがある。
また、言語とか、宗教とか、文化とか、民族とか、このような問題については、これからどうあるべきなのだろうか。これもアルゴリズムで解決できるということなのだろうか。さらには、統治の正統性とか、法の正義とかは、どうなるのだろうか。そもそも、そのような状態において、国家とは何であるのか。
どうもこの本の言っていることは、アルゴリズムということを、極めて肯定的に、あるいは、楽観的に捕らえているとしか思えない。このあたり、この本に今一つ共感できないところでもある。
以上の二点が、この本を読んで思ったことなどである。
書いてあることに全面的に賛同するということはない。しかし、現在の、選挙制度、民主主義のあり方について、考えることは重要である。一読には値する本だと思う。
2022年10月18日記
ザ・バックヤード「京都府立植物園」 ― 2022-12-09
2022年12月9日 當山日出夫
ザ・バックヤード 京都府立植物園
京都の植物園には、確か小学生のころに遠足で行ったような記憶がある。もう半世紀以上も昔の話しになる。そのとき、温室があったのを憶えている。その後、今の住まいになってから、一度か二度、行ったかと思う。ここ十年ぐらいは行っていない。
京都府立植物園というと、ニュースで目にすることがある。京都の北山地区の再開発に関連してである。この植物園の未来も、安泰ということではないようだ。しかし、貴重な施設は残して欲しい。特に、表面的な展示だけではなく、バックヤードにこそ、植物園の重要な役割がある。その意義がよく感じられる番組であった。
身近な花の写真を撮るようになってから、植物園というところには関心がある。とはいえ写真を撮りに行こうという気にはあまりならない。ただ、ぶらりと植物を見ながら歩いてみたい。三脚と、マクロレンズをつけたカメラを持って歩くのは、やめにしておこうかと思う。(まあ、これも、許可されているとしてであるが。)
ただ、番組の中では言っていなかったことだが、植物園の中には、たしか小さな神社があったはずである。これもこの植物園の歴史を物語るものであるかと思う。
この植物園は、これからも残してもらいたい施設の一つである。
2022年12月8日記
ザ・バックヤード 京都府立植物園
京都の植物園には、確か小学生のころに遠足で行ったような記憶がある。もう半世紀以上も昔の話しになる。そのとき、温室があったのを憶えている。その後、今の住まいになってから、一度か二度、行ったかと思う。ここ十年ぐらいは行っていない。
京都府立植物園というと、ニュースで目にすることがある。京都の北山地区の再開発に関連してである。この植物園の未来も、安泰ということではないようだ。しかし、貴重な施設は残して欲しい。特に、表面的な展示だけではなく、バックヤードにこそ、植物園の重要な役割がある。その意義がよく感じられる番組であった。
身近な花の写真を撮るようになってから、植物園というところには関心がある。とはいえ写真を撮りに行こうという気にはあまりならない。ただ、ぶらりと植物を見ながら歩いてみたい。三脚と、マクロレンズをつけたカメラを持って歩くのは、やめにしておこうかと思う。(まあ、これも、許可されているとしてであるが。)
ただ、番組の中では言っていなかったことだが、植物園の中には、たしか小さな神社があったはずである。これもこの植物園の歴史を物語るものであるかと思う。
この植物園は、これからも残してもらいたい施設の一つである。
2022年12月8日記
『人間の解剖はサルの解剖のための鍵である 増補新版』吉川浩満/ちくま文庫 ― 2022-12-10
2022年12月10日 當山日出夫
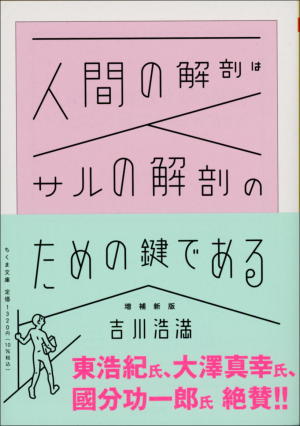
吉川浩満.『人間の解剖はサルの解剖のための鍵である 増補新版』(ちくま文庫).筑摩書房.2022
https://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480438348/
もとは、筑摩書房から二〇一八年に刊行の本である。それに加筆して、文庫化したものである。
以前、単行本が出たときに買って、ざっと読んだ本である。文庫本になり、加筆してある箇所もあるので、今回はじっくりと読んでみることにした。
思うところは、二つのことである。
第一に、やはり読んで面白い。
進化論とかAIとか行動経済学とか、最新の研究動向について、分かりやすく解説してある。なるほど、今の「知」の最前線の様相とは、こんなふうになっているのかと、思わず感心して読んでしまうところがあった。
第二に、もう今となってはちょっとつらいということ。
もう老後の読書と決めて本を読む生活をおくりたいと思っている。以前なら、この本で紹介されているような本を、自分でも読んで考えてみたいと思ったはずである。だが、もうそのような気はあまりおこらない。そんなもんなのかなと思って読んでしまうところがあるというのが、実情でもある。
以上の、二点の相反する感想をいだくのだが、しかし、これは、特に若い人にとってはおすすめの本としておいていいだろう。特に、自然科学と人文学を架橋するというこころみにおいて、この仕事は、かなり成功していると言ってよいと思う。
私の専門の分野である、言語の研究という領域においても、認知科学からのアプローチがあることは知っているのだが、もう追いついていくのがつらくなっているというのが、正直なところである。それよりも、若いころに読んだ、構造主義言語学の本など、もう一度読み直してみたくなっている。
とは言っても、いろいろ興味深いところもある。『利己的な遺伝子』は、かなり以前に読んでいる。だが、この本が、そんなに画期的な論考であるとは、はっきり言って読んだときには思わなかった。『人間の解剖は……』を読んで、『利己的な遺伝子』の価値を再認識したということもある。
以上のようなことを思うのだが、これは非常によくできた読書案内にもなっている。全部の方面については無理であるが、興味のあるところで、簡単に読めそうな本は読んでみようかという気になっている。『サピエンス全史』も買ってはあるのだがまだ読んでいない。これも読んでおきたい。
2022年11月25日記
https://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480438348/
もとは、筑摩書房から二〇一八年に刊行の本である。それに加筆して、文庫化したものである。
以前、単行本が出たときに買って、ざっと読んだ本である。文庫本になり、加筆してある箇所もあるので、今回はじっくりと読んでみることにした。
思うところは、二つのことである。
第一に、やはり読んで面白い。
進化論とかAIとか行動経済学とか、最新の研究動向について、分かりやすく解説してある。なるほど、今の「知」の最前線の様相とは、こんなふうになっているのかと、思わず感心して読んでしまうところがあった。
第二に、もう今となってはちょっとつらいということ。
もう老後の読書と決めて本を読む生活をおくりたいと思っている。以前なら、この本で紹介されているような本を、自分でも読んで考えてみたいと思ったはずである。だが、もうそのような気はあまりおこらない。そんなもんなのかなと思って読んでしまうところがあるというのが、実情でもある。
以上の、二点の相反する感想をいだくのだが、しかし、これは、特に若い人にとってはおすすめの本としておいていいだろう。特に、自然科学と人文学を架橋するというこころみにおいて、この仕事は、かなり成功していると言ってよいと思う。
私の専門の分野である、言語の研究という領域においても、認知科学からのアプローチがあることは知っているのだが、もう追いついていくのがつらくなっているというのが、正直なところである。それよりも、若いころに読んだ、構造主義言語学の本など、もう一度読み直してみたくなっている。
とは言っても、いろいろ興味深いところもある。『利己的な遺伝子』は、かなり以前に読んでいる。だが、この本が、そんなに画期的な論考であるとは、はっきり言って読んだときには思わなかった。『人間の解剖は……』を読んで、『利己的な遺伝子』の価値を再認識したということもある。
以上のようなことを思うのだが、これは非常によくできた読書案内にもなっている。全部の方面については無理であるが、興味のあるところで、簡単に読めそうな本は読んでみようかという気になっている。『サピエンス全史』も買ってはあるのだがまだ読んでいない。これも読んでおきたい。
2022年11月25日記






最近のコメント