『人口で語る世界史』ポール・モーランド/度会圭子(訳)/文春文庫 ― 2023-07-05
2023年7月5日 當山日出夫
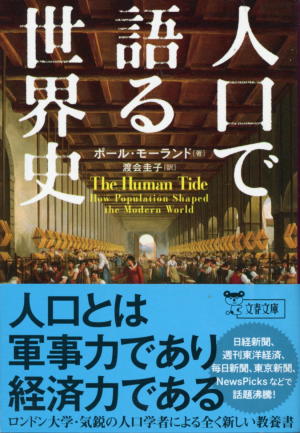
ポール・モーランド.度会圭子(訳).『人口で語る世界史』(文春文庫).文藝春秋.2023(文藝春秋.2019)
https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163910857
これは面白く読んだ。
人口という視点から、世界の歴史……主に一八世紀以降になるが……を、ダイナミックであると同時に緻密に叙述してある。歴史というのを、このような観点から見ることが出来るのかと、認識を新たにした。
一八世紀の英国から話しは始まる。産業革命によって人口が増えた。それは移民となることもあって、世界の歴史に影響を与える。また、社会の近代化によって、乳幼児死亡率の減少、平均寿命の延びによって、人口は増える。そして、社会が変わり、女性の識字率が向上すると必然的に子供の数は少なくなる。結果として、人口減少という方向に向かう。これは、洋の東西を問わず、どの地域、国でも同じように起こる。
これを読むと、今の日本で問題になっている少子高齢化という現象は日本だけの問題ではないことがよく理解される。ただ、小手先の対応では、子供の数は増えない。人口は減っていく。
人口の増減は、また移民の問題とも深くかかわっている。人口は、生まれる子供の数、死ぬ人の年齢、それから、移民による人の移動によって決まる。(ただ、日本の場合は、移民ということはあまり考慮しなくていいかもしれない。が、これも、将来的にはどうなるか分からない。)
人口というパラメータの他に、宗教とか言語とか民族とかを重ねてみるなら、世界の歴史を、これまでとは違った観点から見ることができるだろう。
もとの本は、日本では一九九九年の刊行。その後、ウクライナでの戦争が起こる。さて、人口という観点から見た場合、ウクライナ問題はどのような姿を見せることになるだろうか。また、中国による台湾問題も、見方によっては、中国の人口問題と切り離せないかもしれない。
世界で起こるいろんな出来事に、人口という観点を導入することで、いろんなことが見えてくる。しかし、この本は、単純に人口ですべてが決まると入っているわけではない。が、決して無視することのできない重要な要素であることを教えてくれる。また、その人口の増減ということが、かなり普遍的な現象として起こることも理解できる。
人口のことへの関心にとどまらず、歴史についての、新たな発想に満ちた本であると思う。
2023年3月31日記
https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163910857
これは面白く読んだ。
人口という視点から、世界の歴史……主に一八世紀以降になるが……を、ダイナミックであると同時に緻密に叙述してある。歴史というのを、このような観点から見ることが出来るのかと、認識を新たにした。
一八世紀の英国から話しは始まる。産業革命によって人口が増えた。それは移民となることもあって、世界の歴史に影響を与える。また、社会の近代化によって、乳幼児死亡率の減少、平均寿命の延びによって、人口は増える。そして、社会が変わり、女性の識字率が向上すると必然的に子供の数は少なくなる。結果として、人口減少という方向に向かう。これは、洋の東西を問わず、どの地域、国でも同じように起こる。
これを読むと、今の日本で問題になっている少子高齢化という現象は日本だけの問題ではないことがよく理解される。ただ、小手先の対応では、子供の数は増えない。人口は減っていく。
人口の増減は、また移民の問題とも深くかかわっている。人口は、生まれる子供の数、死ぬ人の年齢、それから、移民による人の移動によって決まる。(ただ、日本の場合は、移民ということはあまり考慮しなくていいかもしれない。が、これも、将来的にはどうなるか分からない。)
人口というパラメータの他に、宗教とか言語とか民族とかを重ねてみるなら、世界の歴史を、これまでとは違った観点から見ることができるだろう。
もとの本は、日本では一九九九年の刊行。その後、ウクライナでの戦争が起こる。さて、人口という観点から見た場合、ウクライナ問題はどのような姿を見せることになるだろうか。また、中国による台湾問題も、見方によっては、中国の人口問題と切り離せないかもしれない。
世界で起こるいろんな出来事に、人口という観点を導入することで、いろんなことが見えてくる。しかし、この本は、単純に人口ですべてが決まると入っているわけではない。が、決して無視することのできない重要な要素であることを教えてくれる。また、その人口の増減ということが、かなり普遍的な現象として起こることも理解できる。
人口のことへの関心にとどまらず、歴史についての、新たな発想に満ちた本であると思う。
2023年3月31日記
映像の世紀バタフライエフェクト「チャーチルVSヒトラー」 ― 2023-07-05
2023年7月5日 當山日出夫
映像の世紀バタフライエフェクト チャーチルVSヒトラー
ヒトラーは、「映像の世紀」シリーズで何回も登場している。チャーチルも、ヒトラーほどではないにせよ、いくたびか出てきている。だが、これまで、この二人を対比的にあつかったことはなかった。
この回、むしろヒトラーのことは無くてもよかったような気もする。確かに同時代を生きた二人ではあるが、対比して見えてくるものが、それほどあるようにも思えない。ここは、チャーチルのことだけで構成した番組であってもよかったように思う。
見て思ったことは、チャーチルについては、ほとんど知らないできたということがある。第二次世界大戦の時のイギリスの首相であり、戦争が終わると選挙に敗れることになった。
歴史の「もし」ということもいくつかある。もし、チャーチルとヒトラーが会談することがあったとしたら、その後の歴史は変わっていたかもしれない。いや、そもそも、イギリスの政治家にチャーチルがいたというそのこと自体が、ある意味で奇跡的なことであるのかとも思ったりする。
2023年7月4日記
映像の世紀バタフライエフェクト チャーチルVSヒトラー
ヒトラーは、「映像の世紀」シリーズで何回も登場している。チャーチルも、ヒトラーほどではないにせよ、いくたびか出てきている。だが、これまで、この二人を対比的にあつかったことはなかった。
この回、むしろヒトラーのことは無くてもよかったような気もする。確かに同時代を生きた二人ではあるが、対比して見えてくるものが、それほどあるようにも思えない。ここは、チャーチルのことだけで構成した番組であってもよかったように思う。
見て思ったことは、チャーチルについては、ほとんど知らないできたということがある。第二次世界大戦の時のイギリスの首相であり、戦争が終わると選挙に敗れることになった。
歴史の「もし」ということもいくつかある。もし、チャーチルとヒトラーが会談することがあったとしたら、その後の歴史は変わっていたかもしれない。いや、そもそも、イギリスの政治家にチャーチルがいたというそのこと自体が、ある意味で奇跡的なことであるのかとも思ったりする。
2023年7月4日記
『街道をゆく 韓のくに紀行』司馬遼太郎/朝日文庫 ― 2023-07-06
2023年7月6日 當山日出夫
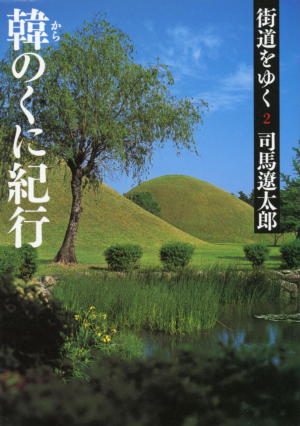
司馬遼太郎.『街道をゆく 韓のくに紀行』(朝日文庫).朝日新聞出版.2008
https://publications.asahi.com/kaidou/02/index.shtml
もとは、一九七一年から七二年、「週刊朝日」連載。
「街道をゆくシリーズ」の二冊目である。つまり、このシリーズが始まって早いころに司馬遼太郎は、韓国に行っている。一九七二年というと、私は高校生のころになる。
この時代の韓国はどんなだったろうか。歴史的には、まだ軍事政権下ということになる。このころ、「北朝鮮」のことがテレビのニュースなどで出てくると、必ず、「朝鮮民主主義人民共和国」と、追加して言っていたのを憶えている。これが、単に「北朝鮮」とだけ呼称するようになったのは、いつごろからになるだろうか。
司馬遼太郎の書いたものとしては、やや異質な感じがする。公平な目で歴史を見るという観点が乏しいと言わざるをえない。とにかく悪いのは、秀吉の朝鮮派兵であり、近代になってからの併合である。そして、あくまでも美しいのは、李氏朝鮮であり、儒教であり、田舎の風景である。
かなりバイアスのかかった見方で書かれている。
だが、この当時、「週刊朝日」というところに書くとなると、このような書き方にならざるをえなかったのか、という観点から、これはこれで、ある意味で歴史的価値のある文章であると読める。
大邱のホテルでのマッサージ師のくだりは、まあ、こんなふうに考えれば考えることもできるかなあ、というぐらいで読んでおくのがいいのだろう。
それにしても、もし、司馬遼太郎が生きていて、今の韓国、あるいは、日韓関係のことを見たらどんなふうに書くだろうかと、思ってみたくなる。
2023年6月30日記
https://publications.asahi.com/kaidou/02/index.shtml
もとは、一九七一年から七二年、「週刊朝日」連載。
「街道をゆくシリーズ」の二冊目である。つまり、このシリーズが始まって早いころに司馬遼太郎は、韓国に行っている。一九七二年というと、私は高校生のころになる。
この時代の韓国はどんなだったろうか。歴史的には、まだ軍事政権下ということになる。このころ、「北朝鮮」のことがテレビのニュースなどで出てくると、必ず、「朝鮮民主主義人民共和国」と、追加して言っていたのを憶えている。これが、単に「北朝鮮」とだけ呼称するようになったのは、いつごろからになるだろうか。
司馬遼太郎の書いたものとしては、やや異質な感じがする。公平な目で歴史を見るという観点が乏しいと言わざるをえない。とにかく悪いのは、秀吉の朝鮮派兵であり、近代になってからの併合である。そして、あくまでも美しいのは、李氏朝鮮であり、儒教であり、田舎の風景である。
かなりバイアスのかかった見方で書かれている。
だが、この当時、「週刊朝日」というところに書くとなると、このような書き方にならざるをえなかったのか、という観点から、これはこれで、ある意味で歴史的価値のある文章であると読める。
大邱のホテルでのマッサージ師のくだりは、まあ、こんなふうに考えれば考えることもできるかなあ、というぐらいで読んでおくのがいいのだろう。
それにしても、もし、司馬遼太郎が生きていて、今の韓国、あるいは、日韓関係のことを見たらどんなふうに書くだろうかと、思ってみたくなる。
2023年6月30日記
100分de名著「林芙美子“放浪記” (1)「悪」の魅力」 ― 2023-07-06
2023年7月6日 當山日出夫
100分de名著 林芙美子“放浪記” (1)「悪」の魅力
『放浪記』は、若い時から折に触れて読み返してきた作品である。最初に『放浪記』に接したのは、学校の教科書でだったと思う。その冒頭の部分、筑豊で行商をしていた子供時代のことを綴ったあたりが、出ていたと記憶する。
『放浪記』の魅力は、私にとっては、底辺で生きることになる女性のたくましさ、それから、全編にただよう詩情である。
これを現代の観点から、特にフェミニズムの視点から読み解くことは可能であろう。
番組を見て思ったことの一つは、『放浪記』の初版を出さないだろうか、ということである。今、普通に読むのは、新潮文庫版であろうと思うのだが、これは、かなり後年になってからの手が加わっているようだ。ここは、是非、初版、初出のものを読んでみたい気がする。
それから、番組の朗読を聞いていてちょっと気になったところ。「待合」ということばが出てきていたが、これは、ちょっと説明してくれた方がいいのではないだろうか。今と昔で、風俗的な違いがある。この意味で、「待合」というのは、今では分かりにくくなってしまったものの一つである。(あるいは、この番組を見る程の人なら、このことばの意味ぐらい知っていて当然ということなのかもしれないが。)
2023年7月4日記
100分de名著 林芙美子“放浪記” (1)「悪」の魅力
『放浪記』は、若い時から折に触れて読み返してきた作品である。最初に『放浪記』に接したのは、学校の教科書でだったと思う。その冒頭の部分、筑豊で行商をしていた子供時代のことを綴ったあたりが、出ていたと記憶する。
『放浪記』の魅力は、私にとっては、底辺で生きることになる女性のたくましさ、それから、全編にただよう詩情である。
これを現代の観点から、特にフェミニズムの視点から読み解くことは可能であろう。
番組を見て思ったことの一つは、『放浪記』の初版を出さないだろうか、ということである。今、普通に読むのは、新潮文庫版であろうと思うのだが、これは、かなり後年になってからの手が加わっているようだ。ここは、是非、初版、初出のものを読んでみたい気がする。
それから、番組の朗読を聞いていてちょっと気になったところ。「待合」ということばが出てきていたが、これは、ちょっと説明してくれた方がいいのではないだろうか。今と昔で、風俗的な違いがある。この意味で、「待合」というのは、今では分かりにくくなってしまったものの一つである。(あるいは、この番組を見る程の人なら、このことばの意味ぐらい知っていて当然ということなのかもしれないが。)
2023年7月4日記
『目的への抵抗』國分功一郎/新潮新書 ― 2023-07-07
2023年7月7日 當山日出夫

2023年7月7日 當山日出夫
國分功一郎.『目的への抵抗-シリーズ哲学講話-』(新潮新書).新潮社.2023
https://www.shinchosha.co.jp/book/610991/
この本については、次の二点が言えるだろう。
第一には、『暇と退屈の倫理学』を受けてのものだということ。
『暇と退屈の倫理学』は読んだ。面白い本だった。これは、その延長線上の議論がいくつか展開されている。つきつめて考えれば、人間にとって自由とはどのようなものなのか、ということについての考察になる。不要不急と言われたが、人間にとって、必要とは何か、あるいは、贅沢とは何か、このことについて考えることになる。
第二には、COVID-19、コロナ禍で人はどうあるべきかという考察であること。
この本を読み、この文章を書いている時点では、コロナ禍というのは、いくぶんは過去のものになった印象がある。だが、二〇二〇年から始まる、三年あまりの月日は、いろんな苦労もあったが、その一方で、いろいろと考えるべきこともあった。それについて、著者は、イタリアの哲学者、アガンベンの言説を引用することで、問題提起をおこなっている。
生存だけに価値を見出すことの問題。死者の権利の問題。移動の自由の問題。
日本では、ネットで炎上するということはなかったが、これらの問題提起は、重要である。(余計なこととして思うことは、では、何故、日本ではアガンベンの提起した議論が論じられることがなかったのだろうか。ここに、日本の現代の社会の抱える根本的な問題があるのではないだろうか。)
ざっと以上の二点を軸とする本である。この本は、講話だという。一般的に言えば、講義の筆記録である。ただ、それが、大学の授業(成績や単位の認定にかかわる)ではなく、学生相手に自由な場面を設定して行われたということは、重要かもしれない。
どのような場面で、どのような相手に対して語られたことばであるかは、コロナ禍でのオンライン会議などを通じて、逆にその意味が明らかになってきていると言ってもいいだろう。
この本を読んで感じることは……考えることの重要性である。まさに哲学と言ってもいい。自分でものごとを考えること、そして、どのような状況で、何について、どう考えるのか、ここのところに自覚的であることの重要性である。言いかえるならば、ただ考えたことの結論があればいいというのではない。
今、対話AIがいろいろと問題になっている。このような状況にあって、自分自身でものごとを考えることの、ある意味ではその楽しさとでも言っていいだろうか、これを感じさせる本である。今まさにこの時代であるからこそ、広く読まれていい本であると思う。
2023年4月28日記
國分功一郎.『目的への抵抗-シリーズ哲学講話-』(新潮新書).新潮社.2023
https://www.shinchosha.co.jp/book/610991/
この本については、次の二点が言えるだろう。
第一には、『暇と退屈の倫理学』を受けてのものだということ。
『暇と退屈の倫理学』は読んだ。面白い本だった。これは、その延長線上の議論がいくつか展開されている。つきつめて考えれば、人間にとって自由とはどのようなものなのか、ということについての考察になる。不要不急と言われたが、人間にとって、必要とは何か、あるいは、贅沢とは何か、このことについて考えることになる。
第二には、COVID-19、コロナ禍で人はどうあるべきかという考察であること。
この本を読み、この文章を書いている時点では、コロナ禍というのは、いくぶんは過去のものになった印象がある。だが、二〇二〇年から始まる、三年あまりの月日は、いろんな苦労もあったが、その一方で、いろいろと考えるべきこともあった。それについて、著者は、イタリアの哲学者、アガンベンの言説を引用することで、問題提起をおこなっている。
生存だけに価値を見出すことの問題。死者の権利の問題。移動の自由の問題。
日本では、ネットで炎上するということはなかったが、これらの問題提起は、重要である。(余計なこととして思うことは、では、何故、日本ではアガンベンの提起した議論が論じられることがなかったのだろうか。ここに、日本の現代の社会の抱える根本的な問題があるのではないだろうか。)
ざっと以上の二点を軸とする本である。この本は、講話だという。一般的に言えば、講義の筆記録である。ただ、それが、大学の授業(成績や単位の認定にかかわる)ではなく、学生相手に自由な場面を設定して行われたということは、重要かもしれない。
どのような場面で、どのような相手に対して語られたことばであるかは、コロナ禍でのオンライン会議などを通じて、逆にその意味が明らかになってきていると言ってもいいだろう。
この本を読んで感じることは……考えることの重要性である。まさに哲学と言ってもいい。自分でものごとを考えること、そして、どのような状況で、何について、どう考えるのか、ここのところに自覚的であることの重要性である。言いかえるならば、ただ考えたことの結論があればいいというのではない。
今、対話AIがいろいろと問題になっている。このような状況にあって、自分自身でものごとを考えることの、ある意味ではその楽しさとでも言っていいだろうか、これを感じさせる本である。今まさにこの時代であるからこそ、広く読まれていい本であると思う。
2023年4月28日記
『悪女について』(後編) ― 2023-07-07
2023年7月6日 當山日出夫
悪女について(後編)
後編になって……これは、かなり原作を改編してあるな、と思う。まあ、原作の小説があるからといってそれに忠実に作らなければならないということではない。しかし、原作の小説としてのインパクトがかなり大きいだけに……読んだのは、も半世紀近く昔のことになるが、強い印象を持って憶えている……このようなドラマの作り方には、ちょっと拍子抜けするという感じがする。
公子というヒロインは、もっと謎めいた存在であったはずである。様々な語りから浮かびあがる彼女の本当の姿はいったい何なのか、これは誰にもわからない。ここのところにこそ、「悪女」の魅力があったと憶えている。
このドラマでは、この「悪女」が、いい人になってしまっている。
それから、たしかに『悪女について』ということでは、田中みな実は適役という気はするのだが、しかし、今一つ役者としてうまくない。といって、他のどの役者ならという気はまったくないのだが。
2023年7月5日記
悪女について(後編)
後編になって……これは、かなり原作を改編してあるな、と思う。まあ、原作の小説があるからといってそれに忠実に作らなければならないということではない。しかし、原作の小説としてのインパクトがかなり大きいだけに……読んだのは、も半世紀近く昔のことになるが、強い印象を持って憶えている……このようなドラマの作り方には、ちょっと拍子抜けするという感じがする。
公子というヒロインは、もっと謎めいた存在であったはずである。様々な語りから浮かびあがる彼女の本当の姿はいったい何なのか、これは誰にもわからない。ここのところにこそ、「悪女」の魅力があったと憶えている。
このドラマでは、この「悪女」が、いい人になってしまっている。
それから、たしかに『悪女について』ということでは、田中みな実は適役という気はするのだが、しかし、今一つ役者としてうまくない。といって、他のどの役者ならという気はまったくないのだが。
2023年7月5日記
『街道をゆく 甲賀と伊賀のみち、砂鉄のみち ほか』司馬遼太郎/朝日文庫 ― 2023-07-08
2023年7月8日 當山日出夫

司馬遼太郎.『街道をゆく 甲賀と伊賀のみち、砂鉄のみち ほか』(朝日文庫).朝日新聞出版.2008
https://publications.asahi.com/kaidou/07/index.shtml
もとは、一九七三年から七五年にかけて、「週刊朝日」連載。
収録するのは、
「甲賀と伊賀のみち」
「大和・壺坂のみち」
「明石海峡と淡路みち」
「砂鉄のみち」
司馬遼太郎の語る日本の歴史は、基本的にコメを基本としている。弥生時代になって米作をおこなうひとびとが日本にやってきて、日本でコメを作るようになった。その影響下に、その後の歴史はずっとある。武士の成立もそうであるし、戦国の時代も、また、江戸時代から近代にいたるまで、米作を基盤に日本の文化があるとする。
だが、時として、米作からはなれた論考を語ることがある。この本の中では、漁業民のことが出てくる。淡路に行ったときのこととしてである。漁業で生計をたててきた人びとのことに思いをはせている。
また、砂鉄のことにふれて、古代の出雲や中国地方において、製鉄をなりわいとしていた人びとのことを、いろいろと考えている。
漁業にせよ、製鉄にせよ、いわゆる非農業民である。これらの人びとが、古代からどのように暮らしてきたのか、これはこれで興味のあるところである。
ところで、ちょっと前のことになるが、NHKで、タタラ製鉄のことをやっていたのを思い出す。これはちょっと大変な仕事であると思って見ていた。今も、タタラの技法は、どうにか受け継がれているようである。
この本をスタートにして、日本における漁業史、あるいは、製鉄史ということを考えてみてもいいのかもしれない。が、今しばらくは、「街道をゆく」を続けて読んでいきたいと思っている。
2023年7月2日記
https://publications.asahi.com/kaidou/07/index.shtml
もとは、一九七三年から七五年にかけて、「週刊朝日」連載。
収録するのは、
「甲賀と伊賀のみち」
「大和・壺坂のみち」
「明石海峡と淡路みち」
「砂鉄のみち」
司馬遼太郎の語る日本の歴史は、基本的にコメを基本としている。弥生時代になって米作をおこなうひとびとが日本にやってきて、日本でコメを作るようになった。その影響下に、その後の歴史はずっとある。武士の成立もそうであるし、戦国の時代も、また、江戸時代から近代にいたるまで、米作を基盤に日本の文化があるとする。
だが、時として、米作からはなれた論考を語ることがある。この本の中では、漁業民のことが出てくる。淡路に行ったときのこととしてである。漁業で生計をたててきた人びとのことに思いをはせている。
また、砂鉄のことにふれて、古代の出雲や中国地方において、製鉄をなりわいとしていた人びとのことを、いろいろと考えている。
漁業にせよ、製鉄にせよ、いわゆる非農業民である。これらの人びとが、古代からどのように暮らしてきたのか、これはこれで興味のあるところである。
ところで、ちょっと前のことになるが、NHKで、タタラ製鉄のことをやっていたのを思い出す。これはちょっと大変な仕事であると思って見ていた。今も、タタラの技法は、どうにか受け継がれているようである。
この本をスタートにして、日本における漁業史、あるいは、製鉄史ということを考えてみてもいいのかもしれない。が、今しばらくは、「街道をゆく」を続けて読んでいきたいと思っている。
2023年7月2日記
ザ・バックヤード「国立公文書館 第2弾」 ― 2023-07-08
2023年7月8日 當山日出夫
日本国憲法の原文は、今では、デジタル・アーカイブで見ることができる。その他、近現代史の貴重な史料の多くが、デジタル公開されている。ただ、これはあまり知られていないことなのかもしれない。
また、アーカイブズというのは、公開が原則である。確かに、ことさら貴重なものは特別に保存する必要がある。しかし、その資料・史料は基本的に、一般に公開されるべきはずのものである。
まあ、このような番組の場合、貴重な史料に目がいくのはしかたがないとは思う。しかし、専門的な観点からするならば、普通の公文書とか、あるいは、古典籍でも内閣文庫の和書、漢籍などが、どのように保存、利用されているのか、このあたりのことが、重要であると思う。
今、公文書の改竄、あるいは、意図的に作成しない、ということが行われている。このことの、歴史的意味を、今こそ多くの人びとが考えなければならない時である。
2023年7月6日記
日本国憲法の原文は、今では、デジタル・アーカイブで見ることができる。その他、近現代史の貴重な史料の多くが、デジタル公開されている。ただ、これはあまり知られていないことなのかもしれない。
また、アーカイブズというのは、公開が原則である。確かに、ことさら貴重なものは特別に保存する必要がある。しかし、その資料・史料は基本的に、一般に公開されるべきはずのものである。
まあ、このような番組の場合、貴重な史料に目がいくのはしかたがないとは思う。しかし、専門的な観点からするならば、普通の公文書とか、あるいは、古典籍でも内閣文庫の和書、漢籍などが、どのように保存、利用されているのか、このあたりのことが、重要であると思う。
今、公文書の改竄、あるいは、意図的に作成しない、ということが行われている。このことの、歴史的意味を、今こそ多くの人びとが考えなければならない時である。
2023年7月6日記
神田伯山の これがわが社の黒歴史 エステー“エレカル家電”の興亡 ― 2023-07-08
2023年7月8日 當山日出夫
神田伯山の これがわが社の黒歴史 (4)エステー“エレカル家電”の興亡
この商品、今出せば売れるんじゃないか、というのが正直な感想。何しろCOVID-19、コロナ禍の世の中である。かなり収まってきたとはいうものの、今後のことについてはまだどうなるかわからない。ここ数年で、空気の除菌というということについての社会の意識は大きく変わった。
五五〇〇じゃなくて、五五〇〇〇円でもいいと思う。機能を高めて、高品質、高耐久性の商品なら、今なら、また勝負できるかもしれない。ただ、同様の商品はすでに多くあるから、再度参入というのも、難しいといえばいえそうである。
この「黒歴史」のシリーズ、これまでの放送はだいたい見てきていると思う。どの回も面白かった。ビジネスの失敗とはいっても、それは長い目で見れば成長につながっている。ただ失敗だけに終わらせず、そこからどのようにして次につなげていくかが重要になるだろう。
放射線測定器のことは、知らなかった。まあ、住んでいる地域が、そんなに気にしなくてもいい地域だということもあるだろう。二〇一一の当時、九八〇〇円で放射線測定器が買えるなら、これは多くの人びとの要望に応えるものであったと思う。
それから、やはりうまいと感じるのは、神田伯山の語り。語りで人を魅了する技能にかけて、さすが講談師である。この語りの魅力が、この番組の基本にある。
2023年7月7日記
神田伯山の これがわが社の黒歴史 (4)エステー“エレカル家電”の興亡
この商品、今出せば売れるんじゃないか、というのが正直な感想。何しろCOVID-19、コロナ禍の世の中である。かなり収まってきたとはいうものの、今後のことについてはまだどうなるかわからない。ここ数年で、空気の除菌というということについての社会の意識は大きく変わった。
五五〇〇じゃなくて、五五〇〇〇円でもいいと思う。機能を高めて、高品質、高耐久性の商品なら、今なら、また勝負できるかもしれない。ただ、同様の商品はすでに多くあるから、再度参入というのも、難しいといえばいえそうである。
この「黒歴史」のシリーズ、これまでの放送はだいたい見てきていると思う。どの回も面白かった。ビジネスの失敗とはいっても、それは長い目で見れば成長につながっている。ただ失敗だけに終わらせず、そこからどのようにして次につなげていくかが重要になるだろう。
放射線測定器のことは、知らなかった。まあ、住んでいる地域が、そんなに気にしなくてもいい地域だということもあるだろう。二〇一一の当時、九八〇〇円で放射線測定器が買えるなら、これは多くの人びとの要望に応えるものであったと思う。
それから、やはりうまいと感じるのは、神田伯山の語り。語りで人を魅了する技能にかけて、さすが講談師である。この語りの魅力が、この番組の基本にある。
2023年7月7日記
『転落』カミュ/前山悠(訳)/光文社古典新訳文庫 ― 2023-07-09
2023年7月9日 當山日出夫

カミュ.前山悠(訳).『転落』(光文社古典新訳文庫).光文社.2023
https://www.kobunsha.com/shelf/book/isbn/9784334754778
『転落』の新しい訳である。むかし、新潮文庫版で読んだことは覚えているのだが、この作品についてさほど鮮明な記憶はなかった。今回、光文社古典新訳文庫で新しく訳がでたので、読んでみることにした。
これほど面白い小説だったのか、というのがまず思うことである。アムステルダムの夜、酒場、そこで語られる物語……この語りのなかに思わず引きこまれて読んでしまう。小説としての面白さということでも一級の作品であることが理解される。
そして思うことは、この小説の語りはいったい何なのだろう。寓話のかたまりのような印象をうける。『ペスト』とか『異邦人』とか読んだ印象が残っているせいかもしれない。カミュの作品にあることばをそのまま単純に受けとめるのではなく、そこに隠された寓意というものを詮索したくなる。
全体を通しての語りのうまさ、物語的面白さ、それと、寓意……これがないまぜになったところにこの作品の魅力があるといってよい。
ただ、今になって、その寓意の意味するところを詮索して読んでみようという気にもならないでいる。小説的な面白さだけで、私には十分である。
2023年4月3日記
https://www.kobunsha.com/shelf/book/isbn/9784334754778
『転落』の新しい訳である。むかし、新潮文庫版で読んだことは覚えているのだが、この作品についてさほど鮮明な記憶はなかった。今回、光文社古典新訳文庫で新しく訳がでたので、読んでみることにした。
これほど面白い小説だったのか、というのがまず思うことである。アムステルダムの夜、酒場、そこで語られる物語……この語りのなかに思わず引きこまれて読んでしまう。小説としての面白さということでも一級の作品であることが理解される。
そして思うことは、この小説の語りはいったい何なのだろう。寓話のかたまりのような印象をうける。『ペスト』とか『異邦人』とか読んだ印象が残っているせいかもしれない。カミュの作品にあることばをそのまま単純に受けとめるのではなく、そこに隠された寓意というものを詮索したくなる。
全体を通しての語りのうまさ、物語的面白さ、それと、寓意……これがないまぜになったところにこの作品の魅力があるといってよい。
ただ、今になって、その寓意の意味するところを詮索して読んでみようという気にもならないでいる。小説的な面白さだけで、私には十分である。
2023年4月3日記
最近のコメント