オンライン授業あれこれ(その一四) ― 2020-08-01
2020-08-01 當山日出夫(とうやまひでお)
続きである。
やまもも書斎記 2020年7月25日
オンライン授業あこれこ(その一三)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/07/25/9271484
水曜日ごとに教材の配信などしている。この週は、最後のまとめと、それから、四回目のレポート課題。
さきほど確認してみたところ、LMSを見ている学生の割合は、半分ほど。前期の授業もおわりにちかづいたので、LMSを確認しておこうという学生が、ちょっとは増えたのかもしれない。
しかし、すでに三回のレポートは締め切ってしまっている。また、それに対する講評……どんなことが書いてあればいいのか……について、示してある。遅れて提出しても、もう無理である。
四回のレポートの課題としたことは、ほぼ、例年の前期試験の問題の出題と重なっている。普通の授業ができたのと、おおむね同じ程度のことを、レポートに書いたことになる。これを、四回、きちんと提出してくれていれば問題ない。今のところ、まったく見当外れな内容のレポートというのはあまりない。
まあ、中には、配信した教材をまったく読まずに勝手に調べて書いたと思われるものがあったりしたが、そのようなものについては、その旨を注意しておいた。たしかに自分で本を読んだりして勉強することは悪いことではない。しかし、その前に、まずこちらが配信したことがらに目を通して、その上で何かを言うのでなければならない。
今のところ、夏休みあけ、後期のことはまったく不明としかいいようがないのだが、楽観的になる要因はほとんどない。現状のままで推移するなれば、たぶん、後期は、一部の授業を除いてオンラインで、ということになるだろう。
それにそなえて、学生の方が、インターネットの回線の整備とか、パソコンの準備とか、してくれているのならいいのだが、はたしてどうだろうか。依然として、スマホのまま。あるいは、スマホも持っていない。このような状況が継続するようなら、授業のライブ配信ということは、ためらってしまう。
それに、送信された画像を見て、それで授業を受けた気持ちになってしまうということも、また困ることである。これを考えてみるならば、教材資料をとにかく読んで、レポートを書くというのが、一番確実に学習につながる方式ではあるのかとも思う。
ともあれ、後期からの授業がどうなるかは、その時になって考えることにする。
その前に、最後のレポートをきちんと提出してくれるのを待っていることにする。その上で、これまでに提出されたものを、再度チェックして採点・評価ということになる。
2020年7月31日記
続きである。
やまもも書斎記 2020年7月25日
オンライン授業あこれこ(その一三)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/07/25/9271484
水曜日ごとに教材の配信などしている。この週は、最後のまとめと、それから、四回目のレポート課題。
さきほど確認してみたところ、LMSを見ている学生の割合は、半分ほど。前期の授業もおわりにちかづいたので、LMSを確認しておこうという学生が、ちょっとは増えたのかもしれない。
しかし、すでに三回のレポートは締め切ってしまっている。また、それに対する講評……どんなことが書いてあればいいのか……について、示してある。遅れて提出しても、もう無理である。
四回のレポートの課題としたことは、ほぼ、例年の前期試験の問題の出題と重なっている。普通の授業ができたのと、おおむね同じ程度のことを、レポートに書いたことになる。これを、四回、きちんと提出してくれていれば問題ない。今のところ、まったく見当外れな内容のレポートというのはあまりない。
まあ、中には、配信した教材をまったく読まずに勝手に調べて書いたと思われるものがあったりしたが、そのようなものについては、その旨を注意しておいた。たしかに自分で本を読んだりして勉強することは悪いことではない。しかし、その前に、まずこちらが配信したことがらに目を通して、その上で何かを言うのでなければならない。
今のところ、夏休みあけ、後期のことはまったく不明としかいいようがないのだが、楽観的になる要因はほとんどない。現状のままで推移するなれば、たぶん、後期は、一部の授業を除いてオンラインで、ということになるだろう。
それにそなえて、学生の方が、インターネットの回線の整備とか、パソコンの準備とか、してくれているのならいいのだが、はたしてどうだろうか。依然として、スマホのまま。あるいは、スマホも持っていない。このような状況が継続するようなら、授業のライブ配信ということは、ためらってしまう。
それに、送信された画像を見て、それで授業を受けた気持ちになってしまうということも、また困ることである。これを考えてみるならば、教材資料をとにかく読んで、レポートを書くというのが、一番確実に学習につながる方式ではあるのかとも思う。
ともあれ、後期からの授業がどうなるかは、その時になって考えることにする。
その前に、最後のレポートをきちんと提出してくれるのを待っていることにする。その上で、これまでに提出されたものを、再度チェックして採点・評価ということになる。
2020年7月31日記
追記 2020-08-09
この続きは、
やまもも書斎記 2020年8月9日
オンライン授業あれこれ(その一五)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/08/09/9276805
この続きは、
やまもも書斎記 2020年8月9日
オンライン授業あれこれ(その一五)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/08/09/9276805
『エール』あれこれ「ふたりの決意」(再放送) ― 2020-08-02
2020-08-02 當山日出夫(とうやまひでお)
『エール』第5週「ふたりの決意」
https://www.nhk.or.jp/yell/story/week_06.html
本放送のときのことは、
やまもも書斎記 2020年5月10日
『エール』あれこれ「ふたりの決意」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/05/10/9244938
前回は、
やまもも書斎記 2020年7月30日
『エール』あれこれ「愛の狂騒曲」(再放送)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/07/30/9273258
この週で、裕一は音楽家になる決意をかためることになる。レコード会社との契約も、なんとかなった。これは、ひとえに音のがんばりであった。
いろいろ印象に残るシーンがあるが……東京に出ることになる裕一を見送る父の三郎との別れの場面が印象的であった。三郎は、東京に出る裕一を暖かく見守っている。
そういえば、このドラマ、これまでのところ……通常の放送を見てのことだが……敵役というような人物があまり出てきてはいない。いい人ばかりということでもないのだが、そんなに悪い人もいない。殆どの登場人物は、裕一と、それから音のふたりのことを、応援している。ただ、その思いは、立場によって様々である。
父親は父親として、また、母親は母親として、裕一のことを思っている。また、藤堂先生や、銀行の仲間たちも、裕一の味方といっていいだろう。無論、この週の、副音声の解説を担当していた鉄男も、その後、裕一とともにあゆむことになる。
これからの展開は、以前の放送で見て知っているのだが……結局、裕一は、周囲のひとびとにめぐまれていることになる。ただ、あまり無かったかもしれないのが、運のめぐりあわせ、ということかもしれない。(それも、最終的には、ヒット曲を出すことでなんとかなるのだが。)
このドラマ、古山裕一という一人の作曲家の物語でありながら、妻の音をはじめとする、周囲の人びとの物語でもある。ただ、あまり時代的背景とか世相とかという部分は描かない方針のようではある。
ともあれ、次週から、東京での作曲家生活がスタートすることになる。新たな登場人物として、バンブーの夫婦も出てきた。今後の展開を、もう一度見ることにしよう。
2020年8月1日記
『エール』第5週「ふたりの決意」
https://www.nhk.or.jp/yell/story/week_06.html
本放送のときのことは、
やまもも書斎記 2020年5月10日
『エール』あれこれ「ふたりの決意」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/05/10/9244938
前回は、
やまもも書斎記 2020年7月30日
『エール』あれこれ「愛の狂騒曲」(再放送)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/07/30/9273258
この週で、裕一は音楽家になる決意をかためることになる。レコード会社との契約も、なんとかなった。これは、ひとえに音のがんばりであった。
いろいろ印象に残るシーンがあるが……東京に出ることになる裕一を見送る父の三郎との別れの場面が印象的であった。三郎は、東京に出る裕一を暖かく見守っている。
そういえば、このドラマ、これまでのところ……通常の放送を見てのことだが……敵役というような人物があまり出てきてはいない。いい人ばかりということでもないのだが、そんなに悪い人もいない。殆どの登場人物は、裕一と、それから音のふたりのことを、応援している。ただ、その思いは、立場によって様々である。
父親は父親として、また、母親は母親として、裕一のことを思っている。また、藤堂先生や、銀行の仲間たちも、裕一の味方といっていいだろう。無論、この週の、副音声の解説を担当していた鉄男も、その後、裕一とともにあゆむことになる。
これからの展開は、以前の放送で見て知っているのだが……結局、裕一は、周囲のひとびとにめぐまれていることになる。ただ、あまり無かったかもしれないのが、運のめぐりあわせ、ということかもしれない。(それも、最終的には、ヒット曲を出すことでなんとかなるのだが。)
このドラマ、古山裕一という一人の作曲家の物語でありながら、妻の音をはじめとする、周囲の人びとの物語でもある。ただ、あまり時代的背景とか世相とかという部分は描かない方針のようではある。
ともあれ、次週から、東京での作曲家生活がスタートすることになる。新たな登場人物として、バンブーの夫婦も出てきた。今後の展開を、もう一度見ることにしよう。
2020年8月1日記
追記 2020-08-08
この続きは、
やまもも書斎記 2020年8月8日
『エール』あれこれ「夢の新婚生活」(再放送)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/08/08/9276448
この続きは、
やまもも書斎記 2020年8月8日
『エール』あれこれ「夢の新婚生活」(再放送)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/08/08/9276448
『源氏物語』(12)匂兵部卿・紅梅・竹河・橋姫 ― 2020-08-03
2020-08-03 當山日出夫(とうやまひでお)

阿部秋生・秋山虔・今井源衛・鈴木日出男(校注・訳).『源氏物語』(12)匂兵部卿・紅梅・竹河・橋姫.1998
https://www.shogakukan.co.jp/books/09362092
続きである。
やまもも書斎記 2020年7月31日
『源氏物語』(11)横笛・鈴虫・夕霧・御法・幻
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/07/31/9273660
第一二冊目である。「匂兵部卿」から「橋姫」までをおさめる。
この冊を読んで思うことを書くならば、次の二点ぐらいだろうか。
第一には、「匂兵部卿」「紅梅」「竹河」。
この三巻については、『源氏物語』の成立論においても、いろいろ問題のある部分であることは承知しているつもりである。その目で読むせいもあるのだろうか、やはり、これらの巻は、それまでの光源氏の物語と、筆致が異なるように感じられてならない。別作者とまで言う気はないが、もし、同じ作者……おそらくは紫式部……であったとしても、これらの部分は、独立して別に書いたとしか思えない。(はっきりいって、ここの部分は、読んでいてつまらないのであるが。)
第二には、「橋姫」。
ここから、いよいよ「宇治十帖」にはいる。確かに、ここにきて、文章が変わってきている。また、登場人物のおもむきもことなる。これまでの『源氏物語』の本編、それも「紫の上」系の物語であれば、そんなに大きくは登場しなかったであろう、弁の君など、それから、宇治とのつかいをする召使いなど……これらの登場人物の描写が、これまでの物語とは異なった雰囲気を作りだしている。
そして、仏教。本編でも、紫の上にせよ、光源氏にせよ、多くの登場人物は出家の願いをもっており、また、現に出家している。仏道へのあこがれといってよいか。
だが、薫の仏教への思いは、ちょっと違っていると感じるところがある。「宇治十帖」になって、この物語は、仏教への思いが異なってきている。このあたり、日本における、いわゆる仏教文学という観点から見るならば、『源氏物語』「宇治十帖」は、かなり異色の作品と言ってよいのではなかろうか。
つづけて「宇治十帖」を読んでいくこととしたい。
2020年6月29日記
https://www.shogakukan.co.jp/books/09362092
続きである。
やまもも書斎記 2020年7月31日
『源氏物語』(11)横笛・鈴虫・夕霧・御法・幻
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/07/31/9273660
第一二冊目である。「匂兵部卿」から「橋姫」までをおさめる。
この冊を読んで思うことを書くならば、次の二点ぐらいだろうか。
第一には、「匂兵部卿」「紅梅」「竹河」。
この三巻については、『源氏物語』の成立論においても、いろいろ問題のある部分であることは承知しているつもりである。その目で読むせいもあるのだろうか、やはり、これらの巻は、それまでの光源氏の物語と、筆致が異なるように感じられてならない。別作者とまで言う気はないが、もし、同じ作者……おそらくは紫式部……であったとしても、これらの部分は、独立して別に書いたとしか思えない。(はっきりいって、ここの部分は、読んでいてつまらないのであるが。)
第二には、「橋姫」。
ここから、いよいよ「宇治十帖」にはいる。確かに、ここにきて、文章が変わってきている。また、登場人物のおもむきもことなる。これまでの『源氏物語』の本編、それも「紫の上」系の物語であれば、そんなに大きくは登場しなかったであろう、弁の君など、それから、宇治とのつかいをする召使いなど……これらの登場人物の描写が、これまでの物語とは異なった雰囲気を作りだしている。
そして、仏教。本編でも、紫の上にせよ、光源氏にせよ、多くの登場人物は出家の願いをもっており、また、現に出家している。仏道へのあこがれといってよいか。
だが、薫の仏教への思いは、ちょっと違っていると感じるところがある。「宇治十帖」になって、この物語は、仏教への思いが異なってきている。このあたり、日本における、いわゆる仏教文学という観点から見るならば、『源氏物語』「宇治十帖」は、かなり異色の作品と言ってよいのではなかろうか。
つづけて「宇治十帖」を読んでいくこととしたい。
2020年6月29日記
追記 2020-08-04
この続きは、
やまもも書斎記 2020年8月4日
『源氏物語』(13)椎本・総角
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/08/04/9275173
この続きは、
やまもも書斎記 2020年8月4日
『源氏物語』(13)椎本・総角
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/08/04/9275173
『源氏物語』(13)椎本・総角 ― 2020-08-04
2020-08-04 當山日出夫(とうやまひでお)

阿部秋生・秋山虔・今井源衛・鈴木日出男(校注・訳).『源氏物語』(13)椎本・総角.1998
https://www.shogakukan.co.jp/books/09362093
続きである。
やまもも書斎記 2020年8月3日
『源氏物語』(12)匂兵部卿・紅梅・竹河・橋姫
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/08/03/9274836
第一三冊目である。「椎本」「総角」をおさめる。
「宇治十帖」を読んでいる。「桐壺」から順番に読んできて、「宇治十帖」になると、これは、色好みの物語ではない、と強く感じるところがある。むしろ、近代的な、恋愛心理小説に近いと言っていいかもしれない。
ここまでの主な登場人物は、薫、匂宮、大君、中君、である。この四人の、それぞれの思惑のいきちがい、微妙な心理の交錯が、宇治の里を舞台にしてくりひろげられる。
これまで読んできた印象としては、「若菜」(上・下)あたりから、『源氏物語』は大きく展開する。光源氏という当代随一の貴公子を軸とした、色好みの物語であったものが、人間の心理のうち、そのゆれうごき、すれちがい、といったことを綿密に見つめる筆致に変わっていく。特にそれを強く感じるのが、「夕霧」の巻ぐらいからである。
勝手な妄想をするならばであるが……「若菜」(上・下)を書いたところで、作者は、色好みの物語を書くことを、超越してしまったとも解釈できようか。といって、「宇治十帖」別作者説をとなえようとは思わない。ただ、『源氏物語』を順番に読みながら、それを書いている作者の、人間を見る目の深化というものを感じてしまうのである。
それから、「総角」における、大君の死の描写は印象的である。『源氏物語』には多くの人の死が描かれるが、そのなかでも特に印象に残る場面である。
大君が亡くなり、次は浮舟の登場となる。続けて読むことにしよう。
2020年7月1日記
https://www.shogakukan.co.jp/books/09362093
続きである。
やまもも書斎記 2020年8月3日
『源氏物語』(12)匂兵部卿・紅梅・竹河・橋姫
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/08/03/9274836
第一三冊目である。「椎本」「総角」をおさめる。
「宇治十帖」を読んでいる。「桐壺」から順番に読んできて、「宇治十帖」になると、これは、色好みの物語ではない、と強く感じるところがある。むしろ、近代的な、恋愛心理小説に近いと言っていいかもしれない。
ここまでの主な登場人物は、薫、匂宮、大君、中君、である。この四人の、それぞれの思惑のいきちがい、微妙な心理の交錯が、宇治の里を舞台にしてくりひろげられる。
これまで読んできた印象としては、「若菜」(上・下)あたりから、『源氏物語』は大きく展開する。光源氏という当代随一の貴公子を軸とした、色好みの物語であったものが、人間の心理のうち、そのゆれうごき、すれちがい、といったことを綿密に見つめる筆致に変わっていく。特にそれを強く感じるのが、「夕霧」の巻ぐらいからである。
勝手な妄想をするならばであるが……「若菜」(上・下)を書いたところで、作者は、色好みの物語を書くことを、超越してしまったとも解釈できようか。といって、「宇治十帖」別作者説をとなえようとは思わない。ただ、『源氏物語』を順番に読みながら、それを書いている作者の、人間を見る目の深化というものを感じてしまうのである。
それから、「総角」における、大君の死の描写は印象的である。『源氏物語』には多くの人の死が描かれるが、そのなかでも特に印象に残る場面である。
大君が亡くなり、次は浮舟の登場となる。続けて読むことにしよう。
2020年7月1日記
追記 2020-08-06
この続きは、
やまもも書斎記 2020年8月6日
『源氏物語』(14)早蕨・宿木
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/08/06/9275816
この続きは、
やまもも書斎記 2020年8月6日
『源氏物語』(14)早蕨・宿木
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/08/06/9275816
モミジの種子 ― 2020-08-05
2020-08-05 當山日出夫(とうやまひでお)
水曜日なので写真の日。今日は花ではなく、モミジの種子である。
前回は、
やまもも書斎記 2020年7月29日
ユウゲショウ
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/07/29/9272881
我が家にはいくつかのモミジの木がある。種類はいろいろとあるようだが、細かいところまでは分からないままでいる。そのうちのいくつの木は、春になると種子を見ることができる。見ていると、これはかなり長く残る。秋になって冬枯れという季節になっても、茶色くなったものを目にする。
梅雨があけてから、急に暑くなった。今年は、まだツユクサを目にしていない。例年、七月のうちには写真に撮っていたかと思うのだが、我が家のうちのツユクサのあたりを見てみても、まだ青い花を見ることがない。
そうかと思うと、百日紅の花が例年よりも早く咲いたようである。桔梗の花の咲くのは、逆に去年よりも遅かった。
どうも天候の不順ということが、身の周りの咲く花にも、いろんな形で影響しているようである。
雨の日がつづいて、それから急に暑くなったので、写真をとりに外に出かけるということがない。掲載の写真は、撮りおきのストックからである。
水曜日なので写真の日。今日は花ではなく、モミジの種子である。
前回は、
やまもも書斎記 2020年7月29日
ユウゲショウ
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/07/29/9272881
我が家にはいくつかのモミジの木がある。種類はいろいろとあるようだが、細かいところまでは分からないままでいる。そのうちのいくつの木は、春になると種子を見ることができる。見ていると、これはかなり長く残る。秋になって冬枯れという季節になっても、茶色くなったものを目にする。
梅雨があけてから、急に暑くなった。今年は、まだツユクサを目にしていない。例年、七月のうちには写真に撮っていたかと思うのだが、我が家のうちのツユクサのあたりを見てみても、まだ青い花を見ることがない。
そうかと思うと、百日紅の花が例年よりも早く咲いたようである。桔梗の花の咲くのは、逆に去年よりも遅かった。
どうも天候の不順ということが、身の周りの咲く花にも、いろんな形で影響しているようである。
雨の日がつづいて、それから急に暑くなったので、写真をとりに外に出かけるということがない。掲載の写真は、撮りおきのストックからである。
Nikon D500
TAMRON SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD
2020年8月4日記
『源氏物語』(14)早蕨・宿木 ― 2020-08-06
2020-08-06 當山日出夫(とうやまひでお)
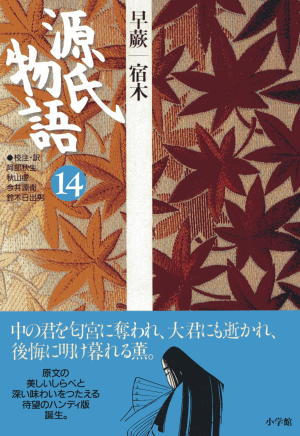
阿部秋生・秋山虔・今井源衛・鈴木日出男(校注・訳).『源氏物語』(14)早蕨・宿木.1998
続きである。
やまもも書斎記 2020年8月4日
『源氏物語』(13)椎本・総角
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/08/04/9275173
第一四冊目である。「早蕨」「宿木」をおさめる。
「宇治十帖」になって、やはり筆致が変わってきていると感じる。
第一に、心理描写が非常に屈折してきている。これまでの本編、特に、「紫の上」系の巻では、心理描写がストレートであった。しかし、ここにきて、そう多くはない登場人物……中の君、宮、薫……主にこの三人の、こころのうちを微細に描いている。そして、それは、時としてすれ違う心理でもある。
第二に、落ちぶれた高貴な姫君が、地位のある男性に見初められて幸せを得る……これは、たとえば、「末摘花」の話しでもあるかもしれない……それが、視点を、男性の側にではなく、女性の側において描いている。特に中の君の心中は複雑である。匂宮に見出されて京につれてこられたとはいうものの、正妻という地位ではない。そうこうしているうちに、匂宮は夕霧の娘の六の君と結婚してしまうことになる。だが、ともかくも子どもができるということで、何とか地位を保っているというところであろうか。
以上の二点が、「宇治十帖」をここまで読んで感じるところである。
やはり、これは、『源氏物語』の本編を書いた作者でなければ書くことができない、人間の心理描写であると思う。光源氏の物語が、男性に視点をおいた色好みの物語であったとして、「宇治十帖」になると、それを、女性の視点を介して、しかも、複数の男性のおもわくをもふくんで、心理劇のドラマとして物語が進行する。
それから、「宿木」の終わりで、浮舟が登場するのだが、これも、ある意味では、長谷寺の霊験譚をなぞっていいるのだろう。また、その浮舟を、薫がかいま見るシーンは、印象的である。
続けて、読むことにする。浮舟がこれからどうなるか、である。
2020年7月2日記
やまもも書斎記 2020年8月4日
『源氏物語』(13)椎本・総角
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/08/04/9275173
第一四冊目である。「早蕨」「宿木」をおさめる。
「宇治十帖」になって、やはり筆致が変わってきていると感じる。
第一に、心理描写が非常に屈折してきている。これまでの本編、特に、「紫の上」系の巻では、心理描写がストレートであった。しかし、ここにきて、そう多くはない登場人物……中の君、宮、薫……主にこの三人の、こころのうちを微細に描いている。そして、それは、時としてすれ違う心理でもある。
第二に、落ちぶれた高貴な姫君が、地位のある男性に見初められて幸せを得る……これは、たとえば、「末摘花」の話しでもあるかもしれない……それが、視点を、男性の側にではなく、女性の側において描いている。特に中の君の心中は複雑である。匂宮に見出されて京につれてこられたとはいうものの、正妻という地位ではない。そうこうしているうちに、匂宮は夕霧の娘の六の君と結婚してしまうことになる。だが、ともかくも子どもができるということで、何とか地位を保っているというところであろうか。
以上の二点が、「宇治十帖」をここまで読んで感じるところである。
やはり、これは、『源氏物語』の本編を書いた作者でなければ書くことができない、人間の心理描写であると思う。光源氏の物語が、男性に視点をおいた色好みの物語であったとして、「宇治十帖」になると、それを、女性の視点を介して、しかも、複数の男性のおもわくをもふくんで、心理劇のドラマとして物語が進行する。
それから、「宿木」の終わりで、浮舟が登場するのだが、これも、ある意味では、長谷寺の霊験譚をなぞっていいるのだろう。また、その浮舟を、薫がかいま見るシーンは、印象的である。
続けて、読むことにする。浮舟がこれからどうなるか、である。
2020年7月2日記
追記 2020-08-07
この続きは、
やまもも書斎記 2020年8月7日
『源氏物語』(15)東屋・浮舟
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/08/07/9276160
この続きは、
やまもも書斎記 2020年8月7日
『源氏物語』(15)東屋・浮舟
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/08/07/9276160
『源氏物語』(15)東屋・浮舟 ― 2020-08-07
2020-08-07 當山日出夫(とうやまひでお)
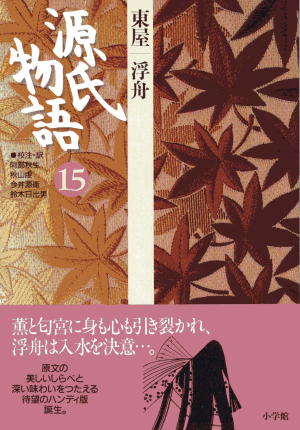
阿部秋生・秋山虔・今井源衛・鈴木日出男(校注・訳).『源氏物語』(15)東屋・浮舟.1998
続きである。
やまもも書斎記 2020年8月6日
『源氏物語』(14)早蕨・宿木
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/08/06/9275816
第一五冊目である。「東屋」「浮舟」をおさめる。
こんなことは、『源氏物語』「宇治十帖」について常識的なことだと思うが、やはり読んでみて強く感じるのは、次の二点。
第一には、継子の物語であること。
王朝の昔、継子の物語が多く愛好されたことは知られていることであろう。その目でみるならば、ヒロインの浮舟は、継子である。それが、貴公子に見初められて……という、分かりやすいストーリーの大筋が用意されている。
第二は、二人の男に愛される女。
これは継子同様、日本文学における重要なテーマの一つである。この物語の場合は、浮舟をめぐって、薫と匂宮があらそう形になる。
以上の二つの大きな骨格のもとに、中の君を配して、主に四人の登場人物……薫、匂宮、浮舟、中の君……の、たがいの心理のうちを描いていく。それは、必ずしも、相手の気持ちに深く共感するというものではなく、むしろ、反目であったり、すれちがいであったりする。その心理描写が、実にリアルである。このリアルな心理描写が、「宇治十帖」の魅力であると強く感じる。
さて、残りはあと一冊である。続けて読んでしまうことにしよう。
2020年7月3日記
追記 2020-08-10
この続きは、
やまもも書斎記 2020年8月10日
『源氏物語』(16)蜻蛉・手習・夢浮橋
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/08/10/9277129
この続きは、
やまもも書斎記 2020年8月10日
『源氏物語』(16)蜻蛉・手習・夢浮橋
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/08/10/9277129
『エール』あれこれ「夢の新婚生活」(再放送) ― 2020-08-08
2020-08-08 當山日出夫(とうやまひでお)
『エール』第7週「夢の新婚生活」
https://www.nhk.or.jp/yell/story/week_07.html
本放送のときのことは、
やまもも書斎記 2020年5月17日
『エール』あれこれ「夢の新婚生活」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/05/17/9247572
前回は、
やまもも書斎記 2020年8月2日
『エール』あれこれ「ふたりの決意」(再放送)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/08/02/9274498
再放送を見ての印象は、最初の放送のときと基本的にかわらない。裕一の音のバカップルと、裕一のダメさ、しかし、それをささえる妻の音……ここのあたりは、うまく作ってあると感じるところである。
再放送ということで見ていると、脇役の、木枯とか、久志とか、さらには、千鶴子というメンバーが、実に充実していると感じるところがあった。そして、みんな歌が巧い。歌の巧い役者を選んできたというよりも、むしろ、本職の歌手のなかからドラマの演技もできる人を選んできた、というところだろう。このドラマの魅力は、随所におりこまれている、歌のシーンにあると言ってもいいかもしれない。
それから、この週の解説(副音声)は、喫茶バンブーの楫取保だった。裕一と音の味方として、応援する視点からの語りがよかったと思う。また、喫茶バンブーは、ドラマの展開のうえでも、重要なアクセントになっているところがある。
とにかく、裕一はレコード会社との契約も無事に延長できたようだし、音も「椿姫」の一次選考にはとおった。次週、「紺碧の空」となる。これからの再放送も楽しみに見ることにしよう。
2020年8月7日記
『エール』第7週「夢の新婚生活」
https://www.nhk.or.jp/yell/story/week_07.html
本放送のときのことは、
やまもも書斎記 2020年5月17日
『エール』あれこれ「夢の新婚生活」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/05/17/9247572
前回は、
やまもも書斎記 2020年8月2日
『エール』あれこれ「ふたりの決意」(再放送)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/08/02/9274498
再放送を見ての印象は、最初の放送のときと基本的にかわらない。裕一の音のバカップルと、裕一のダメさ、しかし、それをささえる妻の音……ここのあたりは、うまく作ってあると感じるところである。
再放送ということで見ていると、脇役の、木枯とか、久志とか、さらには、千鶴子というメンバーが、実に充実していると感じるところがあった。そして、みんな歌が巧い。歌の巧い役者を選んできたというよりも、むしろ、本職の歌手のなかからドラマの演技もできる人を選んできた、というところだろう。このドラマの魅力は、随所におりこまれている、歌のシーンにあると言ってもいいかもしれない。
それから、この週の解説(副音声)は、喫茶バンブーの楫取保だった。裕一と音の味方として、応援する視点からの語りがよかったと思う。また、喫茶バンブーは、ドラマの展開のうえでも、重要なアクセントになっているところがある。
とにかく、裕一はレコード会社との契約も無事に延長できたようだし、音も「椿姫」の一次選考にはとおった。次週、「紺碧の空」となる。これからの再放送も楽しみに見ることにしよう。
2020年8月7日記
追記 2020-08-14
この続きは、
やまもも書斎記 2020年8月14日
『エール』あれこれ「紺碧の空」(再放送)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/08/14/9278391
この続きは、
やまもも書斎記 2020年8月14日
『エール』あれこれ「紺碧の空」(再放送)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/08/14/9278391
オンライン授業あれこれ(その一五) ― 2020-08-09
2020-08-09 當山日出夫(とうやまひでお)
続きである。
やまもも書斎記 2020年8月1日
オンライン授業あれこれ(その一四)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/08/01/9274131
前期の授業は終わった。次週、最後のレポートの締め切り日。それを待って、評価・採点ということになる。
第四回目のレポートを提出してくる学生がいるのだが、さかのぼって過去のものを提出してきたりする。しかし、これを受け取ることはできない。
第一に、締切の期限を過ぎている。期限厳守というのは、基本的ルールである。
第二に、すでにレポートの講評という形で、何を書けばいいか正解を示してある。これを見ることができる状態で、レポートを受け取ることはできない。
ところで、やはり気になるのが、後期からのこと。COVID-19の感染の段階の基準が公表されたのだが、これにてらすと、どう考えても、京都や大阪は安心していられない。最悪の場合は、後期の授業もオンラインでということになりうる。どうやら今の情勢では、そうなりそうな公算が高いと言わざるをえない。
しかしながら、大学生のインターネット通信環境が劇的に改善されたという話しを聞かない。各自が、自分のコンピュータを持ち、光回線などで、インターネットにつながっているようになったということが達成できているのならいいのだが、そのような情報は入ってこない。
もし、仮に、後期から通常の授業ができるようになったとしても、大学生としての勉強にコンピュータとインターネットは必需品である。その認識を持っていてくれるだろうか。このあたりの情報がはいってこないのが、なんとももどかしいのだが……つまりは、コンピュータが使える学生はオンライン授業についてくることができた、しかし、そうではない学生は脱落していってしまった、ということなのかもしれない。学生にアンケートをとるとしても、そもそも、インターネットにつながっていないと、アンケートに回答すること、いやそれ以前にアンケートを見ることすらできないのが、実際のところである。
LMSを確認してみると、オンライン授業の方針を説明したメッセージを学生に送信したのが、4月16日である。このメッセージを、いまだに見ていない学生が少なからず存在する。つまりは、まったく、インターネットにアクセスできていないとしかいいようがない。このシステムは、スマホでも見ることができるのだが、スマホも持っていないか、あるいは、それを使って大学のホームページにアクセスしてみようという気がないか、ということなのだろう。
これは、もうどうしようもないとしかいいようがいない。
ともあれ、後期どうなるか、九月になってからの判断を待つしかない。
2020年8月8日記
続きである。
やまもも書斎記 2020年8月1日
オンライン授業あれこれ(その一四)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/08/01/9274131
前期の授業は終わった。次週、最後のレポートの締め切り日。それを待って、評価・採点ということになる。
第四回目のレポートを提出してくる学生がいるのだが、さかのぼって過去のものを提出してきたりする。しかし、これを受け取ることはできない。
第一に、締切の期限を過ぎている。期限厳守というのは、基本的ルールである。
第二に、すでにレポートの講評という形で、何を書けばいいか正解を示してある。これを見ることができる状態で、レポートを受け取ることはできない。
ところで、やはり気になるのが、後期からのこと。COVID-19の感染の段階の基準が公表されたのだが、これにてらすと、どう考えても、京都や大阪は安心していられない。最悪の場合は、後期の授業もオンラインでということになりうる。どうやら今の情勢では、そうなりそうな公算が高いと言わざるをえない。
しかしながら、大学生のインターネット通信環境が劇的に改善されたという話しを聞かない。各自が、自分のコンピュータを持ち、光回線などで、インターネットにつながっているようになったということが達成できているのならいいのだが、そのような情報は入ってこない。
もし、仮に、後期から通常の授業ができるようになったとしても、大学生としての勉強にコンピュータとインターネットは必需品である。その認識を持っていてくれるだろうか。このあたりの情報がはいってこないのが、なんとももどかしいのだが……つまりは、コンピュータが使える学生はオンライン授業についてくることができた、しかし、そうではない学生は脱落していってしまった、ということなのかもしれない。学生にアンケートをとるとしても、そもそも、インターネットにつながっていないと、アンケートに回答すること、いやそれ以前にアンケートを見ることすらできないのが、実際のところである。
LMSを確認してみると、オンライン授業の方針を説明したメッセージを学生に送信したのが、4月16日である。このメッセージを、いまだに見ていない学生が少なからず存在する。つまりは、まったく、インターネットにアクセスできていないとしかいいようがない。このシステムは、スマホでも見ることができるのだが、スマホも持っていないか、あるいは、それを使って大学のホームページにアクセスしてみようという気がないか、ということなのだろう。
これは、もうどうしようもないとしかいいようがいない。
ともあれ、後期どうなるか、九月になってからの判断を待つしかない。
2020年8月8日記
追記 2020-08-16
この続きは、
やまもも書斎記 2020年8月16日
オンライン授業あれこれ(その一六)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/08/16/9279025
この続きは、
やまもも書斎記 2020年8月16日
オンライン授業あれこれ(その一六)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/08/16/9279025
『源氏物語』(16)蜻蛉・手習・夢浮橋 ― 2020-08-10
2020-08-10 當山日出夫(とうやまひでお)
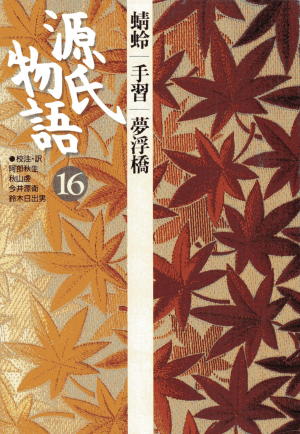
阿部秋生・秋山虔・今井源衛・鈴木日出男(校注・訳).『源氏物語』(16)蜻蛉・手習・夢浮橋.1998
https://www.shogakukan.co.jp/books/09362096
続きである。
やまもも書斎記 2020年8月7日
『源氏物語』(15)東屋・浮舟
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/08/07/9276160
第一六冊目である。「蜻蛉」「手習」「夢浮橋」をおさめる。
ようやく『源氏物語』の小学館版を読み終えた。やはり、現代では、このテクストが、最も一般的な本だと思う。あるいは、新しい岩波文庫版(現時点ではまだ完結していないが)……これも、新しい標準的なテクストになり得るだろう。
ともあれ、『源氏物語』を読むときは、菅原孝標女になったような気分で、ただひたすらに読むことにしている。他の本には基本的に手をださなかった。だいたい、一冊を一日の割合で読むことができただろうか。
これまでに、新潮日本古典集成版でも読んでいるし、岩波文庫版(既刊分)についても、読んでいる。小学館版は、新編日本古典文学全集と同一内容で、読みやすく組版してある、古典セレクション版で読むことにした。
読み終わって感じることなど書いてみる。二点ほどある。
第一に、たぶん、『源氏物語』の作者としては、「宇治十帖」は、本編と同一人物……紫式部……なのだろうという、印象である。最初から読んできた印象としては、あくまでも印象であるが、紫の上系の物語と、玉鬘系の物語は、異なる。それが、「若菜」(上・下)で、融合することになるのだが、このあたりから、作者の筆致が変わってくる。「色好み」の物語から、近代的な意味合いでいう心理小説とでもいうべき方向に、変わってくる。それを強く感じるのは、「夕霧」からである。
光源氏の死を経て、次に、薫……光源氏からすれば不義の子ということになるが……を主人公とした物語を構想したのであろう。そして、そこで考えられたのが、落ちぶれた高貴な娘にいいよる、二人の貴公子という設定。「宇治十帖」の大君の死までは、大君、中の君、それから、薫、匂宮の、心理ドラマである。
第二に、「宇治十帖」の後半になって、浮舟を登場させることによって、二人の男性から言い寄られた女性のその後を描いてみせた。ただの物語ではなく、非常に深い心理ドラマとして。
たぶん、浮舟という女性の造形は、『源氏物語』本編では描けなかったものである。なかでも、仏教への深い傾倒、この世のこと、特に男性との関係を厭うこころのうち、そして、それを理解できないでいる、薫と匂宮。また、薫と匂宮とでは、女性に対する感じ方もちがっている。
以上の二点を思ってみる。
おそらく、『源氏物語』研究の分野では、とっくに常識的に言われていることなのだろうと思う。が、ここは、余生の読書である。ただ、楽しみのためにと思って読んでいる。
そうはいっても、王朝貴族の文学の世界において、『源氏物語』と『今昔物語集』は、意外と近いところにあるのだろうという気もする。特に、宇治川に身投げした浮舟が発見されるあたりの経緯は、実に説話的といってよい。しかし、その一方で、無事に生きのびることになった浮舟のこころのうちの心理の綾とでもいうべきものは、『源氏物語』の作者の、独擅場であろう。
COVID-19の影響いかんによっては、後期の大学の授業もどうなるかわからない。時間がとれるようなら、再度、『源氏物語』を読むことで時間をつかってみたい。
2020年7月4日記
https://www.shogakukan.co.jp/books/09362096
続きである。
やまもも書斎記 2020年8月7日
『源氏物語』(15)東屋・浮舟
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/08/07/9276160
第一六冊目である。「蜻蛉」「手習」「夢浮橋」をおさめる。
ようやく『源氏物語』の小学館版を読み終えた。やはり、現代では、このテクストが、最も一般的な本だと思う。あるいは、新しい岩波文庫版(現時点ではまだ完結していないが)……これも、新しい標準的なテクストになり得るだろう。
ともあれ、『源氏物語』を読むときは、菅原孝標女になったような気分で、ただひたすらに読むことにしている。他の本には基本的に手をださなかった。だいたい、一冊を一日の割合で読むことができただろうか。
これまでに、新潮日本古典集成版でも読んでいるし、岩波文庫版(既刊分)についても、読んでいる。小学館版は、新編日本古典文学全集と同一内容で、読みやすく組版してある、古典セレクション版で読むことにした。
読み終わって感じることなど書いてみる。二点ほどある。
第一に、たぶん、『源氏物語』の作者としては、「宇治十帖」は、本編と同一人物……紫式部……なのだろうという、印象である。最初から読んできた印象としては、あくまでも印象であるが、紫の上系の物語と、玉鬘系の物語は、異なる。それが、「若菜」(上・下)で、融合することになるのだが、このあたりから、作者の筆致が変わってくる。「色好み」の物語から、近代的な意味合いでいう心理小説とでもいうべき方向に、変わってくる。それを強く感じるのは、「夕霧」からである。
光源氏の死を経て、次に、薫……光源氏からすれば不義の子ということになるが……を主人公とした物語を構想したのであろう。そして、そこで考えられたのが、落ちぶれた高貴な娘にいいよる、二人の貴公子という設定。「宇治十帖」の大君の死までは、大君、中の君、それから、薫、匂宮の、心理ドラマである。
第二に、「宇治十帖」の後半になって、浮舟を登場させることによって、二人の男性から言い寄られた女性のその後を描いてみせた。ただの物語ではなく、非常に深い心理ドラマとして。
たぶん、浮舟という女性の造形は、『源氏物語』本編では描けなかったものである。なかでも、仏教への深い傾倒、この世のこと、特に男性との関係を厭うこころのうち、そして、それを理解できないでいる、薫と匂宮。また、薫と匂宮とでは、女性に対する感じ方もちがっている。
以上の二点を思ってみる。
おそらく、『源氏物語』研究の分野では、とっくに常識的に言われていることなのだろうと思う。が、ここは、余生の読書である。ただ、楽しみのためにと思って読んでいる。
そうはいっても、王朝貴族の文学の世界において、『源氏物語』と『今昔物語集』は、意外と近いところにあるのだろうという気もする。特に、宇治川に身投げした浮舟が発見されるあたりの経緯は、実に説話的といってよい。しかし、その一方で、無事に生きのびることになった浮舟のこころのうちの心理の綾とでもいうべきものは、『源氏物語』の作者の、独擅場であろう。
COVID-19の影響いかんによっては、後期の大学の授業もどうなるかわからない。時間がとれるようなら、再度、『源氏物語』を読むことで時間をつかってみたい。
2020年7月4日記





最近のコメント