『「宣長問題」とは何か』子安宣邦 ― 2018-10-06
2018-10-06 當山日出夫(とうやまひでお)

子安宣邦.『「宣長問題」とは何か』(ちくま学芸文庫).筑摩書房.2000 (青土社.1995)
http://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480086143/
本居宣長についての本を読んでいる。
前回は、
やまもも書斎記
『本居宣長』芳賀登
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/10/01/8967240
『「宣長問題」とは何か』は、以前に買ってしまってあった本である。買った時に、ざっと目をとおしたかと思うのだが、今回、改めて読み直してみることにした。
著者(子安宣邦)の言う「宣長問題」とは、次のようなものである。
「私がいま宣長を再浮上させ、いま問わなければならぬ「宣長問題」をこのように問題構成し、このように論じようとするのは、私たちの「日本」についてのする言及が、「日本」という内部を再構成し、「日本人」であることをたえず再生産するような言説となることから免れるためである。」(p.15)
そして、つづけて次のようにある、
「国語学が宣長と「やまとことば」の神話を共有しながら、〈国家語=国語〉をたえず再生産する近代の学術的言説であった(以下略)」(p.15)
このことについては、私としても特に異論があるということではない。いや、国語学、日本語学という学問の片隅で仕事をしてきた人間のひとりとして、このようなことには、自覚的であったつもりでいる。(そのうえで、あえて、自分の勉強してきたことを、国語学と言いたい気持ちでいるのだが。)
近代の国語学、日本語学、特にその歴史的研究という分野においては、基本的に宣長の国学の流れをうけつぎながら、その神道論だけは排除してきた歴史……端的にいえば、このようにいえるかもしれない。このような歴史を概観しながらも、であるなば、なおのこと、その学問の出自ということについて、考えてみなければならないと思う。
ところで、この本を読んで、納得のいったことの一つが契沖の評価。
「こうして契沖が再発見され、彼による国学の学問的な〈始まり〉の意義が、国学的道統の〈初祖〉荷田春満に代って強調されることになるのである。」(p.124)
今日から振り返ってみたとき、宣長の師匠は、賀茂真淵であり、さらに、その文献学的方法論の淵源をたどれば、契沖にたどりつく。荷田春満からはじまる国学の流れは、近代になってから、平田篤胤の門流によってひろめられた。(そういえば、私が、高校生のころ勉強した日本史の知識では、国学の「四大人」として、荷田春満からおぼえたのを、思い出す。)
ともあれ、今のわれわれにとって、『古事記』が「古典」であり、それを読み解くには、古代日本語……「やまとことば」といってもいいかもしれない……の研究と密接に関連している、このことはたしかである。だが、これも、ある意味では、本居宣長からの学問の継承のうえにのっているにすぎないとも言えるかもしれない。このところに、私としては、自覚的でありたいと思っている。
この本は、「宣長問題」に答えを出しているという本ではない。そうではなく、今の日本において、日本を語ろうとするとき、日本の古典を、あるいは、日本語について語ろうとするとき、本居宣長という存在を避けてとおることはできない、このことのもつ意味を再確認させてくれる本である。
http://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480086143/
本居宣長についての本を読んでいる。
前回は、
やまもも書斎記
『本居宣長』芳賀登
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/10/01/8967240
『「宣長問題」とは何か』は、以前に買ってしまってあった本である。買った時に、ざっと目をとおしたかと思うのだが、今回、改めて読み直してみることにした。
著者(子安宣邦)の言う「宣長問題」とは、次のようなものである。
「私がいま宣長を再浮上させ、いま問わなければならぬ「宣長問題」をこのように問題構成し、このように論じようとするのは、私たちの「日本」についてのする言及が、「日本」という内部を再構成し、「日本人」であることをたえず再生産するような言説となることから免れるためである。」(p.15)
そして、つづけて次のようにある、
「国語学が宣長と「やまとことば」の神話を共有しながら、〈国家語=国語〉をたえず再生産する近代の学術的言説であった(以下略)」(p.15)
このことについては、私としても特に異論があるということではない。いや、国語学、日本語学という学問の片隅で仕事をしてきた人間のひとりとして、このようなことには、自覚的であったつもりでいる。(そのうえで、あえて、自分の勉強してきたことを、国語学と言いたい気持ちでいるのだが。)
近代の国語学、日本語学、特にその歴史的研究という分野においては、基本的に宣長の国学の流れをうけつぎながら、その神道論だけは排除してきた歴史……端的にいえば、このようにいえるかもしれない。このような歴史を概観しながらも、であるなば、なおのこと、その学問の出自ということについて、考えてみなければならないと思う。
ところで、この本を読んで、納得のいったことの一つが契沖の評価。
「こうして契沖が再発見され、彼による国学の学問的な〈始まり〉の意義が、国学的道統の〈初祖〉荷田春満に代って強調されることになるのである。」(p.124)
今日から振り返ってみたとき、宣長の師匠は、賀茂真淵であり、さらに、その文献学的方法論の淵源をたどれば、契沖にたどりつく。荷田春満からはじまる国学の流れは、近代になってから、平田篤胤の門流によってひろめられた。(そういえば、私が、高校生のころ勉強した日本史の知識では、国学の「四大人」として、荷田春満からおぼえたのを、思い出す。)
ともあれ、今のわれわれにとって、『古事記』が「古典」であり、それを読み解くには、古代日本語……「やまとことば」といってもいいかもしれない……の研究と密接に関連している、このことはたしかである。だが、これも、ある意味では、本居宣長からの学問の継承のうえにのっているにすぎないとも言えるかもしれない。このところに、私としては、自覚的でありたいと思っている。
この本は、「宣長問題」に答えを出しているという本ではない。そうではなく、今の日本において、日本を語ろうとするとき、日本の古典を、あるいは、日本語について語ろうとするとき、本居宣長という存在を避けてとおることはできない、このことのもつ意味を再確認させてくれる本である。
『本居宣長』芳賀登 ― 2018-10-01
2018-10-01 當山日出夫(とうやまひでお)
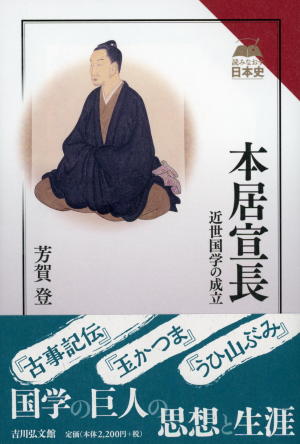
かなり以前に出た本の再刊である。これも「本居宣長」のタイトルで刊行されたもの。
なぜ、私が、今になって「本居宣長」を読んでいるかというと……近代になってからの国文学、国語学という研究分野の成立に、本居宣長が深く関与しているということを、確認したいためである。あるいは、逆説的にいえば、今、本居宣長を論じる、その方法論が、まさにかつて本居宣長が、『源氏物語』を読み、『古事記』を読んだ、その方法論によっている、このことの確認でもある。それほどまでに、国文学、国語学、さらには、現代の日本文学、日本語学の研究領域において、本居宣長の影響は及んでいると感じる。
さて、この芳賀登の『本居宣長』であるが、これは、歴史学者が書いた本居宣長の評伝であり、近世における国学という学問の成立過程を論じてある。
付箋をつけた箇所を引用しておく。
「文献学はその意味で幽玄不可思議な神道の存在を前提に考えられたのである。」(p.51)
「ただ今日、宣長学の本質を古道学に求めるか、それとも主情主義文芸に求めるかという形で問題をたてる人がいるが、これは両者がはじめから統一するもののない双曲線として位置づけるものであるだけに、かかる見解をとることはできない。」(p.54)
この本は、上述の引用のように、かなり割り切った考え方で本居宣長の学問をみている。
とはいえ、今日、二一世紀の現代において、本居宣長を論じようとするならば、その神道論と、文献実証主義の方法論と、さらには、「もののあはれ」の文芸論、これらを、総合的にとらえるには、どうすればよいか、ということになる。あるいは、今日の学問において、これらのうち、何を継承していて、何を継承していないか……無論、神道論を継承していないことになるのだが……ここのところにふみこんで考えることが必要になる。少なくとも、国文学、国語学という研究分野のことについて考えて見るならば、このような自覚的反省の視点が必要になってくるだろう。
さらに、本居宣長についての本、そして、本居宣長の書いたものを、読んでいきたいと思っている。
なぜ、私が、今になって「本居宣長」を読んでいるかというと……近代になってからの国文学、国語学という研究分野の成立に、本居宣長が深く関与しているということを、確認したいためである。あるいは、逆説的にいえば、今、本居宣長を論じる、その方法論が、まさにかつて本居宣長が、『源氏物語』を読み、『古事記』を読んだ、その方法論によっている、このことの確認でもある。それほどまでに、国文学、国語学、さらには、現代の日本文学、日本語学の研究領域において、本居宣長の影響は及んでいると感じる。
さて、この芳賀登の『本居宣長』であるが、これは、歴史学者が書いた本居宣長の評伝であり、近世における国学という学問の成立過程を論じてある。
付箋をつけた箇所を引用しておく。
「文献学はその意味で幽玄不可思議な神道の存在を前提に考えられたのである。」(p.51)
「ただ今日、宣長学の本質を古道学に求めるか、それとも主情主義文芸に求めるかという形で問題をたてる人がいるが、これは両者がはじめから統一するもののない双曲線として位置づけるものであるだけに、かかる見解をとることはできない。」(p.54)
この本は、上述の引用のように、かなり割り切った考え方で本居宣長の学問をみている。
とはいえ、今日、二一世紀の現代において、本居宣長を論じようとするならば、その神道論と、文献実証主義の方法論と、さらには、「もののあはれ」の文芸論、これらを、総合的にとらえるには、どうすればよいか、ということになる。あるいは、今日の学問において、これらのうち、何を継承していて、何を継承していないか……無論、神道論を継承していないことになるのだが……ここのところにふみこんで考えることが必要になる。少なくとも、国文学、国語学という研究分野のことについて考えて見るならば、このような自覚的反省の視点が必要になってくるだろう。
さらに、本居宣長についての本、そして、本居宣長の書いたものを、読んでいきたいと思っている。
『本居宣長』熊野純彦(内篇) ― 2018-09-29
2018-09-29 當山日出夫(とうやまひでお)

熊野純彦.『本居宣長』.作品社.2018
http://www.sakuhinsha.com/philosophy/27051.html
続きである。
やまもも書斎記 2018年9月22日
『本居宣長』熊野純彦(外篇)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/09/28/8965901
この本の後半、内篇になって、著者(熊野純彦)は、本居宣長の内側へとはいっていく。その著作を読み解きながら、その思考のあとをたどろうとしている。このとき、先行する本居宣長研究も膨大なものになる。この本の巻末には、そのリストが掲載になっている。
もちろん、本居宣長の著作も膨大な量になる。そして、それを論じようとするならば、『万葉集』『古今和歌集』『新古今和歌集』をはじめとして、古代から中世、あるいは、近世までの和歌の歴史に通暁しておく必要があるだろう。無論、『源氏物語』は必読である。そして、『古事記』と『古事記伝』がある。(おそらく、『古事記伝』を全巻にわたって精読したという仕事をした人は、ほとんどいないと言っていいかもしれない。近年のものとしては、神野志隆光の『本居宣長『古事記伝』を読む』全四巻がある。この本のことについては、追ってふれることにしたいと思っている。)
本居宣長の著作……『石上私淑言』『紫文要領』それから、『古事記伝』などについては、ひととおり知っておく必要がある。『玉かつま』も読むべきである。とにかく、本居宣長を論じるということは、大変な仕事であることは、国語学という学問の片隅で仕事をしてきた人間としては、実感する。
この意味で読んでみて、この本、熊野純彦の『本居宣長』は、そのあつかっているテキスト、資料の範囲についていえば、きちんと読み込んである、そのような印象をうける。
この内篇で、著者(熊野純彦)が描き出している本居宣長のイメージは、非常に平明で理性的である。古代の神道信仰について言及するときでも、本居宣長としては、それなりの理性的判断で、そう信じて、そう語っている、というように理解される。
内篇においても、一般の本居宣長の論をふまえて、まず、「もののあはれ」にふれる。それから、『古事記伝』における古代の信仰世界にはいっていく。ここのながれは、あくまでも、本居宣長の著作に即しながら、また、『源氏物語』などに言及しつつ、きわめて冷静な筆致で、その思想のあとをたどっている。これは、古代の神道においても、同様である。
が、読み進めていくと、最後の方にきて、『古事記伝』から踏み込んで『古事記』を読んでいく、というようになってくる。古代文学としての『古事記』の叙述そのものにふれるところが多くなってくる。ここは、やはり、『古事記伝』を読みながら『古事記』そのものの世界に入り込んでいるということになるのであろう。
きわめて、合理的で(今日の目からみれば、そうではないところもあるかもしれないが)、明晰な、本居宣長のイメージが、この本では展開される。そして、その一方で、文献の解読にのめり込んでいく研究者としての本居宣長の心情にふれるにいたる。ここは、人文学にかかわる研究者として、共感できるものとしての、本居宣長ということになる。たぶん、この『本居宣長』を読んで、今日の読者が感じるものとしては、研究者としての熊野純彦が、本居宣長に共感し、共鳴していく部分においてであろう。そして、それは、きわめて理性的に読めるものとして叙述されている。
だが、最後にきて、研究者の情念とでもいうべき部分にふれることになる。『うひ山ぶみ』の一節を引用したあとで、このようにある。
「この一文から本居の静寂主義しか読みとることのできない読者がいたとすれば、その者はしょせん本居の思考と無縁なままにとどまる。一節をむすぶことばに震撼されることがないのなら、その者はおよそ宣長に典型をみる、学知のいとなみの無償な立ちようとは所縁がないままでありつづけることだろう。」(p.871)
そして、最後、この本は、本尾宣長の遺言でふいに終わっている。小林秀雄の『本居宣長』を意識してのことだと思われる。
http://www.sakuhinsha.com/philosophy/27051.html
続きである。
やまもも書斎記 2018年9月22日
『本居宣長』熊野純彦(外篇)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/09/28/8965901
この本の後半、内篇になって、著者(熊野純彦)は、本居宣長の内側へとはいっていく。その著作を読み解きながら、その思考のあとをたどろうとしている。このとき、先行する本居宣長研究も膨大なものになる。この本の巻末には、そのリストが掲載になっている。
もちろん、本居宣長の著作も膨大な量になる。そして、それを論じようとするならば、『万葉集』『古今和歌集』『新古今和歌集』をはじめとして、古代から中世、あるいは、近世までの和歌の歴史に通暁しておく必要があるだろう。無論、『源氏物語』は必読である。そして、『古事記』と『古事記伝』がある。(おそらく、『古事記伝』を全巻にわたって精読したという仕事をした人は、ほとんどいないと言っていいかもしれない。近年のものとしては、神野志隆光の『本居宣長『古事記伝』を読む』全四巻がある。この本のことについては、追ってふれることにしたいと思っている。)
本居宣長の著作……『石上私淑言』『紫文要領』それから、『古事記伝』などについては、ひととおり知っておく必要がある。『玉かつま』も読むべきである。とにかく、本居宣長を論じるということは、大変な仕事であることは、国語学という学問の片隅で仕事をしてきた人間としては、実感する。
この意味で読んでみて、この本、熊野純彦の『本居宣長』は、そのあつかっているテキスト、資料の範囲についていえば、きちんと読み込んである、そのような印象をうける。
この内篇で、著者(熊野純彦)が描き出している本居宣長のイメージは、非常に平明で理性的である。古代の神道信仰について言及するときでも、本居宣長としては、それなりの理性的判断で、そう信じて、そう語っている、というように理解される。
内篇においても、一般の本居宣長の論をふまえて、まず、「もののあはれ」にふれる。それから、『古事記伝』における古代の信仰世界にはいっていく。ここのながれは、あくまでも、本居宣長の著作に即しながら、また、『源氏物語』などに言及しつつ、きわめて冷静な筆致で、その思想のあとをたどっている。これは、古代の神道においても、同様である。
が、読み進めていくと、最後の方にきて、『古事記伝』から踏み込んで『古事記』を読んでいく、というようになってくる。古代文学としての『古事記』の叙述そのものにふれるところが多くなってくる。ここは、やはり、『古事記伝』を読みながら『古事記』そのものの世界に入り込んでいるということになるのであろう。
きわめて、合理的で(今日の目からみれば、そうではないところもあるかもしれないが)、明晰な、本居宣長のイメージが、この本では展開される。そして、その一方で、文献の解読にのめり込んでいく研究者としての本居宣長の心情にふれるにいたる。ここは、人文学にかかわる研究者として、共感できるものとしての、本居宣長ということになる。たぶん、この『本居宣長』を読んで、今日の読者が感じるものとしては、研究者としての熊野純彦が、本居宣長に共感し、共鳴していく部分においてであろう。そして、それは、きわめて理性的に読めるものとして叙述されている。
だが、最後にきて、研究者の情念とでもいうべき部分にふれることになる。『うひ山ぶみ』の一節を引用したあとで、このようにある。
「この一文から本居の静寂主義しか読みとることのできない読者がいたとすれば、その者はしょせん本居の思考と無縁なままにとどまる。一節をむすぶことばに震撼されることがないのなら、その者はおよそ宣長に典型をみる、学知のいとなみの無償な立ちようとは所縁がないままでありつづけることだろう。」(p.871)
そして、最後、この本は、本尾宣長の遺言でふいに終わっている。小林秀雄の『本居宣長』を意識してのことだと思われる。
追記 2018-10-01
『本居宣長』熊野純彦(外篇) ― 2018-09-28
2018-09-28 當山日出夫(とうやまひでお)

『本居宣長』というタイトルの本を読んでいる。これまでに読んだものは、次のとおり。
やまもも書斎記 2018年3月15日
『本居宣長』小林秀雄
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/03/15/8803701
やまもも書斎記 2018年9月3日
『本居宣長』子安宣邦
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/09/03/8955300
やまもも書斎記 2018年9月10日
『本居宣長』相良亨
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/09/10/8958519
やまもも書斎記 2018年9月14日
『本居宣長』田中康二
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/09/14/8960094
そして、熊野純彦の『本居宣長』である。
熊野純彦.『本居宣長』.作品社.2018
http://www.sakuhinsha.com/philosophy/27051.html
やまもも書斎記 2018年3月15日
『本居宣長』小林秀雄
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/03/15/8803701
やまもも書斎記 2018年9月3日
『本居宣長』子安宣邦
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/09/03/8955300
やまもも書斎記 2018年9月10日
『本居宣長』相良亨
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/09/10/8958519
やまもも書斎記 2018年9月14日
『本居宣長』田中康二
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/09/14/8960094
そして、熊野純彦の『本居宣長』である。
熊野純彦.『本居宣長』.作品社.2018
http://www.sakuhinsha.com/philosophy/27051.html
ちょっと高い本であるが、熊野純彦の、それも、最新の本居宣長の本ということで、買って読むことにした。900ページ近い大冊である。「外篇」と「内篇」にわかれている。「外篇」の方は、近代になってからの本居宣長をめぐる言説について。そして、「内篇」で、本居宣長の著作そのものについて、というだいたいの構図になっている。
まずは、前半の「外篇」からである。「近代の宣長像」とある。
読んでみての印象としては、本居宣長研究としては、よく書けている、しかし、どこかもの足りない気がしてならない。それは、本居宣長をめぐる言説としては、主に、政治思想史の面からのとりくみを中心に記述してあるせいである。
近世、江戸時代、一八世紀のころに本居宣長は活躍した。その学問の系譜は、主に、平田篤胤に継承されることになり、近代の国学を経て、今にいたる。そのなかで、大きく、二つの筋道があることになる。
第一は、平田篤胤を経て継承され、発展することになった、皇国思想の淵源としての、本居宣長である。
第二は、その国学研究の文献研究の延長にあるものとしての、近代の、国文学・国語学という研究分野である。
これらのうち、この熊野純彦野の『本居宣長』では、第一の皇国思想の、その政治思想の面に、着目して論じてある。言い換えるならば、第二の、国文学・国語学の基礎をきずいたものとしての、本居宣長の研究の側面には、ほとんどふみこむことがない。
これは、これで一つの方針ではあると思う。しかし、若いころより国語学という分野で勉強してきた私としては、いささかものたりない気がしないではない。近代になってからの国文学・国語学という研究分野の成立と発展に、どのように本居宣長が寄与しているのか、何を継承し、また、何を継承していないのか、このあたりが、どうしても関心が向くことになる。私の立場としては、やはり国語学という勉強の視点から本居宣長を読むことになる。
そうはいっても、例えば、和辻哲郎、津田左右吉などの本居宣長論について、言及してある。これらの著作は、近代の、国文学という学問と無縁ではない。時枝誠記も出てくる。たしかに、近代になってから、日本の文化史、精神史、とでもいうべき分野になにがしかかかわろうとするならば、本居宣長の仕事は、避けて通ることのできないものにちがいない。また、これまでに私が読んだ、『本居宣長』……小林秀雄からはじまって、子安宣邦、相良亨などについても、ふれてある。
だが、正直にいって、「外篇」(前半部)を読んだ限りでは、一つの本居宣長のイメージがわいてこない。それは、やはり、この外篇において、本居宣長そのものではなく、それについての言説の歴史を読み解いていくということになっているせいだろう。いろんな本居宣長のイメージが錯綜して語られることになっているので、今ひとつ、明確な印象が残らなかったというのが、まず感じるところである。
たしかに、近代になってからの本居宣長についての言説を見るだけでも、価値のあることである。日本とは何であるのか、ということを考えようとすると、どうしても、本居宣長ぐらいまではさかのぼって論じる必要がある。この「外篇」の最後のところでは、1968年、大学紛争の時代……当時の研究者にとって、本居宣長を読むということがどういう意味であったのか検証されている。このあたりのことは、興味深い。
政治思想史の面にかたよっているという傾向はあるものの、近代になってからの本居宣長の研究史、受容史とでもいうべきものを、緻密にまとまあげてある本書は、重要な意味があると思う。ただし、この著者(熊野純彦)の意図としては、研究史ということではないようである。むしろ、本居宣長がどう読まれてきたかを通じて、近代の精神史を描きたかったのであろう。
であるならば、なおのこと、近代における本居宣長の読まれ方が、「国学」から「国文学」になり、さらには、現代においては「日本文学」になっているという状況の流れのなかに位置づけるということもあってよかったのではないだろうか。
まずは、前半の「外篇」からである。「近代の宣長像」とある。
読んでみての印象としては、本居宣長研究としては、よく書けている、しかし、どこかもの足りない気がしてならない。それは、本居宣長をめぐる言説としては、主に、政治思想史の面からのとりくみを中心に記述してあるせいである。
近世、江戸時代、一八世紀のころに本居宣長は活躍した。その学問の系譜は、主に、平田篤胤に継承されることになり、近代の国学を経て、今にいたる。そのなかで、大きく、二つの筋道があることになる。
第一は、平田篤胤を経て継承され、発展することになった、皇国思想の淵源としての、本居宣長である。
第二は、その国学研究の文献研究の延長にあるものとしての、近代の、国文学・国語学という研究分野である。
これらのうち、この熊野純彦野の『本居宣長』では、第一の皇国思想の、その政治思想の面に、着目して論じてある。言い換えるならば、第二の、国文学・国語学の基礎をきずいたものとしての、本居宣長の研究の側面には、ほとんどふみこむことがない。
これは、これで一つの方針ではあると思う。しかし、若いころより国語学という分野で勉強してきた私としては、いささかものたりない気がしないではない。近代になってからの国文学・国語学という研究分野の成立と発展に、どのように本居宣長が寄与しているのか、何を継承し、また、何を継承していないのか、このあたりが、どうしても関心が向くことになる。私の立場としては、やはり国語学という勉強の視点から本居宣長を読むことになる。
そうはいっても、例えば、和辻哲郎、津田左右吉などの本居宣長論について、言及してある。これらの著作は、近代の、国文学という学問と無縁ではない。時枝誠記も出てくる。たしかに、近代になってから、日本の文化史、精神史、とでもいうべき分野になにがしかかかわろうとするならば、本居宣長の仕事は、避けて通ることのできないものにちがいない。また、これまでに私が読んだ、『本居宣長』……小林秀雄からはじまって、子安宣邦、相良亨などについても、ふれてある。
だが、正直にいって、「外篇」(前半部)を読んだ限りでは、一つの本居宣長のイメージがわいてこない。それは、やはり、この外篇において、本居宣長そのものではなく、それについての言説の歴史を読み解いていくということになっているせいだろう。いろんな本居宣長のイメージが錯綜して語られることになっているので、今ひとつ、明確な印象が残らなかったというのが、まず感じるところである。
たしかに、近代になってからの本居宣長についての言説を見るだけでも、価値のあることである。日本とは何であるのか、ということを考えようとすると、どうしても、本居宣長ぐらいまではさかのぼって論じる必要がある。この「外篇」の最後のところでは、1968年、大学紛争の時代……当時の研究者にとって、本居宣長を読むということがどういう意味であったのか検証されている。このあたりのことは、興味深い。
政治思想史の面にかたよっているという傾向はあるものの、近代になってからの本居宣長の研究史、受容史とでもいうべきものを、緻密にまとまあげてある本書は、重要な意味があると思う。ただし、この著者(熊野純彦)の意図としては、研究史ということではないようである。むしろ、本居宣長がどう読まれてきたかを通じて、近代の精神史を描きたかったのであろう。
であるならば、なおのこと、近代における本居宣長の読まれ方が、「国学」から「国文学」になり、さらには、現代においては「日本文学」になっているという状況の流れのなかに位置づけるということもあってよかったのではないだろうか。
追記 2018-09-29
この続きは、
やまもも書斎記 2018年9月29日
『本居宣長』熊野純彦(内篇)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/09/29/8966263
この続きは、
やまもも書斎記 2018年9月29日
『本居宣長』熊野純彦(内篇)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/09/29/8966263
『本居宣長』田中康二 ― 2018-09-14
2018-09-14 當山日出夫(とうやまひでお)

やまもも書斎記 2018年3月15日
『本居宣長』小林秀雄
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/03/15/8803701
やまもも書斎記 2018年9月3日
『本居宣長』子安宣邦
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/09/03/8955300
やまもも書斎記 2018年9月10日
『本居宣長』相良亨
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/09/10/8958519
『本居宣長』小林秀雄
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/03/15/8803701
やまもも書斎記 2018年9月3日
『本居宣長』子安宣邦
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/09/03/8955300
やまもも書斎記 2018年9月10日
『本居宣長』相良亨
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/09/10/8958519
『本居宣長』のタイトルの本を順次読んでいっている。この本も、『本居宣長』である。中公新書で、比較的最近に出た本。
著者は、近世文学の研究者であるので、非常に整理された形で、本居宣長の人生と仕事がまとめてある。
各章は、基本的に次のように整理して書いてある。
二十歳代 学問の出発
三十歳代 人生の転機
四十歳代 自省の歳月
五十歳代 論争の季節
六十歳代 学問の完成
七十歳代 鈴屋の行方
この本も、若い時の京都遊学の時期からはじめて、年代をおって、その時々の宣長の仕事を手際よく紹介してある。
この本を読んで感じたことを、書き留めておくならば、次の二点になる。
第一には、宣長の文献実証主義の方法論、これを、京都遊学の時に接した契沖の学問に由来するものであるとしている。これは、確かにそのとおりなのであろうが、ただ、これが、後年の『古事記伝』の仕事の基礎として、その学問的方法論にどう結びついているのか、ここのところについては、あまり踏み込んで記述されていない。
現在、宣長の仕事を振り返ったとき、神道論には共感するところがあまりないかもしれないが、しかし、『古事記』を読んでいった文献実証主義の方法論は、確実に現代の学問に受けつがれている。テクストを読んで、何を明らかにしたいかという究極の目標となるものと、そのための方法論は、密接に関係していると思うのだが、この本では、ここは、きれいに切り離して論じてある。
第二には、「もののあはれ」の論について、この本では、「もののあはれ」ではなく、「もののあはれ」を「しる」ということの意味について触れてある。ここのところの指摘は重要であると思う。
「宣長は「物のあはれを知る」ことをめぐって、感動という心の情的側面だけでなく、理解という心の知的側面を明確に指摘した。この学説を「物のあはれ」論ではなく、「物のあはれを知る」説と呼ばなければならない理由がここにある。」(p.91)
以上、二つの点が、この本を読んで思ったところである。
さらに付け加えるならば、宣長は真淵に師事したことは言うまでもないが、歌については、『万葉』風の歌を詠むことはなく、真淵とすれちがいに終わってしまっていることなど、興味深い。宣長にとって『万葉』の歌は、どのような意味をもっていたのであろうか……『古事記伝』において資料として使うのではなく、歌集として読んでどう思っていたのか……ここのところが、この本を読んでの気になるところである。
『本居宣長』相良亨 ― 2018-09-10
2018-09-08 當山日出夫(とうやまひでお)

相良亨.『本居宣長』(講談社学術文庫).講談社.2011 (東京大学出版会.1978)
http://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000211536
本居宣長そのものを読むべきなのだが、その周辺を読んでいる。「本居宣長」のタイトルをもつ本である。この本も、タイトルは、『本居宣長』になっている。
やまもも書斎記 2018年3月15日
『本居宣長』小林秀雄
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/03/15/8803701
やまもも書斎記 2018年9月3日
『本居宣長』子安宣邦
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/09/03/8955300
読んでの印象は……これはこれで、ひとつの宣長論になっている、ということ。本書の基軸としてあるのは、〈もののあはれ〉と〈神道論〉である。
一般に、宣長について論じるときの課題となることは、この二つ……〈もののあはれ〉と〈神道論〉である。それに、それに近づくための、実証的な文献学的方法論、となるであろうか。
この本では、宣長の学問的方法論、文献実証主義について触れるとろこはない。そのかわり、若い時の〈もののあはれ〉論が、どのようにして、後年の〈神道論〉につながっていくのか、そのつながりを論じてある。
どちらかといえば、かなり理性的に宣長の思想というものが捉えられている。宣長を絶賛するでもないし、特に否定的な立場にたつわけでもない。その人生の歩み、京都遊学のころから説きおこして、〈もののあはれ〉とは何であるか、そして、それを論じることが、どのようなプロセスで、『古事記伝』に見られる、後年の〈神道論〉につながっていっているのか、順番にテキストを解読する方法で、論じてある。
先に結論を示して、なぜこのように考えることになるのか、という論じ方ではなく、順番にテキストを読んでいくことで、読み解いてあるので、読んでいって、ややまどろしくある。が、読み終わって、なるほど、〈もののあはれ〉を論じること……人間のこころの素直な状態を理想化すると言っていいだろうか……が、〈神道論〉につながっていくことが、よく理解される。
では、そのような思想の形成が、どのような学問的方法論に支えられていたのか……今日の目からは、このところが気になることであるが、この本では、そこのところには踏み込んでいない。あえてふれることを避けているかのごとくである。が、これは、これとして、一つの方針であろう。
読みながら付箋をつけた箇所を一つ引用しておくと、
「後年の彼が強調したところの、ミチなどというものもただ嘗ては道路の意のみであり、道徳、道義、天道、人道、心道、道理などという意味はなかったのだという主張も、すでにこの『石上私淑言』に現れている。道々しきものもなく、「物のあはれ」をしる人々が穏しく生きた世界、それが神代であったのである。」(p.142)
本書に言わんとするところは、ここに端的に示されている。
それから、次のような箇所、
「われわれにとってとって、したがって、問題なのは、宣長における漢意の否定という仕方における「理」の否定である。西洋近代思想の知識を輸入して、それによってこの宣長を批判することは容易であるが、単なる知識ではなく、真にわれわれの内面に、宣長的思想の洗礼あるいはわれわれの内にある宣長的発想の資質をこえて、「理」に対する把握を真に確立しえないかぎり、宣長を軽々に批判することはできないであろう。宣長にとどまることはできないが、超えることは今日においてなお容易なことではない。」(p.216)
宣長の魅力、そして、それを超えることの難しさ……これは、小林秀雄の『本居宣長』に十分に書き尽くされていることだと思う。宣長を考えることは、現代のわれわれの古代研究の方法論、それが、近代的な文献実証主義であるとしても、それを自覚的に再確認していく仕事になるはずである。この意味では、宣長の学問の方法論について、考えてみる必要がある。
残る『本居宣長』は、田中康二(中公新書)、熊野純彦、そして、村岡典嗣、である。
http://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000211536
本居宣長そのものを読むべきなのだが、その周辺を読んでいる。「本居宣長」のタイトルをもつ本である。この本も、タイトルは、『本居宣長』になっている。
やまもも書斎記 2018年3月15日
『本居宣長』小林秀雄
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/03/15/8803701
やまもも書斎記 2018年9月3日
『本居宣長』子安宣邦
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/09/03/8955300
読んでの印象は……これはこれで、ひとつの宣長論になっている、ということ。本書の基軸としてあるのは、〈もののあはれ〉と〈神道論〉である。
一般に、宣長について論じるときの課題となることは、この二つ……〈もののあはれ〉と〈神道論〉である。それに、それに近づくための、実証的な文献学的方法論、となるであろうか。
この本では、宣長の学問的方法論、文献実証主義について触れるとろこはない。そのかわり、若い時の〈もののあはれ〉論が、どのようにして、後年の〈神道論〉につながっていくのか、そのつながりを論じてある。
どちらかといえば、かなり理性的に宣長の思想というものが捉えられている。宣長を絶賛するでもないし、特に否定的な立場にたつわけでもない。その人生の歩み、京都遊学のころから説きおこして、〈もののあはれ〉とは何であるか、そして、それを論じることが、どのようなプロセスで、『古事記伝』に見られる、後年の〈神道論〉につながっていっているのか、順番にテキストを解読する方法で、論じてある。
先に結論を示して、なぜこのように考えることになるのか、という論じ方ではなく、順番にテキストを読んでいくことで、読み解いてあるので、読んでいって、ややまどろしくある。が、読み終わって、なるほど、〈もののあはれ〉を論じること……人間のこころの素直な状態を理想化すると言っていいだろうか……が、〈神道論〉につながっていくことが、よく理解される。
では、そのような思想の形成が、どのような学問的方法論に支えられていたのか……今日の目からは、このところが気になることであるが、この本では、そこのところには踏み込んでいない。あえてふれることを避けているかのごとくである。が、これは、これとして、一つの方針であろう。
読みながら付箋をつけた箇所を一つ引用しておくと、
「後年の彼が強調したところの、ミチなどというものもただ嘗ては道路の意のみであり、道徳、道義、天道、人道、心道、道理などという意味はなかったのだという主張も、すでにこの『石上私淑言』に現れている。道々しきものもなく、「物のあはれ」をしる人々が穏しく生きた世界、それが神代であったのである。」(p.142)
本書に言わんとするところは、ここに端的に示されている。
それから、次のような箇所、
「われわれにとってとって、したがって、問題なのは、宣長における漢意の否定という仕方における「理」の否定である。西洋近代思想の知識を輸入して、それによってこの宣長を批判することは容易であるが、単なる知識ではなく、真にわれわれの内面に、宣長的思想の洗礼あるいはわれわれの内にある宣長的発想の資質をこえて、「理」に対する把握を真に確立しえないかぎり、宣長を軽々に批判することはできないであろう。宣長にとどまることはできないが、超えることは今日においてなお容易なことではない。」(p.216)
宣長の魅力、そして、それを超えることの難しさ……これは、小林秀雄の『本居宣長』に十分に書き尽くされていることだと思う。宣長を考えることは、現代のわれわれの古代研究の方法論、それが、近代的な文献実証主義であるとしても、それを自覚的に再確認していく仕事になるはずである。この意味では、宣長の学問の方法論について、考えてみる必要がある。
残る『本居宣長』は、田中康二(中公新書)、熊野純彦、そして、村岡典嗣、である。
『本居宣長』子安宣邦 ― 2018-09-03
2018-09-03 當山日出夫(とうやまひでお)

子安宣邦.『本居宣長』(岩波現代文庫).岩波書店.2001(岩波書店.1992 加筆)
https://www.iwanami.co.jp/book/b255689.html
本居宣長を読みたいと思っている。私ももう還暦をとうにすぎた。これから、新規な本を読むよりも、古典を読んで時間をつかいたい。『源氏』『万葉』を、古典として読んでおきたい、そのように強く感じるようになってきている。
今日、〈古典〉を、国語学、国文学という立場から読むとすると、どうしても、国学の伝統、なかでも、本居宣長という存在を避けてとおることはできない。
今年、明治150年ということで、明治維新関係の本を読んでみようかと思い、『夜明け前』(島崎藤村)を読んだ。それから、『本居宣長』(小林秀雄)、『やちまた』(足立巻一)などを読んでみた。
やまもも書斎記 2018年2月23日
『夜明け前』(第一部)(上)島崎藤村
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/02/23/8792791
やまもも書斎記 2018年3月15日
『本居宣長』小林秀雄
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/03/15/8803701
やまもも書斎記 2018年3月19日
『やちまた』足立巻一
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/03/19/8806507
本居宣長は全集(筑摩版)は持っている。その他、思想大系とか、岩波文庫とか、いくつか本がある。本格的に本居宣長について読む前に、今、出ている本で、本居宣長について、その概要を読んでおきたいと思った。小林秀雄の本は読んだ。次に、読んでみようと手にしたのが、子安宣邦の『本居宣長』である。
何故、私は、本居宣長にひかれるのだろう。その学問の目標としたところ、いにしえの心を明らかにするということ、これについては、現代の立場からは、かなり批判的な眼で見るということになっている。学問の究極の目的については、もはや現代において共感するところはないといってよい。
だが、しかし、本居宣長という人物は魅力的である。その没後の門人であり、幕末から明治にかけて多大な影響があった、平田篤胤については、あまり読もうという気はおこらないでいる。(近年、その再評価の動きがあることは承知しているつもりでいるが。)
今の自分をかえりみて、考えることは次の二点。
第一には、その究極のところに共感できないかもしれないが、しかし、その考えたことは、たどってみたいという魅力がある。それは、いにしえの心であり、もののあわれ、である。
とはいえ、今、『古事記』を読んで、そこにいにしえの心を読みとるような読み方は、できない。現代からは、もっと批判的な読み方をすることになる。だが、その宣長の古事記の「よみ」の文献実証主義とでもいうべきものは、今日においても、継承しうるものである。
また、『源氏』などを読んで、〈もののあわれ〉を感じるように読んでみたい、という気持ちがある。無論、現代では、『源氏』のコーパスの利用というようなことも念頭においてということではあるが。
第二には、上記にもふれたことだが、私の学んできた、国語学における文献実証主義という学問的方法論は、宣長が『古事記』などを読んだ方法と、非常に親和性がよい。だからこそ、近代の国語学、国文学という学問分野が、近世の国学の延長線上に位置し得ているということがある。
文献実証主義という方法論を自覚した上で、では宣長が実際にどのように考えてきたのか、たどってみたいという気がしている。
以上の二点が、今、心にうかぶことである。
『本居宣長』(子安宣邦)は、主に『古事記伝』の方法論について論じた本である。『古事記』には古代の正しい清い心が書かれている。それは『古事記』が、古代の正しい清い心の時代に生まれた本だからである。この同語反復的な価値観のなかに、『古事記伝』という偉大な業績がなりたっている。
この本では、特に近代になってからの文献学的な国語学の成立との関係については、言及がない。しかし、今の私の立場から読解してみるならが、近代的な文献実証主義に耐えるもの、あるいは、その出発点、さらには、その到達点としての、『古事記伝』という仕事をイメージすることになる。
『古事記伝』は、自分の目で読んでおきたい本の一つとしてある。
『日本思想史の名著30』苅部直 ― 2018-07-28
2018-07-28 當山日出夫(とうやまひでお)

苅部直.『日本思想史の名著30』(ちくま新書).筑摩書房.2018
http://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480071590/
ちくま新書で、『~~の名著30』というのが、いくつか出ているが、これもその一つとみればいいだろうか。雑誌『ちくま』に連載したものをあつめた本である。
読んで感じることは、次の二点。
第一は、「日本思想史の名著」としてとりあげてある〈古典〉そのものを読む、というよりも、それが現代において、どのように読まれているかを軸にしてある点。これをつよく感じるのが、「Ⅰ」のところに収められている諸編。
『古事記』
「憲法十七条」
『日本霊異記』
『愚管抄』
『歎異抄』
『立正安国論』
『神皇正統記』
これらの書物については、原典をどう読むかというよりも、これらの本の思想史的位置づけ、あるいは、後世……特に近現代において……どのように受容されて読まれてきているか、という観点から記述してあることである。
第二は、「Ⅱ」以降の諸編において、名前ぐらいは、むかし高校の日本史の授業で教科書に出てきたことを覚えている人物について、その概略をしめしてあることである。おおむねそのように人物・著作を選んであると感じる。
たとえば、「Ⅱ」では、
山崎闇斎
新井白石
伊藤仁斎
荻生徂徠
『葉隠』
山片蟠桃
海保青陵
本居宣長
平田篤胤
などである。
これらの著作の多くは、岩波の「日本思想大系」で読むことができる。そして、その思想の概略を示すときにも、基本的には、現代の視点から考えることを忘れてはいない。それは、近年の平田篤胤の再評価などに見ることができる。
以上の二点が、読んで感じるところである。さらに加えるならば、「Ⅲ」「Ⅳ」で、
教育勅語
日本国憲法
がとりあげられていることであろうか。教育勅語については、一般にイメージされているのとは異なって、その持っていた近代的な側面を重視している。また、日本国憲法についても、必ずしも護憲派という立場で書かれてはいない。むしろ、現代においては、日本国憲法が、かつての教育勅語になっているとさえ指摘している。
新しいところでは、
丸山眞男『忠誠と反逆』
相良亨『日本人の心』
が取り上げられている。
私が、読んだ感想としては、すでに読んだことのある本であったり(『古事記』などは、昔、その本文データを自分でパソコンに入力したことがある)、歴史の教科書に名前が出てきた人物で、おおよそのことは知っているつもりでいたが、実際にその著作を、きちんと読んではいなかったり、というような事例が多くあることになる。まったく未知の人物というものは、基本的に出てきてはいない。
これから本を読む手がかりとして、この本は、恰好のブックガイドとなっている。
なお、この本では、「中国」それから「支那」の語を使っていない。「チャイナ」と言っている。このことについては、きちんと断り書きがある。これはこれで、筋の通った態度でつらぬいている。いたずらな日本礼賛にもなっていないし、また、事大的にもなっていない。
私としては、この本を読んで、「思想大系」をひもときたくなっている(これは、全巻、買って揃えてある)。また、丸山眞男とか和辻哲郎とかも、再度、読んでおきたいと思う。
http://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480071590/
ちくま新書で、『~~の名著30』というのが、いくつか出ているが、これもその一つとみればいいだろうか。雑誌『ちくま』に連載したものをあつめた本である。
読んで感じることは、次の二点。
第一は、「日本思想史の名著」としてとりあげてある〈古典〉そのものを読む、というよりも、それが現代において、どのように読まれているかを軸にしてある点。これをつよく感じるのが、「Ⅰ」のところに収められている諸編。
『古事記』
「憲法十七条」
『日本霊異記』
『愚管抄』
『歎異抄』
『立正安国論』
『神皇正統記』
これらの書物については、原典をどう読むかというよりも、これらの本の思想史的位置づけ、あるいは、後世……特に近現代において……どのように受容されて読まれてきているか、という観点から記述してあることである。
第二は、「Ⅱ」以降の諸編において、名前ぐらいは、むかし高校の日本史の授業で教科書に出てきたことを覚えている人物について、その概略をしめしてあることである。おおむねそのように人物・著作を選んであると感じる。
たとえば、「Ⅱ」では、
山崎闇斎
新井白石
伊藤仁斎
荻生徂徠
『葉隠』
山片蟠桃
海保青陵
本居宣長
平田篤胤
などである。
これらの著作の多くは、岩波の「日本思想大系」で読むことができる。そして、その思想の概略を示すときにも、基本的には、現代の視点から考えることを忘れてはいない。それは、近年の平田篤胤の再評価などに見ることができる。
以上の二点が、読んで感じるところである。さらに加えるならば、「Ⅲ」「Ⅳ」で、
教育勅語
日本国憲法
がとりあげられていることであろうか。教育勅語については、一般にイメージされているのとは異なって、その持っていた近代的な側面を重視している。また、日本国憲法についても、必ずしも護憲派という立場で書かれてはいない。むしろ、現代においては、日本国憲法が、かつての教育勅語になっているとさえ指摘している。
新しいところでは、
丸山眞男『忠誠と反逆』
相良亨『日本人の心』
が取り上げられている。
私が、読んだ感想としては、すでに読んだことのある本であったり(『古事記』などは、昔、その本文データを自分でパソコンに入力したことがある)、歴史の教科書に名前が出てきた人物で、おおよそのことは知っているつもりでいたが、実際にその著作を、きちんと読んではいなかったり、というような事例が多くあることになる。まったく未知の人物というものは、基本的に出てきてはいない。
これから本を読む手がかりとして、この本は、恰好のブックガイドとなっている。
なお、この本では、「中国」それから「支那」の語を使っていない。「チャイナ」と言っている。このことについては、きちんと断り書きがある。これはこれで、筋の通った態度でつらぬいている。いたずらな日本礼賛にもなっていないし、また、事大的にもなっていない。
私としては、この本を読んで、「思想大系」をひもときたくなっている(これは、全巻、買って揃えてある)。また、丸山眞男とか和辻哲郎とかも、再度、読んでおきたいと思う。
『仕事としての学問』マックス・ウェーバー ― 2018-07-27
2018-07-27 當山日出夫(とうやまひでお)

マックス・ウェーバー.野口雅弘(訳).『仕事としての学問 仕事としての政治』(講談社学術文庫).講談社.2018
http://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000310640
従来は『職業としての学問』のタイトルで知られているものである。その新訳。
私が『職業としての学問』(岩波文庫版)を読んだのは、いつのころだったろうか。たしか、大学生になって、日吉の教養の時のことだったように覚えている。そのころ、この本は「必読書」であった、といってよいであろうか。
新しい訳が講談社学術文庫で出たので読んでみた。タイトルが『仕事としての学問』に変えてある。また、かなり丁寧な註解がついている。その当時(ウェーバーがこの本の講演をおこなった当時)の、学問的な、社会的な背景などについて、解説してあるので、読みやすかった。
この本については、これまでにいろんなところでいろんなふうに語られてきている。特に、私が付け加えるほどのこともないにちがいない。とはいえ、自分で読んで思ったことなど書いてみるならば、次の二点になるだろうか。
第一は、学問のおかれている社会的状況である。この講演は、ドイツとアメリカの比較からはじまっている。学者、研究者は、どのようにして、そのキャリアを形成していくことになっているのか、から説きおこされている。
これは、その当時にあってのドイツとアメリカの違いとして読めばいいだろう。そして、現代において、この本を読むときには、現代日本の研究者のキャリア形成の事情とひきくらべて読むことになる。
今の日本の状況はどうか……どう考えて見ても、一世紀前のドイツとも、アメリカとも、違っている。単純に言えることではないかもしれないが、今日の日本で、研究者の道を選ぶというのは、かなりの冒険である。あるいは、無謀と言ってもいいかもしれないような側面がある。
にもかかわらず、世の中を見ていると、若い優秀な人たちが出てきていることは確かでもある。本人の努力もあるのだろうが、運の良さとでもいうしかないところも、そのどこかにはあるにちがいない。
第二は、学問の存在意義である。これは、一世紀ほど前のこの文章を読んでも、今に通じるところがあると感じる。端的に言うならば……学問は、それを研究することに価値があると、それ自体において語ることができるのだろうか、ということになる。
たとえば、次のような箇所。
「こうした事情を前提にした上で、学問は誰かにとって「使命を帯びた仕事」たる価値があるのか、そして学問はそれ自身で客観的に価値ある「使命」をもつのか。これもまた価値判断の問題であり、それについては教室ではなにも言えません。というのも、教室で教えることの〈前提〉になっているのは、この肯定だからです。」(p.77) 〈 〉傍点
このことは今も変わらないだろうと思われる。いやむしろ、現代の方が、その「価値判断」をめぐっては、より混沌とした状況にあるともいえようか。
なぜ、その学問は研究するに価するのか、それを学問自身において語ることは、容易ではない。
だが、そうであるにもかかわらず、特に大学で教えられるような研究については、なぜ、それを教える価値があるのか、そのことについて明かにすることを、強く要請されている。たとえば、人文学はいったい何の役にたつのか、教養とは何か、その説明をもとめる要求は、より強くなってきているといっていいかもしれない。
以上の二点が、何十年ぶりかに、『仕事(職業)としての学問』を、再読してみて、強く印象にのこることである。
教室で語るときは、それを勉強することが、自明のこととして価値あること……そのように語ることになる。が、それと同時に、なぜ、それを教える価値があるのかの説明ももとめられる。
この本、講談社学術文庫という学生にとってはなじみのあるシリーズである。今の若い人たちは、この本を読んでどのように思うだろうか。気になるところである。
http://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000310640
従来は『職業としての学問』のタイトルで知られているものである。その新訳。
私が『職業としての学問』(岩波文庫版)を読んだのは、いつのころだったろうか。たしか、大学生になって、日吉の教養の時のことだったように覚えている。そのころ、この本は「必読書」であった、といってよいであろうか。
新しい訳が講談社学術文庫で出たので読んでみた。タイトルが『仕事としての学問』に変えてある。また、かなり丁寧な註解がついている。その当時(ウェーバーがこの本の講演をおこなった当時)の、学問的な、社会的な背景などについて、解説してあるので、読みやすかった。
この本については、これまでにいろんなところでいろんなふうに語られてきている。特に、私が付け加えるほどのこともないにちがいない。とはいえ、自分で読んで思ったことなど書いてみるならば、次の二点になるだろうか。
第一は、学問のおかれている社会的状況である。この講演は、ドイツとアメリカの比較からはじまっている。学者、研究者は、どのようにして、そのキャリアを形成していくことになっているのか、から説きおこされている。
これは、その当時にあってのドイツとアメリカの違いとして読めばいいだろう。そして、現代において、この本を読むときには、現代日本の研究者のキャリア形成の事情とひきくらべて読むことになる。
今の日本の状況はどうか……どう考えて見ても、一世紀前のドイツとも、アメリカとも、違っている。単純に言えることではないかもしれないが、今日の日本で、研究者の道を選ぶというのは、かなりの冒険である。あるいは、無謀と言ってもいいかもしれないような側面がある。
にもかかわらず、世の中を見ていると、若い優秀な人たちが出てきていることは確かでもある。本人の努力もあるのだろうが、運の良さとでもいうしかないところも、そのどこかにはあるにちがいない。
第二は、学問の存在意義である。これは、一世紀ほど前のこの文章を読んでも、今に通じるところがあると感じる。端的に言うならば……学問は、それを研究することに価値があると、それ自体において語ることができるのだろうか、ということになる。
たとえば、次のような箇所。
「こうした事情を前提にした上で、学問は誰かにとって「使命を帯びた仕事」たる価値があるのか、そして学問はそれ自身で客観的に価値ある「使命」をもつのか。これもまた価値判断の問題であり、それについては教室ではなにも言えません。というのも、教室で教えることの〈前提〉になっているのは、この肯定だからです。」(p.77) 〈 〉傍点
このことは今も変わらないだろうと思われる。いやむしろ、現代の方が、その「価値判断」をめぐっては、より混沌とした状況にあるともいえようか。
なぜ、その学問は研究するに価するのか、それを学問自身において語ることは、容易ではない。
だが、そうであるにもかかわらず、特に大学で教えられるような研究については、なぜ、それを教える価値があるのか、そのことについて明かにすることを、強く要請されている。たとえば、人文学はいったい何の役にたつのか、教養とは何か、その説明をもとめる要求は、より強くなってきているといっていいかもしれない。
以上の二点が、何十年ぶりかに、『仕事(職業)としての学問』を、再読してみて、強く印象にのこることである。
教室で語るときは、それを勉強することが、自明のこととして価値あること……そのように語ることになる。が、それと同時に、なぜ、それを教える価値があるのかの説明ももとめられる。
この本、講談社学術文庫という学生にとってはなじみのあるシリーズである。今の若い人たちは、この本を読んでどのように思うだろうか。気になるところである。
『知性は死なない』與那覇潤 ― 2018-06-08
2018-06-08 當山日出夫(とうやまひでお)

與那覇潤.『知性は死なない-平成の鬱をこえて-』.文藝春秋.2018
http://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163908236
與那覇潤の本については、すでに触れた。
やまもも書斎記 2018年6月1日
『日本人はなぜ存在するか』與那覇潤
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/06/01/8863726
この『日本人は……』は、いい本だと思った。(が、『中国化する日本』は、あまり感心しなかったが。)買うのは、こちら『知性は死なない』の方が先に買ってあったのだが、読む順番としては、後になった。結果的に、刊行順に読んだことになる。
これは、現代日本において、もっとも良心的な知性のあり方を示している本ではないだろうか。
著者が「うつ」の病を得て、大学の職を辞めるまで、それからの闘病生活、そして、それと平行してあった、平成のおわりの日本の状況……社会的、知的な……についての分析である。
読みながら付箋をつけた箇所をいくつか引用してみよう。
「身体ではなく言語を基盤とする、社会をつくったことで生まれてしまった、永久革命のようにいつまでもつづく、「現時点での正統性」にたいする〈無限の〉挑戦。これが、もともとの意味でいう反知性主義の本質です。」(p.142) 〈 〉原文傍点
「ソ連の社会主義であれアメリカの自由主義であれ、超大国のインテリたちがグランドデザインを描こうとしてきた、言語によって普遍性が語られる世界秩序に対する、身体的な――4章のことばでいえば、反正統主義ないし反知性主義的な反発。(中略)そういう目でみることで、はじめて目下の世界で起きていることが理解できるのだと、私は感じています。」(p.195)
「すなわち、帝国とは〈言語〉によって駆動される理性にもとづき、官僚機構が制度化されたルールをもうけて統治している空間であり、逆に民族とはむしろ「ここからここまでが『われわれ』の範囲だ』という、〈身体〉的な実感にもとづく帰属集団のことである、と。」(p.197) 〈 〉原文傍点
反知性主義をどう理解するか、この点について、いくぶん留保しておくとしても、ここで指摘されているようなことは、しごくまっとうなことであるように思える。国語学という、日本語の研究にかかわっているものとして、いろいろ考えるところのある本でもある。
また次のような箇所。
「教壇に立っているかぎり、教師は政権の批判であれ天皇制の否定であれ、どんな極論でものべることができます。その教員の真価がわかるのは、授業の教室という「自分が権力者でいられる場所」を離れたさいに、どれだけ普段の言行と一致しているかをみることによってでしょう。」(p.169)
これも、しごくまっとうなことである。だが、これがいかに困難なことか、著者の体験した事例がこの本では、具体的に述べられている。この箇所を読むと、現代日本における、大学というところをむしばんでいる知的な荒廃というべきものは、ほとんど救いがたいところまできていると感じざるをえない。
知的に当たり前のことを、ごく普通に当たり前に語る……このことの難しさ、ここにこそ現代日本のおかれている知的退廃がある。本書を読んで感じるのは、著者の知的平衡感覚のバランスの良さである。これは当たり前のことである。この当たり前のことが、普通に通用しない大学というものならば、その大学の方がおかしい。
平成という時代も、あと一年もない。一年後には、次の年号になって、新しい時代を迎えていることだろう。その時になって、平成という時代をふりかえるとき、このような良心的な知性が存在したということを示す本として残ることだろうと思う。
「うつ」という病を経ることによって、身体感覚とのバランスを視野にいれた素直な知性のありかた、このような知性をもつ著者のさらなる活躍を願う次第である。
==============================
明日、東京で、語彙・辞書研究会の発表です。家を留守にするので、二日ほどこのブログをお休みにさせてもらいます。家を離れたときぐらいは、ネットから自由でありたいとも思いますので。
http://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163908236
與那覇潤の本については、すでに触れた。
やまもも書斎記 2018年6月1日
『日本人はなぜ存在するか』與那覇潤
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/06/01/8863726
この『日本人は……』は、いい本だと思った。(が、『中国化する日本』は、あまり感心しなかったが。)買うのは、こちら『知性は死なない』の方が先に買ってあったのだが、読む順番としては、後になった。結果的に、刊行順に読んだことになる。
これは、現代日本において、もっとも良心的な知性のあり方を示している本ではないだろうか。
著者が「うつ」の病を得て、大学の職を辞めるまで、それからの闘病生活、そして、それと平行してあった、平成のおわりの日本の状況……社会的、知的な……についての分析である。
読みながら付箋をつけた箇所をいくつか引用してみよう。
「身体ではなく言語を基盤とする、社会をつくったことで生まれてしまった、永久革命のようにいつまでもつづく、「現時点での正統性」にたいする〈無限の〉挑戦。これが、もともとの意味でいう反知性主義の本質です。」(p.142) 〈 〉原文傍点
「ソ連の社会主義であれアメリカの自由主義であれ、超大国のインテリたちがグランドデザインを描こうとしてきた、言語によって普遍性が語られる世界秩序に対する、身体的な――4章のことばでいえば、反正統主義ないし反知性主義的な反発。(中略)そういう目でみることで、はじめて目下の世界で起きていることが理解できるのだと、私は感じています。」(p.195)
「すなわち、帝国とは〈言語〉によって駆動される理性にもとづき、官僚機構が制度化されたルールをもうけて統治している空間であり、逆に民族とはむしろ「ここからここまでが『われわれ』の範囲だ』という、〈身体〉的な実感にもとづく帰属集団のことである、と。」(p.197) 〈 〉原文傍点
反知性主義をどう理解するか、この点について、いくぶん留保しておくとしても、ここで指摘されているようなことは、しごくまっとうなことであるように思える。国語学という、日本語の研究にかかわっているものとして、いろいろ考えるところのある本でもある。
また次のような箇所。
「教壇に立っているかぎり、教師は政権の批判であれ天皇制の否定であれ、どんな極論でものべることができます。その教員の真価がわかるのは、授業の教室という「自分が権力者でいられる場所」を離れたさいに、どれだけ普段の言行と一致しているかをみることによってでしょう。」(p.169)
これも、しごくまっとうなことである。だが、これがいかに困難なことか、著者の体験した事例がこの本では、具体的に述べられている。この箇所を読むと、現代日本における、大学というところをむしばんでいる知的な荒廃というべきものは、ほとんど救いがたいところまできていると感じざるをえない。
知的に当たり前のことを、ごく普通に当たり前に語る……このことの難しさ、ここにこそ現代日本のおかれている知的退廃がある。本書を読んで感じるのは、著者の知的平衡感覚のバランスの良さである。これは当たり前のことである。この当たり前のことが、普通に通用しない大学というものならば、その大学の方がおかしい。
平成という時代も、あと一年もない。一年後には、次の年号になって、新しい時代を迎えていることだろう。その時になって、平成という時代をふりかえるとき、このような良心的な知性が存在したということを示す本として残ることだろうと思う。
「うつ」という病を経ることによって、身体感覚とのバランスを視野にいれた素直な知性のありかた、このような知性をもつ著者のさらなる活躍を願う次第である。
==============================
明日、東京で、語彙・辞書研究会の発表です。家を留守にするので、二日ほどこのブログをお休みにさせてもらいます。家を離れたときぐらいは、ネットから自由でありたいとも思いますので。
最近のコメント