『ロリータ』ウラジーミル・ナボコフ/若島正(訳) ― 2020-10-01
2020-10-01 當山日出夫(とうやまひでお)
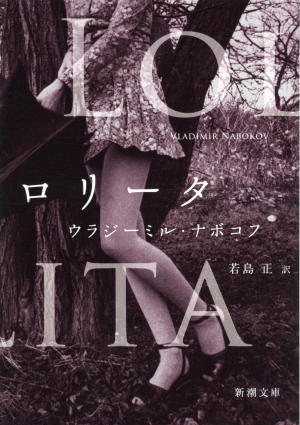
ウラジーミル・ナボコフ.若島正(訳).『ロリータ』(新潮文庫).新潮社.2006
https://www.shinchosha.co.jp/book/210502/
『文学こそ最高の教養である』(光文社新書)に掲載の作品を読んでいっている。ナボコフについて、一つの章が設定されている。ナボコフといえば、『ロリータ』だろうと思うのだが、あいにくと、実はまだきちんと読んでいない作品であった。これを機会に、この作品も読んでおくことにした。
読んだのは新潮文庫の新訳版である。この旧訳版が出たのが、たしか私の学生のころであったかと記憶している。訳者あとがきでは、一九八〇年ということらしい。これが出たとき、かなり話題になった本であるという気はあったのだが、何故か、手にとらずにきてしまった。その後、ただ「ロリータ」ということばが、一人歩きしてきた印象がある。ここは、まずもとの作品を読んでおくべきであろう。
が、読み終わって、正直いって、よく分からない作品という印象がある。にもかかわらず、読んだ感じとしては、これは何かすごい文学なのだろう、とも感じる。その文学としてのすごさのようなものが、残念ながら、今一つ明瞭に輪郭がつかめない。
「ロリータ」と呼ばれる少女と、それにのめり込んでいく中年の男性……人口に膾炙したところでは、この男女の物語なのだが、それだけではない。その当時のアメリカの社会の物語でもあり、また、ふんだんに出てくることば遊びの文学でもある。(ただ、ここのところが、日本語訳で読んでいるので、はっきりとつかめないのがもどかしい。)
新しい新潮文庫版には、かなりの注がついている。しかし、この注は、再読のときに読んでほしいともある。この作品、一読しただけでは、その細部を味読するところまでは難しいようだ。他のナボコフの作品……『文学こそ最高の教養である』でとりあげてある……を読んでから、再度、ふりかえって、もう一度読んでみたい気がする。
いまだに、文学史的な評価という点では、定まったところが無いとのことである。そうかなと思う。ここは、一般に語られる「ロリータ」ということばをとりはらって、虚心になって作品を読んでおくべきである。
2020年9月25日記
https://www.shinchosha.co.jp/book/210502/
『文学こそ最高の教養である』(光文社新書)に掲載の作品を読んでいっている。ナボコフについて、一つの章が設定されている。ナボコフといえば、『ロリータ』だろうと思うのだが、あいにくと、実はまだきちんと読んでいない作品であった。これを機会に、この作品も読んでおくことにした。
読んだのは新潮文庫の新訳版である。この旧訳版が出たのが、たしか私の学生のころであったかと記憶している。訳者あとがきでは、一九八〇年ということらしい。これが出たとき、かなり話題になった本であるという気はあったのだが、何故か、手にとらずにきてしまった。その後、ただ「ロリータ」ということばが、一人歩きしてきた印象がある。ここは、まずもとの作品を読んでおくべきであろう。
が、読み終わって、正直いって、よく分からない作品という印象がある。にもかかわらず、読んだ感じとしては、これは何かすごい文学なのだろう、とも感じる。その文学としてのすごさのようなものが、残念ながら、今一つ明瞭に輪郭がつかめない。
「ロリータ」と呼ばれる少女と、それにのめり込んでいく中年の男性……人口に膾炙したところでは、この男女の物語なのだが、それだけではない。その当時のアメリカの社会の物語でもあり、また、ふんだんに出てくることば遊びの文学でもある。(ただ、ここのところが、日本語訳で読んでいるので、はっきりとつかめないのがもどかしい。)
新しい新潮文庫版には、かなりの注がついている。しかし、この注は、再読のときに読んでほしいともある。この作品、一読しただけでは、その細部を味読するところまでは難しいようだ。他のナボコフの作品……『文学こそ最高の教養である』でとりあげてある……を読んでから、再度、ふりかえって、もう一度読んでみたい気がする。
いまだに、文学史的な評価という点では、定まったところが無いとのことである。そうかなと思う。ここは、一般に語られる「ロリータ」ということばをとりはらって、虚心になって作品を読んでおくべきである。
2020年9月25日記
『ヴェネツィアに死す』トーマス・マン/岸美光(訳) ― 2020-10-02
2020-10-02 當山日出夫(とうやまひでお)

『文学こそ最高の教養である』の本を読んでいる。
この作品、若いときに手にとっているかと思うのだが、今となっては忘れてしまっていた。久しぶりに読んでみた。昔読んだときのタイトルは『ベニスに死す』であったかと思う。
近年になって、トーマス・マンの作品のいくつかを読んだり、読みかえしたりしている。
『ブッデンブローク家の人びと』『魔の山』『ある詐欺師の告白』『トニオ・クレーゲル』などは読んでいる。この作品を読んでおきたいと思ったのは、『文学こそ最高の教養である』で紹介されていたからである。再度、この作品も読んでおきたいと思って、光文社古典新訳文庫版で読んでみることにした。
この作品に描かれていることで、印象に残るのは次の二点ぐらいだろうか。
第一には、エロス。
ヴェネツィアをおとずれた作家、アッシェンバッハは、ふとしたこととから一人の少年を目にする。そして、その少年のもつ「美」に魂をうばわれてしまう。ここは、きわめて耽美的な感情が描かれる。
といって、アッシェンバッハは、その少年となんらかの交渉をもつということはない。ただ、見つめているだけである。そして、自分自身の耽美的な感情のなかに埋もれていく。
ここには、究極的な「美」と「エロス」の世界があると感じる。
第二は、老い。
主人公である、作家のアッシェンバッハは、もう老人といってよいだろう。少なくとももう若くはない。その老いの心境、でありながら、美しい少年にこころひかれていくこころのうちを描いている。
ここに描かれているのは、まさしく、年をとった人間の姿である。もう若くはないという年齢になった人間のありさまを、見事に描きだしていると感じる。このような老いを描いた部分とでもいうべきところに、若いときに、この作品を読んでさほど気持ちが向かなかったのは、無理もないことかもしれない。
若いときに読んでも、また、年をとってから読んでも、この作品は魅力的である。
以上の二点が、『ヴェネツィアに死す』を読んで思うことなどである。
ところで、この作品は、『ベニスに死す』という映画、ヴィスコンティ監督の作品で有名かもしれない。私は、この映画は見てはいないが、著名な映画であることは知っている。そして、そこで使われたのが、マーラーの交響曲五番であることは、よく知られていることだろう。
この作品を読みながら、時として、マーラーの曲が、頭のなかをよぎるような印象があった。
続けて、『だまされた女/すげかえられた首』を読むことにしたい。
2020年9月17日記
近年になって、トーマス・マンの作品のいくつかを読んだり、読みかえしたりしている。
『ブッデンブローク家の人びと』『魔の山』『ある詐欺師の告白』『トニオ・クレーゲル』などは読んでいる。この作品を読んでおきたいと思ったのは、『文学こそ最高の教養である』で紹介されていたからである。再度、この作品も読んでおきたいと思って、光文社古典新訳文庫版で読んでみることにした。
この作品に描かれていることで、印象に残るのは次の二点ぐらいだろうか。
第一には、エロス。
ヴェネツィアをおとずれた作家、アッシェンバッハは、ふとしたこととから一人の少年を目にする。そして、その少年のもつ「美」に魂をうばわれてしまう。ここは、きわめて耽美的な感情が描かれる。
といって、アッシェンバッハは、その少年となんらかの交渉をもつということはない。ただ、見つめているだけである。そして、自分自身の耽美的な感情のなかに埋もれていく。
ここには、究極的な「美」と「エロス」の世界があると感じる。
第二は、老い。
主人公である、作家のアッシェンバッハは、もう老人といってよいだろう。少なくとももう若くはない。その老いの心境、でありながら、美しい少年にこころひかれていくこころのうちを描いている。
ここに描かれているのは、まさしく、年をとった人間の姿である。もう若くはないという年齢になった人間のありさまを、見事に描きだしていると感じる。このような老いを描いた部分とでもいうべきところに、若いときに、この作品を読んでさほど気持ちが向かなかったのは、無理もないことかもしれない。
若いときに読んでも、また、年をとってから読んでも、この作品は魅力的である。
以上の二点が、『ヴェネツィアに死す』を読んで思うことなどである。
ところで、この作品は、『ベニスに死す』という映画、ヴィスコンティ監督の作品で有名かもしれない。私は、この映画は見てはいないが、著名な映画であることは知っている。そして、そこで使われたのが、マーラーの交響曲五番であることは、よく知られていることだろう。
この作品を読みながら、時として、マーラーの曲が、頭のなかをよぎるような印象があった。
続けて、『だまされた女/すげかえられた首』を読むことにしたい。
2020年9月17日記
『ネヴァー・ゲーム』ジェフリー・ディーヴァー ― 2020-10-03
2020-10-03 當山日出夫(とうやまひでお)

ジェフリー・ディーヴァー.池田真紀子(訳).『ネヴァー・ゲーム』.文藝春秋.2020
https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163912691
毎年、秋になると、ジェフリー・ディーヴァーの新作の翻訳が文春から出る。これは、ずっと買って読むことにしてきている。さかのぼれば『ボーン・コレクター』あたりから、続けていることになる。
これは、新しいシリーズである。主人公は、コルター・ショウ。懸賞金ハンターである。これまでの、リンカーン・ライムやキャサリン・ダンスが、警察の側、いわば組織の側に身をおく立場であったのに対して、新しい主人公は、そのような公的な後ろ盾をもたない。いわゆる一匹狼的な生き方である。
読んで思うことは、次の二つぐらいだろうか。
第一に、ミステリとして見た場合、トリックの大筋は、古典的なミステリの名作でつかわれているもののアレンジになっている。ミステリを読んできた人間なら、あああの作品のトリックの変形バージョンか、とすぐ気付く。
この意味では、あまりミステリとしての目新しさを感じることがない。しかし、一つの作品としての完成度は高いと言っていいだろう。
第二に、舞台はシリコンヴァレーである。特に、ゲームの世界の裏と表、なかんずく闇の部分とでもいうところを描いている。これは、まさに時事的なテーマである。(だからということもないが、ジェフリー・ディーヴァーの作品は、その時代を映すものになっている。文庫本になるのを待たずに買って読むことにしているのは、そのせいもある。)
以上の二つのことが読んで思うことなどである。
訳者あとがきによれば、このシリーズは、次作でも続くらしい。また、リンカーン・ライムの新作もあるようだ。となれば、COVID-19でロックダウンしたニューヨークが舞台になるのかと思う。来年もつづけて読むことができればと思う。
2020年10月2日記
https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163912691
毎年、秋になると、ジェフリー・ディーヴァーの新作の翻訳が文春から出る。これは、ずっと買って読むことにしてきている。さかのぼれば『ボーン・コレクター』あたりから、続けていることになる。
これは、新しいシリーズである。主人公は、コルター・ショウ。懸賞金ハンターである。これまでの、リンカーン・ライムやキャサリン・ダンスが、警察の側、いわば組織の側に身をおく立場であったのに対して、新しい主人公は、そのような公的な後ろ盾をもたない。いわゆる一匹狼的な生き方である。
読んで思うことは、次の二つぐらいだろうか。
第一に、ミステリとして見た場合、トリックの大筋は、古典的なミステリの名作でつかわれているもののアレンジになっている。ミステリを読んできた人間なら、あああの作品のトリックの変形バージョンか、とすぐ気付く。
この意味では、あまりミステリとしての目新しさを感じることがない。しかし、一つの作品としての完成度は高いと言っていいだろう。
第二に、舞台はシリコンヴァレーである。特に、ゲームの世界の裏と表、なかんずく闇の部分とでもいうところを描いている。これは、まさに時事的なテーマである。(だからということもないが、ジェフリー・ディーヴァーの作品は、その時代を映すものになっている。文庫本になるのを待たずに買って読むことにしているのは、そのせいもある。)
以上の二つのことが読んで思うことなどである。
訳者あとがきによれば、このシリーズは、次作でも続くらしい。また、リンカーン・ライムの新作もあるようだ。となれば、COVID-19でロックダウンしたニューヨークが舞台になるのかと思う。来年もつづけて読むことができればと思う。
2020年10月2日記
『エール』あれこれ「不協和音」 ― 2020-10-04
2020-10-04 當山日出夫(とうやまひでお)
『エール』第16週「不協和音」
https://www.nhk.or.jp/yell/story/week_16.html
前回は、
やまもも書斎記 2020年9月27日
『エール』あれこれ「先生のうた」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/09/27/9299563
この週になって、戦争はいよいよ泥沼の状態になっていく。が、その時代を生きた人びとにとっては、それがその日常であり生活であったのであろう。
印象に残るのは、次の二点。
第一に、ニュース歌謡。
ラジオのニュース番組……それも戦争にかんするもの……と同時に、音楽が作られ放送されていた。このことは、このドラマで初めて知ったことになる。そのニュース歌謡の第一人者として、裕一は活躍することになる。
第二、音楽挺身隊。
音は、小山田先生の作った音楽挺身隊に入って活動を開始する。自宅の音楽教室をしめざるをえなくなって、なんとか歌を歌う場所を見つけようとすると、音楽挺身隊しか残されていない状況であった。しかし、その音楽挺身隊に音はなじめないでいる。戦意昂揚を目的とする音楽に、音は関心がない。
以上の二点、裕一と音を軸にして、関内の三姉妹のそれぞれの生活が描かれていた。姉の吟の夫は、戦争に赴くことになる。妹の梅の方は、特高に監視される生活ということで、文学作品の発表もままならない状況にある。さらには、久志や木枯も戦争のなかで生きていかざるをえない。
また、喫茶店の竹……バンブーが竹になった……も、閉店を考えるという。
それぞれに、戦局が悪化するにしたがって、日常生活のいろんな面で、戦争というものを感じて生きていくことになる。
週の最後、裕一のもとに召集令状が来たところで終わった。これは、見たところ海軍からだったようだが。さて、次週はどうなるのだろうか。戦争は、さらに過酷なものになっていくのだろう。この時代を、裕一や音たちは、どのように生きていくことになるのだろうか。ただ、裕一は、戦争が終わってからも、「長崎の鐘」などで活躍することは分かっているのだが、それまでに戦争の時代をどう生きることになるのか。次週以降の展開を楽しみに見ることにしよう。
2020年10月3日記
『エール』第16週「不協和音」
https://www.nhk.or.jp/yell/story/week_16.html
前回は、
やまもも書斎記 2020年9月27日
『エール』あれこれ「先生のうた」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/09/27/9299563
この週になって、戦争はいよいよ泥沼の状態になっていく。が、その時代を生きた人びとにとっては、それがその日常であり生活であったのであろう。
印象に残るのは、次の二点。
第一に、ニュース歌謡。
ラジオのニュース番組……それも戦争にかんするもの……と同時に、音楽が作られ放送されていた。このことは、このドラマで初めて知ったことになる。そのニュース歌謡の第一人者として、裕一は活躍することになる。
第二、音楽挺身隊。
音は、小山田先生の作った音楽挺身隊に入って活動を開始する。自宅の音楽教室をしめざるをえなくなって、なんとか歌を歌う場所を見つけようとすると、音楽挺身隊しか残されていない状況であった。しかし、その音楽挺身隊に音はなじめないでいる。戦意昂揚を目的とする音楽に、音は関心がない。
以上の二点、裕一と音を軸にして、関内の三姉妹のそれぞれの生活が描かれていた。姉の吟の夫は、戦争に赴くことになる。妹の梅の方は、特高に監視される生活ということで、文学作品の発表もままならない状況にある。さらには、久志や木枯も戦争のなかで生きていかざるをえない。
また、喫茶店の竹……バンブーが竹になった……も、閉店を考えるという。
それぞれに、戦局が悪化するにしたがって、日常生活のいろんな面で、戦争というものを感じて生きていくことになる。
週の最後、裕一のもとに召集令状が来たところで終わった。これは、見たところ海軍からだったようだが。さて、次週はどうなるのだろうか。戦争は、さらに過酷なものになっていくのだろう。この時代を、裕一や音たちは、どのように生きていくことになるのだろうか。ただ、裕一は、戦争が終わってからも、「長崎の鐘」などで活躍することは分かっているのだが、それまでに戦争の時代をどう生きることになるのか。次週以降の展開を楽しみに見ることにしよう。
2020年10月3日記
追記 2020-10-11
この続きは、
やまもも書斎記 2020年10月11日
『エール』あれこれ「歌の力」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/10/11/9304566
この続きは、
やまもも書斎記 2020年10月11日
『エール』あれこれ「歌の力」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/10/11/9304566
講義がはじまった(その二) ― 2020-10-05
2020-10-05 當山日出夫(とうやまひでお)
続きである。
やまもも書斎記 2020年9月28日
講義がはじまった
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/09/28/9299906
火曜日は、大学院での講義。秋学期だけである。これも、大学の方から事前に連絡があって、オンラインにするかどうか問合せがあった。履修する学生は、LMSで確認してみると、登録者が二名である。であるならば、教室で十分にできると判断して、教室での授業希望と回答しておいた。
それに、秋学期のこの講義の予定では、「長恨歌」を読むことになっている。金沢文庫本「白氏文集」巻十二である。書写は、鎌倉時代であるが、その本文、訓点については、平安時代にさかのぼることができるテクストである。
このようなテクスト、訓点資料を読むような場合、やはり、直接顔を合わせて、ここのところはこう読むのですよと、一緒に本を見ながら、逐一指示しながら勉強していくのが一番である。というよりも、このようにしてしか、教えることができないものである。
先週、第一回があった。履修者は二名。いずれの学生も以前に教えたことのある学生だった。通常は、第一回のときは、まず自分の自己紹介から話しをすることにしているのだが、これはかなり省略することができた。ざっと今年の授業の方針などについて説明。
日本語学の講義であるが、周辺のこととして、日本文学についても考えることにした。「長恨歌」は「源氏物語」などに多大の影響を与えている作品として著名である。まず、そのあたりのことから話しをしてみようかと思う。
また、一昨年もこのテクストを読んでいるのだが、そのときは、全体を通読するのが最後の時間になってしまった。今年は、まず最初に、全体の訓読文を読んでおくつもりでいる。全体がどんなストーリーの展開になっているのかを知ったうえで、では、平安時代に読まれたテクストは、どんなものであったのか、それを見ていく、このような方針にしようと思う。
教室は、小さい。全部はいっても、十数名程度だろうか。学生が二人なので、教師の私をふくめて三人。これなら十分に距離を保つことができる。ただ、困ることは……教室においてあるモニタに、私のPCの画面を映して見せることがある。あることば、用語、概念などを説明するようなとき、ジャパンナレッジに接続して、その項目を検索してみて、それを見ながら話しをするということにしている。しかし、教室で、距離をおいて座ると、モニタの画面の文字が小さいと見えない。これはこまるので、あらかじめ適当な項目を紙にプリントアウトしておいて、それを配布しようかと思う。学生は、後で、自分でWEBに接続してその項目を確認することができる。
今のところ、COVID-19は、そう感染が拡大ということはなさそうである。逆に、終息するということもないようだが。ともあれ、今の状態がつづくなら、なんとか教室での講義を続けることができるかと思う。
まずは、「源氏物語」と「長恨歌」というような話しからはじめるつもりでいる。
2020年10月4日記
続きである。
やまもも書斎記 2020年9月28日
講義がはじまった
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/09/28/9299906
火曜日は、大学院での講義。秋学期だけである。これも、大学の方から事前に連絡があって、オンラインにするかどうか問合せがあった。履修する学生は、LMSで確認してみると、登録者が二名である。であるならば、教室で十分にできると判断して、教室での授業希望と回答しておいた。
それに、秋学期のこの講義の予定では、「長恨歌」を読むことになっている。金沢文庫本「白氏文集」巻十二である。書写は、鎌倉時代であるが、その本文、訓点については、平安時代にさかのぼることができるテクストである。
このようなテクスト、訓点資料を読むような場合、やはり、直接顔を合わせて、ここのところはこう読むのですよと、一緒に本を見ながら、逐一指示しながら勉強していくのが一番である。というよりも、このようにしてしか、教えることができないものである。
先週、第一回があった。履修者は二名。いずれの学生も以前に教えたことのある学生だった。通常は、第一回のときは、まず自分の自己紹介から話しをすることにしているのだが、これはかなり省略することができた。ざっと今年の授業の方針などについて説明。
日本語学の講義であるが、周辺のこととして、日本文学についても考えることにした。「長恨歌」は「源氏物語」などに多大の影響を与えている作品として著名である。まず、そのあたりのことから話しをしてみようかと思う。
また、一昨年もこのテクストを読んでいるのだが、そのときは、全体を通読するのが最後の時間になってしまった。今年は、まず最初に、全体の訓読文を読んでおくつもりでいる。全体がどんなストーリーの展開になっているのかを知ったうえで、では、平安時代に読まれたテクストは、どんなものであったのか、それを見ていく、このような方針にしようと思う。
教室は、小さい。全部はいっても、十数名程度だろうか。学生が二人なので、教師の私をふくめて三人。これなら十分に距離を保つことができる。ただ、困ることは……教室においてあるモニタに、私のPCの画面を映して見せることがある。あることば、用語、概念などを説明するようなとき、ジャパンナレッジに接続して、その項目を検索してみて、それを見ながら話しをするということにしている。しかし、教室で、距離をおいて座ると、モニタの画面の文字が小さいと見えない。これはこまるので、あらかじめ適当な項目を紙にプリントアウトしておいて、それを配布しようかと思う。学生は、後で、自分でWEBに接続してその項目を確認することができる。
今のところ、COVID-19は、そう感染が拡大ということはなさそうである。逆に、終息するということもないようだが。ともあれ、今の状態がつづくなら、なんとか教室での講義を続けることができるかと思う。
まずは、「源氏物語」と「長恨歌」というような話しからはじめるつもりでいる。
2020年10月4日記
追記 2020-10-12
この続きは、
やまもも書斎記 2020年10月12日
講義がはじまった(その三)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/10/12/9304897
この続きは、
やまもも書斎記 2020年10月12日
講義がはじまった(その三)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/10/12/9304897
『麒麟がくる』あれこれ「三淵の奸計」 ― 2020-10-06
2020-10-06 當山日出夫(とうやまひでお)
『麒麟がくる』第二十六回「三淵の奸計」
https://www.nhk.or.jp/kirin/story/26.html
前回は、
やまもも書斎記 2020年9月29日
『麒麟がくる』あれこれ「羽運ぶ蟻」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/09/29/9300247
この回では、「天下」もまた「麒麟」もことばとしては出てきていなかった。そのかわりのキーワードになるのが「上洛」ということばであった。
越前に身をよせている義昭。この義昭にしたがうかたちで、上洛し、京の都を平定するものが、すなわち、次の時代の覇権をにぎるということなのだろうが、では、誰が、それをはたすのか。各地の大名は、自分のところの領地を治めるのに手一杯で、とても上洛できそうではない。かろうじて、上洛できそうなのが、朝倉と織田という展開であった。
とりあえず越前にいる義昭としては、朝倉をたのむことになる。しかし、その朝倉に上洛する気概が見られない。領国内、また、朝倉の一族も、いろいろとトラブルをかかえているようだ。
結局は、朝倉を見限って、織田をたのむことになるのだが、そこで計略があったことになる。
ただ、見ていて思ったことであるが、朝倉から織田に乗り換えるのに、あのような謀殺がはたして本当に有効であり、また、必用であったのだろうか。ちょっとこのあたり、説得力に欠ける筋書きのように思えた。
また、興味深かったのは、伊呂波太夫という存在。公家でもない、武家でもない、といって、庶民というわけでもない。当時の身分や社会秩序からは、離れた存在としてあるようだ。この伊呂波太夫の目をとおすことによって、その戦国の時代を、ある意味で距離をおいて見ることができるようになっている。
このドラマは、これまで意図的に「天下」ということばをつかってきていないと思って見ている。「天下」の覇者になるのは、いったい誰なのかをめぐって、これまでの多くのドラマが作られてきたことを思うと、ここは、かなり意図的にそのように作っているのだろうと思う。
はたして、義昭の上洛は果たせるのか……歴史の結果としては分かっていることなのだが、ここは、このドラマの次の展開を楽しみに見ることにしよう。
次回以降、義昭の上洛をめぐってさらに物語は大きく動くようだ。楽しみに見ることにしよう。
2020年10月5日記
『麒麟がくる』第二十六回「三淵の奸計」
https://www.nhk.or.jp/kirin/story/26.html
前回は、
やまもも書斎記 2020年9月29日
『麒麟がくる』あれこれ「羽運ぶ蟻」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/09/29/9300247
この回では、「天下」もまた「麒麟」もことばとしては出てきていなかった。そのかわりのキーワードになるのが「上洛」ということばであった。
越前に身をよせている義昭。この義昭にしたがうかたちで、上洛し、京の都を平定するものが、すなわち、次の時代の覇権をにぎるということなのだろうが、では、誰が、それをはたすのか。各地の大名は、自分のところの領地を治めるのに手一杯で、とても上洛できそうではない。かろうじて、上洛できそうなのが、朝倉と織田という展開であった。
とりあえず越前にいる義昭としては、朝倉をたのむことになる。しかし、その朝倉に上洛する気概が見られない。領国内、また、朝倉の一族も、いろいろとトラブルをかかえているようだ。
結局は、朝倉を見限って、織田をたのむことになるのだが、そこで計略があったことになる。
ただ、見ていて思ったことであるが、朝倉から織田に乗り換えるのに、あのような謀殺がはたして本当に有効であり、また、必用であったのだろうか。ちょっとこのあたり、説得力に欠ける筋書きのように思えた。
また、興味深かったのは、伊呂波太夫という存在。公家でもない、武家でもない、といって、庶民というわけでもない。当時の身分や社会秩序からは、離れた存在としてあるようだ。この伊呂波太夫の目をとおすことによって、その戦国の時代を、ある意味で距離をおいて見ることができるようになっている。
このドラマは、これまで意図的に「天下」ということばをつかってきていないと思って見ている。「天下」の覇者になるのは、いったい誰なのかをめぐって、これまでの多くのドラマが作られてきたことを思うと、ここは、かなり意図的にそのように作っているのだろうと思う。
はたして、義昭の上洛は果たせるのか……歴史の結果としては分かっていることなのだが、ここは、このドラマの次の展開を楽しみに見ることにしよう。
次回以降、義昭の上洛をめぐってさらに物語は大きく動くようだ。楽しみに見ることにしよう。
2020年10月5日記
追記 2020-10-13
この続きは、
やまもも書斎記 2020年10月13日
『麒麟がくる』あれこれ「宗久の約束」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/10/13/9305222
この続きは、
やまもも書斎記 2020年10月13日
『麒麟がくる』あれこれ「宗久の約束」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/10/13/9305222
キキョウ ― 2020-10-07
2020-10-07 當山日出夫(とうやまひでお)
水曜日は花の写真。今日はキキョウである。
前回は、
やまもも書斎記 2020年9月30日
葛の花
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/09/30/9300588
キキョウ「桔梗」の花というと、秋の花のイメージがある。が、我が家で咲く桔梗の花は、例年、七月ごろに咲きはじめる。見ていると、花の時期はかなりながい。八月、九月になっても、花をつけているのが見える。しかし、花のさかりというべきは、まだかなり暑い時期のころのことになる。
我が家に咲く桔梗の花は白いものである。池のほとりに植わっていて、池の方向に花を咲かせる。そのため、花の咲いている正面からの写真を撮ることができない。せいぜい、横向きの写真である。
この花、どうも去年よりも花の咲くのが、数が少なくなってきているように思える。特に世話をしているというのでもないが、さて、来年も無事に花を咲かせてくれるだろうか。あるいは、桔梗は、栽培しようと思えば、種を売っている。これまで、自分の家のまわりで自然に咲く花を写してきたが、そろそろ種をまいてみるのもいいかもしれないと思うようになってきた。
水曜日は花の写真。今日はキキョウである。
前回は、
やまもも書斎記 2020年9月30日
葛の花
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/09/30/9300588
キキョウ「桔梗」の花というと、秋の花のイメージがある。が、我が家で咲く桔梗の花は、例年、七月ごろに咲きはじめる。見ていると、花の時期はかなりながい。八月、九月になっても、花をつけているのが見える。しかし、花のさかりというべきは、まだかなり暑い時期のころのことになる。
我が家に咲く桔梗の花は白いものである。池のほとりに植わっていて、池の方向に花を咲かせる。そのため、花の咲いている正面からの写真を撮ることができない。せいぜい、横向きの写真である。
この花、どうも去年よりも花の咲くのが、数が少なくなってきているように思える。特に世話をしているというのでもないが、さて、来年も無事に花を咲かせてくれるだろうか。あるいは、桔梗は、栽培しようと思えば、種を売っている。これまで、自分の家のまわりで自然に咲く花を写してきたが、そろそろ種をまいてみるのもいいかもしれないと思うようになってきた。
Nikon D500
AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED
AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR
2020年10月5日記
『だまされた女/すげかえられた首』トーマス・マン/岸美光(訳) ― 2020-10-08
2020-10-08 當山日出夫(とうやまひでお)

トーマス・マン.岸美光(訳).『だまされた女/すげかえられた首』(光文社古典新訳文庫).光文社.2009
https://www.kotensinyaku.jp/books/book74/
『文学こそ最高の教養である』に出ていた本を順に読んでいる。トーマス・マンの続きである。
解説によると、トーマス・マンのエロス的な作品として、『ヴェネツィアに死す』と一緒に刊行する予定だったらしい。そういわれてみると、たしかに、エロスにみちた作品である。
トーマス・マンの作品は、今では、もうあまり読まれないのかもしれない。私が、トーマス・マンの名前を知っているのは、若いときに読んだ北杜夫を通じてであった。若いときに『魔の山』を手にとったこともある。なんとも難解な作家であるというイメージをもっていた。『トニオ・クレーゲル』は何度か読みかえしたものである。近年になって、『ブッデンブローク家の人びと』を読んでみて、少しイメージが変わった。謹厳実直な作品でありながら、どことなくユーモアを感じさせる。
これらの作品、『ヴェネツィアに死す』『だまされた女/すげかえられた首』を読んでみて感じるところは、エロスというものを描きながら、そこになんとなくユーモアのようなものがあることである。ユーモアを描こうとした作品ではないのであろうが、登場人物が大真面目で真剣になればなるほど、それをはたから見ていて、なにがしか滑稽なものを感じずにはいられない。
ところで、興味深いのは『すげかえられた首』である。なんとも荒唐無稽な話しといってしまえばそれまでかもしれないが、近年の、生命科学、医学の進歩によって、ひょっとすると、この小説で描いたような問題が、現実のものとなり得るのかもしれない、いや、すでに現実の課題であるといっても過言ではない、そんな気がしてならない。
他のトーマス・マンの作品も読んでおきたい、あるいは、さらに再読してみたいと思うが、とりあえずは、『文学こそ最高の教養である』の本を順番に読んでいくことにする。
2020年9月20日記
https://www.kotensinyaku.jp/books/book74/
『文学こそ最高の教養である』に出ていた本を順に読んでいる。トーマス・マンの続きである。
解説によると、トーマス・マンのエロス的な作品として、『ヴェネツィアに死す』と一緒に刊行する予定だったらしい。そういわれてみると、たしかに、エロスにみちた作品である。
トーマス・マンの作品は、今では、もうあまり読まれないのかもしれない。私が、トーマス・マンの名前を知っているのは、若いときに読んだ北杜夫を通じてであった。若いときに『魔の山』を手にとったこともある。なんとも難解な作家であるというイメージをもっていた。『トニオ・クレーゲル』は何度か読みかえしたものである。近年になって、『ブッデンブローク家の人びと』を読んでみて、少しイメージが変わった。謹厳実直な作品でありながら、どことなくユーモアを感じさせる。
これらの作品、『ヴェネツィアに死す』『だまされた女/すげかえられた首』を読んでみて感じるところは、エロスというものを描きながら、そこになんとなくユーモアのようなものがあることである。ユーモアを描こうとした作品ではないのであろうが、登場人物が大真面目で真剣になればなるほど、それをはたから見ていて、なにがしか滑稽なものを感じずにはいられない。
ところで、興味深いのは『すげかえられた首』である。なんとも荒唐無稽な話しといってしまえばそれまでかもしれないが、近年の、生命科学、医学の進歩によって、ひょっとすると、この小説で描いたような問題が、現実のものとなり得るのかもしれない、いや、すでに現実の課題であるといっても過言ではない、そんな気がしてならない。
他のトーマス・マンの作品も読んでおきたい、あるいは、さらに再読してみたいと思うが、とりあえずは、『文学こそ最高の教養である』の本を順番に読んでいくことにする。
2020年9月20日記
『幸福について』ショーペンハウアー/鈴木芳子(訳) ― 2020-10-09
2020-10-09 當山日出夫(とうやまひでお)

ショーペンハウアー.鈴木芳子(訳).『幸福について』(光文社古典新訳文庫).光文社.2018
https://www.kotensinyaku.jp/books/book268/
『文学こそ最高の教養である』の本である。
ショーペンハウアー、あるいは、ショーペンハウエルは、名前はむろん知ってはいるが、これまで手にとることはなかった。ただ、「デカンショ」として、知っていた名前ということになるだろうか。そのせいか、昔の教養主義の親分のような感じがして、なんとなく遠ざけてしまっていたというのが、正直なところである。ただ、『読書について』などの著作が広く読まれていることは、知識としてはもっていた。
この『幸福について』であるが、はっきりいって、よく分からないというのが、本当のところかもしれない。それは、ショーペンハウアーの考えている「幸福」ということと、現代、二一世紀の今日において考える「幸福」というのが、どうも微妙に違っているせいだろうかと思う。
とはいえ、読んでなるほどと思うところがいくつかある。
「心の真の深い平和と完全な心の安らぎ、健康に次いで最も貴重な地上の財宝は、孤独のなかにしかなく、持続的気分としては、徹底した隠棲のうちにしか見出すことができない。」(pp.225-226)
この本を読んで違和感を感じるところがあるとしたら、たぶん、この本が一九世紀のドイツの読者を相手に書かれていることに起因するのだろう。名誉について論じたところとか、女性のあり方について言及したあたりのところは、ちょっと今日の価値観からすれば、素直には受け入れがたいところを感じないではない。
最も深く共感するのは、第六章「年齢による違いについて」かと思う。今よりは、ずっと人びとの平均寿命が短かった時代ではあるが、それでも、老年、老い、というものをどう考えるかというのは、人間にとって幸福とはなにかを考えるうえで、重要なテーマである。この章を読んで、そういうものなのであろう、と深く共感するところがある。
このあたりが、この本が古典として、今なお読まれ続けているゆえんであろうか。確かに、書かれた時代的制約のようなものを感じはするのだが、それを越えて、人間の一生というものに、深く考察をめぐらせている。
まあ、私も、この年になって……還暦をとうにすぎた……このような本を読んでいられるというのも、幸福といっていいのだろうと思う。
2020年9月20日記
https://www.kotensinyaku.jp/books/book268/
『文学こそ最高の教養である』の本である。
ショーペンハウアー、あるいは、ショーペンハウエルは、名前はむろん知ってはいるが、これまで手にとることはなかった。ただ、「デカンショ」として、知っていた名前ということになるだろうか。そのせいか、昔の教養主義の親分のような感じがして、なんとなく遠ざけてしまっていたというのが、正直なところである。ただ、『読書について』などの著作が広く読まれていることは、知識としてはもっていた。
この『幸福について』であるが、はっきりいって、よく分からないというのが、本当のところかもしれない。それは、ショーペンハウアーの考えている「幸福」ということと、現代、二一世紀の今日において考える「幸福」というのが、どうも微妙に違っているせいだろうかと思う。
とはいえ、読んでなるほどと思うところがいくつかある。
「心の真の深い平和と完全な心の安らぎ、健康に次いで最も貴重な地上の財宝は、孤独のなかにしかなく、持続的気分としては、徹底した隠棲のうちにしか見出すことができない。」(pp.225-226)
この本を読んで違和感を感じるところがあるとしたら、たぶん、この本が一九世紀のドイツの読者を相手に書かれていることに起因するのだろう。名誉について論じたところとか、女性のあり方について言及したあたりのところは、ちょっと今日の価値観からすれば、素直には受け入れがたいところを感じないではない。
最も深く共感するのは、第六章「年齢による違いについて」かと思う。今よりは、ずっと人びとの平均寿命が短かった時代ではあるが、それでも、老年、老い、というものをどう考えるかというのは、人間にとって幸福とはなにかを考えるうえで、重要なテーマである。この章を読んで、そういうものなのであろう、と深く共感するところがある。
このあたりが、この本が古典として、今なお読まれ続けているゆえんであろうか。確かに、書かれた時代的制約のようなものを感じはするのだが、それを越えて、人間の一生というものに、深く考察をめぐらせている。
まあ、私も、この年になって……還暦をとうにすぎた……このような本を読んでいられるというのも、幸福といっていいのだろうと思う。
2020年9月20日記
『盤上の向日葵』柚月祐子 ― 2020-10-10
2020-10-10 當山日出夫(とうやまひでお)


柚月祐子.『盤上の向日葵』(上・下)(中公文庫).中央公論新社.2020 (中央公論新社.2017)
https://www.chuko.co.jp/bunko/2020/09/206940.html
https://www.chuko.co.jp/bunko/2020/09/206941.html
柚月祐子という作家は、良質のエンタテイメントが書ける作家だと思う。この作品、出たときに話題になった本であるという認識はもっていた。が、なんとなく手にしそびれてしまっていた。このたび、中公文庫版で上下二冊で出たので、これで読んでみることにした。
読み始めて、ふと思い浮かぶのは、松本清張の著名な作品である。たぶん、犯人はこの人物なんだろうなあ、そして、それを追いかける刑事たちのことがでてくるんだろう……と思って読み進めることになった。
この小説は、二つのストーリーが平行して進行する。一つは、山中で発見された死体。その死体と一緒に埋められていた将棋の駒。これは、どうやら世に希な逸品であるらしい。この将棋の駒を追って、捜査をすすめる刑事たち。他の一つは、信州の諏訪で、父親から虐待をうけている少年の話し。貧しいのだが、頭脳は優秀である。将棋に興味がある。それを見出した、ある男性が、その少年の世話をやくことになり、また将棋をおしえる。やがて少年は、東京に出て東大にはいる。そして、将棋の世界にかかわっていくことになる。
二つのストーリーが並んで進んでいって、最後に一緒になったところで、事件の真相があきらかになる。小説の作り方としては、月並みではあるが、しかし、そこは柚月祐子ならではの、筆力である。読者を、物語のなかにひきずりこんでいく。巧い書き方である。
ただ、読んでいてちょっと気になったのが、時代設定。平成のはじめごろにしてある。これは、いったい何の意図があってのことだろうと思って読んでいた。文庫本の解説を書いているのは、羽生善治である。これを読んで、なるほど、この時代設定でなければ、このような将棋の世界はありえなかったのかと、納得がいく。
それから、どうでもいいことだが……この文庫本には、大量の誤植がある。中央公論新社のHPに正誤表が掲載になっている。たぶん、本の作り方としては、先に単行本が出たときの組版データを流用して、文庫本にしているはずだと思うのだが、いったいどのような手続きで組版すれば、このような誤植になるのか、そこが、ある意味で興味深い。
しかし、私は、将棋については、とんと素人である。駒の動かし方、最初の並べ方をかろうじて知っている程度である。とても、その駒を進めて勝負するところの描写を理解するにいたらない。これは、誤植があっても、ほとんど意味のないことなので、そのまま読むことにした。
2020年10月9日記
https://www.chuko.co.jp/bunko/2020/09/206940.html
https://www.chuko.co.jp/bunko/2020/09/206941.html
柚月祐子という作家は、良質のエンタテイメントが書ける作家だと思う。この作品、出たときに話題になった本であるという認識はもっていた。が、なんとなく手にしそびれてしまっていた。このたび、中公文庫版で上下二冊で出たので、これで読んでみることにした。
読み始めて、ふと思い浮かぶのは、松本清張の著名な作品である。たぶん、犯人はこの人物なんだろうなあ、そして、それを追いかける刑事たちのことがでてくるんだろう……と思って読み進めることになった。
この小説は、二つのストーリーが平行して進行する。一つは、山中で発見された死体。その死体と一緒に埋められていた将棋の駒。これは、どうやら世に希な逸品であるらしい。この将棋の駒を追って、捜査をすすめる刑事たち。他の一つは、信州の諏訪で、父親から虐待をうけている少年の話し。貧しいのだが、頭脳は優秀である。将棋に興味がある。それを見出した、ある男性が、その少年の世話をやくことになり、また将棋をおしえる。やがて少年は、東京に出て東大にはいる。そして、将棋の世界にかかわっていくことになる。
二つのストーリーが並んで進んでいって、最後に一緒になったところで、事件の真相があきらかになる。小説の作り方としては、月並みではあるが、しかし、そこは柚月祐子ならではの、筆力である。読者を、物語のなかにひきずりこんでいく。巧い書き方である。
ただ、読んでいてちょっと気になったのが、時代設定。平成のはじめごろにしてある。これは、いったい何の意図があってのことだろうと思って読んでいた。文庫本の解説を書いているのは、羽生善治である。これを読んで、なるほど、この時代設定でなければ、このような将棋の世界はありえなかったのかと、納得がいく。
それから、どうでもいいことだが……この文庫本には、大量の誤植がある。中央公論新社のHPに正誤表が掲載になっている。たぶん、本の作り方としては、先に単行本が出たときの組版データを流用して、文庫本にしているはずだと思うのだが、いったいどのような手続きで組版すれば、このような誤植になるのか、そこが、ある意味で興味深い。
しかし、私は、将棋については、とんと素人である。駒の動かし方、最初の並べ方をかろうじて知っている程度である。とても、その駒を進めて勝負するところの描写を理解するにいたらない。これは、誤植があっても、ほとんど意味のないことなので、そのまま読むことにした。
2020年10月9日記





最近のコメント