『小萩のかんざし』北村薫 ― 2021-02-26
2021-02-26 當山日出夫(とうやまひでお)
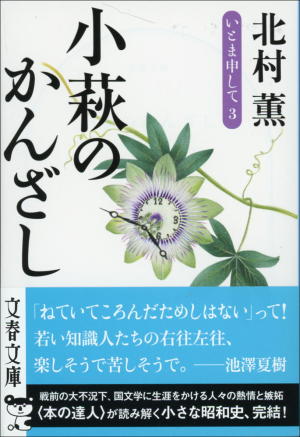
北村薫.『小萩のかんざし-いとま申して3-』(文春文庫).文藝春秋.2021(文藝春秋.2018)
https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784167916411
「いとま申して」のシリーズは、その一冊目のときから読んできている。文春文庫版が出たので買って読んでみた。読んで思うところは多々ある。
私は、慶應の国文で学んだ。昭和50年の入学である。池田彌三郎先生にもならったし、また、加藤守雄先生の講義にも出たことがある。折口信夫全集は、確か、学部の一年のときに、奨学金で買ったのを覚えている。このとき、一冊……古代研究のなかの一冊だったと思うが……が欠けていたので、これは早稲田辺りの古書店をめぐって買ってそろえた。その後、新しい全集が出たときにも、買ってそろえた。
慶應の国文で学ぶとき、二つの方向がある。あるいは、あった、というべきか。一つは、折口信夫につらなる民俗学的な国文学研究である。もうひとつは、厳格な文献研究である。えてして、慶應の国文というと折口信夫のことが話題になるかもしれないが、そうとばかりはいえない。謹厳実直な文献学の流れも確かなものとしてある。
ただ、そのなかにあって、私が選んだのは、国語学という方面、それも文献にもとづく国語史という方向であった。だが、慶應には国語学の先生がいなかった。そのため、大学の外で、山田忠雄先生に個人的に師事することになった。一方、慶應においては、斯道文庫の太田次男先生のもとで、「白氏文集」の古写本の勉強もした。その結果としてつくったのが、「神田本白氏文集」の漢字索引であり、訓点語索引である。
今でも、折口信夫については、興味関心はある。いや、いまだにその影響をうけているといってもいいかもしれない。日本の古典文学を読むとき、折口信夫の発想にひきつけて読むということがぬけきれないでいる。
私が慶應の国文に抱いているものは、無論、一つには矜恃ということもある。しかし、それだけではなく、複雑に愛憎半ばする感情がどことなくある。
ところで、『小萩のかんざし』である。この三冊目になって、慶應の国文で折口信夫のもとで学ぶことになった、著者(北村薫)の父君のことが、評伝風に記される。そのなかで、慶應で私がならったり、接したりした経験のある、幾人かの人びとの名前がでてくる。
この本で、折口信夫とならんでとりあげられているのは横山重である。私の勉強したことは、どちらかといえば、横山重の流れをくむ方向であったということになるのであろうかとも思うことになる。
率直に読んで思ったことを記すならば、この本のようなことは、私には書けないな、ということである。私には、折口信夫の時代の慶應の国文を、ここまで冷静に落ち着いて書くことはできない。まだ、学生のときの気持ちが、自分のなかで生きている。いや生きているというよりも、うずくとでもいった方がいいだろう。
もし、私が折口信夫について何か書くとするならば、厳格な文献学的な検証ということにならざるをえないだろう。いや、いまでは、そのようにしか、折口信夫を読むことができないといっていいかもしれない。
無論、近代文学、国文学、芸能史、としてただ読むことはできるかもしれない。いまだにその学問は魅力的でありつづけている。
折口信夫の古代研究のいくつかは、学生のときに精読したことがある。綿密にノートをとりながら細かに読んだことがある。そのとき分かったことは、その論理にはいくつか飛躍があることである。おそらく、今の時代の論文としては、査読をとおることはまずないだろう。それ以来ということもないが、学生のときから、折口信夫がこう書いているということを、金科玉条のように語る人を、避けてきたということがある。
『小萩のかんざし』であるが……ある時代の慶應の国文の雰囲気を見事に描き出しているといっていいだろう。そして、主人公である北村薫の父君は、かならずしも折口門下の主流という位置にとどまることがなかった。その微妙な距離感が、今の私が読んで、若いときの思い出を発掘していくことことになる。それは、決して、楽しいうれしい思い出ばかりとは限らない。
今の慶應の国文の学生は、この本をどう読むだろうか。最後にふとそんなことを思ってみる。
2021年2月16日記
https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784167916411
「いとま申して」のシリーズは、その一冊目のときから読んできている。文春文庫版が出たので買って読んでみた。読んで思うところは多々ある。
私は、慶應の国文で学んだ。昭和50年の入学である。池田彌三郎先生にもならったし、また、加藤守雄先生の講義にも出たことがある。折口信夫全集は、確か、学部の一年のときに、奨学金で買ったのを覚えている。このとき、一冊……古代研究のなかの一冊だったと思うが……が欠けていたので、これは早稲田辺りの古書店をめぐって買ってそろえた。その後、新しい全集が出たときにも、買ってそろえた。
慶應の国文で学ぶとき、二つの方向がある。あるいは、あった、というべきか。一つは、折口信夫につらなる民俗学的な国文学研究である。もうひとつは、厳格な文献研究である。えてして、慶應の国文というと折口信夫のことが話題になるかもしれないが、そうとばかりはいえない。謹厳実直な文献学の流れも確かなものとしてある。
ただ、そのなかにあって、私が選んだのは、国語学という方面、それも文献にもとづく国語史という方向であった。だが、慶應には国語学の先生がいなかった。そのため、大学の外で、山田忠雄先生に個人的に師事することになった。一方、慶應においては、斯道文庫の太田次男先生のもとで、「白氏文集」の古写本の勉強もした。その結果としてつくったのが、「神田本白氏文集」の漢字索引であり、訓点語索引である。
今でも、折口信夫については、興味関心はある。いや、いまだにその影響をうけているといってもいいかもしれない。日本の古典文学を読むとき、折口信夫の発想にひきつけて読むということがぬけきれないでいる。
私が慶應の国文に抱いているものは、無論、一つには矜恃ということもある。しかし、それだけではなく、複雑に愛憎半ばする感情がどことなくある。
ところで、『小萩のかんざし』である。この三冊目になって、慶應の国文で折口信夫のもとで学ぶことになった、著者(北村薫)の父君のことが、評伝風に記される。そのなかで、慶應で私がならったり、接したりした経験のある、幾人かの人びとの名前がでてくる。
この本で、折口信夫とならんでとりあげられているのは横山重である。私の勉強したことは、どちらかといえば、横山重の流れをくむ方向であったということになるのであろうかとも思うことになる。
率直に読んで思ったことを記すならば、この本のようなことは、私には書けないな、ということである。私には、折口信夫の時代の慶應の国文を、ここまで冷静に落ち着いて書くことはできない。まだ、学生のときの気持ちが、自分のなかで生きている。いや生きているというよりも、うずくとでもいった方がいいだろう。
もし、私が折口信夫について何か書くとするならば、厳格な文献学的な検証ということにならざるをえないだろう。いや、いまでは、そのようにしか、折口信夫を読むことができないといっていいかもしれない。
無論、近代文学、国文学、芸能史、としてただ読むことはできるかもしれない。いまだにその学問は魅力的でありつづけている。
折口信夫の古代研究のいくつかは、学生のときに精読したことがある。綿密にノートをとりながら細かに読んだことがある。そのとき分かったことは、その論理にはいくつか飛躍があることである。おそらく、今の時代の論文としては、査読をとおることはまずないだろう。それ以来ということもないが、学生のときから、折口信夫がこう書いているということを、金科玉条のように語る人を、避けてきたということがある。
『小萩のかんざし』であるが……ある時代の慶應の国文の雰囲気を見事に描き出しているといっていいだろう。そして、主人公である北村薫の父君は、かならずしも折口門下の主流という位置にとどまることがなかった。その微妙な距離感が、今の私が読んで、若いときの思い出を発掘していくことことになる。それは、決して、楽しいうれしい思い出ばかりとは限らない。
今の慶應の国文の学生は、この本をどう読むだろうか。最後にふとそんなことを思ってみる。
2021年2月16日記
最近のコメント