『東條英機』一ノ瀬俊也 ― 2020-12-25
2020-12-25 當山日出夫(とうやまひでお)
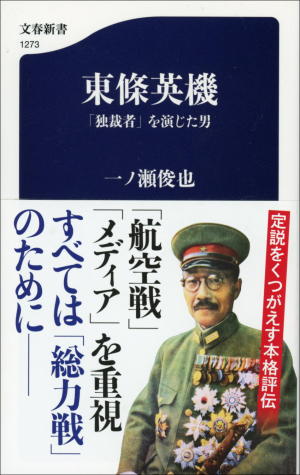
一ノ瀬俊也.『東條英機-「独裁者」を演じた男-』(文春新書).文藝春秋.2020
https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784166612734
夏に出た本だが、しばらく積んであった。先日、NHKで東條英機の番組があったのを見たこともあって、取り出してきて読んでおくことにした。
やまもも書斎記 2020年12月11日
NHK 昭和の選択 「太平洋戦争 東條英機 開戦への煩悶」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/12/11/9325592
この本は、東條英機の評伝という形をとっているが、中心となるのは、昭和になってから陸軍の中枢に出て、総理になり、開戦にいたる経緯。そして、その退陣と、戦後の東京裁判まであつかってある。
はっきりいって、この本を読んで、東條英機という人物がよくわからない、というのが実際のところである。常識的な知識としては、東京裁判のA級戦犯であり、日本の戦争の責任者ということになる。
だが、それを、ヒトラーのような独裁者と一律にみなしていいかとなると、かなり疑問が残る。
私の思うところとしては、東京裁判を経て戦後の日本が再スタートするにあたり、戦争をどうとらえるかとなったとき、浮上してきたのが東條英機という人物であったように思われてならない。東條英機のような、悪人を必要とした……まあ、端的にいえば、こうなるだろうか。
その一方で、この本を読むと、東條英機の生前の、社会の人びとの東條英機に対する評価ということについて、かなりの言及がある。そこそこ人びとに支持されていたということがわかる。しかし、インテリ受けする宰相ではなかったようだ。このあたりが、日本を戦争にみちびいた「独裁者」というイメージの形成につながっていくところでもあろうかと思う。
ところで、この本を読んで感じることの一つは、この一冊の本の背景にある、膨大な歴史研究の積み重ねである。昭和の歴史というのは、自分の生きてきた時代でもあり、昭和の戦前もなにがしかその延長でとらえてしまっているところがある。歴史学の研究の対象として考えるということがあまりない、というのが実際のところである。しかし、文中で言及される数多くの先行研究にふれると、昭和の歴史というものが、重要な研究課題であり、数多くの研究の蓄積があることが実感される。
歴史学研究の方法論にのっとった昭和史研究の存在というものに気づかせてくれる本でもある。
2020年12月24日記
https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784166612734
夏に出た本だが、しばらく積んであった。先日、NHKで東條英機の番組があったのを見たこともあって、取り出してきて読んでおくことにした。
やまもも書斎記 2020年12月11日
NHK 昭和の選択 「太平洋戦争 東條英機 開戦への煩悶」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2020/12/11/9325592
この本は、東條英機の評伝という形をとっているが、中心となるのは、昭和になってから陸軍の中枢に出て、総理になり、開戦にいたる経緯。そして、その退陣と、戦後の東京裁判まであつかってある。
はっきりいって、この本を読んで、東條英機という人物がよくわからない、というのが実際のところである。常識的な知識としては、東京裁判のA級戦犯であり、日本の戦争の責任者ということになる。
だが、それを、ヒトラーのような独裁者と一律にみなしていいかとなると、かなり疑問が残る。
私の思うところとしては、東京裁判を経て戦後の日本が再スタートするにあたり、戦争をどうとらえるかとなったとき、浮上してきたのが東條英機という人物であったように思われてならない。東條英機のような、悪人を必要とした……まあ、端的にいえば、こうなるだろうか。
その一方で、この本を読むと、東條英機の生前の、社会の人びとの東條英機に対する評価ということについて、かなりの言及がある。そこそこ人びとに支持されていたということがわかる。しかし、インテリ受けする宰相ではなかったようだ。このあたりが、日本を戦争にみちびいた「独裁者」というイメージの形成につながっていくところでもあろうかと思う。
ところで、この本を読んで感じることの一つは、この一冊の本の背景にある、膨大な歴史研究の積み重ねである。昭和の歴史というのは、自分の生きてきた時代でもあり、昭和の戦前もなにがしかその延長でとらえてしまっているところがある。歴史学の研究の対象として考えるということがあまりない、というのが実際のところである。しかし、文中で言及される数多くの先行研究にふれると、昭和の歴史というものが、重要な研究課題であり、数多くの研究の蓄積があることが実感される。
歴史学研究の方法論にのっとった昭和史研究の存在というものに気づかせてくれる本でもある。
2020年12月24日記
最近のコメント