『彼岸過迄』夏目漱石 ― 2019-12-06
2019-12-06 當山日出夫(とうやまひでお)
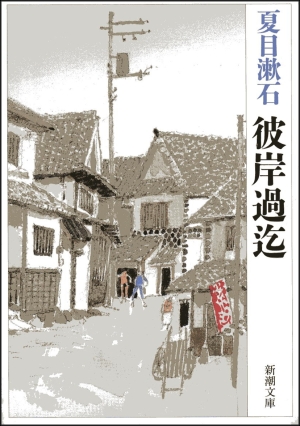
夏目漱石.『彼岸過迄』(新潮文庫).新潮社.1952(2010.改版)
https://www.shinchosha.co.jp/book/101011/
続きである。
やまもも書斎記 2019年11月29日
『門』夏目漱石
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/11/29/9182718
現代のわれわれは、この作品が漱石の「修善寺の大患」の後の作品であることを知っている。この体験が、漱石の作品にどのような影響があるのか、それは漱石研究の分野において研究のなされていることだろうと思う。ただ、今の私としては、二一世紀の読者として、自分の思うとおりに読んでみたいと思っている。
この作品を読んで思うことは、次の二点だろうか。
第一には、探偵について。
漱石は、「探偵」を最も嫌っていたと思う。『猫』など読むと、「探偵」ほど下劣な人間はいないという意味のことが書いてある。それが、この『彼岸過迄』になると、なぜ、「探偵」のまねごとなどしているのだろうか。あれほど嫌っていたと思う「探偵」のことを書いているのはなぜだろう。
第二には、その「探偵」にはいりこんでいく作者について。
ひょっとすると漱石は、人のこころを「探偵」することの楽しみ……無論、それは小説という架空の世界においてであるが……に気付いたのかもしれない。この作品の後半の部分になると、登場人物のこころのうちを「探偵」として、観察し、のぞき見ているような気がしてならない。
そう思って読むと、この次の『行人』も、『こころ』も、人のこころのうちを「探偵」してさぐる物語であるとも読める。
以上の二点が、『彼岸過迄』を読んで思うことなどである。
さらに書けば、この作品のなかで印象的なのが、子ども(幼児)の死と葬儀のシーン。漱石の作品を読んでいくなかで、このところは、特別に印象に残るものと感じる。近代文学のなかで、「父」や「母」を描いたものは多くあると思うが、幼い幼児とその死を描いたものが、他にどれくらいあるだろうか。
また、この時代、子どもの死というものも、そんなに珍しいことではなかった、ということもあるかと思う。乳幼児死亡率が激減するのは、戦後になって近年になってからのことである。
それから、この作品中の女性、千代子が、女学生ことばをつかっている。漱石の作品中で、女学生ことばをつかう女性は、作品中で独特の位置にある。若い女性として、下女も登場するのだが、これは、別のことばをつかっている。おそらく「役割語」というような観点を導入して分析するならば、漱石の作品中での登場人物のことばというのは、かなり興味深いことになるかと思う。これは、おそらくは、文学研究と言語研究の両方にまたがった研究になるにちがいない。
ところで、この作品『彼岸過迄』は、まさに「彼岸過迄」ぐらいの連載になるということで、このタイトルになったようだ。特に、小説としての構想があったというのではないように思える。もし、最初から緻密に構想して書いたとするならば、どうも全体としてチグハグな印象の残る作品である。そうではなく、まさに作者(漱石)が書いているように、どのようなストーリーの展開になるか、特に決めたこともなく、思いつくままに書いていった結果が、このような小説になった。そして、それは、人のこころのうちを「探偵」する物語になった。このように思ってみる。
次は、順番に読んでいって『行人』である。
https://www.shinchosha.co.jp/book/101011/
続きである。
やまもも書斎記 2019年11月29日
『門』夏目漱石
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/11/29/9182718
現代のわれわれは、この作品が漱石の「修善寺の大患」の後の作品であることを知っている。この体験が、漱石の作品にどのような影響があるのか、それは漱石研究の分野において研究のなされていることだろうと思う。ただ、今の私としては、二一世紀の読者として、自分の思うとおりに読んでみたいと思っている。
この作品を読んで思うことは、次の二点だろうか。
第一には、探偵について。
漱石は、「探偵」を最も嫌っていたと思う。『猫』など読むと、「探偵」ほど下劣な人間はいないという意味のことが書いてある。それが、この『彼岸過迄』になると、なぜ、「探偵」のまねごとなどしているのだろうか。あれほど嫌っていたと思う「探偵」のことを書いているのはなぜだろう。
第二には、その「探偵」にはいりこんでいく作者について。
ひょっとすると漱石は、人のこころを「探偵」することの楽しみ……無論、それは小説という架空の世界においてであるが……に気付いたのかもしれない。この作品の後半の部分になると、登場人物のこころのうちを「探偵」として、観察し、のぞき見ているような気がしてならない。
そう思って読むと、この次の『行人』も、『こころ』も、人のこころのうちを「探偵」してさぐる物語であるとも読める。
以上の二点が、『彼岸過迄』を読んで思うことなどである。
さらに書けば、この作品のなかで印象的なのが、子ども(幼児)の死と葬儀のシーン。漱石の作品を読んでいくなかで、このところは、特別に印象に残るものと感じる。近代文学のなかで、「父」や「母」を描いたものは多くあると思うが、幼い幼児とその死を描いたものが、他にどれくらいあるだろうか。
また、この時代、子どもの死というものも、そんなに珍しいことではなかった、ということもあるかと思う。乳幼児死亡率が激減するのは、戦後になって近年になってからのことである。
それから、この作品中の女性、千代子が、女学生ことばをつかっている。漱石の作品中で、女学生ことばをつかう女性は、作品中で独特の位置にある。若い女性として、下女も登場するのだが、これは、別のことばをつかっている。おそらく「役割語」というような観点を導入して分析するならば、漱石の作品中での登場人物のことばというのは、かなり興味深いことになるかと思う。これは、おそらくは、文学研究と言語研究の両方にまたがった研究になるにちがいない。
ところで、この作品『彼岸過迄』は、まさに「彼岸過迄」ぐらいの連載になるということで、このタイトルになったようだ。特に、小説としての構想があったというのではないように思える。もし、最初から緻密に構想して書いたとするならば、どうも全体としてチグハグな印象の残る作品である。そうではなく、まさに作者(漱石)が書いているように、どのようなストーリーの展開になるか、特に決めたこともなく、思いつくままに書いていった結果が、このような小説になった。そして、それは、人のこころのうちを「探偵」する物語になった。このように思ってみる。
次は、順番に読んでいって『行人』である。
最近のコメント