新潮日本古典集成『源氏物語』(二) ― 2019-12-02
2019-12-02 當山日出夫(とうやまひでお)
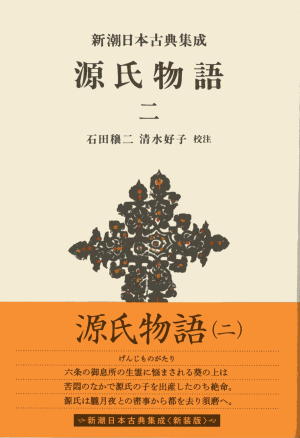
石田穣二・清水好子(校注).『源氏物語』(二)新潮日本古典集成(新装版).新潮社.2014
https://www.shinchosha.co.jp/book/620819/
続きである。
やまもも書斎記 2019年11月25日
新潮日本古典集成『源氏物語』(一)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/11/25/9181049
前回読んだ時のものは、
やまもも書斎記 2019年2月21日
『源氏物語』(二)新潮日本古典集成
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/02/21/9038816
『源氏物語』を再度読んでおきたいと思って(いや、再度ならず何度でもであるが)、新潮版で読んでいる。第二冊目である。「紅葉賀」から「明石」までをおさめる。
読んでいるのは、後期の講義の準備ということもある。『源氏物語』と「文字」というのは、どのような関係にあるのか、自分なりに読んで考えてみたかったからである。
第二冊目を読んで思うことは次の二点。
第一には、「文字」という語で「ことば」の意味につかってある用例が目につく。これは、とりもなおさず、『源氏物語』の世界が、「文字」の基盤の上になりたっていることを意味することになる。
第二には、『源氏物語』が、(現代風に言うならば)文字コミュニケーションの上に成立していることの確認である。歌を詠むとき、そのほとんどは、紙に書いたものとしてわたされている。そのとき、どのような筆跡であるか、どのような紙(料紙)であるかについても、言及がある。
以上の二点などが、第二冊目を読んで、自分なりに納得のいったところである。
ところで、須磨・明石に流謫の身となった光源氏は、京に残してきた紫の上と頻繁に手紙のやりとりをしている。また、それを、「日記」のようなものと表現した箇所もある。このようなところを読むと、文字・文書・消息が読めるものとして、その登場人物が造形されていることがわかる。
そういえば、まだ幼い紫の上に、光源氏が、手習いを教えるシーンがあった。「若紫」。
現在、われわれは、『源氏物語』を書かれた文学作品として享受している。文字に書かれることを前提としている。しかし、平安時代において、文字が書けた人はいったいどれほどいただろうか。おそらくは、一部の貴族層に限られていたと想像してまちがいないだろう。
「須磨」「明石」を読むと、現地の人びと(下層のといっていいだろう)については、「さへづる」と言っている。そのことばが、京の貴族たちのことばと違っているということである。
文学を読むとき、書かれたものしか残っていない。これは当然のことなのかもしれない。だが、その書くということが、日本語の、日本文学の歴史のなかで、どのような意味をもってきたものなのか、あらためて考えてみたいものである。
https://www.shinchosha.co.jp/book/620819/
続きである。
やまもも書斎記 2019年11月25日
新潮日本古典集成『源氏物語』(一)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/11/25/9181049
前回読んだ時のものは、
やまもも書斎記 2019年2月21日
『源氏物語』(二)新潮日本古典集成
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/02/21/9038816
『源氏物語』を再度読んでおきたいと思って(いや、再度ならず何度でもであるが)、新潮版で読んでいる。第二冊目である。「紅葉賀」から「明石」までをおさめる。
読んでいるのは、後期の講義の準備ということもある。『源氏物語』と「文字」というのは、どのような関係にあるのか、自分なりに読んで考えてみたかったからである。
第二冊目を読んで思うことは次の二点。
第一には、「文字」という語で「ことば」の意味につかってある用例が目につく。これは、とりもなおさず、『源氏物語』の世界が、「文字」の基盤の上になりたっていることを意味することになる。
第二には、『源氏物語』が、(現代風に言うならば)文字コミュニケーションの上に成立していることの確認である。歌を詠むとき、そのほとんどは、紙に書いたものとしてわたされている。そのとき、どのような筆跡であるか、どのような紙(料紙)であるかについても、言及がある。
以上の二点などが、第二冊目を読んで、自分なりに納得のいったところである。
ところで、須磨・明石に流謫の身となった光源氏は、京に残してきた紫の上と頻繁に手紙のやりとりをしている。また、それを、「日記」のようなものと表現した箇所もある。このようなところを読むと、文字・文書・消息が読めるものとして、その登場人物が造形されていることがわかる。
そういえば、まだ幼い紫の上に、光源氏が、手習いを教えるシーンがあった。「若紫」。
現在、われわれは、『源氏物語』を書かれた文学作品として享受している。文字に書かれることを前提としている。しかし、平安時代において、文字が書けた人はいったいどれほどいただろうか。おそらくは、一部の貴族層に限られていたと想像してまちがいないだろう。
「須磨」「明石」を読むと、現地の人びと(下層のといっていいだろう)については、「さへづる」と言っている。そのことばが、京の貴族たちのことばと違っているということである。
文学を読むとき、書かれたものしか残っていない。これは当然のことなのかもしれない。だが、その書くということが、日本語の、日本文学の歴史のなかで、どのような意味をもってきたものなのか、あらためて考えてみたいものである。
追記 2019-12-09
この続きは、
やまもも書斎記 2019年12月9日
新潮日本古典集成『源氏物語』(三)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/12/09/9186983
この続きは、
やまもも書斎記 2019年12月9日
新潮日本古典集成『源氏物語』(三)
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/12/09/9186983
最近のコメント