『死の家の記録』光文社古典新訳文庫 ― 2019-02-01
2019-02-01 當山日出夫(とうやまひでお)
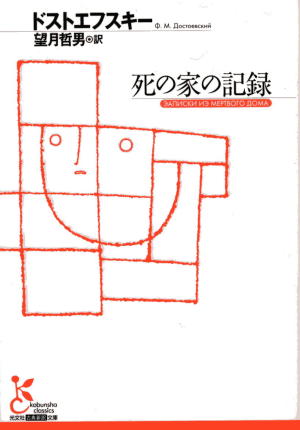
ドストエフスキー.望月哲男(訳).『死の家の記録』(光文社古典新訳文庫).光文社.2013
http://www.kotensinyaku.jp/books/book164.html
無論、フィクションとしての小説という形式で書いてあるので、文字通りこの作品に書いてあることをうけとめることはないだろうと思う。が、読んで、あの時代のロシアのシベリア流刑はこんなふうだったのかと、思わず納得するところがある。
この作品を読んで感じるところは、次の二点。
第一に、まさにシベリア流刑という境遇がどんなものであったかの興味・関心である。
その収容所の様子からはじまって、日常生活の細々したこと、食事とか入浴とか労働とか。また、病院がどんなであったのか、とか。
小説から離れて、歴史的な興味・関心で読んでみて、とても面白い。
第二に、収容所というところに入れられた人間でありながら、希望を捨てていないこと。
この作品に登場するのは、主に流刑の境遇にある人びとである。だが、いつかは、社会に復帰できるという望みを捨ててはいない。自暴自棄になることはない。絶望はない。言うならば、全編に感じることのできるヒューマニズムとでも言うべきものがある。
以上の二点が、この作品を読んで感じるところである。
ともあれ、ドストエフスキーの文学を理解するうえで、シベリア流刑ということは重要な意味をもっている。その体験を、どのように文学的に表現しているのか、ということでこの作品を読むことになる。この作品に流れているヒューマニズム……このような観点で、ドストエフスキーはシベリア流刑をとらえていたのか、これはとても貴重なことである。
それから、『罪と罰』で、最後、ラスコーリニコフは、シベリア流刑になるのだが……そこでの生活は、楽ではないかもしれないが、絶望するようなものではなかったろう、このような思いをいだくこともできる。
http://www.kotensinyaku.jp/books/book164.html
無論、フィクションとしての小説という形式で書いてあるので、文字通りこの作品に書いてあることをうけとめることはないだろうと思う。が、読んで、あの時代のロシアのシベリア流刑はこんなふうだったのかと、思わず納得するところがある。
この作品を読んで感じるところは、次の二点。
第一に、まさにシベリア流刑という境遇がどんなものであったかの興味・関心である。
その収容所の様子からはじまって、日常生活の細々したこと、食事とか入浴とか労働とか。また、病院がどんなであったのか、とか。
小説から離れて、歴史的な興味・関心で読んでみて、とても面白い。
第二に、収容所というところに入れられた人間でありながら、希望を捨てていないこと。
この作品に登場するのは、主に流刑の境遇にある人びとである。だが、いつかは、社会に復帰できるという望みを捨ててはいない。自暴自棄になることはない。絶望はない。言うならば、全編に感じることのできるヒューマニズムとでも言うべきものがある。
以上の二点が、この作品を読んで感じるところである。
ともあれ、ドストエフスキーの文学を理解するうえで、シベリア流刑ということは重要な意味をもっている。その体験を、どのように文学的に表現しているのか、ということでこの作品を読むことになる。この作品に流れているヒューマニズム……このような観点で、ドストエフスキーはシベリア流刑をとらえていたのか、これはとても貴重なことである。
それから、『罪と罰』で、最後、ラスコーリニコフは、シベリア流刑になるのだが……そこでの生活は、楽ではないかもしれないが、絶望するようなものではなかったろう、このような思いをいだくこともできる。
『白夜』ドストエフスキー ― 2019-02-02
2019-02-02 當山日出夫(とうやまひでお)

ドストエフスキー.安岡治子(訳).『白夜/おかしな人間の夢』(光文社古典新訳文庫).光文社.2015
http://www.kotensinyaku.jp/books/book207.html
光文社古典新訳文庫でドストエフスキーの作品を読んでいる。調べてみると、この『白夜』という作品は、他にもいくつかの訳がでている。ドストエフスキーの作品のなかでは、異色の短篇ということで有名らしい。
私が読んでみて感じるところとしては、次の二点だろうか。
第一には、この作品も、『貧しき人々』とおなじように、男女の会話、というよりも独白的な台詞のやりとりで進行する。ここに描き出される恋物語は、淡くはかなく、純情可憐である。『カラマーゾフの兄弟』や『悪霊』を書いた作家が、こんなふんわりとした印象をあたえる恋の物語を書いていたのかという、新鮮さがある。
これは深読みかもしれないのだが……独白的な台詞のやりとりのなかで、お互いに幻想がふくらんでいくような印象をいだく。いったいどこまでが本心、本当のことであり、また、どこからが、妄想とでもいうべき領域になるのか、その境目が混沌としている。
第二は、最後の二人の男女の別れのシーンのイメージの鮮烈さである。くっきりとした印象で、最後の別れの場面が描き出される。ドストエフスキーの作品は、視覚的なイメージのくっきりとた場面が強く印象に残る……たとえば『悪霊』の最後の場面など……この作品でも、かろやかな女性の動作が、きわめて印象的である。
以上の二点が、この『白夜』を読んで感じるところである。
ドストエフスキーの作品、調べてみると、文庫本などで他にも読める作品がある。長編では、『未成年』がある(これは、実は、まだ読んでいない)。が、光文社古典新訳文庫版では、この本でとりあえず出ているのは読んだことになる。これから、折りをみつけて、他の作品をふくめて、ドストエフスキーの作品を、再読、再々読と読んでいきたいと思う。
http://www.kotensinyaku.jp/books/book207.html
光文社古典新訳文庫でドストエフスキーの作品を読んでいる。調べてみると、この『白夜』という作品は、他にもいくつかの訳がでている。ドストエフスキーの作品のなかでは、異色の短篇ということで有名らしい。
私が読んでみて感じるところとしては、次の二点だろうか。
第一には、この作品も、『貧しき人々』とおなじように、男女の会話、というよりも独白的な台詞のやりとりで進行する。ここに描き出される恋物語は、淡くはかなく、純情可憐である。『カラマーゾフの兄弟』や『悪霊』を書いた作家が、こんなふんわりとした印象をあたえる恋の物語を書いていたのかという、新鮮さがある。
これは深読みかもしれないのだが……独白的な台詞のやりとりのなかで、お互いに幻想がふくらんでいくような印象をいだく。いったいどこまでが本心、本当のことであり、また、どこからが、妄想とでもいうべき領域になるのか、その境目が混沌としている。
第二は、最後の二人の男女の別れのシーンのイメージの鮮烈さである。くっきりとした印象で、最後の別れの場面が描き出される。ドストエフスキーの作品は、視覚的なイメージのくっきりとた場面が強く印象に残る……たとえば『悪霊』の最後の場面など……この作品でも、かろやかな女性の動作が、きわめて印象的である。
以上の二点が、この『白夜』を読んで感じるところである。
ドストエフスキーの作品、調べてみると、文庫本などで他にも読める作品がある。長編では、『未成年』がある(これは、実は、まだ読んでいない)。が、光文社古典新訳文庫版では、この本でとりあえず出ているのは読んだことになる。これから、折りをみつけて、他の作品をふくめて、ドストエフスキーの作品を、再読、再々読と読んでいきたいと思う。
『まんぷく』あれこれ「完成はもうすぐ!?」 ― 2019-02-03
2019-02-03 當山日出夫(とうやまひでお)
『まんぷく』第18週「完成はもうすぐ!?」
https://www.nhk.or.jp/mampuku/story/index18_190128.html
前回は、
やまもも書斎記 2019年1月27日
『まんぷく』あれこれ「ラーメンだ!福子!」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/01/27/9029292
萬平のインスタントラーメン(即席ラーメン)は、完成への道筋が見えてきたようである。
この週になって、本格的にインスタントラーメンの開発にとりかかる。お湯をかければできあがるラーメンということをめざして、スープの作り方、麺の作り方と、いろいろ試行錯誤を重ねることになる。見ていると、できあがってくるラーメンのスープも麺も、その色合いが、現在のチキンラーメンの色と似てくる。これは、インスタントラーメンの完成に向かって確実に歩んでいることを示しているのだろう。
特に大事件が起こるという展開ではなく、ただ、ひたすら萬平のラーメン開発に没頭する、そして、それを支える福子の描写がほとんどであった。そのラーメンもそう簡単にはできない。失敗の連続である。
ところで、インスタントラーメンの本筋と関係ない話しとしては、画家の忠彦のところで仕事をしているモデル(壇蜜)の登場が、なにやら不穏な感じがしないでもない。とはいえ、穏やかでないのは、妻の克子だけなのかもしれないが。
ともあれ、事件らしい事件もおこらない、ひたすらインスタントラーメンの開発だけに情熱をかたむける萬平と、それを支える福子のことだけで、このドラマは進行している。これはこれとして、脚本のたくみさなのだろうと思う。
そして、次週、いよいよインスタントラーメンの完成が見えてくるようだ。楽しみに見ることにしよう。
『まんぷく』第18週「完成はもうすぐ!?」
https://www.nhk.or.jp/mampuku/story/index18_190128.html
前回は、
やまもも書斎記 2019年1月27日
『まんぷく』あれこれ「ラーメンだ!福子!」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/01/27/9029292
萬平のインスタントラーメン(即席ラーメン)は、完成への道筋が見えてきたようである。
この週になって、本格的にインスタントラーメンの開発にとりかかる。お湯をかければできあがるラーメンということをめざして、スープの作り方、麺の作り方と、いろいろ試行錯誤を重ねることになる。見ていると、できあがってくるラーメンのスープも麺も、その色合いが、現在のチキンラーメンの色と似てくる。これは、インスタントラーメンの完成に向かって確実に歩んでいることを示しているのだろう。
特に大事件が起こるという展開ではなく、ただ、ひたすら萬平のラーメン開発に没頭する、そして、それを支える福子の描写がほとんどであった。そのラーメンもそう簡単にはできない。失敗の連続である。
ところで、インスタントラーメンの本筋と関係ない話しとしては、画家の忠彦のところで仕事をしているモデル(壇蜜)の登場が、なにやら不穏な感じがしないでもない。とはいえ、穏やかでないのは、妻の克子だけなのかもしれないが。
ともあれ、事件らしい事件もおこらない、ひたすらインスタントラーメンの開発だけに情熱をかたむける萬平と、それを支える福子のことだけで、このドラマは進行している。これはこれとして、脚本のたくみさなのだろうと思う。
そして、次週、いよいよインスタントラーメンの完成が見えてくるようだ。楽しみに見ることにしよう。
追記 2019-02-10
この続きは、
やまもも書斎記 2019年2月10日
『まんぷく』あれこれ「10歩も20歩も前進です!」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/02/10/9034402
この続きは、
やまもも書斎記 2019年2月10日
『まんぷく』あれこれ「10歩も20歩も前進です!」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/02/10/9034402
『君たちはどう生きるか』吉野源三郎 ― 2019-02-04
2019-02-04 當山日出夫(とうやまひでお)
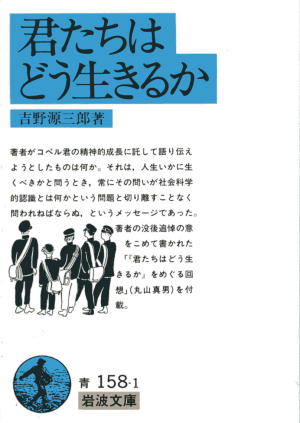
吉野源三郎.『君たちはどう生きるか』(岩波文庫).岩波書店.1982 (新潮社.1937)
https://www.iwanami.co.jp/book/b246154.html
話題になっている本ということで読んでみることにした。
この本が読まれる現代という時代が、ある意味でいびつなのかもしれないとも思うが、しかし、ここは、なるべく肯定的にこの本を読んでみたいと思う。
この本が最初に出たのは、1937(昭和12)年である。日中戦争のはじまったころということになる。
読んでみて、たしかにいい本だという気になる。今の時代、これほどストレートに、若者にどう生きるべきかを問いかける本は珍しいかもしれない。いや、今日においても、青少年向けの啓発本の類は多くある。教育関係の本もたくさんある。だが、現代のそれらとは、やはり趣を異にするところがあるように思える。そして、そこのところが、今、この本が読まれている理由であるのだろう。
それは、おそらく、現実をふまえながらも理想を語る、その精神のあり方にあるのだと感じる。
昭和のはじめごろ、戦前……社会においては、階級、階層ということが厳然としてあった。また、旧習になじんだままの硬直した組織というものがあった。そのような時代の背景の中において、個々の人間として、どのように生きるべきか、その理想を語っている。いや、理想が形になって表現されているというのではない。現実にある社会のなかで、どのように生きるべきか考えること、それ自体に価値がある、ここが重要なポイントになるのだろう。
おそらく、現代においてこの本が読まれているのは、社会の階層とか組織の中の人間とか、現代社会にも通じるところを読みとってのことだと思う。
が、それよりも私が、この本について感じる魅力は、その真面目さである。社会の中でいきることについて、コペル君も、おじさんも、きわめて真面目である。このような社会と人間について真面目に考えてみるということこそ、現代において失われてしまったものなのかもしれない。真面目に理想を語る、このことの意味を考えて見る必要があると感じるのである。
この本が今読まれているという現実から、今日の社会の病理を分析することも可能だろう。そのような読み方もあってよいと思う。が、今から八〇年ほど前に書かれたこの本の語らんとしたこと、その理想を素直に受けとめることもできる。私は、そのようにこの本を読んでおきたい。
https://www.iwanami.co.jp/book/b246154.html
話題になっている本ということで読んでみることにした。
この本が読まれる現代という時代が、ある意味でいびつなのかもしれないとも思うが、しかし、ここは、なるべく肯定的にこの本を読んでみたいと思う。
この本が最初に出たのは、1937(昭和12)年である。日中戦争のはじまったころということになる。
読んでみて、たしかにいい本だという気になる。今の時代、これほどストレートに、若者にどう生きるべきかを問いかける本は珍しいかもしれない。いや、今日においても、青少年向けの啓発本の類は多くある。教育関係の本もたくさんある。だが、現代のそれらとは、やはり趣を異にするところがあるように思える。そして、そこのところが、今、この本が読まれている理由であるのだろう。
それは、おそらく、現実をふまえながらも理想を語る、その精神のあり方にあるのだと感じる。
昭和のはじめごろ、戦前……社会においては、階級、階層ということが厳然としてあった。また、旧習になじんだままの硬直した組織というものがあった。そのような時代の背景の中において、個々の人間として、どのように生きるべきか、その理想を語っている。いや、理想が形になって表現されているというのではない。現実にある社会のなかで、どのように生きるべきか考えること、それ自体に価値がある、ここが重要なポイントになるのだろう。
おそらく、現代においてこの本が読まれているのは、社会の階層とか組織の中の人間とか、現代社会にも通じるところを読みとってのことだと思う。
が、それよりも私が、この本について感じる魅力は、その真面目さである。社会の中でいきることについて、コペル君も、おじさんも、きわめて真面目である。このような社会と人間について真面目に考えてみるということこそ、現代において失われてしまったものなのかもしれない。真面目に理想を語る、このことの意味を考えて見る必要があると感じるのである。
この本が今読まれているという現実から、今日の社会の病理を分析することも可能だろう。そのような読み方もあってよいと思う。が、今から八〇年ほど前に書かれたこの本の語らんとしたこと、その理想を素直に受けとめることもできる。私は、そのようにこの本を読んでおきたい。
『いだてん』あれこれ「雨ニモマケズ」 ― 2019-02-05
2019-02-05 當山日出夫(とうやまひでお)
『いだてん~東京オリムピック噺~』2019年2月3日、第5回「雨ニモマケズ」
https://www.nhk.or.jp/idaten/r/story/005/
前回は、
やまもも書斎記 2019年1月29日
『いだてん』あれこれ「小便小僧」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/01/29/9030061
この回になって、ようやく第一回の放送にストーリーが回収されてきたことになる。羽田でのオリンピック選手選考である。そのマラソンで、四三は優勝する。しかも、世界記録であるという。
このあたり、もうちょっと国威高揚……というか、ある意味でのナショナリズムというか、を感じさせる描き方ができたのかもしれないが、まったくそんな雰囲気は無かった。なんだか、どんちゃんさわぎのなかで、競技がおこなわれ、選手が決まったようである。はては、嘉納治五郎までが、天狗倶楽部の面々と一緒になって、うかれさわいでいた。
まあ、一つには、ようやく「一等国」になったとはいえ、一般庶民の視線からみれば、オリンピックはおろか、スポーツというものさえ、いったいなんだかわからない時代だったのだろう。わけがわからないままに、なんとなく勢いにまかせて出場することになったのが、ストックホルム大会ということになる。
今のところ、スポーツとは無縁ところにいるのが、足袋を作っている播磨屋の店主(ピエール瀧)である。これから、四三のマラソンをささえるであろう足袋を作ることになるはずだが、今のところ、自分の作った足袋に不満を言われて憤っている。
それから、やはり志ん生。ようやく落語家の弟子入りがかなったところ。スポーツにも、オリンピックにも、関心はないようだ。その志ん生が、なぜ、1964年の東京オリンピック招致までの話しを、高座で語ることになるのか、そのわけというのはまだ描かれていない。
ともあれ、オリンピックには、その時の国際情勢、また、参加国のナショナリズムというものが、どうしてもつきまとう。それを、無理に振り払おうとしているドラマの作り方であることは理解できるのだが、それが、見ていて面白いかどうかは、また別である。(私は、今のところ、これはこれで一つの作り方だと思って見ているのだが。)
スポーツに打ち込む若者の純真な姿を肯定的に描くことと、ナショナリズムを払拭して描くこと、このところを、これからこのドラマはどう描いていくことになるのだろうか。宮藤官九郎の脚本に期待して見ることにしよう。
『いだてん~東京オリムピック噺~』2019年2月3日、第5回「雨ニモマケズ」
https://www.nhk.or.jp/idaten/r/story/005/
前回は、
やまもも書斎記 2019年1月29日
『いだてん』あれこれ「小便小僧」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/01/29/9030061
この回になって、ようやく第一回の放送にストーリーが回収されてきたことになる。羽田でのオリンピック選手選考である。そのマラソンで、四三は優勝する。しかも、世界記録であるという。
このあたり、もうちょっと国威高揚……というか、ある意味でのナショナリズムというか、を感じさせる描き方ができたのかもしれないが、まったくそんな雰囲気は無かった。なんだか、どんちゃんさわぎのなかで、競技がおこなわれ、選手が決まったようである。はては、嘉納治五郎までが、天狗倶楽部の面々と一緒になって、うかれさわいでいた。
まあ、一つには、ようやく「一等国」になったとはいえ、一般庶民の視線からみれば、オリンピックはおろか、スポーツというものさえ、いったいなんだかわからない時代だったのだろう。わけがわからないままに、なんとなく勢いにまかせて出場することになったのが、ストックホルム大会ということになる。
今のところ、スポーツとは無縁ところにいるのが、足袋を作っている播磨屋の店主(ピエール瀧)である。これから、四三のマラソンをささえるであろう足袋を作ることになるはずだが、今のところ、自分の作った足袋に不満を言われて憤っている。
それから、やはり志ん生。ようやく落語家の弟子入りがかなったところ。スポーツにも、オリンピックにも、関心はないようだ。その志ん生が、なぜ、1964年の東京オリンピック招致までの話しを、高座で語ることになるのか、そのわけというのはまだ描かれていない。
ともあれ、オリンピックには、その時の国際情勢、また、参加国のナショナリズムというものが、どうしてもつきまとう。それを、無理に振り払おうとしているドラマの作り方であることは理解できるのだが、それが、見ていて面白いかどうかは、また別である。(私は、今のところ、これはこれで一つの作り方だと思って見ているのだが。)
スポーツに打ち込む若者の純真な姿を肯定的に描くことと、ナショナリズムを払拭して描くこと、このところを、これからこのドラマはどう描いていくことになるのだろうか。宮藤官九郎の脚本に期待して見ることにしよう。
追記 2019-02-12
この続きは、
やまもも書斎記 2019年2月12日
『いだてん』あれこれ「お江戸日本橋」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/02/12/9035214
この続きは、
やまもも書斎記 2019年2月12日
『いだてん』あれこれ「お江戸日本橋」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/02/12/9035214
梅の冬芽 ― 2019-02-06
2019-02-06 當山日出夫(とうやまひでお)
水曜日なので花の写真。今日は梅であるが、まだ花は咲いていない。冬芽の様子である。
前回は、
やまもも書斎記 2019年1月30日
雑木林の冬
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/01/30/9030377
我が家の庭に一本の梅の木がある。老木である。毎年、花を咲かせるのだが、その時期はかなり遅くなってからである。ニュースなどで、梅の開花の便りを目にするようになってから、ようやく咲き始める。紅梅である。
その梅の冬芽の様子を写してみた。今年の冬は比較的あたたかいせいだろうか、去年に比べて、その冬芽の色の変化が早いように思う。見ると、その冬芽が、なんとなく紅色に色がついてきているのがわかる。
撮影した日の前日は雨だった。まだ、前夜の雨に濡れているのが見てとれる。朝のうちにカメラと三脚を持って庭に出て写したものである。
カメラは、NikonのD500である。D7500を持っているのだが、いろいろ考えて新しく買うことにした。モデルとしては、D7500より古い機種にはなる。だが、NikonのDXカメラのなかでは、最上位に位置する機種になる。使ってみると、やはり操作性がいい。Nikonのフラッグシップ機である、D5の操作性をうけついでいる。特にフォーカスポイントの選択がやりやすい。私のように花の写真の接写が多い場合には、この機能は非常に重宝する。
来月には、この梅の木に花の咲いた状態の写真を写せるかと思っている。
水曜日なので花の写真。今日は梅であるが、まだ花は咲いていない。冬芽の様子である。
前回は、
やまもも書斎記 2019年1月30日
雑木林の冬
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/01/30/9030377
我が家の庭に一本の梅の木がある。老木である。毎年、花を咲かせるのだが、その時期はかなり遅くなってからである。ニュースなどで、梅の開花の便りを目にするようになってから、ようやく咲き始める。紅梅である。
その梅の冬芽の様子を写してみた。今年の冬は比較的あたたかいせいだろうか、去年に比べて、その冬芽の色の変化が早いように思う。見ると、その冬芽が、なんとなく紅色に色がついてきているのがわかる。
撮影した日の前日は雨だった。まだ、前夜の雨に濡れているのが見てとれる。朝のうちにカメラと三脚を持って庭に出て写したものである。
カメラは、NikonのD500である。D7500を持っているのだが、いろいろ考えて新しく買うことにした。モデルとしては、D7500より古い機種にはなる。だが、NikonのDXカメラのなかでは、最上位に位置する機種になる。使ってみると、やはり操作性がいい。Nikonのフラッグシップ機である、D5の操作性をうけついでいる。特にフォーカスポイントの選択がやりやすい。私のように花の写真の接写が多い場合には、この機能は非常に重宝する。
来月には、この梅の木に花の咲いた状態の写真を写せるかと思っている。
Nikon D500
AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED
AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED
『感情教育』フローベール ― 2019-02-07
2019-02-07 當山日出夫(とうやまひでお)
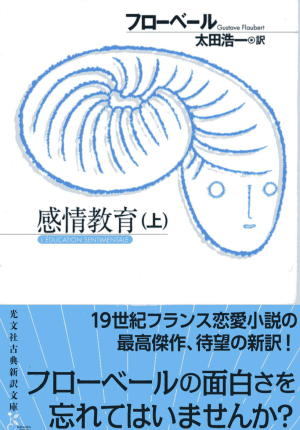
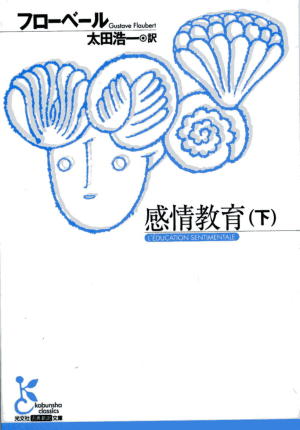
フローベール.太田浩一(訳).『感情教育』上・下(光文社古典新訳文庫).光文社.2014
https://www.kobunsha.com/shelf/book/isbn/9784334753009
https://www.kobunsha.com/shelf/book/isbn/9784334753030
ドストエフスキーを読んでいって、ふとフランス近代の小説を読んでみたくなった。十九世紀自然主義文学である。単なる気まぐれであるが。フローベールを、読んでおきたくなった。
その『ボヴァリー夫人』は、以前に読んでいる。が、これも別の訳で読み直してみることにして、(これについては、また別に書くつもり)、『ボヴァリー夫人』と並んで名高い『感情教育』を読んでみることにした。実は、この作品は、まだ読んでいない本であった。
読んでみて感じるところは……次の二点になるだろうか。
第一には、近代自然主義文学ということになるのであるが、どうも、この小説の主人公の恋愛感には、ついていけない。この主人公、同時に二人の女性と恋をしている。この感覚が、現代の我々の恋愛感覚からすると、どうにも理解できない。
まあ、この時代のこの人びとの恋とはこのようなものであると言われればそれまでである。しかし、今ひとつ、主人公の感情に共感できないままで終わってしまった。
第二には、この小説の歴史的背景である。フランス革命後の二月革命の時のことを背景にしてある。このあたりのことも、昔、高校でならった世界史の知識をそう越えるものではない私としては、手にあまる。このような読者のことを思ってであろうが、上巻の始めに、この小説の歴史的背景について解説がある。読んではみるのだが、もうこの年になってからでは、すんなりと頭におさまらない。
もうすこし、近代ヨーロッパ史の知識を勉強しておくべきであった。歴史の勉強というよりも、近代の西欧の文学作品を理解するためにも、歴史の知識は必要である。そう思ってはみるものの、もう手遅れにちかい・・・
以上の二点が、『感情教育』を読んでみて感じるところである。あるいは、フランス語に堪能ならば、そして、近代のフランスの歴史の知識が十分にあるのならば、原文で読んで面白く読める作品なのであろうとは思う。
https://www.kobunsha.com/shelf/book/isbn/9784334753009
https://www.kobunsha.com/shelf/book/isbn/9784334753030
ドストエフスキーを読んでいって、ふとフランス近代の小説を読んでみたくなった。十九世紀自然主義文学である。単なる気まぐれであるが。フローベールを、読んでおきたくなった。
その『ボヴァリー夫人』は、以前に読んでいる。が、これも別の訳で読み直してみることにして、(これについては、また別に書くつもり)、『ボヴァリー夫人』と並んで名高い『感情教育』を読んでみることにした。実は、この作品は、まだ読んでいない本であった。
読んでみて感じるところは……次の二点になるだろうか。
第一には、近代自然主義文学ということになるのであるが、どうも、この小説の主人公の恋愛感には、ついていけない。この主人公、同時に二人の女性と恋をしている。この感覚が、現代の我々の恋愛感覚からすると、どうにも理解できない。
まあ、この時代のこの人びとの恋とはこのようなものであると言われればそれまでである。しかし、今ひとつ、主人公の感情に共感できないままで終わってしまった。
第二には、この小説の歴史的背景である。フランス革命後の二月革命の時のことを背景にしてある。このあたりのことも、昔、高校でならった世界史の知識をそう越えるものではない私としては、手にあまる。このような読者のことを思ってであろうが、上巻の始めに、この小説の歴史的背景について解説がある。読んではみるのだが、もうこの年になってからでは、すんなりと頭におさまらない。
もうすこし、近代ヨーロッパ史の知識を勉強しておくべきであった。歴史の勉強というよりも、近代の西欧の文学作品を理解するためにも、歴史の知識は必要である。そう思ってはみるものの、もう手遅れにちかい・・・
以上の二点が、『感情教育』を読んでみて感じるところである。あるいは、フランス語に堪能ならば、そして、近代のフランスの歴史の知識が十分にあるのならば、原文で読んで面白く読める作品なのであろうとは思う。
追記 2019-02-08
『ボヴァリー夫人』については、
やまもも書斎記 2019年2月8日
『ボヴァリー夫人』フロベール
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/02/08/9033686
『ボヴァリー夫人』については、
やまもも書斎記 2019年2月8日
『ボヴァリー夫人』フロベール
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/02/08/9033686
『ボヴァリー夫人』フロベール ― 2019-02-08
2019-02-08 當山日出夫(とうやまひでお)

フロベール.山田𣝣(訳).『ボヴァリー夫人』(「世界の文学」15).中央公論社.1965
『感情教育』を新しい訳で読んで、次に手にしてみたのが、『ボヴァリー夫人』である。
やまもも書斎記 2019年2月7日
『感情教育』フローベール
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/02/07/9033293
『ボヴァリー夫人』は、以前に新潮文庫の訳で読んでいる。
やまもも書斎記 2017年6月16日
『ボヴァリー夫人』フローベール
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2017/06/16/8598263
二年前に読んだことになる。今回は、古い訳になるが、中央公論社の「世界の文学」を古書で買って読むことにした。訳が変わるとまた印象も変わるかと思って。
この古い訳で読んでみてであるが、ようやく『ボヴァリー夫人』という小説が、世界文学のなかで、特に十九世紀フランスの自然主義文学のなかで、特に評価の高い理由がわかったような気がする。
なるほど、ボヴァリー夫人(エンマ)とは、こんなふうに考える女性であったのかと、どうにか、その心情によりそう形で、小説が読めたように思う。といって、エンマの気持ちが十分に理解できたというのではない。が、少なくとも、小説を読んでいって、その心理の動きをたどることができた。フランスの自然主義文学ということである。ここは、とにかく主人公の心理の流れを自分のなかに感じ取らないでは読んだことにならないだろう。
はっきり言って、『感情教育』は読んでよく分からなかった。その主人公の心理についていけなかったと言ってよい。だが、今回、『ボヴァリー夫人』については、どうにか、主人公のエンマの気持ちの動きに、読んでいってついていけたように感じる。(といって、エンマの行為に賛成するということではないが。)
読んでいて、ふと小説中のエンマの心のうちによりそってしまっていることに気付くことがあった。こういうのを自然主義文学というのだなと得心する。
この作品、また時間をおいて再々度、読み返してみたい作品である。登場人物の心のうちによりそって読むことこそ、文学を読む楽しみである。
『感情教育』を新しい訳で読んで、次に手にしてみたのが、『ボヴァリー夫人』である。
やまもも書斎記 2019年2月7日
『感情教育』フローベール
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/02/07/9033293
『ボヴァリー夫人』は、以前に新潮文庫の訳で読んでいる。
やまもも書斎記 2017年6月16日
『ボヴァリー夫人』フローベール
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2017/06/16/8598263
二年前に読んだことになる。今回は、古い訳になるが、中央公論社の「世界の文学」を古書で買って読むことにした。訳が変わるとまた印象も変わるかと思って。
この古い訳で読んでみてであるが、ようやく『ボヴァリー夫人』という小説が、世界文学のなかで、特に十九世紀フランスの自然主義文学のなかで、特に評価の高い理由がわかったような気がする。
なるほど、ボヴァリー夫人(エンマ)とは、こんなふうに考える女性であったのかと、どうにか、その心情によりそう形で、小説が読めたように思う。といって、エンマの気持ちが十分に理解できたというのではない。が、少なくとも、小説を読んでいって、その心理の動きをたどることができた。フランスの自然主義文学ということである。ここは、とにかく主人公の心理の流れを自分のなかに感じ取らないでは読んだことにならないだろう。
はっきり言って、『感情教育』は読んでよく分からなかった。その主人公の心理についていけなかったと言ってよい。だが、今回、『ボヴァリー夫人』については、どうにか、主人公のエンマの気持ちの動きに、読んでいってついていけたように感じる。(といって、エンマの行為に賛成するということではないが。)
読んでいて、ふと小説中のエンマの心のうちによりそってしまっていることに気付くことがあった。こういうのを自然主義文学というのだなと得心する。
この作品、また時間をおいて再々度、読み返してみたい作品である。登場人物の心のうちによりそって読むことこそ、文学を読む楽しみである。
『紫文要領』本居宣長 ― 2019-02-09
2019-02-09 當山日出夫(とうやまひでお)

日野龍夫(校注).『本居宣長集』(新潮日本古典集成 新装版).新潮社.2018
https://www.shinchosha.co.jp/book/620878/
去年、「本居宣長」という本をいくつか読んだ。これは、その時に読もうと思って買っておいたものである。その後、『失われた時を求めて』を読んだり、ドストエフスキーを読んだりしていた。手元にあった本なので、何気なく読み始めた。
『紫文要領』……これは、本居宣長の物語論、もののあはれ論、源氏物語論を代表する著作である。
読んで思うことは次の三点になるだろうか。
第一に、江戸時代の国学という学問の中に、それまでの古典研究が流れ込んでいることの確認である。無論、宣長は、旧来の伝統的な勧善懲悪的物語解釈をしりぞけている。この意味では、従来の研究を否定しているのだが、それだけではない。やはり、この著作の中には、中世以来、『源氏物語』を読んできた歴史的経緯というものが、集約されている。ただ、それが、否定的文脈で言及されることが多いので、「物の哀」という宣長の主張が全面に出たような印象となっているだけのことである。
第二に、宣長の独創というべき「物の哀」論である。物語、特に、『源氏物語』を読むとき、そこに「物の哀」を感じてこそ読んだことになる、この宣長の「発明」とでもいうべき、「物の哀」論には、なるほどと感じ入るところがある。
第三に、「物の哀」論に見られるような、主情主義・情緒主義的文芸理解、これが、特に宣長の独創というべきではなく、広く近世の儒学……例えば、荻生徂徠など……においても、指摘できることである。これは、主に、この校注本の注釈や解説によることになる。
以上の三点が、『紫文要領』を読んで、私の感じ取ったところである。
この本を読んでみて、『源氏物語』を読んでおきたくなった。私も、もう還暦は過ぎた。が、古希にはまだいくぶんの年月が残されている。まだ、元気で本が読めるうちに読んでおきたい本というものがある。『源氏物語』もその一つ。去年読んだ『失われた時を求めて』もそうである。
『源氏物語』は、若い時に、一通り読んでいる。古い岩波の古典大系で読んだ。だが、順番に「桐壺」の巻から読むということはなかった。「若菜」の巻を中心にして……『源氏物語』は「若菜」の巻をきちんと読んでおけば理解できるというのが、習った池田彌三郎先生の言っていたことである……紫上系の巻、玉鬘系の巻、そして、宇治十帖と読んでいったかと憶えている。
国語学というようなことを勉強してきたので、日本国語大辞典などをひいて、用例をとして、『源氏物語』を目にすることは日常的にあった。そして、今では、国立国語研究所の歴史コーパスで、『源氏物語』を自在にあつかうことができるようになっている。
『源氏物語』は、「桐壺」から順番に自分の目で読んでおきたい、そう思う。もう、老後の読書である。『源氏物語』を読んで、論文を書こうという気はない。ただ、自分自身のための読書として読んでおきたいのである。
本居宣長『紫文要領』を手がかりとして、『源氏物語』を読むことにしたい。
https://www.shinchosha.co.jp/book/620878/
去年、「本居宣長」という本をいくつか読んだ。これは、その時に読もうと思って買っておいたものである。その後、『失われた時を求めて』を読んだり、ドストエフスキーを読んだりしていた。手元にあった本なので、何気なく読み始めた。
『紫文要領』……これは、本居宣長の物語論、もののあはれ論、源氏物語論を代表する著作である。
読んで思うことは次の三点になるだろうか。
第一に、江戸時代の国学という学問の中に、それまでの古典研究が流れ込んでいることの確認である。無論、宣長は、旧来の伝統的な勧善懲悪的物語解釈をしりぞけている。この意味では、従来の研究を否定しているのだが、それだけではない。やはり、この著作の中には、中世以来、『源氏物語』を読んできた歴史的経緯というものが、集約されている。ただ、それが、否定的文脈で言及されることが多いので、「物の哀」という宣長の主張が全面に出たような印象となっているだけのことである。
第二に、宣長の独創というべき「物の哀」論である。物語、特に、『源氏物語』を読むとき、そこに「物の哀」を感じてこそ読んだことになる、この宣長の「発明」とでもいうべき、「物の哀」論には、なるほどと感じ入るところがある。
第三に、「物の哀」論に見られるような、主情主義・情緒主義的文芸理解、これが、特に宣長の独創というべきではなく、広く近世の儒学……例えば、荻生徂徠など……においても、指摘できることである。これは、主に、この校注本の注釈や解説によることになる。
以上の三点が、『紫文要領』を読んで、私の感じ取ったところである。
この本を読んでみて、『源氏物語』を読んでおきたくなった。私も、もう還暦は過ぎた。が、古希にはまだいくぶんの年月が残されている。まだ、元気で本が読めるうちに読んでおきたい本というものがある。『源氏物語』もその一つ。去年読んだ『失われた時を求めて』もそうである。
『源氏物語』は、若い時に、一通り読んでいる。古い岩波の古典大系で読んだ。だが、順番に「桐壺」の巻から読むということはなかった。「若菜」の巻を中心にして……『源氏物語』は「若菜」の巻をきちんと読んでおけば理解できるというのが、習った池田彌三郎先生の言っていたことである……紫上系の巻、玉鬘系の巻、そして、宇治十帖と読んでいったかと憶えている。
国語学というようなことを勉強してきたので、日本国語大辞典などをひいて、用例をとして、『源氏物語』を目にすることは日常的にあった。そして、今では、国立国語研究所の歴史コーパスで、『源氏物語』を自在にあつかうことができるようになっている。
『源氏物語』は、「桐壺」から順番に自分の目で読んでおきたい、そう思う。もう、老後の読書である。『源氏物語』を読んで、論文を書こうという気はない。ただ、自分自身のための読書として読んでおきたいのである。
本居宣長『紫文要領』を手がかりとして、『源氏物語』を読むことにしたい。
追記 2019-02-18
この続きは、
やまもも書斎記 2019年2月18日
『源氏物語』(一)新潮日本古典集成
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/02/18/9037548
この続きは、
やまもも書斎記 2019年2月18日
『源氏物語』(一)新潮日本古典集成
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/02/18/9037548
『まんぷく』あれこれ「10歩も20歩も前進です!」 ― 2019-02-10
2019-02-10 當山日出夫(とうやまひでお)
『まんぷく』第19週「10歩も20歩も前進です!」
https://www.nhk.or.jp/mampuku/story/index19_190204.html
前回は、
やまもも書斎記 2019年2月3日
『まんぷく』あれこれ「完成はもうすぐ!?」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/02/03/9031798
やっとインスタントラーメンの完成のヒントを得たようだ。
この週も、インスタントラーメンの開発の試行錯誤の展開だった。いろいろと試してみるが、どれもうまくいかない。麺の乾燥法にどうやら問題があるらしい、というあたりまではなんとかこぎつけた。
土曜日、最後のシーンは、福子が天ぷらを揚げるのを見ていた萬平がひらめくところでおわっていた。次週、おそらく、この油をつかった方法でもって、インスタントラーメンの完成ということになるのかもしれない。
ところで、克子のところの話し。モデルでやってきていた秀子(壇蜜)によって、忠彦の画風が一変してしまった。ここのところの経緯が、インスタントラーメンの開発の話しに混じって、うまく描かれていたように思う。
萬平は、やはり「ものづくり」の人間である。研究所で働いているときの萬平の姿が、生き生きと描かれていた。そして、失敗しても、それは、一つの事例の積み重ねとして、次への一歩になるという、前向きの姿勢が、見ていて好ましい。見ている人間に、生きていく元気を与えてくれる。
次週、いよいよ、インスタントラーメンが完成することになると思われる。どんなラーメンができあがるのか、楽しみに見ることにしよう。
『まんぷく』第19週「10歩も20歩も前進です!」
https://www.nhk.or.jp/mampuku/story/index19_190204.html
前回は、
やまもも書斎記 2019年2月3日
『まんぷく』あれこれ「完成はもうすぐ!?」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/02/03/9031798
やっとインスタントラーメンの完成のヒントを得たようだ。
この週も、インスタントラーメンの開発の試行錯誤の展開だった。いろいろと試してみるが、どれもうまくいかない。麺の乾燥法にどうやら問題があるらしい、というあたりまではなんとかこぎつけた。
土曜日、最後のシーンは、福子が天ぷらを揚げるのを見ていた萬平がひらめくところでおわっていた。次週、おそらく、この油をつかった方法でもって、インスタントラーメンの完成ということになるのかもしれない。
ところで、克子のところの話し。モデルでやってきていた秀子(壇蜜)によって、忠彦の画風が一変してしまった。ここのところの経緯が、インスタントラーメンの開発の話しに混じって、うまく描かれていたように思う。
萬平は、やはり「ものづくり」の人間である。研究所で働いているときの萬平の姿が、生き生きと描かれていた。そして、失敗しても、それは、一つの事例の積み重ねとして、次への一歩になるという、前向きの姿勢が、見ていて好ましい。見ている人間に、生きていく元気を与えてくれる。
次週、いよいよ、インスタントラーメンが完成することになると思われる。どんなラーメンができあがるのか、楽しみに見ることにしよう。
追記 2019-02-17
この続きは、
やまもも書斎記 2019年2月7日
『まんぷく』あれこれ「できたぞ!福子!」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/02/17/9037049
この続きは、
やまもも書斎記 2019年2月7日
『まんぷく』あれこれ「できたぞ!福子!」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/02/17/9037049





最近のコメント