『青天を衝け』あれこれ「栄一、海を越えて」 ― 2021-12-21
2021-12-21 當山日出夫(とうやまひでお)
『青天を衝け』第40回「栄一、海を越えて」
https://www.nhk.or.jp/seiten/story/40/
前回は、
やまもも書斎記 2021年12月14日
『青天を衝け』あれこれ「栄一と戦争」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2021/12/14/9447855
この回で描いていたのは、渋沢栄一の民間外交。
晩年の渋沢栄一は、日米の民間外交に尽力した。そのことは、知られていることだと思うが、さて、これは果たして成果があったというべきなのだろうか。いや、そのようなことよりも、渋沢栄一のような努力をはらう人物が、かつての日本には存在したということの方が重要なことであろう。
ただ、あえて批判的に見るならばであるが……渋沢栄一が日米の民間外交に力をつくしたのは、主に移民をめぐる問題においてであった。だが、なぜ、明治から大正の日本から、そんなに多くの移民がアメリカに渡ったのか、その歴史的背景についての描写がなかったのが恨まれる。日本から、アメリカ以外の国へも移民は行っているはずなのだが、なぜ、アメリカにおいて、大きな問題になったのか。ここのところの、日本における事情、アメリカにおける事情、それぞれについて、もう少し説明があった方がよかったのではないだろうか。これは、今日にもつながる、日本の対米感情、また、アメリカの対日感情の源泉でもあろう。ただ、勤勉な日本人が排斥されただけではなかったろう。(あるいは、あえてここのところについては、説明は避けるという方針であったのだろうか。)
この回で、徳川慶喜が亡くなる。大正の初めである。喜作も亡くなる。そして、いよいよ次週が最終回ということになる。徳川家康も出ていたが、最終回も登場するのだろうか。ともあれ、このドラマは、年初のスタートが少し遅れ、さらに、オリンピック、パラリンピックと中断もあった。それでも、どうにか、渋沢栄一の最晩年までを描いてきた。
近代の日本をドラマでどう描くか、いろいろと興味関心のあったところである。それに、こたえてくれるドラマになっていたかと思う。(まあ、その歴史観に批判がないわけではないが。)
最終回を楽しみに見ることにしよう。
2021年12月20日記
『青天を衝け』第40回「栄一、海を越えて」
https://www.nhk.or.jp/seiten/story/40/
前回は、
やまもも書斎記 2021年12月14日
『青天を衝け』あれこれ「栄一と戦争」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2021/12/14/9447855
この回で描いていたのは、渋沢栄一の民間外交。
晩年の渋沢栄一は、日米の民間外交に尽力した。そのことは、知られていることだと思うが、さて、これは果たして成果があったというべきなのだろうか。いや、そのようなことよりも、渋沢栄一のような努力をはらう人物が、かつての日本には存在したということの方が重要なことであろう。
ただ、あえて批判的に見るならばであるが……渋沢栄一が日米の民間外交に力をつくしたのは、主に移民をめぐる問題においてであった。だが、なぜ、明治から大正の日本から、そんなに多くの移民がアメリカに渡ったのか、その歴史的背景についての描写がなかったのが恨まれる。日本から、アメリカ以外の国へも移民は行っているはずなのだが、なぜ、アメリカにおいて、大きな問題になったのか。ここのところの、日本における事情、アメリカにおける事情、それぞれについて、もう少し説明があった方がよかったのではないだろうか。これは、今日にもつながる、日本の対米感情、また、アメリカの対日感情の源泉でもあろう。ただ、勤勉な日本人が排斥されただけではなかったろう。(あるいは、あえてここのところについては、説明は避けるという方針であったのだろうか。)
この回で、徳川慶喜が亡くなる。大正の初めである。喜作も亡くなる。そして、いよいよ次週が最終回ということになる。徳川家康も出ていたが、最終回も登場するのだろうか。ともあれ、このドラマは、年初のスタートが少し遅れ、さらに、オリンピック、パラリンピックと中断もあった。それでも、どうにか、渋沢栄一の最晩年までを描いてきた。
近代の日本をドラマでどう描くか、いろいろと興味関心のあったところである。それに、こたえてくれるドラマになっていたかと思う。(まあ、その歴史観に批判がないわけではないが。)
最終回を楽しみに見ることにしよう。
2021年12月20日記
追記 2021年12月28日
この続きは、
やまもも書斎記 2021年12月28日
『青天を衝け』あれこれ「青春はつづく」
https://yamamomo.asablo.jp/blog/2021/12/28/9451374
この続きは、
やまもも書斎記 2021年12月28日
『青天を衝け』あれこれ「青春はつづく」
https://yamamomo.asablo.jp/blog/2021/12/28/9451374
紅葉 ― 2021-12-22
2021-12-22 當山日出夫(とうやまひでお)
水曜日は写真の日。今日は紅葉である。
前回は、
やまもも書斎記 2021年12月15日
ピラカンサ
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2021/12/15/9448088
例年通りに、だいたい一一月の下旬から一二月の上旬にかけて、我が家のもみじは紅葉する。毎年、写真に撮っているが、今年は望遠レンズ(150-600mm)を使ってみた。去年までは、70-300mmを使っていた。
我が家の紅葉を見ていると、朝の時間帯の方がきれいに見える。ちょうど、NHKの朝ドラが終わったぐらいの時間に庭にでると、朝日があたっている。それを、逆光で見ると、もみじの紅葉した葉が光に透けてみえる。
テレビのニュースなどで、どこそこの紅葉が見頃であるとかいうようになると、我が家のもみじも色づき始める。特に遅いことも早いこともないようである。そんなに見事に紅葉しているとは思わないが、そこは写真に撮ると、なんとなく綺麗に見えるものである。
冬になって花の姿が少なくなった。我が家で咲いている花といえば、山茶花と椿ぐらいであろうか。春になるまで花を見ることはないが、冬は冬の景色を写していきたいと思う。
水曜日は写真の日。今日は紅葉である。
前回は、
やまもも書斎記 2021年12月15日
ピラカンサ
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2021/12/15/9448088
例年通りに、だいたい一一月の下旬から一二月の上旬にかけて、我が家のもみじは紅葉する。毎年、写真に撮っているが、今年は望遠レンズ(150-600mm)を使ってみた。去年までは、70-300mmを使っていた。
我が家の紅葉を見ていると、朝の時間帯の方がきれいに見える。ちょうど、NHKの朝ドラが終わったぐらいの時間に庭にでると、朝日があたっている。それを、逆光で見ると、もみじの紅葉した葉が光に透けてみえる。
テレビのニュースなどで、どこそこの紅葉が見頃であるとかいうようになると、我が家のもみじも色づき始める。特に遅いことも早いこともないようである。そんなに見事に紅葉しているとは思わないが、そこは写真に撮ると、なんとなく綺麗に見えるものである。
冬になって花の姿が少なくなった。我が家で咲いている花といえば、山茶花と椿ぐらいであろうか。春になるまで花を見ることはないが、冬は冬の景色を写していきたいと思う。
Nikon D500
TAMRON SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2
2021年12月20日記
『同志少女よ、敵を撃て』逢坂冬馬 ― 2021-12-23
2021年12月23日 當山日出夫(とうやまひでお)

逢坂冬馬.『同志少女よ、敵を撃て』.早川書房.2021
https://www.hayakawa-online.co.jp/shopdetail/000000014980/
これがデビュー作であるという。おどろくしかない。
主な舞台は、第二次世界大戦のころのソ連と東欧。独ソ戦である。ソ連軍において、女性だけで組織された狙撃兵部隊。そこに加わることになる少女、セラフィマ。過酷な訓練の後、独ソ戦の激戦地を転戦する。そして、最後にめぐりあうことになる仇敵。
久々に読んだ戦争冒険小説である。最近では、戦争冒険小説、戦争ミステリ、という範疇の作品が少なくなったように思う。
だが、これはただの戦争冒険小説ではない。少女が主人公であり、狙撃兵であり、ソ連軍として独ソ戦を戦う。そこにある、友情、軍人としての職務、憎しみ、悲しみ……ありとあらゆる感情をのみこんで、少女は戦場にたつ。
この作品、アガサ・クリスティー賞の大賞受賞作ということだが、他にも賞を取るにちがいない。(すくなくとも、これを書いている時点では、直木賞の候補になっている。)
この小説が傑出しているのは、その戦争観にあるといってもいいかもしれない。女性の目、少女の目から、そして、ソ連の目から、独ソ戦を見ている。そこには、冷徹な狙撃兵としての闘志もあれば、女性としての感情もある。そして、何よりも重要だと思うのは、戦争と性の問題を避けてはいない。いったい戦場で何があったのか、冷静に見る視点がある。
また、独ソ戦をソ連の側から描くといっても、必ずしも、ナチス=悪、という図式になっていない。ソ連共産党賛美でも忌避でもない。ソ連軍、ドイツ軍としての、軍人、兵士のおかれた立場や生き方にせまっている。いうならば、戦場の論理を描いているともいえるだろうか。
どれほどこの作品が受け入れられるか、どのような賞を取ることになるのか、見ていきたいものである。
2021年12月20日記
https://www.hayakawa-online.co.jp/shopdetail/000000014980/
これがデビュー作であるという。おどろくしかない。
主な舞台は、第二次世界大戦のころのソ連と東欧。独ソ戦である。ソ連軍において、女性だけで組織された狙撃兵部隊。そこに加わることになる少女、セラフィマ。過酷な訓練の後、独ソ戦の激戦地を転戦する。そして、最後にめぐりあうことになる仇敵。
久々に読んだ戦争冒険小説である。最近では、戦争冒険小説、戦争ミステリ、という範疇の作品が少なくなったように思う。
だが、これはただの戦争冒険小説ではない。少女が主人公であり、狙撃兵であり、ソ連軍として独ソ戦を戦う。そこにある、友情、軍人としての職務、憎しみ、悲しみ……ありとあらゆる感情をのみこんで、少女は戦場にたつ。
この作品、アガサ・クリスティー賞の大賞受賞作ということだが、他にも賞を取るにちがいない。(すくなくとも、これを書いている時点では、直木賞の候補になっている。)
この小説が傑出しているのは、その戦争観にあるといってもいいかもしれない。女性の目、少女の目から、そして、ソ連の目から、独ソ戦を見ている。そこには、冷徹な狙撃兵としての闘志もあれば、女性としての感情もある。そして、何よりも重要だと思うのは、戦争と性の問題を避けてはいない。いったい戦場で何があったのか、冷静に見る視点がある。
また、独ソ戦をソ連の側から描くといっても、必ずしも、ナチス=悪、という図式になっていない。ソ連共産党賛美でも忌避でもない。ソ連軍、ドイツ軍としての、軍人、兵士のおかれた立場や生き方にせまっている。いうならば、戦場の論理を描いているともいえるだろうか。
どれほどこの作品が受け入れられるか、どのような賞を取ることになるのか、見ていきたいものである。
2021年12月20日記
映像の世紀プレミアム(20)「中国 “革命”の血と涙」 ― 2021-12-24
2021-12-24 當山日出夫(とうやまひでお)
映像の世紀プレミアム (20) 中国 “革命”の血と涙
これで、四月からはじまった、「映像の世紀」「新・映像の世紀」「映像の世紀プレミアム」の再放送は、順番に全部見ていったことになるかと思う。どれも、録画しておいて、後日ゆっくりと見ることにした。
「中国」の回は、今年の八月の放送。この時も見ている。
私は、一九五五(昭和三〇)年の生まれであるので、物心ついて中国というものを意識するようになったとき、それは、毛沢東の国であった。子どものころ、ラジオをつけると、中国からの日本語放送が聞こえてきたのを覚えている。(これは、今でもあるのだろうか。)
改めて再放送を見て思うことを書いてみるならば、次の二点ぐらいになる。
第一は、映像についての資料批判。
冒頭は、中国共産党のプロパガンダ映画からはじまっていた。映像を映した後、実は、これは後になってから撮影された再現映像……まあ、やらせ映像であるのだろうが……であるとあった。このような指摘は、これまでの「映像の世紀」のシリーズでは、あまりなかったことである。
映像資料として残っているからといって、それが信じられるものではない。いや、場合によると、それが、やらせのプロパガンダ映像であることがわかるならば、そのプロパガンダの意図を見抜くことが、必要になってくる。
この意味では、天安門事件のときの、戦車の前に立つ男の映像の謎がきわだってくる。
第二は、文化大革命と天安門事件。
文化大革命も天安門事件も、中国の近代史にとっては大きな事件であると認識する。文化大革命については、今では、歴史的に評価することができる時点にいる。だが、天安門事件については、逆に、今なお歴史的にこの事件があったことすら、中国政府は公式に認めているとはいいがたい。それが、現在の中国のメディア政策に影を落としているといっていいだろう。
今から考えるならば、文化大革命は、東西冷戦のさなかにあって、そのすきまでおこった出来事のように思えてならない。(番組では、東西冷戦について触れることはまったくなかったが。)
見ていて、天安門事件が、まさに一九八九年の出来事であったこことについて認識を新たにした。ベルリンの壁の崩壊した年である。もし、このとき、天安門にあつまった人びとの声で、中国社会が変わることがあったなら、と思わずにはいられない。
以上の二つのことを思ってみる。
以前の放送のときにも感じたことだが、毛沢東についてのサルトルの発言の音声が残っているのは、とても興味深い。サルトルでも、毛沢東を評価していた時代があったのかと、改めて感じる。
番組の終わりは、現在の習近平の姿を写して終わっていた。これから、中国がどうなるかわからない。あるいは、あるでこごとをきっかけにして、激変する可能性がないではない。ともあれ中国を支配する王朝は、いずれ交替するときがくる。
それから、「映像の世紀」シリーズを再放送で見てきたことで、書いておくならば、もしこれから後、どのような企画があるかわからないが、実現するならば是非とも見たいものがある。それは……天皇、である。
2021年12月23日記
映像の世紀プレミアム (20) 中国 “革命”の血と涙
これで、四月からはじまった、「映像の世紀」「新・映像の世紀」「映像の世紀プレミアム」の再放送は、順番に全部見ていったことになるかと思う。どれも、録画しておいて、後日ゆっくりと見ることにした。
「中国」の回は、今年の八月の放送。この時も見ている。
私は、一九五五(昭和三〇)年の生まれであるので、物心ついて中国というものを意識するようになったとき、それは、毛沢東の国であった。子どものころ、ラジオをつけると、中国からの日本語放送が聞こえてきたのを覚えている。(これは、今でもあるのだろうか。)
改めて再放送を見て思うことを書いてみるならば、次の二点ぐらいになる。
第一は、映像についての資料批判。
冒頭は、中国共産党のプロパガンダ映画からはじまっていた。映像を映した後、実は、これは後になってから撮影された再現映像……まあ、やらせ映像であるのだろうが……であるとあった。このような指摘は、これまでの「映像の世紀」のシリーズでは、あまりなかったことである。
映像資料として残っているからといって、それが信じられるものではない。いや、場合によると、それが、やらせのプロパガンダ映像であることがわかるならば、そのプロパガンダの意図を見抜くことが、必要になってくる。
この意味では、天安門事件のときの、戦車の前に立つ男の映像の謎がきわだってくる。
第二は、文化大革命と天安門事件。
文化大革命も天安門事件も、中国の近代史にとっては大きな事件であると認識する。文化大革命については、今では、歴史的に評価することができる時点にいる。だが、天安門事件については、逆に、今なお歴史的にこの事件があったことすら、中国政府は公式に認めているとはいいがたい。それが、現在の中国のメディア政策に影を落としているといっていいだろう。
今から考えるならば、文化大革命は、東西冷戦のさなかにあって、そのすきまでおこった出来事のように思えてならない。(番組では、東西冷戦について触れることはまったくなかったが。)
見ていて、天安門事件が、まさに一九八九年の出来事であったこことについて認識を新たにした。ベルリンの壁の崩壊した年である。もし、このとき、天安門にあつまった人びとの声で、中国社会が変わることがあったなら、と思わずにはいられない。
以上の二つのことを思ってみる。
以前の放送のときにも感じたことだが、毛沢東についてのサルトルの発言の音声が残っているのは、とても興味深い。サルトルでも、毛沢東を評価していた時代があったのかと、改めて感じる。
番組の終わりは、現在の習近平の姿を写して終わっていた。これから、中国がどうなるかわからない。あるいは、あるでこごとをきっかけにして、激変する可能性がないではない。ともあれ中国を支配する王朝は、いずれ交替するときがくる。
それから、「映像の世紀」シリーズを再放送で見てきたことで、書いておくならば、もしこれから後、どのような企画があるかわからないが、実現するならば是非とも見たいものがある。それは……天皇、である。
2021年12月23日記
『戦争と平和』(六)トルストイ/望月哲男(訳)光文社古典新訳文庫 ― 2021-12-25
2021-12-25 當山日出夫(とうやまひでお)
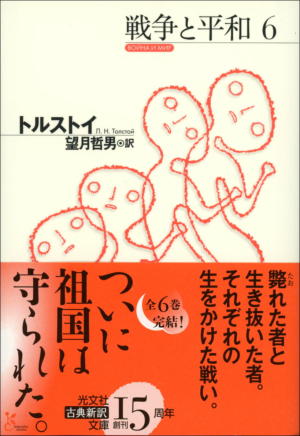
トルストイ.望月哲男(訳).『戦争と平和』(六)(光文社古典新訳文庫).光文社.2021
https://www.kotensinyaku.jp/books/book349/
続きである。
やまもも書斎記 2021年12月18日
『戦争と平和』(五)トルストイ/望月哲男(訳)光文社古典新訳文庫
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2021/12/18/9448741
六冊目(最終巻)である。
『戦争と平和』を読むのは、何度目かになる。これを、光文社古典新訳文庫の新しい版で読んで思うことは、まず何よりも、こんなにも面白い小説であったのか、という新鮮なおどろきである。何よりも、登場人物……ピエール、アンドレイ、ナターシャ、マリヤなどが生き生きとしている。
この作品が、世界文学のなかの名作として読まれてきている理由が、ようやく納得いったというのがいつわらざるところである。
以前に読んだ時には、この小説の歴史観というものにひかれて読んだかと思う。この小説の随所に、トルストイの歴史観が披露される。これはこれで面白いのだが、それよりも、一九世紀はじめのロシア貴族たちの日常の生活、戦争、恋、失恋、そして戦争……これらがダイナミックな、大きな物語を構成している。その物語の面白さ、ついつい読みふけってしまうところがある。
これは、新しい光文社古典新訳文庫版の、訳文の良さ、それから、ささいなことかもしれないが、栞としてついている登場人物一覧(家系図)、これによるところが大きいと感じる。なにしろ、登場人物が多く、そして、ロシア語の人名は分かりづらい。これを、栞の家系図を参照しながら読んでいくと、どの人物のことについて今語られているのか、さほど混乱することがない。
これは、もう一度読んでみたい。小説というものが、近代の西欧の文学の形式として作りあげられたものであるとして、この作品は、やはりその最高峰に位置するものの一つであると思う。(さらには、『アンナ・カレーニナ』もすばらしいと思う。)
登場人物は、ロシア貴族である。一般庶民ではない。だが、そのようなことを思って見ても、まさにロシア的としかいいようのない人びとである。このような作品こそ、あるいは国民文学(ロシアの)というのかもしれない。そして、これは、世界文学となっている。
それから、印象に残ることとしては、トルストイの文学にある、宗教的な深さというものがあるだろう。その宗教観に同意するかどうかは別にして、ここには人間のこころの深みある宗教というものへの深い洞察がある。これも、トルストイ文学の大きな魅力と感じるようになった。
まさに、古典文学であり、世界文学の名作であると強く感じる。
2021年11月6日記
『カムカムエヴリバディ』あれこれ「第8週」 ― 2021-12-26
2021-12-26 當山日出夫(とうやまひでお)
『カムカムエヴリバディ』第8週
https://www.nhk.or.jp/comecome/story/details/story_details_08.html
前回は、
やまもも書斎記 2021年12月19日
『カムカムエヴリバディ』あれこれ「第7週」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2021/12/19/9449039
この週で、「安子編」が終わり「るい編」につながることになった。
安子編の終わり。
安子は、雉真の家を出る決意をかためる。だが、その場合、るいをおいていかなければならなくなる。そんななかで、算太が行方不明になる。大阪に行ったらしい。大阪まででかけた安子は、たおれることになる。ロバートが介抱してくれることになったが、そこをるいに見られてしまう。
るいは、椎茸が嫌い(hate)だと言っていた。それと同じように、安子のことも嫌い(hete)だと言う。るいに見放されてしまった安子は、アメリカに行くことになる。
るい編のはじまり。
雉真の家で成長したるいは、祖父の千吉の死とともに、岡山を出る。大阪に向かう。ひとりで自立して生きていくことにした。だが、額の傷は、もとのままである。就職がうまくいかないところを、クリーニング店の夫婦に拾われて世話になることなる。いい人たちのようだ。
普通なら、週を分けて放送するところかと思うが、この週の中で、前半と後半で、安子編からるい編に、切り替わることになった。異例の展開というべきであろうか。
もう岡山の安子のことは出てこないのだろうか。ちょっとさみしい気がする。ただ、行方不明になった算太のその後のことがまったく出てきていなかたので、これからひょっとすると算太の再登場ということは、あり得ることかもしれないと思う。
慌ただしい展開であったので、安子編を十分に振り返ることなく、次の時代になっている。時代としては、一九六二(昭和三七)年のことになる。雉真の家で、雪衣が見ていた朝ドラが、「娘と私」であった。昭和三六年度の作品。その最終回というと、昭和三七年の春のことになる。
ちなみに、皇太子御成婚は、一九五九(昭和三四)年のことであるから、この時にテレビが普及しだしたとして、大阪の小さなクリーニング屋さんにテレビがあっても、おかしくはないかもしれない。
次週から、るい編が本格的にスタートする。番組HPのデザインもかわった。今年のうちにどのような展開になるのか、楽しみに見ることにしよう。
2021年12月25日記
『カムカムエヴリバディ』第8週
https://www.nhk.or.jp/comecome/story/details/story_details_08.html
前回は、
やまもも書斎記 2021年12月19日
『カムカムエヴリバディ』あれこれ「第7週」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2021/12/19/9449039
この週で、「安子編」が終わり「るい編」につながることになった。
安子編の終わり。
安子は、雉真の家を出る決意をかためる。だが、その場合、るいをおいていかなければならなくなる。そんななかで、算太が行方不明になる。大阪に行ったらしい。大阪まででかけた安子は、たおれることになる。ロバートが介抱してくれることになったが、そこをるいに見られてしまう。
るいは、椎茸が嫌い(hate)だと言っていた。それと同じように、安子のことも嫌い(hete)だと言う。るいに見放されてしまった安子は、アメリカに行くことになる。
るい編のはじまり。
雉真の家で成長したるいは、祖父の千吉の死とともに、岡山を出る。大阪に向かう。ひとりで自立して生きていくことにした。だが、額の傷は、もとのままである。就職がうまくいかないところを、クリーニング店の夫婦に拾われて世話になることなる。いい人たちのようだ。
普通なら、週を分けて放送するところかと思うが、この週の中で、前半と後半で、安子編からるい編に、切り替わることになった。異例の展開というべきであろうか。
もう岡山の安子のことは出てこないのだろうか。ちょっとさみしい気がする。ただ、行方不明になった算太のその後のことがまったく出てきていなかたので、これからひょっとすると算太の再登場ということは、あり得ることかもしれないと思う。
慌ただしい展開であったので、安子編を十分に振り返ることなく、次の時代になっている。時代としては、一九六二(昭和三七)年のことになる。雉真の家で、雪衣が見ていた朝ドラが、「娘と私」であった。昭和三六年度の作品。その最終回というと、昭和三七年の春のことになる。
ちなみに、皇太子御成婚は、一九五九(昭和三四)年のことであるから、この時にテレビが普及しだしたとして、大阪の小さなクリーニング屋さんにテレビがあっても、おかしくはないかもしれない。
次週から、るい編が本格的にスタートする。番組HPのデザインもかわった。今年のうちにどのような展開になるのか、楽しみに見ることにしよう。
2021年12月25日記
追記 2021年12月30日
この続きは、
やまもも書斎記 2021年12月30日
『カムカムエヴリバディ』あれこれ「第9週」
https://yamamomo.asablo.jp/blog/2021/12/30/9451845
この続きは、
やまもも書斎記 2021年12月30日
『カムカムエヴリバディ』あれこれ「第9週」
https://yamamomo.asablo.jp/blog/2021/12/30/9451845
『代表制民主主義はなぜ失敗したのか』藤井達夫 ― 2021-12-27
2021-12-27 當山日出夫(とうやまひでお)

藤井達夫.『代表制民主主義はなぜ失敗したのか』(集英社新書).集英社.2021
https://books.shueisha.co.jp/items/contents.html?isbn=978-4-08-721194-8
なるほど、安倍晋三のやったことは民主主義の破壊であった、ということが実感できる。
著者は、「民主主義」=「選挙」ではないといっている。漠然と、選挙で選ばれた議員が政治にかかわることを、民主主義だと思っているむきもあるかもしれないが、そうではないということに気づかされる。そして、民主主義を、その歴史からたどって、本当に民主主義を実践するには、いかにして可能なのか、問いかけるところがある。
すくなくとも、少数意見、反対意見への尊重ということがない場合、民主的とはいえない。(この意味では、安倍政権の時代は、とても民主主義の時代ということはできないことになる。)
この著者は、いわゆる一九五五年体制を評価している。その時代にあっては、政党は、ある一定の社会の階級、あるいは、階層を代表するものであり、それを基盤に選挙がおこなわれ、議員が選出されていた……このことに一定の評価を与えている。これは、昭和の昔が良かったという懐古でない。政党というものが、何を代表して組織され、選挙にのぞみ、何を実現することを、その存在意義としているのか、明確であった時代ということになろうか。それが、今日では、政党政治は、人気投票、あるいは、ポピュリズムになってしまっている。
現状の政治の問題点の分析には、なるほどと思うところが多くある。しかし、ではどうすればよいのかということになると、(私の見る限り)あまり説得力がないように読める。これは、この著者の責任ではないだろう。それほど、現在の、日本の、あるいは、世界の民主主義は危機に瀕しているいってよい。有効な対処が見いだせないでいる状況である。
現代の日本の政治状況を考えるうえでは、役に立つ一冊といっていいだろう。
2021年12月10日記
https://books.shueisha.co.jp/items/contents.html?isbn=978-4-08-721194-8
なるほど、安倍晋三のやったことは民主主義の破壊であった、ということが実感できる。
著者は、「民主主義」=「選挙」ではないといっている。漠然と、選挙で選ばれた議員が政治にかかわることを、民主主義だと思っているむきもあるかもしれないが、そうではないということに気づかされる。そして、民主主義を、その歴史からたどって、本当に民主主義を実践するには、いかにして可能なのか、問いかけるところがある。
すくなくとも、少数意見、反対意見への尊重ということがない場合、民主的とはいえない。(この意味では、安倍政権の時代は、とても民主主義の時代ということはできないことになる。)
この著者は、いわゆる一九五五年体制を評価している。その時代にあっては、政党は、ある一定の社会の階級、あるいは、階層を代表するものであり、それを基盤に選挙がおこなわれ、議員が選出されていた……このことに一定の評価を与えている。これは、昭和の昔が良かったという懐古でない。政党というものが、何を代表して組織され、選挙にのぞみ、何を実現することを、その存在意義としているのか、明確であった時代ということになろうか。それが、今日では、政党政治は、人気投票、あるいは、ポピュリズムになってしまっている。
現状の政治の問題点の分析には、なるほどと思うところが多くある。しかし、ではどうすればよいのかということになると、(私の見る限り)あまり説得力がないように読める。これは、この著者の責任ではないだろう。それほど、現在の、日本の、あるいは、世界の民主主義は危機に瀕しているいってよい。有効な対処が見いだせないでいる状況である。
現代の日本の政治状況を考えるうえでは、役に立つ一冊といっていいだろう。
2021年12月10日記
『青天を衝け』あれこれ「青春はつづく」 ― 2021-12-28
2021-12-28 當山日出夫(とうやまひでお)
『青天を衝け』最終回「青春はつづく」
https://www.nhk.or.jp/seiten/story/41/
前回は、
やまもも書斎記 2021年12月21日
『青天を衝け』あれこれ「栄一、海を越えて」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2021/12/21/9449605
いろいろとあったが、このドラマもようやく終わった。終わってみればであるが、面白かったというのが、率直な感想である。
今年のドラマは異例であった。そもそも新年のスタートが遅れて開始になった。また、途中、オリンピック、パラリンピックで、中断するということもあった。そのせいであろうか、序盤、前半のあたり、栄一の故郷の血洗島を舞台にしたところは、丁寧に江戸時代の農民の生活が描かれていたのに対して、後半になって、パリに行くあたりのところから、スピードがあがってきた。明治維新以降の渋沢栄一について、近代日本の歩みと併行して考えるべきところがあるかと思うのだが、見ていて、かなり省略して描いていると感じるところがあった。
確かに、近代日本を描くことはむずかいしのだろう。特に、渋沢栄一を主人公とするとなると、近代日本の経済のみならず、社会のあり方や政治についても、触れざるをえない。その人生を肯定的に描くことになるにせよ、日本の近代の歴史は、決して明るい面ばかりではない。
渋沢栄一は、昭和六年まで生きた。満州事変の年である。近代日本において、大きく歴史が動くときであったといえる。
また、渋沢栄一については、膨大な伝記資料がのこされている。それは、デジタル版にもなっている。ドラマとして、渋沢栄一の人生そのものについては、あまりフィクションの入りこむ余地はなかったといえる。
だが、その人生を通じて、幕末から近代日本を生きた人間の軌跡をどう描くかとなると、また難しい問題があるだろう。いうなれば、単に「坂の上の雲」の時代だけを描けばいいというわけではない。
『論語と算盤』は、買ってもっている。ドラマが終わったのを契機に、自分の目で考えながら読んでみたいと思う。「近代」という時代について、考えてみたいと思う。
さて、来年からは、『鎌倉殿の13人』である。時代劇エンタテインメントとして、どのような作り方になるのか、これも楽しみに見ることにしようと思っている。
2021年12月27日記
『青天を衝け』最終回「青春はつづく」
https://www.nhk.or.jp/seiten/story/41/
前回は、
やまもも書斎記 2021年12月21日
『青天を衝け』あれこれ「栄一、海を越えて」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2021/12/21/9449605
いろいろとあったが、このドラマもようやく終わった。終わってみればであるが、面白かったというのが、率直な感想である。
今年のドラマは異例であった。そもそも新年のスタートが遅れて開始になった。また、途中、オリンピック、パラリンピックで、中断するということもあった。そのせいであろうか、序盤、前半のあたり、栄一の故郷の血洗島を舞台にしたところは、丁寧に江戸時代の農民の生活が描かれていたのに対して、後半になって、パリに行くあたりのところから、スピードがあがってきた。明治維新以降の渋沢栄一について、近代日本の歩みと併行して考えるべきところがあるかと思うのだが、見ていて、かなり省略して描いていると感じるところがあった。
確かに、近代日本を描くことはむずかいしのだろう。特に、渋沢栄一を主人公とするとなると、近代日本の経済のみならず、社会のあり方や政治についても、触れざるをえない。その人生を肯定的に描くことになるにせよ、日本の近代の歴史は、決して明るい面ばかりではない。
渋沢栄一は、昭和六年まで生きた。満州事変の年である。近代日本において、大きく歴史が動くときであったといえる。
また、渋沢栄一については、膨大な伝記資料がのこされている。それは、デジタル版にもなっている。ドラマとして、渋沢栄一の人生そのものについては、あまりフィクションの入りこむ余地はなかったといえる。
だが、その人生を通じて、幕末から近代日本を生きた人間の軌跡をどう描くかとなると、また難しい問題があるだろう。いうなれば、単に「坂の上の雲」の時代だけを描けばいいというわけではない。
『論語と算盤』は、買ってもっている。ドラマが終わったのを契機に、自分の目で考えながら読んでみたいと思う。「近代」という時代について、考えてみたいと思う。
さて、来年からは、『鎌倉殿の13人』である。時代劇エンタテインメントとして、どのような作り方になるのか、これも楽しみに見ることにしようと思っている。
2021年12月27日記
椿 ― 2021-12-29
2021-12-29 當山日出夫(とうやまひでお)
冬休みで、今年の最後になるが、水曜日はいつものとおりに写真の日。今日は椿である。
前回は、
やまもも書斎記 2021年12月22日
紅葉
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2021/12/22/9449852
我が家にいくつか椿の木がある。どれも花はそんなにきれいに咲かない。他に山の方を見ると、藪椿がある。これは、赤い花をいくつか咲かせる。この冬はまだ咲かない。
家の玄関を出たところの木である。毎日のように目にしている。写真は、先月のうちに撮影しておいたもののストックからである。今では花がさいているのだが、おおきくぼてっとした花が咲く。写真に撮るのにはむいていない。
それよりも蕾の方が写真向きである。これは、秋になると蕾を見ることができる。見ていると、まるかった形のものが徐々にとがってきて、先端が赤くなる。毎年、この椿の花が咲くと、冬になったと感じる。
今年も、水曜日は写真の日ととして続けてくることができた。毎年、同じように、同じ花を写している。特に、花を求めて家を出てどこかに行くということもない。家にいるときは、留守番をしなければならない生活になっているので、なかなかその時間がとれない。また、写す写真は、自分の家から歩いて行ける範囲と決めている。
来年も、同じように写真を撮ることができたらと思っている。
冬休みで、今年の最後になるが、水曜日はいつものとおりに写真の日。今日は椿である。
前回は、
やまもも書斎記 2021年12月22日
紅葉
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2021/12/22/9449852
我が家にいくつか椿の木がある。どれも花はそんなにきれいに咲かない。他に山の方を見ると、藪椿がある。これは、赤い花をいくつか咲かせる。この冬はまだ咲かない。
家の玄関を出たところの木である。毎日のように目にしている。写真は、先月のうちに撮影しておいたもののストックからである。今では花がさいているのだが、おおきくぼてっとした花が咲く。写真に撮るのにはむいていない。
それよりも蕾の方が写真向きである。これは、秋になると蕾を見ることができる。見ていると、まるかった形のものが徐々にとがってきて、先端が赤くなる。毎年、この椿の花が咲くと、冬になったと感じる。
今年も、水曜日は写真の日ととして続けてくることができた。毎年、同じように、同じ花を写している。特に、花を求めて家を出てどこかに行くということもない。家にいるときは、留守番をしなければならない生活になっているので、なかなかその時間がとれない。また、写す写真は、自分の家から歩いて行ける範囲と決めている。
来年も、同じように写真を撮ることができたらと思っている。
Nikon D500
TAMRON SP AF 180mm F/3.5 Di MACRO 1:1
2021年12月28日記
『カムカムエヴリバディ』あれこれ「第9週」 ― 2021-12-30
2021-12-30 當山日出夫(とうやまひでお)
『カムカムエヴリバディ』第9週
https://www.nhk.or.jp/comecome/story/details/story_details_09.html
前回は、
やまもも書斎記 2021年12月26日
『カムカムエヴリバディ』あれこれ「第8週」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2021/12/26/9450889
年末なので、第9週は二日だけだった。これまでをふりかえって思うことを書いてみる。
このドラマのいいところ……概ね朝ドラはそうなのだけれども……日常を丁寧に描いていることである。安子編における、和菓子屋「たちばな」の日常生活が、じっくりと描かれていた。これが、このドラマに奥行きと安心感を与えることになっていた。
るい編になって、舞台は大阪のクリーニング店になった。ここで、昭和戦後の大阪のクリーニング店の日常が丁寧に描写されている。クリーニング店の夫婦も、いい人である。(これまで、このドラマでは、基本的に悪い人は出てきていない。)
クリーニング店に来た客、弁護士(の卵)の男性と、宇宙人と名付けた謎の男性。さて、るいは、これからどちらの男性にひかれていくことになるのだろうか。まあ、次週の予告で、サッチモと言っていたので、ジャズをメインにストーリーは展開するのかと思うが。
『カムカムエヴリバディ』は、一〇〇年の物語であるという。るい編は、大阪を舞台にして、どのような運びになるのだろうか。そして、ラジオの英語講座は、どのようにるいの人生にかかわることになるのか。来年の放送を楽しみに見ることにしよう。
2021年12月29日記
『カムカムエヴリバディ』第9週
https://www.nhk.or.jp/comecome/story/details/story_details_09.html
前回は、
やまもも書斎記 2021年12月26日
『カムカムエヴリバディ』あれこれ「第8週」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2021/12/26/9450889
年末なので、第9週は二日だけだった。これまでをふりかえって思うことを書いてみる。
このドラマのいいところ……概ね朝ドラはそうなのだけれども……日常を丁寧に描いていることである。安子編における、和菓子屋「たちばな」の日常生活が、じっくりと描かれていた。これが、このドラマに奥行きと安心感を与えることになっていた。
るい編になって、舞台は大阪のクリーニング店になった。ここで、昭和戦後の大阪のクリーニング店の日常が丁寧に描写されている。クリーニング店の夫婦も、いい人である。(これまで、このドラマでは、基本的に悪い人は出てきていない。)
クリーニング店に来た客、弁護士(の卵)の男性と、宇宙人と名付けた謎の男性。さて、るいは、これからどちらの男性にひかれていくことになるのだろうか。まあ、次週の予告で、サッチモと言っていたので、ジャズをメインにストーリーは展開するのかと思うが。
『カムカムエヴリバディ』は、一〇〇年の物語であるという。るい編は、大阪を舞台にして、どのような運びになるのだろうか。そして、ラジオの英語講座は、どのようにるいの人生にかかわることになるのか。来年の放送を楽しみに見ることにしよう。
2021年12月29日記
追記 2022年1月9日
この続きは、
やまもも書斎記 2022年1月9日
『カムカムエヴリバディ』あれこれ「第10週」
https://yamamomo.asablo.jp/blog/2022/01/09/9454621
この続きは、
やまもも書斎記 2022年1月9日
『カムカムエヴリバディ』あれこれ「第10週」
https://yamamomo.asablo.jp/blog/2022/01/09/9454621










最近のコメント