『半分、青い。』あれこれ「仕事が欲しい!」 ― 2018-07-01
2018-07-01 當山日出夫(とうやまひでお)
『半分、青い。』第13週「仕事が欲しい!」
https://www.nhk.or.jp/hanbunaoi/story/week_13.html
前回は、
やまもも書斎記 2018年6月24日
『半分、青い。』あれこれ「結婚したい!」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/06/24/8901850
この週のみどころは、律の結婚と、鈴愛の漫画家としてのスランプ、この二点である。そして、鈴愛は、人生の岐路に立つことになる。
第一に、律の結婚。
この週は、月曜日にいきなり律のプロポーズがあった。それを、鈴愛は断ったことになるのだが、時は流れ、律は結婚してしまった。そのいきさつは描かれていない。どういういきさつで、律は結婚することになったのか、ここは、見る者の想像力に委ねられているかのごとくである。
秋風のオフィス、それから、鈴愛のところに、律から結婚を知らせる葉書が来た。それを見て、鈴愛は、岐阜のつくし食堂に電話する。「律、結婚した」と言っていた。これが、疑問の文なのか、あるいは、断定の文なのか、ちょうどその中間ぐらいの微妙な言い方だった。その事実を認めて確認したいような、あるいは、事実として認めたくないような、鈴愛の感情がよく表現されていたと思う。
葉書の住所をたよりに、鈴愛は、律の新婚の家まででかけてしまう。そこで、妻のより子と会う。ただ、顔を見ただけで帰ってきた。和子さんの声がしていた。ここで、とにかく、律が結婚して新しい家庭をもったことを、自分の目で確認してきたことになる。
律の結婚は、鈴愛にとって、とてもとても悲しいできごとであった。
第二に、漫画家としての行き詰まり。
「一瞬に咲け」の次の作品が描けなくなってしまっている。ナレーションで、廉子が言っていた。才能とは、湧き出るときは泉のように湧き出るが、しぼむときは風船のようにしぼんでしまう、もとにはもどらない、と。これは、おそらく、脚本作家としての、北川悦吏子の実感でもあるのだろう。漫画と脚本と、ジャンルは違うとはいえ、創作にかかわるものの立ち向かうべき宿命のようなものである。自分の才能との対決である。努力してどうにかなるというものではない。
その鈴愛に、秋風は言う。ネームなしで、漫画を描いてみろ、と。昔、漫画にあこがれていた時のことを思い出して、初心にかえってやってみろ。たぶん、これは、漫画家である鈴愛にとって、最後のチャレンジになるのだろうと予感させる。
果たして、鈴愛は、漫画家として成功する道を歩むことができるのか、あるいは、漫画家に挫折して、別の人生をさぐるのか、次週以降の展開が気になるところである。ドラマは、ちょうど中盤である。漫画家人生の次が待っているのかもしれない。
以上の二点が、この週で見どころと感じたとことである。
結婚もできず、漫画家としても行き詰まった鈴愛の今後はどうなるのであろうか。はたして、漫画家としての将来はあるのか、また、律が結婚してしまって鈴愛はどうする。決断のときである。岐阜から東京に出てきて一〇年。年は三〇前である。結婚にも、仕事にも挫折するとしたら、その後、どんな人生があるというのか。
なお、さらに付け加えれば、律の飼っていた亀のフランソワが死んでしまった。結婚のことはともかく、フランソワの死のことは、律は鈴愛に報告すべきだったのではないだろうか。律と鈴愛がいて、それから、その側にいたのがフランソワであった。律と鈴愛にとって、フランソワは、人生の友であったのではなかったろうか。
『半分、青い。』第13週「仕事が欲しい!」
https://www.nhk.or.jp/hanbunaoi/story/week_13.html
前回は、
やまもも書斎記 2018年6月24日
『半分、青い。』あれこれ「結婚したい!」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/06/24/8901850
この週のみどころは、律の結婚と、鈴愛の漫画家としてのスランプ、この二点である。そして、鈴愛は、人生の岐路に立つことになる。
第一に、律の結婚。
この週は、月曜日にいきなり律のプロポーズがあった。それを、鈴愛は断ったことになるのだが、時は流れ、律は結婚してしまった。そのいきさつは描かれていない。どういういきさつで、律は結婚することになったのか、ここは、見る者の想像力に委ねられているかのごとくである。
秋風のオフィス、それから、鈴愛のところに、律から結婚を知らせる葉書が来た。それを見て、鈴愛は、岐阜のつくし食堂に電話する。「律、結婚した」と言っていた。これが、疑問の文なのか、あるいは、断定の文なのか、ちょうどその中間ぐらいの微妙な言い方だった。その事実を認めて確認したいような、あるいは、事実として認めたくないような、鈴愛の感情がよく表現されていたと思う。
葉書の住所をたよりに、鈴愛は、律の新婚の家まででかけてしまう。そこで、妻のより子と会う。ただ、顔を見ただけで帰ってきた。和子さんの声がしていた。ここで、とにかく、律が結婚して新しい家庭をもったことを、自分の目で確認してきたことになる。
律の結婚は、鈴愛にとって、とてもとても悲しいできごとであった。
第二に、漫画家としての行き詰まり。
「一瞬に咲け」の次の作品が描けなくなってしまっている。ナレーションで、廉子が言っていた。才能とは、湧き出るときは泉のように湧き出るが、しぼむときは風船のようにしぼんでしまう、もとにはもどらない、と。これは、おそらく、脚本作家としての、北川悦吏子の実感でもあるのだろう。漫画と脚本と、ジャンルは違うとはいえ、創作にかかわるものの立ち向かうべき宿命のようなものである。自分の才能との対決である。努力してどうにかなるというものではない。
その鈴愛に、秋風は言う。ネームなしで、漫画を描いてみろ、と。昔、漫画にあこがれていた時のことを思い出して、初心にかえってやってみろ。たぶん、これは、漫画家である鈴愛にとって、最後のチャレンジになるのだろうと予感させる。
果たして、鈴愛は、漫画家として成功する道を歩むことができるのか、あるいは、漫画家に挫折して、別の人生をさぐるのか、次週以降の展開が気になるところである。ドラマは、ちょうど中盤である。漫画家人生の次が待っているのかもしれない。
以上の二点が、この週で見どころと感じたとことである。
結婚もできず、漫画家としても行き詰まった鈴愛の今後はどうなるのであろうか。はたして、漫画家としての将来はあるのか、また、律が結婚してしまって鈴愛はどうする。決断のときである。岐阜から東京に出てきて一〇年。年は三〇前である。結婚にも、仕事にも挫折するとしたら、その後、どんな人生があるというのか。
なお、さらに付け加えれば、律の飼っていた亀のフランソワが死んでしまった。結婚のことはともかく、フランソワの死のことは、律は鈴愛に報告すべきだったのではないだろうか。律と鈴愛がいて、それから、その側にいたのがフランソワであった。律と鈴愛にとって、フランソワは、人生の友であったのではなかったろうか。
『老いの荷風』川本三郎(その二) ― 2018-07-02
2018-07-02 當山日出夫(とうやまひでお)

続きである。
やまもも書斎記 2018年6月30日
『老いの荷風』川本三郎
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/06/30/8906347
川本三郎.『老いの荷風』.白水社.2017
https://www.hakusuisha.co.jp/book/b285611.html
この本を読んで、国語学の観点から興味深い点があったので、別に書きとめておきたい。それは、「てよだわ言葉」についてである。
『濹東綺譚』のお雪である。
「六月のある日、玉の井を歩いていた「わたくし」は雨に降られる。いつもの習慣で傘を持っている。その傘を開くと、「檀那、そこまで入れてってよ」と、女(お雪)が傘のなかに飛び込んでくる。『濹東綺譚』のことの場面は『放蕩』の娼婦との出会いを繰り返している。/さらに面白いことがある。/『放蕩』の娼婦の言葉は、当然、フランス語ではなくて、日本語になっている。それが、明治の女学生のあいだで流行った「てよだわ言葉」。/貞吉はカフェで会った安飯屋に入る。料理は女にまかせる。女は献立書(メニュー)を見ながら言う。「何でもよくって?」/夏目漱石『三四郎』の明治の新しい女、美禰子が使っている「てよだわ言葉」である。昭和になると女学生から一般の女性のあいだにも広がった。」(p.92)
「『放蕩』のパリの娼婦と『濹東綺譚』の娼婦が、同じ場面で同じ「てよだわ言葉」を使っている。両者の類似を感じざるを得ない。」(p.92)
漱石の作品の中の女性たち、なかでも若い女性たちが、女学生ことばを使っていることは、既に知られていることだろう。(さらにいえば、『道草』『明暗』になると、この女学生ことばの様相が変わってくる。ここに漱石の作品の新たな展開を見ることもできよう。)
だが、『濹東綺譚』のお雪のことは、気づかなかった。この本を読んではじめて、そうかと思った次第である。
そして、次の疑問は、何故、荷風は、お雪に、女学生ことばを使わせているのであろうか、ということである。単なる娼婦ではない、そこに何かしら新時代の女性としての側面を描きたかったのだろうか。ここは『濹東綺譚』を読んで、考えて見たいところである。少なくとも、『濹東綺譚』のお雪は、単なる下町の娼婦ではないと、そのことばから言えそうである。
やまもも書斎記 2018年6月30日
『老いの荷風』川本三郎
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/06/30/8906347
川本三郎.『老いの荷風』.白水社.2017
https://www.hakusuisha.co.jp/book/b285611.html
この本を読んで、国語学の観点から興味深い点があったので、別に書きとめておきたい。それは、「てよだわ言葉」についてである。
『濹東綺譚』のお雪である。
「六月のある日、玉の井を歩いていた「わたくし」は雨に降られる。いつもの習慣で傘を持っている。その傘を開くと、「檀那、そこまで入れてってよ」と、女(お雪)が傘のなかに飛び込んでくる。『濹東綺譚』のことの場面は『放蕩』の娼婦との出会いを繰り返している。/さらに面白いことがある。/『放蕩』の娼婦の言葉は、当然、フランス語ではなくて、日本語になっている。それが、明治の女学生のあいだで流行った「てよだわ言葉」。/貞吉はカフェで会った安飯屋に入る。料理は女にまかせる。女は献立書(メニュー)を見ながら言う。「何でもよくって?」/夏目漱石『三四郎』の明治の新しい女、美禰子が使っている「てよだわ言葉」である。昭和になると女学生から一般の女性のあいだにも広がった。」(p.92)
「『放蕩』のパリの娼婦と『濹東綺譚』の娼婦が、同じ場面で同じ「てよだわ言葉」を使っている。両者の類似を感じざるを得ない。」(p.92)
漱石の作品の中の女性たち、なかでも若い女性たちが、女学生ことばを使っていることは、既に知られていることだろう。(さらにいえば、『道草』『明暗』になると、この女学生ことばの様相が変わってくる。ここに漱石の作品の新たな展開を見ることもできよう。)
だが、『濹東綺譚』のお雪のことは、気づかなかった。この本を読んではじめて、そうかと思った次第である。
そして、次の疑問は、何故、荷風は、お雪に、女学生ことばを使わせているのであろうか、ということである。単なる娼婦ではない、そこに何かしら新時代の女性としての側面を描きたかったのだろうか。ここは『濹東綺譚』を読んで、考えて見たいところである。少なくとも、『濹東綺譚』のお雪は、単なる下町の娼婦ではないと、そのことばから言えそうである。
『西郷どん』あれこれ「生かされた命」 ― 2018-07-03
2018-07-03 當山日出夫(とうやまひでお)
『西郷どん』2018年7月1日、第25回「生かされた命」
https://www.nhk.or.jp/segodon/story/25/
前回は、
やまもも書斎記 2018年6月26日
『西郷どん』あれこれ「地の果てにて」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/06/26/8903399
この週の見どころは、「敬天愛人」と「革命」だろうか。
第一に、敬天愛人。
沖永良部島で西郷は流人生活をおくる。そこで、島の人びとに接し、また、子どもたちの教育にもあたることになる。ここでの西郷の生き方は、「敬天愛人」と言うのがふさわしいかもしれない。ただ、ドラマのなかでは、このことばは使っていない。
島に流罪になって、過酷な生活の中で、それでも生きている。そこには、島の人びとの、西郷に寄せる敬意がある。西郷は、先生と慕われている。この島での流人生活を経て、西郷は、再びよみがえることになる。
このような西郷の生活の根底にある理念としては、「敬天愛人」の語がふさわしいように感じられた。これは、今後の幕末の動乱を生きることになる西郷の人格の根底にあるものとなるであろう。
第二に、革命。
島に流人として住んでいる男……川口雪篷……は、ナポレオンについて語り、「革命」に言及する。
このあたり、時代考証としてどうかな、という気がしないではない。幕末、フランスのナポレオンが英雄視されていたことはいいとしても、「革命」ということを、西郷はどう考えていたのだろうか。ただ、倒幕のことを意味しているのか。この当時の幕末の志士たちにとって、「革命」とはどういうことばであったのか、ここはいろいろ考えることができるだろう。無論、「易姓革命」のことまで視野に入れてのことではあるが。(明治維新を「革命」と考えるかどうか、このあたり歴史学の方でも議論になるところであると思っている。)
以上の二点、敬天愛人と革命が、この回でのポイントかなと思って見ていた。
ともあれ、「革命」のことばに見送られるようにして、西郷は、流罪の島から帰還することになる。これからは、いよいよ倒幕の志士としての活躍が待っているようである。そして、愛加那との再会。
そして、この週も、西郷が島流しになっている間に、生麦事件と薩英戦争が起こっていた。これらの歴史上の事件の描き方については、いろいろ意見のあるところだろうと思う。特に、薩英戦争の帰趨は、その後の薩摩藩の方針に大きく影響したはずである。
ところで、次回は、スペシャルのようだ。いったい何の意図があってNHKは、このような構成にしているのか、理解に苦しむところである。ドラマが始まって半年が過ぎ、これからいよいよ、倒幕から明治維新になる流れのなかで、今後を展望しておくということなのだろうか。
『西郷どん』2018年7月1日、第25回「生かされた命」
https://www.nhk.or.jp/segodon/story/25/
前回は、
やまもも書斎記 2018年6月26日
『西郷どん』あれこれ「地の果てにて」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/06/26/8903399
この週の見どころは、「敬天愛人」と「革命」だろうか。
第一に、敬天愛人。
沖永良部島で西郷は流人生活をおくる。そこで、島の人びとに接し、また、子どもたちの教育にもあたることになる。ここでの西郷の生き方は、「敬天愛人」と言うのがふさわしいかもしれない。ただ、ドラマのなかでは、このことばは使っていない。
島に流罪になって、過酷な生活の中で、それでも生きている。そこには、島の人びとの、西郷に寄せる敬意がある。西郷は、先生と慕われている。この島での流人生活を経て、西郷は、再びよみがえることになる。
このような西郷の生活の根底にある理念としては、「敬天愛人」の語がふさわしいように感じられた。これは、今後の幕末の動乱を生きることになる西郷の人格の根底にあるものとなるであろう。
第二に、革命。
島に流人として住んでいる男……川口雪篷……は、ナポレオンについて語り、「革命」に言及する。
このあたり、時代考証としてどうかな、という気がしないではない。幕末、フランスのナポレオンが英雄視されていたことはいいとしても、「革命」ということを、西郷はどう考えていたのだろうか。ただ、倒幕のことを意味しているのか。この当時の幕末の志士たちにとって、「革命」とはどういうことばであったのか、ここはいろいろ考えることができるだろう。無論、「易姓革命」のことまで視野に入れてのことではあるが。(明治維新を「革命」と考えるかどうか、このあたり歴史学の方でも議論になるところであると思っている。)
以上の二点、敬天愛人と革命が、この回でのポイントかなと思って見ていた。
ともあれ、「革命」のことばに見送られるようにして、西郷は、流罪の島から帰還することになる。これからは、いよいよ倒幕の志士としての活躍が待っているようである。そして、愛加那との再会。
そして、この週も、西郷が島流しになっている間に、生麦事件と薩英戦争が起こっていた。これらの歴史上の事件の描き方については、いろいろ意見のあるところだろうと思う。特に、薩英戦争の帰趨は、その後の薩摩藩の方針に大きく影響したはずである。
ところで、次回は、スペシャルのようだ。いったい何の意図があってNHKは、このような構成にしているのか、理解に苦しむところである。ドラマが始まって半年が過ぎ、これからいよいよ、倒幕から明治維新になる流れのなかで、今後を展望しておくということなのだろうか。
追記 2018-07-17
この続きは、
やまもも書斎記 2018年7月17日
『西郷どん』あれこれ「西郷、京へ」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/07/17/8919788
この続きは、
やまもも書斎記 2018年7月17日
『西郷どん』あれこれ「西郷、京へ」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/07/17/8919788
セイヨウイボタノキ ― 2018-07-04
2018-07-04 當山日出夫(とうやまひでお)
水曜日は花の写真の日。今日はセイヨウイボタノキ。
前回は、
やまもも書斎記 2018年6月27日
ネジキ
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/06/27/8904132
我が家の駐車場の垣根の木である。これまで、春になると花の咲くのを目にしてきたが、特に名前を気にすることなくすごしてきた。身の周りの草花など写真に撮るようになって気になった。WEBで聞いてみると、セイヨウイボタノキとのことである。
セイヨウイボタについては、Google検索では、かなりの情報を得ることができる。だが、このセイヨウイボタは、日本国語大辞典(ジャパンナレッジ)を見てもヒットしない。立項していないようである。
イボタはある。今日は、イボタの項目を見てみることにする。
水蝋・疣取
「いぼたのき(水蝋樹)」に同じ。
とある。「いぼた」の用例は、万葉集目安(室町末)から見える。
イボタノキでは、
水蝋樹・疣取木
モクセイ科の半落葉低木。各地の山野に生える。高さ一・五〜二メートル。
とあり、さらに説明がある。用例は、地方落穂集(1763)、日本植物名彙(1884)にある。また、この木の名(いぼた)は、『言海』にあるよし。
『言海』を見ると、
いぼた
樹ノ名、高サ三四尺ヨリ丈餘ニ至ル、枝葉、共ニ對生ス、葉は楕圓(イビツ)ナリ、枝上ニ二三寸ノ穂ヲナシ、枝ヲ分チテ、五瓣ノ小花、集リ開ク、ねずみもちノ花に異ナラズ、實、熟スレバ、黒ク、鼠ノ糞ニ似タリ。コゴメバナ。
掲載の写真は、初夏の時、五月に撮影しておいたものである。
水曜日は花の写真の日。今日はセイヨウイボタノキ。
前回は、
やまもも書斎記 2018年6月27日
ネジキ
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/06/27/8904132
我が家の駐車場の垣根の木である。これまで、春になると花の咲くのを目にしてきたが、特に名前を気にすることなくすごしてきた。身の周りの草花など写真に撮るようになって気になった。WEBで聞いてみると、セイヨウイボタノキとのことである。
セイヨウイボタについては、Google検索では、かなりの情報を得ることができる。だが、このセイヨウイボタは、日本国語大辞典(ジャパンナレッジ)を見てもヒットしない。立項していないようである。
イボタはある。今日は、イボタの項目を見てみることにする。
水蝋・疣取
「いぼたのき(水蝋樹)」に同じ。
とある。「いぼた」の用例は、万葉集目安(室町末)から見える。
イボタノキでは、
水蝋樹・疣取木
モクセイ科の半落葉低木。各地の山野に生える。高さ一・五〜二メートル。
とあり、さらに説明がある。用例は、地方落穂集(1763)、日本植物名彙(1884)にある。また、この木の名(いぼた)は、『言海』にあるよし。
『言海』を見ると、
いぼた
樹ノ名、高サ三四尺ヨリ丈餘ニ至ル、枝葉、共ニ對生ス、葉は楕圓(イビツ)ナリ、枝上ニ二三寸ノ穂ヲナシ、枝ヲ分チテ、五瓣ノ小花、集リ開ク、ねずみもちノ花に異ナラズ、實、熟スレバ、黒ク、鼠ノ糞ニ似タリ。コゴメバナ。
掲載の写真は、初夏の時、五月に撮影しておいたものである。
Nikon D7500
AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR
追記 2019-06-12
2019年については、
やまもも書斎記 2019年6月12日
セイヨウイボタノキ
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/06/12/9085304
2019年については、
やまもも書斎記 2019年6月12日
セイヨウイボタノキ
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2019/06/12/9085304
『変身』カフカ ― 2018-07-05
2018-07-05 當山日出夫(とうやまひでお)

世界文学の名作の読み直し。今日は『変身』である。
フランツ・カフカ.高橋義孝(訳).『変身』(新潮文庫).1952(2011.改版)
http://www.shinchosha.co.jp/book/207101/
これを読んだのは、高校生ぐらいの時だったろうか。なんとも奇妙な物語を読んだという印象であったのを覚えている。今回、数十年ぶりに再読してみて、やはり、不可解な、奇妙な小説であるという印象は変わらない。最初に読んだ時の印象として強く覚えていたのは、虫になったザムザに妹がリンゴを投げつけるシーン。今回、再読しても、このシーンは印象的である。
今の新潮文庫版は、改版して、活字が大きくなっている。解説も、新しいのがついている。それを見ると、この作品にどのような寓意を読みとるか、これまでにいろんな解釈がなされてきたらしい。読んで、「時代」を感じたのは、
「『変身』をマルクス主義的に解釈し、資本主義社会における公的生活と私的生活との矛盾が描かれているという解釈もある。」(p.134)
これは、有村隆広による新しい解説。高橋義孝閲とあるが、書かれたのは、1985年の日付がはいっている。
ベルリンの壁の崩壊が、1989年のことだから、1985年に書かれた解説に、このようなマルクス主義的解釈があったとしても、これはこれでおかしくはない。だが、今、二一世紀になって、このような解釈をする読み方はもう流行らないだろう。
それよりも、今日の、特に日本の視点で読むならば……虫に変身してしまうということの寓意は、たとえば「ひきこもり」、あるいは、逆に、「虐待」などを、感じて読むことができる。残念ながら、このようなニュースに接することが、最近、多いように思う。
この『変身』という小説は、その時代によって、多様に解釈がなされて読み継がれていくことになるのであろう。そして、どのような時代になって、『変身』の寓意が、何かしら社会の不条理を淡々と描いた作品として読めるのだとも思う。
カフカという作家、若い時に『変身』は読んだのだが、それ以外の作品は読まずにきている。他の作品も読んでおきたいと思う。
フランツ・カフカ.高橋義孝(訳).『変身』(新潮文庫).1952(2011.改版)
http://www.shinchosha.co.jp/book/207101/
これを読んだのは、高校生ぐらいの時だったろうか。なんとも奇妙な物語を読んだという印象であったのを覚えている。今回、数十年ぶりに再読してみて、やはり、不可解な、奇妙な小説であるという印象は変わらない。最初に読んだ時の印象として強く覚えていたのは、虫になったザムザに妹がリンゴを投げつけるシーン。今回、再読しても、このシーンは印象的である。
今の新潮文庫版は、改版して、活字が大きくなっている。解説も、新しいのがついている。それを見ると、この作品にどのような寓意を読みとるか、これまでにいろんな解釈がなされてきたらしい。読んで、「時代」を感じたのは、
「『変身』をマルクス主義的に解釈し、資本主義社会における公的生活と私的生活との矛盾が描かれているという解釈もある。」(p.134)
これは、有村隆広による新しい解説。高橋義孝閲とあるが、書かれたのは、1985年の日付がはいっている。
ベルリンの壁の崩壊が、1989年のことだから、1985年に書かれた解説に、このようなマルクス主義的解釈があったとしても、これはこれでおかしくはない。だが、今、二一世紀になって、このような解釈をする読み方はもう流行らないだろう。
それよりも、今日の、特に日本の視点で読むならば……虫に変身してしまうということの寓意は、たとえば「ひきこもり」、あるいは、逆に、「虐待」などを、感じて読むことができる。残念ながら、このようなニュースに接することが、最近、多いように思う。
この『変身』という小説は、その時代によって、多様に解釈がなされて読み継がれていくことになるのであろう。そして、どのような時代になって、『変身』の寓意が、何かしら社会の不条理を淡々と描いた作品として読めるのだとも思う。
カフカという作家、若い時に『変身』は読んだのだが、それ以外の作品は読まずにきている。他の作品も読んでおきたいと思う。
京都国立近代美術館「ユージン・スミス」 ― 2018-07-06
2018-07-06 當山日出夫(とうやまひでお)
京都国立近代美術館でやっている「横山大観展」を見てきたのは、先週のことである。このとき、四階では、コレクション・ギャラリーの展示があった。その中に、ユージン・スミスの写真も展示されていた。
京都国立近代美術館でやっている「横山大観展」を見てきたのは、先週のことである。このとき、四階では、コレクション・ギャラリーの展示があった。その中に、ユージン・スミスの写真も展示されていた。
平成30年度 第2回コレクション展
http://www.momak.go.jp/Japanese/collectionGalleryArchive/2018/collectionGallery2018No02.html
ユージン・スミスの名前は知っている。日本で有名になっているのは、水俣の取材写真においてであるかもしれない。このユージン・スミスの作品を、京都国立近代美術館では、かなり収集しているとのことである。
今回、展示されていたのは、そのコレクションから、『ライフ』などで活躍していた時代の作品をあつめたもの。「カントリー・ドクター」「スペインの村」などの写真群が展示されていた。
見て感じたことを書いておけば次の二点になるだろうか。
第一に、その絵画的作風とでもいうべきものである。
明暗の対比、構図のとりかた、いかにも絵画的である。極端なたとえになるかもしれないが、レンブラントなどを彷彿とさせる、光の描写が印象的である。これは、モノクロ写真ならではの効果といえるかもしれない。また、構図の視点から見ても、これも、いかにも絵画的という印象をうけるものが多くあった。
第二に、にもかかわらず、写真としてのリアリズムである。
『ライフ』などで活躍した写真家として、写真のリアリズムから離れることがない。いや、リアリズムを追求するなかに、上述の絵画的な作風が枠組みとしてある、というべきだろうか。
以上の二点が、ユージン・スミスの作品を見ながら感じていたことであった。
絵画的な構図とか、リアリズムとか、現代の写真が、むしろ、忘れてしまったことかもしれない。写真が芸術であるとして、その原点がどこにあるかを強く印象づける作品群であった。横山大観を見た後であったので、より強くこのことが印象に残っているということなのかもしれない。
http://www.momak.go.jp/Japanese/collectionGalleryArchive/2018/collectionGallery2018No02.html
ユージン・スミスの名前は知っている。日本で有名になっているのは、水俣の取材写真においてであるかもしれない。このユージン・スミスの作品を、京都国立近代美術館では、かなり収集しているとのことである。
今回、展示されていたのは、そのコレクションから、『ライフ』などで活躍していた時代の作品をあつめたもの。「カントリー・ドクター」「スペインの村」などの写真群が展示されていた。
見て感じたことを書いておけば次の二点になるだろうか。
第一に、その絵画的作風とでもいうべきものである。
明暗の対比、構図のとりかた、いかにも絵画的である。極端なたとえになるかもしれないが、レンブラントなどを彷彿とさせる、光の描写が印象的である。これは、モノクロ写真ならではの効果といえるかもしれない。また、構図の視点から見ても、これも、いかにも絵画的という印象をうけるものが多くあった。
第二に、にもかかわらず、写真としてのリアリズムである。
『ライフ』などで活躍した写真家として、写真のリアリズムから離れることがない。いや、リアリズムを追求するなかに、上述の絵画的な作風が枠組みとしてある、というべきだろうか。
以上の二点が、ユージン・スミスの作品を見ながら感じていたことであった。
絵画的な構図とか、リアリズムとか、現代の写真が、むしろ、忘れてしまったことかもしれない。写真が芸術であるとして、その原点がどこにあるかを強く印象づける作品群であった。横山大観を見た後であったので、より強くこのことが印象に残っているということなのかもしれない。
『渋江抽斎』森鷗外 ― 2018-07-07
2018-07-07 當山日出夫(とうやまひでお)
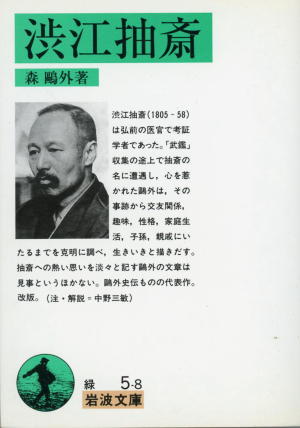
森鷗外.『渋江抽斎』(岩波文庫).岩波書店.1940(改版.1999)
https://www.iwanami.co.jp/book/b249228.html
東京国立博物館での森鷗外の展示を見て、この本を読んでおきたくなった。
やまもも書斎記 2018年6月23日
東京国立博物館「帝室博物館総長森鷗外の筆跡」を見てきた
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/06/23/8900996
『渋江抽斎』は、鷗外の岩波版「全集」も「選集」も、それから、「歴史文学集」も持っている。なかで、一番、手軽に読める本、そして、注釈がついている本ということで、岩波文庫の新しい版で読むことにした。
読み直すのは何回目になるだろうか。やはりこの本は、何度読んでも面白い。
その理由としては、次の二点だろうか。
第一は、鷗外は、渋江抽斎を、同時代の人間であるかのように見なしている。そもそも、この本の発端は、鷗外が、武鑑を集めていくなかで、見いだした、渋江氏という名前の探索から始まる。
有名な一節、
「もし抽斎がわたくしのコンタンポランであったならば、二人の袖は横町の溝板の上ですれ合ったはずである。」(その六、p.24)
この感覚を、その後さらにおよそ一世紀を経た今でも、なにがしか共有できる、ぎりぎりのところにあるのかもしれない。
第二は、(これは、誰かがこの作品について書いていたことで覚えていることなのだが……その誰かは忘れてしまった……)『渋江抽斎』は、ドキュメンタリー、ノンフィクションとしての方法論で書かれている。言われてみれば、たしかにそのとおりである。武鑑の収集で目にした人物の事跡を追って、鷗外は探索の手を伸ばしている。その探索の跡にしたがって、この作品は展開する。
まさに、ノンフィクションとしての面白さ、である。
以上の二点が、この作品についての、面白さ……私なりに感じる……の要因であろうかと思う。
だが、これも、(強いて言うならということだが)、江戸時代の漢詩文、あるいは、考証学という世界がどんなものであったか、ある程度のなじみがないと、この作品世界の中に入っていけないかもしれない。ただ、私の場合、大学の時に勉強したのが、国語学を軸とした、周辺の文献学のあたり……その他には、折口信夫につらなる民俗学があるのだが……であったことが、幸いに、予備知識として役にたっているということがある。
渋江抽斎といえば、『経籍訪古志』なのであるが、この本が、だいたいどのような本であるかは、学生の時に勉強した知識のなかにある。といっても、これを精読したというところまではしてはいないけれど。
そして、先日、東京国立博物館での鷗外の展示を見て、晩年の鷗外が、どのような知的環境のなかにあったか、その一端に触れることによって、さらに、興味関心がたかまったということもある。
ともあれ、『渋江抽斎』は、とにかく面白い。この作品を面白いと思って読める、読書の感覚というものを、なんとか継承していきたいものであると思う。さらにつづけて『伊沢蘭軒』『北条霞亭』と読もうと思っている。それから、中村真一郎の著作なども。
そういえば、去年の夏、いまごろのことであったろうか、中村真一郎『頼山陽とその時代』(上・下、ちくま学芸文庫)を読んだのであった。この本について、何か、感じたことを文章に書いておきたいと思って、まだはたしていない。これも、できれば、さらに再々読しておきたい本の一つである。
『半分、青い。』あれこれ「羽ばたきたい!」 ― 2018-07-08
2018-07-08 當山日出夫(とうやまひでお)
『半分、青い。』第14週「羽ばたきたい!」
https://www.nhk.or.jp/hanbunaoi/story/week_14.html
前回は、
やまもも書斎記 2018年7月1日
『半分、青い。』あれこれ「仕事が欲しい!」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/07/01/8906998
この週で、鈴愛の人生は大きく動いた。
第一に、週の前半。漫画家をやめる。
ここで鈴愛は、漫画家の道を断念する。ここ描き方は、かなりシリアスなものがあったと感じる。漫画という創作にかかわる仕事に行き詰まったとき、その先にあるのは、自分に才能があるかどうかの見極めである。鈴愛は、ここで、自分には漫画家としての才能が無いと、自ら判断を下しておりる決断をしている。
ジャンルは違うとはいえ、ドラマの脚本を書く仕事も、創造にかかわる仕事である。ここで、作者(北川悦吏子)は、暗黙のうちに、自分はこれからも脚本家としてドラマを書いていく……この決意を、語っていたように見ていて感じるところがあった。
漫画家としての才能について、厳しくつきつけられたのは、恩師・秋風羽織との合作の形で発表されることになった、「月が屋根に隠れる」である。これが、鈴愛の単独の作品であれば、また次に頑張ればいいとなったかもしれない。しかし、合作という形をとることによって、茫漠とストーリーを考えるのと、それを、確実に一つのイメージとして、絵に描いていくこととは、大きな隔たりがある。それをつきつけられて、鈴愛は自らの才能に絶望することになった。
このような創造にかかわる仕事について、シリアスな描き方をするのは、ある意味で、脚本家である北川悦吏子に、それだけの自信があってのことであろうと思う。自信というよりも、自らの覚悟といってもいいかもしれない。
第二に、その後の鈴愛である。
その間の紆余曲折は、あっさりと省略して、いきなり百円ショップのアルバイト店員ということになってしまった。ここで、ボクテと裕子の登場、あるいは、故郷の岐阜の家族が出てこなかったら、まるで違うドラマがいきなりはじまったかのごとくである。
その百円ショップも、なにかいわくがありげである。オーナーの三姉妹。それから、映画監督とその助手(助監督)の二人。
このドラマでは、この時代の世相をあまり描かないようでもある。鈴愛が、転職した時期は、バブル崩壊後の失われた時代でもある。この時代の若者が、どのように考えて仕事を選んでいったのか、このあたりの事情は、このドラマでは描いていない。バブル崩壊と、漫画家失業とが、重なったのが鈴愛の人生の不運という気がしないでもないが、このような方向からは、ドラマは描かないようである。
職を探すにあたって、漫画家をやっていたという経歴は、無職であったより悪い……という意味のことを言っていたかと思うが、言い得て妙である。だが、このところは、あっさりと流してしまって、百円ショップ・大納言のアルバイト店員になるところからスタートしていた。
以上の二点が、この週の見どころかと思う。
前半と後半で、まったく違った状況で生きる鈴愛。それを、一つの週の中でつないで見せたのは、脚本のうまさというべきであろうか。そして、次週は、結婚ということになるのだろうか。
ところで、律はもう出てこないのだろうか。これも今後の展開で気になるところである。
『半分、青い。』第14週「羽ばたきたい!」
https://www.nhk.or.jp/hanbunaoi/story/week_14.html
前回は、
やまもも書斎記 2018年7月1日
『半分、青い。』あれこれ「仕事が欲しい!」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/07/01/8906998
この週で、鈴愛の人生は大きく動いた。
第一に、週の前半。漫画家をやめる。
ここで鈴愛は、漫画家の道を断念する。ここ描き方は、かなりシリアスなものがあったと感じる。漫画という創作にかかわる仕事に行き詰まったとき、その先にあるのは、自分に才能があるかどうかの見極めである。鈴愛は、ここで、自分には漫画家としての才能が無いと、自ら判断を下しておりる決断をしている。
ジャンルは違うとはいえ、ドラマの脚本を書く仕事も、創造にかかわる仕事である。ここで、作者(北川悦吏子)は、暗黙のうちに、自分はこれからも脚本家としてドラマを書いていく……この決意を、語っていたように見ていて感じるところがあった。
漫画家としての才能について、厳しくつきつけられたのは、恩師・秋風羽織との合作の形で発表されることになった、「月が屋根に隠れる」である。これが、鈴愛の単独の作品であれば、また次に頑張ればいいとなったかもしれない。しかし、合作という形をとることによって、茫漠とストーリーを考えるのと、それを、確実に一つのイメージとして、絵に描いていくこととは、大きな隔たりがある。それをつきつけられて、鈴愛は自らの才能に絶望することになった。
このような創造にかかわる仕事について、シリアスな描き方をするのは、ある意味で、脚本家である北川悦吏子に、それだけの自信があってのことであろうと思う。自信というよりも、自らの覚悟といってもいいかもしれない。
第二に、その後の鈴愛である。
その間の紆余曲折は、あっさりと省略して、いきなり百円ショップのアルバイト店員ということになってしまった。ここで、ボクテと裕子の登場、あるいは、故郷の岐阜の家族が出てこなかったら、まるで違うドラマがいきなりはじまったかのごとくである。
その百円ショップも、なにかいわくがありげである。オーナーの三姉妹。それから、映画監督とその助手(助監督)の二人。
このドラマでは、この時代の世相をあまり描かないようでもある。鈴愛が、転職した時期は、バブル崩壊後の失われた時代でもある。この時代の若者が、どのように考えて仕事を選んでいったのか、このあたりの事情は、このドラマでは描いていない。バブル崩壊と、漫画家失業とが、重なったのが鈴愛の人生の不運という気がしないでもないが、このような方向からは、ドラマは描かないようである。
職を探すにあたって、漫画家をやっていたという経歴は、無職であったより悪い……という意味のことを言っていたかと思うが、言い得て妙である。だが、このところは、あっさりと流してしまって、百円ショップ・大納言のアルバイト店員になるところからスタートしていた。
以上の二点が、この週の見どころかと思う。
前半と後半で、まったく違った状況で生きる鈴愛。それを、一つの週の中でつないで見せたのは、脚本のうまさというべきであろうか。そして、次週は、結婚ということになるのだろうか。
ところで、律はもう出てこないのだろうか。これも今後の展開で気になるところである。
追記 2018-07-15
この続きは、
やまもも書斎記 2018年7月15日
『半分、青い。』あれこれ「すがりたい!」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/07/15/8916952
この続きは、
やまもも書斎記 2018年7月15日
『半分、青い。』あれこれ「すがりたい!」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/07/15/8916952
『かもめ』チェーホフ ― 2018-07-09
2018-07-09 當山日出夫(とうやまひでお)

チェーホフ.神西清(訳).『かもめ・ワーニャ伯父さん』(新潮文庫).1967(2004.改版)
http://www.shinchosha.co.jp/book/206502/
チェーホフの戯曲を読んでいる。
チェーホフの作品のいくつかを去年、読み返した。
やまもも書斎記 2017年10月19日
『かわいい女・犬を連れた奥さん』チェーホフ
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2017/10/19/8708363
やまもも書斎記 2017年10月20日
『ともしび・谷間』チェーホフ
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2017/10/20/8709033
やまもも書斎記 2017年10月30日
『六号病棟・退屈な話』チェーホフ
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2017/10/30/8717513
そして、戯曲『かもめ』『ワーニャ伯父さん』『桜の園』『三人姉妹』である。神西清訳で、新潮文庫で読める。これら、今の本は、改版して字が大きくきれいになっている。解説を書いているのは、池田健太郎である。
まずは、『かもめ』から。
戯曲作家としてのチェーホフの名が、この作品によって定まったということらしい。
私の今の生活では、演劇というものを見ない。これまでの人生の中でも、演劇というものにはあまり接しては来なかった。(とはいっても、東京に住んでいるとき、国立劇場の文楽公演のかなりは見ているのだが。)
だから、演劇について素養があるというわけではない。戯曲という形式の文学作品として読むことになる。
『かもめ』、この作品も再読である。若い時、学生のころ、昔の新潮文庫版で目をとおしたことはあった。だが、特に、チェーホフの世界にひかれるということはなく過ぎてしまっていた。それよりも、ロシア文学といえば、ドストエフスキーを読む、そのような時代でもあった。
年をとってから、再び、チェーホフの戯曲を読んで見て、登場人物の台詞のなかに、この世界が凝縮されてあるような印象をうける。ドストエフスキーなどとは違った意味で、世紀末のロシアというものを感じさせる。そして、そこに強く共感する自分があることに気づく。
チェーホフの戯曲は、難解ということではないが、しかし、登場人物の関係が錯綜しているともいえる。様々な登場人物の相互の関係が、微妙にからまりあっている。一読しただけでは、よくわからない。二度、三度と、繰り返し読んで、ようやく、ストーリーの展開、そこでの登場人物の台詞の意味、というようなものが頭にはいってくるようになる。
『かもめ』も三回、四回ぐらい、去年から、読み返してみただろうか。
この作品、最後のシーンが印象的であるが……なぜ、このような結末になっているのか、ちょっと理解しかねるところがないではない。
だが、この作品の核心は、最後のところで出てくるニーナ台詞であろう。
「わたしたちの仕事で大事なものは、名声とか光栄とか、わたしが空想していたものではなくって、じつは忍耐力だといういうことが、わたしにはわかったの。得心が行ったの。」(pp.120-121)
ニーナは、人生に失敗したかもしれないが、絶望してはいない。未来に希望を託している。この作品を読んでいって、終わりのところのニーナのこの台詞に、深い感銘をおぼえる。が、それも、最後のシーンで暗転してしまうのだが。
ともあれ、この後のチェーホフの作品『ワーニャ伯父さん』『桜の園』『三人姉妹』と、この未来への希望という方向に、発展していっていることは、順番に作品を読んでいくことによって理解されるところである。
一九世紀末から二〇世紀の初めにかけて、それは、ロシア革命の前夜でもあるのだが、この時代のロシアを生きたチェーホフにとって、近代とは、未来への希望を感じるものであった。その後、ソ連の成立があり、二度の世界大戦を経て、そのソ連も崩壊するという歴史の結果を知っている、今日、二一世紀の今になって読んでみても、一世紀のときのへだたりがあるにもかかわらず、これからの世界の未来になにがしかの希望を、この作品から感じとることができる。
http://www.shinchosha.co.jp/book/206502/
チェーホフの戯曲を読んでいる。
チェーホフの作品のいくつかを去年、読み返した。
やまもも書斎記 2017年10月19日
『かわいい女・犬を連れた奥さん』チェーホフ
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2017/10/19/8708363
やまもも書斎記 2017年10月20日
『ともしび・谷間』チェーホフ
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2017/10/20/8709033
やまもも書斎記 2017年10月30日
『六号病棟・退屈な話』チェーホフ
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2017/10/30/8717513
そして、戯曲『かもめ』『ワーニャ伯父さん』『桜の園』『三人姉妹』である。神西清訳で、新潮文庫で読める。これら、今の本は、改版して字が大きくきれいになっている。解説を書いているのは、池田健太郎である。
まずは、『かもめ』から。
戯曲作家としてのチェーホフの名が、この作品によって定まったということらしい。
私の今の生活では、演劇というものを見ない。これまでの人生の中でも、演劇というものにはあまり接しては来なかった。(とはいっても、東京に住んでいるとき、国立劇場の文楽公演のかなりは見ているのだが。)
だから、演劇について素養があるというわけではない。戯曲という形式の文学作品として読むことになる。
『かもめ』、この作品も再読である。若い時、学生のころ、昔の新潮文庫版で目をとおしたことはあった。だが、特に、チェーホフの世界にひかれるということはなく過ぎてしまっていた。それよりも、ロシア文学といえば、ドストエフスキーを読む、そのような時代でもあった。
年をとってから、再び、チェーホフの戯曲を読んで見て、登場人物の台詞のなかに、この世界が凝縮されてあるような印象をうける。ドストエフスキーなどとは違った意味で、世紀末のロシアというものを感じさせる。そして、そこに強く共感する自分があることに気づく。
チェーホフの戯曲は、難解ということではないが、しかし、登場人物の関係が錯綜しているともいえる。様々な登場人物の相互の関係が、微妙にからまりあっている。一読しただけでは、よくわからない。二度、三度と、繰り返し読んで、ようやく、ストーリーの展開、そこでの登場人物の台詞の意味、というようなものが頭にはいってくるようになる。
『かもめ』も三回、四回ぐらい、去年から、読み返してみただろうか。
この作品、最後のシーンが印象的であるが……なぜ、このような結末になっているのか、ちょっと理解しかねるところがないではない。
だが、この作品の核心は、最後のところで出てくるニーナ台詞であろう。
「わたしたちの仕事で大事なものは、名声とか光栄とか、わたしが空想していたものではなくって、じつは忍耐力だといういうことが、わたしにはわかったの。得心が行ったの。」(pp.120-121)
ニーナは、人生に失敗したかもしれないが、絶望してはいない。未来に希望を託している。この作品を読んでいって、終わりのところのニーナのこの台詞に、深い感銘をおぼえる。が、それも、最後のシーンで暗転してしまうのだが。
ともあれ、この後のチェーホフの作品『ワーニャ伯父さん』『桜の園』『三人姉妹』と、この未来への希望という方向に、発展していっていることは、順番に作品を読んでいくことによって理解されるところである。
一九世紀末から二〇世紀の初めにかけて、それは、ロシア革命の前夜でもあるのだが、この時代のロシアを生きたチェーホフにとって、近代とは、未来への希望を感じるものであった。その後、ソ連の成立があり、二度の世界大戦を経て、そのソ連も崩壊するという歴史の結果を知っている、今日、二一世紀の今になって読んでみても、一世紀のときのへだたりがあるにもかかわらず、これからの世界の未来になにがしかの希望を、この作品から感じとることができる。
追記 2018-07-16
この続きは、
やまもも書斎記 2018年7月16日
『ワーニャ伯父さん』チェーホフ
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/07/16/8918134
この続きは、
やまもも書斎記 2018年7月16日
『ワーニャ伯父さん』チェーホフ
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2018/07/16/8918134
『西郷どん』あれこれ「西郷どん」スペシャル2 ― 2018-07-10
2018-07-10 當山日出夫(とうやまひでお)
NHKはいったい何を考えているのか……まあ、確かに、前回のスペシャルもそれなり面白かったといえば、面白かったのであるが、しかし、無くてもよかったように思う。ここにきて、スペシャル第二弾である。
ドラマの展開としては、遠島になっていた西郷が、呼び戻されて、これから倒幕の志士として活躍する、その直前で、今後の展開についての解説といったところだろうか。
取り上げられていた登場人物は、坂本竜馬、勝海舟、岩倉具視、桂小五郎、である。ドラマとしては、これらの登場人物によって、幕末から明治維新を描こうということである。
ちょっと気になったこと……それは、「革命」ということばを、番組中で使っていたことである。明治維新は、「革命」なのであろうか。いや、そうではなく、これからこのドラマは、明治維新を「革命」として描こうという意思表示ととらえるべきかもしれない。
歴史学の分野においても、明治維新を「革命」ととらえる考え方には、いろいろあるはずである。それをふまえたうえで、「革命」ということでドラマが展開することになるのだろう。
この「革命」のことば……「易姓革命」ということばでは古くからある用語である。だが、今日のような意味で使われるようになったのは、新しいことだろう。だが、そのようなことをいうのは、野暮である。ここは、「明治維新=革命」という歴史観に沿って、このドラマがつくってあるのだと、理解しておけばよい。その意図を鮮明にしたという意味でのスペシャルであった。
NHKはいったい何を考えているのか……まあ、確かに、前回のスペシャルもそれなり面白かったといえば、面白かったのであるが、しかし、無くてもよかったように思う。ここにきて、スペシャル第二弾である。
ドラマの展開としては、遠島になっていた西郷が、呼び戻されて、これから倒幕の志士として活躍する、その直前で、今後の展開についての解説といったところだろうか。
取り上げられていた登場人物は、坂本竜馬、勝海舟、岩倉具視、桂小五郎、である。ドラマとしては、これらの登場人物によって、幕末から明治維新を描こうということである。
ちょっと気になったこと……それは、「革命」ということばを、番組中で使っていたことである。明治維新は、「革命」なのであろうか。いや、そうではなく、これからこのドラマは、明治維新を「革命」として描こうという意思表示ととらえるべきかもしれない。
歴史学の分野においても、明治維新を「革命」ととらえる考え方には、いろいろあるはずである。それをふまえたうえで、「革命」ということでドラマが展開することになるのだろう。
この「革命」のことば……「易姓革命」ということばでは古くからある用語である。だが、今日のような意味で使われるようになったのは、新しいことだろう。だが、そのようなことをいうのは、野暮である。ここは、「明治維新=革命」という歴史観に沿って、このドラマがつくってあるのだと、理解しておけばよい。その意図を鮮明にしたという意味でのスペシャルであった。





最近のコメント