雪柳 ― 2022-05-11
2022年5月11日 當山日出夫(とうやまひでお)
水曜日は写真の日。今日は雪柳である。
前回は、
やまもも書斎記 2022年5月4日
オオイヌノフグリ
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2022/05/04/9487329
先月の写真の撮りおきのストックからである。雪柳も春を感じる花のひとつといっていい。我が家の近所の、少し行ったところで、毎年、雪柳の花が咲く。たわわにというか、ふさふさにというか、こんもりというか、とにかく白い塊がゆらゆらと風にふわふわしているのが目にはいる。
我が家にもちょっとだけある。ほんの小さな木なので、そんなに多くの花が咲くことはない。しかし、毎年、春になると白い花が咲く。これも、接写してみると、ちょっと違ったイメージになる。遠くから見るのと、近くに寄って見るのとでは、かなり印象がことなる。
今は、小手毬の花が咲いている。空き地を見るとヘビイチゴの花も見える。池のほとりでは紫蘭の花が咲いている。そろそろ、我が家の周囲の花も初夏のものになりそうである。
水曜日は写真の日。今日は雪柳である。
前回は、
やまもも書斎記 2022年5月4日
オオイヌノフグリ
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2022/05/04/9487329
先月の写真の撮りおきのストックからである。雪柳も春を感じる花のひとつといっていい。我が家の近所の、少し行ったところで、毎年、雪柳の花が咲く。たわわにというか、ふさふさにというか、こんもりというか、とにかく白い塊がゆらゆらと風にふわふわしているのが目にはいる。
我が家にもちょっとだけある。ほんの小さな木なので、そんなに多くの花が咲くことはない。しかし、毎年、春になると白い花が咲く。これも、接写してみると、ちょっと違ったイメージになる。遠くから見るのと、近くに寄って見るのとでは、かなり印象がことなる。
今は、小手毬の花が咲いている。空き地を見るとヘビイチゴの花も見える。池のほとりでは紫蘭の花が咲いている。そろそろ、我が家の周囲の花も初夏のものになりそうである。
Nikon D500
TAMRON SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD
2022年5月10日記
映像の世紀バタフライエフェクト「ヴェルヴェットの奇跡」 ― 2022-05-12
2022年5月12日 當山日出夫(とうやまひでお)
映像の世紀バタフライエフェクト「ヴェルヴェットの奇跡 革命家とロックシンガー」
二〇二二年五月九日の放送。録画しておいて、翌日の朝に見た。
これを見て思ったことはいろいろとあるが、まず何よりも、この番組はいつの編集になるのだろうかという、素朴が疑問がある。はたして、二〇二二年二月の、ロシアのウクライナ侵略の後の編集にかかわるものなのだろうか。チェコスロバキアの、プラハの春とその弾圧、そして、その後の一九八九年の共産主義国家の崩壊、このことを語るのに、今年のロシアとウクライナとのことを抜きにしては、もはや語ることはできない。歴史の結果、共産圏諸国は崩壊したが、その後さらに次の段階として、ロシアのことがある。(さらには、中国のこともあるのだが。)
これまでの「映像の世紀バタフライエフェクト」では、かつての「映像の世紀」シリーズで使った映像資料を主につかって、再編集したものであった。だが、この回は、ほとんどが新しいものである。(昨年、「映像の世紀」シリーズを再放送したのは、その全部を見ている。)
ただ、ロックが革命を導いたとするのは、やや短絡的であるかとも思う。だが、それに様々な社会の動き、人びとの思いを象徴させることはできる。
月並みな感想になるが、つまるところは、表現の自由とメディアということになるにちがいない。
番組では、中国の劉暁波のことに言及があった。(中国において、劉暁波が再評価される動きが表面化するときがあるとするならば、その時こそ、中国共産党一党支配の終わりの始まりかもしれないとも思う。)
2022年5月10日記
映像の世紀バタフライエフェクト「ヴェルヴェットの奇跡 革命家とロックシンガー」
二〇二二年五月九日の放送。録画しておいて、翌日の朝に見た。
これを見て思ったことはいろいろとあるが、まず何よりも、この番組はいつの編集になるのだろうかという、素朴が疑問がある。はたして、二〇二二年二月の、ロシアのウクライナ侵略の後の編集にかかわるものなのだろうか。チェコスロバキアの、プラハの春とその弾圧、そして、その後の一九八九年の共産主義国家の崩壊、このことを語るのに、今年のロシアとウクライナとのことを抜きにしては、もはや語ることはできない。歴史の結果、共産圏諸国は崩壊したが、その後さらに次の段階として、ロシアのことがある。(さらには、中国のこともあるのだが。)
これまでの「映像の世紀バタフライエフェクト」では、かつての「映像の世紀」シリーズで使った映像資料を主につかって、再編集したものであった。だが、この回は、ほとんどが新しいものである。(昨年、「映像の世紀」シリーズを再放送したのは、その全部を見ている。)
ただ、ロックが革命を導いたとするのは、やや短絡的であるかとも思う。だが、それに様々な社会の動き、人びとの思いを象徴させることはできる。
月並みな感想になるが、つまるところは、表現の自由とメディアということになるにちがいない。
番組では、中国の劉暁波のことに言及があった。(中国において、劉暁波が再評価される動きが表面化するときがあるとするならば、その時こそ、中国共産党一党支配の終わりの始まりかもしれないとも思う。)
2022年5月10日記
『戦場のコックたち』深緑野分/創元推理文庫 ― 2022-05-13
2022年5月13日 當山日出夫(とうやまひでお)

深緑野分.『戦場のコックたち』(創元推理文庫).東京創元社.2019(東京創元社.2015)
http://www.tsogen.co.jp/np/isbn/9784488453121
深緑野分の作品としては、こちらの方が先の刊行である。『ベルリンは晴れているか』がよかったので、さかのぼってこれも読んでみたいと思った。
やまもも書斎記 2022年4月15日
『ベルリンは晴れているか』深緑野分/ちくま文庫
https://yamamomo.asablo.jp/blog/2022/04/15/9481872
第二世界大戦に参戦したアメリカ軍の兵士のものがたりである。兵士といってもコックである。戦場で食事を作るのが任務である。そのコックたちを主人公にした、戦場ミステリである。そして、傑作である。
読んで思うことはいろいろあるが、二つばかり書いてみる。
第一には、ミステリとしてよくできていること。戦場が舞台なのだが、出てくる謎は、日常の謎である。ミステリだからといって、殺人事件がおこるわけではない。日常の不思議な謎を、コックたちの推理が鮮やかに解きあかす。そして、その謎も日常の謎でありながら、やはり戦場ならではのものである。
そして、連作短篇という形式をとっていながら、全体として大きな物語になっている。このような小説のつくりは珍しいということではないが、しかし、読んでみて巧みに作ってあると感じさせる。全体を通じての大きな謎もまた魅力的なものになっている。
第二には戦場小説としてよくできていること。ここではあえて戦場小説と書いてみた。戦争小説というのとはちょっと違う。たしかに、なかには戦闘場面も出てはくるのだが、全体としては、戦場、また、そのやや後方における、軍隊と兵士の物語ということで展開する。
これが、普通の戦争冒険小説とは、ひと味違った魅力になっている。ノルマンディー上陸作戦から、ベルリンまでの戦場が描かれる。だが、その最前線の戦闘の場面よりも、後方の兵站のことなどが、主に小説の舞台になっている。この意味においては、新しいスタイルの戦争小説といっていいのだろう。
以上の二点のことを思ってみる。
さらに書いてみるならば、この小説を、単なるミステリ、戦場小説としては、今では読むことができない。二〇二二年二月のロシアによるウクライナ侵略からこのかた、戦場、戦争というものが、毎時のニュースで報道されるようになてきている。この社会情勢のなかでは、この小説で描かれている、戦場における兵士たちの描写が、非常に印象深い。ただの小説のなかのこととしては、読み過ごすことができないものがある。
この作品は、今こそ広く読まれていい作品であると思う。
2022年5月12日記
http://www.tsogen.co.jp/np/isbn/9784488453121
深緑野分の作品としては、こちらの方が先の刊行である。『ベルリンは晴れているか』がよかったので、さかのぼってこれも読んでみたいと思った。
やまもも書斎記 2022年4月15日
『ベルリンは晴れているか』深緑野分/ちくま文庫
https://yamamomo.asablo.jp/blog/2022/04/15/9481872
第二世界大戦に参戦したアメリカ軍の兵士のものがたりである。兵士といってもコックである。戦場で食事を作るのが任務である。そのコックたちを主人公にした、戦場ミステリである。そして、傑作である。
読んで思うことはいろいろあるが、二つばかり書いてみる。
第一には、ミステリとしてよくできていること。戦場が舞台なのだが、出てくる謎は、日常の謎である。ミステリだからといって、殺人事件がおこるわけではない。日常の不思議な謎を、コックたちの推理が鮮やかに解きあかす。そして、その謎も日常の謎でありながら、やはり戦場ならではのものである。
そして、連作短篇という形式をとっていながら、全体として大きな物語になっている。このような小説のつくりは珍しいということではないが、しかし、読んでみて巧みに作ってあると感じさせる。全体を通じての大きな謎もまた魅力的なものになっている。
第二には戦場小説としてよくできていること。ここではあえて戦場小説と書いてみた。戦争小説というのとはちょっと違う。たしかに、なかには戦闘場面も出てはくるのだが、全体としては、戦場、また、そのやや後方における、軍隊と兵士の物語ということで展開する。
これが、普通の戦争冒険小説とは、ひと味違った魅力になっている。ノルマンディー上陸作戦から、ベルリンまでの戦場が描かれる。だが、その最前線の戦闘の場面よりも、後方の兵站のことなどが、主に小説の舞台になっている。この意味においては、新しいスタイルの戦争小説といっていいのだろう。
以上の二点のことを思ってみる。
さらに書いてみるならば、この小説を、単なるミステリ、戦場小説としては、今では読むことができない。二〇二二年二月のロシアによるウクライナ侵略からこのかた、戦場、戦争というものが、毎時のニュースで報道されるようになてきている。この社会情勢のなかでは、この小説で描かれている、戦場における兵士たちの描写が、非常に印象深い。ただの小説のなかのこととしては、読み過ごすことができないものがある。
この作品は、今こそ広く読まれていい作品であると思う。
2022年5月12日記
『人間とマンボウ』北杜夫/中公文庫 ― 2022-05-14
2022年5月14日 當山日出夫(とうやまひでお)

北杜夫.『人間とマンボウ』(中公文庫).中央公論新社.2022(中央公論社.1972 中公文庫.1975)
https://www.chuko.co.jp/bunko/2022/04/207197.html
これは、以前に中央公論社で刊行になり、中公文庫でも刊行されていたものの、文庫本の新版である。北杜夫の「どくとるマンボウ」のシリーズのいくつかは学生のときに手にしたのだが、この本は読まずに過ぎてしまっていた。
タイトルどおり、様々な人物についてのエッセイ集ということになる。読んで非常に面白い本である。印象に残ることを、二つばかり書いておきたい。
第一に、三島由紀夫。
三島由紀夫との交流について書いてある。三島由紀夫が、『楡家の人びと』を激賞した話しは有名だと思う。この本で出てくるのが、『白きたおやかな峰』についての文章。書簡の引用という形で掲載してある。これを読むと、三島由紀夫は、文学の鑑賞眼においても、一流の見識を有していたことが理解される。
ここに掲載の三島由紀夫関係の文章は、すぐれた三島論の一つであり、また、三島由紀夫の残したすぐれた文学論の一つといっていいだろう。
第二に、斎藤茂吉。
父親の斎藤茂吉についての、いくつかの文章を収録してある。斎藤茂吉については、北杜夫の書いた評伝四部作は読んだ。それといくぶん重複するところはあるかと感じるが、しかし、ここに収められた文章は、子供の北杜夫でしか書けない斎藤茂吉である。斎藤茂吉についての文章として読んで、非常に面白い。
以上の二点が印象に残るところである。
この他、近現代の作家についての文章が収められている。遠藤周作や辻邦生、手塚治虫などについて書かれたものもある。どれも面白い。
どくとるマンボウの主なものは読んできたつもりであるが、読みそびれているものがいくつかある。今でも読める本がある。今は三島由紀夫を軸に呼んでいるのだが、折をみて北杜夫の本も読んでおきたい。
2022年5月13日記
https://www.chuko.co.jp/bunko/2022/04/207197.html
これは、以前に中央公論社で刊行になり、中公文庫でも刊行されていたものの、文庫本の新版である。北杜夫の「どくとるマンボウ」のシリーズのいくつかは学生のときに手にしたのだが、この本は読まずに過ぎてしまっていた。
タイトルどおり、様々な人物についてのエッセイ集ということになる。読んで非常に面白い本である。印象に残ることを、二つばかり書いておきたい。
第一に、三島由紀夫。
三島由紀夫との交流について書いてある。三島由紀夫が、『楡家の人びと』を激賞した話しは有名だと思う。この本で出てくるのが、『白きたおやかな峰』についての文章。書簡の引用という形で掲載してある。これを読むと、三島由紀夫は、文学の鑑賞眼においても、一流の見識を有していたことが理解される。
ここに掲載の三島由紀夫関係の文章は、すぐれた三島論の一つであり、また、三島由紀夫の残したすぐれた文学論の一つといっていいだろう。
第二に、斎藤茂吉。
父親の斎藤茂吉についての、いくつかの文章を収録してある。斎藤茂吉については、北杜夫の書いた評伝四部作は読んだ。それといくぶん重複するところはあるかと感じるが、しかし、ここに収められた文章は、子供の北杜夫でしか書けない斎藤茂吉である。斎藤茂吉についての文章として読んで、非常に面白い。
以上の二点が印象に残るところである。
この他、近現代の作家についての文章が収められている。遠藤周作や辻邦生、手塚治虫などについて書かれたものもある。どれも面白い。
どくとるマンボウの主なものは読んできたつもりであるが、読みそびれているものがいくつかある。今でも読める本がある。今は三島由紀夫を軸に呼んでいるのだが、折をみて北杜夫の本も読んでおきたい。
2022年5月13日記
『ちむどんどん』あれこれ「フーチャンプルーの涙」 ― 2022-05-15
2022年5月15日 當山日出夫(とうやまひでお)
『ちむどんどん』第5週「フーチャンプルーの涙」
https://www.nhk.or.jp/chimudondon/story/week_05.html
前回は、
やまもも書斎記 20220年5月8日
『ちむどんどん』あれこれ「青春ナポリタン」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2022/05/08/9488621
五月一五日は、沖縄復帰の日である。この日の日付は、憶えている。特に沖縄に関心があったということではなく、たまたま京都の葵祭の日と同じであるということで、記憶に残っているのだが。
暢子は、東京に行くことになった。そこには、賢秀ニーニーの力があった。ボクサーとして成功したということのようだ。これで、比嘉家の借金もどうにかなり、暢子も東京に行けることになった。
沖縄編は、もうちょっとあっても良かったかと思うが、ここは、五月一五日に合わせて、東京編に展開していくということなのだろう。
ちょっと気になることがいくつかある。
第一に、フーチャンプルー。
比嘉家は貧乏である。それは分かっているのだが、晩御飯が、フーチャンプルーだけということは、どうかなと思う。もっと他に食べるものは、なかったのだろうか。
第二に、サンダル。
一九七二年、暢子は山原から東京に旅立つのだが、バスに乗るときサンダルだった。学校には靴を履いて通っているのだが、東京に行くのに、飛行機になるか船になるかはわからないが、サンダル履きで行くというのは、どうなのだろうか。
ささいなことかもしれないが、ちょっと気になったことである。
それから、さらに書いておくならば、何故、ニーニーはお金を、比嘉家に送らなかったのだろうか。自分の家族の家に送ればいいのにと思うが、ここは何か事情があったのだろうか。
それに、その当時、日本から沖縄(返還前)にお金を送るとして、円の現金で、しかも一万円札を普通の封筒に入れて送るということは、あったのだろうか。
いろいろ気になるところはある。
沖縄編では、いろんな場面で暢子は「ありがとう」と言っていたように思う。このドラマは、家族とありがとうの物語なのかもしれない。
次週から、東京編がはじまるようだ。
さて、暢子は東京に行くとして、住むところとか、働くところとかの、あてはあってのことなのだろうか。とにかく東京に行きさえすればどうにかなるでは、ちょっと無謀なような気もする。
ともあれ、東京での暢子の生活がどのようになるか、楽しみに見ることにしよう。
2022年5月14日記
『ちむどんどん』第5週「フーチャンプルーの涙」
https://www.nhk.or.jp/chimudondon/story/week_05.html
前回は、
やまもも書斎記 20220年5月8日
『ちむどんどん』あれこれ「青春ナポリタン」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2022/05/08/9488621
五月一五日は、沖縄復帰の日である。この日の日付は、憶えている。特に沖縄に関心があったということではなく、たまたま京都の葵祭の日と同じであるということで、記憶に残っているのだが。
暢子は、東京に行くことになった。そこには、賢秀ニーニーの力があった。ボクサーとして成功したということのようだ。これで、比嘉家の借金もどうにかなり、暢子も東京に行けることになった。
沖縄編は、もうちょっとあっても良かったかと思うが、ここは、五月一五日に合わせて、東京編に展開していくということなのだろう。
ちょっと気になることがいくつかある。
第一に、フーチャンプルー。
比嘉家は貧乏である。それは分かっているのだが、晩御飯が、フーチャンプルーだけということは、どうかなと思う。もっと他に食べるものは、なかったのだろうか。
第二に、サンダル。
一九七二年、暢子は山原から東京に旅立つのだが、バスに乗るときサンダルだった。学校には靴を履いて通っているのだが、東京に行くのに、飛行機になるか船になるかはわからないが、サンダル履きで行くというのは、どうなのだろうか。
ささいなことかもしれないが、ちょっと気になったことである。
それから、さらに書いておくならば、何故、ニーニーはお金を、比嘉家に送らなかったのだろうか。自分の家族の家に送ればいいのにと思うが、ここは何か事情があったのだろうか。
それに、その当時、日本から沖縄(返還前)にお金を送るとして、円の現金で、しかも一万円札を普通の封筒に入れて送るということは、あったのだろうか。
いろいろ気になるところはある。
沖縄編では、いろんな場面で暢子は「ありがとう」と言っていたように思う。このドラマは、家族とありがとうの物語なのかもしれない。
次週から、東京編がはじまるようだ。
さて、暢子は東京に行くとして、住むところとか、働くところとかの、あてはあってのことなのだろうか。とにかく東京に行きさえすればどうにかなるでは、ちょっと無謀なような気もする。
ともあれ、東京での暢子の生活がどのようになるか、楽しみに見ることにしよう。
2022年5月14日記
追記 2022年5月22日
この続きは、
やまもも書斎記 2022年5月22日
『ちむどんどん』あれこれ「はじまりのゴーヤーチャンプルー」
https://yamamomo.asablo.jp/blog/2022/05/22/9492792
この続きは、
やまもも書斎記 2022年5月22日
『ちむどんどん』あれこれ「はじまりのゴーヤーチャンプルー」
https://yamamomo.asablo.jp/blog/2022/05/22/9492792
世界サブカルチャー史 欲望の系譜「アメリカ 闘争の60s」 ― 2022-05-16
2022年5月16日 當山日出夫(とうやまひでお)
世界サブカルチャー史 欲望の系譜「アメリカ 闘争の60s」
https://www.nhk.jp/p/ts/GLP33Y7513/episode/te/M9KKVK5R1N/
「世界サブカルチャー史」ということなのだが、扱っているのは、アメリカのことがほとんどという構成であった。まあ、これは、第二次大戦後の世界において「サブカルチャー」が生まれ、そして、世界を牽引していったのがアメリカという国であるという事情を考えれば、これはこのようになることなのかもしれない。この回での例外は、英国のビートルズということになるだろうか。
しかし、六〇年代をあつかうならば、日本においては、安保闘争のこともあり、また、フランスでは五月革命もあった。これらにまったく触れることがないというのも、ちょっと物足りない気もする。また、サブカルチャーといいながら、キューバ危機など、かなり政治的なことにも言及があった。ただ、これは、時代の背景説明として必要であったともいえるかもしれないが。
私は、一九五五年の生まれなので、六〇年代というと記憶にあるうちのことになる。登場した映画などについては、憶えているものが多い。映画館で見たということではないが、その時代の記憶として、ああこのような映画があったなと思い出す。そして、あの映画は、今から歴史的に振り返ってみるならば、そのような意味があり、解釈ができるのかと、これはこれとして、新知見であった。
結局、六〇年代に生まれた、サブカルチャー……それは、カウンターカルチャーということになるのだが……この新しい流れの行き着くところは、今にいたるまで明確になっていないということなのかもしれない。この六〇年代に若者であった世代が、歳をとって社会の大人になっていくのが、その後の歴史、また、二一世紀になってからの歴史ということになろうか。
今、二一世紀の今日からふりかえってみるならば、かつてのカウンターカルチャーの熱気が、今の社会には感じられない。社会に対する、世界に対する、希望と絶望がないまじった混乱した状況というものを、今となっては懐かしく思い出すことになる。(このようなことを感じるのは、私自身が年をとってしまったということなのだと思うが。)
こうもいえようか……社会が健全であるためには、その社会に対する抵抗の成分をふくんでいなければならない、と。この意味では、六〇年代のカウンターカルチャーの流れの検証ということは、今になお必要なことであろう。
ところで、番組のなかで、「ティファニーで朝食を」が出てきていた。映画は見ていないが、原作(翻訳)は読んでいる。この作品、再度、読みなおしてみたくなった。
次回は、六月の放送になるらしい。続きもまた見ることにしよう。
2022年5月15日記
世界サブカルチャー史 欲望の系譜「アメリカ 闘争の60s」
https://www.nhk.jp/p/ts/GLP33Y7513/episode/te/M9KKVK5R1N/
「世界サブカルチャー史」ということなのだが、扱っているのは、アメリカのことがほとんどという構成であった。まあ、これは、第二次大戦後の世界において「サブカルチャー」が生まれ、そして、世界を牽引していったのがアメリカという国であるという事情を考えれば、これはこのようになることなのかもしれない。この回での例外は、英国のビートルズということになるだろうか。
しかし、六〇年代をあつかうならば、日本においては、安保闘争のこともあり、また、フランスでは五月革命もあった。これらにまったく触れることがないというのも、ちょっと物足りない気もする。また、サブカルチャーといいながら、キューバ危機など、かなり政治的なことにも言及があった。ただ、これは、時代の背景説明として必要であったともいえるかもしれないが。
私は、一九五五年の生まれなので、六〇年代というと記憶にあるうちのことになる。登場した映画などについては、憶えているものが多い。映画館で見たということではないが、その時代の記憶として、ああこのような映画があったなと思い出す。そして、あの映画は、今から歴史的に振り返ってみるならば、そのような意味があり、解釈ができるのかと、これはこれとして、新知見であった。
結局、六〇年代に生まれた、サブカルチャー……それは、カウンターカルチャーということになるのだが……この新しい流れの行き着くところは、今にいたるまで明確になっていないということなのかもしれない。この六〇年代に若者であった世代が、歳をとって社会の大人になっていくのが、その後の歴史、また、二一世紀になってからの歴史ということになろうか。
今、二一世紀の今日からふりかえってみるならば、かつてのカウンターカルチャーの熱気が、今の社会には感じられない。社会に対する、世界に対する、希望と絶望がないまじった混乱した状況というものを、今となっては懐かしく思い出すことになる。(このようなことを感じるのは、私自身が年をとってしまったということなのだと思うが。)
こうもいえようか……社会が健全であるためには、その社会に対する抵抗の成分をふくんでいなければならない、と。この意味では、六〇年代のカウンターカルチャーの流れの検証ということは、今になお必要なことであろう。
ところで、番組のなかで、「ティファニーで朝食を」が出てきていた。映画は見ていないが、原作(翻訳)は読んでいる。この作品、再度、読みなおしてみたくなった。
次回は、六月の放送になるらしい。続きもまた見ることにしよう。
2022年5月15日記
『鎌倉殿の13人』あれこれ「果たせぬ凱旋」 ― 2022-05-17
2022年5月17日 當山日出夫(とうやまひでお)
『鎌倉殿の13人』第19回「果たせぬ凱旋」
https://www.nhk.or.jp/kamakura13/story/19.html
前回は、
やまもも書斎記 2022年5月10日
『鎌倉殿の13人』あれこれ「壇ノ浦で舞った男」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2022/05/10/9489216
日本一の大天狗、後白河院であった。
見どころはいくつかあったと思うが、印象に残っている野は、次の二つぐらいだろうか。
第一に、頼朝、義経、そして、後白河院、これらの思惑の交錯。誰が悪いということはないように思うが、まあ、強いていえば、一番悪いのは、後白河院ということになろうか。これも、院という立場で王家の存立を第一に考えねばならないということを考えると、なるほどこのような振る舞いもあり得るのかとも思う。
後白河院に比べれば、頼朝はどうだろうか。鎌倉に武家政権を樹立しようという意図は分かるのだが、ここは後白河院との知恵比べということになる。結果としては、義経追討のためという名目で、全国の領地の実質的支配権を手にすることになる。この流れとしては、頼朝の方が上手であったと見るべきかもしれない。
第二に、義経をめぐる里と静。この二人の女性の心理劇というものが、面白く描かれていた。まあ、結果的には、里のたくらみが裏目に出て、義経をより窮地に追い込むことになったのだが。
それにしても、里の三浦透子がよかった。これからのさらなる飛躍が期待できる女優だと思う。
以上の二つのことぐらいを書いてみる。
それから、見せ場だったのが、義経の殺陣のシーン。戦術の天才である義経だが、武芸にもたけている。
また、ちょっとだけ映っただけだったが、藤原秀衡(田中泯)が迫力があった。これから、義経の最期のところで、また登場することになるだろうか。
ところで、北条義時はというと、この回においても、歴史の流れのなかの目撃者という位置である。義時が歴史の表舞台に登場するのは、後年の承久の乱ということになるのだろうか。
次週以降、頼朝と義経の対立はつづく。楽しみに見ることにしよう。
2022年5月16日記
『鎌倉殿の13人』第19回「果たせぬ凱旋」
https://www.nhk.or.jp/kamakura13/story/19.html
前回は、
やまもも書斎記 2022年5月10日
『鎌倉殿の13人』あれこれ「壇ノ浦で舞った男」
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2022/05/10/9489216
日本一の大天狗、後白河院であった。
見どころはいくつかあったと思うが、印象に残っている野は、次の二つぐらいだろうか。
第一に、頼朝、義経、そして、後白河院、これらの思惑の交錯。誰が悪いということはないように思うが、まあ、強いていえば、一番悪いのは、後白河院ということになろうか。これも、院という立場で王家の存立を第一に考えねばならないということを考えると、なるほどこのような振る舞いもあり得るのかとも思う。
後白河院に比べれば、頼朝はどうだろうか。鎌倉に武家政権を樹立しようという意図は分かるのだが、ここは後白河院との知恵比べということになる。結果としては、義経追討のためという名目で、全国の領地の実質的支配権を手にすることになる。この流れとしては、頼朝の方が上手であったと見るべきかもしれない。
第二に、義経をめぐる里と静。この二人の女性の心理劇というものが、面白く描かれていた。まあ、結果的には、里のたくらみが裏目に出て、義経をより窮地に追い込むことになったのだが。
それにしても、里の三浦透子がよかった。これからのさらなる飛躍が期待できる女優だと思う。
以上の二つのことぐらいを書いてみる。
それから、見せ場だったのが、義経の殺陣のシーン。戦術の天才である義経だが、武芸にもたけている。
また、ちょっとだけ映っただけだったが、藤原秀衡(田中泯)が迫力があった。これから、義経の最期のところで、また登場することになるだろうか。
ところで、北条義時はというと、この回においても、歴史の流れのなかの目撃者という位置である。義時が歴史の表舞台に登場するのは、後年の承久の乱ということになるのだろうか。
次週以降、頼朝と義経の対立はつづく。楽しみに見ることにしよう。
2022年5月16日記
追記 2022年5月24日
この続きは、
やまもも書斎記 2022年5月24日
『鎌倉殿の13人』あれこれ「帰ってきた義経」
https://yamamomo.asablo.jp/blog/2022/05/24/9493457
この続きは、
やまもも書斎記 2022年5月24日
『鎌倉殿の13人』あれこれ「帰ってきた義経」
https://yamamomo.asablo.jp/blog/2022/05/24/9493457
すみれ ― 2022-05-18
2022年5月18日 當山日出夫(とうやまひでお)
水曜日は写真の日。今日はすみれである。
前回は、
やまもも書斎記 2022年5月11日
雪柳
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2022/05/11/9489497
先月の撮りおきのストックからである。我が家の周囲には、三種類のぐらいのすみれの花を確認できる。すみれについては、厳密にその種類を確定することは、難しいかもしれない。(まあ、これは、私に植物についての知識が無いからなのだが。)図鑑などをたよりに、すみれの種類を調べてみようと毎年思うのだが、今年も果たせなかった。
駐車場の隅に咲く花である。とても小さい。うっかりしていると見過ごしてしまう。写真に撮るにも地面近くなので、苦労する。だが、今年も同じように同じような場所にすみれの花の咲くのを確認できるのも、楽しみの一つである。
庭に出ると、紫蘭の花がそろそろ終わりかけである。ドクダミの花が咲きかけている。カナメモチの白い花が見えるようになってきている。躑躅の花が咲いている。紫陽花を見ると小さなつぼみが見える。そろそろ初夏から梅雨の季節にかけての花になろうとしている。
水曜日は写真の日。今日はすみれである。
前回は、
やまもも書斎記 2022年5月11日
雪柳
http://yamamomo.asablo.jp/blog/2022/05/11/9489497
先月の撮りおきのストックからである。我が家の周囲には、三種類のぐらいのすみれの花を確認できる。すみれについては、厳密にその種類を確定することは、難しいかもしれない。(まあ、これは、私に植物についての知識が無いからなのだが。)図鑑などをたよりに、すみれの種類を調べてみようと毎年思うのだが、今年も果たせなかった。
駐車場の隅に咲く花である。とても小さい。うっかりしていると見過ごしてしまう。写真に撮るにも地面近くなので、苦労する。だが、今年も同じように同じような場所にすみれの花の咲くのを確認できるのも、楽しみの一つである。
庭に出ると、紫蘭の花がそろそろ終わりかけである。ドクダミの花が咲きかけている。カナメモチの白い花が見えるようになってきている。躑躅の花が咲いている。紫陽花を見ると小さなつぼみが見える。そろそろ初夏から梅雨の季節にかけての花になろうとしている。
Nikon D500
SIGMA APO MACRO 150mm F2.8 EX DG OS HSM
2022年5月17日記
映像の世紀バタフライエフェクト「宇宙への挑戦 夢と悪夢 天才たちの頭脳戦」 ― 2022-05-19
2022年5月19日 當山日出夫(とうやまひでお)
面白かった。録画しておいて、翌日の朝にゆっくりと見た。
アポロ11号の月着陸の時は、家にいて(たしか夏休みだった)、テレビを見ていたのを思い出す。あのころ、たしかに宇宙開発には夢があった。しかし、それは、今となってははかないものであったといえるかもしれない。
一つには、宇宙ロケットの開発は、第二次世界大戦中のドイツV2に由来する。このことは、これまでにさんざん語られてきたことであろう。そして、その中心にいたのが、フォン・ブラウンであった。以前の「映像の世紀」シリーズでも、目にした記憶がある。少なくとも、戦後の宇宙開発は、戦時中の軍事技術の上に構築されてきた。
もう一つは、現代、そして将来において、宇宙開発は、これまた軍事技術と切り離して考えることができないということだろう。現在のウクライナでの戦争は、様々な宇宙開発の技術の応用でもある。また、将来の火星探査も、これまた軍事技術と切り離して考えることもできない。
このようなことを思ってはみるのだが、しかし、一方で、宇宙開発には確かに夢がある。この番組は、宇宙にかけた夢の物語であり、また、同時にそれが、軍事技術とともにあるという現実の世界の姿の物語でもあった。そして、科学と技術の発展に根本的に必要なのは、ヒューマニズムであることを強く訴えかける内容であったと思う。
さて、次回は、スターリンとプーチンのことになるようだ。これも楽しみに見ることにしよう。
2022年5月17日記
面白かった。録画しておいて、翌日の朝にゆっくりと見た。
アポロ11号の月着陸の時は、家にいて(たしか夏休みだった)、テレビを見ていたのを思い出す。あのころ、たしかに宇宙開発には夢があった。しかし、それは、今となってははかないものであったといえるかもしれない。
一つには、宇宙ロケットの開発は、第二次世界大戦中のドイツV2に由来する。このことは、これまでにさんざん語られてきたことであろう。そして、その中心にいたのが、フォン・ブラウンであった。以前の「映像の世紀」シリーズでも、目にした記憶がある。少なくとも、戦後の宇宙開発は、戦時中の軍事技術の上に構築されてきた。
もう一つは、現代、そして将来において、宇宙開発は、これまた軍事技術と切り離して考えることができないということだろう。現在のウクライナでの戦争は、様々な宇宙開発の技術の応用でもある。また、将来の火星探査も、これまた軍事技術と切り離して考えることもできない。
このようなことを思ってはみるのだが、しかし、一方で、宇宙開発には確かに夢がある。この番組は、宇宙にかけた夢の物語であり、また、同時にそれが、軍事技術とともにあるという現実の世界の姿の物語でもあった。そして、科学と技術の発展に根本的に必要なのは、ヒューマニズムであることを強く訴えかける内容であったと思う。
さて、次回は、スターリンとプーチンのことになるようだ。これも楽しみに見ることにしよう。
2022年5月17日記
『青の時代』三島由紀夫/新潮文庫 ― 2022-05-20
2022年5月20日 當山日出夫(とうやまひでお)
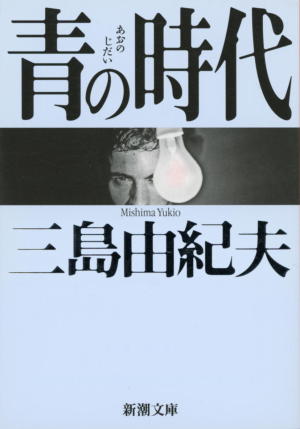
三島由紀夫.『青の時代』(新潮文庫).新潮社.1971(2011.改版)
https://www.shinchosha.co.jp/book/105020/
書誌を書いて気づくのだが、この文庫本が出たのは、三島が亡くなった翌年のいことになる。没後の刊行である。
この作品を読むのは、はじめてである。名前は知っていた。光クラブの事件に題材をとった作品であることも知ってはいた。が、何となく手にすることなく過ぎてしまっていた作品である。
読んで思うことは、次の二点。
第一に、ある時代を描こうとした作品なのだろうということ。この作品の成立は、昭和二五年である。まだ戦後間もないころといってよい。光クラブの事件は、同時代の事件といってよいのだろう。その時代のなかにあって、同時代を三島の目で描いて見せた、ということになろうか。
第二に、行動と認識。この作品には、短い序文がついている。そのなかで、三島由紀夫自身が、行動と認識と述べている。こうある……「人は行動するごとく認識すべきであっても、認識するごとく行動すべきではないとすれば」。この小説における、行動と認識はどう考えることができるだろうか。光クラブという詐欺事件において、それが欺瞞とわかっていて行動している主人公は、はたして自らの行動をどう認識していたとすべきなのだろうか。
以上の二点のことを思って見る。
おそらく、行動と認識ということは、三島由紀夫の文学をつらぬくキーワードといってよいだろう。結局、最後になって、三島由紀夫は、ある行動に出ることになったのだが、その背後には、三島由紀夫なりの認識があってのことになろうか。
2022年5月16日記
https://www.shinchosha.co.jp/book/105020/
書誌を書いて気づくのだが、この文庫本が出たのは、三島が亡くなった翌年のいことになる。没後の刊行である。
この作品を読むのは、はじめてである。名前は知っていた。光クラブの事件に題材をとった作品であることも知ってはいた。が、何となく手にすることなく過ぎてしまっていた作品である。
読んで思うことは、次の二点。
第一に、ある時代を描こうとした作品なのだろうということ。この作品の成立は、昭和二五年である。まだ戦後間もないころといってよい。光クラブの事件は、同時代の事件といってよいのだろう。その時代のなかにあって、同時代を三島の目で描いて見せた、ということになろうか。
第二に、行動と認識。この作品には、短い序文がついている。そのなかで、三島由紀夫自身が、行動と認識と述べている。こうある……「人は行動するごとく認識すべきであっても、認識するごとく行動すべきではないとすれば」。この小説における、行動と認識はどう考えることができるだろうか。光クラブという詐欺事件において、それが欺瞞とわかっていて行動している主人公は、はたして自らの行動をどう認識していたとすべきなのだろうか。
以上の二点のことを思って見る。
おそらく、行動と認識ということは、三島由紀夫の文学をつらぬくキーワードといってよいだろう。結局、最後になって、三島由紀夫は、ある行動に出ることになったのだが、その背後には、三島由紀夫なりの認識があってのことになろうか。
2022年5月16日記












最近のコメント